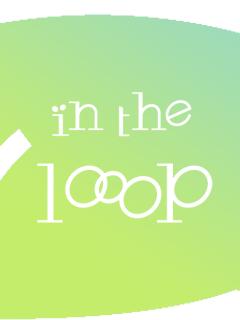お世話になっております。
ループス直人です。
先月、In the looop で記事を書いてくださっている方で集まる「ITLブロガー・ミーティング」のようなものを開催したのですが、その時にブロガー同士の話し合いから感じたことをちょっと書いてみます。AMNさんもブロガーパートナーを募集していたり、少しタイムリーかな、というような気持ちもあったりして。
20010年くらいから注目され始めた「ソーシャルメディアマーケティング」。でも、ブロガーミーティングを終えて、改めて考えてみると「ブロガーって、“ソーシャルメディアマーケティング” って言われてるもののこと、一番よくわかってるんじゃないかな」なんて考えが頭をよぎりました。彼らって、企業の中ではエンジニアだったり、営業だったり、もちろんマーケティング担当の方の場合もありますが、基本は専門職に従事しながら、その傍らで書いているケースが多いわけです。会社としてオフィシャルな活動でない場合もたくさんあるんでしょうけどね。
でも、もしかしたら御社で細々とブログ記事を書いているエンジニアが、実はソーシャルメディアを使ったマーケティングについては達人級のノウハウを持っているかもしれません。社内ブロガー、もしくはアンオフィシャルな潜在ブロガーが、実はソーシャルメディアマーケティングを志向する会社が一番最初に注目すべき資産なんじゃないか。
(社内ブロガーに配置している企業が、ソーシャルメディアマーケティングについて無知なはずはないかも知れませんけどね・・・。)
そんな可能性を提案したくて、このエントリを書きました。
ブロガーとソーシャルメディア
「ソーシャルメディアマーケティング」という、実はけっこう小さな世界を表す言葉。
ブロガー同士で「ソーシャルメディアマーケティングってどう思う?」っていう話をすると、みんな「うーん」ってなる。わからないんじゃなくて、「ソーシャルメディアをマーケティングに使うこと」が当たり前すぎて、あえてそこだけにフォーカスして語る意味を感じないというか。
そんなに多くのブロガーと情報交換したわけではないのですが、ブロガーにソーシャルメディアマーケティングの話を聞いて帰ってくるのはこんなところではないでしょうか?
マーケティング?
・・・ちょっと良くわからないけど、言いたいのは、自分が好きな製品・サービスであったり、主義・主張であったり、 「面白い!」と思ったもので、それが伝わるならなんでもいい。でも広く伝えるといってもお金をかけられるわけじゃないしね。ソーシャルメディアでつながってる友達は仕事や興味も近いし、仲がいいからシェアもしてくれて、自然に広がっていくんだ。
中にはネットでちょっと有名なやつもいて、たまにそいつが紹介してくれると爆発的にヒットする記事も出てくるよ。そういう時ってなんていうか、こう、気持ちがいいんだよね。世の中に受け入れられたみたいで。目立つしね。
これって、ソーシャルメディアマーケティングの本質、結構ストレートに表現していると思うんですよね。別に魔法の杖だなんて言ってないですよ。用語の正しい定義なんてどうでもよくって。
「本当に伝えたいこと」があって、「それに価値を認める人」がいて、その両方を「ソーシャルメディア」がつないだ。それだけのことです。
ソーシャルメディアマーケティングの「可能性」と「現実」
前項で申し上げたかったのは、ブロガーがいかにソーシャルメディアマーケティングに慣れ親しんでいるか、ということです。
もちろん、マーケティングに利用できるソーシャルテクノロジーの理解は大前提。実際に、本気で使っているからわかっている点こそが重要です。例えば、ソーシャルメディアマーケティングの「可能性」と「現実」。ご興味ございますでしょうか?
可能性
ブロガーは、いちいち意識してないでしょうけど、本質的にソーシャルメディアの可能性を信じています。彼らが使っている「ブログ」というツールがそもそも「ソーシャルテクノロジー」の一部ですしね。一応ですが、ここでは「ソーシャルテクノロジー」を、「オープン」で「個人が手軽に利用」できて、「共有の仕組み」があって、「双方向性がある」、などの特徴をもった一連のネットサービスを支える技術・仕組みというゆるい意味合いで使っています。
で、ソーシャルメディアマーケティングの「可能性」。たくさんあるのでしょうけどひとつには「個人が広く世界に向けて、情報発信できる可能性」が挙げられると思います。
理屈的には、ネットを通じて日本国民の8割くらいには情報を届けられます。可能性があるだけで、実際どこまで届けられるかという問題はあるのですが、ネット以前はその可能性は特殊な職業・立場を除けば限りなくゼロに近いものでした。ソーシャルテクノロジーがネットにおける個人による情報発信の参加障壁を大きく下げ、利用者も増えたことで環境としては整った。あとはそのインフラに載せる情報が他のユーザーに支持されれば、もしかしたら思いもよらない広がりが得られるかもしれない。これはソーシャルテクノロジーによって情報の伝播が発信者のさじ加減ではなく、中継者の後押しによって起きたパラダイムシフトです。
ソーシャルテクノロジーが、コミュニケーションインフラとしてのインターネットのポテンシャルを最大化した、こういう見方をしてもよいでしょう。ブロガーはそのポテンシャルに期待しているわけです。
ブロガーだけでなく、企業にもその可能性に賭けているところはたくさんあります。でもブロガーの場合、特筆すべきなのはその「主体性」と「能動性」です。伝えたいものがある、伝えたいことがある。その気持ちがスタート地点にあるから、モチベーションも湧くし、息の長い改善の努力もできるし、始めたばかりの孤独にも耐えられる。
その情報発信によって成果が得られるまでの期間が長期に渡ると考えた場合、モチベーションの維持は大きな問題です。だから最初からその可能性を理解し、信じ、賭けようと思う人間に仕事を任せるべきです。
現実
そして経験豊富なブロガーは、「広く世界に情報を届ける」という野心について、インフラは整ったものの実際にそれがいかに難しいかという現実を熟知しています。
渾身の主張が世の中に全く受け入れられない時、日々更新を続ける努力になんの反応も得られない時、自分のアイデアが必要とされていないことに気づいた時・・・。多くのブロガーが肩を落とし、続ける意欲を失い、それでも意思の力で書き続けるのです。
私もブログを始めたばかりのころは、頑張って書いた記事を公開してもせいぜい数十から数百人くらいの方にしか見ていただけず、残念な気持ちになりました。弊社の斉藤も、IT Media オルタナブログで書き始めた初月は、月間2000人くらいの訪問者数だったと思います。半年たっても1.2万人。それが1年後には約8.3万人にまでなります。
その間の、1年に渡る試行錯誤は大変なものがあったそうです。こうして現実を乗り越え、一定の認知を得るまでに至ったブロガーが持っている「手応え」というか「感触」、そして「ノウハウ」は、会議室で行う検討会議100時間分より価値があるでしょう。
思想信条がはっきりしている
前述の通り、ブログはある程度「書き続けるモチベーション」がないと続きません。そしてそのモチベーションは多くの場合その人なりの「理念」や「思想信条」のようなもので支えられています。「その時書きたいこと」のもっと源流で、心の深いところで支える気持ちです。
ブロガーが集まって行うミーティングでも、ブログを書き続ける理由として「勉強のため」「ひとと繋がれるから」「実現したいことがある」、様々な想いが見られました。そしてその多くは、その人が書く記事全体を通してそこはかとなく感じられるものです。
ソーシャルメディアマーケティングのようなものは、どうしたってそれなりに属人的になるものです (特に小規模な場合は)。しかもその属人性、つまり個性が顧客に伝わるわけですから、担当者のアサインは慎重にならざるを得ません。特に「思想信条」のようなものは押し付けることができません 。Googleのあるマネージャに言わせると、「人間の根っこの部分は変えられない、それをやろうとすると、それこそ洗脳しないといけなくなる」というわけです。
「ソーシャルメディア担当」のようなものをアサインするにあたって、その方の「思想信条」って考慮されていますか?
ブログには思想信条、コンテンツ作成能力、興味のあるカテゴリなどが現れますから、そこから担当者候補を見つけるというのは案外効率がいいのではないかと思います。
自律駆動型のマーケティング改善活動
ブロガーは、自分の書いたものをなるべくたくさんの人に見てもらいたいと考えます。記事を書くのには頭も時間も使いますから、それは当然であり強い願いです。
そのため、ブロガーは自分で書いた記事が、どうしたら効率良く興味のある読み手に届くのかについて普段から高い関心を持ち、より多くの人に読まれるために日々改善をおこなっています。内発的動機に支えられるその改善活動は記事執筆のための努力と比例して大きくなり、とどまるところを知りません。WEB解析やソーシャルメディアマーケティングはごく当たり前。顧客象の推定や記事の内容・書き方によるA/Bテスト、タイトルや内容、画像の工夫などおよそ時間と予算の許す限り心を砕いて行われます。
こういった活動から、ブロガーは自分の興味ジャンルにプラスアルファして、WEB解析やソーシャルメディアマーケティングの知識を持っていることが多いです。特に大切なのは、情報発信するコンテンツの評判によって顧客の求めるものを推測していく活動です。バナー広告のA/BテストやWEBサービスのスプリットテストに似ていますが、ブログの場合「同時に複数バージョンをリリースしてどちらが受けるか試す」ということができません。その内容はその時一度きりのものだからです。なので、改善は必ずしも定量的な分析に基づくわけではなく、より有機的、感覚的に行われます。このちょっと特殊な改善活動の経験はかなり属人的であるため、大変貴重です。
同じコンテンツ、同じ内容でも、より相手の興味を喚起し、納得させるような書き方を、ブロガーは日々模索しているのです。
終わりに
以上です。
いつもどおりというか、いつもにも増して散漫な内容でしたが、お楽しみいただけましたでしょうか。
顧客開発やマーケティングについて書かれた本では、しばしばエンジニアや製品開発部門は「マーケットから遠いところにあり、顧客のニーズをわかっていない」というような言われ方をしますが、ブログやソーシャルメディアという手段でオープンに外の世界とつながっている人たちに限っていえば、そうでもないような気がします。
むしろテーマによっては、定量調査や市場分析レポートを介して顧客と向き合っている経営企画部門よりも、ずっと世間の肌感覚をわかっている可能性も否定できません。まあ、ケースバイケースですけどね。あくまでも。
それでは、よろしくお願い致します。
photo by aJ GAZMEN ツ GucciBeaR
by 許 直人