伝説の土8番組『コント55号の世界は笑う』のVTRは、わずか1本しか残っていないという。当時テレビ番組は、一度録画したビデオテープの上に重ねて撮っていたからだ。では、なぜ一本だけは残っているのだろうか。なぜなら萩本欽一が、次の週のコントをどうしても思いつかず、「次回だけ前にやったのをもう一回放送してくれない?」と頼み込んだからだ。それが皮肉にも、貴重な番組VTRを残す結果になったのだ。
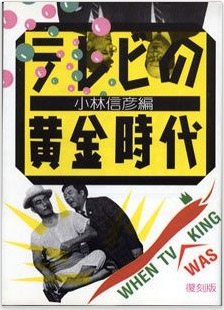
コント55号は「同じネタを二度使わない」という厳しいルールを自らに課したコンビだった。それは前代未聞のことだった。今でこそ「新ネタ」ということが重い価値があるようになったが、当時は決してそうではなかった。コメディアンは十八番であるネタを何度も何度も繰り返し演じ、完成度を極限まで高めることこそが「芸」とされ、その完成度の高さこそ価値のあるものだった。その"常識"をコント55号は破壊したのだ。もちろん、「同じネタを二度使わない」というルールは完全に守られたわけではない。冒頭に挙げたような例外もあったし、「机」などの代名詞的なコントは何度か再演されることもあった。だが、『お昼のゴールデンショー』や『世界は笑う』で演じられるコントのほとんどは、新ネタだった。しかも、驚くべきことにそのほとんどがアドリブだったという。結果、コント55号がテレビでコントを披露したネタ数は、実に3631本にのぼったという。
なぜそんなことができたのだろうか。彼らが修業をした浅草では台本があるのは「コメディ」(喜劇)だけだという。コントには3つの基本形がある。それが「天丼」「仁丹」「丸三角」だ。それだけで台本は必要なかった。だから彼らに言わせれば、台本があるものは「コント」ではないのだ。浅草の芸人はみんなそれを徹底して訓練されるため、本番前に演出家から「今日は天丼」と言われ、設定と役割を決めると後はほとんどがアドリブだった。
コント55号は、それをそのままテレビに持ち込んだのだ。だから「設定」こそが肝になる。それを考えた重要なブレーンの1人が岩城未知男だった。そしてその設定をふくらませ、話をどんどん変えていく役割を担ったのが萩本だった。本番前に萩本が坂上に設定を耳打ちすると坂上二郎がたった一言答えて舞台に立つ。するとコント55号のコントが生まれるのだ。
「二郎さん、今度はマラソンのコーチと選手でいこう」
「はいよっ」
ただそれだけだ。
(参考)『テレビの黄金時代』小林信彦:著/『昭和40年男』2014年6月号/『ふたりの笑タイム』小林信彦・萩本欽一:著/『テレビリアリティの時代』大見崇晴:著/『なんでそーなるの』萩本欽一:著
■1月のAOL特集
共演がご縁でくっついたセレブカップルたち【フォト集】

