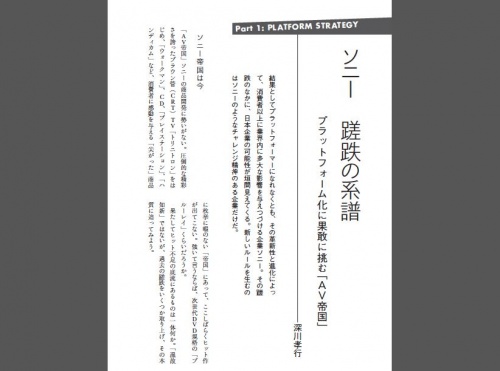
※『IT批評 1号 特集:プラットフォームへの意思』(2010年12月刊行)より深川孝行さんの「ソニー 蹉跌の系譜」を転載。
■ソニー 蹉跌の系譜
プラットフォーム化に果敢に挑む「AV帝国」
結果としてプラットフォーマーになれなくとも、その革新性と進化によって、消費者以上に業界内に多大な影響を与えつづける企業ソニー。その蹉跌のなかに、日本企業の可能性が垣間見えてくる。新しいルールを生むのはソニーのようなチャレンジ精神のある企業だけだ
●ソニー帝国は今
「AV帝国」ソニーの商品開発に勢いがない。圧倒的な精彩さを誇ったブラウン管(CRT)TV「トリニトロン」をはじめ、「ウォークマン」、CD、「プレイステーション」、「ハンディカム」など、消費者に感動を与える「尖がった」商品に枚挙に暇のない「帝国」にあって、ここしばらくヒット作が出てこない。強いて言うならば、次世代DVD規格の「ブルーレイ」くらいだろうか。
果たしてヒット不足の底流にあるものは一体何か。「温故知新」ではないが、過去の蹉跌をいくつか取り上げ、その本質に迫ってみよう。
●ベータ:技術優位も「家電王国」のVHS支持であえなく劣勢に
ビデオ規格をめぐる、いわゆる「ベータ対VHS戦争」はつとに有名で、いまさら詳述することもないだろう。ある意味圧倒的ブランド力と技術力を誇る「SONY」にとって初めて味わった大きな挫折ではないだろうか。
1975年、「家庭用VTRの決定版」としてソニーは「ベータ(β)マックス」を発表。しかし翌76年には日本ビクター(現JVCケンウッド)・松下電器産業(現・パナソニック)連合(当時ビクターは松下の傘下)が強力な対抗馬「VHS」をぶつけてくる。この勝負、80年代の半ばまでには、包囲網を固めたVHSの優勢でほぼ決着がついてしまう。
「高性能へのこだわり」が、ある意味ベータの敗因だろう。
ソニーは70年代に入ると家庭用VTRの統一規格を目論み、これまで同社が進めてきたビデオ方式「U規格」をベースにしたベータを開発。従来同様「高画質」にこだわった味付けを前面に押し出した自信作だった。
U規格にはもともと松下、ビクターも参画したことがあって、ソニーは今回も両社にラブコール。広範な技術支援も約束するなどかなり大盤振る舞いで臨んだ。
だが、起死回生を懸けたAVメーカーの老舗・ビクターが密かに温めていた「VHS」を、〝親会社〞の総帥・松下幸之助翁に直談判。画質でやや劣るものの、構造が簡単で軽量、取り扱いやすく製造工程も楽、加えてビデオテープの容量もベータの当初1時間に対し、こちらは標準録画で2時間。スポーツや映画などのTV番組に十分対応できる、といった「お茶の間目線」から幸之助翁はVHSを選ぶ。「水道哲学」(安価で使い方が簡単な製品で普及を促す)を実践してきた幸之助翁にとって、VHSはまさに「お誂え向き」のアイテムだったわけである。
VHSの商品化に乗り出した松下は、「ナショナルのお店」を背景にした圧倒的な販売力、そして幸之助翁が持つ絶妙なる「業界外交」の手腕を駆使して「デファクトスタンダード」を目指す。技術やノウハウも可能な限りオープンとし、OEMにも積極的に応じた。またこれと並行して消費者がVHSをより楽しめるように豊富なソフトを用意するなどシェア拡大の「仕掛け」づくりにも余念がなかった。
一方迎え撃つソニー側だが、高性能を追求するがゆえの「煩雑さ」が最後までネックとなっていく。新技術を次々に商品に盛り込むチャレンジ精神は、ある意味「ソニーらしさ」として評価すべきだろう。だが、マイナーチェンジを頻繁に繰り返すあまり、一般消費者はもとより販売店や製造現場でも混乱を誘発していたことは確かだ。例えば、ベータの微妙なバージョン変更は最終的に10を超え、同じ陣営内でも本家のソニー以外採用しなかった規格や、旧機種では再生に不具合が生じるものなどさえ出現した。テープも同様に多種多様のバージョンを乱発、消費者にとっては分かりづらかったようだ。
加えて、複雑になっていくベータ機器の製造に音を上げた日立などがソニーに対しOEMを依頼するものの、「努力の結晶」を安易に相手先ブランドで供給するという行為は、「SONY」の沽券に掛けてもできるはずがなかった。
こうして、ベータ陣営から電機メーカーが続々と「戦線離脱」、VHSのデファクトスタンダード化は確実となる。それでもソニーは「映像は画質が命」のこだわりを持ってこれに抗い続けた。しかし「なぜソニーはVHSを作らないのか」という消費者からの強い要望もあって、88年ついにVHS参入という苦渋の決断を行うのである。
確かに業界関係者の中には、「品質を追い過ぎマーケットが求める〝そこそこの性能〞に妥協できなかったのが敗因」と手厳しい意見もある。高い品質によってマーケットがつくられるケースも多く、品質かマーケットかの選択は企業にとって頭を悩ませる問題だ。
ソニーの場合、後述するように品質重視を通すことで、数多くの失敗を繰り返している。しかし、どれほどの会社がこうした失敗を重ねるだけの体力と精神力を持っているだろうか。一方で、ソニーはその企業風土に安住することで、失敗を繰り返していないだろうか。そうした視点から、もう少し事例を追ってみよう。
●MD:携帯音楽向けとして君臨するがインターネット到来で時代の役目を終える
1979年に突如出現した「ウォークマン」は「携帯音楽プレーヤー」という、いちジャンルを構築するまでのメガヒット作となった。しかし、音楽データの収納方法が「カセットテープ」(コンパクトカセットテープ)を使ったアナログ方式であるため、直後に登場したデジタル方式に比べ、音質や品質維持、選曲の容易性などで数段劣っていた。
そしてこれを解決する方策としてソニーは、蘭フィリップス社と共同で手掛けて成功を収めたCDの光学ディスク技術を応用し、ウォークマン向けのコンパクトなデジタル音声メディアの開発を急ぐ。これがMD(ミニディスク)である。
MDは1992年にリリースされ、同時に「MDウォークマン」(MZ-1、MZ-2P)を発売、若者を中心に瞬く間に絶大な支持を集める。しかしその一方で技術にこだわったがための問題も噴出、これがかえってオーディオマニアから「音質が悪い」という誤解を招く結果ともなっていく。
「テープレコーダーの雄」を自負する同社にとって、録音の際の「歪み」など絶対に許すことはできない。このため徹底的な防止策を講じた結果、この制御データのためにMDメディア容量の半数を費やしてしまい、60分のメディアでは5〜6曲しか入らないという状況となってしまった。またどうしてもCDをまるごとコピーしようとする際は、音質を落とさなければならない。高音質を追求しようとする同社の努力は見事だが、皮肉にもこれがかえって仇となった格好だ。(その後この機構は改善されている)
その後も数々の改良を重ねながらMDは90年代を通じてその存在感を増していく。そして当時別規格のDCCで挑んだ松下との戦いにも勝利、同社をMDの軍門に下すなど快進撃を果たす。
しかし「iPod」に代表される、フラッシュメモリーやHDD内蔵型の「携帯デジタル音楽プレーヤー」が台頭してくると、桁外れの楽曲収容力に対抗することはできず、ソニーは09年MD製造からの完全撤退を決意する。
CDでデジタル化の試みに成功したソニーが、携帯型音楽プレーヤーでもデジタル音源を求めた挑戦だったが、デジアナ転換までのビジョンがあったのか、単なるメディアの選択に過ぎなかったのか。成功するとビジョンの有無がなし崩しに問われないが、長期間の覇権を築いたMDの最後なだけに気にかかる点だ。
●メモリースティック:「ベータ」と同じ轍を踏んだ「高性能を誇る孤高」
フラッシュメモリーの急激な高性能化・低廉化を受けて、これをAV家電向けの次世代記憶メディアとして使おうという戦略から、ソニーは富士通などと共同で「メモリースティック」(MS)を開発、1997年に市場投入した。その狙いはデジカメの画像・映像データの記憶媒体としてであり、取り外しが簡単でしかもPCなど他のAV機器とのデータのやり取りに供する、というのが基本コンセプトである。その後、ソニーグループが放った携帯型ゲーム機「PSP」や携帯音楽プレーヤー、携帯電話などモバイル機器への需要も期待されていた。
ところが翌99年に松下、東芝、サンディスクの3社連合による「SDカード」が出現。SDが着々とシェアを伸ばして行く一方で、MSはじわじわと勢力を失っていく。
こうして見るとかつての「ベータ対VHS戦争」の時と全く同じ軌跡といっていいだろう。
松下陣営の場合、SDの開発コンセプトは明快だった。それは「AV家電間で情報をやり取りするにはコストパフォーマンス、転送時間、使い勝手を考えれば〝物理的メディア〞としてのSDを使うのが一番いい」というものだ。そしてソニーと同様、デジカメなどAV機器全般で共通して使える記憶媒体としてSDを強力に推し進めるのだが、その基本的コンセプトがソニーと松下とでは若干異なっていた。
当時のソニーはトップだった出井伸之氏が推進する「ネットワーク(NW)戦略」(後のコネクト戦略)一色だった。「コンテンツ(ソフト)とハードとの融合」に代表されるこの発想は、簡単に言えば、音声や画像・映像といったリッチコンテンツ・データはネットのブロードバンドやブルートゥース、Wi-Fiといった無線システムでやり取りする、という一大構想だ。ただこの考え方を忠実に踏襲するとすればMSは「大容量の記憶媒体」ではあるものの、「転送媒体」としての効果はあまり期待していない、ということになる。事実ソニーの首脳陣たちの中にMSの「転送媒体」としての重要性に着目する人間はいなかったように思える。
一方松下の場合、これとは全く正反対で、自らが手掛けるデジカメやビデオムービーはもちろん、DVDレコーダー、TV、携帯電話、ノートPCなどありとあらゆるAV機器に漏れなくSDスロットを設け、プラットフォーム=SDの使用場面の拡大に血道を上げた。
「NWによるデータ送受信」は次世代AV機器に必須のアイテムだが、転送速度の確保や転送の確実性を担保するにはかなり高度な技術が必要だ。またこれに対応する仕組みをAV機器全てに盛り込むとなれば、コストアップも覚悟しなければならない。取り扱いも複雑になりかねず、ごく普通の消費者にとってはややハードルが高いだろう。
一方SDが目指す「直接受け渡し」であれば誰でもが直感できる。AV家電を「先端情報端末」ととらえるソニーと、「あくまでも洗濯機や冷蔵庫と変わらない家電」と見る松下の違いが、ここでも如実に表れた。加えて松下の場合、SDのコアであるフラッシュメモリーの主要メーカー、東芝とサンディスクを陣営内に迎え入れた点も大きな利点だ。
またSD側はシェアアップの秘策として高機能化する携帯電話に目をつけ、記憶メディアとして一回り小ぶりの「miniSD」を提案(その後より小型の「microSD」へとシフト)、携帯メーカー各社の囲い込みに成功する。SD陣営は1億台に迫る国内携帯電話端末の大部分を押さえ、「MD対SD戦争」の勝利を確実にするのである。
「2000年の発売以来世界中で累計1億台を販売した、据え置き型ゲーム機『PS2』にMSスロットを搭載する努力をソニーはしなかった。同機はDVD再生機としての機能も持つマルチAV端末としての顔もウリだったのだから、データの受け渡しのためのMSスロットを搭載すればSDカードの独走を許さなかったハズ」といった指摘も当然多い。現にその後に登場したPSPはMSに対応、PS3はMSとSDの両方対応となっている。
純粋に性能だけを見ると、例えば最大データ転送速度はSDの20MB/秒に対し、MSは最高位の「Pro系32GB」で60MB/秒と実に3倍を誇る。このためデジカメの連写での威力はいまだに絶大だ。
SDがデファクトスタンダードを握ったものの、MSが追求した「コンパクトな高速・大容量ストレージ」というコンセプトは間違っていない。SDも結局は、このポリシーの上で成功を収めている。だが、それだけに抱える問題が大きい。ある意味、技術の現場と営業、経営の乖離が失敗の本質と見えるからだ。こうした問題はソニーだけでなく、技術の評価が高い企業全般によく起こる事例だ。
●コクーン:コンセプトが早すぎた「HDD型ビデオ」
2002年11月に登場したチャンネルサーバー「コクーン」(CSV-E77)は、結論から言うならば「市場投入の時期が一歩早すぎた」というべきだろう。当時としては巨大な「160GB」のHDDを搭載、EPモードで最大1 0 0時間、同時に2チャンネル録画可能という能力は、当時にあってまさに「怪物」だ。ちなみに「チャンネルサーバー」としてソニーは前作の「CSV-S55」を出しており、「コクーン」はこのいわば「二代目」に当たる。
前述したように、ソニーはこの頃「コンテンツとハード、サービスの融合」に向けてひた走っており、コクーンはこれを具現化した商品でもあった。実際同社は同機を「ユビキタス・バリュー・ネットワーク」を実現するマルチ端末と自負、「ハードがユビキタスでNWにつながる環境を実現し、ハードとコンテンツやサービスがシームレスにつながることで、ソニーならではの新たな価値を提供する世界」を強調して見せている。そしてコクーンはこれを実現するために、ネット常時接続型のNW機能を備えた「ホームAVゲートウェイ製品群」の嚆矢という位置付けだった。
地上波チューナとMPEG-2エンコーダの二段構えで2番組同時録画を実現、録画中でも他チャンネルの番組を視聴できたり、予約録画を実行中に今観ている番組を録画することも可能など、ビデオになかった画期的な技がぎっしり。加えてNW機能もふんだんに盛り込まれ、NWインターフェイスを前作の56kbpsモデムからイーサネットに変更、専用HPを介して外出先からでも録画予約を実現させている。またユーザーの好みのジャンルを認識、例えば「ゴルフ」をよく録画する場合は、後は関連番組を自動収録する「学習式自動録画予約機能」という「離れ業」まで備える。ただしDVDなど保存用の記録媒体は一切ない。ストレージは大容量のHDDに任せ、一杯になったら不必要な番組を消せばいい、という、いかにも「ソニーらしい」スマートな発想だ。
しかし、次世代を彷彿させる「決定版」であるにも関わらず、消費者の反応は今ひとつ。最大の原因は、「一歩先に進み過ぎた」ことだ。当時、日本市場はビデオの買い替え需要としてDVDレコーダーが普及しつつあり、またHDDを備えたタイプも徐々に市場に顔を出し始めていた。実勢価格も急速に10万円を切り、こうなると同約13万円と高価で、かつDVD録画機能を持たないコクーンには分が悪い。
消費者の大多数は案外保守的で、ビデオからDVDを飛び越えて「コクーン」へとなびかなかった。またビデオテープやDVDなど外部媒体に「物理的」に映像を記録し、物体として保存したいという願望は、ことさら日本人には強いのである。
DVDの規格をめぐっては業界内でドタバタ劇が演じられ、松下やパイオニアが主導権を握る形で市場は動いていた。しかしソニーは「ベータと同じ轍は踏まない」と考えたのか、DVDレコーダーにはあまり熱心ではなく、ビデオからDVDを飛び越えていきなりHDDへと「TV番組録画機」を進化させ、消費者を誘おうと考えていたようである。
だが、この目論見は前述のようにうまくいかず、結局ソニーはHDD&DVDレコーダー「スゴ録」を2003年にリリースした。まさに「周回遅れ」の戦略的失敗と言っていいだろう。
今やHDDは家庭用録画機に欠かせない存在だ。その意味では、ソニーの着眼点と技術力が生かされた、いかにもソニーらしさが表れている事例と言える。
しかし同時に、ベータの例に学びDVDをあえて遠ざけたことが、かえって裏目に出てしまった。失敗を生かすナレッジマネジメントは誰もが簡単に口にするが、残念ながらそれがいかに難しいかを示す好例とも言えるだろう。
●ウォークマン: ネット対応に遅れ「i P o d」にお株を奪われる
iPodの快進撃ぶりを今さらくどくど説くのも野暮というものだろう。周知の通り1979年の登場以来20年余にわたり営々と築き上げてきたウォークマンの牙城は、2001年に新風のごとく登場した米国発の「にくい奴」にあっけなく崩されてしまった。
原因については、前述のMDの項でも述べているが、1にも2にも「MP3」にまつわるソニー側の苦渋と逡巡にほかならないだろう。
実は昨今主流となった、フラッシュメモリーやHDDをストレージとする「携帯デジタル音楽プレーヤー」の開発に関して、ソニーは「iPod」よりも2年先を走っていた。
1990年代の終わりに韓国ベンチャーが「MP3プレーヤー」を開発、業界をあっと言わせると、ソニーは間髪入れずに99年「NW-MS7」というメモリースティック(64MB)型プレーヤーをリリース。
ただし著作権保護を徹底させるため、MP3非対応とし、また独自開発したATRAC系(正確にはATRAC3)のコーデックに固執した。当時はすでに米国発のP2P「ナップスター」による問題が囁かれ始めていたころである。ネットを使いコピーされた音楽MP3が自由にやり取りされるという「野放図」が、著作権侵害であるのは至極当然である。しかし現実問題としてMP3はネット環境における音楽データのデファクトスタンダードとして確立しており、これに背を向けることは巨大な市場を失うことも意味する。とはいえ世界に冠たるエクセレントカンパニーが違法コピーを助長するわけにはいかず、またソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)という有力な音楽企業を擁する身でもある。こうした矛盾にソニーは2000年代の大半を苦しみもがく。まさに「ハムレット」の心境といったところだろう。
実際、このメモリースティックウォークマン(NWウォークマン)では、MP3をATRAC3にエンコードするソフトを付けることで対応しようとした。しかし作業が煩雑な上に音質が低下するため、とりわけヘビーユーザーにはすこぶる不評で、この怨恨が後々まで「ウォークマン不信」として残った、と指摘する向きも多い。
こうした混乱の間隙を突く形で、MP3に対応したiPodが登場。ソニー側がこれに本格的な反撃の狼煙を上げたのは、何と4年近く経過した04年にリリースしたHDD型NWウォークマン「NW-HD1」から。ただしこれも相変わらずATRAC3を踏襲したタイプで、MP3に慣れたユーザーには不評だった。さすがのソニーも「iPod一人勝ち」を看過できず、この年戦略を一変、MP3対応への〝解禁〞を打ち出すのである。
しかしウォークマンの低迷の背景には、こうしたハード・ソフト的なテクノロジーの部分ばかりではなく、もっと広範な「仕掛け」、つまりは「いかに手軽に音楽を楽しめるか」というグランドデザインについて、アップルの方が数段上手だった、と見る向きは多い。
例えば、携帯デジタル音楽プレーヤーはPCを通じて音楽データをダウンロードするが、PC側で楽曲をリッピングしたり転送したりするソフトを俗に「ミュージックボックス」と呼ぶ。ウォークマンでは「Sonic Stage」、iPodでは「iTunes」がそれだ。そして後者の場合、女性や初心者でも直感的に分かる使いやすい味付けに徹している。これに対して前者は使い勝手が悪く、いかにも「玄人向き」といったスタイルである。
また、iPodの場合、このiTunes を使いネット上で楽曲を購入できる「iTunes Music Store」を設立。後に映画やTV番組、iPod向けの各種アプリケーションの販売までも網羅する「iTunes Store」へと進化させている。アップルにとって「iPod」は自社製品の販売に消費者を誘う「ポータル」であり、これを通じて、PCやiPhone、iPadの購入・利用につなげていこうとする壮大なビジョンが存在する。つまりハード、ソフト、サービスが横串で貫かれているイメージである。
では翻ってソニーの場合はどうかというと、ウォークマンにこれほど大きな戦略の〝尖兵〞となることは求めていない。言うなれば「偉大なる音楽プレーヤー」どまりだ。
ただ、こうした時代の流れで、音楽レーベルを抱えるとはいえ頑なに著作権保護にこだわる姿勢は、エクセレントカンパニーである「SONY」と評価できる点だ。企業の理念とは何かを問いかける課題といえよう。
iPodの台頭でウォークマンの低迷は続いているが、様々な対抗策がここへきて功を奏し始めているのか、はたまた低価格によるシェア奪取策が効き始めたのか、2010年に入ってからウォークマンの国内シェアは徐々に盛り返し、8月には週間販売台数でついにiPodを上回っている。
●悲願のNW化へ
このように今回はソニーの蹉跌を取り上げたが、これは同社が依然として日本、いや世界を代表する先端的AV機器メーカーであり、「SONY」というブランドは圧倒的だからでもある。裏を返せば、技術に対する妥協を一切許さず、単に「売れればいい」という安易な手法に陥らない、ある意味「職人集団」であることが、ブランド価値を高め、そして維持しているともいえるだろう。
「良いも悪いもSONYの名が新聞に載らなくなったら終わりだ」とあるソニー社員は強調する。つまり何かと注目されるのが「ソニー」であり、ある意味「強さ」なのである。
しかし、インターネットが急速に発達し、AV機器もかつてのような「機器づくり腕の見せ所」から、搭載されるソフトへと比重が移りつつある。極端な話、昨今の据え置き型PCのように「世界中から部品やデバイスを集めればかなりの品質のものが拵えられる」という現象がAV機器にも押し寄せている。世に言う「AVデジタル機器のPC化」だ。そしてこうした時代的変化の中で、ソニーをはじめわが国の電機メーカーが、体質改変を迫られているのも、また事実だろう。そんな中ソニーは米グーグルと広範な戦略提携を結び、加えて「ネットTV」に本腰を入れるなど、悲願の「NW化」の実現に向けて大きな一歩を踏み出した。果たして吉と出るか凶と出るか、「AV帝国」の一挙手一投足に当分目が離せないだろう。
※『IT批評 1号 特集:プラットフォームへの意思』(2010年12月刊行)より深川孝行さんの「ソニー 蹉跌の系譜」を転載
『IT批評』
http://shinjindo.jp/contents/it.html

■関連記事
アップルと任天堂のUI思想(立命館大学映像学部教授サイトウ・アキヒロ)
揺れるネット社会の規範――求められるIT教育は?(大賀真吉)
ソーシャル・ジャーナリズムの可能性(ジャーナリスト 岩上安身)

