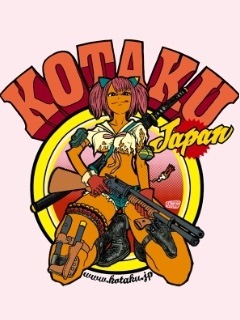ライアン・ゴズリング主演最新作映画『オンリー・ゴッド』が1月25日(土)に公開されます。そこで今回は、『ドライヴ』に続き、再びライアン・ゴズリングとタッグを組んだ、ニコラス・ウィンディング・レフン監督にインタビューして参りました!
【大きな画像や動画はこちら】
デンマーク出身のニコラス・ウィンディング・レフン監督は、24歳の時に撮った、借金地獄に陥る麻薬密売人を描くバイオレンス・スリラー『プッシャー』で大成功を収め、以降、トム・ハーディー主演の実在の囚人の半生を描いた『ブロンソン』、ライアン・ゴズリング演じるドライバーの生き様をクールに描くクライム・サスペンス『ドライヴ』などの作品で、高い評価と多くのファンを獲得しています。
しかし、レフン監督は第3作目の『Fear X』で(評価は高いにもかかわらず)興行面で大失敗したために負債を抱えます。そして、大変な苦労を経験しながらも復活を遂げているのです(当時の様子は、『プッシャー』のDVDに特典映像として入っているドキュメンタリー映画『ギャンブラー』に収録)。
そんなレフン監督の最新作『オンリー・ゴッド』は、タイ・バンコクの裏社会に生きる男ジュリアン(ライアン・ゴズリング)が、彼の兄を殺した謎の男チャン(ヴィタヤ・パンスリンガム)を討てと、母親に命じられることから始まるクライム・ドラマ。監督には今作の話を中心にお聞きしました。
――今作でご自身にとって何か新たな試みはありましたか?
ニコラス・ウィンディング・レフン監督(以下、レフン):まずは女性。あと、性機能障害も新しい要素ですね。子を支配する母親像を描けたのも面白かったです。私は自分が撮ってみたいものを映画にすることが多いんです。映画を作る度に、別のタイプの作品にしようとしています。私は結果よりも、その過程のクリエイティブな部分を楽しんでいるんです。
――監督の映画の主人公は裏社会の人物が多いですが、彼らのような人々を主人公にする理由はなんですか?
レフン:自分でもよくわかりませんね。誇張された現実の一つの典型なのだと思います。シェークスピアの王侯貴族の話のように、我々の身の回りを写す鏡のような誇張された、現実でありながら、我々のものではない世界。ファンタジーであり可能性の世界。それこそがドラマです。
私は犯罪ファンではありませんし、実際、犯罪の現場を見たこともないので、そのようなことをほとんど知りません。しかし、死の可能性がある世界に興味を持っています。そこにはドラマがあふれていますからね。
――今作には『ヴァルハラ・ライジング』や『ドライヴ』と共通する雰囲気やテーマを感じます。その観点で見ると、主人公はジュリアンではなくチャンなのではないかと思うのですが、これは意図的なのでしょうか?
レフン:その通りです。『ヴァルハラ・ライジング』、『ドライヴ』、そして『オンリー・ゴッド』のキャラクターは別の見た目で登場しているだけで、中身は同じ人物です。
『ヴァルハラ・ライジング』ではマッツ・ミケルセンが、見た目から「ワン・アイ(一つ目)」と呼ばれる、過去のない男を演じました。『ドライヴ』ではライアン・ゴズリングが、行動から「ドライバー(運転手)」と呼ばれる、過去のない男を演じました。
そして『オンリー・ゴッド』では、ヴィタヤ・パンスリンガムが警官を演じていますが、彼は今までの男たちのような呼ばれ方をしていません。それは神が、彼にチャンという名前を持つことを許したからです。
私はこのキャラクターが大好きで、また彼の映画を撮りたいと思っています。誰が彼を演じるかはわかりません。わかっていることは、次の舞台は東京だということだけです。
――今作の舞台をタイに選んだ理由はなんですか?
レフン:あまり予算がなかったからです。タイでは手頃な費用で撮影ができますからね。加えて、西洋人から見て、ビジュアル的に強く異国を感じさせる世界を探していたというのもあります。
バンコクはとてもユニークで、昼は西洋的な街でありながら、夜は完全にアジア的な街になります。そこで映画を撮るということは、私からすると、まるでおとぎ話の世界を写しているかのようでした。
――それぞれのシーンはセットではなく、タイに実際にある風景なのでしょうか?
レフン:美術にあまりお金をかけられなかったので、可能な限りほとんどそのままを撮っています。もちろん、イスや壁紙などは変えたりしました。壁紙はなんといっても安いので、たくさん使いましたね。シーンのほとんどはバンコクのチャイナタウンとゲイクラブで撮っています。
――ムエタイ選手の像が登場するシーンなどを始めとして、多くのシーンで握り拳が強調されていましたが、どんな意味が込められているのでしょうか?
レフン:拳を握りしめた状態の腕は、非常に原始的な男性のシンボルです。そして、握り拳自体は原始的な暴力行為を明確に表したものでもあります。さらにそれは、ストーリーが展開する中で、ジュリアンが母親との関係に問題を抱えているため、去勢される必要性に気づき、その結果、暴力へ向かうということも表しています。
この映画全体で、握り拳は性と暴力を。そして、手のひらを開くのは、非常に宗教的な服従を意味しています。
――ムエタイを登場させたのも、ムエタイが宗教的な側面を含んだ格闘技だからでしょうか?
レフン:私は格闘技のことはほとんど知らないんです。なので、「タイだから、ムエタイ」としただけです。しかし、そう決めた後で、ムエタイに関して沢山学びました。その中で行われる儀式やその戦い方にとても魅力を感じましたね。
――ムエタイが登場する中、チャンは剣を使いますよね。なぜ、彼には剣を持たせたのでしょうか?
レフン:あれはタイで処刑に使われていた剣のレプリカで、クールなアイデアだと思ったんです。ヴィタヤをチャンに配役した当初は、彼が剣道の有段者であることは知りませんでした。なので、まず最初に「この役は剣の使い方を練習をする必要があるよ」と伝えたんですが、彼は「素晴らしい、もう使い方は知ってるよ」と言っていました。
私は剣の練習は大変だろう思っていたので、これはラッキーでしたね。最初に会った時は、彼は太っていました。そのため、彼は1年半かけて体重を落としたんですよ。
――そのチャンが、犯罪者を処分した後にカラオケに行くというシーンが繰り返し登場しますが、この流れにはどのような意味が込められているのでしょうか?
レフン:西洋ではカラオケはお酒を飲みながらやるものです。しかし、タイではカラオケをもっと真剣でした。私にはそれがちょっと馬鹿馬鹿しく思えたんですが、チャイナタウンへ行ったとき、とても変わったクラブを見つけたんです。
そこでは、クラブの中で中国人の男性が、中国語で民謡のような曲を歌っていました。彼は他の客に囲まれているにも関わらず、まるで自分のためだけに歌っているかのように歌っていたんです。私の目にはそれが非常にタイ的で、素晴らしい光景に感じられました。
また、様々な宗教において、歌には罪を清める意味があります。そこで私は、チャイナタウンのクラブで歌っていた人は、もしかしたら罪を清めるような、深い意味のある行為を行っていたのではないか? と考えたんです。そこで、『オンリー・ゴッド』では、暴力行為の罪を、祈りを捧げるかのように、歌うことで清めています。そういった意図で、カラオケのシーンを入れました。
――ジュリアンの母親がストリップバーで、マッチョな男たちがポーズを決めるのを見るシーンがあり、思わず笑ってしまったのですが、あれにはどのような意図があったのでしょうか?
レフン:私も笑えるシーンだと思いますよ(笑)。バンコクのゲイクラブへ行った時に思いついたシーンです。その店ではタイ人のボディービルダー風の男たちが舞台に上がるんですが、その客は日本人の女性たちでした。
それを見て、「凄い、なんて歪んだ構造が生まれてるんだ!」と感じて、映画に使いたいと思ったんです。絵を描くようなもので、アイデアがやっている内に生まれてきました。どうして好きかはわからなくても、とにかく何らかの意味を感じたんです。
ジュリアンの母親はすべてを性に関連付け、それがたとえ自分の子供であっても、貪り食います。性における親と子に関係は非常に複雑です。多くの古代ギリシャの物語はそれらを分析しようとしましたが、その関係は理解するのが困難です。それらは男性の目線から見た父親が原因となる性機能障害の話ですが、それが(今作のように)母親が原因で息子に起る性機能障害となると、より難解になります。
――監督の作品はいつも音楽が印象的ですが、毎回どのようにして選んでいるのでしょうか?
レフン:音楽は、心の中にある感情を引き出すことができると思っているので、私は色んなタイプの音楽が好きです。しかし、楽器もできないし歌も下手なので、かわりに映画をある種の曲のように作っています。
例えば、『ブロンソン』が曲だとしたら、ペット・ショップ・ボーイズが歌うでしょう。実際、あの映画を作っている時にはずっとペット・ショップ・ボーイズを聞いていました。
『ヴァルハラ・ライジング』は静寂の映画で、私が撮った映画の中で唯一、現代が舞台ではない作品です。なので、楽譜のあるものは使いたくありませんでした。そこでドイツのアインシュテュルツェンデ・ノイバウテンのような曲を入れました。日本でいうと、メルトバナナみたいな雰囲気ですね。メルトバナナも大好きなロックバンドです。
『ドライヴ』は、クラフトワークです。レトロなビートを刻むエレクトロ・ミュージック初期の雰囲気。そして、『オンリー・ゴッド』はタイの北部にあるイーサーン地方の伝統音楽です。イーサーン音楽は、今作の音楽を担当したクリフ・マルティネスが教えてくれました。今作はそこからインスピレーションを得ています。
――監督の作品では、一枚絵のようなかっちりとしたシーンが連続しますが、構図は事前に考えるのでしょうか?
レフン:ストーリーボード(絵コンテ)を描いたりはしません。実際に現場に行って、私が見たいものを探します。これはフェティッシュなピンナップ写真を撮る感覚に近いのかもしれませんが、私はより原始的に、朝起きた時に「今日はこれが見たいな」と思ったものを撮っているんです。
――監督は映画をストーリーの時系列に沿って撮るそうですが、その理由はなんですか?
レフン:クリエイティブな部分が成り行きに従わざるを得なくなるからです。多くの映画は、マニュアルに従って、パズルのピースをはめていくかのように機械的に撮影されます。しかし、私はそのやり方は非常につまらないと思います。
自分は、どのような過程で最終地点に至るかが分からない方が好きなんです。いわば、セックスをするようなものですね。どのような結末に至るかは知っていても、どうやって結末に向かうかはわかりません。時系列順に撮ると、すべてが頻繁に変化していくので、その変化に従うしかないんです。
――今後の作品ではどのような挑戦をしようと思っていますか?
レフン:色んなジャンルのものをやりたいですね。映画を作り始めた頃はとても若かったですが、今は年をとって、子供も生まれて、より頭も冴えるようになりました。その過程で好みが色々と変わったように、これからやってみたいことも変わっていくと思います。
――以前、ゲームを使ってストーリーを語ることに興味があるとおっしゃっていましたが、それは何故ですか?
レフン:私自身はゲーマーではなく、娘がやるのを見る程度なのですが、ゲームは非常に魅力的だと思っています。なぜなら、見ている側がキャラクターがどのように行動するかを決めるなど、より能動的に参加できるからです。ゲームではどんなものであれ、その環境に入り込み、自分を操作するという一人称的な体験をします。
映画は、見ている側が頭の中で決断を迫られたり、そのキャラクターの動機を理解しようとしますよね。基本的にゲームも同じような道具ではありますが、映画はゲームのように機械的にキャラクターにジャンプをさせたり、パズルを解かせることはできません。また、芸術はより精神的なものですが、ゲームはプレイヤーを芸術のそういった部分に触れやすくさせることが可能です。このような点に魅力を感じています。
――監督の次回作、『アイ・ウォーク・ウィズ・ザ・デッド(原題)』はゾンビ映画なのでしょうか?
レフン:『ウォーキング・デッド』は大好きですが、ゾンビ映画ではありません。ここ10年ほど、ずっとホラー映画を撮ろうと思ってきました。そして今、本格的にやるよう、自分に半ば強制しているんです。どうなるかはわかりませんが、コメディにはならないでしょう。
でも実は、今度はコメディ映画を撮ろうとライアン(ゴズリング)と決めているんです。我々はよく話をするんですよ。
――ライアン・ゴズリングは俳優を一時休止するといった噂もありましたが?
レフン:彼は辞めませんよ。もっとお金が必要ですからね。今彼は一本映画を撮っています。インターネットに書いてあることを全部信じてはいけませんよ(笑)。
変態行為を行うシーンですら、いちいちカッコよかったライアン・ゴズリングが、俳優を引退しないようなので一安心。これからもレフン監督と仲良く映画を作っていただきたい。彼の初監督作品であり自ら脚本も手がけたダーク・ファンタジー映画『ハウ・トゥ・キャッチ・ア・モンスター(原題)』の公開も楽しみですね!
映画『オンリー・ゴッド』は、2014年1月25日(土)新宿バルト9ほか全国でロードショー。
(傭兵ペンギン)
関連記事