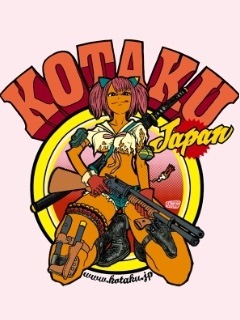過去を振り返ると、SFには女性のロボットが多く登場します。これはなぜなのでしょうか?
【大きな画像や動画はこちら】
以下より、io9のチャーリー・ジェーン・アンダーソン記者による考察をどうぞ。「脚本家が男だからだろう」なんて野暮なことは言わず、じっくり読んでみてください。
なお、本記事には映画『エクス・マキナ』、『her/世界でひとつの彼女』、ドラマ『ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ』、『PERSON of INTEREST 犯罪予知ユニット』などのネタバレが含まれています。

本来、性別は必要ない?
---------------------------------------
1927年、フリッツ・ラング監督のディストピア未来都市を舞台にした映画『メトロポリス』が公開され、「映画至上最も美しいロボット」と言われるアンドロイドの「マリア」が生まれました。彼女が人々に与えた影響力は凄まじく、その証拠に彼女の出現以降、ヒューマノイドを想像する際に「女性だったら...」と発想させるようになったのです。
『地上最強の美女バイオニック・ジェミー』の戦闘ロボットや『宇宙家族ジェットソン』のお手伝いさんロージー、最近だと『サラ・コナー クロニクル』に女子高生の姿をしたターミネーターや、『her/世界でひとつの彼女』のOS音声が女性の性別を持つAIとして登場しています。
しかし、よく考えてみれば、人工知能に性別は必要ありません。極端に言えば、肉体すら不要なのです。
---------------------------------------
『ターミネーター』のT-800や『エクス・マキナ』のエイヴァなど、AIを持つロボットには人間の女性や男性の姿形をしたものが数多く存在します。
観客もそういったことが当たり前という認識ですが、io9のチャーリー・ジェーン・アンダーソン記者は「実際のところAIに性別は必要ない」と主張。にも関わらず、何故女性AIが多いのでしょうか......?
---------------------------------------
体が必要な場合があるとすれば、それはある種のタスクをこなすことを目的としてデザインされた場合。つまり、AIに性別が必要な理由は、人間との相互関係にあると考えられます。事実、AIの性別はユーザーに起因していることが多いです。AIが己の目的のために男性や女性のアイデンティティーが必要とされる唯一の理論的な理由は、法もしくは道徳により人間らしくなる必要があるからと考えられます。
コンピュータが話す相手によって性別を選ぶ様子が最も興味深く描写されているのは、1966年に出版されたロバート・A・ハインラインの『月は無慈悲な夜の女王』でしょう。この作品に登場する高性能コンピュータのマイクには、ミシェールという女性人格があるのです。
---------------------------------------

この透けた体にこそ魅力が詰まっている
---------------------------------------
近年公開された『エクス・マキナ』にはAIのエイヴァが登場します。エイヴァは元バレリーナのアリシア・ヴィキャンデルが演じており、その身体能力を最大限に発揮し、動きは完璧すぎるほど滑らか。それに加え、見とれるほど美しい動きと潤んだ大きな目、囁くように穏やかな声をしています。
ストーリー中盤、人工知能のエイヴァを人間らしくする上で、女性らしさがどれほど重要なのかということ、また人間と相互関係を結ぶ上で、そのフェミニズムが純粋に存在しているものなのか? という話題が出ます。
エイヴァの体は、有名なIT企業の社長であるネイサンという男性によって創造されたもので、彼女が持つアイデンティティーは外面上の女性らしさと関係がありません。彼女は課せられた試験をクリアするために、その女性らしさを最大限利用しますが、それ以外に女性である理由は特に見当たらないのです。
---------------------------------------

ダンスと性サービスを提供するこの女性は一体...?
---------------------------------------
本作は男性色の強い作品であり、ケイレブとネイサンというタイプの異なる男性2人の女性に対する態度は、エイヴァとの相互関係を通して観客に伝えられます。エイヴァは彼らの態度を映し出すレンズにすぎません。
しかし、『エクス・マキナ』において発生する多くのドラマは、エイヴァのチューリング・テストの相手として選ばれたケイレブが、AIのエイヴァを「苦悩の乙女」と見てしまうだけでなく、その麗しい外見に性的な魅力を感じてしまうという事実から発生するのです。これは人工物との関係の確信と言えるでしょう。
私たちは、例えAIがより複雑で異なる概念を持っていると理解していても、そのユーザーインターフェースを「彼ら自身」として見たいと感じているのです。
---------------------------------------
確かに、AIの外見は、製造者が作った容器にすぎません。しかし、あまりにもAIの行動や思考、仕草が人間と変わりない場合、その外見を「製作者の意図を反映させた作り物」と切り離して、AIのアイデンティティーとリンクさせずに考えるのは難しいと思われます。
---------------------------------------
官能的なダンスを披露した『メトロポリス』のマリア以降、1960年代を迎えるまで、ガイノイド(人間の女性に似せて作られたヒューマノイド)はほぼ登場していません。しかし、60年代の「性の革命」と同時期に、人間を誘惑するロボットが多く描かれるようになりました。
70年代になると、「フェムボット」という言葉が一般的に使われるようになり、テレビシリーズの『地上最強の美女バイオニック・ジェミー』では、顔面を剥がすと機械の顔が露わになる美しい女性ロボットが登場。彼女を通して、ロボットの持つ残酷さは、女性らしさで隠すことができると視聴者にインプットしたのです。
優秀すぎるエリート妻を持つ劣等感の塊の夫たちが、妻たちの脳に「従順ワイフチップ」を埋め込んで、大人しくいつも笑顔で従順で常日頃からドレスアップし、いつなんどき求めても熱いセックスに応じるロボットにしてしまうという恐ろしい悪夢を描いた『ステップフォード・ワイフ』(2004年にニコール・キッドマン主演でリメイク)のロボット妻は、文化的象徴にもなりました。
80年代になると、空山基が描いたエロティックでメタリックな質感の女性が火付け役となり、セクシーなイメージのガイノイドがブームになります。
『チェリー2000』や『ときめきサイエンス』といった映画では、より性的魅力を持つ人工女性が、『ブレード・ランナー』や『EVE/イヴ』にはセクシーかつ暴力的なガイノイドが描かれました。また、女性ロボットはミュージックビデオにも多く出演するようになりました。
---------------------------------------
多くのポップカルチャーが「AIが人間に牙を剥くようになったら...」というテーマを扱う中、今やSF映画だけでなく様々な場面で女性ロボットを目にします。
殺人ロボットやコンピュータが女性の場合、私たちはその女性らしさに「魔性」を感じ、不安を覚えるとアンダーソン記者は語っています。一方、女性AIの中には母親や秘書といった役目を担っているものもいますが、この場合、女性の形にすることで、観客にそのロボットの有能性や脅威の無さをアピールしているとのこと。
---------------------------------------
小説の中には女性AIの在り方をユニークに表現しているものがあります。例えば、エイミー・トムスン著の『ヴァーチャル・ガール』では、メインキャラクターが肉体を得た時にキーボードやカメラ、プリンターといった周辺機器と変わらない扱いを受けるのです。
---------------------------------------

人間界によく溶け込んでいたキャメロン
---------------------------------------
『ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ』の女子高生ターミネーターであるキャメロンは、彼女の持つ少女の外見にアイデンティティーがリンクしています。
彼女は外見のモデルとなったアリソン・ヤングの人間としての生活を「記憶」しており、バレエのレッスンを受けたがるのです。また、ジョン・コナーと性別に帰する関係を築く際、それがジョンをコントロールしようとしている上での行動なのか? といった、キャメロンにとっての具体的な意味が観客に明確に伝えられない形で描かれました。
「女性ロボットとの性的関係」という点において、近年で最も印象的だった女性AIキャラクターは、おそらく『her/世界でひとつの彼女』に登場したスカーレット・ヨハンソン演じる「人工知能型OS・サマンサ」ではないでしょうか。
彼女は音声だけの存在にも関わらず、ホアキン・フェニックスに対して積極的に愛を持って接しており、擬似セックスを行い、肉体の代わりになろうとしたのです。(それだけでなく、彼のキャリアのサポートをして本の出版や人生における重大な決断までさせてしまいます。しかし、最終的にはその親密すぎる関係に終止符を打つべく、サマンサは自分の意思で「移動」していきました。
---------------------------------------

ハッカーは「マシン」を1人の人間として扱っていた。
『her』ではOSを人間の女性のように扱っていますが、『PERSON of INTEREST 犯罪予知ユニット』では全く正反対のアプローチをとっています。
---------------------------------------
このドラマに出てくるのは、アメリカ国内の全ての監視カメラや個人所有の携帯電話、パソコン、銀行口座の情報を把握する「マシン」。
精巧にできたこのAIは、人間よりも優秀で会話も成り立ち、意思も持っているにも関わらず、登場人物のほとんどがマシンのことを「それ」と呼んでいます。マシンのことを「彼女」と呼ぶのは、熱狂的なハッカーであり拷問や殺人を平然と行う異常者で、マシンに強い執着心を持つルートただ一人なのです。
人間ではないものを、接する側の態度次第で「人間と同等」もしくはそれ以上の存在にする分かりやすい例が『ラースと、その彼女』でしょう。
シャイで女性と話すのが極端に苦手な田舎町の好青年ラースが恋人として選んだのはアダルトサイトのリアルドール「ビアンカ」。ビアンカはリアルドールなので、もちろん自分の意見を言う、自らの足で行動するといったことはありません。しかし、ラースとビアンカの周りの人々がビアンカを1人の人間の女性として受け入れることをきっかけに、動かないリアルドールが次第に意思のある人間の女性のような存在感を放つようになっていくのです。
さて、ここで『エクス・マキナ』に話を戻しましょう。あの映画が素晴らしい要素の1つに「不気味の谷現象」の描き方があります。
「不気味の谷現象」とは、人間がロボットに対して親近感を持つことは不可欠であるにも関わらず、人は「人間に近い」ロボットを奇妙に感じてしまい、親近感を持てないといった、人間の感情的反応に関するロボット工学上の概念(Wikipedia参照)ですが、エイヴァにはこの現象が該当しません。というのも、彼女が最も魅惑的に見えるのは彼女が機械部分を見せている時だからです。
映画の終盤で、クローゼットの中に仕舞われた全裸の女性が映し出されますが、彼女らはまるで肉の塊のよう。一方のエイヴァは機械部分が見えているにも関わらず、性的魅力に溢れています。エイヴァの性的魅力とは、その光り輝く不自然さにあり、そんな彼女との性的なふれあいはネクロフィリアに近いと言えるかもしれません。
---------------------------------------
アンダーソン記者は、最後にこう締めくくっています。
---------------------------------------
つまり、人間とのつながりが必要な場合を除いて、そもそもAIに性別が必要ないと考えるとするならば、女性ロボットや女性AIの物語とは、共有することのできない「入れ物」に対して私たちが抱く感情や不安感を投影した「警告のおとぎ話」に思えてならないのです。
---------------------------------------
※注:元ネタは、io9のチャーリー・ジェーン・アンダーソン記者がワールドコンの「The Gendered AI」というパネルに強い影響を受けて書いたものです。
[via io9]
不気味の谷現象[Wikipedia]
(中川真知子)
関連記事
- 確定申告を高速化! 全自動のクラウド会計ソフト「freee」で16連射すると...?
- コンビニで買える! 支払い地獄を避けられるVプリカギフトの天使な使い方
- スタートアップ企業がやるべき 「PRを駆使した伝え方」とは