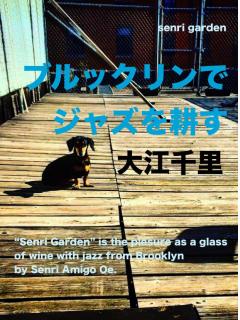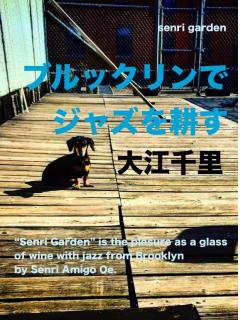「ちゅるちゅるちゅるちゅる」
冬の訪れ。壁の下方を這うチューブの中を暖かいお湯が滑る。その音が聞こえると「ああ、冬だな」と思う。夜明けに聞こえるこの音で「また一年が過ぎた」そう思うと同時に今月も路頭に迷わずこの部屋で暖かく過ごせることに心で手を合わす。
摂氏マイナス7度のシカゴから帰るとNYはすっかり秋を深めた装いだった。それが「Snow Storm(雪嵐)が来るよ!」という友達のメールで一気にスワッと沸き立った。ついさっきまでLAの山火事の話をしていたのだ。
NYに戻るとまずモレを食べる。メキシコの歌謡曲をジュークボックスで聞きながらポロ(チキン)のモレを食す。赤と緑のスパイスは赤唐辛子とハラペーニョ。白いんげんのピューレとあわのようなご飯。それをトルテイーヤで包んで口に放り込む。5 stars!
時差ボケのせいで味の感覚が遅れる。じわっと後から来るスパイス。格別。
夜早い時間に就寝。なので夜明けに目覚める。一日どこでいつ眠たくなってもおかしくないような気がするので、なるだけ椅子に座らず、何かに集中できるように仕事を目の前に置いて片っ端から片す。眠ると勿体無い。
ぴもシカゴがかなりの重労働だったようでずっと蛇のように丸まってソファで寝息を立てている。でも一応ダディが動くと「また次の旅が始まった? 置いてかれないようにしないと」とそわそわする。じろ?
そんなある日。久しぶりに会う友人とアッパーイーストサイドのフレンチへ。
この店のバーで気軽に集って軽いご飯を食べようという魂胆。本当に予約すると懐を気にしないと大変な結末になるこのレストランも、普段使いのバーでの会食だと僕でも行ける。
友人もサンフラン、ダラス、サンテエゴ、ハワイと旅をして体内時計がわけわからなくなっているはずなのに、人懐っこい笑顔で、僕のグラスにシャンパンを勢いよく注ぐ。乾杯!
僕はカツレツを頼み、赤ワインを嗜み、二人はあちこち話に花が咲く。ブルックリンに住んでいるのでこのアッパーイーストサイドの店での振る舞い方がわからない。膝が破れたジーンズに野球帽。TシャルはぴちゃんTシャツ。どうやらそれが奇異に見えたらしく隣の女性が話しかけてきた。
「失礼になったら許してくださいね。あなたは何をやっているの? そんな格好でこのレストランにいるって普通じゃないわ」
「ああ、僕は音楽家なんですよ。ジャズをやっているんです」
ワイン、音楽、旅、国籍、、いろんな話が始まった。
彼らは(彼女と彼女の彼)スイスからついさっき到着したばかりなのだった。空港からここへ一直線。
「ここへ帰って来ると、ああ、NYに戻ってきたって思えるの。時間も戻る。感覚も戻る。最高よ」
僕はちょっと緊張していたけれど、ブルックリンに戻ると同じことを思う。だから彼女の言う「最高よ」に乾杯した。メニューに自分みたいなものを見つけはしゃぐ。水菜のサラダか。オレ!
心が深い場所で通じる嬉しさで店を出た後、僕はいつもよりたくさんの距離を歩いてマンハッタンを縦に横切った。友達がくれたいい時間が遠くになればなるほど、胃の中のフレンチがこなれていつもの自分に戻る。寂しいような嬉しいような。
ふと、夜空を見上げると、見慣れない「浅黒い鉛色」をしていた。
翌日、目がさめると外は雪景色だった。雪が降るとすぐに除雪車で片すのでNYの雪景色はなんだか愛想はないけれど、季節外れの雪はどこか、まだそぐわないせっかちさとべちゃっとしたテキスチャーが妙に愛らしかった。11月の落ち葉が泣き腫らした頬に落ちたツケマのようだ。
とけ始める歩道の雪の中でそれは一瞬宝石のようにきらめいた。
家に帰るとまたいつになく眠たくなりベッドに怠惰に横たわる。そしてあの、あの「音」で再び目がさめる。
「ちゅるちゅるちゅるちゅる」
暖かいお湯がチューブの中を走り始める。ニューヨークに住む人たちを温め勇気付けるこの音。冬が来た。これを聞きながら再び僕はうつらうつら目を閉じる。2回目の夢の入り口へ。
気がつくとぴが僕の体に自分の体をくっつけて「ふう」とため息をついていた。
文・写真 大江千里 (C) Senri Oe , PND Records 2018