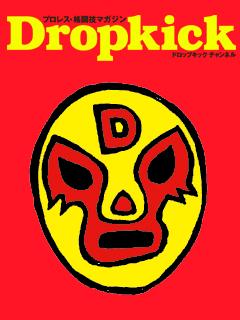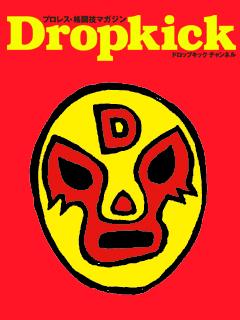 Dropkick
Dropkick
小橋建太とその時代——小橋が三沢に勝ったのは、ヒョードルvsノゲイラと同じ月だった
きっと年間ベストバウト、年間ベスト興行の最有力候補になるんだろう。5月11日、日本武道館で小橋建太の引退興行が行なわれた。
内容に関しては、もうみなさんご存知のことと思う。ハヤブサの開会宣言。引退セレモニーには川田利明も来た。メインは約40分の激闘。小橋の負担を軽くするための8人タッグなのかと思ったら、そうではなかった。それだけの時間、それだけの人数が必要なくらい小橋のプロレス人生が長く、深く、濃く、それに重いものだったってことなのだ。
いやもう、ツイッターで情報を見てるだけでも泣きそうになった。ツイッター見てたってことは、僕は会場に行ってない。そりゃ見たいに決まってるが、何か気が引けた。「俺なんかが行くのもどうなのか」という気分。好きか嫌いかなんて聞かれるまでもなく小橋のことは好きだけど、でもやっぱり、僕は熱心なファンとは言えなかったからなぁ、と。
80年代の一時期、プロレスを“定点観測”しなくなっていた僕がファンに戻ったきっかけは、深夜にたまたま見た全日本プロレス中継だった。伝説のブリティッシュ・ブルドッグスvsマレンコ兄弟。涙が出るくらい感動したのを覚えている。
そのとき、若手の有望株だったのが小橋だった。解説の馬場さんに器用貧乏と言われながらひたすら頑張る姿が印象的だった。90年代、天龍が抜けた全日本で、小橋はどんどん存在感を増していく。
ただ、小橋の真の黄金期、四天王プロレスからノアでの活躍となると、また僕は定点観測しなくなっていた。“そのとき家にいて、夜中も起きてたら見る”くらい。見たらもちろん引き込まれるんだが、毎週見るというわけではなかった。凄すぎて引いてしまうというか、果てしなくエスカレートする危険な技とカウント2.9の連続に、怖さを感じたのだ。プロレスにおいて危険な技をかけるということは、危険を承知で相手が受けるということ。「そこまでやっちゃっていいのか。他のやり方があるんじゃないのか。ヤバいんじゃないのかこれ」と、どうしても(感動しながら)思ってしまう。
仕事がメチャクチャ忙しい時期でもあった。いまはいろいろ自分のペースで調整できるようになっているけど、20代、30代前半のころはもうやみくも。ひたすら取材に行って原稿書いて徹夜してという日々。なかなか仕事以外のものに気持ちが向かなかった。
僕がメチャクチャに仕事してた時期というのは、つまり格闘技ブームだ。K-1がドーム興行を行ない、PRIDEが人気を博し、魔裟斗が登場した。そういう時代だ。そしてその時代が、小橋の全盛期にも重なるということになる。
小橋のキャリアをちょっと調べてみた。三沢光晴とのタッグで最強タッグに優勝(世界タッグ戴冠)を初めて果たしたのが1993年。K-1とパンクラスとUFCがスタートした年だ。三冠ヘビー級初戴冠は96年。ノア旗揚げの2000年には、PRIDE GPで桜庭和志vsホイス・グレイシーが実現している。
ヒザの手術と欠場を経て復帰した小橋が三沢を下し、GHC王座を獲得したのは2003年の3月だった。同じ月に行なわれたのがエメリヤーエンコ・ヒョードルvsアントニオ・ホドリゴ・ノゲイラのPRIDEヘビー級タイトルマッチ。小橋は連続防衛を果たして“絶対王者”と呼ばれることになったが、それはREBORN期のPRIDEと同じ時代だったわけだ。
もの凄く大ざっぱに歴史を語るときには、90年代後半から00年代前半は“格闘技の時代”ということになる。格闘技が大ブームとなり、プロレスが衰退した、とされる時期だ。ミスター高橋本の影響も忘れるわけにはいかない。
でもじつは、そういう時期に、プロレス史に残る名レスラー・小橋建太が全盛期を迎え、とてつもない名勝負を連発していたわけだ。ずっと見続けたファンからしたら「プロレスが落ち目だなんて誰が言いやがった」って気持ちだったんじゃないか。
小橋が格闘技や格闘技ブームについてどう考えていたかはわからない。ただ、小橋とそのライバルたちがやってきたのは、格闘技が盛り上がる中で“プロレスでしかできない表現”を突き詰める作業だったんじゃないかとは思う。UWF時代の前田日明が天龍のプロレス、その体を張った迫力に危機感を抱いたという話は有名だが、小橋たちがやっていたのも、格闘家が「これは真似できない」と思うプロレスであり、ファンが格闘技に“引け目”を感じないプロレスだった。
プロレスにしかできないことをやる。プロレスにしかないエモーションを引き出す。それを“王道”というのかもしれない。しかし小橋たちは、王道を突き詰めた果てにおそろしく先鋭的なプロレスに行き着いた。“王道”は“普通”という意味ではなかった。いや“普遍”だから“先鋭”に行き着いたのか。
小橋建太は歴史に残るレスラーであり、時代を象徴する先鋭的なレスラーでもあった。プロレスを突き詰め、突き抜けた。だからこそ、その輝きは永遠のものになる。(橋本宗洋)
2013/05/15(水) 12:34 帰ってきた二階堂綾乃イラスト&コラム「電車で突然キス」
2013/05/18(土) 10:17 好調な米女子格シーンの裏メインテーマ「ラウジー vs サイボーグ」への道■MMA Unleashed