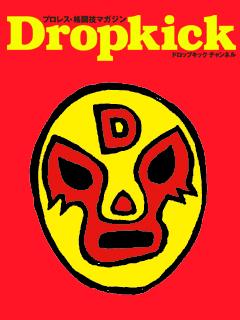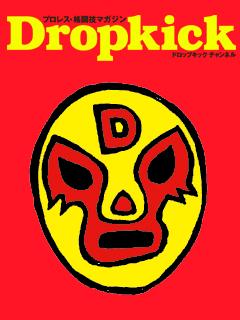唐突にスタートした「総合格闘技が生まれた時代」シリーズ。まだプロレスと格闘技が交じり合っていたグレーな時代。MMAがバーリトゥードと呼ばれていた時代。UFCやK-1、パンクラスが産声を上げた1993年という奇跡の時代。ペドロ・オタービオを武藤敬司がタコ殴りにしていたハチャメチャな時代……プロレスが格闘技に変換していくダイナミズムに満ち溢れたあの時代を振り返っていきます。最初のゲストは元修斗ウェルター級王者にして、青木真也や北岡悟を輩出したことで知られるパレストラ東京の設立者、中井祐樹先生です。
――今日は中井先生に、総合格闘技がMMAと呼ばれるようになっていった現在までのお話をうかがいしたいのですが、その土台となった修斗の浦田(昇、日本修斗協会会長兼コミッショナー)さんが先日、お亡くなりになられました。
中井 コミッショナーがずっと闘病をされていたことは知っていましたが本当に残念です……。寂しいですけど、これからも気を引き締めて格闘技のために尽くしていくしかないと思ってます。いま僕自身はプロ修斗の運営に関わってはいませんが、格闘技に携わる身としてコミッショナーの教えを粛々とやっていくしかないですよね。コミッショナーを失なったことで修斗はまた違うものになってくと思うんですよ。それは残された人たちがどう描いていくかで変わっていくでしょうし、現実、浦田コミッショナーこそが修斗だったと思います。修斗の創始者である佐山(聡)先生からも信頼されていたコミッショナーが修斗の象徴だったんですよ。コミッショナーの戒名には「修斗」という2文字が入ってましたが、それは本人が望んでいたと遺族の方から聞きました。
――浦田さんは旧UWF時代から携わってきたわけですし、格闘技に対する思い入れの深さは他人に計り知れないでしょうね。
中井 そのUWF時代につながりがあった藤原(喜明)さん、高田(伸彦)さん、山崎(一夫)さんも告別式に来られてましたね。あと川尻(達也)くんや五味(隆典)くんの姿もありました。修斗でチャンピオンだった彼らがUFCという世界の舞台で活躍してることはコミッショナーも喜んでいたと思いますよ。
――中井先生がその修斗で活躍されていた頃と比べると、総合格闘技の環境はガラリと変わってきてますね。
中井 いやあ、凄いことになってますよねぇ。でも、絶対にこうなると思っていたんですよ(笑)。それは自分が携わってきた修斗の手によるものではなかったかもしれないですけど、あのときに思い描いていた格闘技のかたちにはなっているので。自分としては「もっと時間はかかるのかな」って思っていたし、日本の団体ではなくアメリカ主導ではありますが、総合格闘技が広まっていくのはこういうことだったのかな……と。
――いま日本の格闘技市場は冬の時代と言われたりしますが、大局的に見ると、総合格闘技というジャンルが目まぐるしく発展していく過程は肌で感じてきたわけですね。
中井 はい。かつてPRIDEを楽しんでいたファンだったり、いま総合をやろうとしてる方からすれば「あんまり盛り上がってないのかな……」と思うでしょうし、たしかにメディアの取り上げられ方には昔と差はあるのかもしれません。でも、大局的に見れば、これも普及の一つのかたちだと考えていますね。もう試合レベルもとんでもないことになってますから。それはビックリですよ。やっぱり昔は「見える範囲」の世界だったわけですから。
――見える範囲と言いますと?
中井 総合をやってる人たちが見える範囲にしかいなかったので。それこそ三茶のシューティングジム(スーパータイガージム)にしかいなかったわけですよ(笑)。
――総合格闘技は三軒茶屋だけの文化! なんだかオシャレに聞こえますね(笑)。
中井 いまや総合をやってる人は世界の隅々までにいるわけですし、世界の頂きは相当の高さになってるわけですよ。いやあ、本当に凄いことになったなって。
――中井先生をはじめ、タイガージムに来るような方々は熱狂的なプロレス少年だったりするわけですから、当時格闘技とプロレスとの線引きが曖昧だったことに愛憎入り交じるところはあったんじゃないですか?
中井 そうですねぇ……。ボクはプロレスが大好きで、中学を卒業したらUWFに入ろうとしてたんですけどね(笑)。
――「中学卒業→プロレス入り」の発想は正しいプロレスファンのあり方ですね!
中井 ハハハハハ。でも周りから「高校くらいには行け!」と言われて不貞腐れてレスリングを始めたんですけど。そんな高校生活を送って大学に進んで高専柔道に出会ったりしてるうちに「格闘技をやりたいな」と思うようになって。あの頃『格闘技通信』ができたりしましたけど、あの雑誌はUWFとリンクしてたじゃないですか。
――空手やキックの文脈ではなくUWFムーブメントからの創刊でしたね。
中井 でも、(第二次)UWFは自分は理想とする格闘技とは違ったんですね。ボクは「ファイトをスポーツにしよう」という佐山先生の考えに惹かれてシューティングジムに入門したんですけど、やっぱり当時はプロレスとは愛憎半ばする感情はあって。いまはフラットなんですけど。日本のMMAはプロレスとのリンクなしでは語れないところはありますが、ボクはリアルファイトであるという前提で進みたい気持ちが強かったので。
――UWF系側が当時を回顧すると、興行を軸にして徐々に競技化を目指していくというものになりますけど、中井先生はそんなU系の動きをどう見ていたんですか?
中井 もともと佐山先生もその方向だったのが、途中で路線変更をしてアマチュア会員に教えることによって裾野を広げていくようになって。佐山先生のように選手をやりながらジムをやるのは当時としては画期的なことだったと思うんです。ジム経営ってアニマル浜口さんや栗栖正伸さんくらいじゃないですかね。
――プロレス界の二大虎の穴ですね(笑)。
中井 そこはプロレスファンとしてチェックしてましたね(笑)。でも、総合格闘技を教えるジムは例がなかったんじゃないですか。当時は「新格闘技」と呼ばれていてそれがのちにシューティング、そして修斗と名前は変わるんですけど。独自のやり方で確立していったのは間違いないんですが、佐山先生もUWFの中でシューティングを実現させたかったと思うんです。そこらへんのことは佐山先生と詳しい話をしたことはないから定かではないですけど。
――佐山先生とはそういった会話はされなかったんですか?
中井 いやもうジムに足を踏み入れたら簡単には口はきけないですよ。
――佐山先生と弟子の関係性を表すものといえば、YouTubeのシューティング合宿動画がありますけど。いまあんなハードな指導をしたら大変な騒ぎになりそうですね。
中井 ……世に残っちゃいましたよね(苦笑)。
――残ってしまいました(笑)。あのスパルタ指導があたりまえだったんですか?
中井 いやいや、そんなことはないですよ。特別合宿やトップの選手を指導するときのものだと思います。あの映像は私がシューティングに入門する1年くらい前のものなんです。ボクは先生に「あの練習をやってください!」とお願いしたんです。
――直訴してましたか(笑)。
中井 でも、ボクが入った頃は先生は半分燃え尽きていたと思うんですよ。シューティングに1期や2期の選手を送り出した安心から落ち着いていたんですね。ボクが入った頃は合宿とかはなかった時期で、それでも日々の練習はあって佐山先生の特別練習もあったんですけど。ボクはなんとかしてあの地獄の合宿をやりたかったんですけど、先生は「あれはやるほうもシンドいんだ」って言ってたんです。
――佐山先生のエネルギーも半端じゃないですしょうね(笑)。
中井 あの指導はおそらく絵作りの部分もあったと思うんですよね。先生は「本物のスポーツにする」と覚悟を決めてやられてましたし、ボクはそこに興味がありましたから。そこなんですよね。プロレスにいがみ合う感情がなかったといえば嘘になりますけど、プロレスと切り離したところで「シューティングとはこういうスポーツなんだ」と世の中に伝えていかないといけませんでしたから。
――おのずとプロレスに対して過激な発言というのは飛び出しやすくはありますよね。
中井 そうですよねぇ。若いときにメディアに出た発言はそういうものは多かったと思います(ニッコリ)。
――ハハハハハ。昔はギラギラされてたんですね。
中井 そこは若気の至りではあります。世の中のいろんなことがわかってなかったりしたり。でも、そのときの本心ではあったので否定はしませんけど。いまでは思い出ですよね。
――そのギラギラ感って猪木さんの異種格闘技戦の熱から生まれてるするわけですね。
中井 去年の大晦日も猪木さんの興行があってそこで青木(真也)くんが使ってもらって。2年前の大晦日も猪木さんとのコラボだったじゃないですか。猪木さんは世間と向き合ってきたんだと思うし、異種格闘技をやって世間に認知させようとしていたと思うんですよ。その結果、80年代の新日本プロレスブームだったと思うし、いまにも繋がっていて。
――猪木さんの影響を受けた方々が独自に格闘技文化を担っていくのは面白いですよね。熱がありすぎて当時の選手や団体って中東の宗教戦争並に対立してたじゃないですか。
中井 あのときの状況は……いまのファンにはまったくわかってもらえないかもしれないですよね(笑)。それはもう一大物語で。
――最近のファンからすれば、あの時代のクライマックスのひとつとして安生(洋二)さんが前田(日明)さんを殴ったなんて意味がわからないですよねぇ。
中井 ボクらはああいう時代を生き抜いてきてるので格闘技に対するタフさが違うんですよ(笑)。もちろんいまの選手のほうが競技的には強いし、技術はあるんですけど、そこはあくまで競技の枠の中の話なので。当時はその枠を突破してアピールしないと生き残れなかったところはありますね。あの激動のときはそうやって生まれたんでしょうねぇ……。
――そんな中、1993年にUFCが始まったときはどうでしたか?
中井 グレイシー柔術のことは佐山先生がUFCが始まる前から口にしていたんです。「打撃は下手くそだけど寝技は凄く強いから」と。それは入門してデビューするかしないくらいのことなんですけど、(夢枕)獏さんとかからグレイシーのビデオが回ってきて佐山先生も見たんじゃないんですかね。
――獏さんは当時の格闘技ネットワークの中心人物でしたね。
中井 それで「中井もグレイシーと闘う準備をしとけ!」と言われてまして。でも、ボクは映像を見たわけじゃないので、たとえばオイルレスリングみたいなのイメージだったんですよ(笑)。
――そこはプロレス大百科的なイメージですね(笑)。
中井 UFCで初めてグレイシーを観て「これか、先生が言っていた奴らは!」と。ちょっと僕らとやってることは似てるようで違うもので。僕らは同じ用具でリングで闘いますけど、向こうは素手だったし、服装もバラバラだったし、闘う場所はケージでしたし。スポーツというより「どの格闘技が強いのか?」という異種格闘技戦の雰囲気で。実際にUFCはホリオンの発案で「グレイシーを売り込むため」のものでしたし。決して無視はできないなと思ってはいましたけど、UFCで闘うことは現実的ではなかったですよね。
――シューティングとは違う競技だ、と。
中井 そうですね。向こうの選手が日本に来てグローブをはめてリングで闘うかといったら難しいでしょうし、ボクはシューティングを認知させることで精一杯だったのでUFCに出ることは考えられませんでした。その中で市原(海樹)さんがいち早くUFCに出場されたことは凄いことだと思いましたよ。
――日本人として初めてUFCに出場されてホイス・グレイシーと闘いましたね。
中井 平(直行)さんも見に行ってますしね。ボクは下っ端の選手だったこともあるんですけど、そういった動きは現実的には考えてなかったですよね。
――UFC、いわゆるバーリトゥードとのリンクが現実的になっていったのはやはりバーリトゥード・ジャパントーナメントからですか?
中井 そうですね。UFCのスタートからヒクソン来日まで1年ちょいありますから。ヒクソン来日が決まってから視野に入ってきた感じですね。
――バーリトゥードとシューティングの大きな違いはどうのように分析されていたんですか?
中井 グラウンド打撃の有無の違いに気づかされましたね。いま思うとそれは大きな大きな違いだったんです。シューティングの公式戦にはグラウンドパンチがなかったんですけど、それによってサブミッションの質が変わってくるということにすらボクらは気づいていなかったんですよ。それを一回目のバーリトゥード・ジャパンで身を持って知ることになって。
――当時シューティングのチャンピオンだった川口健次選手や草柳和宏選手がまさかの一回戦敗退という現実があって。
中井 二回目のバーリトゥード・ジャパンにボクが出たときまでにそこは修正していった感じですね。テイクダウンのアプローチの仕方はそれほど違いはなかったんですけど、なんでもありの場合はパンチを被弾しないで進めないといけないので。
――いまとなってはグラウンドパンチの有無の違いは大きいですけど、当時はまだ……。
中井 やってる側でもわかってなかったんです。知らなかったんですよ。
――中井先生は一回目のバーリトゥード・ジャパン直後にバーリトゥードルールでアートゥー・カチャー戦を経験されたり、グランドパンチ解禁となった初の修斗公式戦で草柳選手と闘ったりしてましたけど、そこは日本格闘技界の歴史の転換点だったんですね。
中井 そこにはエンセン井上という援軍を得て急速に進んでいったんですね。エンセンはグレイシー柔術の教えを受けた人間なので。そのエッセンスを受け入れることは僕らがやってきた格闘技を否定された面もあったんですけど……そういう時代だったんですよね。
――葛藤を経て進化していったわけですね。
中井 もともと僕らがやってきたことにそれを足していく。そういったレジスタンスをやってる感覚はありましたよ。やっぱりグラウンドパンチはバイオレンスだと思っていたんです。「このスポーツを世に広めるときにグラウンドパンチありだと見た人がどう思うかな?」と。当時の雑誌もそんな論調でしたしね。「こんなスポーツは認められない!」という声の大合唱でしたから。
――相手に馬乗りになったり、顔面を足蹴にする格闘技は野蛮である、というような。
中井 そこにも目を見張る技術はあるいう風潮に変わっていくんですけどね。それくらい当時の格闘技界は動揺はしていたと思うんですよ。そりゃそうですよね。自分がやってきたことが否定されるわけですから。
――それと同時に過激なものを見てみたい欲求も見る側にあったと思うんですね。
中井 そこで理解が進んだ面もあったんですよね。グラウンドパンチがあるから試合が面白く見えたでしょうし。だからまあ格闘技にとっては必要な痛みだったんでしょう。
――U系ではパンクラスがいち早く完全競技化していきましけど、そこにはどんな意識があったんですか?
中井 どの時期のパンクラスなのかによりますよね……。掌底ルールのときはまた違うんですけど。誤解を恐れずにいうと修斗ってオープンフィンガーグローブ(以下、OFG)のムーブメントだと思ってるんです。よくよく考えるとプロレスと別れていくきっかけはOFGというか、ナックルで攻撃ができるって基本プロレスの発想ではないと思うんです。猪木さんのナックルアローはべつとして(笑)。これが(ナックルを叩きながら)が僕らの持ち味だと思ってるんですけど、プロレス団体でOFGを最初に取りれたのはキングダムですよね?
――公式に導入したのはキングダムですね。
中井 そのときに修斗内部に「キングダムは脅威になるのか?」という話をしたんですけど、結論としては「さほどならないだろう」と。でも、キングダムという団体はなくなりましたけど、結果、桜庭(和志)選手を生んでそれがPRIDEのピースのひとつになっていったじゃないですか。自分の予感は当たってはいたんですね。
――OFGはプロレスとの決別の証というのは腑に落ちますね。
中井 それも原体験があって、猪木さんの異種格闘技戦を見ても猪木さんには打撃がないからファンで目線で凄く怖かったんですよ。モンスターマンの打撃に打撃で返せなくて、組むしか術がなかった猪木さんが不安だったんですね。ウィリー(・ウィリアムス)とやったときも怖かったし。当時は「猪木さんが負けたら俺が闘ってやる!」という気持ちがあったので子供の頃から打撃は必要だという考え方になったんですね(笑)。
――子供ながらにそんな分析を(笑)。
中井 打撃があれば、テイクダウンも簡単にできて腕十字も取りやすいはずだ、と。つまりボクシングができるアントニオ猪木が理想だったんですよ(笑)。プロレスリングは素手でやるものだからナックルがないのは仕方がないとは思っていたんですけど。やっぱりポイントはナックルですよね。UWFも結局、顔面パンチがなかったから、あのOFGこそが修斗の象徴なんです。でも、猪木さんは一試合だけOFGをつけてるんですよね。チャック・ウェプナー戦のときに。
――佐山先生の考案のものですよね。
中井 あの時代にOFGを付けて試合をやってるんですよ!(興奮気味に)。
――異種格闘技戦で毎回使用していたら格闘技の歴史は変わったかもしれませんね(笑)。打撃以外にも柔道やレスリングの技術を足していく発想をする方もいたでしょうし、猪木さんの異種格闘技戦ってある意味で格闘技の啓蒙活動にはなってたんですね。
中井 ボクもプロレス最強を信じていたひとりなので、そこで足らない部分を考えていたのはたしかです(笑)。スープレックスも相手に腰を落とされたらちゃんと投げられないと考えて実用的なテイクダウンになってきましたし。それがUWFで濾過されていったわけですよね。そうして総合格闘技がOFGをつけて闘うスポーツだと考えたらものの見事に広まったと思うんですよね……
「あの頃、PRIDEに対して複雑な気持ちだったことをいま思い出しましたよ」……葛藤する中井先生のインタビュー後編はコチラ
【語ろう学生プロレス】
「ガクセイプロレスラー・ライジング 卒業後のリアルなリング」今成夢人インタビュー