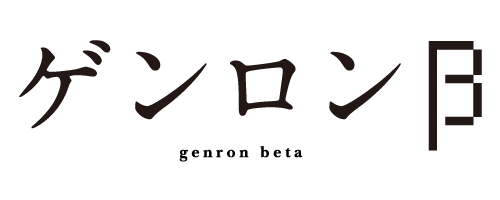
9
2016年12月9日号
編集長:東浩紀 発行:ゲンロン
目次
- 『観光客の哲学』第2部「家族の哲学(断片)」より断章 東浩紀
- ポスト・シネマ・クリティーク #12 片渕須直監督『この世界の片隅に』 渡邉大輔
- 「ポスト」モダニズムのハード・コア――「貧しい平面」のゆくえ #15 黒瀬陽平
- 日常の政治と非日常の政治 #8【最終回】 「POST-TRUTH」の時代に 西田亮介
- 人文的、あまりに人文的 #8 山本貴光×吉川浩満
- 浜通り通信 #45 小名浜のヤンキーが見た「小名浜竜宮」 小松理虔
- フクシマ・ノート #11 戦後津島とDASH村、失われたふたつの浪江町「開拓史」 二上英朗
- 批評再生塾定点観測記 #5 状況・社会 横山宏介
- メディア掲載情報
- ゲンロンカフェイベント紹介
- 編集部からのお知らせ
- 編集後記
- 読者アンケート&プレゼント
- 次号予告
カオス*ラウンジ新芸術祭2016 市街劇「小名浜竜宮」に出品された村井祐希の作品《Omelet Embankment Section》の一部。中之作の海沿いにある清航館の前庭に展示された。スーパー堤防にヒントを得た大きくいびつな箱のような構造物で、シリコン樹脂で固めた絵の具を綱のように手繰りつつ、構造物の上に登ることができる。村井は『美術手帖』2016年12月号のアート界注目の新人100人を紹介する特集でも取り上げられている。
撮影=小松理虔
『観光客の哲学』第2部「家族の哲学(断片)」より断章
東浩紀
@hazuma
下記に掲載するのは、ぼくが現在執筆中の新著『観光客の哲学』こと『ゲンロン0』の第2部から抜粋した断章である。『ゲンロン0』は、『ゲンロン』の創刊準備号という立て付けになっているが(そしてそれが出ないあいだに『ゲンロン』はすでに4号が刊行されているが)、実質的にはぼくの書き下ろしの新著である。いまのところ2017年4月刊行の予定で動いている。
同著の一部は、本誌のバックナンバーですでに紹介したことがある(『ゲンロン観光通信 #3』『ゲンロン観光通信 #7』および『ゲンロンβ4』)。そちらを読まれた方はご存じのとおり、その時点では同著には「ですます」体の文章が採用されていた。というよりもぼくはこの数年、「ですます」での表現に強く傾いていた。しかし今回、あらためて、本誌に求められるもの、いまのぼくに寄せられている期待を熟慮した結果、完成稿は「だである」体に統一することとした。そのためにまた少なくない修正作業が発生しており、そのせいで刊行が遅れているが、そのぶん内容は読者の期待には応えていると信じている。
ぼくがこの本で試みているのは、ひとことで言えば、『存在論的、郵便的』以来の――『動物化するポストモダン』以来のではないことに注意してほしい――新たな主著を書くことである。ぼくはそんな本は書きたくなかった。ひとことで言えば面倒だし、だれが読むのかもわからないからである。けれども、たぶんそれがないと、というよりもだれかがそういう時代錯誤なことをやらないと、批評はもうさきに進まない。『ゲンロン4』の巻頭言を書き、「現代日本の批評」の共同討議を修正しながら、ぼくはそんなことを考えていた。
刊行を期待されたい。
■
第1章「家族の脱構築のために」より
第1部では、(1)21世紀の世界が、単数のリバタリアンな市場のうえに無数のコミュニタリアンな国民国家が乗っかっている二層の世界として捉えられること、したがって(2)現代の政治哲学の問題の多くが、その二層の原理の衝突として解釈できること、そして(3)そんな時代の「新しいよき市民」のモデルとして、ふたつの原理を往復する「観光客=郵便的マルチチュード」が想定できること、以上3点を明らかにした。「観光客」の存在から新たな哲学を構想するという本書の目的は、ここまでの議論であるていど達成されたことと思う。
第2部では、以上の結論のうえで、「不気味なもの」や「子ども」について考えるふたつの草稿を掲載する。ただし両者はあくまでも草稿で、第1部のようにはまとまった議論になっていない。
(……)
ふたつの草稿は、いっけんかなり離れた主題を扱っている。一方は情報社会の新たな主体について論じ、他方はテロリズムの罠からの脱却を扱っている。けれどもその両者は、本書のここまでの議論から必然的に導かれる、同じひとつの問いに関係している。それはすなわち、この二層構造の世界において、もしかりにリバタリアンな市場に生きる「ビジネスマン」の拠りどころが「個人」であり、コミュニタリアンな国家に生きる「国民」あるいは「市民」の拠りどころが「国家」あるいは「共同体」であるとすれば、観光客=郵便的マルチチュードの拠りどころはいったいなにになるのか、という問いである。
人間のアイデンティティをどこに求めるかは、政治思想の性格を大きく決定する。個人を出発点にすれば資本主義を肯定することになるし、共同体を出発点にすれば国家主義を肯定することになる。かつて共産主義なる政治思想が、個人でも国家でもない第三のアイデンティティとして、「階級」なる概念を提示したことがあった。というよりも、共産主義の革命性は、本当はこのアイデンティティの発明にこそあった。共産主義は階級に依拠していたからこそ、国家の存在を否定しつつも、個人の無秩序な自由の集積=資本主義を批判することができたからである。けれども、その共産主義は冷戦崩壊とともに影響力を失った。それゆえぼくたちはいま、リバタリアニズムとコミュニタリアニズムが正面からぶつかる、二層構造の世界に生きることになっている。
この状況を脱するためには、個人でも国家でも階級でもない、第四のアイデンティティの発明あるいは発見が必要である。ロシアの思想家、アレクサンドル・ドゥーギンは「第四の政治理論」の必要性を訴えている。彼によれば、自由主義は個人の思想で、全体主義は国家の思想で、共産主義は革命の思想であり、それぞれ一長一短があるがいずれも現代に役立たない。それゆえいまは「第四の政治理論」として、ハイデガーの「現存在」の再解釈に依拠した新しい思想が必要なのだという。
ドゥーギンは極右の体制派として知られ、この主張もロシアの地政学的拡張主義(ユーラシアニズム)と深く結びついており、ぼくはけっして彼の立場に同意するわけではない。そもそも「現存在」は、すでにいちど全体主義(ナチズム)にイデオロギーの要として利用されている。
しかし彼のこの整理そのものは有益である。(……)

