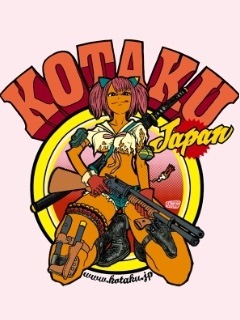『リング』でJホラーブームを世界的に巻き起こした中田秀夫監督が、元AK48の前田敦子さんと成宮寛貴さんを主演に迎えた最新映画『クロユリ団地』が5月18日(土)に公開されます。
そこで今回は、今作で再度本格的な日本式ホラー映画を作り上げた監督の中田秀夫さん、そして脚本を担当した三宅隆太さん(『呪怨 白い老女』『七つまでは神のうち』監督・脚本)、加藤淳也さん(『篤姫ナンバー1』、『王様ゲーム』脚本)にインタビューして参りました。
『クロユリ団地』に込められた思い、前田敦子さんの女優としての魅力、そして恐怖表現の奥深さがわかる言葉の数々は以下より。
【大きな画像や動画はこちら】
ーー中田監督は「『クロユリ団地』はご自身の作ってきたホラー映画の集大成」といったことをおっしゃっていましたが、このタイミングで作ることに何かきっかけや特別な思いはあったのでしょうか?
中田秀夫(以下、中田):プロデューサーから「オリジナルのホラー映画を」ということだけが決まっている段階で声をかけられました。ちょうど震災のドキュメンタリー『3.11後を生きる』の撮影中に今回の話をもらって、その時はすごく対極的なものに感じたんですよね。それでまあ......作るに至った理由はいろいろあります(笑)。
今回「10年ぶりのホラー」と言われていて、確かにしばらく自分が撮っていたサスペンス作品だったりミステリー作品だったりというのは、いわゆるホラーというジャンルの映画とは呼ばれないし、この世ならざるものは登場しないんですが、ヒッチコック的にサスペンス、スリラーという風にとらえると、ジャンルとしては分けられてしまいますけど、それほど違ったことはやっていないんですよね。
作り手として、僕は少なくとも「ホラーだからこうしなければいけない」と凝り固まるのは好きじゃないので、集大成と言っているのは次は違うジャンルのものを作りたいなっていう思いがあるのと、「これが区切りだよ」っていう意味があったりします(笑)。でも完成した時に集大成だとは思ったんですよね。別に今までの表現を踏襲して前見てやりましたといことではない意味で、集大成と言っていいかなと。
テレビドラマから数えると、ホラーというジャンルに関わって20年やってきて、ある種いろんな方から学ばせていただきながらここまできてるんですよね。怖い脚本家たちからの叱咤激励を受けながら作って、初号試写で大げんかになるくらいのことも過去にはあったわけです(笑)。そんなことを経てきているので、そういう思いをぶつけながらできた作品ではあります。
ーー今作は非常に豪華な布陣で製作されています。そして、Jホラーは世界的にも影響力の大きいジャンルです。そういった面で、製作に当たってプレッシャーもあったのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
三宅隆太(以下、三宅):それはそうです。やっぱり、Jホラーの末席に身を置かせていただく身としては、『リング』の中田監督の下で書かせていただく事自体がそもそもプレッシャーですからね(笑)。
でも中田監督は非常に気さくな方なので、早い段階で僕らのプレッシャーを取り除いてくれました。お陰で「どういう風に中田監督の期待に応えていくか?」という気持ちにシフトできましたし、気合も相当入りましたね(笑)。それに、今の日本映画界では、これだけの予算と規模でオリジナルのホラーを作るのはほぼ不可能です。これは絶好の機会だと、燃えました(笑)。
加藤淳也(以下、加藤):三宅さんもおっしゃいましたけど、今ホラー映画を作ろうとすると大体出ても2000万円の予算なんですよね。ひどいと1000万円以下の予算、3日間で撮るというのが一般的だったり。
三宅:3日というのは72時間ですよ。3日間寝ずにフル稼働ということです(笑)。
ーーそれは過酷ですね......。
加藤:それを当たり前とは言っちゃいけないんですけど、そういう状況で仕事してきたので、お話をいただいた時は「こんな良い環境の現場に参加させてもらっていいの?」って思いました。絶好の機会ですよね。
ーー今作では前田敦子さんが女優として非常に魅力的に感じられたのですが、前田さんの演技はいかがでしたか?
中田:撮影時はまだAKB48のメンバーだったんですけど、「女優、映画女優としてやっていくんだ」という決意の強さはすごく感じました。実際彼女はツイートしたりもしていますけど、今いろんな映画をたくさん見てますよね。
現場で僕は彼女に「いろんな監督が言うだろうけど、アイドル前田敦子ではなくて、アイドル前田敦子をそぎ落としてもそこに残る、繊細であったり、傷つきやすかったりする20代の女性としての前田敦子を全部ぶつけてください。あなたにしかできない明日香であってほしい。」というようなことを言ったんですよね。まあラフに言えば、型にはまらなくていいんだということを伝えたかったと。それを言ったら彼女も安心してくれました。
彼女は初めてのホラー映画主演で「どう大変な現場なのだろうか?」というのと、僕に対する会う前のイメージが「堅い」というのがあったみたいで、不安を感じていたみたいなんですよね。でも僕は堅くなる時もあるけど、ホラーは一発ギャグのような表現が「最恐」だったりもするわけです。『リング』の貞子が這ってくるとか、『呪怨』の俊雄がパンツ一丁で膝小僧を抱えているとか、あれだけを抜き出すと一発ギャグの世界で、実際テレビでパロディーにされることもある。だから「ホラーの現場はけっこう笑いが絶えないんだよ」っていう話をしたら彼女も安心してくれました。
とはいえ、彼女はアイドルとして画面の中心で見つめられてきた存在で、多くの人に見つめられてきた人というのは、演技の上手い下手に関わらずスター性というか輝きを持っているわけです。僕が関心したのは、集中力の高さ。なおかつ持続力もある。僕は大体最低でも5テイクまでやって粘るんだけど、最終的にワンテイク目を選んだりするんですよ。ところが彼女の場合は、テイクを重ねるたびによくなるので最後のテイクを採用する場合がかなりの確率でありました。そこは凄いなと思いましたね。
あと、泣いている芝居の時にテストでもう泣き出しちゃって、「まずい、この子はよく泣くとこで有名だった」と慌ててカメラ回したんですけど(笑)、彼女は2テイク目もちゃんと泣くことができるんですよね。そういった点で、ある意味では女優としてずっとやってきたわけではない彼女の良さが出たんじゃないかなと思います。
 左から加藤淳也さん、中田秀夫さん、三宅隆太さん
左から加藤淳也さん、中田秀夫さん、三宅隆太さん
ーーホラー映画というのは「どうしたら本当に怖くなるのか?」という分析と緻密な構築が肝心だと思うのですが、今作で特別気をつかった点があれば教えて下さい。
中田:僕はクライマックスですね。まああんまり詳しくは言わないほうがいいので(笑)、なんとか地獄のシーンと表現しますが、そのなんとか地獄の「なんとか」を作るのに三宅さんと加藤さんと何度も相談しましたね。ものすごく大変なことになってもいけないし、かといって怖くないといけないし......。そこはけっこう悩みましたし、難しかったです。「ありえへん中でも、ありえへんわー」というのを作りたかったので。
ーー三宅さんは以前ラジオで「ホラー映画のジャンルの裾を広げていくような表現を作品に入れている」とおっしゃっていましたが、今作ではそういった意識はあったのでしょうか?
三宅:確かにそれはありましたね。ただ、そもそもストーリー自体がまったく決まっていなかったので(笑)、まずは物語の手がかりを探るところから始めました。
色々と話し合ううちに、中田監督が、スウェーデン映画『ぼくのエリ 200歳の少女』が非常にお好きで、今回の企画も、どこか通底するものにしたいとおっしゃったんです。そこで「あの映画のどの辺りがお好きですか?」と訊ねたら、「孤独な魂が呼び合うところだ」と。そのお言葉から、今回の指針のようなものは見えた気がしました。
そもそも僕は、ホラーというよりも、心霊に強いこだわりがあります。心霊というと、「ユーレイでしょ」とか「オバケでしょ」となりがちだけど、いやいや、ちょっと違うんじゃないの、という。「心霊」の「心(しん)」というのは「心(こころ)」であるという点が重要だと思うんです。肉体的に生きてるか死んでるかに関わらず、ひとには「心」というものがある。「心」が持ち得ている微細さや複雑さ、心と心が関わりあったり、すれ違ったりすることから生まれる「心のドラマ」を、「恐怖という切り口」で描くのが「心霊ホラー」である、と。この辺りの考え方は、僕自身が心理カウンセラーの仕事をしていることとも関わってくるのかもしれません。
そういったこともあって、中田監督のおっしゃる「孤独な魂が呼び合う」物語をつくるのであれば、今回の主人公・二宮明日香も、多くの人が気づきにくい微細な心のバイブレーション」に気づくことのできる人物として描きたいと考えました。それには彼女自身が、今回の物語がスタートする以前から「恐怖」にまつわる大きな体験や記憶を持っていなければならない。そこをどう設定するかが勝負でした。「恐怖」は想像力を育む大切な感情です。恐怖を知らなければ他人の不安や恐れに気づくこともできません。傷つくことを知らなければ他人に優しくできないのと同じです。なので、今回の「ジャンルの裾野を拡げる試み」は、取り立てて何か新しいジャンルと混ぜようということではなく、元々本来「心霊」という題材の中にあるはずのものを、どうやって2013年に見ても新鮮なものとして描いていけるかがポイントだと思いました。
やっぱり、今の時代にいわゆるアメリカンなホラー映画のスタイルを無理に真似して、ワーキャーするようなものを作っても意味がないわけです。日本の観客にとって「恐怖の対象」になり得ないだけではなく、そこで描かれる「恐怖の質」自体を、観客がそもそも信じることができないんじゃないか? と思うんですよね。震災があったり、景気が悪かったり......ここ数年、日本では本当にいろんなことがありましたし、インターネットの普及や、核家族化が進んだことで、近隣の住人はもちろん、家族の中ですらコミュニケーションが難しくなってきている。そんな状況の中でも、「信じられるホラー映画」にしたい、と。
ーー今作では登場人物の抱えている孤独感が非常に生々しく、鑑賞していていたたまれない気持ちに何度もなったのですが、それは心霊への恐怖以外の感情を観客に与えようという意図があったのでしょうか?
三宅:今作に限らず、それはあります。例えば、心霊ホラーには必ず、「幽霊が見える人」というキャラクターが出てきます。霊能者のときもあれば、単なる高校生のときもありますが、いずれにせよ、そもそも「生きている人の心がわからない人に、死んでいる人の姿など見えるはずがない」と僕は思うんです。つまり、生き死にに関わらず「人間の心」を感じ取れるか否かは、霊能力の有無ではなくて、想像力の有無に左右される、と。便利で賑やかな世の中になればなるほど、人の心の微細な感情や想いには鈍感になりがちです。その点に関しては、個人的に大きな危惧を感じています。この15年間、心霊映画にこだわってきたのも僕の中にそういう思考があるからなんですよね。
ーー今回はそういった感覚が中田監督の出してきたテーマにバッチリはまったと?
三宅:そうですね。ドンピシャだと思いました(笑)。『ぼくのエリ 200歳の少女』も大好きな作品でしたしね。
ーー今作はアメリカでもすでに大きな注目を浴びていますが、Jホラーが世界的な評価を得ている要因はなんだと思いますか?
中田:ビジネス上で言うと、『Departed』という作品を手がけた韓国系のアメリカ人のプロデューサーがいて、彼の目の付け所が非常に上手かったというのが大きいです。作品面の話をすると、以前アメリカ人の15歳の少年から「あなたのホラー映画が好きです。そして、あなたのホラー作品を『Quiet Horror(訳:静かなホラー)』と称したい」と言われたことがあるんです。要するに、静かな間合いを重視するホラー映画であると。これは僕の映画に限らず、清水崇監督の作品だったり、『The EYE 【アイ】』だったりもそうなんですよね。
アメリカのホラーは、サム・ライミ監督が言ってましたけど、10分に一回ジャンピングスケアー、心臓が飛び跳ねるような恐怖があればストーリーはどうでもいいと。あくまでもプロデューサーとしての彼の意見ですよ。要はハロウィンの時のお化け屋敷のようなものを観客は見たがるわけだから、別にストーリーを見に来ているわけではないと。彼の言葉の要約としてはものすごく悪い言い方に聞こえるかもしれませんけど、それはそれで一つの考え方なんですよね。
そういったホラーに対してそうではないもの、まさに三宅さんが「心霊」とおっしゃったけど、僕らの作品はより日常に近いものを表現しているわけです。やっぱりアメリカ人、しかも若い観客から見て、Jホラーの恐怖感は目からうろこだったんじゃないですかね。「僕らが感じる身近な恐怖ってこんなことだよね」とか、先ほどの「心」という話にもつながっているんだと思いますけど、80年代のスプラッターに飽きた観客が90年代、何か違うものに飢えていたんだと思います。
三宅:スプラッターと呼ばれる「肉体破壊の見せ方」に重きを置いたホラー映画は、僕らが若いころ見ていたアメリカの映画にはたくさんありました。そういった映画群は特殊メイクなどの技術向上が素晴らしかった一方、あまりにも表現が「物理的」すぎたためにホラー映画にとって一番大切な「恐怖」という感情からはかけ離れていってしまった。視覚にだけ訴えかける手法が限界に来たんだと思います。じゃあ、その先は何なのか? そこに一連のJホラーと呼ばれる「物理的ではない表現」が中心の「心霊ホラー」が殴り込みをかけて成功したわけですが、僕は単なる「表現の物珍しさ」だけだったら、Jホラーはあそこまでのブームにはならなかったと思います。清水崇監督の『The Grudge』(邦題『THE JUON/呪怨』)だって、9・11より前だったらアメリカでは当たらなかったんじゃないか、と。
あの事件を経験したことで、多くのアメリカ人は、自分とは違う価値観の人たちが、自分たちが時間を前に進めている間にも、ずっと時間を止めたまま自分たちを恨んでいる可能性がある、ということを身をもって理解したんだと思います。そういった経験がなければ、目に見える物理的なものとは違う心の存在を意識する土壌がなかったら、『The Grudge』も「グンゼのパンツを履いた白塗りの子供が膝をかいているだけ」に見えたんじゃないか、と(笑)。
加藤:今ってやっぱり作りごとが普通に信じられなくなっている時代だと思うんです。アメコミヒーロー映画を見ても、「ヒーローになるためにはこうでなければいけない」ということをしっかり説明しちゃうんですよね。「作り物なんだからこれでいいじゃない!」とはなかなか言えない時代になってきていて、そういう意識がJホラーの恐怖と一致したんじゃないかと思います。
ーーJホラーの身近な恐怖が、想像力を刺激して、想像力を育むものとして非常に有効な時代になったことが大きいと。
三宅:そう思います。例えば、「日が暮れてから山に入ると妖怪に襲われる」という類の怪談は、かつて懐中電灯が無かった時代の子供たちへの警鐘です。「暗くなってから山道を歩くと、足を踏み外して谷へ落ちてしまうかもしれないから危ないよ」という教育的な配慮が基にあるわけです。闇を恐れなさい、自然を怖がりなさい、もっともっと想像しなさい、と。そういった教育的要素は、怪談からホラー映画へと引き継がれていった。映画館という暗闇の中で、恐怖を感じながら、学びながら、現実世界での危機管理能力をも高めていく。ホラー映画の役割というのは本来そういうものだと思います。
 チームワークバッチリ
チームワークバッチリ
ーー最後に、お三方が今までに見てきた中で最も恐怖を感じた映画を教えてください。
中田:職業的にホラー映画だったりドラマをやるようになってからは『たたり』とか、『四谷怪談』とかですかね。そういった作品は怖いという純粋な感情よりも、作り手として、映画オタク的な観点から見て好きですね。純粋に一番怖いと思ったのは、中学生くらいの時に立ち見で見た『エクソシスト』ですかね。『オーメン』も怖かったけど、やっぱり『エクソシスト』かな。
加藤:ホラー映画ではないですけど、怖くてもう一度見る勇気がないのは『震える舌』ですね。野村芳太郎監督の映画は全部怖かったです。
同じ野村芳太郎監督の作品だと、子供の頃テレビで『八つ墓村』を見たんですけど、最初の落ち武者の虐殺のシーンですでに見ていられなくて、それこそトイレとか行けなくなりました。ある程度大人になった時に、もう大丈夫だろうと思って見直したら、虐殺シーンも「特殊メイクじゃん」って冷静に見られて怖くなかったんですけど、逆に最後の(森美也子役の)小川眞由美さんがものすごいメイクで登場するシーンが怖くて怖くて(笑)。子供の頃にはなんとも思わなかったシーンなのに、大人になってから怖く思えたというのは面白いですね。
三宅:僕もホラー映画ではないんですが、『SF/ボディ・スナッチャー』っていう1978年の映画(フィリップ・カウフマン版)ですね。これは、寝ている間に周りの人間が宇宙人にのっとられて、価値観が入れ替わってしまうという話なんです。それで入れ替わっていない元の価値観の人間は指を差されて、「お前はこっち側に来てない」って叫ばれるんですよね。誇張して描かれてはいるものの、たった一晩で人間の価値観がひっくり返ってしまうというのは、現実世界でいつも起きていることです。そして、だんだんとひっくり返った人間が多数になっていって、元の人間は少数になってゆく。ようするに四面楚歌ですね。追い詰められた主人公たちは、諦めて寝てしまうことで多数派に取り込まれるか、あるいは信念を曲げずに、寝ないで頑張るかという選択を迫られる。
中田:嫌だねぇ(笑)。
三宅:ええ、本当に(笑)。この映画に一箇所すごく好きなシーンがあるんです。周りがみんな宇宙人になってしまっている中、主人公たちも無感情を装って、「多数派のあなたたちと同じ側の人ですよ」というフリをして敵陣を突っきるという場面。それって、生き残ってる仲間たちからすると、一見裏切っているように、正義に反しているように見えるんですけど、実は違ってて、本当の正義を勝ち取るために、ほんのいっとき、向こう側のフリをしてるだけなんですよね。この行動は正しい未来を見据えているからこそのものなんですけど、僕自身ものすごく影響を受けました。生き方や仕事の姿勢も含めて学んだというか。価値観を否定された時こそ、いっとき敵の言い分に乗っかったフリをして、むしろそれをチャンスに自分の価値観を貫き通すべきであり、その必要がある、と。『SF/ボディスナッチャー』は怖かったと同時に、生きる為の勇気をもらった作品ですね。
ーー本日はお忙しい中、ありがとうございました。
中田、三宅、加藤:ありがとうございました。
『クロユリ団地』は5月18日(土)公開。
(スタナー松井)
関連記事
- ボードゲームを500タイトル以上作り出したデザイナーが、アイデアを生む秘訣を語る! ライナー・クニツィアにインタビュー【後編】
- 【招待券プレゼント】『クロユリ団地』公開記念イベント「戦慄!絶叫!中田秀夫 崩壊前夜祭」開催
- 『洞窟物語』から9年、開発室Pixelの新作アクション『Gero Blaster』制作へのこだわりとは(インタビューあり)