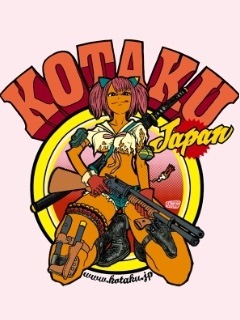ヤクザが伝染していくだけでは済まない、超展開ファンタジー・アクション映画『極道大戦争』。今回は本作を手がけた三池崇史監督にお話を伺いました。
【大きな画像や動画はこちら】
とにかくぶっ飛んだ内容となっている本作の製作過程でのエピソード、監督の役者起用法、筋肉論、監督にとっての面白い映画などについて語っていただいています。

全人類ヤクザ化!?
――「ヤクザが伝染していく」という設定はどのようにして生まれたのでしょうか?
三池崇史(以降、三池):新宿のロボットレストランに行って、その勢いで飲み屋に行ったら殺陣(たて)師が苦し紛れに、飲んだ勢いで出したアイディアで、イケるんじゃないかなと思ったんですね。
よく考えると怖いし、ヤクザからすると周りが全員ヤクザになったら困る。カタギがあってのヤクザなので、そういうバランスは崩れるなと。なんか勢いですよね。思いがけなく言った一言から話を作ろうという流れになりました。
――ヤクザの伝染に始まり、さらに想像を超える展開が続きますが、最初からあそこまで壮大なスケールの物語を想定していたのでしょうか?
三池:先ほどの飲み会の後に、『猫侍』などの監督で元々自分の助監督としてずっとついていた山口義高(本作の脚本家)が一旦プロットにまとめたんです。その時点からかなり走っていましたね。
これから監督して業界でやっていこうとしている人間の不安とか不満みたいなものが、ポンとはじけていたんだと思うんですよ。無理にはじける要素のない人がはじけた話を作っていくのではなくて、何かしらの理由があって炸裂する人たちを選んで、その人たちのパワーを借りながら自分も楽しみました。むしろ「まあまあ」と抑える側でしたね(笑)。
――超展開の嵐の中、意外にも戦闘はあまりトリッキーではない、シンプルな素手の肉弾戦が多いと感じたのですが、そういった演出には何か理由はあるのでしょうか?
三池:まずは日本刀を持った極道の闘いから、最終的には素手で決着をつけましょうという展開になりますよね。しかし、一方ではもっと戦うべき大きな存在がいると。そことの戦いには地球のためとか人類のためといった大義があるわけです。
でも、「俺とこいつ、どっちが強いんだ?」という闘いにも同じ価値があるべきだなと思うんです。僕らの世代で言うと、初めてブルース・リーを見た時の「肉体と肉体がぶつかって、それで映画ができるんだ」っていう感覚が残っているんですよね。あの時の驚きというのには未だに影響を受けているので、アクションは割りとアナログになりました。
――格闘シーンを撮る時に意識していることはなんでしょうか?
三池:格闘映画になりすぎないようにはしてます。アングル的にきれいに技をおさめすぎないようにとか、カットを割りすぎず、できればワンカットで全部いくようにするとか。なかなか安全の面や双方の身体能力の差もあるので、難しいんですけどね。
例え少しぐしゃぐしゃっとなっても、できれだけ一連で撮りたいというのはあります。なぜなのかはわからないんですけど、隙間というか間を残したいんです。映画的にいえば不完全なのかもしれないですけど、そういうところにアクションの本質があるような気がするので、あんまりビシビシとカットを割れない、割りたくないと思っちゃいますね。
――本作で日本映画デビューを果たしたヤヤン・ルヒアンさんは、まさしくワンカットの格闘アクションの凄まじさで名を上げた方ですが、本作での彼のアクションはいかがでしたか? 振り付けにも関わったのでしょうか?
三池:やっぱりすごかったですね。振り付けはこっちが作ったものをベースに、あくまでも出演者として、日本のアクションをリスペクトしてもらった上で、アイディアは出してもらいました。
「こういう流れからあと2発で倒したいんだけど、どういう技がある?」と聞くと、「これとこうだね」と返ってきたり。しかも、その時にアクション映画だったらこう、シラットだったらこうって答えてくれるんですよ。「じゃあ、シラットで」ってお願いしましたね(笑)。
――そこはシラットなんですね!
三池:アクション映画じゃなくて極道映画ですから(笑)。
もっと『レイド』でのヤヤン・ルヒアン的な動きを見せることもできたんでしょうけど、そっちの方向ではなく、あくまでも「狂犬」という役を演じてもらいました。今ではすっかり役者ですけど、彼は役者をやっていて格闘の勉強をしたのではなく、全く逆で、元々役者ではない人ですからね。
今回は「狂犬」という役としてのアクション、長引かせるつもりはない、一発でも早く倒したいというアクションの連続に徹してもらいました。そういったところは役者として楽しんでいたんじゃないかなと、現場では感じましたね。
――根性試しのような殴り合いのシーンは確かにヤヤンさんらしくなくて、新鮮に感じました。
三池):やっぱりあの状況だと技じゃなくて、どっちが最後まで立っていられるかが勝負だろうなというのがありましたね。ヤヤンさんとしてはどう決着がつくのかというのが当然気になりますよね。それでこういう風にしようと思っていると伝えたら、「それはいい」という感じで頷いてくれましたね。

主人公のヤクザ・影山亜喜良(市原隼人)と殺し屋・狂犬(ヤヤン・ルヒアン)
――監督は各作品で体格のいい、筋肉のある役者さんの体をほぼ必ず露出させる傾向にあると感じるのですが、そういった表現がお好きなのでしょうか?
三池:やっぱり世代的に「映画って本当に面白いな」と思ったきっかけの作品が『燃えよドラゴン』なんですよね。大して二枚目でもないブルース・リーが、当時小学6年生~中学1年生の人間にとっては神のような存在だったんです。
なぜ神なのかというと、動きもそうですが、その動きを制御する、コントロールする肉体に惹かれましたよね。実際にあれが闘える筋肉なのかどうかは別として、柔道には柔道に強い体型、相撲には相撲に強い体型、そしてジークンドーにはジークンドーに適した体型があると。極真空手の体型とは明らかに違う、無駄を排した体型ですよね。
市原隼人くんだったらボクシングをやっているので、肩のあたり、上半身の筋肉はボクサー的なんです。伊藤英明であれば、空から飛び降りたりとかサーフィンしたりとか潜ったりとか、オールマイティーに遊ぶために鍛えられた筋肉がついている。思いっきり遊ぶためにはあのくらいの肉体がいるわけです。もちろんジムで鍛えてはいるんですが、目的がはっきりしています。きれいに見せるためじゃなくて、遊ぶための筋肉を作っているんですよね。
健康のため、役者としてきれいに見せるためといった理由で鍛えた筋肉には惹かれないんですけど、「目的のある筋肉」はいいなと思います。それがあるのかどうかは役者を見て直感的に判断して、「これは見せましょうよ」とか言いますね。もったいないと思うんですよ、服を着ていることが(笑)。
筋肉フェチなわけではないんですけど、目的があって鍛えられた肉体って心意気の現れじゃないですか。何よりもその人のキャラクターというか性格が出る。役もそうですけど、それ以前に「その人が何者であるか?」というのを示していると思うんです。肉体表現者としては一番真価を問われるところですしね。金持ちだったら高いシャツを着ればいい。でも高いシャツを脱いで裸になったら金持ちには見えない。本作に関しては、まあヤクザにも色々ありますけど、裸になった時にヤクザに見えるかどうかというところですよね。
女性の場合、裸というとどうしてもポルノみたいな方向に見られてしまうのでなかなかできないんですけど、女優ももっと自由なことができれば、もっと面白い役がたくさんできるのにとは思います。女性はどうしても何かをまとっていないといけないので、女優としての限界というのはそこにあるんだろうなとも感じますね。
――伊藤英明さんが『悪の教典』では殺人鬼を演じたり、稲垣吾郎さんが『十三人の刺客』では鬼畜な役を演じたりと、監督の作品では、それまでの世間のイメージとはかけ離れた役柄を演じて成功する役者さんが多いと感じます。そういった大胆な配役は常に確信を持って行っているのでしょうか?
三池:まず芸能界で売れているということはかなり不満がたまっているという風に感じるんですね。伊藤英明で言うと、映画の中で人を助けすぎている。だからあれだけ殺す映画があっても許されるんじゃないかなと(笑)。
意識しているかどうかは別として、本人もどこかで思っている気がするんですね。自分のイメージを守らなきゃいけない、その守ろうとしている自分がつまらないといった、どこか不満を押し殺している部分がある。立場的に好き勝手はできないといった大人の気持ちがあって、でもその気持ちが嫌というようなものを抱えながらみんなやっていると思うんですよ。
となると、僕は役者が「自分はそうじゃないんだけど、監督がこの人だからしょうがないよね」という最初の言い訳に使える存在なわけです(笑)。三池の映画だから......というフリをしながら、本性を表すことができる、やりたかったことをやりたいようにやれるというのが、自分たちの映画では多いんですよね。
稲垣吾郎と最初に仕事をした(『十三人の刺客』の)最初のカットは全然台本にもないんですが、大名行列の途中で竹の筒にオシッコをするシーンで、それを撮ってもう終わりだったんですね。京都へわざわざ来てもらって、竹の筒にオシッコだけして「お疲れさま」でSMAPが帰るみたいな(笑)。その時の彼は「オシッコするだけ? 台詞もないの? もっとまとめて撮ると思ってた、面白い!」って笑ってるんですよね。
売れている人ほど本番とか舞台に立っている状況が日常になっているので、この映画の中に立っている自分は非日常という面白さを与える、奇をてらわず、こうしたら面白く見えるだろうなと計算したものではない状況を作ると、無理なく眠っている牙が出るんです。そういう作業はやっぱり現場としては面白いですよね。高島礼子さんにどういう不満があったのか? とかまでは僕にはわからないですけど(笑)。
何かを守ってはいるんですけど、同時に壊す集団であるという匂いがないと本当のエンターテインメントになっていかないんじゃないかという気がします。破壊する集団であるべきというか。自分で何かを持っている人にはもってこいなんですよね、自分を破壊できるわけですから。
そういう意味でも『極道大戦争』はリリー・フランキーさん始め、色んな人たちが色んな自分を破壊してますよね。逆に市原くんは昔から破壊しながらやってきているので、今回のような守る側に立つと光ってくる。閉じ込められている、囚われている役にピッタリだと思います。
影山(市原隼人さん)は杏子(成海璃子さん)を、そして世界を守れるのか?
――本作は、そういったキャラクターたちによってストーリーが転がっている印象を受けました。実際のところ、ストーリーとキャラクターのどちらを軸に製作していったのでしょうか?
三池:やっぱりキャラクターがこういう人だから、こういう展開になっていくというのが正しいと思います。話をこう持っていきたいがために彼はこう言うとか、そのためにこういうキャラクターがいて、こういう行動をとるとかではなく、バラバラっと出てきた人間たちがガッと集まったら、こういう話になっちゃったという。それは脚本上でもそうですね。勢いで作っています。
原作があるといった、映画的な制約からも開放されている作品なので、ある意味行き当たりばったりな、乱暴な作り方です。だからこそできる映画で、そういうのも面白いと思うんですよね。今回はそれに徹したというか、徹することを許してくれました。普通の会社だったら止めますよ(笑)。大人が映画を作ろうとして許されることではないです。まず、あの脚本を読んで「おっ、いいじゃん!」って言うのは日活しかありえません(笑)。
しかも、この映画誰に見せようとしているんだ? っていうのもありますよね。今どきはこうだから、ここの層を狙っていこうというのもあんまり考えていないですから。自分たちが何を見たくて、作りたいかどうかというのが中心にあるという。でも、これが映画のあるべき姿だとは思いますね。
――「サヨナラ、軟弱で退屈な日本映画」といったコメントをされていますが、三池監督にとって「強硬で面白い映画」とはどういった作品でしょうか?
三池:一番好きなのはポール・バーホーベン監督の『スターシップ・トゥルーパーズ』ですかね。あの作品を見た時の喜びは大きかったです。あくまでもハリウッド映画として見たんですけど、監督によってハリウッドもここまで変えることができるんだと感じたので。
もちろん面白かったんですけど、あの無茶苦茶っぷりには「なんだこれ!」ってなりましたからね。しかも金をかけて作って、世界中で絶賛と顰蹙を買いまくるという。後にカルト的な人気が出たとはいえ、当時はどちらかというと顰蹙のほうが数的には多かったと思います(笑)。
あと、『スターシップ・トゥルーパーズ』はデジタル初期の作品ですが、宇宙空間で宇宙船がバリバリ割れていくCGの美しさは凄いなと思いました。あれより美しいCGってあんまり見たことがない。無茶苦茶さとそういうものが色々と混ざっているんですよね。それがパート2になるといきなりローバジェットになって、また違う意味で「なんだこれ!」と度肝を抜かれて(笑)。
そういった「なぜこれが生まれたの?」っていうものに対する尊敬の念はあるかもしれないです。やっぱり同じアイデアでも作るスタッフによって、全く違ってくるというのは、作っている側としては心地いいんです。同じようなものがたくさん出てくると、自分たちが存在する意義ってあんまりないような気がしてしまうので。だから、たまにこういう勇気を与えてくれる映画が出てくると嬉しいんですよね。
『極道大戦争』は6月20日(土)TOHOシネマズ新宿ほか全国ロードショー。
(C) 2015「極道大戦争」製作委員会
(スタナー松井)
関連記事
- 確定申告を高速化! 全自動のクラウド会計ソフト「freee」で16連射すると...?
- コンビニで買える! 支払い地獄を避けられるVプリカギフトの天使な使い方
- スタートアップ企業がやるべき 「PRを駆使した伝え方」とは