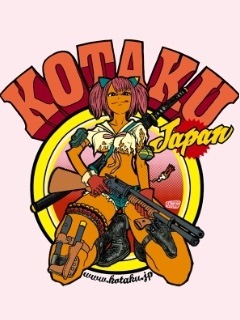行方不明となった猫を探す盲目の少女を主人公にしたゲーム『Beyond Eyes』をご存知でしょうか? 目の見えない主人公が周りの音などから頭の中で作り上げた景色を元にプレイする、一風変わった感動のゲームとなっています。
【大きな画像や動画はこちら】
以下より、米Kotakuクリス・スエレントロップさんのレビューをどうぞ。
やりがいはあるものの、時に不快な『Beyond Eyes』は、主人公が盲目というユニークなゲームです。主人公レイは盲目の少女のため、プレイヤーもゲーム内で見ることができません。
しかし、直接「見る」ことができない代わりに、レイは音や匂い、触感などを通じて周りの世界を可視化していきます。時折遠くで鳴く鳥の声、鐘の音色、それらが聞こえるときは遠くにかすかな光景が浮かび上がります。
しかし、普段はレイの周りのとても近い位置しか可視化することはできません。一寸先は広大な未知の白い世界が広がっています。
盲目でない者にとって、目が見えない状況を『Beyond Eyes』がどれだけうまくインタラクティブに描けているのかはわかりません。レイに関して書き加えると、彼女は事故で見る術を失ったという設定で、彼女の周りに可視化される世界が実際のものの形や色が元になっていることも、それで説明がつきます。
生まれつき盲目の人はレイのように周りの情景を心に描くのかどうかはわかりませんが、本作ではゲームの中で視界を奪われる感覚を与えることに成功しています。
なお、レイが聞こえていると思っているものが、常に現実と合致するとは限りません。物干し紐に近づいたと思ったらそれが案山子になったり、木でキツツキが鳴いているかと思えば、それが歩行者用信号機だったりといったことも起きます。
私はあまりゲームでは心を動かされないのですが、『Beyond Eyes』のクライマックスには感動しました。しかし、ゲーム全体としてはそこまで好きではないというのも正直なところです。それがゲームのせいなのか、私のせいなのかはわかりません。
このゲームで思い出したのは、数年前のニューヨーク・タイムズ・マガジンのエッセイでした。それは、現在「Slate」の文化面の編集長をしているダン・コイスさんによる『文化の野菜を食べる』(Eating Your Cultural Vegetables)というもの。
そのエッセイの中で、コイスさんは自身の「意欲的な」文化との関係を分析していました。コイスさんにとってそれは、ゆっくりとしていて難しく、すぐに理解できるものでも、簡単に理解できるものでもありませんでした。そこでコイスさんはケリー・ライヒャルト監督の映画『Meek's Cutoff』を挙げています。
本作はニューヨーク・タイムズの映画評論家A・O・スコットさんが「新鮮なオリジナルさ」、「タフで静かな体験」と熱狂的なレビューをしていた作品です。加えておくと、私がこの映画を2011年にマンハッタン、アッパー・ウエスト・サイドのアートシアターで見た時には、クレジットが始まるとともに観客がブーイングしていました。
コイスさんにとって、この映画は見る価値のあるものでしたが、後から振り返ってみて初めて価値がわかる類のものでした。「つまり、直感的に好きな作品だったわけではなく、見て以来何度も何度も思い返して考えてしまう」、「しかし映画鑑賞時には自分の席にじっと座ってスクリーンに集中するのが難しかったです。風に吹き荒らされた高原から別の高原へと長い時間をかけてオーバーラップしていく中で、私の思考は様々な方向へと歩み去っていきました」。
このコイスさんのエッセイは、私が『Beyond Eyes』をプレイして感じた感覚そのものでした。レイはゲーム中の大半を、行方知らずになった彼女の猫探しに費やします。パステルカラーの水彩風景の中を彼女が探索していくのは、私にとって単調さとフラストレーションが交互にやってくる体験でした。
自分で操作する中、猫の鳴き声が聞こえる方向にレイがゆっくりと向かい、レイの手がフェンスや並木に触れると、そこで初めて行く手を遮るものが可視化されます。
実際に盲目になったら、大変でしょうし、フラストレーションも溜まるでしょう。その点で『Beyond Eyes』は成功していると言えます。
しかし、「文化のほうれん草」(ゲームのほうれん草も含む)の愛食家と公言する自分は、(昔のボスで雑誌編集長のマイケル・キンズリーさんの言葉を借りれば)そのほうれん草がチョコレートアイス味であった方がずっといいと考えます。例えば『Journey』とか『Popo & Yo』、『The Talos Principle』とか『dys4ia』とかいった作品の方が良いということです。
しかしその一方で、コイスさんがこう書いていたのは正しくもあります「文明化された映画鑑賞者として私が頑なに信じているのは、私の短い注意力持続時間を無視したような映画作品を見れば、その作品は私の退屈の下に穴を掘り、それがずっと心に残る印象を形作るということです」。
世の中には「文明化されたゲーマー」なんて存在しないと考えるバカもいますが、彼らこそが馬鹿者です。もしもゲームが、私達が考えているゲーム像へとなりつつあるのであれば、そこには『Beyond Eyes』のようなゲームの居場所だってあります。
私達が「難しい」ゲームについて話すときには、大抵は『スペランキー』や『ダークソウル』のような、訓練と繰り返しにより極めることのできるものを指します。しかし、別の種類の「難しい」ゲームも存在するのです。
それはたった一度のプレイ体験のために作られたもので、ゲームをプレイした後に振り返って、初めてその意味を理解できたり、他のプレイヤーと語り合うことで理解できたりするものです。
評論家でデザイナーのラナ・ポランスキーさんは最近のエッセイ「流れに逆らって」(Against Flow)の中で、ゲームのプレイヤーとクリエイターは、プレイヤーをスムーズで洗練されたインタラクションによって瞑想状態に置くことに固着するあまり、ゲームの感情的なポテンシャルを制限しているのではないかと懸念しています。
「特にゲームプレイという行為で無感覚な主観性をつくるために流れ/フローが省略され、この無感覚な主観性が理想的なプレイヤー反応として昇華されるという危機を迎えている」、「これは挑発的で不協和音的、感情的なチャレンジが必要な作品を作る大胆不敵なデベロッパーへの評価が落とされるだけでなく、良いゲームがあるべき姿という通念に対して根本的に不信仰的である」とポランスキーさんは書いています。
もしかしたら、途中の苛立たしい3時間を味わうことなしに『Beyond Eyes』の最後の部分の感動を味わうことはできなかったかもしれません。このイライラが心理的な共感反応へと導いたのかもしれないわけです。その感覚、他の人物の経験を「目撃する」のではなく「共感する」感覚、それは他のどの媒体よりもゲームという媒体が上手くできます。
それでもなお、私はコイスさんが「意欲的な映画」に対してそうであるように、『Beyond Eyes』をプレイしている間よりも、プレイした後のほうが好きになれる作品だと願いたいです。そしてプレイしていない今現在、私はこの作品が大好きです。
『Beyond Eyes』はXbox One向けに先行リリースされており、公式サイトによると今後PC、Mac、Linuxでもリリース予定のようです。
[via Kotaku]
(abcxyz)
関連記事
- 確定申告を高速化! 全自動のクラウド会計ソフト「freee」で16連射すると...?
- コンビニで買える! 支払い地獄を避けられるVプリカギフトの天使な使い方
- スタートアップ企業がやるべき 「PRを駆使した伝え方」とは