プロレスラーの壮絶な生き様を語るコラムが大好評! 元『週刊ゴング』編集長小佐野景浩の「プロレス歴史発見」――。今回取り上げるのは「三沢光晴」!! 全日本プロレス系の話題のたびに、いい話がこぼれ落ちてくる三沢光晴。プロレスがますます好きになる小佐野節を今回も堪能してください!
イラストレーター・アカツキ@buchosenさんによる昭和プロレスあるある4コマ漫画「味のプロレス」出張版付きでお届けします!
4月度更新記事一覧! レイザーラモンRG、柳澤健「レスリングのルーツ」、太田章「フォックスキャッチャーの時代」などが読める!
http://ch.nicovideo.jp/dropkick/blomaga/201504
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
――今回のテーマは「三沢光晴」でお願いします!
小佐野 わかりました。三沢との出会いから話すと、私は80年から『ゴング』でアルバイトを始めたんだけど、月刊誌だからそんなに取材は必要なかったこともあって、若手レスラーたちと喋る機会はなかったんです。三沢は81年の春に全日本プロレスに入団したんだけど、初めて喋ったのは84年の1月。
――だいぶあとになるんですね。
小佐野 日本テレビで番組対抗のかくし芸大会ってあったでしょ。
――鶴田さんが白雪姫に扮したりするやつですね(笑)。
小佐野 そこで全日本チームが優勝かなんかして、副賞としてグアム旅行を獲得したんですよ。そこでグアム特訓をやると。『ゴング』は月刊誌だけど、記者を派遣することになって、ボクが行くことになったんです。そのときに越中(詩郎)さん、冬木(弘道)さん、(ターザン)後藤くんがいて。そこで三沢、川田(利明)と話す機会ができたんです。
――しかし、副賞でそんなに大人数を連れていけるんですね。さすが当時のテレビは予算があるなあ(笑)。
小佐野 天龍(源一郎)さんくらいかな、来なかったのは。ほぼ全員参加ですよ。とはいっても、グアムでも三沢とそこまで話し込んだわけじゃないんだけどね。
――あの当時、若手プロレスラー三沢光晴にはどんな評判があったんですか?
小佐野 三沢は前年の札幌大会でルー・テーズ杯の決勝を越中さんと争っていたけど、キャリア的には下から2番目。川田が一番下で、その次が三沢、3番目が後藤だったから。でも、メキシコ遠征の大抜擢を受けたくらいだから、評価は高かったんですよ。
――メキシコ遠征というのは“大抜擢”になるんですか?
小佐野 というか、海外に行けることが凄いんです。81年8月にデビューして、2年半の84年3月に海外に行けるなんて昔の全日本ではありえないもん。だって大仁田(厚)さんや渕(正信)さんは海外遠征までに6年以上かかってるし。
――新日本と違って、全日本の海外遠征のあり方は違うんですかね。
小佐野 まず全日本には若手同士が切磋琢磨するような状況はなかった。新日本の前座はヤングライオンという若手同士の闘いがあったけど、全日本は単なる“前座”。というのは、全日本には日本プロレスから流れてきたベテランレスラーがいっぱいいたから。
――あー、なるほど。
小佐野 そうするとキャリアに差のある選手の闘いになる。三羽烏と言われた渕、大仁田、ハル薗田にしても、伊藤正男さんや桜田さん相手に5~6年近く、ひたすらやられ続けるというね。同期同士で競って上を目指すという世界ではないんだから。三沢と一緒にメキシコ遠征が決まった越中さんも、三沢の3年先輩だからね。
――そう考えると三沢さんは大抜擢ですね。
小佐野 三羽烏がようやく海外に出て、越中さんだけが残って、後藤が入ってきた1年後に三沢が入門してきた。その81年に国際プロレスが潰れて、冬木さんとアポロ菅原さんがやってきた。そのとき全日本の現場監督が佐藤昭雄さんに変わって、全日本の前座の路線が変わったんです。
――どう変わったんですか?
小佐野 佐藤昭雄さんは17歳で日本プロレスに入ったんだけど、日プロにも若手同士で切磋琢磨する環境はなかった。自分がそうだったから、よけいに若い者同士で競わせたかったんですよね。で、82年に川田も入ってきて、なんとなく全日本の若手が揃ってきた。そこで佐藤さんは、それまでボディスラムやドロップキックしかやっちゃいけない若手にそれぞれ個性を見つけてあげて「おまえはこうしたほうがいい」と教え始めたんです。
――前座に“革命”が起きたんですね。
小佐野 あの頃の新日本の前座は髙田延彦vs山崎一夫が注目されていた時期だったと思うんだけど。全日本では越中vs三沢が名物カードになった。デビュー間もない三沢がバンバン飛んでいたしね。なぜそれが許されたというと、現場監督の佐藤さんが、若手の技を嫌がらずに受けてあげていたから。
――現場監督自ら身体を張ったら、ほかのベテランレスラーも従わないといけないですね。
小佐野 そうそう。ブッカーの佐藤さんが受けるんなら、ほかの選手も受けないといけない。だから若手を伸び伸びと育てられたわけ。ただ、佐藤さんも古い世界の人間だから、やたらと大技を使うことは許されない。「なぜその技を使うのか?」ということを噛み砕いてプロレスを教えていたんですよね。
――海外に行かせたのは、より伸び伸びと育てられるからですか?
小佐野 それもあるけど、当時は海外という“空白期間”を経ないとメインイベンターになれない。下から這い上がっていくなんて当時はありえなかったから。だから佐藤さんにとってみれば、三沢光晴というのはひとつの“実験台”だったんです。キャリア3年でも、こうやれば上に行けるんだというプロレスラーを作りたかったんです。三沢にはそれだけの素質があるし、前座にこのままいて負け癖がついてイメージも悪くなる前に海外に行かせてあげたいと。そのあと2代目タイガーマスクになったのは馬場さんの考えだけどね。
――メキシコに渡った三沢さんはすぐに2代目タイガーマスクとして帰国しますよね。
小佐野 越中さんと2人でメキシコに渡り、サムライ・シローとカミカゼ・ミサワになった。メキシコに行ったのは3月で、7月頭には馬場さんからメキシコに電話があって。電話を受けたのは越中さんだったのかな。「三沢を日本に帰してくれ」と。それが2代目タイガーマスクの誕生です。
――タイガーマスクありきのメキシコ遠征ではなかったんですね。
小佐野 馬場さんは本当は佐山タイガーを全日本に上げようとしたけど、ギャラが高いと。そのときに全日本と提携していたジャパンプロレスの大塚(直樹)さんが「梶原(一騎)先生と交渉はできますよ。タイガーマスクの中身に入る選手はいますか?」と。そこで馬場さんの頭に浮かんだのは三沢光晴だった。
――2代目タイガーマスクは、まず“器”ありきのプロジェクトだったんですね。
小佐野 それだけ馬場さんが三沢光晴の実力を買っていたわけですよね。若手の頃から受け身は凄くて、三沢の受け身は音だけでわかると言われてましたから。受け身の音を聞いた馬場さんが「あれ、三沢だろ」って言うくらいで。
――そこまで違うんですか!(笑)。
小佐野 うん、三沢の受け身は音がバラけない。そもそも全日本出身の選手は「受け身の音だけで顔を見なくても全日本出身かどうかわかる」って言いますからね。天龍さんも2000年に全日本に戻ったとき、05年にノアに上がったときに「全日本の受け身の音だ!」って感じたそうだから。秋山準も全日本の受け身の音にこだわりを持ってますよ。
――そこまで徹底的に受け身を練習するんですね。しかし、メキシコに取り残された越中さんも複雑ですよねぇ。
小佐野 翌年の夏には新日本に移籍しちゃうんだけど。三沢が売り出されたことが悔しいというよりは、メキシコに一人取り残されてしまった。ほっぽり出されてしまったことが大きな理由になったと思う。
――全日本の海外遠征って“放置主義”ですよね。
小佐野 あの時代は全員放置ですね。ジャンボ鶴田以外は、天龍さんもファンクスに面倒見てもらったのは初めだけで、あとは放置。天龍さんはジョージアでブッカーのオレイ・アンダーソンとぶつかって1ヵ月試合から干されたりしてたからね。飯が食えない(笑)。
――天龍さんクラスで放置って凄いですねぇ。
小佐野 それは教育方針というか、馬場さんの中には「レスラーは自分で食っていくもんだ」という考えがあったんでしょうね。馬場さんがアメリカでそうやって稼いでいたからかもしれないけど。評判が良ければ日本に戻すという感じで、ビジネスライクだったんですよね。
――馬場さん、シビアですね。
小佐野 取り残された越中さんとすれば、全日本は俺を必要としていないけど、新日本は必要としてくれる。移籍したのはそういうことだと思うんですよ。
――当時としては若手が移籍するのは珍しいですよね。
小佐野 それに越中さんは馬場さんの付き人だったんだから。で、三沢は帰国して2代目タイガーマスクとしてのお披露目をしたあと、越中さんへの日本食を持って、またメキシコに戻ってるんですよ。それは対戦相手を探す目的もあったんです。自分の手の合う相手を見つけにね。
作/アカツキ
――しかし、キャリア3年で2代目タイガーマスクってハードルが高いですよね。
小佐野 それに初代タイガーと比べて身体が大きいじゃない。そうすると空中殺法が綺麗じゃないというか。三沢も士道館の添野館長のところに習いに行ったけど、ついにローリングソバットはマスターできなかった。スピンキックはできたけど。
――三沢タイガーはローリングソバットはやりませんでしたね。
小佐野 川田はできたんですよ。川田は三沢のトレーニングパートナーとして一緒に士道館に通っていてね。身体の小さい川田のほうがいろいろとおぼえちゃうわけです。あの頃の川田は三沢より細かったから。
――2代目は川田さんでもよかったんですかね?(笑)。
小佐野 2代目タイガーは初代より身体が大きくてヘビー級で対応できるという触れ込みだったんだけど。まず初代の動きができることが大前提でしょ? 初代の動きだけをさせるなら川田のほうがよかったんだよね。で、川田は習った動きを得意気に見せてくれるんですよ(笑)。
――ハハハハハハ! 川田さんらしいですね(笑)。
小佐野 「こんなことできるんですよ!」って。馬場さんは「……リング上ではやるなよ」と注意していたけど(笑)。
――せっかくの2代目タイガーが台なしになりますよね(笑)。
小佐野 初代の動きを真似しなきゃいけないのは大変だったと思う。三沢と仲良くなったのはタイガーになったあとなんだけど、ファンにサインを書いても「俺じゃねえしなあ」って感じでね。
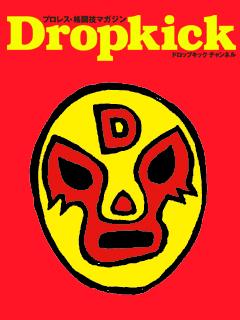
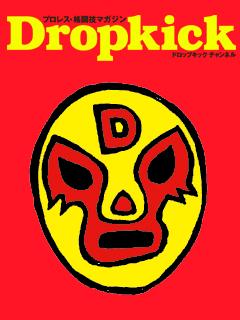

コメント
コメントを書く数年前の全日本で、脱臼か亜脱臼で立てなくなったKAI選手に対して、秋山選手が「骨折したのならともかく、脱臼くらいならとにかく立ち上がれよ!(潮崎)豪とかに何か言うならまずそれからだろう!俺らはみんなそうしてたよ!」と激しくコメントしていた事を思い出しました。
こういう選手の素顔やいい話はゴングの記者の方から、「プロレスはゴールのないマラソンのようなもの」「シュートを越えたものがプロレス」「俺の人生にも一度くらい幸せなことがあってもいいだろう」「心を折る」といった名セリフは週刊(月刊、DX)プロレスで多く目にするような気がします。