
今回はgrshbさんのブログ『grshbの日記』からご寄稿いただきました。
※すべての画像が表示されない場合は、http://getnews.jp/archives/510725をごらんください。
■コミュニケーション能力とは何か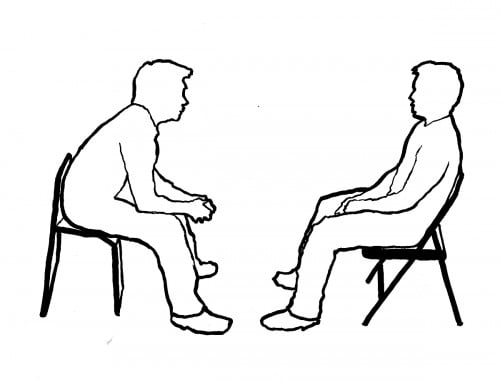
(画像が見られない方は下記URLからご覧ください)
http://px1img.getnews.jp/img/archives/2014/02/2.jpg
企業の採用ページに記載される「こんな学生を募集しています!」の欄で決まって目にする項目の一つに「コミュニケーション能力がある」というものがある。それを見た学生のほとんどは「コミュニケーション能力って何…?」と考えることだろう。僕もその学生のうちの一人だ。ちょうど良い機会なので、コミュニケーション能力とは何なのか、あるいは何故多くの企業が口を揃えてコミュニケーション能力のある学生を募集しているのかについて考えてみたい。
●「コミュニケーション能力」という言葉はマジックワード
主に意味が曖昧で、使う側の思想によって便利に扱うことが出来る言葉や幅広い意味を持つ呼称(特に蔑称)を指して呼ばれている。
具体的な中身を伴わない主張をする際に都合良く用いられることが多いため、一部では使用すること自体も嫌われている節がある。「マジックワード」 『はてなキーワード』
http://d.hatena.ne.jp/keyword/マジックワード
少し考えてみると、もしかすると少しも考えなくたって分かることかも知れないけど、コミュニケーション能力という言葉がとても曖昧なことに気がつく。そもそもが能力というのは、状況に応じて求められ方が変わってくる。だから一口に「コミュニケーション能力」と言っても、状況によって、あるいは置かれた状況が選り分けている立場によってその言葉が指すところは変わってくる。
●何故企業は学生にコミュニケーション能力を求めるのか
どの企業も学生に対してコミュニケーション能力を求めるのは、コミュニケーション能力という言葉がそのように多義的であるからこそなのではないだろうか。企業が想定するコミュニケーション能力と学生が想定するコミュニケーション能力とでは、置かれた状況が異なる以上その内容も変わってくる。企業はある特定の概念であるコミュニケーション能力を学生に対して求めているわけではなくて、「我々企業が考えるコミュニケーション能力」を上手く読み取れる能力を学生に対して求めている。言ってみれば、この能力こそが就職活動において企業が学生に求める「コミュニケーション能力」ということになるだろう。
●コミュニケーション能力とはなにか
視点を変えて、そもそもコミュニケーション能力とはなにかについて考えてみよう。状況によってその指すところは異なるといったものの、広義のコミュニケーション能力として普遍的な法則はある。「コミュニケーション能力」という言葉は見れば分かるように「コミュニケーション」と「能力」の2つの単語を組み合わせた語だ。「コミュニケーション」する「能力」ということになる。では「コミュニケーション」とはなにかについて考える必要がある。
●コミュニケーションとは何か
それは互いを知り合うことだ。更にそれを分解すると、自分を知ってもらうことと、相手を知ることの2つに分けられる。その2つのどちらもが重要だけど、でも優先させるべきはどちらだろうか。多分ここで意見が2つに別れる。自分のことを知ってもらうことが主たるコミュニケーションだという人もいれば、相手のことを知る事がコミュニケーションだという人も居るだろう。僕は後者、「相手のことを知る事がコミュニケーションだ」という立場をとっている。
●どうして相手のことを知ることがコミュニケーションなのか
これは多分、生物学的?に解釈するのが手っ取り早いんではないかと思う。そもそもどうしてコミュニケーションする必要があるのか。それは自分が生き残る確率を少しでも高めるためだ。こんなことを言っても何を突飛なことをと思われるかも知れないけど、どうしてヒトが言葉を使うようになったのかを考えればそのことは明白だし、原始的な世界だけでなく現代において考えてみても、コミュニケーションを取らない人間はそうでない人間に対して死亡する確率が高い。現代では生物としての死というより、社会的な死の確率が高まるだけかも知れないけど、社会的に死んでしまえば生物としての死の確率もうんと高まる。
死のリスクを下げるための手段がコミュニケーションであるという前提に立つと、どうして「自分のことを知ってもらうこと」よりも「相手のことを知ること」が重要なのかは明白だろう。『ハンター・ハンター』とか『ジョジョの奇妙な冒険』で強調されるように、能力もののバトル漫画では自分の能力を知られることは戦闘時のリスクを高めるけど、相手の能力を知ることは戦闘を優位に運ぶために重要な戦術となる。コミュニケーションもこれと同じだ。自分により有利な形で相手との情報の非対称性を持つことは、自分が生存するために必要なキーとなる。
もちろん我々は周りの人と戦っているわけではないから、自分のことを知られてそんなに困ることはないけど、よく考えて見れば他人に知られても良い情報と知られるとまずい情報がはっきりと分かれていることに気がつくだろう。現代においても闘争状態がなくなったわけではなくて、そのレベルが大幅に引き下げられただけで、(主に社会的な)生死を賭けた闘争は存在している。繰り返しになるけど、そうした社会的生存競争の枠組みの中では、相手のことを知ることは自らの生存率を引き上げるためにとても重要な戦術だ。
●コミュニケーションの枠組みは「相手の情報優先」が前提
誰がどう見ても明らかなように現代人はどうしようもなく平和ボケしている。それでも普通に生きていけるくらいに平和になったことは喜ぶべきことなのだろう。それでも、上記したようなコミュニケーションの性質は変わらない。「自分のことを知ってもらうことこそがコミュニケーションだ!」なんて言う人は少なからずいるけど、基本的には相手の事を知ることがコミュニケーションだ。こちらにとって相手の事を知ることがコミュニケーションなのと同様に、相手にとってもこちらのことを知ることがコミュニケーションになる。
とは言え、自分のことを知ってもらうこともまた重要になる場面はある。というかこれはバランスの問題で、大体の場合において少なからず自分のことは知ってもらう必要がある。この時、「自分のことを知ってもらうこと」は「相手が自分のことを知ろうとしている」という前提に立って行われるべきだろうと僕は考えている。多分それが健全なコミュニケーションが図られる社会というものだろう。
つまり、こちらから「僕のことを知って知って」と自らの情報を開示するのではなくて、相手が知ろうとした内容について自らの情報を開示すべきだ。ちょうどネットワーク上のサーバーがこちらの要求に応じて必要な情報を送ってくる動きと似ている。考えてみれば、相手が知ろうとも思わないような、言い方は悪いがどうでもいい情報を並べ立てられたら、正直な話相手は鬱陶しいと思ってしまうだろう。それは相手がこちらに対してどうでもいい情報ばかりを並べ立てた時も同様だ。円滑なコミュニケーションを図るためには、相手が自分についてのどんな情報を要求しているのかを上手く汲み取って、その要求に基づいた情報の開示を行わなければならない。
最初に出した企業と就活生の例についてもこれは当てはまる。企業が求めているのは両者にとって共通の、あるいは特定の概念としての「コミュニケーション能力」ではなくて、企業の言うコミュニケーション能力の如何を上手く読み取れる能力ということになる。互いが相手のことを知ろうとしているという前提に立てば、こちらが相手の情報を知ろうと健全に振る舞えることこそがコミュニケーション能力だ。そしてその時知ろうとする相手のことの中には、相手がこちらについて知ろうとしている情報が何なのかも含まれる。そうしたメタメッセージまで含めて相手の事を知ることがコミュニケーション能力ということになるのだろう。
執筆: この記事はgrshbさんのブログ『grshbの日記』からご寄稿いただきました。
寄稿いただいた記事は2014年02月07日時点のものです。
■関連記事
「安倍総理が水を飲んだら民主党議員が『下痢するぞ』と汚いヤジ」みんなの党・和田議員が『Twitter』で明かす
フォアグラ弁当中止運動した保護団体「動物はあなたのごはんじゃない」 ネットでは「他人を巻き込むな」「何を食ってるか調べたい」の声
「動物はあなたのごはんじゃない」の波紋が広がる 「植物はあなたのごはんじゃない」とのパロディイラストも
【2014年02月03日~02月09日あなたの運勢】ガジェ通12星座占い ベスト3
フランスの漫画展示会『アングレーム国際漫画祭』開催 韓国が慰安婦説明会を開催しようと強行するも中止に

