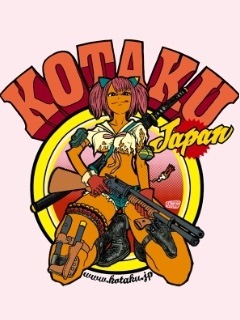ストーリー面にしても、映像面にしても編集にしても、BGMにしても、誰が見ても非の打ち所がない完璧な映画など、存在しないかもしれません。しかし、製作者の血のにじむ努力と奇跡の組み合わせで、「ストーリーテリングとは何か」を教えてくれる完璧に近い映画は一定数あるのです。
【大きな画像や動画はこちら】
では、io9がまとめた「ストーリーテリングを教えてくれるほぼ完璧な映画10本」を紹介したいと思います。
■『素敵な相棒 ~フランクじいさんとロボットヘルパー』

ボケの進行がどこまで進んでいるのか分からなくて観客を困惑させるのもリアルでイイ
この映画を一際輝かせているのは、老人演じるフランク・ランジェラの皮肉と悪賢いパフォーマンス、そして美しい自然の中に映える真っ白なロボット。
その上、「キャラクタースタディ(中心となるキャラクターの性格を描写すること)」が、フランクとスーザン・サランドン演じるジェニファーとの関係を通して自然に描かれているのも注目すべきところです。そして、映画の後半で明かされるフランクのキャラクターの意外性...。この映画は、全体を通してメインキャラクターに「捻り」を加えています。
本作は、「記憶と自我/個性というテーマにテクノロジーがどれほど影響できるのか」を描くことに最大限の努力を投じ、テーマを言い換えるだけに止まらず、新なる方法を研究しているのです。
■『悪いことしましョ!』

結局元どおり
ブレンダン・フレイザーとエリザベス・ハーレイのリメイク版のことではありません。1967年に公開されたぺーター・クックとダドリー・ムーアのオリジナル版の方です。
クック演じる悪魔のスピゴットは、食堂でコックとして働き、ウェイトレスのマーガレットへの想いを苦に自殺を図ろうとしたスタンリー(ムーア)に、魂と引き換えに7つの願いを叶えてやると取引を持ちかけます。
早速、契約を交わし、次々と願いを叶えてもらうスタンリーですが、全てがうまくいきません。本ストーリーは、スタンリーの片思いやてんやわんやだけに従事するのではなく、スピゴットの秩序や調和への視点や、永遠の世界のために神におべっかを使い続けることに辟易している理由にも触れられています。
21世紀の映画の基準としては多少遅いと感じられるかもしれませんが、それでもクックとムーアのコミック・タイミングは申し分なく、皮肉の使い方も逸品です。ムーアの願いは一貫して幸福の追求ですが、あくまで彼のエゴを満たすものです。
それを皮肉めいた捻りが決して荒々しくない方法で覆し、徐々に「何故、彼は幸せになれないのか」ということをあらわにしていきます。
■『未来世紀ブラジル』

様々なリストでランクインする本作。見ないわけにはいかない
奇抜なビジュアルとほろ苦くヘンテコなユーモアに加え、『未来世紀ブラジル』はグロテスクな世界観を描いた映画の傑作と言えます。
荒廃した町、テロリストの攻撃、官僚社会...、実際に存在する要素を限りなく不可思議にしたものが本作の中に詰め込まれています。観客は、そのようなリアリティの中にディストピアの世界をしっかりと固定させた可笑しな感覚があるからこそ、ジョナサン・プライス演じるサム・ラウリーの苦境に、より共感するのです。
その他に、この作品がやってのけた難解なこと。それは、サムの住む世界は十分に奇怪であるにも関わらず、夢と妄想のシーケンスを非現実なものだと観客に認識できるようにしたことでしょう。
ストーリーテラーにとって、異様な世界を舞台に設定しても、より奇怪なファンタジーの世界観を作れば、区別させつつ厚みを出すことが可能ということを学ぶことができます。
■『ゴーストバスターズ』

『ゴーストバスターズ』の素晴らしいところは、ゴーストやゴーストバスターズという設定をリアルの世界にうまい具合に落とし込むことに成功していることでしょう。撮影もナチュラルライトを使うといったように、現実的なスタイルで行われています。(『ゴーストバスターズ』をあらゆる角度から検証したサイト「Overthinking Ghostbusters」を見れば、その凄さがもっとわかるでしょう)
本作が何故こうもユニークなホラーコメディになれたのか、何故、ゴースト退治の会社を興した負け組のストーリーがこうも愛されているのかは、完全にファンタジーの世界として描くのではなく、どんな時でも現実から完全に切り離してしまうことなく物語を進めているからと言えます。
また多くの素晴らしい80年代映画同様、『ゴーストバスターズ』は、そのキャラクターと状況の説明に時間を費やしているため、見た人の愛着と理解を得やすいとも言えるでしょう。
■『アイアンマン』

無駄がなくコンパクト
大半がアドリブで構成されているといっても過言で無いにも関わらず、本作はそのセリフや要素ひとつひとつに全く無駄がありません。
武器販売者だったトニー・スタークが、過去を悔いて生まれ変わる様子は見ていて気持ちよく、またロバート・ダウニー・Jrとグウィネス・パルトロウのとジェフ・ブリッジスの間で繰り広げられるやりとりはキャラクターの魅力を引き出すことに成功しています。
例えば、ブリッジスがピザを持ってくるところ、もしくはダウニー・Jrとパルトロウが口喧嘩をするシーンはとても自然で、彼らが長に渡って関係を持っており、それが変化しつつあるということを観客に伝えるのに役立っています。
アクション映画のジャンルとして、クライマックスに多少の物足りなさを感じますが、本作のテーマとキャラクター構築の上では完璧なまとめ方だったと言えるでしょう。
■『マルコヴィッチの穴』

私利私欲のために利用されるマルコヴィッチ
奇想天外なストーリーを展開させるのが得意なことで知られるチャーリー・カウフマン。本来ならば、『マルコヴィッチの穴』だけでなく、『エターナル・サンシャイン』や『アダプテーション』もこのリストに加えたいところでしたが、今回は有名俳優の頭の中に入り、その脳内を体験できるという混乱をきたす内容に加え、監督の初長編作品である『マルコヴィッチの穴』をチョイス。
カウフマンは概念や理論、非現実的なストーリーのマスターであり、作品の中で奇妙な物体によって人間のエゴやアイデンティティがワープするということに焦点を合わせた素晴らしいストーリーテラーでもあります。
『マルコヴィッチの穴』は、ドアをくぐると有名俳優の頭の中に入り、観察したりコントロールすることができるという不思議で強烈なアイディアだけで観客の心を掴んだのではなく(勿論、最初はそうだったでしょう)、驚くほど個人的な理由でマルコヴィッチを利用するクレイグ(ジョン・キューザック)の自己中心性と、彼の人生の終わりをもたらす誘惑といった要素が加わり、ストーリーとしてしっかりしたものが出来上がっていたからこそ、考えさせられるものに仕上がっています。
本作のエンディングは衝撃的で、クレイグの全ての間違いの極致と感じられるでしょう。
■『ターミネーター』

ジャンルなんてものはツール
スラッシャームービー、ノワール・スリラー、テクノ・スリラー、そしてロマンスをバランスよくまとめ、他には無いストーリーに作り上げたのが『ターミネーター』。それだけでなく、アクションシーンにおける殺人ロボットの笑いのタイミング(コミック・タイミング)から美しいカメラワークまで、語るべき部分はたくさん存在します。
しかし、この映画の何がそんなに完璧に近くさせていて、ストーリーテラーにおいて学ぶべきことが多いのかと言えば、ジャンルというものを、サラ・コナーのキャラクターアーク(話が進むにつれてキャラクターに起きる一連の内面的変化)を描いていくためのツールキットとして使っているところでしょう。
低予算ゆえの地味な雰囲気すら、サバイバルというストーリーの中で効果を出しています。しかし、質素や地味だけで終わることなく、ラストでは未来の技術を詰め込んだ金属スケルトンを披露し、ジャンルに対する観客の期待にもしっかり応じているのです。
■『アップストリーム・カラー』

語らないが、全て見せる
『プライマー』でデビューした元エンジニアのシェーン・カルース監督長編SF作品『アップストリーム・カラー』。「心の連鎖」を描いた本作は、『プライマー』同様に難解で、一度見た程度では理解できません。
しかし、複雑に見えて非常にシンプルな関係と、おぞましい科学を合わせたこのストーリーは、難解でありつつも「明瞭さ」を非常に大切にしています。というのも、カルース監督は、登場人物に何かに対する説明を一切させておらず、全てを映像で見せているからです。
カルース監督は、全てのプロットを像と並列で伝える方法をとっており、「聴覚」よりも「視覚」の究極の例となっています。曖昧さを残したまま迎えるエンディングも、「結局何が伝えたいのかわからなかった」ではなく、「次は何が起こるのだろうか」と観客に予想させる為に計算されているからなのです。
■『もののけ姫』

グロテスクなまでに鮮やかな色使いも印象的
このリストに登場する映画を撮影した監督は、一様にストーリーテリングに長けていますが、日本を代表するアニメ監督の宮崎駿もその一人。彼の作品の多くはこのリストにランクインすることができますが、中でも特別なのが『もののけ姫』でしょう。
この映画は、美しさと動きの良さだけでなく、村の少女らを守るためにタタリ神を殺したことで呪いをもらってしまった少年アシタカに対し、同情を寄せさせる上手さがあります。そして、「自然や人間の関わり」といった話題のテーマを、人間の心に語りかけつつ、簡潔ではなく複雑に描いているのです。
また、産業主義や開発、自然破壊に対するメッセージというと、破壊のみが悪といった印象を与えやすいのですが、本作の場合、タタラ場の長であるエボシ御前がどれほど人々から敬われているのかということも様々な場面で丁寧に描かれています。
その上で、エボシとサン(もののけ姫)の両方がお互いの世界で生きながらお互いを理解する、もしくは相互破壊に直面する必要があるということを伝えているのです。
『もののけ姫』は人を圧倒する力を持ち、泣かせるだけでなく、見た後にも考えさせる余韻を残す作品と言えるのです。
■『28日後...』

究極のポスト・アポカリプスといえばコレ
『28日後...』は、これまでのゾンビの概念を壊し、ダッシュするゾンビ(厳密にはゾンビではありませんが)を登場させたことで一気に知名度をあげた作品です。しかし、この映画の良さは駿足ゾンビの意外性だけでなく、ポスト・アポカリプスのストーリーテリングにもあるのです。
映画冒頭から漂うパラノイアと侘しさ、凶暴なウィルスに感染した猿が解き放たれた研究室、直ぐに明らかになる世界の状況。静まり返り、誰も居なくなった場所を写すことで、そこが危険な場所であるという極度な不快感を伝えています。
しかし、この映画の中で一番恐ろしいのは、レイジ(凶暴性)ウィルスの存在ではなく、クリストファー・エクルストン演じるヘンリー・ウェスト少佐の種族維持のための「レイプ」指示でしょう。これこそが、真のアポカリプスの恐怖です。
数多くのポスト・アポカリプス映画が「人間がモンスターと化す」というアイディアを採用していますが、この女性をレイプして人間の数を強制的に増やすというのは、とても本能的であり、実際にそのような状況に直面した時に起こらないと言えないからこそ体の芯から冷えるような恐ろしさを秘めています。
最後に、io9の記者が本リスト制作を前に開いたミーティングで名前があがった作品を下に紹介しておきたいと思います。
---------------------------------------
『ボディ・スナッチャー』(1978年)
『ロストボーイ』(1987年)
『ローズマリーの赤ちゃん』(1968年)
『リトル・ショップ・オブ・ホラーズ』(1986年)
『狼男アメリカン』(1981年)
『ヘルボーイ』(2004年)
『パンズ・ラビリンス』(2006年)
『遊星からの物体X』(1982年)
『バタリアン』(1985年)
---------------------------------------
興味があれば、これらも是非チェックしてみてください。
[via io9]
(中川真知子)
関連記事
- 猪子寿之、藤村龍至らが語る。未来のマンション価値は「コミュニティ」にあるという提言
- ピリ辛お鍋にキリッと冷えた一杯で、冬の大人グルメを楽しもうよ
- 0コンマ以下への挑戦。ビールの世界に隠されたイノヴェーションとは?