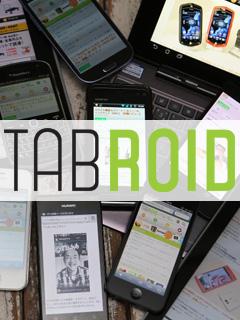「週刊の漫画雑誌が、そのままスマホで読める」
「週刊の漫画雑誌が、そのままスマホで読める」
紙の雑誌と同じ作品が載っていて、同じ日に発売され、紙より安い。そんな、漫画好きなら誰もがイメージする「デジタル雑誌」にいまいちばん近いのが『Dモーニング』です。
月額たった500円で読み放題、アプリの操作性もグッド。私・ワタナベ(TOP写真:右端)はリリース当初から読んでます。
「Dモーニング」がリリースされて約半年が経ちますが、今の「Dモーニング」はどういう考えで編集・運営されているのか? その裏側を知りたくて編集部&運営スタッフにインタビューしてきました。
お話をうかがったのは、モーニング編集部の島田英二郎編集長(TOP写真:中央下)と竹本佳正さん(同:左)、アプリの開発/運営を担当するエキサイト株式会社の岡田英之さん(同:左から2人め)と小島靖彦さん(同:左から3人め)です。
100万人規模の読者に「当たり前のもの」を

--まず、アプリでの週刊誌配信を半年やって、いま感じていることをお聞かせください
島田: なにしろ前例がないチャレンジだから、ビジネスも仕組みも全て手探りです。やってることは「毎週スマホでモーニングが読める」ってだけの、とてもシンプルで当たり前なことなんですが。こっちは全てをかけて腹をくくって作ってても、それがまだ理解されてないとは感じますね。

--どうせアプリはオマケ程度のものだろうとか、そういう誤解を受けやすいと?
島田: そう。「まさか月額500円で雑誌が丸ごと読めるようなモノを出してくるはずがない」って思われてるのではないでしょうか。かくいう私自身もデジタルについて無知なほうですが、「Dモーニング」はそういう私のようなユーザーに読んでほしいと思ってます。
--あくまで週刊誌として?
島田: アーリーアダプター層や、マンガを前のめりに読んでくれる「アツい読者」も当然コアなユーザーとしていてくれるけど、週刊誌ってのはそうじゃない「冷たい読者」のほうが断然多いわけです。つまり100万、200万人の冷淡な人たち。その人たちが当たり前に読んでくれるモノを目指してるわけです。けっきょく週刊誌はそこに向けた商売ですからね。

岡田: アプリ制作を担当した僕らも、もともと週刊漫画誌の読者であり、同時に電子書籍ユーザーでもあったのですが、なぜスマホで紙の雑誌と同じものを読むっていう「当たり前のこと」ができないんだろう、と思っていました。そんなとき「Dモーニング」を一緒に作ろうというお話をいただいて。
--そんな両社が協業して、アプリ開発にあたっての苦労話などは?
竹本: 当初、我々「モーニング」側はデジタル制作の感覚を持ち合わせていなかったので、インターフェースも「画面の動きはもっとピタっと止まる感じで」とか非常にふわっとした要望をエキサイトさんに出しまくっていたんです。「とにかくコレじゃダメなんです!」って(笑)。
 小島: そうそう、僕たちも「どうしたら納得してもらえるんだろう」と試行錯誤を何度も繰り返しました。でもこのやりとりのおかげで、一周まわって標準的で使いやすいものができたと自負しています。特にビューアは島田編集長の言う「冷たい読者」の方々にも「おっ!」と思ってもらえるような仕上がりになっているはずです。--操作感が自然で気持ちいいですよね小島: ええ。ツールバーの上のスライダーも、雑誌をパラパラとめくる感覚に近付けようと考えた、Dモーニングオリジナルの自信作です。動かした距離でページの進むスピードが変わるのですが、毎号およそ500ページある中でどのくらいのスピードが適しているのか、編集部とギリギリまでこだわりました。この独特の感触はぜひ実際に使って体験してもらえたら。
小島: そうそう、僕たちも「どうしたら納得してもらえるんだろう」と試行錯誤を何度も繰り返しました。でもこのやりとりのおかげで、一周まわって標準的で使いやすいものができたと自負しています。特にビューアは島田編集長の言う「冷たい読者」の方々にも「おっ!」と思ってもらえるような仕上がりになっているはずです。--操作感が自然で気持ちいいですよね小島: ええ。ツールバーの上のスライダーも、雑誌をパラパラとめくる感覚に近付けようと考えた、Dモーニングオリジナルの自信作です。動かした距離でページの進むスピードが変わるのですが、毎号およそ500ページある中でどのくらいのスピードが適しているのか、編集部とギリギリまでこだわりました。この独特の感触はぜひ実際に使って体験してもらえたら。
(TABROID補足:ページを早送りするスライダーは現在のところiOS版のみ使えます。将来的にはAndroid版でも採用したいとのこと)
紙とデジタル、そして日本の漫画文化とビジネス
--アプリやウェブなら毎日の更新もできますが、あえて週刊ペースにこだわる理由は?
島田: 日本の漫画市場って描き手はもちろん、読み手も非常にレベルが高いんです。それは50年間もの週刊誌の歴史が作り上げたもので、漫画を週刊ペースで心臓の鼓動のように読み続けることで獲得してきたものだと思います。これは他国にはない、日本で独自に発達した文化なんですよ。
--しかし、どの雑誌も部数は減少しています
島田: ええ。自然の流れとして紙の「モーニング」の部数は縮小していくとは思ってますが、日本の成熟した漫画読者のレベルは単行本を読むだけの習慣では維持できないでしょう。先ほども言ったように、心臓の鼓動のように漫画に触れることが必要だし、週刊誌を毎週読むというライブ感をもっと読者に楽しんでほしい。そこには紙とかデジタルといった媒体の違いは関係がないと思って「Dモーニング」を作っています。
--ところで、ビジネスとして「Dモーニング」自体での採算は採れているのでしょうか?
岡田: ビジネスとしての採算は採れ始めていますよ。iOSユーザーの課金率は15%とアプリとしては驚異的に高い水準ですし、Androidもまだ母数が少ないながら、iOS以上の高い課金率で購読者を獲得しています。
--リリースから5ヶ月で、すでに採算ベースにはのせられたということですね
島田: ええ。しかしそれよりもこの5ヶ月で得られた大きな成果は、他に誰もやってないことをやったことで得られた知見の蓄積です。ビジネスとしての「Dモーニン グ」の現状ってのは半分は予想していた通りだけど、とにかく前例がないから予想できないことだらけ。読者アンケートをとってみたら思いもよらない結果が出てきたり。

--紙の雑誌だけをやっていたら得られなかった読者の声があったと
島田: 「Dモーニング」の読者は元々紙の「モーニング」を読んでた人が多いんですが、「紙のモーニングの購読をやめた理由」を訊いたところ、「いちいち雑誌を捨てるのが面倒くさい」とかビックリするような結果がゴロゴロ出てきました。「離れていった読者の声」を聴くのが当然一番むつかしい。今まで20年、多くの編集長が雑誌の部数が落ちることに悩み続けてきて、自分たちの作るものは本当に支持を得ているのか不安に思い続けてきたわけです。少なくとも最近のモーニングに関しては、部数の減少は、内容に対する不満より、「捨てることへの抵抗感」や「コンビニにわざわざ買いに行くのが面倒」などの雑誌の形態そのものに原因がある可能性が高い。その事実は本当に言葉にできないくらいに私にとっては衝撃でした。
同業者と争うつもりはない。競合はSNSやYouTubeだ
--今後、紙の競合誌がデジタルに進出してくると思うのですが迎撃体制は?
島田: モーニング以外にも、電子化に目を向けている雑誌はあるんだと思います、本当はほかにもやってくれるところが出てきたほうがいいんです。
--つまり他誌をライバル視はしていないと?
島田: どこかの編集部が「Dモーニング」のような電子化をやるっていうなら、共有可能なデータは可能な限りお教えできればと思っています。今の段階ではノウハウは共有してみんなで一斉に走ったほうがいいんですよ。モーニング一誌の力なんて言うまでもなく微々たるものです。ライバルはお互いの雑誌じゃなくてパズドラとかYouTube、それとSNSとかなんだから。電車に乗ってみれば、みんな雑誌じゃなくてスマホいじってるのはわかるでしょう。漫画というエンターテイメントが一丸とならなければ、ゲームやSNSから時間は奪い返せないと思います。
少数の悪意より大多数の善意あるファンに向けて
--SNSといえば、Twitterなどで誌面の画像を無制限にシェアできる機能には本当に驚かされました。
島田: それも「ユーザーが望んでいる機能」だからやるということです。一握りの悪意あるユーザーのために、本当のお客さん(ファン)の楽しみを制限するのは基本的に不健全だと思います。少数の悪意のために大多数の善人が縛られるというカタチですね。もちろん慎重に進めることが大前提ですが。

竹本: なにより、友達と漫画の話をするときもコマやページの有無で伝わり方が全く違ってしまうと思うので、ユーザーにもっと楽しんでもらうための機能としてページ画像共有を提供しています。
島田: どんな商売でもそうだけど、「我々の都合」を優先しないでお客さんが本当に欲しいものを提供するのが大事なのでしょう。書店さんと共存していくことはもちろん一番大事なことです。でも電子化でもっと雑誌が読まるようになれば、やがて漫画単行本の売り上げも増えて、書店にもプラスになることには確信があります。
―単行本の売り上げとDモーニングの購読者数に相関関係は?
島田: 今はまだ見えないです。それはもっと購読者数が増えてから明らかになっていくんでしょう。
今の電子書籍ってのは、紙が落とした影なのでは
島田
: 紙のモーニングには掲載されていて「Dモーニング」にはない作品も確かにあります(TABROID注:「バガボンド」「ビリーバット」の2作品)。これは作家さんがデジタルで読まれることを想定して書いていないからで、それは我々も実にもっともな理由だと思っています。逆に、今後は紙よりデジタルで読ませることを意図した漫画も誕生してくるでしょう。

--現在、Dモーニングにも掲載されている作品の作家さんは紙とデジタル両方で読まれることを意識して作るようになっていますか?
島田: いや、まだそうでもないですね。今のところ、作家さんたちの本拠地はやっぱり紙なんです。遠い将来には、電子コミックが紙の発行部数を超えるときも来るかもしれない。でも今はまだ漫画であれ小説であれ「電子出版オンリーで出して大ヒットした作品」は現れていない。
--確かにそうですね
島田: つまり電子書籍ってのは、今のところ紙の影みたいなものなのでは。 本体である紙がなくなれば影である電子書籍もなくなってしまうように思えます。時には、光源と紙の位置関係によって影である電子書籍のほうが大きく見えることもあるだろうけど。デジタル化の流れというのはまだ始まったばかり。これから何代かの編集長が引き継いでいくような長い期間で、ゆっくりと変化していくんだろうと思いますね。
インタビューを終えて
前人未到のビジネスを切り開いて行く体験談や、ネット企業と出版社の協業、そしてマンガの未来にまで広がったこのインタビュー、話し手の皆さんがそれぞれに「顧客ニーズや新しいチャレンジから逃げないで向き合う」姿勢を熱く語っていたのが強く印象に残っています。
こうした作り手たちが今後もより良いマンガやアプリを世に送り出していくのだろうな、と今後に一段と期待させられました。
・月500円の価値は大アリ! 発売日にモーニング最新号が読めちゃう『Dモーニング』
・「会長 島耕作」連載開始! アプリ雑誌『 #Dモーニング 』の月額500円はオトク? それとも... 【コラム】
・島社長でボケて! 「Dモーニングでボケて」クッキングパパや宇宙兄弟の公式お題が出題中
・ユーザー登録不要! 「モーニング」「アフタヌーン」「イブニング」を無料で読める『モアイ』をオープン
[Dモーニング]
(ワタナベダイスケ)