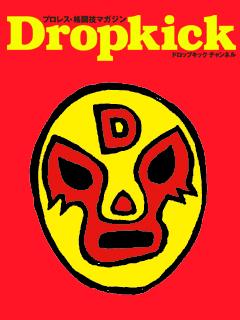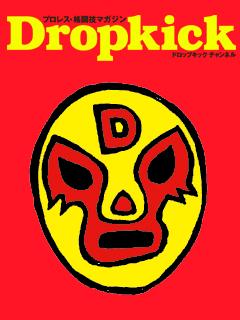斎藤文彦・最新著作
『プロレス入門』神がみと伝説の男たちのヒストリー

https://www.amazon.co.jp/dp/4828419071/ref=cm_sw_r_tw_dp_x_.ROZxbW0XSD1C
Dropkick「斎藤文彦INTERVIEWS」バックナンバー
■プロレス史上最大の裏切り「モントリオール事件」
http://ch.nicovideo.jp/dropkick/blomaga/ar1010682
■オペラ座の怪人スティング、「プロレスの歴史」に舞い戻る
http://ch.nicovideo.jp/dropkick/blomaga/ar1022731
■なぜ、どうして――? クリス・ベンワーの栄光と最期
http://ch.nicovideo.jp/dropkick/blomaga/ar1039248
■超獣ブルーザー・ブロディ
http://ch.nicovideo.jp/dropkick/blomaga/ar1059153
■「プロレスの神様」カール・ゴッチの生涯……
http://ch.nicovideo.jp/dropkick/blomaga/ar1077006
――こないだターザン山本さんをインタビューしたときに、ベースボール・マガジン社が『ベースボール・フライデー』という暴露系雑誌を作ったことがあるという話になりまして。
フミ斎藤(以下、フミ) それは異様に面白かったと評価されている山本さんのインタビュー?
フミ 思いつきでそういう雑誌が80年代前半に企画されたことはたしかですね。そのときボクもまだ若かったから、どういう事情でそんな本を出すことになったのかは知る由もないんだけど。当時は20歳そこそこの学生ですよ。
――ヤング斎藤文彦!
フミ アメリカの大学に通うため向こうに6年間住んでいたんですけど、そのあいだに3回帰国してるんです。アメリカの大学の夏休みは6、7、8月の3ヵ月間もあって長いですからね。その81年、82年、83年の夏休みを『月刊プロレス』編集部のアルバイトとして過ごしたんです。修行中のプロレス記者ともいえるんですけど(笑)。
――『月刊プロレス』時代から関わってたんですね。
フミ 『週プロ』初代編集長の杉山さんにはいろいろと教わりましたし、山本さんはまだ「ターザン山本」を名乗ってなかった頃ですよ。
フミ 「隆司」もじつはペンネームで。ボクは山本さんの後ろをちょこちょこと付いて歩いてたんですよ。山本さんと一緒に京王プラザのロビーでレスラーを待ち伏せして、アブドーラ・ザ・ブッチャーの部屋を突撃取材したり。
――山本さんと一緒にゲリラ取材をやってたんですね。
フミ 「ブッチャーが部屋に戻ったらしい」という情報を聞いたら、ロビーからブッチャーの部屋に電話するんです。ブッチャーから「いまから部屋に上がってこい」と取材OKの返事をもらって、2〜3時間ほど話を聞くんですよね。
――いまのプロレス取材とはやり方が全然違うんですね。
フミ あるとき京王プラザで山本さんと一緒に張り込んでいたんですけど、待ち人が来なかったときがあって。そうしたらタイガー戸口さんがふらりと横切って「あれ、あんたら何してるの? 時間があるならお茶でも飲もうよ」と。京王プラザの2階にある喫茶店で2時間くらいお話するんだけど、それがものすご〜〜〜く収穫が多いんですよ(笑)。「プロレスってこういう世界なのか!」と驚きと発見がありまして。
――戸口さんの話は深そうですね(笑)。
フミ あるときタイガー・ジェット・シンを待ち伏せしてたら上田馬之助さんに声をかけられて、喫茶店でお話したこともありましたね。上田さんの話も、もの凄く収穫があったんですよ。話が弾んで「これから一杯飲みに行くんだけど、あんたらも来るか?」なんてお誘いをいただいたりしまして。
――いまは団体の広報を通して取材するのが一般的ですが、当時はゲリラ取材が許されてたんですか?
フミ あの時代は新日本と全日本の2団体しかなくて。馬場さんワールドと猪木さんワールドしかなかった。マスコミの数も少なかったし、顔はなんとなく知れているから、そういう取材の仕方も成立したんですよね。
――顔なじみだったから許されてたんですね。
――『ファイト』はI編集長の私小説的世界でしたね。
フミ 地の利が圧倒的に不利だったので『ファイト』の根本はゲリラ取材なんですね。山本さんはそのゲリラ殺法を『ファイト』で身につけてるからフットワークが軽かった。山本さんが朝から晩まで一度も編集部に来ない日がけっこうあったんですけど、それは遊んでるんじゃなくて、どこかで張り込みをしてるんです。長州力のマンションの前で張り込んでいたり、誰かがホテルの喫茶店で密会してるところをマークしたり。山本さんはカバンの中にキャノンのカメラを忍ばせておいたから、何かあったら自分で写真を撮ってたんです。あの時代は携帯電話なんてないから、山本さんはポケットに十円玉をたくさん詰め込んでいて、何かあると公衆電話から編集部に電話をかけてきてたんですね。
――それは当時のプロレスマスコミとして異色の存在だったわけですよね。
フミ そうでしょうね。こういうことを言うと『ゴング』や東スポの悪口に聞こえちゃうかもしれないから、そこは誤解しないで聞いてもらいたんですけど、当時のプロレスマスコミは、宣伝媒体としての役割が大きかったんですね。それを表すものとして、後年長州力さんの「マスコミなんて東スポさえありゃいいんだよ」という有名な発言がありますよね。
――プロレス団体の立場からすれば、マスコミは宣伝媒体として存在してるという意識が強いわけですよね。
フミ 昔のプロレスにはシリーズ興行というシステムがありましたよね。新日本や全日本は年間8〜9シリーズあって、ひとつのシリーズで3週間近く巡業する。70年代なんかは1シリーズ8週間近くやっていたりしたんです。それこそ夏に東京を出て、戻ってきたら秋だったりするんですよ(笑)。
――その長い旅にマスコミはついて回る。
フミ そうすると記者とレスラーは親しくなるし、団体とマスコミも一蓮托生の関係になる。プロレスが盛り上がることは、媒体にとってもいいことでしょう。持ちつ持たれつみたいもんで、団体側が「こうやって報道してね」というものをそのまま活字にするかたちが昭和30年代から昭和50年代までの伝統というか慣習だった。
――団体からすれば無料で広告を打ってるようなもんですよね。
フミ それが変わっていったのは第1次UWFという団体の登場からでしょうね。UWFが誕生したことによって本当の意味でのプロレスマスコミができたと言えるんですよね。
――UWFがジャーナリズム精神を生んだと?
フミ そこに『月刊プロレス』の週刊化が重なったことが大きいですね。まずボクが経験した『月刊プロレス』編集部の話からすると、ボクは単なるアルバイト小僧で。いつも終電ギリギリで家に帰って、朝9時には編集部に出てくる。ほかの編集者は一番早くて11時くらいの出社なんですけど。それまでに炊事場でお湯を沸かして、2つあった魔法瓶をいっぱいにして。当時は禁煙システムじゃないから、各机に灰皿が置いてあるんですけど、吸い殻が山盛りになってるんですよ。それを毎朝片付けていたんですね。
――雑用をこなしてたんですね。
フミ 『週プロ』初代編集長の杉山さんは、会社で言えば部長的なポジションだったんです。編集長という役職はついてるんだけど、実質上編集長的な作業をしていたのは山本さんなんですよ、最初から。
――あ、そうなんですか。
フミ 杉山さんは『週刊ベースボール』からプロレス編集部に配属された管理職だから。
――杉山さんは優秀な編集者でしたけど、プロレスというジャンルにはあまり興味はなかったそうですね。
フミ そこが強みでもあり弱みでもあったし、ちょっとプロレスをバカにしていたところもあったかもしれない。ただ、プロレスに興味はないけど、プロレスという業界は面白いと思っていた。杉山さんは最初からそういうスタンスだったんですよ。
――誌面は山本さんが取り仕切っていたんですね。
フミ 山本さんが『ファイト』から移籍してきたのは81年。最初は『プロレスアルバム』をひとりで作っていたんだけど、途中から『デラックスプロレス』を担当するようになって、ハルク・ホーガンにギターを弾かせたり、タイガーマスクを海に連れて行ったり、いろんなバラエティ企画をやってたんです。雑誌の付録として人気レスラーのステッカーとか、VHSテープに張るラベルやアイロンプリントを考えたのも全部山本さんなんです。
――ヤングターザン、有能ですね!(笑)。
フミ あと、これは知らない方が多いと思うけど、『月刊プロレス』が『週刊プロレス』になったんじゃなくて、中身としては『デラックスプロレス』が『週刊プロレス』になったんです。
――方向的には『デラプロ』だったんですね。
フミ そうすると『週プロ』と内容が被ってる『デラプロ』のほうの売り上げがズトンと落ちていったんです。なので『デラプロ』はマガジンインマガジンとして「月刊クラッシュギャルズ」をという誌面刷新を打ち出して、女子プロ雑誌に方向転換していったんですね。
――当時は女子プロブームでしたね。
フミ のちに『週プロ』で次長を務める宍倉(清則)さんが編集長代行をやっていたんですけど。あと週刊化に関して、これも皆さんおぼえてないかもしれないですけど、83年の第1回IWGP決勝戦。あのときには週刊化がすでに決まっていて、IWGP決算号と言ってIWGP公式リーグ戦だけを一冊にまとめた増刊号を出したんですね。それが『週刊プロレス』のテスト版だったんです。
――幻のゼロ号があったんですね。
フミ そこで面白いのは週刊化に合わせるように、プロレス界に事件が相次いで起こったんです。テスト号を出したIWGP決勝戦でアントニオ猪木さんの“舌出し失神KO事件”。経営不振によるクーデター事件が起きて、そしてタイガーマスクの引退。長州力の維新軍団やUWF勢が新日本を離脱していった。
――それだけ事件が相次いだら普通は団体が潰れてますね……。
フミ そういう激動の中で創刊したての『週刊プロレス』にジャーナリズムとしてのチャンスがめぐってきたわけです。週刊化されたときに「日刊だと浅すぎる。月刊だと遅すぎる」というキャッチコピーがありましたよね。毎週毎週、駅の売店に雑誌が並ぶことでジャーナリズムのかたちになっていったと思うんですよね。