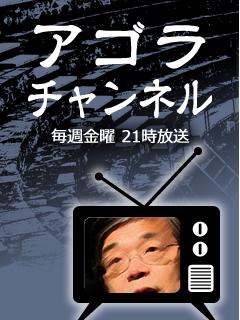
めるまがアゴラちゃんねる
2012年11月第3週号
2012/11/19(月) 07:51
めるまがアゴラちゃんねる、第018号をお届けします。
発行が遅れまして申し訳ございません。
コンテンツ
・「ゲーム産業の興亡」(28)カジュアルゲーム分野で有料課金に成功したPopCap Games
・『世界金融バブル 宴の後の二日酔い』藤沢数希氏×池田信夫 第一回「暴走したマネーゲーム」(その2)
アゴラは一般からも広く投稿を募集しています。多くの一般投稿者が、毎日のように原稿を送ってきています。掲載される原稿も多くなってきました。当サイト掲載後なら、ご自身のブログなどとの二重投稿もかまいません。投稿希望の方は、テキストファイルを添付し、システム管理者まで電子メールでお送りください。ユニークで鋭い視点の原稿をお待ちしています http://bit.ly/za3N4I
アゴラブックスは、あなたの原稿を電子書籍にして販売します。同時にペーパーバックとしてAmazon.comサイト上で紙の本も販売可能。自分の原稿がアマゾンでISBN付きの本になる! http://bit.ly/yaR5PK 自分の原稿を本にしてみませんか?
特別寄稿:
新 清士
ゲーム・ジャーナリスト
「ゲーム産業の興亡」(28)
カジュアルゲーム分野で有料課金に成功したPopCap Games
2001年から、2005年あまりにかけて、パソコン向けのアメリカではネット流通を立ち上げる仕組みが積極的に行われる様になった(現在でも続いているが、またいずれ触れる)。これまで、無料サイトで広告収入モデル以外しか選択肢のなかったユーザーに対して、初めてダウンロード販売による収益の道を開いた「Real Arcade」の仕組みを真似るようにして、次々に類似のサービスが立ち上が多くがパズルゲームや、マリオを簡単にしたようなアクションゲームで、年齢層の高いユーザーを意識しているような軽いゲームが一般的であった。「Real Arcade」や2003年には1億ドルを売り上げて、カジュアルゲーム市場のなかで、一歩先んじた存在になるようになった。
多くのネット流通プラットフォームが立ち上がったが、実際にはほとんどのサービスは失敗している。特にパソコン向けのソフトウェアのプラットフォームは、他企業に依存せず、自社で決して展開することは難しくなく、競争が激しくなったからだ。「Real Arcade」でさえ成功できず、2009年には「Game House」と名前を変え、ネット流通プラットフォームを続けながらも、自社オリジナルのゲームを開発することに力点を置くようにシフトしている。
「Real Arcade」とValveの「Steam」との最大の違いは、自社開発のオリジナルゲームにキラータイトルがなかったことだ。人気の出たタイトルを持つ企業は、自社でネット流通を展開した方が、収益性が高いということに気がつくようになり、「Real Arcade」にもゲームを展開するが、数あるプラットフォームの1社と考え、より力を入れるのは自社サイトを基準とするという方向に転換が進むようになった
■気軽に遊べる落ちモノパズルの大成功が牽引する成功
カジュアルゲームの分野で、最も成功したといえるのが、2000年にシアトルで創業したPopCap Gamesで、最近では「Plants vs. Zombies」というタワーディフェンス型のヒットタイトルを生みだしたことで、断トツに高い評価を集めている。2011年には、エレクトロニックアーツによって、6億5000万ドルで買収が行われ、ヒットタイトルを連発するゲーム開発の実力から考えると安すぎるのでは、という意見も出たが、「ゲームを継続的に開発できる環境を優先した」といった内容を同社幹部は、話している。
同社が、初期の段階で最も成功を引き起こしたのは、2001年にリリースした、「Bejeweled(ビジュエルド)」だ。元々はウェブベースでFlashを使って開発されていたものだ。内容は宝石をつかった典型的な落ち物パズルなのだが、3つの宝石をワンクリックで並べると消すことができ、同時に多数の宝石を消すことができればコンボになり豪華な演出で盛り上げてくれる。「テトリス」などに比べても、はるかに簡単なゲームだが、奥が深くゲームはカジュアルユーザーには大きくヒットすることになった。データサイズも小さいので、ナローバンド回線でも十分に遊ぶことができたからだ。
このシリーズは、現在でも遊ばれ続けており、「Bejeweled 2」、「Bejeweled 3」、「Bejeweled Blitz」、「Bejeweled Twist」など、シリーズの展開が続いている。さらにデータサイズの小ささは、移植が容易にするため、様々なデバイスでの展開を容易にしている。スマホ、Xbox Live Arcade、iTunes、ニンテンドーDSなど、ブラウザ、Facebookなどありとあらゆるデバイス向けに、多様な展開を行っているとこに特徴がある。しまいには、アメリカの飛行機会社の機内サービスとして、シートのテレビ画面で遊ぶことができるようになっているぐらいの長寿命ゲームになっている。7500万本以上がダウンロード販売に成功していると見られている。
PopCap Gamesは誕生当初、収益を上げるために、三段階の方式を採っていた。当然、アメリカのユーザーは、なかなかお金を払わないことを前回指摘していたが、それでも、ユーザーに触れてもらう機会をつくらなければ話にならない。そのため、第一にFLASHで作成された無料のウェブバージョンを展開し、それが気に入ったら、ゲーム内容が豪華になっているダウロードバージョンをダウンロードしてもらい、さらにそれなりに楽しんでもらう(たっぷり30分は遊べる。現在では多くのゲームが30分制限を付けていることが多い)。それで、最後に購入してもらうというものだ。一般的にパソコン版は、15ドルから、20ドルで販売されている。その価格帯によって、開発費が回収できたら、様々なデバイスへと価格を下げながら、展開を押し進めていくとい戦略だ。
宣伝を主な収益源としていたPogo.comといったところと違い、最終的にはゲームを購入してもらうことが大きく目標になっているところが違う。ただし、実際にはお金を払ってもらうまで達することは容易ではない。販売のモデルとしては、ウェブのFLASH版で基本的に同じモデルを用意しておき、そのバージョンで遊ぶユーザーが100とすると、ダウンロードにまで至ってくれるのは10、さらに購入にまで至ってくれるのは1という販売モデルを取っていることを明らかにしている。結局課金ユーザーは1%に留まっているのだ。アイテム課金ではないが、2009年にクリス・アンダーソンが「フリーミアム」モデルという言葉が登場する前から、そのモデルはゲーム分野ではすでに登場していた。
■ネットでは広告モデルのみだったのが有料課金のできる時代に
それまで広告収入以外では、利益を上げることができなかったカジュアルゲーム市場はこうした形で、ユーザーから収益を上げられる企業へと転換できるようになった。2007年には各種立ち上がってきている様々なデジタル流通プラットフォームでも、販売を行う一方で、自社のネット流通にも積極的に取り組むようになった。一方で、Real Arcadeは力を失っていった。
PopCap Gamesは様々なカジュアルゲームをリリースしているが、ビル・ゲイツが「Xbox Live Arcade」の立ち上げの際にプロモーションのために「お気に入りゲーム」として紹介した、パズルゲームの「Zuma」(2004年、このゲームは1998年の日本企業のゲームセンター用の「パズループ」ゲームシステムをそのままコピーしたクローンだという指摘がある)、コミカル要素が高く世界中で大ヒットしたタワーディフェンスゲームの
「Plants vs. Zombies」(2010年)など質の高いゲームをヒットさせている。
ネット流通の成功であっても、結局は、キラータイトルの役割は非常に需要だ。これは、家庭用ゲーム機といったモデルとも同じだ。ただ、一度キラータイトルを手にすることができれば、徹底して様々なネット流通を利用して販売機会を広げていく、という点が、ダウンロード型のゲームの特徴だ。パッケージゲームの購入が必要な家庭用ゲーム機の販売モデルとも、常にサーバにアクセスしていることを前提とするソーシャルゲームとも大きく違っている点だ。
□ご意見、ご質問をお送り下さい。すべてのご質問に答えることはできないかもしれませんが、できる範囲でメルマガの中でお答えしていきたいと思っています。連絡先は、sakugetu@gmail.com です。また、既存の執筆記事情報をまとめたサイトもスタートしました。「新清士オフィシャルブログ」http://blog.livedoor.jp/kiyoshi_shin/ ご参照いただければ幸いです。
新 清士(しん きよし)
ジャーナリスト(ゲーム・IT)。1970年生まれ。慶應義塾大学商学部、及び、環境情報学部卒。他に、立命館大学映像学部非常勤講師。国際ゲーム開発者協会日本(IGDA日本)副代表。日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)理事。米国ゲーム開発の専門誌「Game Developers Magazine」(2009年11月号)でゲーム産業の発展に貢献した人物として「The Game Developer 50」に選出される。連載に、日本経済新聞電子版「ゲーム読解」、ビジネスファミ通「デジタルと人が夢見る力」など。
Twitter ID: kiyoshi_shin
世界金融バブル 宴の後の二日酔い
藤沢数希×池田信夫
続き(1.暴走したマネーゲーム)
池田:資本主義の流れから言うと、もともとは産業資本主義から始まって、成熟してくると、金融資本主義になるって言われます。イギリスがその最初ですが、アメリカがこういう風になるのは必然という感じもするんだけど、でもそれってやっぱりどっかで落とし穴があって、金融だけでこんなにむちゃくちゃに儲かるのはおかしい。
藤沢:金融ってあくまでサポート役なはずで、経済活動の黒子なのに、金融が主役になっちゃってるんですよ。さらに金融が主役になっちゃうと金融機関ってたくさんお金を持ってるから、政治家にもいっぱい献金できるし、あと、回転ドアって言われてますけど、ゴールドマン・サックスなどの投資銀行から、アメリカの財務省などの政府の要職に就いたり、そこからまた投資銀行に戻ってきたり、いい意味でも悪い意味でも人の交流がある。
こうして、民間の金融機関の政治力もどんどん強くなってって、そういうのがある意味で行き着いた先がリーマンショックだったんですよね。
池田:前に経済学者の池尾和人さんと、リーマンショックの直後に対談をして、世界はなぜ不況に陥ったのかっていう本を一緒に書いたことがあるんだけど、あの時に彼も言ってたのは、アメリカの投資銀行のビジネスモデルというのは、藤沢さんの本にも書いてありますが、元々は顧客企業の財務アドバイザーや、機関投資家が市場で取引するときの仲介業務だった。
また、リスクを取る自己勘定取引ではアービトラージ(鞘取り)するとか、要するに価格の歪みを利用してその歪みが均衡状態になるまでのとこで儲けるというのがもともとのコンセプトだったわけですよね。ところが、その価格のゆがみってのはそういうテクニックが発達すればするほどすぐなくなってしまうと。そうするとだんだん自ら歪みをを作り出してバブルを作っていくようなビジネスにみんなが行き始めた。
藤沢さんの専門の金融技術も、もともとは理論価格を計算して現実の価格との鞘を取るというものだったけど、それでもうける時代はとっくに終わって、「レギュラトリー・アービトラージュ」といわれる税制などの歪みを利用してもうけるものが多くなった。そのあとは「仕組債」といわれる複雑な金融商品をつくって、中身をブラックボックスにして顧客をだますようなビジネスが横行した。それがリーマンの破綻で、一挙にデフォルトになったわけですね。
藤沢:元シティ・グループのCEOのチャールズ・プリンスが言ってたんですけど、「音楽がなってる間は、とにかく踊り続けなければいけない」ってね。確かにみんなでバブルを作って、それに乗っかって行くって、みんなすごく儲かるんですよ。はじけるまではね。
昔は、外資系投資銀行は、「飛ばし」で企業の会計操作を幇助するとか、あとは複雑なデリバティブで投資家からたくさん手数料と取るとか、そういうビジネスをして儲けていて、そういう意味では、事業会社や投資家「から」儲けていたんですけど、バブルが巨大になりすぎて、それを取り巻く金融機関も巨大になりすぎて、最後は世界経済全体を人質にして金を儲ける、というようになったと思うんです。こういう、みんなでバブルを作って、それに乗って行く、という大きな流れの中で、マネーゲームの規模がインフレートして行ったんですよね。
グローバル経済を使って、ものすごい博打を売って、自分たちは"Too Big to Fail"だから、大失敗したときのリスクは全て納税者に押し付けつつ、自分たちはいいとこは取れる、というような仕組みが作られていったわけですよ。だからすごいモラルハザードなんです。
金融機関の規模が大きくなって、すごく複雑になっていって、システミックリスクがどんどん増大していった。こうしてバブルを作って、そこで儲けながら、バブルがはじけた時のコストを納税者に押し付けたわけですね。
池田:いまはどうなんですか? 2008年まではそういう良い時代だったかもしれないけど、あの後ガタガタになって、この本を見ると規制されてがんじがらめにされつつあるようですが。
藤沢:金融機関は基本的に規制業種だから、どうやって規制されるかとか、法律とかで決められるゲームのルールで自分たちの儲けが大きく変わるわけです。そういった法規制に、うまくいい感じに儲かるように穴が空いていたら、みんな黙ってるけど、自分たちが不利なところは必死でロビー活動する。
それで規制監督当局と民間のプレイヤーとの、悪い感じの共同作業というか、そういうので、世界の金融機関はどんどん暴走するような方向にいったわけですよね。それでリーマン・ショックが起こった。それから一気に規制を強めようということになっているのですが、それは実は言うほど簡単ではないんです。
金融規制のすごく難しいところは、金融機関は多国籍企業だから、アメリカが規制すると今度はイギリスに行っちゃうよ、と。イギリスが規制しても、スイスとか香港に穴が開いてますよ、という感じで、世界同時に上手く規制しないと、ダメなんですよ。だから、一言で規制すると言っても、非常に難しいんです。やっぱり規制が緩くて、好き勝手できる方に行っちゃうから。
池田:ケイマンとか行っちゃうと、かえってわからなくなるんですね。私も取材したことがあるけど、すごい世界ですよ。熱帯の椰子の木しかない小島に、巨大な金融センターがあって、そこだけがニューヨークの真ん中みたいになっている。
大蔵省で銀行についての資料を調べようとすると、簡単な登記簿しかない。法人税を取ってないから、財務諸表も何もないのです、大蔵省に。でもすごいビルがあって勤務している人がたくさんいるので、ケイマンみたいな小さな国としては、所得税や消費税で十分です。
ケイマンの監督官庁が知らないわけだから、世界中の誰も知らない。ロシアの国有企業の経営者が会社の金を横領して送金したり、麻薬の代金をマネーロンダリングしたりする金がケイマンに流れ込んでいるといわれますが、実態はまったくわからない。
藤沢:で、いまはもう複雑すぎて、だれもよくわからないんです。世界の金融機関は社会に提供している付加価値以上のものを受け取り過ぎているんだけど、それを規制するのは非常に難しいんですよね。各国に主権があるわけだし。
だからアメリカとか、ある意味で怖い国がリーダーシップを取って、世界的に規制していくしかないんです。スイスにしたって、香港にしたって、アメリカに睨まれたら言うこと聞くしかないわけで。だから金融機関は変わるべきだとは思ってますけど、ほんとに世界がみんながフェアに幸せになるように上手く規制をしていくのは、ことのほか難しいですね。
新着記事
- お知らせ「言論アリーナチャンネル」の無料チャンネルへの運用移行 39ヶ月前
- 2014年12月第4週 135ヶ月前
- 2014年12月第3週号 136ヶ月前
- 2014年12月第2週号 136ヶ月前
- 2014年12月第1週 136ヶ月前