younghopeさん のコメント
このコメントは以下の記事についています
平和的手段での平和構築①第二次大戦以降、植民地経営は、抵抗運動や植民地への経済投資の負担で、宗主国にはマイナスの事業となりました(『21世紀の戦争と平和』から)
私は、植民地という問題にかなり早い段階で関心を持ちました。一九六六年に外務省に入省し、その九月から英国陸軍学校でロシア語を勉強しました。この学校では英国の軍人がロシア語やアラビア語を学ぶと同時に、植民地の軍人や傭兵的軍人を教育する場でもありました。グルカ軍やイエーメン軍の将校が私たちといっしょに将校宿舎にいたのです。
一九六〇 年代初め、アラブ連合共和国のガマール・ナセル大統領のアラブ民族主義に触発され、イエーメンで独立運動が勢いを持ちました。 一九六七 年、英国軍隊は 一八三九 年以来の支配を終え、イエーメンから撤退し、南イエーメンの独立が宣言されました。
そして、一九六八年、ポンド切り下げの数週間後、ハロルド・
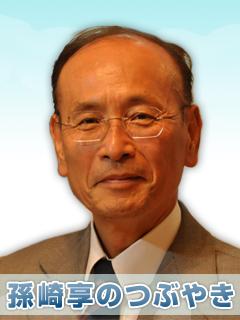
金融緩和し、かなりのマネーが、金利が高くなれば、米国に流れていく。政府だけでなく、金融会社、企業、個人投資家が米国債、米国株に投資することになる。国家が買えばしおずけになるというより、米国の借金経営をバックアップすることになる。日本に対しては、今までの政策以上のことは、米国もできないことが分かっているのに、慌てふためいている。頼ることしかできないが、頼ることができないと、日本がどの国とも対等に外交をしていかなければならないので、敵か味方の選別しかしないと短絡的に考えると、いつか来た道をたどるしかない。いつ自立できるのであろうか。
Post