changeさん のコメント
このコメントは以下の記事についています
徳川慶喜は大政奉還を行います。朝廷が主体の政治になることが確定しました。
そのあり様が検討されます。
新しい体制で、一番重要な点は、有力藩の藩主が入っていますが、徳川慶喜が入っていないことです。
十二月九日一八時頃から、御所内・小御所にて明治天皇臨席のもと、最初の三職会議が開かれます。
会議は冒頭、中山忠能より開会を宣し、を述べて曰く、
「徳川内府政権を奉還し、将軍職を辞するを以て、其の請を充し給う。因て王政の基礎を肇設し、萬世不抜の国是を建定し給はんとす。各皆聖旨を奉体し、以て公議を盡すべし」との勅旨を述べます。
ここで、山内容堂が、「『此の小会議に速やかに徳川内府を召して出席せしめ、朝議に参与せしむべし』と述べます。
ここから、徳川慶喜の出席を巡り激しい議論が起こります。
会議は紛糾し結論が出ません。一時休憩となります。
その模様を晩年後述した
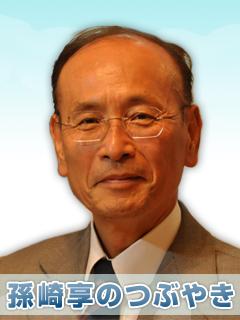
当事者であり、わかっていないはずがないのに、西郷の「得ざる時は之れあるのみ」と剣を示したそうであるという伝聞言葉に引っかかり、少し調べてみた。
「西郷から岩倉、岩倉から浅野、浅野から土佐藩の後藤象二郎に説得が重ねられ,豊信(容堂)は心折れ、王政復古を議定した」という表現は、権力闘争が武力の結果であることを強く暗示している。
一方、岩倉公実記の「豊信(容堂)猶ほ~決っせんのみ」の文章とほとんど同じであるが、浅野長勲自叙伝では、最初に武力誇示者西郷が加えられている。
このあたりの差異がどうして出たのか興味のあるところです。そのあたりの論考があると面白い。
Post