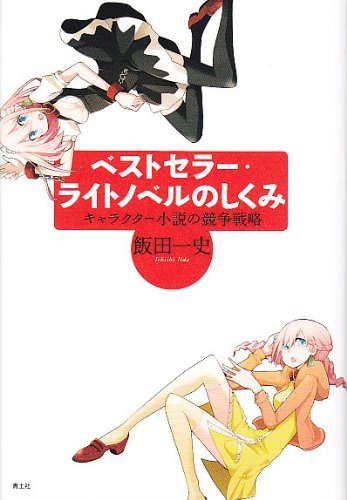こんなまとめを見つけた。
・ラノベとミステリについて(http://togetter.com/li/31907)
・続・ラノベとミステリについて(http://togetter.com/li/33363)
・続々・若い読者を取り込むには?(http://togetter.com/li/34035)
・ラノベとミステリについてリターンズ(http://togetter.com/li/383982)
まとめられているツイートは数多く、論点は多岐にわたるが、あえて乱暴に要約するなら「なぜライトノベルで(本格)ミステリが少ないのか」を議論しているようだ。
たしかに考えてみれば不思議なことである。エンターテインメント小説全般ではミステリは最も多くの読者を獲得しているジャンルだ。往年の赤川次郎や西村京太郎、昨今の東野圭吾、伊坂幸太郎などは、狭い意味での本格ミステリ作家ではないかもしれないにせよ、本格の技法を応用することによって膨大な読者を獲得している。
なぜ、ライトノベルではこれと同じことが起こらないのか。いくつもの意見が挙がっているが、たとえば実は起こっているが目立たないだけだという可能性も考えられるだろう。
まとめのなかでもふれられているが、野村美月の『文学少女』シリーズなどは、思わせぶりな伏線やミスディレクションといったテクニックを使いこなしているという意味で、非常に本格ミステリ的だといえる。こういう作品を本格ミステリの一種だとみなすならば、必ずしも現代ライトノベルに本格ミステリが見あたらないとはいえなくなるだろう。
しかし、怪しい事件が起こって探偵が乗り出し、意外で論理的な解決が待ち受けているというようないわゆる「ガチガチの本格」がライトノベルに少ないことは事実だと思う。
なぜか。上記のまとめのなかでは本格ミステリは量産が困難だから、という意見が多いようだ。現代ライトノベルはセールスの問題から必然的に量産を余儀なくされる。そのペースで本格を書きつづけることはできないというのだ。
一理はあると思うが、実は反論がないこともない。本格ミステリの量産は必ずしも不可能ではないのだ。たとえばエラリイ・クイーンは一年間で『Xの悲劇』、『Yの悲劇』、『ギリシャ棺の謎』、『エジプト十字架の謎』とミステリ至上に冠絶する傑作を立て続けに発表している。
アガサ・クリスティなども多作だし、何より日本ではハイレベルな本格ミステリ漫画を驚異的なペースで刊行しつづけている加藤元浩という作家がいる。同時に二本の本格ミステリ漫画連載を書きつづけるあの異才のことを考えると、「本格は量産できない」というのは一面的な見方に見えてくる。
もっとも、クイーンの話は長い作家歴のピークでのことだし、加藤のことは超例外だと考えるべきなのかもしれない。全体的に見れば、本格ミステリプロパーの作家ですら、歳を取るほどに「ガチガチの本格」と呼ばれるような作品の数は少なくなっていく傾向があるように見える。
かつていわゆる新本格ミステリを代表する作家だった綾辻行人や有栖川有栖にしても、これぞ傑作!という本格ミステリは数年に一度あるかどうか、というところだ。傑作レベルといえるレベルの本格ミステリを量産することは、不可能ではないにしろ、どんな作家にとっても簡単ではないということか。
さらにいえば、ライトノベルリテラシーと本格ミステリリテラシーを併せ持つ作家はきわめて少ないということにも注目するべきだと思う。本格ミステリの傑作を書くために高度な本格ミステリリテラシーが必要であるということはだれにでもわかるだろう。
作品全体を広く見通して精緻なロジックなり意外なトリックを構築するためには、過去の作品に関する知識や、それらを応用して新しい展開を生み出す発想力がどうしても必要になる。それが本格ミステリリテラシーだ。
一方、おもしろいライトノベルを書くためには高度なライトノベルリテラシーが必要であるという認識はまだ常識にはなっていないようだ。まとめのなかでもいくつかライトノベル執筆をあなどっているとしか思われない発言はいくつかある。
しかし、ライトノベルを書くことそのものはともかく、ライトノベルでヒットを出すことは簡単ではない。たとえばライトノベル業界で最も有名な新人賞である電撃大賞は毎回数千もの応募作が集まる限りなく狭い門であり、しかもそれを受賞してもその後がうまくいくという保証はない。じっさいにライトノベルでベストセラーを連発している作家たちは、きわめて高い能力をもっているとしか思われない。
仮によくいわれる「イラストが綺麗ならOK」「エロいだけでいいんだろ」「できあいの萌えキャラさえ出しとけば売れる」といった言葉が真実であった時代があるとしても、既にそれは終わってしまった。
当然ながら簡単に模倣可能な方法論は簡単に模倣作が乱発し飽きられる。ひとにぎりのベストセラーライトノベル作家たちは(たとえ一見、簡単に書いているように見えるとしても)きわめて独創性の高い方法論を駆使しているとしか考えられないのだ。
しかも、オタク文化全体の変遷とともに、ライトノベルリテラシーは日進月歩で変化している。通常の何倍も早い時間の進み方を意味するドッグイヤーという言葉があるが、ライトノベルイヤーも決して遅くはない。流行はものすごい速度で変わっていくのである。
もちろん、本格ミステリのなかにも「ライトノベル的なるもの」は存在している。たとえばホームズなり中善寺敦彦なり火村英生に「萌えキャラ」的なところがないわけではない。
だからまとめのなかで語られているように、たとえば西澤保彦の『チョーモンインシリーズ』に「ライトノベルっぽさ」を感じるのはわかる。しかし、仮にいまこのシリーズをどこかのライトノベルレーベルから出したとしてもヒットはしないだろう。
これは断言できる。なぜなら、『チョーモンインシリーズ』はいまのライトノベルのトレンドに合わせて書かれていないからだ。それは致命的に古く、しかもピントが合っていないのである。
ほかのジャンルで活躍している作家がライトノベルで必ずしも活躍できないのはかぜか。非常に単純な話で、ライトノベルを書くことがむずかしいからだ。ほかのジャンルで一流の技量があればライトノベルも書けるというような簡単なものではないのだ。
ライトノベルを書くことは簡単ではないし、一流のライトノベル作家は他のジャンルの一流どころと比べても何ら恥じるところがない立派な仕事を成し遂げているという認識を広めなければならない。なぜならそれが事実だからだ。現状ではライトノベル作家は不当に低く見られている。
ただ、と一方では思う。あるいは、その時々で最も流行しているエンターテインメントの作家はしょせんリスペクトなど受けられないものなのかもしれない。リスペクトを当然視しはじめるところから権威主義が始まり、純粋な実力勝負が妨げられるのかもしれない。
SFやミステリにしても、パルプフィクションとして、不当に低く見られていた時期はあった。そしてその時期こそ、ジャンルの黄金時代だったということも考えられる。リスペクトを求め始めれば、その文化は結局は権威主義かして伝統芸能と化してゆく運命なのかもしれない。真実はわからないが、ぼくはそんなふうにも思うのである。
もしかしたら「この程度の小説、おれにだって書けるよ」と読者に嘯かせるくらいがちょうどいいのかもしれない。じっさいには決して書けはしないのだが、「おれにだって書ける」という幻想が意味をもっているということは十分に考えられる。
だれにでも書けるように見えて、だれにも書けない小説――それが結局、いちばん受ける作品なのかもしれないのだ。自分ならそれくらい書ける? そう思うなら、書いてみればいい。すぐに数千万からの年収が手に入ることだろう。ま、ぼくは無理だというほうが賭けるけどね。