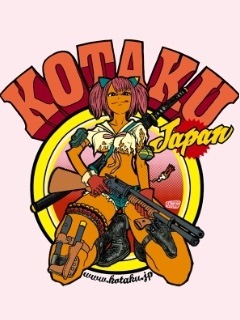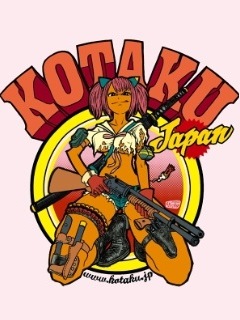小説、マンガ、テレビドラマに映画と、あらゆるフィクション作品に登場するロボットたち。20世紀中盤の電子楽器の登場以来、音楽作品の題材としても、たくさんのアーティストにインスピレーションを与えてきました。 本日はロンドンにある一風変わった博物館「ウェルカム・コレクション」のスタッフ、ロバート・ビッダーさんが選んだ、ロボットやサイボーグやアンドロイドをモチーフにした楽曲群をご紹介します。 詳細は以下より。
【大きな画像や動画はこちら】
「ウェルカム・コレクション」は医学、科学、人間とアートをテーマにした博物館で、つい先日まで、フィクションと現実世界に見られる機械の体や強化人間を特集した「スーパーヒューマン展」を行なっていました。 ビッダーさんは展示の準備をしている間、人体のメカニズムを工場に見立てたフリッツ・カーンのイラスト作品「産業の神殿としての人体」に惹かれ、どうしてもある音楽グループのことを思い出さずにいられなかったそう。それが、クラフトワークです。
『The Robots』クラフトワーク
クラフトワークは70年代に電子音楽グループの先駆けとして、その後の数多くのアーティストに大きな影響を与えました。1978年のアルバム『ザ・マン・マシン』(邦題:人間解体)には、上記のフリッツ・カーンや、映画監督フリッツ・ラングによる『メトロポリス』、哲学者ニーチェの『ツァラトゥストラはこう語った』に登場する「超人」など、ドイツから生まれた作品や思想の影響を感じさせる部分があるとビッダーさんは言います。 人間とテクノロジーの関わりを表現してきたクラフトワーク作品のなかでも象徴的だったのが、1977年のシングル『The Robots』(上)です。
『Freedom of Choice』ディーヴォ
クラフトワークのアメリカ的アプローチと言われてきたグループが、ディーヴォ。確かにメンバー全員が同じ服、電子楽器を使用する、楽曲の哲学的テーマなど、クラフトワークと似た点もありましたが、実際のところはまったく別のタイプのグループだったと言うべきでしょう。 彼らはクラフトワークほど人間と機械のテーマにこだわってはいませんでしたが、
『メカニカル・マン』や『スマート・パトロール/Mr. DNA』などの楽曲ではサイボーグを使って「人間の退化」(退化=de-evolutionはバンド名の語源)という彼らのセオリーを描いてみせました。 上の『フリーダム・オブ・チョイス』のビデオでは、髪がなく空に浮かぶ未来のロボトイドとなったディーヴォのメンバーが登場。ローラースケートに興じる若者と古代ローマ人とドーナツを通して、消費社会の落とし穴について描いています。うーん深い。
『Geburt Einer Nation』ライバッハ
スロベニアの実験音楽バンド、ライバッハは、ファシスト的なイメージをたびたび使用しては物議を醸してきました。彼らはそれを風刺やパロディだと主張していますが、実際、その風刺を理解せず真に受けてファンになる人も多くいたそうです。 機械音のサンプリングやドシンドシンと歩くような音から、インダストリアルやインダストリアル・メタルのカテゴリに入れられることもありますが、その型にはまらない多様なスタイルを持っていました。歌詞には人間とテクノロジーの関係のようなものもちらほら表れ、最も顕著だったのが彼らのコンセプト・アルバム『ジーザス・クライスト・スーパースターズ』で、この中でキリストはジャッジ・ドレッドやロボコップのようなキャラクターとして描かれます。クイーンの『ワン・ビジョン』のドイツ語カバーである『ゲバート・アイナー・ネイション』は、ライバッハのみなさんと雄ジカたちが繰り広げる超人的ファンタジー、だそうです。
映画『ムーンウォーカー』マイケル・ジャクソン
若干マニアックな方向に行っているようなので、このあたりでマイケル・ジャクソンを。1988年のミュージカル映画『ムーンウォーカー』ではマイケルが巨大ロボットに変身して悪者を退治し、最後は宇宙船に変形して子供たちを守るのでした。さすがマイケル。
『アー・「フレンズ」・エレクトリック?』チューブウェイ・アーミー
イギリスのミュージシャン、ゲイリー・ニューマンはその活動初期に、やはり人間と機械のコンセプトに傾倒した一人。1979年のチューブウェイ・アーミー名義のアルバム『レプリカズ』は、『ブレードランナー』風な未来世界でマッハマンと呼ばれるアンドロイド警察が人間を取り締まるという設定のコンセプト・アルバムでした。 シングル『アー・「フレンズ」・エレクトリック?』では偏執狂的なディストピアの重く憂鬱な物語を描き、当時のヒット曲に。ゲイリー・ニューマンはこの後も同様のテーマの作品を作りました。「トップ・オブ・ザ・ポップス」に出演した時のビデオクリップ(上)では、いかにもロックらしいパフォーマンスをすべて捨て去り、ほとんど動かずに演奏する姿で無機的な不気味さを演出しています。
『オール・イズ・フル・オブ・ラブ』ビョーク
ビョークの歌にはよく人の体を強く意識した歌詞が出てきます。アルバム『メダラ』では、全曲人間の声だけを楽器として使用しました。彼女の曲で機械と人間の関わりを歌った曲は特に思い出されませんが、ビデオクリップの中で2体のロボットのビョークが抱擁を交わす『オール・イズ・フル・オブ・ラブ』は無視できません。 このビデオを監督したのは、数々のミュージックビデオ作品で知られるクリス・カニンガム。彼は活動初期には映画製作に携わり、スタンリー・キューブリックの下で映画『A.I.』の特撮デザインにも関わっていたそうです。
『テクノポリス』イエロー・マジック・オーケストラ
ビッダーさんが日本代表として紹介したのはやはりYMOことイエロー・マジック・オーケストラ。未来都市上空に現れた、宇宙船のような神様の頭(のような坂本龍一さんの顔)の下で演奏するYMOといった感じでしょうか。 また同じ流れにあるグループとして、POLYSICSの名も挙げられました。(そういえば彼らの『ドモアリガトミスターロボット』のPVはモロにロボットですが、この手のはビッダーさんのテイストに合わなかったんでしょうか。あれだけ有名なスティクスの原曲もスルーされてますね。)
『オー・スーパーマン』ローリー・アンダーソン
ローリー・アンダーソンはその楽曲とビジュアル・アートの両方で、人間とテクノロジーの関係を描いて来ました。『オー・スーパーマン』はドラムがなく、サビもない上に非常に謎めいた歌詞の8分半の大作ですが、UKチャートの2位を記録しました。 この曲に登場するスーパーマン(「超人」ですね)とは、人類の力や、欧米の権力などを比喩的に表しているよう。ビデオではロボット的な動きや口の中の光、ボコーダー(ボーカル音声にかかっているエフェクト)などで未来的な雰囲気が出されていますが、何よりもサイボーグ的なものを意識させるのは最後の歌詞の部分です。 ---------------------------------------
「だからお母さん、私を抱いてください。
あなたの長い腕に。
あなたの自動制御の腕に。
あなたの電気じかけの腕に。
あなたの腕に。
あなたの石油化学製の腕に。
あなたの軍事力の腕に。
あなたの電気じかけの腕に。」
---------------------------------------
『テクノロジック』ダフト・パンク
ダフト・パンクはサイボーグに扮した最も有名な現代のグループでしょう。フランス出身の二人がこの格好をするようになったのは2枚目のアルバム発売以降で、素顔を隠すためという理由もあるようですが、一応はこれが音楽ユニットとしてのコンセプトとなっています。 ビデオは不気味なアンドロイドの子どもが出てくる『テクノロジック』。ちなみにこの曲の収録されているアルバムのタイトルは『ヒューマン・アフター・オール』で、「やっぱり人間」というような意味です(同名シングルの邦題は『所詮人間』)。テクノロジーやサイボーグ的なテーマに惹かれるのも、考えてみれば逆にすごく人間らしいことなのかも、とちょっと思ったりして...。
さて、今回は「ウェルカム・コレクション」スタッフ、ロバート・ビッダーさんが選んだロボット/サイボーグ/超人をテーマにしたポップミュージックをご紹介してきました。 人間とは、テクノロジーとは、と考えさせられるヘヴィーなコンセプトに胃もたれしそうな私とあなたのために、最後は海外読者のTohru Rokunoさんがコメントに貼ってくれたパフュームの曲でさわやかにお別れしたいと思います。
『Spring of Life』Perfume
A brief history of cyborgs, superhumans and robots in pop music [io9] (さんみやゆうな)