ベストセラー『国家の品格』の著者藤原正彦が、画家安野光雅との対談を収めた一冊。それなりにおもしろい本なのだが、どうも首をかしげる記述が多すぎる。日本語贔屓が過ぎて、贔屓の引き倒しになってしまっている気がする。たとえば、日本語の語彙の豊かさを語った箇所はこう。
シェークスピアは、四万語を駆使したと言われています。すごいと思うけれど、しかし日本語というのは中学生用の国語辞典を見たって五万語くらい出ています。広辞苑は二十三万語です。
五百年前の一個人と現代の辞典を比べることにどれほどの意味があるのだろう。比較するならせめて同時代の英語と日本語でなければならないだろう。そもそも語彙が多ければ言葉遣いが豊かだということにはならないし、古の日本語はやたらに「をかし」だの「わろし」で済ませてしまう言語ではなかったか。
また、藤原は安野の言葉を受けて、欧米の韻文を批判する。
藤原 その通りです。行末に同じ音を置くことでリズムがでます。例えば、red,head,dead,breadなどを文末に配します。欧米人は好むようですが、私には「無理しているなあ」とか、「駄洒落っぽい」と思えることもあります。リズムは確かに出るのですが。
しかし、文末で韻を踏むのは何も欧米の詩だけではない。藤原が賞賛する漢詩だって原文はそうである。何も日本語を褒めるために外国語を貶すことはないじゃないか。
藤原はいう。
わが国は世界に冠たる文学の国である。全国民がこれに触れ、とりわけ若いうちに触れ、美しい情緒を培い、祖国への深い誇りや自信を得ることは、私の、そして恐らく安野先生の願いでもある。本書がそのための水先案内人となったとしたら幸いである。
本当にそうなのだろうか。日本語はほかの言語より美しい言語なのか。そして、文学とはその美しい言語を通して祖国への自信をはぐくむような代物なのか。何か違うんじゃないの、とぼくなどは思ってしまう。
石川九揚は、西洋言語学を批判した著書『日本語とはどういう言語か』のなかで、こう書いている。
三種類の文字をもつ言語が世界に類例を見ないことからいえば、日本語は非常に特異な言語です。ただしそのことは、先ほどもお話したように、優れたことでも劣ったことでもなく、メリットとデメリットの両方をもたらすことがあると、少し注意深く考えておいたほうがいいと思います。よく「美しい日本語」という言葉を耳にしますが、漢字と平仮名と片仮名の三つの文字が混在して使われるのですから、整合的な美しさに乏しく、一概に「日本語が美しい」とはとてもいえないはずです。
この意見に賛成する。たくさん文字があれば美しい豊かな言語だというなら、日本語にアルファベットを加えればもっと美しい言語が出来るはずだ。そんな話はない。
日本語ブームである。それも、やたらに「美しい日本語」と「祖国への誇り」がワンセットで語られる。たとえば、このサイト(http://meisou03.exblog.jp/)では、「日本の弱体化」を救うため、「美しい日本語」を集めている。
今、日本の弱体化が叫ばれています。有識者の推察によれば、言葉の乱れが大いにこれの原因になっているそうです。
もっと言えば、外国語、特に英語ではとうてい表現できない「美しい日本語」がどんどん廃れていると思います。日本語ならではの美しい、情緒にあふれた言葉に恵まれたかつての日本民族……。これを単なる懐古主義にとどめず、復活しなければ日本民族の滅亡に拍車がかかる、という危惧にとらわれるのは私のみではないと思います。
ここにあるものは、日本民族の象徴としての日本語という概念である。しかし、日本語とはそもそも、外国語である漢語を取り込むことによって成立したものではないか。
この試みは、決して荒唐無稽なものではない。じっさいに、「乱れた日本語」ならぬ「美しい日本語」だけを集めた『美しい日本語の辞典』という本が出版されている。
美しい日本語。乱れた日本語。両者は対極の概念に思える。しかし、そもそも、「言葉の乱れ」とは何か。この点にかんしては藤原も少しふれているが、言葉は乱れるものであり、昔から乱れつづけているものである。たとえば、川口良と角田文幸『日本語はだれのものか』では、清少納言が「言葉の乱れ」を嘆く言葉を取り上げている。
男も女もよろづの事まさりてわろきもの ことばの文字あやしく使いたることあれ。ただ文字一つに、あやしくも、あてにもいやしくもなるは、いかなることにかあらむ。(中略)なんなき事を言ひて、「その事させんとす」と、「言わんとす」「何とせんとす」と言ふを、「と」文字を失ひて、ただ「言はんずる」「里へ出でんずる」など言へば、やがていとわろし。まして文を書きては、言うべきにもあらず。
口語訳は面倒なので省略するが、簡単にいうと、「言はんとす」「何とせんとす」などというべきところを、「と」を除いて「言はんずる」「里へ出でんずる」などと云えば、ひどく「わろし」であるという意味だ。
ようするに、清少納言はその時代の「と抜き言葉」が気にいらなかったわけだ。現代の「らぬき言葉」とそれに対する反発が、日本語の長い歴史を眺めれば決してめずらしい現象ではないことがわかる。
また、清少納言から一千年後の作家兼エッセイストである三島由紀夫はいう。
私は小説ではない随想の文章に、「僕」と書くことを好みません。「僕」という言葉の日常会話的なぞんざいさと、ことさら若々しさを衒ったような感じは文章の気品を傷(そこな)うからであります。私は「僕」という言葉は公衆のまえで使う言葉とは思いません。それは会話のなかだけで使われる言葉でありましょう。
しかし、その三島の使う「日常会話的」も、柳田国男にいわせれば、「あさましい」間違えた日本語である。
今日標準語として余儀なく認められるものの中にも、いたって素性の不明な下品なものが幾らもまじっており、それでいてなおわれわれはいつも形容詞の飢饉を感じているのである。これに対する応急策としては、かの何々的とかいうやつはむしろあさましい鼻元思案であった。歴史になんの根拠もないのみか、中国の元方においてもそんな風には「的」は使っていない。幸いにして今はまだ年寄りや女子供はこれを顧みず、歌謡文芸にまで取り入れようとするほどの勇敢な者もないからよいようなものの、こんなものが日本の標準語になるようであったら、それこそ大変な話ではあるまいか。
このように、一千年間も日本語は「乱れ」つづけていて、その時代の識者に不快感をもたらしていたのである。いまさら「言葉の乱れ」を批判してもどうにもならない。
それでは、「美しい日本語」なんてものは存在しえないのか。しょせんそれは幻なのか。いや、ある、とぼくは思う。正しくは「美しい日本語」はなくても、「美しい日本語の使い方」はある。たとえば、こんな日本語を見ると、ぼくは瞬間的に「美しい」と、狂おしいような感覚を味わうことになる。
わたくしといふ現象は
仮定された有機交流電燈の
ひとつの青い照明です
(あらゆる透明な幽霊の複合体)
風景やみんなといつしよに
せはしくせはしく明滅しながら
いかにもたしかにともりつづける
因果交流電燈の
ひとつの青い照明です
(ひかりはたもち その電燈は失はれ)
隴西の李徴は博學才穎、天寶の末年、若くして名を虎榜に連ね、ついで江南尉に補せられたが、性、狷介、自ら恃む所頗る厚く、賤吏に甘んずるを潔しとしなかつた。いくばくもなく官を退いた後は、故山、かく(常用漢字ではないので出ません。ごめんなさい。)略に歸臥し、人と交を絶つて、ひたすら詩作に耽つた。
宮沢賢治の『春と修羅』と中島敦の『山月記』だ。主観の粋をこえるものではないにしろ、ここにはたしかに「美しい日本語」、「美しい文学」があるように思える。
しかし、それは、即座に「祖国への誇り」につながっていくような、いうなれば漂白された日本語ではなく、増して「正しい日本語」などではありえない。ただ、日本語のもつ可能性を極限まで引き出しているという一点に於いて名文となっているだけである。「美しい日本語」はないが「日本語の美しい使い方」はある、というのはこういう意味だ。
どんな言葉でも、それなりの歴史と、可能性、メリットとデメリットを秘めている。レゴのブロックのようなものだ。組み立てるものが組み立てれば城砦を築くことも出来るその一方、下手糞が造れば奇怪な建物まがいが出来るばかり。ブロックを取り出して美しいの汚いのといっても意味がない。
そして、長い時間のなかで、必要でないブロックは排除され、必要なブロックは補充される。ブロックそのもののかたちが変わることもある。それが「言葉の乱れ」。
若者たちが使う「ら抜き言葉」や「乱れた言葉」を腹立たしく思うひともいると思う。しかし、そんなときは、清少納言も「と抜き言葉」を怒っていたことを思い出そう。
そして、その「乱れ」が、一時のものなのか、それとも時代の流れなのか見極めよう。もしそれが時代の流れならば、どんなに抵抗しても受け入れられていくだろう。「と抜き言葉」も「ら抜き言葉」も同じことだ。

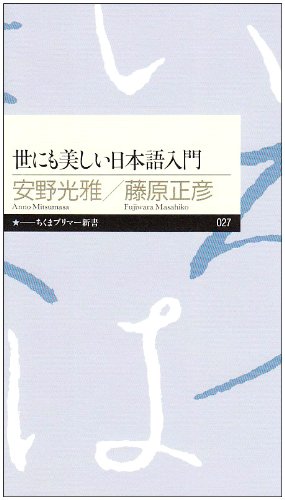

コメント
コメントを書く