そいつは、見たことのある顔をしていた。
森の中から、ふたりで、ずっとおれに話しかけてきた、あの声を発していたやつらのかたわれだ。
説教師(マニパ)ツオギェル――
そう名のっていたっけ。
そいつが、話しかけてくるのである。
もう、やめろ――と。
もう、いいではないかと。
なんだか、うるさい。
なんだか、わずらわしい。
大きなお世話ではないか。
こんなに、自分は今、満ち足りていて、しかも気持ちがいいのに。
どうして、これをやめねばならないのか。
そうだ。
こんなに、幸せなのに……
だが、妙に不安になる。
おまえは、どうして、そんな哀しそうな顔をするのだ。
さっきの、二本足の大きな漢(おとこ)も、そうだ。
哀しそうな顔で、おれを見ていた。
そんな眼で、見られたくない。
そんなに哀しい眼で、おれを見るんじゃない。
哀れに思われたり、可哀そうに思われたりするなら、怖がられた方が、まだマシではないか。
恐れられた方がいい。
独りでもいい。
独りというのは、もともと、よく研がれた薄い刃物の上に、素足で立つようなものだ。
いつ、バランスが崩れて、自分の足を傷つけてしまうかわからない。
それでもいいのだ。
哀れな人間でいるより、怖れられる獣でいることの方が、おれはいいのだ。
あんまり、そこをうるさく言われると、
ほら――
また、背骨が曲がる。
ぎしっ、
みしっ、
そういう音が、耳に響く。
自分の骨が、曲がる音だ。
変形(へんぎよう)してゆく音だ。
ふふん、
あんまり、うるさいことを言うのなら、もう一度、また、あの獣になって、おまえらみんな、喰ってやろうか。
その時、もうひとりのやつが出てきて、服を脱ぎはじめたのだ。
何だろう。
何をする気だろう。
額から、二本の角まで伸ばしている。
ふわっ、
と、そいつが、月の光の中に浮きあがった。
「麗……」
と、そいつの声が聴こえた。
麗?
何のことだ。
人の名前か。
その麗というのは、このおれの名か。
宙に浮いたそいつは、ゆっくりと、おれの眼の前に舞いおりてきた。
半分、獣の顔をしている。
しかし、なんとも痛ましい眼で、おれを見るのだ、そいつは。
気にいらない。
さざ波のように、怒りが広がりかけたが、それがおさまったのは、そいつの顔が妙になつかしかったからだ。
こんな面をしているのに、どこか、遠い昔、自分はこの顔の人間を知っていたのではなかったか。
そのことを考えると、じんわりとした温かみが、身体の中に満ちてくるようだった。
「息子よ……」
と、そいつは言った。
息子!?
何だ、息子というのは。
おれが、おまえの子供だというのか。
その時、ふいに、おれの身体は、そいつに抱きつかれていた。
きえええ……
ぎいいい……
おれの身体から生えているものたちが反応し、そいつに噛みついた。
肉を噛みちぎり、啖(くら)う。
「かまわん、麗……」
と、そいつは言った。
「息子よ、おれを啖え」
と。
■電子書籍を配信中
・ニコニコ静画(書籍)/「キマイラ」
・Amazon
・Kobo
・iTunes Store
■キマイラ1~9巻(ソノラマノベルス版)も好評発売中
http://www.amazon.co.jp/dp/4022738308/
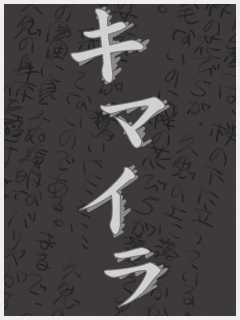

コメント
コメントを書く