私は日々X(旧ツイッター)で国際政治や日本の政治について発信している、今の国際政治や日本の政治がおかしいものだから、私のXはどうしても糾弾調になる。Xが暗くなる。他方私はジョギングやウオーキングを日々東御苑や北の丸公園を散歩し、皇居周辺をジョギングする。東御苑や北の丸公園は都心にあって実に自然が豊かだ。ある時、北の丸公園でタイサンボクの木の周りに出た。タイサンボクは10メートル以上になる大きい木である。そこに大きい白い花が、青空を背景に咲いていた。写真を撮った。そしてこれをXで紹介しようと思った。これが私がXで日々花の写真をアップする始まりである。夏や冬、花はなくなる。そういう時は松の木等をアップする。こうして写真の紹介は二年か🈪年続いた。
今年の初頭であったろうか。九州で講演した。驚いたことに社長さんは私のブログの愛読者であった。加えて管理職クラスの方も読んでいた。この管理職の方は作詞
 孫崎享のつぶやき
孫崎享のつぶやき
随想㉒ 妻・石田あき子の俳句が夫・石田波郷の俳句を呼ぶ
この記事の続きを読む
ポイントで購入して読む
※ご購入後のキャンセルはできません。 支払い時期と提供時期はこちら
- ログインしてください
購入に関するご注意
- ニコニコの動作環境を満たした端末でご視聴ください。
- ニコニコチャンネル利用規約に同意の上ご購入ください。
新着記事
- 尖閣諸島で軍事紛争が起こった時、米国は「日米安保条約が適用される」としているが、そのことは米軍が直ちに軍事行動を起こすことを意味しない。米国議会が承認した時に限られる。条約上の義務はない。これはNATO条約の「必要と認める行動(兵力の使用を含む。)を直ちに執る」と異なる。 20時間前
- ニューズ・ウイーク誌:大統領令の分類と解説。•連邦政府改革、移民と国境管理 、ジェンダーとDEI、関税と貿易、エネルギーと環境(•パリ協定からの離脱、沿岸海洋掘削禁止の撤回、アラスカの石油とガス掘削の解除、TikTok、•WHO脱退、マッキンリーに改名、アメリカ湾に改名、1500人恩赦恩赦 2日前
- ドイツ、2024年のGDPは、市場予想通り0.2%縮小。更にドイツ産業連盟(BDI)はドイツは深刻な経済危機と指摘、25年のGDP)が0.1%縮小するとの見通し。世界的な需要低迷と中国製品との競争、原因は国内要因であり、政府が取り組めなかった18年以来の構造的弱さの結果 3日前
- 「DeepSeekはAIのスプートニク現象」。「DeepSeek はチップを大量に消費する米国のプレーヤーが AI レースに勝つという考えを覆す(WSJ)。中国企業開発生成AIの台頭への警戒感からAI関連銘柄が大きく売られた。エヌビディア(一時時価総額世界一)の株価総額は約92兆円減少。株一日最大下落 4日前
- 『私とスパイの物語』書評、大西広氏 。大西 広:1956年生まれ、経済学者。専門は、マルクス経済学・近代経済学・統計学。京都大学名誉教授。慶應義塾大学名誉教授。 5日前
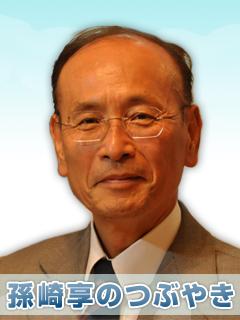

コメント
コメントを書く石田波郷あき子夫妻の句作から戦争のおぞましさを知らされます。
石田波郷の「泉への道後れゆく安けさよ」は大岡昇平の「野火」が放つ厭戦を感じます。
詩集というと、正直、本棚には全くない気がする。遠い昔に、国語とか現代文の授業で得た知識しかない。
詩というと、パッと思い浮かぶのは、寺山修司氏のあの有名な短歌「マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや」くらいである。これは、かつてのサヨク学生としては、ベタすぎるかもしれない。
そのくらい、私は詩とは縁遠いカンジである。
詩というか、歌詞という点で思い出すのは、労働歌或いは革命歌、「インターナショナル」だ。学生時代に学園祭等で先輩達が歌っていたり、何度となく聞く機会や「歌う」機会があり、なんとなく覚えている。といっても、全歌詞を暗記して、そらで歌えるわけではなく、さわりとメロディーを覚えている程度である。
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-11-22/2008112212_01faq_0.html
歌詞の一部に次のようなフレーズがある。
------------引用ここから------------
暴虐の鎖 断つ日 旗は血に燃えて
海を隔てつ我等 腕(かいな)結びゆく
いざ闘わん いざ 奮い立て いざ
あぁ インターナショナル 我等がもの
いざ闘わん いざ 奮い立て いざ
あぁ インターナショナル 我等がもの
------------引用ここから-----------
「海を隔てつ我等 腕(かいな)結びゆく」とか、「あぁ インターナショナル」という言葉使いは、所謂、プロレタリア国際主義、つまりは労働者には国境はいらない!万国の労働者団結して闘おう!みたいなスローガンを高らかに謳った趣旨だろう。
それで、また思い出したのだが、昔、母が「聞け万国の労働者~ とどろきわたるメーデーの~」と歌っていたことがあった。いっときは、労働歌も庶民にとっては身近なものだったのかもしれない。
いずれにせよ、サヨクは、国家の死滅とか、世界政府みたいな観念に親和的であると思われる。冒頭にあげた寺山修司氏の「身捨つるほどの祖国はありや」というフレーズも、国家を相対化しているという点で、サヨク的にはフィットする言い回しだろう。
しかし、今やソ連邦崩壊や中国の改革開放路線を経て、社会主義や共産主義は歴史の1頁に記されるのみになり、グローバル資本主義が世界を席巻するようになった。
そして、その流れに乗って、アメリカ帝国の代名詞たるグローバリズムが世界中に押し付けられようとして、様々な対立の火種になっている。グローバリズムに対する右翼ポピュリズムや保守思想が対抗勢力或いは思潮として力を増している。
かつてサヨクが掲げたプロレタリア国際主義は、グローバリズムと闘う対抗思潮には、明らかになりきれていない。なぜそうなのか?それはそれで、私にとっては興味深い問題だが、目下、私は反米派保守論客や右翼ポピュリズムに反グローバリズムの対抗勢力として、正直、シンパシーを感じている。先ずは、グローバリズム勢力が解体されることが重要だ。
その際、依拠するべき理念は、ロシアのプーチン氏やベロウソフ氏が唱導する主権国家ではないか、と考えている。
孫崎先生の随想から、随分逸れた無粋なハサシになってしまった。ご容赦下さい。
夏目漱石は草枕の冒頭に「智働けば角が立つ.情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ.兎角にこの世は住みにくい」といっているのが、まず頭に浮かんだ。
生きている中で物事を見るとき、はっとするときがある。桜が満開に咲いている姿を見て、「如是」「そのまま」に心奪われてしまう.咲き始めるときから散るときまで、その一瞬一瞬が、素晴らしい。写真は瞬時をとる優れモノといえる。
人間の世界と自然の世界の大きな差を実感することができる。人間世界では始終悩みの中に置かれているが、花などを見ると心救われる思いがする。孫崎さんの気持ちがよくわかる。
>>3
いやいや、インタナショナル、実に懐かしいです。
私の叔父さんはインパールを生き延びた一介の兵士でしたが、戦後は登山と労働運動で人生を終えました。インパールでは夜中になると泉と蛇と蛙を求めて徘徊し昼は沼に身を沈め敵の目を避けたと言ってました。
花に気を取られるのは登山の時だけだっただろうと叔父さんを偲んでます。