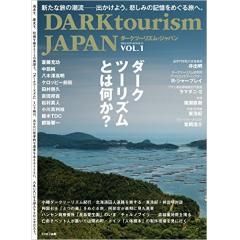明治から大正、昭和、平成へと移りゆく近代化の歴史の流れのなかで、
日本は敗戦、自然災害、公害、差別、交通災害などなど、あらゆる悲しみを体験してきた。
何気なくあなたの町にある古い建物、路傍の慰霊碑、枯れた裏路地─。
そこには、歴史に埋もれた悲しい記憶が宿っているかもしれない。
いままではガイドブックが教えるまま、表通りしか歩かなかった観光の道。
だけど、今日からは知らなかった別の道を歩いてみよう。
「ダークツーリズム」という旅は、あなたに哲学的な思索を与えるとともに、
人生に大いなる深みをもたらすだろう。
文=井出明
text by Akira Ide
写真=中筋純
ダークサイドを見る意義
闇があるから光がある─。
この言葉は、プロレタリア作家小林多喜二が、愛する田口タキに送った恋文の一節である。小樽で育ち、地元の大学を出て銀行に就職した多喜二は、親に売られ、小料理屋で私娼として生きる彼女と運命的な恋に落ちる。エリートである多喜二の求愛に彼女は気後れをするが、手紙では「つらい経験をしたからこそ、これからしあわせの道を探していこう」という流れの話が続く。
人生でダークサイドをまったく持たないという人間はまずいないであろうし、その辛く厳しい過去は人としての魅力を培う。地域にも、光の部分もあれば、かならず悲しみをたたえた記憶もある。悲しみの記憶をめぐる旅人たちは、その地に赴き、亡くなった人たちの思いや、場の記憶を受け継ぐ。そしてそれを持ち帰り、また誰かに伝えていく。
ダークツーリズムとは、戦争や災害をはじめとする人類の悲しみの記憶をめぐる旅である。
私は以前から、戦争や災害の跡を嚆矢として、人身売買や社会差別、そして強制労働などに関連する場を訪れてきた。なぜそのような場所に興味を感じたのかはよくわからなかったが、訪れるたびに「忘れないでおこう」という気持ちだけは強く持つようになっていった。非業の死を遂げた人々の無念の思いを受けとめ、大学という場を通して若い人たちに伝えていくだけでも、〝何らかの価値〟はあるのではないかと考えていた。大学という世界で働いて15年になるが、長いことこの〝何らかの価値〟の正体はわからずにいた。
ところが、ダークツーリズムの研究を進めるうちに、この価値の輪郭がおぼろげながら見えてきた。
防災の世界では、しばしば「人は二度死ぬ」というフレーズが語られる。この言葉の意味するところであるが、肉体的死が「一度目の死」であるのに対し、その人を知る人がいなくなってしまうことを「二度目の死」と呼んでいる。
この「二度目の死」は、多重的な意味を持つ。畑中章宏『災害と妖怪─柳田國男と歩く日本の天変地異』(亜紀書房)では、洪水の多い地域に「蛇崩」や「蛇谷」という地名が多いことを指摘している。
私も洪水を含め、日本各地の自然災害の跡を訪ねたが、そこにはひっそりとお地蔵さんが置れていることも多い。地域開発という流れのなかで、こうした地域の地名が変更され、お地蔵さんが除かれてしまったらどうなってしまうだろうか。
これは、この地で生き、この地で死を迎えた人の記憶を地域が失ってしまったことを意味している。つまり、「二度目の死」が起きてしまっているのである。そうなるとここに住む人々は、以前よりも災害を恐れなくなってしまうだろうし、何より備えを怠ることになりかねない。その結果、久方ぶりに豪雨があると、現住する人々は予想もしなかった新たな死を迎えることになる。
悲しみの記憶を失うことは、生死の問題以外にも様々な弊害を生む。今号でもハンセン病にまつわるダークツーリズムを扱っているが、我々はなんら科学的根拠もなく「ハンセン病」という病歴を持った人々を差別してきた。この問題についても、自分たち自身への問いかけが欠けていたと考えることもできる。
福島第一原発の事故の後、北関東のホテルで福島ナンバーの車を拒むなどのいわれなき差別が続発した。放射能に対する科学的無知が、被災者を拒絶するというあってはならない状況を生み出した。我々が、社会としてハンセン病に関する悲しみを承継できていれば、このような事態は避けられたのかもしれない。
悲しみの場をしばしば訪れてみると、それぞれの惨禍が相互に何らかの構造を持つこともわかってくる。沖縄のひめゆり学徒隊が投げかける問いは多岐にわたるが、そのひとつに自国の軍隊が自国民を必ずしも守るわけではないということに気づく。
これは沖縄以外にも見られ、済州島では1948(昭和23)年の共産主義者の摘発に際して権力側が自国民を虐殺している。また、中国では1989(昭和63)年の第二次天安門事件において、やはり軍が市民に対して銃口を向けた。
こうした軍と市民の悲劇的な記憶を我々一人ひとりは心に留めておくべきだろう。ある者は、軍と市民のあるべき関係を模索するだろうし、また別の者は軍の存在自体に懐疑的になるかもしれない。
勉強や学びなどという言葉を大上段に振りかざさなくとも、悲しみの場に赴き、そこで過ごすのであれば、心に何かが染みはじめる。悲劇の記憶を辿ることは辛く苦しいことかもしれないが、こうした営為を経験するうちに、自分の命が驚くほど多くの偶然と他者からの好意によって支えられていることがわかってくる。
多くのダークツーリストたちとの交流を踏まえて鑑みると、旅を通じてツーリスト自身のなかに内的なイノベーションが起こり、自分の人生を大切に思うようになってくる。そして、いまある自分の命を何らかの形で役立てたいという気持ちも沸き上がってくるのである。
旅人にこのような再生の機会を与える旅のあり方として、ダークツーリズムは非常に大きな可能性を有している。にもかかわらず、我々日本人は、これまであまりにも地域のダークサイドに対して無関心に生きてきたのではないだろうか。むしろ、あえて無視し続けてきたと言っていいかもしれない。
地域の悲しみの記憶は、実は隠すべき対象なのではなく、潜在的に新しい価値を有している。そしてダークサイドの持つ価値は、これまで述べてきたように単に教訓にとどまるわけではなく、生きかたの覚醒や社会構築といったレベルにまで多面的に波及する。こうした価値を重視した場合、悲しみの記憶をめぐる旅は、「ダーク」という言葉を、御為ごかしのように明るい単語に無理に言い換えないほうが本質を突くこともわかる。ダークツーリズムに関する研究や旅行商品の開発は、決して地域の傷を抉るものではなく、地域に新しい価値を見出すための契機となるだろう。
ダークツーリズムの歴史
ダークツーリズムは1990年代からイギリスで提唱されはじめた概念で、初の学術書は2000(平成12)年にJ・レノン教授とM・フォーレー教授によって著された。これまで観光資源として認識されていなかった戦争や災害、そして様々な悲劇の場に人々が訪れる現象を彼らは総称して「Dark tourism」と名づけた。
それ以前から、「War tourism」や「Holocaust tourism」という個別の呼び名はあったが、人類の悲劇をめぐる旅を同じカテゴリーにおいて分析をはじめた功績は大きい。
そして、このDark tourism概念は、今回寄稿をいただいたセントラルランカシャー大学のR・シャープレー教授(10ページ)とP・ストーン教授よってブラッシュアップされていった。
ヨーロッパでは、歴史的記録はポジティブな情報だけでなく、地域にとってはあまり好ましくないネガティブな情報も記録され、一部は展示に供される。つまり、自分にとって都合のいい情報だけを扱うわけではなく、思い出すことも辛く悲しい記憶が、当然のように残されているのである。
本誌の主題である、いわゆる〝負の遺産〟は極めて日本語的な概念であり、英訳しにくいと言われている。英語で遺産を表す「legacy」や伝説を表す「legend」は、決してポジティブな話だけを扱うわけではない。
人類の活動の結果残された記憶は、必然的に良い面もあれば悪い面も併せ持ち、そうした両タイプの記憶を大切にしようとする考え方がヨーロッパには根付いていた。したがって、ダークツーリズムという新しい言葉が現れたときも、人々は違和感なく受け入れることができたのである。
また論文を精査する限り、英語圏であるアメリカでも同様の解釈がなされている。さらに、アジア・アフリカ圏はエリート層が旧宗主国を中心に留学するため、ヨーロッパの考え方が早い段階で現地に入っている。本誌に寄稿いただいたS・ラマダニ氏(68ページ)はオーストラリアのビクトリア大学で観光の修士号を取得されたが、彼はヨーロッパ起源のダークツーリズムの方法論を留学先で学んでおり、その知識を用いてインド洋津波に飲まれたアチェの街を見事に復興させた。
日本型ダークツーリズムの可能性
我々は本誌を通して、地域のダークサイドを記録し、その価値を受け継ぐことの重要性を伝えていきたいと考えているが、実は日本こそ、ヨーロッパと並ぶダークツーリズムの発信拠点になるべきであると確信している。
まず、自然災害が多発することが理由のひとつに挙げられる。ヨーロッパのダークツーリズムの教科書でも、自然災害の跡が観光対象になるとは書かれているが、実は具体的な記述がほとんどない。
これは、ヨーロッパに自然災害があまりないからであり、約250年前のリスボンの地震や、論文では英語圏から発信されているということで、2011年のニュージーランド地震を取り上げているものが散見される程度である。
我が国の場合は、死者を伴う地震災害はもちろん、火山災害でも過去に多くの犠牲者を出している。慰霊や学習などの目的でこうした地域に入りたい外国人はたくさんいるものの、英語での発信がないため、アクセスすることが非常に難しい。
欧米では日本の情報を知りたがっているにもかかわらず、これまでアプローチを諦めてきた節がある。今後は、日本から自然災害に関連したダークツーリズムの情報を積極的に発信することで、すでに欧米で発達したダークツーリズムの方法論と高次のコラボレーションが期待される。 また、ヨーロッパで発達した戦争のダークツーリズムに関しても、日本からは独自の発信が行われるべきであろう。ヨーロッパにおける第二次世界大戦に関する反省は、ヒトラーを悪のシンボルに見立て、二度とファシズムの跳梁跋扈を許さないというというテーゼを確立することを中心に置いていた。したがって、ダークツーリズムの研究もナチズムを復活させないための方法論として分析されることが多かったと言えよう。
一方、日本の第二次世界大戦は、中国に対する侵略の側面もあれば、南方に対しては解放戦争としての性質も有していた。とくに旧南洋庁の島々では、日本の統治を肯定的に評価する声も多々ある。
換言すれば、日本の戦争は多面性を持ち、単純な二元論では割り切ることはできない。日本が公に自己の戦争を肯定することは許されないが、日本の第二次世界大戦に関連するダークツーリズム研究を発信することで、ヨーロッパとは異なる戦争のコンテクストへの理解が広がることも期待される。
さらに、原爆の被害や隠れキリシタンの苦難については、日本に固有のダークツーリズムのコンテンツであり、海外のダークツーリストに対しては、大きな訴求力を持つ。こうした日本に独特の悲劇に関する研究は、日本が国として受け入れるツーリストの幅を広げることにも寄与することだろう。
このように、我が国は今後のダークツーリズムの研究及び発展に独自の立場から貢献することが可能なため、より積極的な立場からこの新しいフロンティア領域を開拓していくことが求められる。
残された課題
雑誌の誌名でもある「Dark tourism」(ダークツーリズム)という言葉は、生まれてまだ20年程度だが、すでにさまざまな問題も現れはじめている。
この新しい旅の形は世界中で広まりつつあるが、ダークツーリズムの聖地とも言われるアウシュビッツでは、ここ10年で入場者数が2倍以上に増えてしまい、博物館には長蛇の列ができている。
実は、アウシュビッツ訪問の拠点となるクラクフからは、ツアーバスが大量に運行しており、悲劇を商売にしているのではないかという批判もある。また、アメリカ同時多発テロの現場であるニューヨークのグラウンド・ゼロでは、大量の観光客の立ち入りが厳粛な祈りを妨げており、ダークツーリズムは物見遊山と区別できないという意見も出ている。
一方、日本において顕著に見られる傾向だが、悲劇の場への来訪を不謹慎とみなす風潮は、ダークツーリズムの普及のための足かせとなっている。
ダークツーリズムの意義を説くことは重要であり、これは私自身の責務として果たさなければならないが、現実の世界では次から次へと様々な問題が起こっている。観光学は理念だけでは成立しない分野であり、現場の問題を解決できなければ絵に描いた餅になってしまう。
本誌は、次号以後もダークツーリズムのあるべき姿を模索し続けていくことになるが、これには確定的な答えはでないだろう。ただ、より良い形に近づける取材と編集の努力は続けなければならない。悲しみの記憶の断絶が、さらに大きな悲しみを招来する可能性がある以上、その記憶を確かなものにすることは非常に重要な意義を持つ。そして、その記憶の承継こそがダークツーリズムが担うべき本質的役割なのである。
本誌を手にとったあなたは、すでにその役割を担う気持ちを持たれたかもしれない。ぜひ、ともに記憶をつなぐ旅路に出よう。
井出明
いで・あきら◉1968年、長野県生まれ。