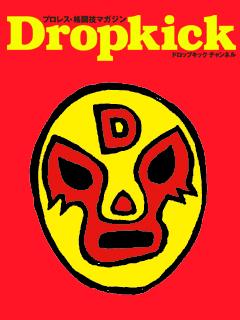■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
いま入会すれば小原道由、田中ケロの新日本プロレストークが読める!
1月更新記事ラインナップはコチラ!
http://ch.nicovideo.jp/dropkick/blomaga/201501
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
――安西さんが『週刊プロレス』に入るきっかけはどういうものだったんですか?
安西 もともとボクは大学浪人時代から『週刊ファイト』でちょろちょろと手伝ってたんですよ。2年間大学浪人してんだけど、浪人1年目にタイガー・ジェット・シンのファンクラブをやってた女の方と知り合う機会があって。ジェット・シンと話ができる数少ない方。
――ジェット・シンのコネクションを持つ女性!(笑)。
安西 その人を通じて当時『週刊ファイト』で働いていた(ターザン)山本さんを紹介してもらったんです。そこから『週刊ファイト』でお手伝いをするようになったんですよ。
――つまり『ファイト』東京部隊ということですよね?
安西 そうそう。『ファイト』は大阪が本隊だったから、山本さんの指令を受けて選手や大会を取材をしたりね。
――謝礼はどれくらいもらえたんですか?
安西 1回の取材で5000円、10000円とかかなあ。それも振り込みというより、山本さんに直接もらったり、たまにI編集長(井上義啓)が上京したときに「よくやってもらってありがとう」とポケットから1万円札をもらったり(笑)。で、ボクが大学に通ってるときに山本さんが『ファイト』からベースボール・マガジン社に移籍して。当時のベースボールは縁故採用が多かったんだけどね。かなりの社員が縁故採用。
――それなのに山本さんも安西さんも入社できたんですか。
安西 いや、ボクはまず大学を卒業して広告代理店に就職した。そこの会社には2年半いたのかな。その頃『月刊プロレス』が『週刊プロレス』に移行してて。編集部員の宍倉(清則)さんから「熱戦譜を書いてみない?」と誘われたんです。
――熱戦譜というのは試合結果欄のことですね。いまは団体増加とともに試合数が多くなっちゃってコーナーそのものがなくなっちゃいましたけど。
安西 広告代理店は13時から14時まで昼休みだったんだけど、近くの喫茶店で食事したあとに熱戦譜の原稿を書いてたんだよ。新日本や全日本から送られてきた試合結果のFAXを鉛筆で原稿に書き直して。終わらないときは当時恵比寿にあったロッシー小川さんの家に泊まって作業したり。『ファイト』のときに女子プロの取材をしていたからロッシー小川さんとは親交があったんです。
――広告代理店には内緒のアルバイトだったんですね。
安西 そのうち『デラックスプロレス』がクラッシュギャルズブームで女子プロ専門誌化してきて、編集長の宍倉さんからけっこう仕事をもらうようになって。当時は神奈川の実家から通勤してたんだけど。会社まで1時間40分かけて通って、仕事が終わったらベースボールまで行って終電まで記事を書いてね。
――ハードですねぇ。
安西 あまりに大変だから目黒にワンルームマンションを借りたんだけど。隣の部屋の学生の男が日曜日の昼になると、彼女を連れ込んで窓を開けっぱなしにして、『笑っていいとも!』増刊号を見ながらSEXしてるんだよっ!
――ハハハハハハハハハ!
安西 その女の子が子犬のように鳴き続けるんだよね。「クウンクウン」って。
――安西さんが鳴くと、子犬の鳴き声には聞こえませんね(笑)。
安西 そこの部屋に借りるときに前の住人に会う機会があったんで住み心地を聞いたんですよ。そうしたらね、「いい部屋だけど、隣の部屋のカップルの声には参るよ。かわいい子だけど、このかわいい子がこんな声を出すのかとビックリするよ」と。 それでもいいやと借りたんだけど。ボクが「猪木勝ち、ジェット・シン負け」という熱戦譜の記録を書いてるときに隣りからそういう声が聞こえてくるとさあ、「……俺はいま何をやってるんだろう?」って虚しくなっちゃって。
――どんな思い出なんですか(笑)。
安西 そんな馬鹿な話はともかく、ベースボールから月10万の報酬が振り込まれたら最低限の生活ができるから、そうなったら広告代理店をやめようと考えたんだよね。それであるときにそのラインを超えたんで会社をやめた。
――よくやめましたねぇ。
安西 俺は大学受験で2浪してるから卒業は24歳。26歳のときに会社をやめたんです。そこから2年半はフリーでやったのかな。そうしたら濱部(良典)さんが『週刊プロレス』を出て『ラクビーマガジン』の編集長として異動していく話になって。濱部さんが欠けた戦力として、普通はなりたくてもなれない社員になれたんですよね。88年4月、29歳のときだね。
――『週プロ』時代の山本さんってどういう方でした?
安西 難しいなあ。
――言葉に詰まりますか(笑)。
安西 おかしな人、エキセントリックな人だって思ってる人もいるんだろうけど、ボクから見たら普通の人なんだけどね。たとえばトークライブで人前で話すときは大声を出したり、パフォーマンスをするわけだけど。普段の山本さんは普通の人としかいいようがないよね。ただ、『週プロ』の部数もどんどん上がっていって、山本さんが偉くなって近寄りがたい存在になっていったよね。山本さんは週末になると編集部を出て1階の応接室にこもっていろんな人に電話をして情報を仕入れて、発想を豊かにして表紙や巻頭記事を作るわけじゃない。やっぱり作る作品がどれも素晴らしかったんですよ。山本さんの担当する記事はいつも圧倒的。とても太刀打ちできない。読んで挫折するというか、お手上げ状態。
――あのオッサンは抜きん出てたんですね。
安西 だからとても尊敬してましたよ。会場で試合取材をするときも「山本さんが見たらどう書くんだろう?」と考えちゃうんですよね。いま試合会場に行くとさ、記者はみんなパソコンを広げて速報記事を書いてるわけでしょ。あったことを書いて、選手がコメントしたことを書いて、自分がどう見たかは問われてないわけじゃないですか。ボクたちが仕事をしていた時代とは違うんだなって思うよね。
――批評性はなくなってますね。活字プロレスの源流は『週刊ファイト』のI編集長だと思うんですけど。
安西 当時は『東スポ』や『ゴング』が入口だったけど、『ファイト』を読んで眼から鱗が落ちるというか『ファイト』だけが真実を書いてくれると錯覚しちゃうんだよね。もの凄く細かい心理描写とかさ、レスラーの日常の生き様が語られていた。「こんな書き方があるんだ」と雷が落ちた。でも、いま思えばほとんどがI編集長の妄想の世界で(笑)。
――「プロレスという名の公園」に居つくプロ格者の青鬼・赤鬼に、自分のプロレス観を代弁させてたりしてましたよね。
☆このインタビューの続きと、小原道由ロングインタビュー、田中ケロなど7本のインタビューが読める「お得な詰め合わせセット」はコチラ http://ch.nicovideo.jp/dropkick/blomaga/ar719107