4
一瞬、九十九三蔵は、出遅れていた。
最初に、宇名月典善が疾(はし)り、それに、菊地良二が続いた。
身を潜めていた所から、ライフルを持った男たちが、宇名月典善の後を追った。
「九十九くん、きみは、ここにいなさい」
久鬼玄造が、九十九の動きを制するように、そう言ったのだ。
玄造は、八津島長安(やつしまちょうあん)の背を押し、
「ゆくぞ」
動いた。
すぐそこに停められていた、空の保冷車の助手席に、玄造と、八津島長安は乗り込んだ。
巫炎が乗っていない方の、空の保冷車だ。
運転席には、はじめから山野丈二(やまのじょうじ)が座っている。
「県道の方だ」
玄造は言った。
久鬼麗一が落下した方角――それは、県道の方角であった。
県道から、この牧場まで、森の中を私道が通っている。
その私道か、県道のどこかへ、玄造は保冷車を停めて、待つつもりなのだ。
かっ、
と、保冷車のヘッドライトが点燈した。
走ってゆく、宇名月典善の背へ、ヘッドライトが当る。
二度、三度、ヘッドライトがパッシングする。
これは、私道か県道で待つという合図であった。
そのパッシングの意味を理解した、というように、森へ駆け込む寸前、典善が左手を高く持ちあげて、一度だけ振った。
牧場の中央に近い岩から二〇メートルほど離れた場所に停まっていたジムニーも、すでに動き出していた。
森の際までジムニーでゆき、そこに車を停めて、久鬼麗一を追おうとしているのである。
何かあったら、現場のできるだけ近い場所へ、保冷車を移動させる――それが、あらかじめ決められていたことだ。
その役目は、運転席の山野丈二が負っている。
しかし、玄造が、八津島長安と一緒に乗り込んでくることまでは、その打ち合わせの中には入っていなかった。
まさか、久鬼麗一が空から来るとは考えていなかったのだが、久鬼麗一が、もしも逃げれば、その逃げた先の、車で移動できるぎりぎりのところまで、保冷車を動かすということになっていたのである。
捕えたら、できるだけ短時間で、久鬼麗一を保冷車の中に入れねばならない。もしも、県道などが、久鬼麗一を捕える現場になったら、いつ、誰に見られるかわからない。
夜、車の通行量は少ないとはいっても、まるで通らないわけではないからだ。
牧場内で、ことがうまくいかなかった場合、どうするかの手筈は、何パターンか、決めてあった。
運転席には、無線機器が備えられている。
銃を持っている者は、それぞれ無線機を持っている。
それで連絡をとりあいながら、保冷車を移動することになる。
そこに残ったのは、吐月(とげつ)と九十九、そして巫炎の乗った保冷車が一台。そして、保冷車の運転手である池畑辰男(いけはたたつお)であった。
その保冷車の中で、激しく何かが叩かれる音が響いていた。
金属が、軋(きし)んで悲鳴をあげる音。
巫炎が、外で起こった異変に気づき、暴れているのである。
「どうするかね、九十九くん……」
吐月が言った。
保冷車の中にいる巫炎のことかと、九十九は思った。
「我々も、行くかね」
吐月は、そう言ったのだ。
行く――というのは、森の中ということだ。
森の中には、あの、久鬼麗一がいる。
久鬼は、獣となって、牛を食べていた。
それを九十九は見ている。
その久鬼がいる森――虎のいる森の中へ入ってゆくようなものだ。
銃もない。
武器もない。
しかし、手負いだ。
象四頭が眠ってしまう量の麻酔弾を打ち込まれている。
さらに言えば、三十三口径のライフルの弾が、身体のどこかに命中している。
それが、どこまで、あの獣の能力を奪っているのかは見当もつかないが、弱っているのは確実であろう。
実際、久鬼は、空を飛べずに、森の中へ落下していったのだ。
空を飛んでいるあいだに、麻酔が効いてきたということなのだろう。
それが、どこまでこちらの安全を保証してくれるのかはわからない。
手負いとなったら、かえって危険になる野性の猛獣は、いくらでもいる。
それとは、逆の心配もあった。
銃で撃たれ、あの高さから落下していった、久鬼の生命だ。
久鬼は無事か。
もしも、久鬼が、あれで致命的な傷を負っているのなら、一刻も早く居場所を見つけて、手当てをせねばならない。
「この二〇年、わたしも、カルサナク寺で見たもののことは、ずっと気になっていた……」
吐月は、久鬼玄造と、チベットのカルサナク寺の地下で、「外法曼陀羅図」を見ている。
「何度も、夢に見たよ……」
吐月は、月を見あげてそうつぶやき、その眼を森に向けた。
「今、あの森の中に、それがいる……」
九十九を見た。
「わたしは行くよ」
そう言って、吐月は歩き出していた。
「おれも行きます」
九十九は、吐月の背へ向かって言った。
並んで歩き出した。
すぐに、森の中へ入った。
森の、濃い匂いが、ふたりを包んだ。
「森はね、九十九くん、わたしの庭のようなものだ……」
歩きながら、吐月がつぶやく。
「森の中で、食料を見つけ、獣を捜したり、獣から逃(のが)れたり……そんなことばかりをして、わたしは、暮らしていたのだよ」
「はい」
九十九はうなずいた。
紀伊半島の山の中で、吐月は、ずっと、自らが口にしたような生活を続けてきたのである。
「急がぬことだ。ゆっくりでいい」
吐月は言った。
初出 「一冊の本 2013年7月号」朝日新聞出版発行
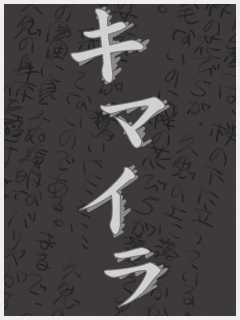
コメント
コメントを書く