紅葉した楓や、ダケカンバの葉が、地に重なっている。
九十九(つくも)の、重い体重がかかるたびに、そこから落葉の匂いがより濃くなってゆくようであった。
枯れ葉の匂いではない。
落葉ではあるが、枯れて枝から離れたものではない。色こそ緑ではないが、充分に湿り気を含んだ、みずみずしい葉の匂いである。
枝と葉の間に、コルク質が生じて、葉が枝から落ちただけのことだ。ただ、その香りが、六月、七月の青葉の匂いではないというだけのことだ。
灯りは消している。
森に入って、すぐ、用意していたハンドライトを点燈したのだが、
「消そう、九十九くん」
吐月(とげつ)がそう言ったのだ。
「月明りがある」
満月でこそないが、それに近い月だ。
「灯りを手にしていると、その灯りが照らすものだけを見てしまうからね。かえって、ものが見えなくなるものだ」
吐月の言葉には、説得力があった。
それは、自身が、こういった文明の利器を使わず、山中に起伏(おきふし)していたからわかることなのだろう。
「はい」
うなずいて、九十九は灯りを消した。
それが、しばらく前のことだ。
消した直後は、一瞬、周囲が真っ暗になったように思えたが、すぐに眼が慣れた。
もともと、月明りで夜の道を歩く分には問題はない。あたりの情景が、それなりに見えるからだ。
江戸の頃、人は、満月の晩は提灯無しで歩いたのだ。
ただ、森の中は、頭上に被さった葉の繁る梢によって月明りが隠され、足元がかなり見えにくくなる。しかし、今、落葉樹の森は、葉の半分近くが散って、ほどよく月の光が注いでくるのである。
確かに、吐月の言う通りであった。
ライトを消したおかげで、森から届いてくる情報量が、はっきり増えたのがわかった。
暗く、青い、深海の底を歩くような気がした。
森に、包まれたようだ。
充分に歩くことができる。
必要になったら、ライトは点ければよい。
こちらがライトを点けていないことにより、むこうからはこちらが見えなくなる。
ライトを点けていると、久鬼(くき)と出会った時、最初に向こうに気づかれてしまう。
気づいた時、久鬼はどう反応するのか。
久鬼が、見つけた途端に自分たちを襲ってくるのではないかと思う半面、いや、もしかしたら、久鬼が、ここにいるのが友人である自分――九十九三蔵(さんぞう)であると気づいてくれるのではないかという淡い期待もあった。
しかし、あの、獣となった久鬼が、自分に気づいてくれるであろうか。
その不安がある。
考えてみれば、自分は無謀なことをしているのではないか。
久鬼玄造(げんぞう)の言う通り、牧場のあの場所で待っていた方がよかったかもしれない。
仮に、久鬼と出会えたとして、いったい、自分はどうすればよいのか。
何か、することがあるであろうか。
なにも思いつかなかった。
吐月はどうなのか。
吐月は、あの久鬼と、これから出会うかもしれないことについて、どう考えているのであろうか。
九十九の心を、覗いたように、
「九十九くん」
吐月が声をかけてきた。
「きみと初めて会った時にも言ったことだが、わたしは、若い頃、仏陀に――つまり、覚者になろうとしていたのだよ……」
低い声だった。
「本気でなろうと思っていた。いや、なれると思っていた。ゴータマ・シッダールタが、過去においてそうなったのなら、自分もまた必ずなれるのだと……」
九十九に、というよりは、吐月は自分に言い聞かせているようであった。
「そして、チベットへ渡り、あの陳岳陵(ちんがくりょう)とカルサナク寺で出会い、その地下で、『外法曼陀羅図』を見たのだ……」
歩きながら、吐月は、微かに笑みを浮かべたようであった。
その笑みの気配があった。
優しい、哀しみに満ちた笑み――
「若かったのだなあ……」
吐月はつぶやいた。
「若い頃は、何でもできると思ってしまう。仏陀にでさえなれるのだと思ってしまう。若さとは、そういうものだ……」
昔の自分をなつかしむような響きがあった。
■電子書籍を配信中
・ニコニコ静画(書籍)/「キマイラ」
・Amazon
・Kobo
・iTunes Store
■キマイラ1~9巻(ソノラマノベルス版)も好評発売中
http://www.amazon.co.jp/dp/4022738308/
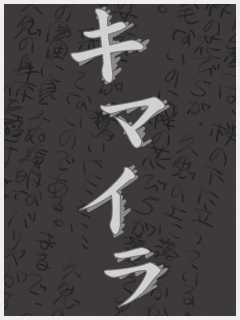

コメント
コメントを書く