一章 獣王の贄(にえ)
2
巫炎(ふえん)は、闇の中で腕を組み、胡坐(あぐら)をかいている。
保冷車の中だ。
いや、正確に言うのなら、保冷車の中に入れられた檻の中だ。
ジーンズをはき、Tシャツを着て、その上に綿のシャツをひっかけている。
闇の中だが、眼を開いている。
開いたその眸が、青く光っている。
しかし――
保冷車とはよく考えたものだ。
普通の車であれば、それがどのようなタイプのものであれ、逃げることはたやすい。窓のガラスを割って、そこから外へ出ればいいだけのことだ。
たとえ、それが強化ガラスであろうが、フィルムを貼ったものであろうが、いったんキマイラ化してしまえば、割ることはできる。
ドアだって、蹴破ることくらいはできるであろう。
それは、久鬼玄造(くきげんぞう)も承知している。
だからと言って、檻の中に巫炎を入れて、その檻をトラックの荷台に載せてゆくのでは目立ちすぎる。ビニールシートで、檻を囲ったとしても、人目を引く。
保冷車が選択されたのは、頑丈で、なお、外から内側を見ることができないからだ。窓もない。
その闇の中で、巫炎は、静かに呼吸しながら、視線を尖らせているのである。
と――
巫炎は闇の中で顔をあげた。
何か、聴こえたような気がしたからだ。
それは、上から聴こえた。
(あひいる……)
空の、ずっと高い所。
そして、また――
(あひいる……)
確かに聴こえた。
人の可聴範囲を遥かに越えた、高い声。
久鬼麗一(れいいち)だ。
「麗!」
巫炎は、顔をあげて、立ちあがっていた。
上から聴こえた――
それが何を意味するのか、巫炎にはわかっている。
人の声が、上から聴こえるというのは、普通、あり得ない。
近くに家があって、屋根の上からその声が届いてくるのか。
否。
屋根であれば、周囲の者たちが騒ぎはじめているはずだ。その騒ぎが伝わってこない。たとえ、それが、樹の上であってもだ。
崖の上から、聴こえてくるのか。
否。
ここが、信州の、牧場であることは、巫炎は知らされている。近くに崖のあることは、聴いていない。
しかも、その声は、ほぼ真上から近づいてきているのだ。
崖の上からならば、こういう聴こえ方はしない。
パラシュートか、パラセールか、そういうもので、上空から声の主が降りてきつつあるというなら、こういう聴こえ方はあるかもしれない。
しかし、それがただの人間なら、このような高い声は発せられない。
唯一、考えられるのは、上空から、久鬼麗一が、その声を発しながら近づいてきているということだ。
その声が、久鬼麗一がキマイラ化していることの証(あかし)であった。
それが、上空から近づいてくるというのも、キマイラ化の証である。おそらく、久鬼麗一は、変形(へんぎょう)し、獣の姿と化し、背から翼まで生やしているのであろう。だから、空からその声が近づいてきているのである。
そして、その声の意味を、巫炎は理解していた。
あのような声を、キマイラ化した者が、どのような時に発するのかを、巫炎は知っている。
獲物を見つけた時だ。
腹をすかせ、飢え、その食を欲している時、その対象となる獲物を見つけた時の声だ。
そして、その声は、悦(よろこ)びに満ちていた。
すぐに、思う存分、その獲物の肉に顔を突っ込み、血ごとその肉を噛み切り、舌で転がし、潰し、呑み込むことができるのだという思いと確信に溢れている声。
来るな――
そう叫ぶべきか。
いや、そう叫んで、久鬼麗一がここから去れば、どこか別の場所で、久鬼麗一は、また血肉を求めることになるであろう。
キマイラ化して、我を忘れている状態の時、人の血肉と動物の血肉を、区別できない。
それを、巫炎はよく知っている。
台湾で、それは、自分がやったことだからだ。
自分は、人の肉を生で食べている。
それも、生きながら。
そして、その時、自分は歓喜の声をあげていたことも覚えている。
それを、久鬼麗一にさせてはならない。
自分の内なる獣、キマイラをコントロールするためには、強い精神力と、訓練が必要である。
それを、自分は、できたはずであった。
台湾では、それができなかった。
それほど絶望していたのだ。
初出 「一冊の本 2013年7月号」朝日新聞出版発行
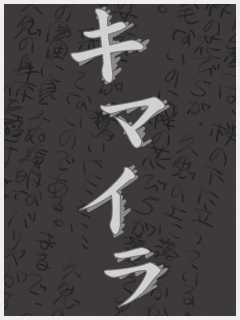
コメント
コメントを書く