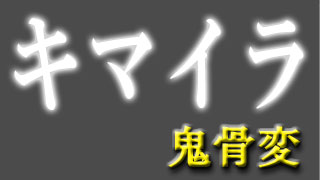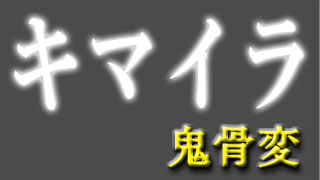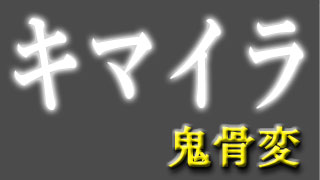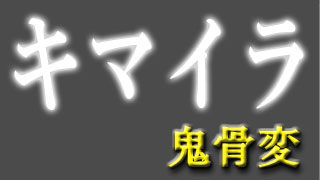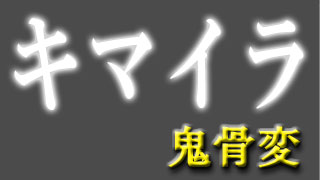-
キマイラ鬼骨変 一章 獣王の贄(にえ) 10
2013-11-13 00:0010 九十九(つくも)の見ている前で、久鬼が静かになっていった。 騒いでいた顎(あぎと)たちの声がおさまってゆき、猫が喉を鳴らすような、低い唸り声のような、甘えるような、そういう声を発するようになった。 獣毛が抜け落ちてゆく。 久鬼の全身から生えていたものが、ゆっくりと、身体の中に消えてゆく。 消えぬものも、あったが、それはまた別のものになってゆく。 それらが、背から生えた、一本ずつの青黒い腕となってゆく。 幾つかあった顔が、久鬼の顔の周囲に集まってゆく。 どこかで、見たことがある―― 九十九はそう思った。 顔が、幾つかある仏像。 腕が何本もある尊神。 獣のような、牙を生やした神。 不動明王? 大威徳明王、ヤマーンタカ? 久鬼は、そのような姿となった。 巫炎(ふえん)の翼が、ばさりと振られた。 久鬼の翼が、ばさりと動く。 ふたりの身体が、ふわりと草の上に浮きあがった。 ゆっくりと -
キマイラ鬼骨変 一章 獣王の贄(にえ) 9 (2)
2013-11-06 00:00啖(くら)えだと? 啖えだと? いいだろう、啖ってやろう。 おれは、噛みついた。 そいつの身体に牙をたててやった。 ぞぶり、 肉を噛みちぎってやった。 生あたたかい血の味が、口の中に広がる。 なつかしい味だ。 美味(うま)い。 呑み込む。 食道を通って、胃の中へ。 どこにある胃か。 すでに、おれの身体から生えたいくつもの顎が、そいつの胸や、尻や、腕の肉を喰っている。 それを呑み込み、消化してゆく。 体内に、その血が溶けてゆくのがわかる。 もう一度―― 左肩の肉を、齧(かじ)りとる。 なんという、不思議な味か。 おれの血が、そいつの血と混ざりあっている。 溶けあっている。 三度目―― それは、できなかった。 おれは、動きを止めていた。 なんということだろう、おれは、思い出している。 そいつ――こいつのことを。 こいつのことを、おれは知っている。 この味を、おれは知っている。 こいつの血と自 -
キマイラ鬼骨変 一章 獣王の贄(にえ) 9 (1)
2013-10-30 00:009 そいつは、見たことのある顔をしていた。 森の中から、ふたりで、ずっとおれに話しかけてきた、あの声を発していたやつらのかたわれだ。 説教師(マニパ)ツオギェル―― そう名のっていたっけ。 そいつが、話しかけてくるのである。 もう、やめろ――と。 もう、いいではないかと。 なんだか、うるさい。 なんだか、わずらわしい。 大きなお世話ではないか。 こんなに、自分は今、満ち足りていて、しかも気持ちがいいのに。 どうして、これをやめねばならないのか。 そうだ。 こんなに、幸せなのに…… だが、妙に不安になる。 おまえは、どうして、そんな哀しそうな顔をするのだ。 さっきの、二本足の大きな漢(おとこ)も、そうだ。 哀しそうな顔で、おれを見ていた。 そんな眼で、見られたくない。 そんなに哀しい眼で、おれを見るんじゃない。 哀れに思われたり、可哀そうに思われたりするなら、怖がられた方が、まだマ -
キマイラ鬼骨変 一章 獣王の贄(にえ) 8 (6)
2013-10-23 00:00巫炎にとっては、あるいは、九十九や吐月は、敵側の人間と見られてもしかたのない関係にあった。 久鬼玄造(くきげんぞう)が、巫炎を保冷車の中に閉じ込め、九十九も吐月も、その久鬼玄造と一緒にこの現場に駆けつけているのである。 それにしても、どうして、巫炎はあの保冷車の中から抜け出すことができたのか。 それが、九十九には不思議であった。 おそらく、今、キマイラ化した久鬼の前に立っている僧衣の男が、巫炎を助けたのではないかと、九十九は思う。 しかし、それを訊ねている時間は、むろん、ない。 ツオギェルは、久鬼の前に立って、しきりと身振り手振りで、何やら話しかけているようであった。 ツオギェルの口が開く。 声は聴こえない。 久鬼の口が開く。 声は聴こえない。 久鬼は、もどかしそうに、身をよじる。 そして、久鬼は、時おり、九十九にも聴こえる高い声で叫ぶ。 それに対して、ツオギェルは、たびたび、自分の両手 -
キマイラ鬼骨変 一章 獣王の贄(にえ) 8 (5)
2013-10-16 00:00しかし、久鬼は、そこに立ったが、すぐには動かなかった。 久鬼の本体――人間の久鬼の顔が、半分、もとにもどっていた。 吊りあがっていた眼尻の角度がわずかに緩やかになっている。 久鬼は、不思議そうな顔をしていた。 今、自分に何が起こったのか、それがわからないという顔だ。 九十九も、久鬼を見つめながら、立ちあがった。 気という力は、もとより物理力ではない。 物理力ではないが、今のような放ち方をすれば、体力は消耗する。 ゆるやかに、全身の細胞に、力がもどってくる。「大丈夫です……」 九十九は、吐月の横に並んだ。 雲斎に救われた。 その思いがある。 石との対話がなかったら、自分は死んでいたところだ。 しかし、そのいったんは永らえた生命(いのち)も、すぐにまたキマイラ化した久鬼の前にさらされることになる。 そう思った時、久鬼の表情に、変化が起こった。 久鬼の眸(め)が、遠くを見つめたのだ。 天上に輝 -
キマイラ鬼骨変 一章 獣王の贄(にえ) 8 (4)
2013-10-09 00:00「九十九くん……」 吐月(とげつ)が、何ごとかを察したように、一歩、退がる。 吐月に声をかけてはいられない。 今やろうとしていることに、全神経、全細胞、それこそ髪の毛一本ずつまで、使って集中しなければならない。 肉体が、別のものに化してゆくようだ。 大地になる。 地球になる。 重力になる。“石”をやっていてよかった。 雲斎(うんさい)に言われて、円空山で、石を割ろうとした。 巨大な石だ。 とても割れそうになかった。 かわりに、九十九は、石を見つめた。 石を見つめながら、大地と対話し、己れ自身と対話をした。 あの体験が、今、自分がやっているこのことを可能にしているのだ。 全身を、熱い、高温の気の塊(かたま)りと化すこと。 しかも、わずかな時間――ふた呼吸で。 寸指波(すんしは)を全身で打つ――その感覚だ。 両足を開く。 腰を落とす。 両手を拳に握って、腕を両脇にたたむ。 これが、どの程度、今 -
キマイラ鬼骨変 一章 獣王の贄(にえ) 8 (3)
2013-10-02 00:00それに、久鬼(くき)が反応した。 いや、反応したのは、久鬼ではなく、久鬼の内部にいる獣であったのかもしれない。 跳んだ。 久鬼の身体が、宙へ跳んだのだ。 幾つもある脚の筋力が使用されたのか、異形の翼が利用されたのか、その両方であったのか。 翼はただ一度、 ばさり、 と、打ち振られた。 そして、久鬼は、走り去ろうとする鹿の背に、後ろから飛び乗っていたのである。 幾つもの足の鉤爪が、鹿の背の肉を、背骨ごと掴んでいた。 その時には、もう、幾つもの頭部が、顎が、首や、頭や、背の肉に牙を立てていたのである。 ぴいいいいいっ! 鹿が、悲鳴をあげた。 だが、すぐにその声は止んでいた。 喉を噛まれ、気管が締められ、塞がって、声を発することができなくなっていたのである。 ぞぶり、 ごつん、 ぬちゃ、 ごぶり、 獣の牙が、肉を噛み、骨を噛み折って、血を啜りあげるおぞましい音が響く。 びりっ、 と、音をたてて -
キマイラ鬼骨変 一章 獣王の贄(にえ) 8 (2)
2013-09-25 00:00「おれを、救う?」 久鬼が、つぶやく。 久鬼の眸に、さらに光が点る。「ああ……」 久鬼は、溜め息のような呼気を吐いた。 一度、二度、眸を閉じたり開いたりした。「夢を、見ていたようだ……」 視線を、周囲にめぐらせた。「長い、夢だ……」 腕を持ちあげる。 その腕を眺める。 左右の手を。 そして、指を。 指先を。 その眸が、自分の身体に移ってゆく。「夢じゃ、なかったのか……」 溜め息とともにつぶやく。「それとも、まだ、夢を見ているのか……」 月光の中に、久鬼は、白い腕を差し伸ばし、そして、「ずいぶん、楽しい夢だったような気がする……」 謡(うた)うように言った。「悪夢であったような気もするが、それはそれで、悦びに満ちたようなものであったような気もするのですよ、九十九……」 久鬼の視線が、九十九にもどった。「何故、救うのです?」 久鬼が言った。「何故、このぼくを、救わねばならないのです……」 ゆっ -
キマイラ鬼骨変 一章 獣王の贄(にえ) 8 (1)
2013-09-18 00:008
九十九は、その獣の正面に立っていた。 無数の首が持ちあがり、無数の眼が九十九を見ていた。 しかし、同時に、同じくらいの無数の首と口が、 げええ、 がああ、 血肉の塊(かたま)りや、何かわからないどろどろとしたものを吐き出し続けていた。 幾つかの口が、体内に溜っている毒素を、赤黒い鶉(うずら)の卵ほどの大きさのものにして、吐き出しているのも、これまでと同じだ。 だが、それらは、この獣の無意識がやっていることのように見えた。 たとえば、それは、心臓の脈動のようなものだ。 たとえば、それは、肺の呼吸のようなものだ。 あるいはそれは、歩行のようなものだ。 心は何か別のことを考えていても、それらの臓器や脚は、自分の動きを続けることができる。 しかし、その獣の本体、その意識は、今、はっきりと九十九に向けられている。「久鬼、おれだ。九十九だ」 九十九は言った。 と―― その獣の中心あたり。 獣 -
キマイラ鬼骨変 一章 獣王の贄(にえ) 7
2013-09-11 00:007
何故、宇名月典善(うなづきてんぜん)がここにいるのか。 龍王院弘(りゅおういんひろし)はそう思った。 自分の方が、かつての師、典善にそう問いたかった。 自分が、典善のもとから去ったのは、このままでは、いつか自分はこの師と闘うことになると考えたからだ。 言い出したのは、典善からだ。 出てゆけと言われたのだ。 このままじゃあ、おめえを殺しちまうかもしれないと、そういうことを言われたのではなかったか。 ちょうどよかった。 龍王院弘自身も、似たようなことを考えていたのだ。 闘ったら、どうなるか。 負けるとは思っていなかった。 しかし、勝てるとも思ってはいなかった。 だが、このまま一緒にいれば、ある時、ふいにその瞬間が来てしまうような気がした。 その結果、自分は典善を殺してしまうかもしれない。 逆に、自分が典善に殺されてしまうかもしれない。 そういう闘いになるであろうということはよくわかっ
1 / 3