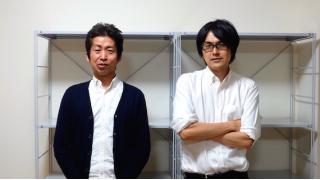-
ライフスタイル化するランニングとスポーツの未来 『走るひと』編集長・上田唯人×宇野常寛・後編(PLANETSアーカイブス)
2018-10-15 07:00550pt
今朝のPLANETSアーカイブスは、雑誌『走るひと』編集長の上田唯人さんと宇野常寛の対談の後編です。ランニングが持つシンプルさと間口の広さ、「ライフスタイルスポーツ」人口の増加とその背景、新しいホワイトカラーの生活とテーマコミュニティ化するランニングの今後についてなど、「PLANETS vol.10」と『走るひと』のコラボレーションの、思想的な背景がわかる対談となっています。(構成:望月美樹子) ※この記事は2016年2月19日に配信した記事の再配信です・前編はこちら
【告知】 本記事に登場する『走るひと』編集長の上田唯人さんが、10月17日(水)に開催されるオンラインサロン・PLANETS CLUBの第8回定例会で、ゲストとして登壇されます。イベントチケットはこちらで販売中。PLANETS CLUB会員以外のお客様も購入可能です。ご参加お待ちしております!
▼雑誌紹介
雑誌『走るひと』
東京をはじめとする都市に広がるランニングシーンを、様々な魅力的な走るひとの姿を通して紹介する雑誌。いま、走るひととはどんなひとなのか。プロのアスリートでもないのになぜ走るのか。距離やタイム、ハウツーありきではなく、走るという行為をフラットに見つめ、数年前とはひとも景色もスタイルも明らかに異なるシーンを捉える。 アーティストやクリエイター、俳優など、各分野で活躍する走るひとたちの、普段とは少し違った表情や、内面から沸き上がる走る理由。もはや走ることとは切っても切れない音楽やファッションなど、僕らを走りたくてしようがなくさせるものたちを紹介している。
https://instagram.com/hashiruhito.jp
https://twitter.com/hashiruhito_jp
■「走ること」の持つシンプルさが間口を広げている
上田:2020年のスポーツ文化を考える時に、もっとこういう視点で読み解いたらいいのにと思うところや、他のカルチャーから学ぶことはありますか?
宇野:他のカルチャーから学べることで言うと、エンターテインメントジャンルのノウハウを取り入れることで、スポーツをアップデートできると思うんですね。まさにeスポーツ学会が実践していることです。近代スポーツや近代体育のロジックが画一的な身体観に基づいている一方で、エンターテインメントは個々のプレイヤーの個性や多様性を使って盛り上げていく特性を持っているので、それを取り入れることでスポーツというゲームの更新ができるはずです。
もう一つはライフスタイルでしょうね。現在のランニング文化の変化は、適度な運動が健康管理の上でポジティブな効果を持つという認識がようやく浸透して、運動がカジュアルなライフスタイルとしてしっかり根付いてきた結果ですよね。その中で、身体を動かすことを含んだ生活を、多様性を帯びつつどうポジティブに見せていくのかということです。運動することが特別ではなくなるのが大事だし、勝手に変わっていくとも思います。
上田:これまで取材をしてきた中で、面白いと思っているのが、ロックバンドのアーティストにめちゃめちゃ走る傾向があることなんです。特に、ボーカルとドラムの人がすごく走っているんですよ。
宇野:へえー。ギターやベースのひとはあんまり走らない(笑)
上田:走ってる人もいるんですけど、気付いたらボーカルとドラムが一緒に走っている。理由の一つはボーカルとドラムが特に体力を使うことです。アーティストにとって、今はCDを売ってどうこうよりも、ライブツアーをしていかに食っていくかが重要だから、それに耐える体力が必要になったということです。
でも、それ以外の背景があるような気もしているんです。ロックの表現が衝動的なことや、有り余ったエネルギーを表現のモチーフにしていることと、走ることの間に関係があるのかなという想像もしていて、『走るひと2』でロックの精神性のようなテーマを少し紐解いてみたんですよ。
例えば、AKB48のまりやぎちゃんが走ったというので、その理由を聞いたんですけど、喘息を患わっていたぱるるの快気を祈って走ったと言うんです。「祈って走る」というのは、論理的に因果関係がないですよね。でも、彼女にとっては、走るという方法で祈りを示すことが、ぱるるを勇気付ける手段になっている。これはどういうことなのかと疑問に思ったんです。
宇野:まりやぎ結構いい奴ですね(笑)。
上田:良い奴なんですよ。クールに見せて、割とそういう人間ぽいところがある。話を聞いているとすごく家族思いだったり、近しい人間への愛情がある人だなというのをすごく感じました。そういうふうに、『走るひと』では人が走ることをいろいろな捉え方でやっているんです。
宇野:面白いですね。変な例えですけど、僕の中で長距離ランナーといえば村上春樹なんです。趣味でずっと走っていて、マラソンまで出ちゃう。ああいう人って、イメージとしては草食動物で穀物を食べている感じなんですよ。一方で、ロックバンドとか短距離ランナーの人たちは、朝まで飲んで喧嘩するような、肉食のイメージがある。だから今のアーティストの話を聞いて思ったのは、もともと草食な人たちのものだったランニングが、肉食の人たちまで巻き込もうとしてるということです。ランニングが多様になってメジャー化していく中で、本来ならコツコツ走ることが性に合わないタイプの人も巻き込みつつある。この比喩で言うと、僕自身はお酒を飲まなくて甘いものが好きなので、お菓子の人間なんですよね。
上田:お菓子の人間かわいいですね(笑)。
宇野:だから僕は歩いて適当にカフェに入って、本読んだりお菓子つまんだりする。僕みたいに、酒飲まなくて甘いモノが好きでオタクで、というようなお菓子型の人間も、ロッカーのような肉食型の人間も、ランニングは同時に包摂しようとしている。僕はランニング史には詳しくないのですが、ガジェットが充実してきたことや、ランニングが都市部のライフスタイルとして定着してきているといった背景があって、間口がどんどん広くなっている。それで、本来なら対象外にあるタイプの人間まで巻き込もうとしている感触があるんですよね。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
【特別対談】加藤貞顕(cakes)×宇野常寛「テキストコミュニケーションとかつて〈本〉と呼ばれたものの未来について」(PLANETSアーカイブス)
2018-02-19 07:00550pt
今回のPLANETSアーカイブスは、cakesやnoteを運営する株式会社ピースオブケイク代表取締役CEOの加藤貞顕さんと宇野常寛の対談をお届けします。「メディアビジネスの未来」をテーマに、『PLANETS』の歴史を振り返るとともに、情報環境の変化や、その中でこれからの時代に求められるコンテンツの形について語り合いました。(構成:大山くまお/初出:「cakes」メディアビジネスの未来【特別編】)※この原稿は2016 年4月29日に配信した記事の再配信です。
最初は自己実現、能力の証明の手段だった
加藤 今回は、「メディアビジネスの未来」というテーマで、宇野さんにお話をお伺いできればと思います。現在は評論家としての活動のほか、PLANETSという会社を立ち上げて、雑誌『PLANETS』の刊行や有料メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」の発行など、さまざまな活動をされています。
まずは、『PLANETS』というメディアの始まりから、今に至るまでのお話を教えていただけますか?
宇野 雑誌の『PLANETS』を最初に作ったのは、もう10年くらい前ですね。当時、京都で普通に会社員をしていたんです。でも物書きをしたい、自分でメディアを作りたいという気持ちが強くなっていて。東京の出版業界に強いコネクションがあったわけでもなく、地方にいるので情報発信の仕事に就くのは難しい。でも、もし自分で雑誌を作って、それが売れたら、自分たちの能力の証明になるんじゃないかと考えたんです。
それで、僕がおもしろいと思っている書き手の人たちに声をかけて、ウェブサイトで評論活動を始めました。その集大成として作った雑誌が『PLANETS』です。
加藤 当時は、宇野さん、27歳くらいですよね。僕、『PLANETS』が創刊されたころのことを覚えています。いきなり、おもしろいことをやっているコンテンツ群がネット上に現れて、雑誌まで出してしまう。ぼくは当時、出版社の編集者だったんですが、なんだこれは、と思いましたよ。『PLANETS』は、最初からビジネスにするという気持ちで立ち上げたのですか?
宇野 いや、そういうわけでもないですね。当時は「自分たちの方が東京の業界人よりアンテナも高いし、おもしろいものが作れるんだ!」という強い気持ちがあって作ったんですけど、今思うと、若さゆえの過ちですよね(笑)。でもね、案外間違ってなかったとも思います。実際、本屋に並んでいる雑誌に同世代の書き手がちらほら載り始めて、まあ、端的に言ってまったく面白くなかったんですよね。だから「これは自分たちでやった方がいい」と思ったんです。僕は昔から、文句ばっかり言って自分では手を動かさないという人たちが一番嫌いなので、自分たちでやってみようとすぐ思ったわけです。
じつは『PLANETS』を作る前、学生の頃の同人サークルのつながりで知り合った編集者に「僕はそこらへんの人たちより、おもしろいものが書けるので仕事をください。その証明のために、僕たちはこれからホームページを立ち上げるし、雑誌も作ります」とメールしたんですよね。
加藤 メールでそんな宣言をしてから『PLANETS』を作ったんですか! かなり気合いが入ってますね。しかも当時、会社員だったんですよね。
宇野 会社員です。出版に関してはほとんど素人でした。当時の直属の上司が、やはり会社員しながらペンネームでずっと本を書いている全共闘世代の人で、彼の影響も大きかったですね。
加藤 へええ。その創刊号は売れたんですか?
宇野 最初は、形になればいいというくらいの気持ちでした。創刊号は200部刷って売り切れたので150部増刷して、これも売り切れました。「よかったよかった、これで次の号も作れるね」くらいの話しかしていなかったと思います。
その後、部数を増やしていき、中身もどんどんやりたいことを妥協せずに放り込んでいった。制作費は全部僕が出していましたけど、最初の頃はみんな手弁当で、儲かったお金は全部他の号につぎ込むという形でしたたね。
加藤 それから『SFマガジン』の編集者から声がかかって、最初の単著『ゼロ年代の想像力』につながったんですか?
宇野 はい。『PLANETS』が売れ始めて、東京の出版社からお仕事をもらうようになった頃、以前に僕がメールを出した編集者の方が『SFマガジン』の塩澤編集長を紹介してくださったんです。そのとき、かなりゴツい企画書を持ち込んで売り込みました。字数的には1万字近い連載プランのような企画書でした。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
【特別対談】落合陽一×田川欣哉 〈人間〉という殻を脱ぎ捨てるために 後編(PLANETSアーカイブス)
2018-01-29 07:00550pt
今朝のPLANETSアーカイブスは、takram design engineeringの田川欣哉さんと『魔法の世紀』で知られるメディアアーティスト落合陽一さんの対談の後編です。デジタルネイチャーの到来によって、私たちの社会と価値観はどのように変容するのか。統治機構や経済の脱人間化から、情報技術の発達が生み出す新しい自然観・宗教観まで、来るべき世界のビジョンを徹底的に語り合います。
(司会:宇野常寛、構成:神吉弘邦/この原稿は、2016 年4月1日に配信した記事の再配信です)
※この記事の前編はこちら。
テクノフォビアと訣別せよ
落合 この前、電車の中でぼおっと、交通事故について思考実験してたんです。自動運転のクルマ同士がぶつかるんですよ。そこへお巡りさんが「じゃ、ちょっと現場を物証しまーす」ってやって来る。「ログデータ見ないとわかんねーな」って、「ログを出してください」って言うんですよ、2台の自動車に(笑)。
で、ログを出してもらうんだけど、それでも分からないから「説明してください」と。「5ミリ秒でここにぶつかりました」「で、こっちのオートシステムが作動しなくなったので当たっちゃいました」みたいなやりとりがあって。「ああそうですか!」ってその通りに調書作ってたら、警察機構の検証なんて存在しないのと一緒ですよね(笑)。
田川・宇野 (笑)。
落合 自動運転車同士の衝突を想定すると、警察機構が形骸化するんですよ。その辺りから、世間の人々はやっとひずみに気が付くんだと思う。「じゃあ、お巡りさんって一体何のためにいたんだろう?」って。
田川 調停者(笑)。
落合 そう、調停者だった。でも、お互いの言い分が食い違わない世界が存在していて、タイムスタンプが押されたデータを交換し合って、「センサーデータはそう反応していた」だけで問題が解決するようになったとき。
その世界における巡査のおじさんの気分って、「自分って関数だな」って思う以外ないですよね。
田川 結局これまでは、人間の振る舞いを機械側が捕捉しきれなかったんだと思うんだよね。例えば「入浴」にしたって、人間って変なこといろいろやるよね。コンピュータ側が人間の多様な振る舞いを捕捉しつくして、理解しにかかってるのが自動運転とかなんだよね。そこでは必ずインとアウトが対応してくる。
落合 関数から出力されたものを関数に入力するループが形成されると新しい関数が生まれるに決まってる。
田川 そう。関数の処理がステップで進んでいく過程を受け切る体勢が、機械側でセンシング的にもアクチュエータ的にも担保され始めると、人間の関数化って一気に進むと思うんだ。
落合 それは超進みますよね。人間はもうデジタルネイチャー化,脱構築化するんだろうなと思うよ。でも、それって幸せなことですよね。「奴隷の世紀」ではなく「魔法の世紀」って名づけることが重要なのであって、ようは心の持ちようの問題なんですよ。本当に「魔法化」っていう言葉が嫌いな人たちがすごくいるんです。「魔法に覆われると人間は退化するんじゃないか」って。そりゃあ魔法使ってるだけの人たちは退化するに決まってんだろ!(笑)。でもそれでいいんじゃないかってことなのに。
田川 そういう人を、英語で「テクノフォビア(テクノロジー恐怖症)」って呼ぶんだよ。講演会とかで話をしていると、よく「社会がそういう方向に進んでしまうことに不安はないのでしょうか?」とか言われるんだけど。
そういうときにはちょっと意地悪に「じゃあ聞きますけど、あなた今、裸足で生活してますか?」と。「靴下と靴を履いている時点で人間機械系なんだけど、それに日々悩んでますか? 『祖先と比べると私の足裏はなんて退化してしまったのか』と日々嘆きながら暮らしていますか?」って言うとさ、反論できる人いないんだよね(笑)。
宇野 それは反論できないですよね。
田川 自動車が世の中に受け入れられていく過程で「馬なし馬車」と呼ばれたり、テレビが普及するときに家具調の箱の中に入れてみたり、これはテクノロジー恐怖症の典型的な現れですよね。
僕の仕事でやっているのは、これから来るテクノロジーをどうやって社会に接続していくかで、そこにデザインの芽生えもあるはずです。
人間中心主義のまやかし
落合 2011年以降、デザインを巡る流れがガラッと変わったじゃない。ちょっと外れたアーティスティックなデザインで評価されていた時代が終わって、takramのようなデザインエンジニアリングに注目が集まるようになった。
今は「デザイン」っていう呼称は本質的にはなくなっていて、ストラテジックなエンジニアリングが美学を持って現れたものを「デザイン」と呼んでいるだけなんだと思う。
田川 『魔法の世紀』には結構デザインの話が書いてあるじゃない。デザインの歴史とか。
落合 第二次世界大戦前後のデザインとか。
田川 純粋に一読者としての興味なんだけどさ、落合くんの話を表層的に聞いていると「この人は人間に関心がなくて、機械にしか興味ないのかな」と思っちゃうよね。でも、デザインについて、あれだけ論じていることを考えると、そんな単純な話じゃない。落合くんの眼差しは、ピンポイントに一点に向かうというよりは、いろいろな分野を多方面的に見てると思うんだけど、本当のところどうなってるのかって気になるんだ。
落合 コンピュータのことをやっていたら、生物がコンピュータにしか見えなくなってきて、それが面白いと思ってるんですよね。森羅万象わりと興味あるし、人間っていう非合理タンパク質機械には心惹かれます。
田川 (爆笑)あぁ、わかったわかった。機械っていう動物園があったら、ヒト科ってのがあって、それはそれでなかなかいいものだ、みたいな話ね(笑)
宇野 人間中心主義とはここ2、300年ぐらいの「流行」に過ぎない、みたいなね。
落合 それまで自然と向き合ってきた人間たちって、そんなに人間中心主義ではなかったような気がするんですよね。
田川 そう思うよ。人間中心主義なんて、完全に機械化の歴史と符号してるからね。「個人」って概念もそうだよね。民主主義の成立の過程で個人という感覚が芽生えたという歴史があるじゃない。
宇野 工業化と市民社会の作った幻想が、カギかっこ付きの「人間」か……。
落合 「人間」イコール映像、イメージの共有文化によって生み出され一人歩きした幻想ってことですよね。
神が死に、今度は人間の番が来た
宇野 恐らくリベラルアーツ的な訓練をしっかり受けた人であるほど、テクノフォビアの傾向が強いと思うんですね。それは間違いなく統治の問題が関わっている。
人間機械系の発想でいくと、今の世の中で代表的なのが民主主義だけれど、それによる統治がうまくいかないのはほぼ明らかになってしまっている。文化的な装置で大衆の内面にアプローチして、熟議に耐えうる「市民」を養成するというビジョンが事実上破綻した今、さっきの自動運転の話のような機械人間系のアプローチの方が、統治の「効率」でいえば圧倒的にいい、という事実への評価ってまた変わってくると思うんですよね。賢い人ほど、薄々それがわかっているから怖いんだと思う。テクノフォビアって言い換えれば今までの自分をかたちづくってきた人間中心主義、民主主義、アート、「個」という幻想。この4点セットを根本から否定されてしまうことへのフォビア(恐れ)だと思うんですよ。
田川 あらゆる思想や思考の土台が溶けちゃうような感じがするから、すごく不安にはなるだろうね。
落合 たしかに。でも、歴史を知っていればそんなに怖くはないような気がするんです。だってコペルニクスが出てきて、キリスト教イデオロギーやばい! 俺たちどうやって思想と思考の土台を保っていこう?! ってなって、デカルトが登場して、ニュートンが登場して、みたいな話でしょう。
田川 そうそう。そこまで引いてみるとね、そうやって人間って進化してきたはずなんだよね。
宇野 逆にお二人に聞いてみたい。そのとき必要なのは、一度民主主義をちゃんと正面から否定した上で次を考えることなんじゃないかと思う。機械人間系の発想で考えると、全体の最適化はそれほど難しくない、だからいつヒトラーが大統領に選ばれるかわからない民主主義よりも、技術的な安全弁をあちこちにつけてマイルドな全体主義やっていく方がいいんじゃないか、って思想は良くも悪くも絶対に力を持ってくる。この問題に思想や文化の言葉の使い手はディストピアSF的な語り口でもいいから向き合うべきだと思う。「テクノロジーは時に人を不幸にする」なんて常識論をドヤ顔で言って満足していないで、自分たちの前提としている人間観のゆらぎ、社会観のゆらぎに向き合わないと誰からも相手にされなくなる。
落合 うん、それはその通りだと思っていて。俺は最近トマス・モアにはまっているんですよ。トマス・モアはキリスト教が宗教改革に覆われていく時期の人で、彼の主著『ユートピア』はルターが95カ条の論題を出す直前に書かれた本です。ヨーロッパの歴史って、キリスト教が死んだことで人間中心主義になっていったんですよね。そのキリスト教が死にかけていたときの人たちは、なにを考えていたのだろうと。
俺はデジタルネイチャー派として、今は「神」の次に「人間」が死にかけていると思ってる。そこでもう一度、過去に戻ろうとしているんだけど、それが宗教に行くのかネイチャーにいくのか、どっちなのかがまだ判別しきれていない。
デジタルネイチャーまでいっちゃうなら、人間の自然観そのものが機械人間系に変わってしまうから、そうなったら俺たちは「機械様」とくっつくことなく離れることなく仲良くやっていけばいいし、むしろ変なルサンチマンは存在しない世界観になっていくと思うんですよ。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
【特別対談】落合陽一 × 田川欣哉 〈人間〉という殻を脱ぎ捨てるために 前編(PLANETSアーカイブス)
2018-01-15 07:00550pt
毎週月曜日は過去の傑作記事を再配信するPLANETSアーカイブスをお届けします。今回は、takram design engineeringの田川欣哉さんと、『魔法の世紀』で知られるメディアアーティスト落合陽一さんの対談です。デザインとエンジニアリングのスペシャリストである2人が、人工知能、アルファ碁、そして、コンピュータによるパラダイム転換がもたらす、人間を中心としない新しい世界観のビジョンを語り合います。 (司会:宇野常寛、構成:神吉弘邦/この原稿は、2016 年4月1日に配信した記事の再配信です)
『魔法の世紀』に辿り着くまで
宇野 落合さんが遅刻しているので、先に田川さんに少し打ち合わせ的に問題意識を共有しておきたい。
この本の編集を指揮していたときに思ったのは、コンセプトメイク的にちょっとずるいというか、チート的な本なんだよね。つまり、ほとんどのメディアアーティストは、与えられた情報環境の中で、それをいかに批評的に打ち返すかというゲームを強いられているんだけど、落合陽一は「既存のメディアアートはもはや無効で、これからは魔法的なテクノロジーを持ったアートだけが有効である。そのアートとはテクノロジーそのものである」というロジックで、さらに「俺はそれを自分で作っている」という論理構成になっている。これをやられると、同じことができない人は反論できないし、極論すると「研究してないやつはこの先アーティストとは呼べない」とすら言えてしまう。
ここに真正面から反論しようとすると、結構大変だと思う。落合君はアートがテクノロジーの発明ではなく、批評で成り立つ時代と状況のほうが特殊だったと言っていて、たとえば19世紀の印象派の登場や20世紀のキュビズムの登場は、ひとつのテクノロジーの発明だったと考える。だから「テクノロジーを開発しない表現行為が批判力を持つこと」がこの先もあり得るのかというレベルで戦わなきゃいけなくなる。ある人たちにとっては当然そうで、それ以外の人たちにはあり得ないことをめぐって論争することになっちゃう。そのせいで、すごく批判しにくい本になっていると思う。
田川 確かに、それはそうかもしれないね。最近『フェルメールの謎〜ティムの名画再現プロジェクト〜』というドキュメンタリー映画を観たんだけど、ティム・ジェニソンという発明家が、フェルメールの絵画の再現にチャレンジするという内容で、それがすごく面白かった。
フェルメールの絵画は本当に写真みたいで、カメラ・オブスクラを使っていたんじゃないかって説があるくらい。だけど、ティムさんは「きっとフェルメールは何らかのもっと高度なツールやテクニックを用いたに違いない」と考えて、当時から入手可能だったレンズや鏡を駆使して、フェルメールと同じような絵を描くための装置を作るんです。彼は一度も油絵を描いたことがないのでフリーハンドで描いたら下手くそなんだけど、その装置を使いこなすことで、フェルメールに近い絵を描いた。それをアートの大家に見せたらすごく喜んで、「本当にこれで描いたのかもしれないね」というコメントをもらうんです。
つまり、表現と技術は常に表裏の関係にあって、新しい表現を求める人たちが、新しいテクノロジーを探求してきた。そうやって、みんな出し抜きあいながらやってきたんだと思う。「この青色は彼にしか出せない」という絵の具が、有名な絵師の手元に秘蔵されていたという話もあるし。その意味では昔から一部のアーティストは、テクニックとメディアとコンテンツの間に区分を作らず、作品の表現面を作るだけじゃなくて、内部の技術的なこともやってきた。だから落合くんも、自分の作った機械でそこを目指すのかなと。
宇野 ずっと彼は「自分はグラフィックスの研究者である」と言っていて、やってることはセザンヌやピカソとあまり変わっていないというのが彼自身の認識なんだよね。
つまり、当時は平面のキャンバスに絵の具を塗るしか方法がなかったから、彼らの感覚にとってリアルなものを描こうとすれば、これまでとは異なった論理で平面を再構成する技法を追求するしかなかったけど、現代のテクノロジーを動員すれば、全く別のビジュアルを根本的に作り出すことができると思っている。
田川 僕が聞いてみたいのは、落合くんが物理現象にこだわる理由なんだよね。ピクセルに行かないじゃないですか。プラズマに触れられる「Fairy Lights in Femtoseconds」も身体性を前提にした作品で、そこには彼なりのエクスタシーがあるんだろうなと思う。
▲ Fairy Lights in Femtoseconds
https://www.youtube.com/watch?v=AoWi10YVmfE
宇野 彼はそこは一貫していますね。初期のいわゆるメディアアートっぽい作品、ゴキブリを使った「ほたるの価値観」とか「アリスの時間」の頃からそう。ああいった作品を「テクノロジー自体がアートだ」と言うようになってから作らなくなったけど、そこは今も変わらない。
あとは場の制御の問題に集中するようになったのも大きい。「Pixie Dust」のあたりで、完全に人間がまだ体験したことのない感覚を発明する、という方向に行ったでしょう。メディア論的に気の利いたメッセージや「政治的に正しい」問題提起よりも「触れるレーザー」を実現してしまうほうが社会批評的にもインパクトがある。これが真のメディアアート、だと開き直りはじめた。
田川 光と音を分けなくてもいいという統一原理的な理解が、落合くんの中にあるときアブダクション的に降ってきたんだろうな。
宇野 一昨年の音波の研究が大きかったんだと思う。僕が最初にインタビューしたのはその頃なんだけど、それまでの彼の研究モチーフは、基本的には「三次元空間にいかに描画するか」に集約されていたと思うんだよね。シャボン玉にモルフォ蝶を描いて浮かべるようなさ。そこには乾さんや藤井さんとの決定的な違いがあって、あの人たちは脳に電極を刺すことを考えているけど、落合くんは最初に会ったときからずっと「脳に電極を刺すことの先に行きたい」と言っていた。あれはちょうど「Pixie Dust」の原型になった音波で物体を浮かべる実験をやっていた頃だね。描画だけ、つまりビジュアルイメージの再構成だけだったら、脳に電極を刺したほうが早いと考える人はまだいると思う。
▲Pixie Dust
https://www.youtube.com/watch?v=NLgD3EtxwdY
田川 それは『魔法の世紀』の巻末の作品集を見ていても、改めてそう思うな。おそらく、あるときから落合くんは表現することをやめたんだよね。それがすごく潔いよい。
宇野 本当はもっと美術プロパー受けする小賢しいメディアアートも作ろうと思えば無限にできる。でも、そういう方向には行かなかった。
田川 これは相当に凄いことで。彼は一度表現を捨てている。でも一方で、彼の研究は視覚芸術的に強烈なインパクトを持っている。実は、そこが強みだったりもする。だから逆説的なんだけど、純粋に表現として見たときに、それが審美的な意味での完成に到達したら、無敵感さえ出てくると思うんだよね。
宇野 最初に会った首からカメラを提げていた頃の落合くんの仮想敵って、やっぱりパースペクティブだったと思うのね。ピントの合っていない眼球からの情報を脳で再構成している人間の視覚体験に対して、パースペクティブ以外のロジックで構成された新しいビジュアルで介入すること。より直接的に、三次元の世界にアクセスできるビジュアルをつくるというのが、ずっと彼のテーマだったと思う。
遠近法の発明は、人類史における最大級の視覚体験への介入だったわけで、当初の落合くんはそれに勝てるレベルのハックを考えていた。だけど実際に出来上がったモノは、それよりもかなりヤバいものになっていて、もはや視覚イメージからは逸脱しつつある。それが『魔法の世紀』の「デジタルネイチャー」につながっている。
田川 ピカソもそうだけど、作家には「○○の時代」っていう区分があるからね。落合くんは今の自分の好奇心の整理が付いた後、どこに向かうのかな。
宇野 「Pixie Dust」から「魔法の世紀」までが「対パースペクティブの時代」で、そこから先はもうちょっと違うものになるんじゃないかな。
田川 従来のテーゼに対するカウンターとして「魔法の世紀」があるとして、それが一定の機能を発揮した後、彼がどんなテーマを設定するのかには興味がある。
落合 お疲れ様です!
(落合さん到着)
宇野 お、来た来た。では僕はもう黙るので、あとは田川さん、よろしくお願いします。
インタラクティブからは2011年に卒業
田川 『魔法の世紀』面白かったです。僕は落合くんと宇野さんの二人のことを知ってるから、二人で書いた本だな、と。宇野くん担当の教科書的によく書かれている部分と、落合くんが持っているコアなスピリットみたいなところがよく一冊にまとめられた本だと思って勉強になりました。表紙にちょっと昔の作品(「A Colloidal Display」2012年)が使われているじゃない。この本で書かれているのは、この写真以降の話が中心になっているよね。
ある瞬間を境に、落合くんの中で、ビフォー・アフターがクッキリ分かれているのかな。落合くんがどこかで表現をやめた瞬間が確実にあるな、と本を読んで感じたから、そこを最初に解説してほしい。
▲A Colloidal Display
https://www.youtube.com/watch?v=tvxJs_4m0ZE
落合 俺はやることがガラッと変わったのが2011年。これ以降、俗に言うインタラクティブなことをやるのを一切やめたんですよ。あの年は震災もあったけど「インタラクティブ」というものが、かつての先鋭的なものから広告やMAKE的な表現に変わった瞬間だと思うんです。
それまで当時の中村勇吾さんが作っていたような作品がメチャクチャ評価されてインタラクティブ・ウェブメディアみたいなものもすごく見かけたのに、いつの間にインタラクティブで閉じた作品それ自体は「そういうのあったな」という感じになった。俺の変化か、社会の変化か分からないけど、チームラボもインタラクティブなものを作ることをやめてしまった。今までコンピュータ表現をやってきた俺はどこを目指すのか、考えた時期があったんです。
田川 僕にも同じくらいの時期にアクションという単位で行ったり来たりをカウントする表現自体が、少し古臭く見えた瞬間があった。
人間と機械のつながりをアクション単位で説明するよりは、場のポテンシャルの方程式みたいなことで、定常的に釣り合っている状態がいくつかあって、その落ち着き方がいろいろある、という理解の方が楽なんだろうと思って。
人間中心論を超えていく
田川 落合くんにとってインタラクションが古臭く見えたのは、自分の創造性が「人間機械系」から「機械系」に移ったということなの?
落合 むしろ人間を機械で分解してやったら、結局は機械系の真理に落ちるんじゃないかという気づきがあったんですよ。人工知能がそのうち人間の仕組みを解明してくるとするならば、人間はどんな感じに分解されていくんだろうって。人間って部品だし、フィルターでできていると思うから。
人間もきっと、人工知能のディープラーニングと全く同じような方程式で記述されるようになる。そう思ったとき、「場」とか「物理」みたいなもので人間を捉え直していく表現手法があるだろうと思ったんです。そこが2011年。おっしゃるとおり、この年以降は「波」しかやっていないんですよ。
そこからの系譜にいったん区切りが付いたのが今年の頭で、今の俺の中での流行は「人間中心論を超えて場をどう捉えるか」になっているんです。
田川 音波も光も波として統一的な理解ができるけど、それに対して人間の知覚は統一的じゃないじゃない。音は鼓膜で聴くし、光はやっぱり目で捉えるしって。そして、その中で浮かび上がる知覚的イメージはお互いに断絶してて。面白いよね。
落合 色っていうのが一番ヘンなもの。おそらく自然界に存在しなくて、波長ベースの強度分布しかないにも関わらず、人間は赤とか青とか、全く違うものとして認識しているんです。本当はグレースケールで見えるはずじゃないですか。それなのに、波長をセパレートして混ぜ合わせるっていうオリジナリティの高いことをしている。
その人間の時間尺度とか空間尺度とか、振動に対する感覚って独特。人間って揺れているもの以外、知覚できないんですよね。目ですら動きがないと全く知覚できないから。
田川 落合くん、ロケットの打ち上げって見に行ったことある?
落合 1回あります。種子島で。
田川 俺も-Ⅱを結構な至近距離で見たんだけど、あの時に、聴覚と体表の触覚が連続した瞬間を味わった。分かる気するでしょ?
落合 わかります。「あ、揺れてるんだ」って。体感で1Hzくらいの波!
田川 ドォォーーーッ!と来て、自分の身体が揺れる。「音って空気がリアルに振動するんだ!」みたいなね。人間は自分たちが日常生きてる時に、合理的に反応する感覚器だけが今残ってるけど、エネルギーの爆発的な放出を前にすると、人間の感覚器と、それに由来する知覚イメージの断絶は吹っ飛ぶと、その時に思ったんだよね。
落合 その合理的な反応ってきっと、生活の中に閉じ込められた弱いエネルギーたちの集まりなんで、結構セパレートされてる。
でも、強力なプラズマ場とか作ってやって、もう何だかわからない猛烈なエネルギーが出てきて、下手するとエックス線とかも出てるんですけど(笑)、そうなると「あ、人間にとってはこれは音でも光でも触覚でもない何かなんだな」みたいなのがあって、それが俺にとって面白かったんですよ。
田川 そういう意味では、全ては波と釣り合いで考え得るよね。
落合 まぁ、重力波まではそうでしょうね。
人間機械系から、機械人間系へ
落合 しかし、場の釣り合いっていう話題が田川さんからも出てくるのがさすがっていうか慧眼ですよね。
田川 インタラクティブな、コンピュータの入ったプロダクトを作っていくときには、必ずそんなイメージで考えるわけ。インタラクティブではないプロダクトの場合にはなおさら、それが際立つ。
例えば今、僕がこの椅子に座ってるけど、自分の脚と椅子の脚とで合計6つの脚で着地をしていて、その地面と力の釣り合いを保っているわけで、僕と椅子は安定的に一体化しているよね。その安定状態を離脱して、次の安定状態に行くっていうのが「移動」とか「動き」ってことになる。
落合 状態遷移図で書く話になってくる。
田川 多分、全地球上に存在しているオブジェクトは、全部が状態の相関の中で理解できる。次、僕がコップを持つっていうところから鉛筆で書くっていうところまで、それで理解できる。
落合 そうですよね、場の釣り合いの動きだけで。
田川 人間機械系のモデルってさ、やっぱり通信速度とかCPUのクロック数とかセンシングの速度とか、ロジックが一回転するステップにすごい時間がかかってた時代の物差しだと思うんだよね。
だから、その時代の人たちのレイテンシー(遅延時間)に対する考え方も、やっぱりレイテンシーがあるからそれを意識するんだけど、もはやそれがゼロになった人たちってレイテンシーのことなんて考えないと思うんだよね。
落合 ああ、そうですね。
田川 人間の脳内でコンマ2秒くらいの認知の遅延が起こってる時に、それでも、刻々と変化する周囲の状況に対応するために、人間の側は先読みをしながら動く。つまり、人間の側は仮説モデルを頭の中に持っているから、プロダクトの側はできるだけそれに合わせた動きになるようにデザインする、というのが基本なわけじゃない。
全くそれが一致したとき、つまり、人間の脳内で構築されたモデルとプロダクトの動きのズレが完璧に一致したときに何が起こるのか。それは「釣り合っている」というイメージに近い。それを何と呼ぶのかっていう世界。釣り合ってるってことはさ、場的にいくと一体化してるわけ。
落合 一体化してますよね。安定状態にある。
田川 それともうひとつ大きな流れとしては、かつての人間機械系が、主客逆転で機械人間系に移っていくことなんだと思う。
そうなったとき、これは逆説的なんだけど、コンピュータサイエンティストたちは人間を理解するというフェーズに戻らなきゃいけない可能性がある。なぜなら、いわゆる関数として人間を見たときに「この人たちをどうやって命令通りに動かすのか」みたいなことで。
それは従来、政治家とかが取り組んできたことだと思うんだけれども、同じことをコンピュータサイエンティストたちが機械人間系をうまく機能させるために考えなきゃいけないのかもしれないね。全く新しいフィールドがなんか開けてくる(笑)。
落合 政治と立法ですよね! 俺も最近講演会で政治の話すること増えました。人間がやってきたコーディングの過程、法律ってコードだと思うんですけど、それをこっち側が考えて緩めたりしないといけないんだろうなって、最近はすごく思うようになってきました。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
【特別対談】國分功一郎×宇野常寛「哲学の先生と民主主義の話をしよう」前編(PLANETSアーカイブス)
2017-11-20 07:00550pt
今回のPLANETSアーカイブスは、政治論集『民主主義を直感するために』(晶文社)や『中動態の世界 意志と責任の考古学』(医学書院)の著者である哲学者・國分功一郎さんと本誌編集長・宇野常寛の対談です。前編では「保育園落ちた日本死ね」ブログ問題や、反原発・反安保運動について語りました。(構成:中野慧 )
※本記事は、2016年 4月26日に放送されたニコ生の内容に加筆修正を加え、2016年5月27日に配信した記事の再配信です。
▼放送時の動画はこちらから!
http://www.nicovideo.jp/watch/1462950394
放送日:2016年4月26日
民主主義を根付かせるためのキーワードは「直感」
宇野 今回は、1年ぶりにイギリスから帰国した哲学者の國分功一郎さんをお招きして、現在の日本の政治・社会状況について語っていこうと思います。國分さんが、まあ一言で言えば「悪い場所」になりつつある日本から遠く離れているあいだ、僕のほうもこの1年、いわゆる「論壇」的なものとは距離をおいて、毎週木曜朝の「スッキリ!!」以外はほとんど引きこもって自分のメディアからの発信に注力してきたつもりでいます。と、いうことで今回は、そんな二人がこの1年考えてきたことを率直にぶつけあう対談にできたらと思います。
とりあえずはまず、國分さんの新著『民主主義を直感するために』(晶文社)が発売されたわけですけど、その話からしたいなと。
國分 『民主主義を直感するために』で言いたかったことは、本当にタイトルそのままですね。巻末に、辺野古に行ったときのことを書いた「辺野古を直感するために」というルポが載っているんだけど、その「直感」という言葉がキーワードだと思って本のタイトルにも使うことにしたんです。俺は哲学をやっているから理論的なことをよく話すし、理論はもちろん大切だと思っているけど、「現場を通じて具体的に『直感』する」というのもそれと同じぐらい大切だと思っているんだよね。これまでに色んな場所で書いた文章をまとめた本ですが、結果的にとてもいいものになったと思ってます。
「直感」という言葉にはちょっとしたこだわりが込めてあって、まず、「直感」と「直観」という同じ読みの2つの言葉がありますよね。哲学では「直観」のほうを使うことが多いけれど、こちらは非常に理知的なイメージの単語ですね。それに対し「直感」は感覚的です。多くの場合、英語で言う"intuition"は「直観」の方に対応すると思うんですね。すると、「直感」は英語には翻訳不可能だということになる。こう考えると、この言葉は特殊な身体性が織り込まれているというか、「具体的に体で感じ取る」というイメージのとてもいい日本語じゃないかと思うんです。そういう感覚が民主主義をやっていく上で大事なんじゃないかということをこのタイトルに込めました。
宇野 このタイトルに関して僕もいろいろ思うところがあるんですけど、結論から先に言うと「今のこの2016年の日本では民主主義を直感させないほうがいい」と思っています。
國分 いきなり直球が来たね(笑)。さっそく話をはじめましょうか。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
京都精華大学〈サブカルチャー論〉講義録 第13回 教室に「転生戦士」たちがいた頃――「オカルト」ブームとオタク的想像力(PLANETSアーカイブス)
2017-11-13 07:00550pt
今回のPLANETSアーカイブスは「京都精華大学〈サブカルチャー論〉講義録」。80年代のオカルトブームを取り上げます。70年代に始まったオカルトの流行は、『ぼくの地球を守って』など、「前世」や「転生」をモチーフにした一連の作品を生み出しますが、その影響を受けて、現実でも「前世の仲間」を探そうとする若者が大量に現れます(この原稿は、京都精華大学 ポピュラーカルチャー学部 2016年6月10日の講義を再構成したものです/2016年12月2日に配信した記事の再配信です)。
つのだじろうとサブカルチャーとしての「心霊」
「オカルト」というかつて存在したジャンルと、その隣接領域としてのマンガ・アニメについてもう少し考えてみましょう。 つのだじろうの『恐怖新聞』という作品があります。このつのださんは、ミュージシャンのつのだ☆ひろさんのお兄さんですね。彼は藤子不二雄コンビや石森章太郎と同じトキワ荘グループのマンガ家で、初期はギャグマンガやスポーツマンガで知られていました。この時期の代表作『空手バカ一代』はアニメにもなったヒット作です。
しかし70年代半ばからはオカルトブームを背景に、すっかり「心霊マンガ家」になってしまいます。この時期つのださんは『うしろの百太郎』『恐怖新聞』で大ヒットを飛ばすわけですがブームに乗っかったのではなくて、プライベートでも心霊研究をかなり本格的にやっていたので、いわゆる「ガチ勢」ですね。
では『恐怖新聞』を少し読んでみましょう。 平凡な中学生の鬼形礼(きがた れい)という主人公はある日、霊に取り憑かれ呪われてしまい、「恐怖新聞」という、読むと必ず寿命が100日縮まる新聞が毎晩配達されるようになります。この恐怖新聞には「明日誰々が死ぬ」という不吉なことが書かれている。未来を知ることができるから、鬼形礼は不幸なことが起こるのを阻止すべく奮闘して、失敗したり成功したりするんですね。で、読むたびに寿命は縮まっていくので、最後には死んでしまいます。 『恐怖新聞』は心霊マンガなんですが、だんだんストーリーが進むにつれて今読みかえすとおかしな方向にも向かっていきます。たとえば「円盤に乗った少女」という回がありますが、なぜかUFOネタが入ってくるんですよ(笑)。心霊とUFOは全然関係ないですよね。 あるいはこの鬼形くん。物語の後半でなぜか埋蔵金を探しています。埋蔵金っていうのは豊臣秀吉や徳川家康が子孫のためにどこどこの山中に大量の金銀を埋めておいた云々という、例のアレですね。もはやここまで来ると心霊マンガでもなんでもないんですが、当時としてはそれほど不思議なことでもないんです。 当時の、いや、今もいくつか残っているオカルト雑誌を読むとよく分かるんですが、「超能力」も「心霊」も「UFO」も「埋蔵金」もジャンルとしては同じ「オカルト」なんです。当時の「オカルト」は陰謀論や疑似科学によって当時日本社会を覆っていた終わりなき消費社会の日常から逃避させてくる装置だったわけで、その逃避機能を保証する非科学性というところでジャンルの統一性を保っていたんですね。
80年代オカルトブーム絶頂期と『ぼくの地球を守って』
さて、「オカルト」ブームとマンガ・アニメの関係を語る上で外せない作品があります。 1986年から1994年まで少女マンガ誌「花とゆめ」に連載された日渡早紀『ぼくの地球を守って』です。のちにビデオアニメにもなっています。
(『ぼくの地球を守って』映像再生開始)
超古代に、高度な文明で栄えた異星人たちが月に基地を作って、そこで科学者たち男女7人が働いているんですが、恋愛関係のもつれと基地内での伝染病の蔓延によって全員死んでしまいます。その7人が何千年か後に現代日本人に転生してもういちど恋愛をする。当時流行っていた『男女7人夏物語』のようなトレンディドラマに、転生要素を加えたストーリーですね。 これはマンガでもヒットしましたが、オカルト界では大ヒットしました。前世ではヒロインと相手役の男は同じぐらいの年齢なんですが、前世で死亡したタイミングがずれたせいで転生後の再開時にはお姉さんと少年になるわけです。いやあ、いろんな欲望を同時に満たしすぎですよね(笑)。前世ではオラオラ系のイケメン、現世ではインテリ系の美少年をゲット、的な。 彼らは前世で超能力を持っていたのですが、現代日本に転生した主人公たちはだんだん前世の記憶とその能力を取り戻していき、現代日本で起きる事件に立ち向かっていきます。
▲日渡早紀『ぼくの地球を守って(1)』白泉社文庫
実はこの時期、この国では「前世は超古代文明(ムー大陸とかアトランティスとか)の人間で、超能力を持っている」という自称転生戦士たちが現実世界に溢れかえったんです(笑)。この現象についてはインターネット上のサイトにまとまっていますので、それを見ていきましょう。
(参考)『ムー』読者ページの“前世少女”年表 - ちゆ12歳
80年代当時はインターネットがなかったので、オカルト雑誌の「ムー」の投稿欄で「ペンパル」といって要は文通相手を募集したんです。そこに自称転生戦士が「こういう記憶を持っている人、お友達になりませんか?」という募集を出すわけです。というよりも、『ぼく僕の地球を守って』はそのオカルト雑誌の読者投稿欄に着想を得て作られているんです。 実際『ぼく僕の地球を守って』の序盤は「前世にこういう記憶を持っている人いませんか?」とペンフレンド募集をして生まれ変わった仲間が再会するというストーリーです。『幻魔大戦』が代表する転生戦士というサブカルチャーのトレンド、物語フォーマットが流行してオカルトブームにも影響を与え、「ムー」の投稿欄も先鋭化して、さらにそこから『ぼく僕の地球を守って』が生まれ大ヒットしたことで、自称転生戦士がまた増えるというサイクルだったんですね。 この当時、転生戦士はたくさんいました。さきほどのサイトを見てみましょう。
「戦士、巫女、天使、妖精、金星人、竜族の民の方、ぜひお手紙ください」 「前生アトランティスの戦士だった方、石の塔の戦いを覚えている方、最終戦士の方、エリア・ジェイ・マイナ・ライジャ・カルラの名を知っている方などと」
こういった手紙がたくさん「ムー」には掲載されていたわけです。すごいですね。
1979年 『ムー』創刊。創刊号から「自分が地球以外の宇宙人だと思う人と文通がしたいので~す」という14歳の女の子はいますが、まだ前世少女からの投稿はありません。 1980年 まだ前世少女はいません。 「あたし‥‥実は異星人なんだ‥‥」「異星人の仲間どこかにいない‥‥?」(3月号)という15歳の女の子はいますが、本気度は不明。
イラストがいいですね。当時のアニメブームのテイストの絵になっています。
1981年 この時期、「超人ロックが好きで、ロックのようなESPERになりたいとがんばっています」(5月号)という14歳の女の子など、エスパー志望者がやや目立ちます。 1982年 「転生、超能力、SFに興味がある女子」との文通を希望する18歳(4月号)や、「転生について異常なほど興味があり、明るすぎるほどのぼくにお手紙ください」という16歳(10月号)など、転生に関する投稿は少し増えました。 1983年 この頃、「人類救済を目的とするサークル」のメンバー募集(5月号)など、終末を意識した投稿が増加します(たぶん、3月公開の『幻魔大戦』劇場版の影響が大きかったと思われます)。
『幻魔大戦』の映画版がこの年に公開されています。
9月号では、「自分が宇宙とかかわる“光の戦士”か“救世主”だと思う方、連絡してください」という中3の女の子が登場。 10月号には、「前世の記憶がもどり、超常現象の体験がありま~す」という中3の女の子。
ここから、こういう手紙がだんだん増えてきますね。
1984年 「不思議な夢をよく見ます。私には何かの使命があるような…」という高2の少女(3月号)。 「この風景に見覚えのある方おまちしてます」と、イラストを投稿する18歳の女の子(7月号)。
……見覚えがあったら衝撃的ですね。
「古代ギリシアの地中海にいたころの過去世の記憶がある方で、自分の魂、もしくは守護神がギリシア神話に出てくる神々である方と。私の守護神はアポロンですが、同じ系列の仲間を捜しています」という23歳の男性(12月号)。
これもなかなかいい感じですね。当時23歳だと、現在は還暦に近いですよね。1985年だから、これは僕が小学校1年生の頃です。
1985年 「前世の記憶が“平家一門”だったのではと思われる方…そして“葵”という名の源氏方の若い武将にお心当たりの方」からの連絡を待つ17歳の女性(3月号)。 「あたしは幽体離脱、幽体分裂、時間をもどしたり、遅くすすめたり、タイムリープができます。100年に1度の天使のハネを持つ妖霊です」という18歳の女の子が、「マヤ出身の人(白い魂の子)」との文通を希望(3月号)。 ※「弥生時代か飛鳥時代に生きた記憶のある方、ご連絡ください」という高校3年生や、「毛利元就の2男・吉川氏の家系の前生をもたれる方、おききしたい事があります」という17歳(5月号)など、この頃までは、前世が異星や異次元なのは少数派でした。 7月号では、「自分がミヤリア一族だと思われる方、または、ソディラ、セカ、スィール、ミヤ、セヤ、ジィン、マラ、リヤ、トルファン、オルキムの名に心あたりがあるか、自分の魂の名がこのいずれかの方」を探す15歳の女の子が登場。これ以降、カッコイイ名前の尋ね人が増えます。
魂の名とはいったいなんでしょう。当時の文通覧は、住所も公開しているんですよね。これ、なかには実際に「俺が前世の恋人だ」とか言って押しかけてくるケースもあったと思うんですよね。そこでイケメンが来ればいいけれど、そうじゃなかったらどうしたんでしょうね……。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
京都精華大学〈サブカルチャー論〉講義録 第12回 「世界の終わり」はいかに消費されたか――〈宇宙戦艦ヤマト〉とオカルト・ブーム(PLANETSアーカイブス)
2017-10-23 07:00550pt
今回のPLANETSアーカイブスは「京都精華大学〈サブカルチャー論〉講義録」をお届けします。ここからの講義録は「戦後アニメーションと終末思想」がテーマ。今回は70年代半ばに第一次アニメブームを起こした『宇宙戦艦ヤマト』『銀河鉄道999』におけるSF作品の内実の変化と、『幻魔大戦』に代表される「オカルト」というモチーフの浮上を扱います。(この原稿は、京都精華大学 ポピュラーカルチャー学部 2016年6月10日の講義を再構成したものです/2016年11月25日に配信した記事の再配信です。)
冷戦下のリアリティと『宇宙戦艦ヤマト』が描いたもの
今回からは、マンガ・アニメを代表とするオタク系サブカルチャーの想像力とその変質について、戦後消費社会の展開を追いながら話していきたいと思います。
みなさんは「世界の終わり」という言葉を聞いてどんなことを想像するでしょうか?
……そうですね、痛い感じのビジネス中二病のバンド(SEKAI NO OWARI)のことしか思い浮かばないですよね。 でも僕が子どもの頃は、「世界の終わり」ってマンガ・アニメの定番モチーフだったんです。「人類最後の大戦争が起こって人間は滅びるんじゃないか」「大戦争によって本当に世界の終わりがやってくるんじゃないか」というイメージがすごく強かった。 これはなぜかというと、当時は米ソ冷戦の真っ最中だったからですね。どちらも核兵器を大陸間弾道ミサイル(ICBM)に載せていつでも発射できるようにしていて、もしアメリカとソ連が全面戦争になったら報復攻撃の連鎖で世界中が核ミサイルで破壊されてしまうのではないか。そういうイメージに非常にリアリティがあったんです。
それに加えて、特に1970年代から90年代にかけて「ノストラダムスの大予言」というものが大流行しました。「1999年7の月、空から恐怖の大王が下りてくる」というやつですね。それが日本のオカルト好きの間で広く共有されていて、「恐怖の大王って核兵器のことじゃないのか」と言われていたんです。なんとなく、「20世紀の末に世界は核の炎に包まれて人類は滅亡する」という「世界の終わり」のイメージが若者たちのあいだで共有されていたわけです。今回はそういった終末思想が、サブカルチャーの想像力によってどう描かれてきたのかを扱っていこうと思います。 また逆に、「なぜ現代ではそういうモチーフが消滅してしまったのか?」という問題も考えてみたいと思います。いまや「世界の終わり」といえば単にビジネス中二病バンドの名前でしかなくなっているわけですが、このモチーフがなぜそこまで陳腐化してしまったかということですね。
まずはこの作品からみていきましょう。
(『宇宙戦艦ヤマト』映像再生開始)
みなさんはこの作品を知っていますか? あ、さすがにほとんどの人が知っているようですね。でも存在を知っているだけで、中身までは知らないでしょう? この『宇宙戦艦ヤマト』は、一番最初のアニメブームの起爆剤となった作品です。1974年にテレビシリーズの放映が開始され、そのときはそこまでヒットしなかったんですが、再放送でじわじわと人気に火が付いていきました。 ここまでの講義でもお話ししてきたとおり、1970年代までアニメって多くが子ども向け番組だったわけですが、『宇宙戦艦ヤマト』はティーンエイジャーから20代の学生、若い社会人に支持を受け、社会現象とも言える大ヒットになった作品でした。そしてこれをきっかけに、70年代半ばから後半にかけて続々とティーンエイジャーから大人をターゲットにしたアニメが制作されるようになっていきます。
▲宇宙戦艦ヤマト 劇場版 [Blu-ray] 納谷悟朗 (出演), 富山敬 (出演), 舛田利雄 (監督)
『宇宙戦艦ヤマト』は――のちに『機動戦士ガンダム』でも繰り返されることですが――全国にファンクラブができて広がっていき映画化もされたんです。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…
・入会月以降の記事を読むことができるようになります。
・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
戦後史としてのロボットアニメと〈移体性〉――フランス人オタクと日本アニメ熱狂の謎に迫る 『水曜日のアニメが待ち遠しい』著者 トリスタン・ブルネ インタビュー・後編(PLANETSアーカイブス)
2017-10-19 07:00550pt
今回のPLANETSアーカイブスは『水曜日のアニメが待ち遠しい』著者で、日本のアニメ・漫画のフランスでの受容構造を研究しているトリスタン・ブルネさんへのインタビュー後編です。ブルネさんの提唱する「移体性」という概念のもつ可能性について、丸山眞男の「無責任の体系」等とも比較しながら、宇野常寛がお話を伺いました。 ※この記事の前編はこちら
■ 主体性なき日本人の「移体性」
宇野:ブルネさんは研究者としては、日本の歴史を専門にされているそうですね。
ブルネ:日本の「史学史」、つまり日本における歴史の描かれ方を研究しています。博士論文のテーマは、55年に刊行された遠山茂樹らによる『昭和史』と、それへの批判から起こった、いわゆる「昭和史論争」です。この論争は、日本がなぜ戦争という悲惨な歴史を歩むことになったか、そこに至る歴史の描き方を、当時のマルクス主義者である遠山たちと、評論家・亀井勝一郎をはじめとする批判者が議論したものでした。僕はそれを、日本アニメの物語構造を読み解くヒントとしても、重視しているんです。
宇野:なるほど。僕が、ブルネさんは戦後の日本思想の研究者でもあると知って思ったのは、「移体性」という概念が、丸山眞男の言う「無責任の体系」と近いということなんです。つまり、社会にコミットしている自分はじつは自分ではなく、大きなものの顔色を伺った結果、主体的な判断なしで生み出された自分だ、と。ブルネさんの言う、主体でも客体でもない日本人の自己意識の持ち方には、これとの密接なつながりがある。戦後の中流文化を代弁しうる日本のロボットアニメは、同時に、独裁者のいないファシズムを生んでしまう「無責任の体系」と、表裏一体の関係にあると思うんです。
これに対して日本の多くの知識人は、その移体性を捨てろと言ってきた。要するに、近代的な主体になれ、と言ってきたわけです。しかし果たして、そんな単純な問題なのか、という疑問がある。ブルネさんの本で描かれていたのは、むしろそれを捨てることで、戦後の中流家庭はアイデンティティーを見失い、新たな空白が生まれるかもしれない、ということでしょう。その意味であの本は、丸山批判でもあるのではないか。
ブルネ:たしかによく言われる「日本人の主体性のなさ」は、移体性とも関係するかもしれませんね。ただ、日本で梅本克己のようなマルクス主義者が主体性の確立を叫んでいたころ、フランスでは存在論のブームがありました。とくに作家のアルベール・カミュの存在論なんかは、主体と客体の間の不条理を強調している。フランスにも、主体性は自明的にずっとあったわけではないんですね。もうひとつ、第二次世界大戦以前のフランスを含むヨーロッパの国々には、じつは日本的な移体性や、勧善懲悪的ではない大衆文化が多くあったんです。たとえば怪盗をヒーロー化した『アルセーヌ・ルパン』もそうです。しかし戦後に残ったのは、アメリカ型の物語だけだった。善悪はくっきり分けられるようになり、移体性を可能にする抽象的なスペースは失われていった。
宇野:一方の日本の戦後アニメは、移体性を捨てずにどう成熟するのかをずっとテーマにしてきました。ヨーロッパでは失われたのに、なぜ日本では移体性が生き残ったのか。僕の仮説は、日本には元から主体性はなく、移体性しかなかったからというものです。
ブルネ:なるほど。反対にフランスでそうした文化の側面が失われたひとつの原因は、移体性に目を向けることが「ナチス的」と捉えられがちだったからかもしれません。
宇野:実際にナチスのデザイン面は、現代のサブカルチャーに大きな影響を与えていますよね。
ブルネ:そうですね。日本アニメを輸入し始めた1970年後半には、すでにエリートを中心にした大人たちが、戦うロボットに自身を投影して熱狂している子どもたちの姿を見て、「ナチ的だ」「大衆に悪い影響を与えている」「暴力の賛美」などと言っていました。もちろんそこには、戦中の日本の軍国主義のイメージから来る偏見もあります。あと蛇足的なことですが、『グレンダイザー』のオープニングテーマが仏語訳された際、そこに「土地」という単語が入ったんですね。「我々の土地を守れ」といったような歌詞として届けられた。それで「やっぱり差別的だ!」という反応を生んだんです。
宇野:そんな経緯もあったんですね。
ブルネ:ただそうやって、日本アニメが与えてくれる移体性の経験を隠蔽しようとした結果のひとつとして、一部の人々の極右化を招いたと僕は思いますね。
宇野:自分たちのアイデンティティーを表現するカルチャーを持ってないがために、ネオ・ナチのような極右化が起こってしまった、と。
ブルネ:いまのフランスが直面している移民問題の拡大も、それとは無関係ではないはずです。自分たちを物語に仮託できないこと、つまり移体性を経験できない不満を解消するために、「排外主義」という最悪の物語に染まってしまったんじゃないか。僕の少年時代の経験からすると、日本アニメは差別的でも何でもなく、フランス人の子どもも移民系の子どもも、同じように楽しむことのできる、共通の話題だったんですよ。
宇野:日本は先進国の中でも階級差が少ない国だと思うんですが、日本のサブカルチャーの特徴は、エリートからブルーカラーの子どもまで、みんな同じ作品を愛していたことにあると思います。戦後の中流化、つまりフラット化と、アニメ受容のフラット化は重なりながら進んだ。しかし問題は、いまそのアニメの力が失われていることです。
日本では80年代前半に若者向けのサブカルチャーが大きく発展するのですが、その受容者というのは、基本ノンポリです。彼らはベビーブーマーたちを揶揄して「政治的な話をするのはカッコ悪い」と主張していた。ただ、サブカルチャーの受容者たちの中でも、アニメファンを中心とした今で言う「オタク」たちはちょっと違った。彼らは同世代の中では相対的にだけど政治的だったと思います。ただ、それは旧世代のようにイデオロギー回帰しているという意味ではなく、プラグマティズムとリアルポリティクスに基づく態度でした。ところが90年代後半以降になると、このオタクたちの多くは排外主義的な右翼になってしまった。その背景には、かつてアニメが持っていた移体性の力を、日本のアニメファンたちが信じられなくなったことがあると思う。
僕の理解では、かつてのオタクたちが保持していたプラグマティックな政治性は、戦後中流文化の生んだ独特の社会的な立ち位置と、その表現としてのブルネさんのいう「移体性」と深く結びついていた。要するに、戦後中流的な「移体性」的な社会へのコミットの抽象化された表現が「ガンダム」の代表するロボットアニメだった。
しかし、日本社会からは戦後的中流文化は後退し、アニメも移体性の表現を担いきれなくなっていっていると思うんです。
ブルネ:移体性には、自分の欠落を埋め合わせる部分があるので、それがアニメなどのカルチャーから与えられないと、「国民的なプライド」という方向に向かってしまうんでしょうね。アニメも誰かから与えられたものである点は変わらないけれど、想像力という媒介を経ていました。いまの排外主義には、想像力の枯渇しか感じません。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…
・入会月以降の記事を読むことができるようになります。
・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
京都精華大学〈サブカルチャー論〉講義録 第11回 碇シンジとヒイロ・ユイの1995年(PLANETSアーカイブス)
2017-10-02 07:00550pt
毎週月曜日は「PLANETSアーカイブス」と題して、過去の人気記事の再配信を行います。傑作バックナンバーをもう一度読むチャンス! 今回の再配信は「京都精華大学〈サブカルチャー〉論」をお届けします。『新世紀エヴァンゲリオン』が人気を集めるその裏側で、ボーイズラブ的に受容された『新機動戦記ガンダムW』が切り開いたロボットアニメの可能性。戦後日本の〈成熟〉にまつわる問題意識を乗り越える、新たな想像力の萌芽について論じます(この原稿は、京都精華大学 ポピュラーカルチャー学部 2016年5月13日の講義を再構成したものです /2016年11月4日に配信した記事の再配信です )。 「宇野常寛の対話と講義録」配信記事一覧はこちらのリンクから。
ロボットアニメを書き換えた1995年の『新機動戦記ガンダムW』
初代『ガンダム』から『エヴァンゲリオン』に至るまで、ロボットアニメの主人公の少年たちは等身大の悩みを抱えた「内面のある」キャラクターでした。自意識過剰で、「お父さんに認められたい」「女の子をゲットしたい」「大人の男になりたい」とか、そういった思春期の悩みに溢れていましたよね。ところが、そういった悩みを一切抱えていない少年を描いたロボットアニメが登場します。それが、『エヴァンゲリオン』と同じ1995年に放映された、『新機動戦記ガンダムW(ウイング)』です。まずは映像を観てみましょう。
▲新機動戦記ガンダムW Blu-ray Box
これ、オープニングですけど、なんというかすごいですよね。この冒頭から差し込まれる美少年ナルシシズム。ファーストカットがいきなり、謎のポーズを決めている美少年です。いやあ、人間はどういう自意識で生きていたらこんなポーズが取れるんでしょうね。自分は既に完成されていて圧倒的にカッコいいという確信がないと、まず、ムリです(笑)。 そして、このあとに彼が乗るウイングガンダムが出てくる。この時点でもう、この作品ではモビルスーツと主人公の少年の力関係が逆転していることが示されてしまっているわけですね。 で、続いて同じように全能感に溢れた美少年が4人現れます。やっぱりドヤ顔で謎のポーズを取っています。そしてモビルスーツは決めポーズを取る少年の背景に過ぎない。 この『ガンダムW』は、主人公のヒイロ・ユイをはじめ5人の美少年がガンダムに乗って戦うという話です。彼らは最初から全能感に溢れていて、世の中に出て行くための不満とか、巨大な鋼鉄の身体を得て大人社会に認められたいとか、そういった気持ちはまったく持っていないですね。 そして『ガンダムW』は、実は男性ではなく女性ファンから圧倒的な支持を集めました。当時まだボーイズラブ(BL)という言葉は一般的ではありませんでしたが、『ガンダムW』は山のようにBL同人誌が作られて、コミックマーケットでも一大ジャンルになったんですね。一方で、昔ながらの男性ガンダムファンからは「ガンダムが女子に媚びた」「堕落した」と散々批判されていました。実は放送当時はろくに観もしないで、僕もそう思っていました。 実際に同年に放送されていた『エヴァンゲリオン』が社会現象化していく中で、言ってみればまあ宮崎駿や富野由悠季、押井守といった戦後アニメーションの巨匠たちの問題意識を受け継いだ、言ってみれば現代文学的なアニメとして時代の象徴になっていったのに対して、この『ガンダムW』は女子中高生のやり場のない性欲のはけ口程度にしか思われていなかった。 でも、どうなんでしょう。少なくとも僕は今考えると圧倒的にこの『ガンダムW』のほうが『エヴァンゲリオン』より新しかったと思うんですね。 こうして振り返ると『エヴァンゲリオン』は正しく日本的なロボットアニメの文脈を引き継いでいるわけです。主人公のシンジ少年の、屈折した成長願望として巨大ロボットが設定されていて、そしてだからこそ成熟の仮構装置としてのロボットアニメがもはや成立しないことを告発して、しっかり破綻してみせることで時代の精神を代表する作品になっていったわけです。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…
・入会月以降の記事を読むことができるようになります。
・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
戦後史としてのロボットアニメと〈移体性〉――フランス人オタクと日本アニメ熱狂の謎に迫る 『水曜日のアニメが待ち遠しい』 著者 トリスタン・ブルネ インタビュー 前編(PLANETSアーカイブス)
2017-09-25 07:00550pt
今回のPLANETSアーカイブスは、日本史の研究者であり翻訳家でもあるトリスタン・ブルネさんのインタビューの再配信です。フランスにおける日本のサブカルチャー受容の過程をまとめた著書『水曜日のアニメが待ち遠しい』を下敷きに、オタク文化、特にロボットアニメのグローバルな視点から見た本質について語り合います。 (2015年12月4日に配信した記事の再配信です)
なぜ日本のアニメはフランスで受容されたのか
宇野:ブルネさんのご著書『水曜日のアニメが待ち遠しい:フランス人から見た日本サブカルチャーの魅力を解き明かす』を読ませていただきました。本当に素晴らしかったです。たいへん勉強になりました。
ブルネ:ありがとうございます。
▲トリスタン・ブルネ『水曜日のアニメが待ち遠しい』誠文堂新光社
宇野:フランスで日本のアニメやマンガがポピュラリティーを得ているというのは、日本国内でも有名な話です。ただその紹介のされ方は、「フランス人にもわざわざ日本のアニメを追いかけている変わった人がいる」という文脈で、面白おかしくデフォルメされている場合がほとんどだった。また、これは僕自身が日頃から感じていることですが、日本のアニメが海外で支持されている、という話を過剰に解釈して安易なナショナリズムに結びつけてしまう日本人のファンも少なくありません。その中でこの本は、その受容の実態を、フランス人個人の経験とアカデミックな視点の両面からまとまって紹介した、初めての例だと思います。
ブルネ:まさにそれが、この本で目指したことです。僕自身はこれまで計6年ほど日本に住んでいますが、1976年に生まれてから20代半ばまでは、日本アニメを浴びるように見て育った一人のフランス人オタクでした。それが2004年の初来日の際、たまたま日本の踏切の音を聴いて、初めて触れたはずのその音にノスタルジーを感じたことから、自分の人格形成における日本アニメの大きさに気づき、この問題を歴史的に考え始めたんです。ただ状況はフランスでも同じで、日本のアニメやマンガを深刻なイシューとして語ろうとしても、「単なる社会現象だ」と済まされてきた。今回の本の出発点は、「僕たちが生きてきた時代は何だったのか?」ということを、アカデミックな観点を含めて、個人の経験からわかりやすく追おうとしたことにあったんです。
宇野:ご自身が強く惹かれてきた日本アニメの奇妙な魅力と、その結果生まれた、フランスでのポピュラリティーの謎を解き明かしたい、と?
ブルネ:そうですね。「解き明かしたい」と同時に、そもそもそこにある巨大な「謎」の存在を多くの人に知ってほしい、という気持ちでした。誰もが当然のように「日本のアニメはフランスで人気がある」と言いますが、それ自体がすでにおかしな話でしょう。日本とフランスは、社会も文化のあり方も、基本的にはまったく異なる国ですから。
宇野:この本の面白さの最大のポイントは戦後の日本のアニメが結果的にですが、戦後の西側諸国が広く共有していた中流家庭、アッパーミドルのライフスタイルや価値観を表現するものになっていて、それが世界的なポピュラリティーの源泉になった、ということを指摘しているところだと思います。日本アニメのポピュラリティーを語ろうとするとき、アニメが好きな人も嫌いな人も、むしろ逆に日本の独自性に結びつけて考えがちですよね。つまり、アニメ肯定派は、日本の伝統的な価値観が現代の映像文化に引き継がれて開花した、と主張する。一方の否定派は、それをオリエンタリズムと批判する。どちらもグローバルな評価の根拠に、一種の日本性を見ていることは変わりません。が、ブルネさんの本は逆です。むしろ、戦後の先進国に薄く広く共有されていた、アッパーミドルの価値観に注目をされている。
ブルネ:おっしゃったように、日本でもフランスでも、すべての先進国は、戦後の20世紀後半に、それまでの価値観が大きく変わる経験をしました。高度経済成長で物質的に豊かになっただけでなく、人々の人間関係や、日常生活のあり方が変わったわけです。たとえば僕は、パリ郊外の新興住宅地の生まれですが、この「郊外生まれ」という経験も、戦後の先進国ではありふれたものになっていきました。しかし問題は、こうして厚みを増した中間階層の存在を、歴史の上で位置付ける視点がない、ということです。
意外かもしれないんですが、フランスは国家の力が強い国で、いまもエリートを頂点にした階層的な価値観がある社会です。そして国の物語である歴史も、「エリートと民衆の対立」という構図で記述されてきました。ところがこの構図には、支配層であるエリートとも、従来の民衆とも違う、戦後に増えた中間階層の位置がない。歴史から自身の正当性を与えられないことは、不安です。僕は、日本アニメの人気の背景には、こうした中間階層の不安や不満を解消したという点があると思っているんです。
宇野:ただ、ここで素朴な疑問として浮かぶのは、それがなぜアメリカのホームドラマやハリウッド映画ではなかったのか、ということです。これについてはいかがですか?
ブルネ:西ヨーロッパとアメリカは、いつもセットで「西洋」と呼ばれますよね。しかし、ヨーロッパの社会の基本的なユニットは「村」ですが、新大陸であるアメリカにはそれがない。ただ、荒野が広がっているだけです。人の経験の出発点となるものが違うので、フランスからアメリカに行くと違和感があるんですね。一方、一見かけ離れた日本には、フランスと同じような村のユニットがある。その意味で、じつは日本の方が、空間のあり方や、そこでの人々の営みの形態が近いんじゃないでしょうか。
宇野:ユーラシアとアメリカでは、根本的に地理感覚や空間感覚が異なるせいで、ハリウッド映画やアメリカのテレビドラマは、フランスの中産階級のカルチャーを表現するツールになり得なかった、と。
ブルネ:フランスも日本も、郊外の広がりによって何かが失われるという経験をしています。でもアメリカの郊外は、いわばゼロから作られたものでしょう。
宇野:郊外化もモータリゼーションも、日本やヨーロッパにとっては、トラディショナルなものの喪失だったけれど、アメリカにはその喪失感がないということですね。中流化や郊外化を言い換えると、アメリカ的なライフスタイルの受容でもあったと思います。もっとはっきり言うと、ヨーロッパではマーシャル・プランによって、日本ではGHQの占領政策の中で、既存のスタイルを上書きしながら進行したものだった。
ブルネ:実際、日本アニメでは、その喪失感がよく主題になりますよね。たとえば『となりのトトロ』も『平成狸合戦ぽんぽこ』も、埼玉の郊外や多摩ニュータウンで失われたものをテーマに扱っている。しかし同じ経験をしたはずのフランスには、なぜかこの種の物語があまりないんです。フランス人が求めるものがそこにはあったんですね。
宇野:僕は本州で生まれたのですが、10代の頃何年か、北海道に住んでいたんです。今の話で言うと、北海道はアメリカですね。100年前から人が住んでいなかったところがほとんどなので、一見、本州と同じような郊外都市が広がっていも、今おっしゃったような喪失感はありません。しかし本州は違う。中流化を支えた郊外都市はクリーンで明るい一方でどこか物悲しい喪失感が漂っている。国外に住んだことはないですが、北海道と本州の両方を住んだ経験から、その違いは非常に共感できます。
「偽の成熟」としての巨大ロボット
宇野:その一方で、アニメというのは風景を絵に置き換えるわけで、現実より一段、抽象性が高いですよね。そのことによっても、共感性は高まったと思うのですが?
ブルネ:抽象性も大事な要素ですよね。たとえば、フランスで初めて大人気になった日本アニメは、1978年に放送が開始された『UFOロボ グレンダイザー』でした。このグレンダイザーのような巨大ロボットも、抽象性の高いひとつのモチーフです。
宇野:そしてロボットは定義上、人工知能を持つもののはずですが、日本の巨大ロボットは、なぜか乗り物です。ここには直接何かにコミットするのではなく、間接的なコミットでありたい、という欲望があると思うんです。
ブルネ:そうですね。操縦者が必要です。
宇野:日本のロボットアニメはマーチャンダイジングと関係があって、小さい男の子の成長願望に訴えかける表現でした。非常に力強く、大きな身体への憧れでもあった。しかしその一方、どこかであれは偽物だ、という感覚があります。同様に、日本でもヨーロッパでも、アメリカのライフスタイルを取り入れて郊外に家を持ち、中流的な生活を築くことが憧れであると同時に、偽物でもあるという感覚があると思うんです。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…
・入会月以降の記事を読むことができるようになります。
・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
1 / 8