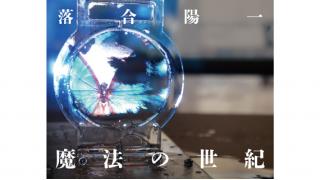-
【本日発売!】『魔法の世紀』まえがき【全文無料公開】 ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.460 ☆
2015-11-27 07:00【チャンネル会員の皆様へお知らせ】
PLANETSチャンネルを快適にお使いいただくための情報を、下記ページにて公開しています。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/ar848098
(1)メルマガを写真付きのレイアウトで読む方法について
(2)Gmail使用者の方へ、メルマガが届かない場合の対処法
(3)ニコ生放送のメール通知を停止する方法について
を解説していますので、新たに入会された方はぜひご覧ください。
【本日発売!】『魔法の世紀』まえがき / 全文無料公開
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.11.27 vol.460
http://wakusei2nd.com
本メルマガで配信されていた落合陽一さんの連載に、大幅な加筆と編集を加えた単行本『魔法の世紀』が、本日11/27に発売されます。画面によって人々が繋がる「映像の世 -
デジタルネイチャーの時代――落合陽一『魔法の世紀』第8回 ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.361 ☆
2015-07-08 07:00220pt※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
デジタルネイチャーの時代落合陽一『魔法の世紀』第8回
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.7.8 vol.361
http://wakusei2nd.com
本日は落合陽一さんの好評連載『魔法の世紀』の最終回、「デジタルネイチャーの時代」をお届けします。人があらゆる理を操る「魔法の世紀」が実現していくなかで、〈人間〉という存在はどうなっていくのか――これまでの連載を総括しつつ、大胆な未来予想を描き出します。
▼お知らせ
本日20:30から、PLANETSチャンネルで落合陽一さんの講義ニコ生「魔法使いの研究室」を放送します!
第3回めとなる今回の講義テーマは「場と場の相互作用」です。Twitterハッシュタグ「#ochyainico」で質問や感想も募集中。
第1回テーマ:光
第2回テーマ:映像と物質
第3回テーマ:場と場の相互作用(今夜生放送!)
※今回で『魔法の世紀』は最終回ですが、PLANETSでは今後も落合陽一さんの最新の研究動向を追いかけるべく、来月より連続ニコ生講義「魔法使いの研究室」の書き起こし連載をスタートします!そちらもお楽しみに。
落合陽一『魔法の世紀』これまでの連載はこちらのリンクから。
こんにちは、落合陽一です。
昨年の連載開始から長く続いてきました魔法の世紀ですが、今回が最終回になります。今まで、たくさんの方々に支えられてきた魔法の世紀の連載ですが、今一度、担当編集者の稲葉ほたてさんと、編集長の宇野常寛さん、そしてPLANETSの皆様に多大な感謝を――。
その一方で、嬉しいお知らせもあります。この連載の書籍化が決定しました。出版社は、このメルマガを運営するPLANETSで、会社としても最初の単行本になるそうです。
さて、前回までに僕は、コンピュータの世紀となる21世紀の美や、そこでの人間の価値観をどうアップデートするのかを語ってきました。その中で、表層・深層の話について、古典的な議論と現代の現象を対応づけながら、議論をしてきました。この最終回では、最後に僕自身が今後実現したいと考えている未来の話をしたいと思います。一体、僕がこれからどういうことをして、世界がどうなっていくのかを書いていきたいと思うのです。
1.コード化する自然:デジタルネイチャー
今年の春から、僕は筑波大学の図書館情報メディア研究科/情報メディア創成学類に自分の研究室を立ち上げました。
Digital Nature Group - 落合陽一 デジタルネイチャー研究室
この研究室を始めるときに、僕がラボの名前として選んだのが「デジタルネイチャー」という言葉でした。
これは僕が考える「魔法の世紀」の世界を象徴させた言葉です。魔法の世紀が21世紀の時代を表した言葉なら、デジタルネイチャーは21世紀の世界を表した言葉だと思ってください。
この連載でも書き続けてきたように、魔法の世紀はリアル/バーチャルの対比構造が、コンピュータによって踏み越えられて、作り変えられていく世界です。とすれば、そうして作り替えられた未来の世界をあらわす「固有名詞」が必要だと思いました。それが、このデジタルネイチャーなのです。ユビキタスコンピューティングという言葉がコンピュータがばら撒かれた世界のあり方だったなら、デジタルネイチャーとはそのコンピュータという存在自体も溶けてしまっているイメージです。
ただし、デジタルネイチャーという言葉を聞いて、サイバーパンクのようなSFチックな意匠で覆われた世界を想像するのは間違いです。まずは、そこについて、いくつか例を出しながら話していきたいと思います。
たとえばスイスのETHという大学で行われている研究を紹介しましょう。これは物体の重心についてのアルゴリズムを使って、3Dプリンターで出力される物体の重心を調整してしまう研究です。
Spin-It: Optimizing Moment of Inertia for Spinnable Objects
上の動画を見ていただければわかりますが、この3Dプリンタを用いると、様々なものがコマに変わってしまいます。もし、あらかじめ重心を調整をしていないマテリアルで、こういう結果を得ようとしたら、外力から重さの不均等を打ち消す程度に合力を調整する必要があります。
もう一つの事例は、僕です。
実は最近、僕はまだ日本で数千件しか例がないという、眼球内にコンタクトレンズを埋め込むインプラント手術を受けました。この手術に使ったコンタクトレンズは、僕の眼球に合わせて度数なども含めた形状の計算をコンピュータで精緻に行っています。
▲疲れた目をリフレッシュ! 遠近兼用 ピンホールメガネ
この視力にまつわる研究は、捉え方によってはデジタルファブリケーションとして行うことができます。ピンホールがメガネの役割を果たすという話を聞いたことがある人も多いと思いますが、例えば、ピンホールの分布を変えて入ってくる光の量をコントロールすることや、一人一人の目にあわせた位置に作ることなどができるでしょう。それをレーザーカッターを用いることで加工すれば、コンピュータ計算を用いてアナログに実装した、ピンホールメガネをつくることができるはずです。
こうした事例から分かるのは、現代のコンピュータというものが、かつての我々の想像を超えて現実世界を制御する力を持ち始めていることです。特に重要なのが、それが私たちが得る情報のあり方を大きく変えて、そのことによって世界像の認識を変えてしまう領域に達してきたことです。
例えば、インプラント手術によって、僕の視力は2.0を超えてしまい、目の前の風景は大きく変わりました。旅行に行けば、他の人には見えない看板の文字が読めるようになり、地平線の向こう側の風景も見えるようになりました。また、視力が2.0を超えたことで、新しい発見も生まれてきました。その発見の一つが、頭が上手く働いていないときには、視力が劇的に低下するというものです。不思議なことに、寝覚めが悪かったり、疲れた夜には視力が下がってしまうのです。どうやら人間の視覚機構は、光学的な情報を得るだけではなくて、それを脳内でパターン認識などを構成する過程まで含めたものであるらしい――こういうことが、体験として理解できてしまうのです。
一方で、重要なのは、こういうアナログな物理世界をデジタル的に制御する手法の「逆」もまた存在しているということです。
上の事例でいえば、コマは空間自体をアクチュエーションして、外力を合成すれば同じ結果を得ることが出来ます。視力については、MITが最近行った研究がそれに当たるでしょう。彼らは、ディスプレイから出る光を上手く調整してぼかして出力することで、ちょうど網膜上で焦点が結ばれることを示したのです。こうすれば、眼鏡なしにディスプレイを見ることが可能になります。
こういう研究から分かるのは、一つの問題を解くのに、ニつの手段があることです。
一つは、コンピュータ計算で作られたピンホールメガネのように「デジタル処理されたアナログな物質」です。もう一つは、ディスプレイそのものが視力に対応した形になるようにした「アナログな物質を変化させるデジタル計算機」です。とすれば、デジタルなアナログで行くか、アナログなデジタルで行くかなど、コスト計算のあとに来る選択の問題でしかありません。
このように、目の前にある世界をデジタルとアナログを行き来しながら問題解決していくのが、デジタルネイチャーの時代の特質だと思います。僕の考えるデジタルネイチャーとは、ユビキタスコンピューティングとプリンティングテクノロジーによって再構成された自然のことです。そこには、電化/非電化に関わらず、何らかの計算機の作用によって生じてきた万物が含まれています。
この背景には、この世界の構成要素である物質や、そこに作用する場などの性質が、コンピュータでかなり精緻にコントロール可能になったことがあります。つまり、デジタル/アナログにかかわらず、全てがコードによって記述されていく時代が来ているのです。
それは、あらゆるものが計算機的な性質を秘めていくような事態と言えるでしょう。人間もその例外ではありません。身体の構成要素である物質は、その構成や素材の水準から制御されていくでしょう。一方で、環境側からのアクチュエーションも盛んに行われていくはずです。
そのとき、この連載でずっと書いてきたようなメディア論も大きく変わります。モノと人間を分けて、「メディアとそれを受容する人間」という対比構造の図式で考えるような、「人間中心主義のメディア意識」は変化を迫られるはずです。なぜなら、人間とはデジタルネイチャーの世界では、せいぜいが計算機で処理されるアクチュエーターであり、認知的なロジックを持ったコンピュータに過ぎないからです。
たとえば、VRコンテンツのことを考えてみましょう。機械をつかったOculus Riftの体感コンテンツとして、様々なアトラクションが作られています。その一つとして、HPIの研究にHaptic Turkというものがあります。これは、人間をアクチュエータとして用いた良い例です。
▲Haptic Turk: a Motion Platform Based on People
音楽ゲームをする感覚で人間をシーケンサーでコントロールして、人をアクチュエータの代わりに使っているのがわかると思います.コンピュータを中心に捉えることで、逆に人間を比較的「安価なアクチュエータ」と考えることができてしまうのです。
2.人間中心主義のメディア意識
今、僕は「人間中心主義のメディア意識」という言葉を使いました。実際、これまでのコミュニケーションメディアは、人間中心主義で構成されていたと思います。
例えば、先日とあるシンポジウムの質問の際に、「あなたはデジタルとは言うが、実はアナログにはアナログの良さがないだろうか。例えば、レコードにはCDにはない暖かみがあると思う」という話をされました。それに対する僕の回答は、「いや、それは現在のCDの規格が、解像度を低めに設定しているだけです。現代の技術で本気で解像度の高いCDを作れば、レコードなんかより遥かに生身の演奏の情報が再現された再生装置が作れますよ」というものです。
CDに人間の生身の魅力が吹き込まれていないのは、デジタルの問題ではなくて、むしろコストを掛けずに大量生産をしたいという資本主義の問題です。
実際のところ、「映像の世紀」である20世紀に我々の周囲に生まれた複製装置は、どれも人間の感覚器の解像度を基準にして作られています。
例えば、アニメやゲームのビジュアル表現におけるコマ送りは、60fpsが基本となっています。これは、人間の目に区別がつかなくなるラインが、1秒に60回程度の書き換えだからです。この数字まで出していれば、充分に滑らかに動いているように見えるのです。また、音であれば、サンプリング周波数が高々40kHzあれば、人間の可聴域である20kHz程度の音まで再生可能です。
【ここから先はチャンネル会員限定!】PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は今月も厳選された記事を多数配信します! 配信記事一覧はこちらから↓
-
「テクネに魂を惹かれて」(落合陽一『魔法の世紀』第7回) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.345 ☆
2015-06-16 07:00220pt※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
「テクネに魂を惹かれて」(落合陽一『魔法の世紀』第7回)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.6.16 vol.345
http://wakusei2nd.com
本日はメディアアーティスト・落合陽一さんの好評連載『魔法の世紀』の最新回をお届けします。 GoogleやApple、ジャスコといったプラットフォーマーが生み出す「多様性」の内実とは? そして、パソコン革命が終わった「次の時代」のアート観とはなにかについて原理的に問い直していきます。
落合陽一『魔法の世紀』これまでの連載はこちらのリンクから。
お久しぶりです落合陽一です。6月も半ばになってきました。新緑の季節ですね。
僕の方は東京大学の博士課程を無事に飛び級で卒業、今月から筑波大で研究室を開きました。今はもう研究論文を書いたり、授業やゼミや月一の公開授業(「魔法使いの研究室 vol.1 テーマ:光」 「vol.2 テーマ:映像と物質」)を行う毎日です。
最近、僕は「人間性を捧げる生活をしているんだよね」とよく口にしています。ここでの「人間性を捧げる生活」とは、「健康で文化的な生活を諦める」という意味ですから、さしづめ僕は人権を研究に捧げているのでしょう。
そんな僕が今回書くのは、魔法の世紀の文化や芸術がどう人間性をアップデートしていけるのかという話です。と言っても、ここでの人間性は、もっと人類の価値観や暮らし、思想、人類に関わること全般を指しているので、ご安心ください。
そもそも有史以来、芸術や文化は、この人間性をどうやって更新するかを目標に存在してきました。そして現在、コンピュータテクノロジーは我々の文化に深く介入しています。ここで重要になるのが、プラットフォームという概念です。というのも、前回の連載で僕は、あらゆるコンテンツはジャスコに吸収されるということを書きましたが、ジャスコとは――コンピュータ文化でこそないものの――プラットフォームそのものだからです。
このジャスコ的なもの=プラットフォームというコンテンツ吸収装置の前で、どうやったら我々は文化的閉塞感を打開していくことができるのでしょうか。
1.Googleに見るジャスコの思想
前回(『魔法の世紀』第6回:早すぎた魔法使いと世界を変えた四人の弟子)、僕はあらゆる機能を包括する「都市」という存在の象徴として、ジャスコを論じました。
しかし、インターネットにおけるGoogleのようなプラットフォームの存在もまた都市におけるジャスコと同じような振る舞いをしているように思います。というのも、ジャスコは都市に生きる人々の導線を制御して、コンテンツへとデリバリーしていきますが、同様にグーグルもインターネット上のコンテンツにまつわる導線を制御して、あたかもネット上のあらゆるコンテンツを吸収しているかのように振る舞っているからです。
また、Googleのようなプラットフォームの凄いところは、「土台」を共通化することでコストの最小化を実現しながらも、ユーザーがその上で行う活動については最大限の多様性を保証してしまうことです。しかし、これもジャスコに似ています。モールの中にある服もレストランもスーパー銭湯も、どれも小さいコストで多くのニーズに応えられる場所です。
故に、いまやプラットフォームから得られるコンテンツは最適解に近くなっています。言わば、iPhoneやApple Watchを身につけて、OSやハードを共通化しながらもその上のアプリは多様化していくことで、体験の多様化が起きるというわけです。
しかし、ここで立ち止まって考えてみましょう。それは、本当に「多様化」なのでしょうか。
そもそも、ジャスコでみんながやっているのは、一体どんなことでしょうか。
結局はシネコンに行って、イオンモールでご飯を食べて帰るという以上のことはしていないようにも見えます。一見して多様化した体験とは言われながらも、その上に乗っている限りにおいては、プラットフォームに規定されたコンテンツ表現の域を出てはいないのです。僕たちは、ジャスコ的なもの、イオンモール的なもの、Google的なものに吸収されていくコンテンツ体験の中にとどまっています。
もちろん、だったら何が問題なのだ……というのもひとつの見解です。規定された枠の中で、その"お作法"を知った上で感動を生み出していく「文脈のゲーム」というのは、昔からある楽しみ方の一つです。
例えば、週刊少年ジャンプは昔からずっと、漫画の掲載順位を連載の人気順で決めて、王道の漫画をメディアミックスで提供しています。こういうポップカルチャーにおいては、ジャンプのような形での多様性は大事にされてきましたし、ニコニコ動画のようなCGMプラットフォームにおいても、運営が提供する仕組みによるコスト低下と価値観の最大化のもと、民主化された表現が多様に生まれています。
確かに、既に可能なことが判明したメディアの上で、こういう民主化された多様性を楽しみ合う表現も大事なものです。しかし、表現の定義を、ひいてはメディアの定義そのものを更新していくような運動もまた重要だと思います。今では特に珍しくもない油絵も、映写機の上でのシネマトグラフも、当時は最先端のメディアであり、各々の時代のアーティストたちがその文法を作り上げてきました。
そのことを我々が忘れてしまったのは、油絵や映画のようなメディアの寿命が長かったからです。
例えば、映画が分かりやすいでしょう。映画は元々トリックアートのような短編映像が作られていたジャンルでしたが、やがてストーリー的な表現手法が混ぜられていくようになっていきました。これは、映画がそのメディアそのものの更新ではなくて、コンテンツの文脈それ自体の更新で自らを定義するようになった歴史といえるでしょう。その果てに生まれたのが、映像表現によるメディアアートでした。
でも、ジャスコやGoogleが問いかけてくるのは、その先にある世界です。
なぜなら、もはやメディアの上に乗ったコンテンツは、全てプラットフォームの下位存在にしかならない時代だからです。どんなコンテンツも、プラットフォーム上の多様化でしかなく、その下にあるプラットフォームそのものの刷新には何も影響を及ぼせない。プラットフォームを越えようといくらあがいても、僕たちはプラットフォームの一部分にしかなれない――。
この連載で指摘してきたような、20世紀的な文脈主義のアート観に乗れば乗るほど、アーティストは単なるジャスコやグーグルの一プロバイダに落ちていくのです。しかし、文化とは果たしてそういうものなのでしょうか?
しかも、この連載でも書いてきたように、ニコニコ動画やYouTubeのようなプラットフォームが複数のコミュニティを生成するようになったことで、僕たちの周りにある「文脈」は飽和状態になりました。その結果、僕が関わってきたメディアアートのような、文脈を複雑に練り上げていくアートは見向きもされなくなりました。そして、本来はメディアそれ自体の刷新を目的にしていたメディアアートは、単なる狭いコミュニティの同業者同士の議論の場以上のものでは、なくなってしまったのでした。
2.パソコン革命の終わり
さて、このプラットフォームにあらゆるコンテンツが吸収されていく時代に、一つの回答を示してきた企業があります。それが、Apple社です。
Apple社の思想は、パーソナルコンピュータを開発してきた人々――アイバン・サザランドから、アラン・ケイ、そしてスティーブ・ジョブズへと連なっていくような、人間の能力を拡張する「エンパワーメント」の存在としてコンピュータを捉えていく系譜の中にあります。これは、人間を雑事から開放しようとコンピュータを使い、現在では人工知能へと接近しているグーグルとは異なる系譜の思想にあります。黎明期のコンピュータ史を見れば分かるように、思想として見たときにパソコンの思想と人工知能の思想は、実は似て非なるものです。
実際、スティーブ・ジョブズはAppleの目指すコンピュータを聞かれて、「人にとっての自転車のようなものを目指す、早く走れたり遠くに行けたりするための道具」と回答しています。人間の身体的特徴や知的能力、表現の自由をコンピュータでいかに拡張していくか――これこそが、パーソナルコンピュータの開発者たちの思想なのです。
そして、彼らのこの姿勢は連載で論じてきたような、コンテクストに依存しない、原理主義的な感動をハードウェアにおいて与えて、人間の新たな可能性を発見していく一つの事例になっているように思います。
ところが、アップルのCM映像を見れば分かりますが、彼らはこれを20世紀後半のヒューマニズムの文脈で捉えようとしています。その結果、そこに流れる映像はスピリチュアル系のようなものになっています。それは本当に豊かな精神性の獲得といえるのでしょうか?
いくらアップルが「お前らしくあれ」「Think different」と呼びかけても、結局はプラットフォームの上に乗せられたアプリで体験できることには限りがあります。Apple WatchもiPhoneも結局のところ、昔からある営みの中に収まる体験がほとんどなのが良い例です。それを彼らは、自身の出自であるカリフォルニアンイデオロギーから来たスピリチュアルな文脈によって正当化しようとしているようにも見えます。
しかし、それは彼らがモノのちからを信じきれなくなりつつあるから、とも言えはしないでしょうか。ハードウェアによる原理的な体験の更新を志向していたはずのAppleが、文脈主義的なブランド戦略に傾いてしまっている――そんなようにも思えるのです。
Macという素晴らしいデバイスを使うことは、本来は人間の個性を浮き彫りにして、根本的に人間性を拡張するはずでした。しかし、現状ではせいぜいリンゴマークのそばに貼られたシールの数という程度にしか、ユーザーの間には違いがありません。
実際、ジョブズの死後に出たApple Watchを僕は3章で好意的に取り上げましたが、あのデバイスが実際に出てきて明らかになったのは、むしろAppleがテクノロジーによる人間のエンパワーメントを諦めて、ブランド戦略に向かったということでした。
それは、Mac、iPhoneと、パーソナルコンピュータの革命を先導してきたApple社が告げた、革命の時代の終わりだったようにも思います。今や人々にGUIのユーザーインターフェイスは浸透して、開発のためのプラットフォームも行き渡りました。その時代に、Apple Watch程度のハードウェアの革新では、人間性のアップデートにつながるほどのインパクトは持てなかったのだと思います。
とすれば、この「Apple以後」の世界において、僕たちアーティストはどうやって自らを刷新していけばいいのでしょうか?
僕はここで再びデジタルカルチャーの大元に戻りたいと思うのです。それは、マウスの発明者であり、ハイパーテキストなどの生みの親であるダグラス・エンゲルバートです。彼は、マウスの発明について聞かれたときに、以下のように答えました。
Mouse was a tiny step of larger project aimed at augmenting human intellect.
――マウスは人間の知性を拡張するためのもっと大きなプロジェクトにおける小さな一歩にすぎなかった。
彼にとって、マウスは単なる操作しやすいユーザーインターフェースの発明ではなかったのです。彼は、人間の知性をコンピュータでいかに拡張していくかという発想から、それを生み出しました。コンピュータは、他の自動車や自転車や冷蔵庫のような装置や単なる道具ではない――そういう確信が、エンゲルバートにはあったのです。
【ここから先はPLANETSチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は6月も厳選された記事を多数配信予定!
配信記事一覧は下記リンクから。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201506
-
【GW特別再配信!】現代の魔術師・落合陽一連載『魔法の世紀』 第2回「グーテンベルクの銀河系からアリスが歩いた世界へ」☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 号外☆
2015-05-06 16:00220pt
現代の魔術師・落合陽一連載『魔法の世紀』
第2回「グーテンベルクの銀河系からアリスが歩いた世界へ」
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.5.6 号外
http://wakusei2nd.com
この春に東京大学大学院で博士号を取得、さらには20代にして筑波大学の助教にも就任し、ますます注目が高まっている「現代の魔術師」ことメディアアーティストの落合陽一さん。このたびPLANETSチャンネルでは、落合さんの最新の研究・関心事を追いかけるべく、連続講義ニコ生「魔法使いの研究室」をスタートしました!
(初回の放送はこちら ※PLANETSチャンネル会員+ニコニコプレミアム会員の方は、5月8日 23:59までタイムシフトでご覧いただけます)
本ニコ生講義が大好評につき、このGWでは過去にPLANETSチャンネルで配信した落合さんの書き下ろし連載「魔法の世紀」の初回と第2回を再配信していきます。
第2回の今回は、アラン・ケイに始まるメディア装置としてのコンピュータの「その先」、そして21世紀の「魔法」が呼び起こす美的感動とはなにかについて解説していきます。(2014.8.20公開の記事を再配信)
落合陽一『魔法の世紀』これまでに配信した記事一覧はこちらから。
こんにちは、落合陽一です。僕は相も変わらず、深夜の研究室で執筆をしています。
いきなりですが、僕はよくカップ麺を食べます。それはお金や時間がないからで、仕方なく毎日自販機で買っているのだと思っていたのですが、どうも最近、自分はそうやって言い訳しているだけで、実はカップ麺そのものが大好きなのだと気づきました。
というのも、カップ麺はある種のメディア装置だからです。
メディアとコンテンツの関係に対応させるならば、カップ麺のカップはメディア、コンテンツは麺とお湯。しかも、カップに入った麺は世に広く普及したメディア装置ですが、お湯を注いで調理するという点では、とてもインタラクティブです。
そもそも食べるという行為の中で、カップ麺と僕の間にはいろいろな関係性を考えることが出来るわけなのですが、僕にとってのカップ麺の「インタラクティブ性」は、お湯の量で麺が様々な食感に変化することです。ちなみに僕が好きなのは、日清のカップヌードルを麺ぎりぎりのライン程度にお湯を注ぎ、濃いスープでふやけた麺を絡ませながら食べることです。ふやけるタイミングも含めて、演劇や映画のようなひとつの時間芸術なのだと思っています。
食べながら、「これは実に興味深いな」と思います。食事のささやかな楽しみです。
さて、前回から始まったこの連載ですが、今回からは具体的な話に入ります。まずは、僕の作品や、他の方の作品を紹介しながら、コンピュータやメディアアートについて書くことから始めようと思います。
■メディア装置は電気羊の夢を見るか?:芸術表現としてのメディア装置、メディアアート
最近、メディアアートという言葉をよく聞くようになってきたのではないでしょうか。たとえば、テレビやネットで「プロジェクションマッピング」が特集されたり、3Dプリンターや電子工作で作ったインタラクティブ作品の呼び名としてメディアアートが使われたり、その用法も様々、捉え方も様々です。
もちろん様々な使い方をされるだけあって、このメディアアートの定義はなかなかに難しいです。一般には現代芸術の一派で「メディアに対して意識的であり、コンピュータや情報技術、電子、電気機器を用いた芸術」などと言われていて、僕もこの定義で考えています。
前回、映像から魔法への転換ポイントとして、「非メディアコンシャス」「物象化」「虚構の消失」という三つのポイントを挙げましたが、おそらく最もわかりにくかったのは「非メディアコンシャス」という言葉だったのではないでしょうか。つまり、メディア装置への意識そのものを芸術表現にしたのがメディアアートです。実際、先の定義の中にも「メディアに対して意識的」とありますが、これがまさに「メディアコンシャス」です。一般に馴染みのない概念をつかって定義されている芸術なので、使い方も捉え方も様々なのはある意味で仕方のないことかなと思います。
現在に至るまで、人類は様々なメディア(媒体)を用いて表現を行ってきました。
油絵ならば、絵の具とカンバスです。この場合、描かれた絵がコンテンツで、メディアがカンバスと絵の具です。本ならば、中の文章がコンテンツで、本がメディアです。つまり、表現をするための媒体がメディアで、表現自体がコンテンツだと思えばいいでしょう。カップ麺ならば、カップがメディアで、麺がコンテンツです……あ、これはしつこいか。
そして重要なのは、実は近代まで芸術家は「メディア上でのみ表現を行ってきた」ことです。それに対して20世紀半ばに誕生したメディアアートが重要なのは「メディアコンシャス」であり、メディア装置を対象とした芸術であること――つまり、「メディアそのもの」を創る試みを芸術表現としたことなのです。そのとき、「メディアとは何か」「何がメディアとなるのか」というメディアアートの問いは、メディアコンシャスそのものになります。
ちなみに、このメディアアートの誕生は、映像表現と切っても切れない関係があります。例えば、ビデオアートの大成者であり「メディアアートの父」と呼ばれる、ナム・ジュン・パイクの作品はわかりやすいでしょう。彼は、映像装置、カメラ、インタラクティブなど現代のあらゆるメディア装置の特徴を備えた作品を残しています。Electronic Superhighway : Nam June Paik / ナム・ジュン・パイク 作品まとめ - NAVER まとめhttp://matome.naver.jp/odai/2135339177356767701/2135412062838268603
映像装置を積み上げた彼の作品たちは、常にメディアと人との関わりを私たちに意識させるものばかりでした。こうしたメディア装置についての思考を意識させる芸術が、まさに古典的なメディアアートでしょう。
僕自身も作品をいくつか作っています。例えば、『Looking-glass timeアリスの時間』という作品では、映像メディアそのものを批評するために装置を作りました。そこには、「もし記録メディアがこの世界に存在しなかったら、どうやって映像を作り出すのだろう?」という問い、あるいは、「いま世界でリアルに加えて、メディア上で同時多発的に流れている複数の時間軸」などに思いを寄せて、作品装置をくみ上げました。これは映像装置への古典回帰でもあります。
https://www.youtube.com/watch?v=c3orYwyuRz4
(Looking-glass time)
実物投影機の方式で、実物の時計からレンズで変換される光学像のみを用いてアニメーションを作っています。つまり、「フィルムを使わない」アニメーション装置です。
また、『Human Breadboard』という作品では、この世界にあるコンピュータと人間、有機物、生命をマクロ的に支配する構造を写し取りました。
https://www.youtube.com/watch?v=7gmJGH54lIo
(Human Breadboard)
1Hzで動くたくさんのコンピュータを相互通信させ、そこに生物的な部品(生の植物、昆虫など)を繋げ、人間をクロックに動作させています。
他にも、映像や写真では少々わかりにくいのですが、『モナドロジー』という作品もあります。ここでは、不思議な三次元的なアニメーションを作り出しました。物体の存在消失、三次元的な動きを実際に用いて実体のアニメーションを作ると、まるで自分が宇宙に浮いているような不思議な感覚がします。
https://www.youtube.com/watch?v=WRnLJsyeQCU
(Monadology)
シャボン玉を消失・出現するメディア装置として捉えて、真っ暗な部屋で非常に弱い点光源のストロボを人間の暗順応に対応させ調節して制作しました。
しかし、これまで非常にたくさんのメディアアートを作ってきた僕ですが、ここ半年ほどは作品を一つも作っていません。なぜだかメディア装置の研究ばかりしています。それは、あることに気づいたのが理由です。どうやら、メディア装置の制作による表現という試みと、メディア装置の研究を行うことは、非常によく似た特徴を持っているのです。というのも、現代における「メディア・アート」の意味の拡大には、どうやらメディアアートとコンピュータ研究の間にある奇妙な相関関係が関わっている気がするからです。
■グーテンベルクの銀河系、星降る前夜――メディア装置としてのコンピュータ
その説明をするために、ここからは少し遠回りをしてコンピュータとは何かを考える旅に出ましょう。今や、この地上に星の数ほどあるコンピュータの在り方を探る旅です。
実は現在、我々が能動的に使うコンピュータは、デスクトップやラップトップなどの「メディア装置としてのコンピュータ」です。例えば仕事ではデスクトップ型、家ではラップトップ型、ちょっとした用事はタブレットで済まし、電車の中ではスマホ……そんな使い方をする人は多いはずです。コンピュータを使って仕事の書類を作ったり、ウェブにアクセスして情報のやり取りをしたり、映画を見たり、誰かにメッセージを送ったり、はたまた生中継に至るまで、さまざまなメディア装置としての使い方があって、みなさんも思い思いに使っているのではないでしょうか。
もちろん、それ以外にも、コンピュータはディスプレイのついたものには限らないわけで、改札やエアコンなどの家電に至るまで、僕たちの身の回りには溢れているのですが、今の世の中が興味津々なのもやはり「メディア装置としてのコンピュータ」なのです。なぜなら、やはりそれこそがエンドユーザーの市場に最も購買されてきたのですし、そこではそのメディア装置としての特徴が駆使されることで「お金稼ぎ」が出来ていたからです。
そんな中、2010年代も半ばを迎えた現在、「スマホの次は何が来るのか?」という記事があちらこちらで話題になり、次の担い手としてグラスウェアや腕時計型のデバイスに注目が集まり、「これからはウェアラブルの時代が来る」なんて言われているわけです。しかし、そのようにしてコンピュータと人が関わるような文脈はどこから創られたのでしょうか。その辺の言葉の歴史や文脈の整理から始めましょう。
さて、前回の連載で、僕はマークワイザーのユビキタスコンピューティングについて触れましたが、消費者サイドで我々の生活とコンピュータを見たときに、二つの欠かせない出来事があります。一つは、ゼロックス・パロアルト研究所での1973年のAltoの発明(暫定DynaBook)、もう一つは1984年のマッキントッシュの発売です。
マッキントッシュとスティーブ・ジョブズについてはもう語るまでもないでしょうから、ここではパーソナルコンピューティングを経て、コンピュータがメディア化していく中で、そのバックグラウンドで大きな影響力を持っていた、二人の「偉人」の話から始めることにします。それは、アラン・ケイとジェフ・ラスキンです。
アラン・ケイは、最初のオブジェクト指向言語「Small Talk」(今でも広く使われるようなプログラミング言語の原型スタイル)と現代型のGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)を持つ最初のコンピュータ「Alto」の生みの親で、DynaBook構想を作り出したコンピュータ史における偉人の一人です。巷では、「未来を予測する最善の方法はそれを発明することだ」という言葉が有名です。
彼のDynaBook構想とは、ひと言で言えば「未来の本(Book)に代わるようなコンピュータを作ろう」という思想でした。ちなみに、彼はDynaBookの構想時にマクルーハンの『グーテンベルクの銀河系』を読み込んだというのは有名な話です。彼の考えたDynaBookとは、以下の様なものでした。
・安価で低電力動作する持ち運び可能なコンピュータ
・マルチメディア(音声・画)が扱える。
・ディスプレイと直感的なユーザーインターフェースを持ち、子どもが紙とペンの代わりに使える
・コンピュータのOS自体が簡単なプログラムで動いていて、エンドユーザーが簡単にプログラミングできる
この思想は1972年の著作『Personal Computer For Children of All ages』の中に書かれたものですが、今から40年以上も前に書かれたとは思えない先見性があります。現在でいうところのタブレットやスマートフォンに近い思想であり、子どもがiPadやiPhoneで遊んでいる光景をみると、着実にそのときは迫っているなと感じるほどです(ただし、最後のプログラミングについての条件が満たされたOSはまだ存在しません。iOSやAndroidは自身をプログラミングしたり、そのソフトウェアの構造が一瞬で見て取れるようなものではないからです)。
そんな彼がXeroxのパロアルト研究所で、そのDynaBook思想を体現する「暫定DynaBook」として開発したのが、現代型のGUIを搭載したデスクトップ型コンピュータのAltoでした。
その時代に、今のiPadのようなコンピュータを想定してモノを作るのがいかに大変なことか――僕には想像もできないです。何しろ、それまでのコンピュータはそもそもマルチウインドウやマウスカーソルなどを備えておらず、コマンドラインインターフェース(よく映画などで、ハッカーが文字だけの画面で打ってますね。あれです)で動かすのが常だったのです。それが、Altoは今見てもなお現代型のデスクトップコンピュータと大枠では差がありません。また、DynaBook構想の元となった1972年の文献には、子どもが板状のディスプレイとキーボードを備えたコンピュータで遊ぶスケッチが描かれており、まさに今の世界を予見しているとさえ思えます。
彼はそのようにして、その先験的なビジョン、実装としてのGUIとオブジェクト思考言語によって、コンピュータの歴史を大きく進めたのです。そして、これを見て影響を受けたスティーブ・ジョブズがAppleで作ったのが、マッキントッシュなのです。
ここからは、近年よくある「スマホの次」を論じるような話に見られる、一つの勘違いがわかります。パーソナルコンピューティングは1984年のマッキントッシュ発売で民主化して、21世紀にスマホに進化したわけではありません。むしろ、スマホを含むパーソナルコンピューティングに関わるメディア装置の形は、1972年にDynaBook構想の形で定義されており、以来基本的には変わっていないのです。
その後、コンピュータカルチャーは2010年代に至るまで、子どもであろうとも誰もが簡単に使えるマルチメディア端末――最終到達点としてのDynaBookを追いかけ続けています。Alto以後、コンピュータはメディア装置としての進歩を続け、パーソナルコンピューティングの時代(パソコン)、Webバブル(ネットワークパソコン)を超えて、今のようなモバイル/ユビキタスの時代(スマホ)になりました。
しかし、私たちの思想的なバックグラウンドは、いまだ一人の偉人が定義した道順をなぞり続けているに過ぎないのです。我々はグーテンベルクの銀河系の中で、ケイの奏でる音楽でダンスをし続けているようなものです。
そしてまた、コンピュータが広くメディア装置になったのが、1973年のこのときと言えるでしょう。
今ではもう当たり前のようにコンピュータはメディア装置として機能していますが、コンピュータがメディアになったのは、実はあらかじめ決まっていた未来ではないと僕は思います。
そもそも最初、コンピュータは戦争用の計算機として、非常に時間のかかる弾道計算をすぐに処理するために生まれました。別に、いつでもどこでもマルチメディアを使うために進歩して来たのは必然ではなく、またエンドユーザーが使うために生まれたものでもないのです。実際、現在も電卓や炊飯器には、そんなディスプレイやカメラ入力のような機能はありません。マクルーハンが『グーテンベルクの銀河系』で語ったメディア論とコンピュータコンテクストが交わるようになったのは、このようにコンピュータがメディア装置としての可能性を明らかにして、そして、その方向へ発展してきたからに過ぎないのです。
ただし、ここで一つ忘れてはいけないのは、コンピュータにはメディアというよりも家電製品に近いような、「道具的側面」もあることです。「紙とペン」だけではなく、生活に役立つ道具としての側面も確かにあるのです。
ここで重要なのが、ジェフ・ラスキンという「ヒューマンインターフェース」の大家です。彼はそもそも1984年のマッキントッシュの開発に関わったことで非常に有名なのですが、その思想の一つに「モーフィングコンピュータ」があります。
それは、ひと言で言えば「コンピュータが機能に応じてその姿を変えて、違う道具になる」という思想です。これは、つまりは形が自由に変わるドラえもんの道具のようなものです。例えば、あるときはハサミになり、あるときはペンになり、あるときは栓抜きになるような道具をイメージしてください。十徳ナイフのような感じですが、そのコンピュータ版だと思って頂ければわかりやすいでしょう。コンピュータの機能は単機能で提供されるが、用途に合わせてその都度インターフェースは変化していくという発想なのです。
もちろん、現状では自由に姿を変化させられるのはディスプレイの中の映像でしかないのですが、皆さんもお気づきのように、これは今のスマートフォンのインターフェースそのものになっています。
つまり、「DynaBook的なマルチメディア装置+2次元モーフィングコンピュータ」の暫定的な実装こそが、現在のスマートフォンやタブレットなのです。しかし、それは1984年にマッキントッシュの登場でパーソナルコンピュータが民主化される以前に、その思想的なバックグラウンドは完成されています。この30年、コンピュータはそれを追いかけて進歩してきたのです。
そこから分かるのは、「パソコンからスマホ」と「スマホからその次」の間には、ものすごく大きな隔たりがあることです。スマホまでは予想された未来でした。しかし、その後はどうなっていくのでしょうか?
-
【GW特別再配信!】現代の魔術師・落合陽一連載『魔法の世紀』 第1回「映像の世紀から、魔法の世紀へ」 ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 号外 ☆
2015-05-05 16:00220pt
メディアアーティスト・落合陽一連載『魔法の世紀』 第1回「映像の世紀から、魔法の世紀へ」
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.5.5 号外
http://wakusei2nd.com
この春に東京大学大学院で博士号を取得、さらには20代にして筑波大学の助教にも就任し、ますます注目が高まっている「現代の魔術師」ことメディアアーティストの落合陽一さん。このたびPLANETSチャンネルでは、落合さんの最新の研究・関心事を追いかけるべく、連続講義ニコ生「魔法使いの研究室」をスタートしました!
(初回の放送はこちら ※PLANETSチャンネル会員+ニコニコプレミアム会員の方は、5月8日 23:59までタイムシフトでご覧いただけます)
本ニコ生講義が大好評につき、このGWでは過去にPLANETSチャンネルで配信した落合さんの書き下ろし連載「魔法の世紀」の初回と第2回を再配信していきます。初回は、テクノロジーでもアートでもない「魔法」の時代とはなにか?を解説しています。(2014.7.17公開の記事を再配信)
落合陽一『魔法の世紀』これまでに配信した記事一覧はこちらから。
■ 前書き――技術でも芸術でもなく
おはようございます、落合陽一です。
僕はコンピュータ研究者とメディア芸術家の、二足のわらじを履いて生きています。人とコンピュータとの関わりをどうやって変えていくかを日々研究しながらも、かたや文化の面からもどのような表現が可能になっていくかを日夜探求しています。コンピュータという知的装置の前で人間はどう関わるのか、そして、それを取り入れてどう生きるべきなのかを、モノを作りながら考え続けて今の年齢になりました。
宇野さんから連載のお話をもらったとき、連載のテーマについてすごく悩みました。コンピュータやテクノロジーの話なのか、これからの文化の話なのか、それとも僕自身の興味ある未来世界のシナリオなのか――。
それは、僕という人間が語るための基軸はどこにあるのかという問題についての悩みでもありました。単に自分の関わるプロジェクトを説明するだけなら、その文脈はいくつも持ち合わせているので困りません。しかし、自分自身について語るときには、やや困難があります。なぜなら僕は、コンピュータ技術と芸術の間で生きている人間で、自分のやっていることを人に説明するとき、自分のモチベーションや意義を、技術と芸術を俯瞰するある種のモノ作りの思想のようなメタの視点から語らないと、なかなか他人に理解されないし、伝わらないからです。
だから、僕の視点から見える世界を語るには、アートでもテクノロジーでもない何か象徴的な言葉が必要だなと常々思っていました。それも、二つの領域を行き来するようなものではなく、そのどちらとも異質で俯瞰的な言葉です。技術でも芸術でもない言葉であり、しかもある種包括的で、世代のキーワードになるような言葉でなくてはならない。そう考えたとき、宇野さんとの対談で出て来た、「魔法の世紀」という言葉が一番しっくりくることに気がついたのでした。
【参考】YouTube270万再生の"空中浮遊"動画で話題――アーティスト落合陽一氏にインタビューしてみた ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.013 ☆
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/ar463252
20世紀は「映像の世紀」でした。文化の面でも、社会の面でも、テクノロジーの面でも、そうです。
映像技術は、20世紀初頭にアニメーションテクノロジーを発端として生まれました。芸術と技術の両面で世界を変えてきた「映像文化」は、アートとテクノロジーこそが文化を織りなすという観点では、まさにその典型です。その発展は、まさにいくつもの領域にまたがり、映画産業を作り出し、テレビジョンはマスメディアの概念を拡大させ、コンピュータ領域も取り込み、映像をインタラクティブ技術に変えました。
そして、フィルム技術、映写技術、通信技術という分野横断的なテクノロジーの進歩と、それに伴う様々な作家の表現。映像技術は時代のコンテクストとともに発展していったのです。
『映像の世紀』という同名のNHKのドキュメンタリーもありましたが、そんな20世紀を振り返るのに「映像」というキーワードは欠かせません。つまり、映像は一つのパラダイムだったのです。そこには、時間と空間、人間同士のコミュニケーション、イメージの伝達ツール、インタラクティブなコンピュータ、虚構と現実などの多くのコンテクストが内包されています。
しかし、それに対して、僕はここで「映像の世紀から魔法の世紀へ」という変革点を語りたいと思っています。僕にとって「魔法」とは、そんな20世紀に映像が持ったようなコンテクストを内包するような、次なる21世紀のパラダイムを表現した言葉なのです。
■「魔法の世紀」
『充分に発達した科学技術は、魔法と見分けが付かない』――「映像の世紀」まっただ中の1973年に、SF作家アーサー・C・クラークは、こんな有名な言葉を残しています。魔法とテクノロジーについて考えたときに皆さんが最初に思い浮かべるのは、この言葉ではないでしょうか。
研究者やエンジニアなど、科学やテクノロジー好きの人間は、この世界に文字通りの「魔法」なんて実現しないと端から信じているので、魔法をあり得ないものとして捉えています。だから、彼らはこの表現に巧妙さを見いだすのだと思います。しかし、この言葉には、有り得ないほどの超技術は文字通りの魔法になりえるのではないかという希望を見いだすことも出来るのです。
実際、アーサー・C・クラークは、20世紀の映画を代表するS.キューブリックの名作『2001年宇宙の旅』の原作者として有名ですが、あの虚構に我々が垣間みた表現は、おそらく21世紀にはこの現実世界でも実現するようになるでしょう。映像で語られるような宇宙の旅の世界を、この地球上に実現するのはやや難しいですが、物体浮遊に関しては研究が進んでいますし、実は僕もそこに関わる一人です。また、政府主導や民間主導での宇宙の開発も進んでいます。
つまり、クラークが描いた「魔法と区別がつかない超技術」の実現は、既に始まっているのです。
ここで重要なのは、なぜそのような技術が実現したのかです。それを可能にしたものこそが、前世紀に戦争の道具として発明され、人類の知的生産からコミュニケーション、映像の中に魔法のような表現などあらゆる場所に革命を実現した「魔法の箱」――コンピュータです。
これらの「超技術」を押し進めるテクノロジー文脈の一つは、間違いなくコンピュータの発展によるデジタルカルチャーです。現在、かつてSFを見て育った子ども達が、このデジタルカルチャーを引っ下げて、コンピュータというツールを多かれ少なかれ巧妙に使い、まさにSFをこの世界に実現しようとしているのです。そう、「魔法の世紀」において、その魔法の素(マナ)となるのは、まさしくコンピュータだと思います。
この連載の目的は、そんなコンピュータとその周囲の文化が織りなすデジタルカルチャーの文脈とその基本的な原理から、コンピュータの特徴を「魔法の世紀」として捉え直すことで見えてくるものについて書いていくことです。
それは、魔法をキーワードにして、デジタルカルチャーを主体に置いたテクノロジーの文脈、メディアアートやインタラクティブアートなどの表現活動、SNSやUGCを始めとしたインターネット文化などが向かう先を理解するために、前世紀的な「映像文化」との対比で読み解いていくということでもあります。
■「魔法」とはなにか
しかし、魔法という言葉に聞き慣れなさを持たれる方もいらっしゃるかもしれません。実際、魔法という言葉は、どの辞書をたどってみても定義がなかなかに一致をみません。強いていえば「常人には不可能な手法や結果を実現する力のこと」と言ったところであると思います。
では、僕たちが考える魔法のイメージはどこから来ているのでしょうか。
例えば、「ハリーポッター」シリーズを思い浮かべてみてください。あの物語において、魔法使いたちは、ホグワーツで修練した魔法技術を用いて、この世界に奇跡を起こす存在として描かれます。
そこでの魔法の描かれ方で僕が注目したいポイントは、魔法のイメージというものが、魔法によって具現化する実際に体感可能な現象として、ストーリーの中で描かれるところです。そして、その魔法の機序原理についてはあまり多くは語られず、そしてそれ自体は別の現実を描いたファンタジー作品ではあれども、その作品内では世界が完結していることです。これらの特徴は、他のファンタジー作品でも同じではないでしょうか。 以下に、それを定式化します。
1.「現実性」:魔法使いの使う魔法は物理世界(現実)に影響をもたらす
2.「非メディアコンシャス」:完全な動作機序(メディア)は明らかではないが使える。
3.「虚構の消失」:魔法ファンタジーの中にもう一つのファンタジーは存在しない。
もちろん、この連載が目的とするのは、そのようなファンタジーの中で魔法使いが駆使するようなものを語ることではありません。しかし、僕はテクノロジーがまるで魔法のように生活の隅々にまで行き渡った現代と、ファンタジーの魔法のそれには多数の共通点があると考えています。
ここからは、そのことを上記3つの定式化に即して、説明していきます。前章で指摘したのがまさに「現実性」に当たりますから、ここからは「非メディアコンシャス」と「虚構の消失」を説明していきましょう。
■ 非メディアコンシャス――「何が充分なら魔法になり得るのか?」
再び、先に挙げたアーサー・C・クラークの言葉に戻りましょう。充分に発達した科学技術は魔法と見分けがつかない(Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic)という言葉には、”sufficiently advanced(充分に発達した)”という表現があります。
一体、何が十分に発達したもので、何が魔法を作るのでしょうか。それは、そこにある科学技術を人が意識しなくなったときです。テクノロジーに関する理屈は理解できても、高度に細分化され発達したテクノロジーが、そこにある技術についてユーザーが気に留めないほど高度に振る舞い、そこに技術があることを秘匿すれば、それは実質的に魔法となるわけです。
テクノロジー自体の存在を意識しないほどテクノロジーが発達する。そして、テクノロジー自体は超常的な何かとして意識されなくなる――そのようなビジョンとして、例えば1993年に、Xeroxパロアルト研究所のマークワイザー博士が「21世紀のコンピュータ(The Computer for the 21st century)」の中で提唱した、ユビキタスコンピューティングがあります。
「ユビキタスコンピュータ(世界にあまねく存在するコンピュータ)」は、まさしくそのような概念です。いつでもどこでも互いに接続されたコンピュータが、人間をサポートすることで、人間はテクノロジーを意識しなくなるというビジョンです。
マーク・ワイザー博士の意に反して、この概念は「いつでもどこでも」が強調され、モバイル通信が盛んに行われる社会のことだと曲解されてしまっているように見えます。みなさんもユビキタスコンピューティングと聞くと、コンピュータの見えない世界というよりは、むしろコンピュータに対して意識的な、スマホなどのモバイル端末がたくさんある世界を想像するのではないでしょうか? それは、当初のマーク・ワイザー博士の意と正反対の世界です。
空気みたいな、植物みたいな、そんなアンビエントなコンピュータを実現する。そうすればコンピュータの存在を意識することはなくなります。ハードウェア的にはまだ遠い世界かもしれません。しかし、我々の意識レベルではそれは遠い未来の話ではないと思います。それどころか、今ここで僕らの中で静かに進行中のことだと考えています。
例えば、Twitterを「喫煙所みたいなもの」と表現したり、ネット回線がない場所で「息がしづらい」と言ってみたりしことはありませんでしょうか?
SNSにどっぷりはまったような人たちにとっては、そのメディアそれ自身は、普段からは意識されない状態になっているので、逆にネットから切断されたときに急にその存在を意識するようになるのです。
僕は、これは既に空気みたいなメディアが実現されつつあるのではないかと思っています。
【ここから先はPLANETSチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は5月も厳選された記事を多数配信予定!
配信記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201505
-
早すぎた魔法使いと世界を変えた四人の弟子(落合陽一『魔法の世紀』第6回) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.310 ☆
2015-04-23 07:00220pt※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
早すぎた魔法使いと世界を変えた四人の弟子(落合陽一『魔法の世紀』第6回)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.4.23 vol.310
http://wakusei2nd.com
今回は、メディアアーティスト・落合陽一さんの好評連載『魔法の世紀』の最新回をお届けします。
なぜ今、現実世界にコンピューティングが物象化していく状況(=魔法の世紀)が訪れたのか? CADやヘッドマウントディスプレイの原型となるテクノロジーを開発した科学者アイバン・サザランドと、その弟子たちの系譜から紐解いていきます。
落合陽一『魔法の世紀』これまでの連載はこちらのリンクから。
「魔法が世界に満ちるまで」
お久しぶりです、落合陽一です。最近、無事に博士になりました。先月まで博士論文を書いていてしばらく時間が取れなかったので、久々の執筆になりました。博論は計算機を用いた場の制御に関するもので、魔法の世紀で連載してきた話の「理系バージョン」みたいなものです。無事に博士号をいただきました。
今回は時間が開いてしまったので、ひとまず仕切り直しというわけで、おさらいの会にします。前回までは、映像の世紀から魔法の世紀に変遷するにあったっての美の変化やアート価値、静から動への変化、テクノロジーやデザインということについて語ってきました。
それに対して、今回はなぜこの世界にコンピューティングが物象化しているのか、という時代性の問題を見直してみようと思います。そのために、以前紹介したコンピュータ科学者・アイバン・サザランドの論文やその弟子への系譜を見ていくことで、サザランドが語った魔法的な価値観がどう引き継がれ、どう世界に溶け込んでいったのかを考えてみようと思います。
「ヴァーチャルリアリティの息吹」
アイバン・サザランドはマサチューセッツ工科大学(MIT)を卒業しています。彼の博士指導教官はクロード・シャノンです。
シャノンとは、標本化定理や暗号理論、情報理論、デジタル回路の研究などで世界一有名な情報学者です。彼が修士号取得時に著した「継電器及び開閉回路の記号的解析」は「20世紀に最も重要で有名な修士論文」と評されるほどのもので、電気回路のスイッチングを論理式に対応づけることで、現代のデジタル回路を成す「デジタル論理回路」の基礎を作ったものです。
では、そんなクロード・シャノンの弟子であるアイバン・サザランドはどんな人物だったのでしょうか。
シャノンがコンピュータの数学的記述法や通信・暗号の基礎を作ったなら、さしづめサザランドは人間とコンピュータが関わる対話的基礎を築いていった人物だと言えるでしょう。
アイバン・サザランドの初期の業績において重要なものは、コンピュータグラフィクス分野の開拓とヴァーチャルリアリティ分野の開拓です。まず、彼がコンピュータフラフィクス分野を生み出したのは1963年のことです。まだメインフレームが当時のコンピューティングの中心だった頃、アイバン・サザランドは世界初のインタラクティブコンピュータグラフィクスシステムであるSketchPadを、MITのメインフレーム(TX-2)の上で実装し、1963年に博士号を授与されました。
▲Ivan Sutherland : Sketchpad Demo (1/2)
SketchPadは今でいうとCADの前身のようなシステムで、タブレットで直接絵を描くことのできるIllustratorのようなものです。その斬新性は、50年後の今見ても明らかです。この功績により、アイバン・サザランドは後のチューリング賞、クーンズ賞、京都賞などを受賞します。
▲アイバン・E・サザランド(第28回京都賞受賞者)からのメッセージ
続いて、アイバン・サザランドはヴァーチャルバーチャルリアリティの礎を築きはじめます。ハーバードの教官を務めていた1968年、彼は指導学生であったボブ・スプロウルとともに世界初のHMDを開発したのでした。
▲Ivan Sutherland - Head Mounted Display
アイバン・サザランドの教鞭の変遷は、それ自体が現代のヴァーチャルリアリティと、コンピュータヒューマンインタラクションの足跡そのものです。ボブ・スプロウルはカーネギーメロン大で教鞭をとった後、サザランドとともにコンサルティングファームを起業しました。それがサンマイクロシステムズに買収されて、後のサンマイクロシステムズ研究所の母体となります。ここから生まれたプログラミング言語やユーザビリティ研究が、やがて1990年代のUNIXブームやその後のインターネットユーザビリティの立役者となります。現代のUNIXサーバやプログラミング言語に関する研究はサンマイクロシステムズのラボラトリーから出芽したものが多いです。
スプロウルだけではありません。後のコンピュータアプリケーションにおけるキーマンのほとんどが、彼のラボラトリーの卒業生なのです。
そして、1968年にアイバン・サザランドはユタ大学に移ります。ユタ大学は当時コンピュータグラフィクス分野で非常に有名な大学でした。マーティン・ニューエルがモデリングしたユタティーポットは今でも使用されているリファレンスオブジェクトで、そこにはユタ大学の名前が現在でも残されています。
▲ユタティーポット
言ってみれば、これは当時のUnityちゃんや初音ミクみたいな、3D表示するサンプルのオブジェクトです。ユタ大学に移ったサザランドは、コンピュータグラフィクスの研究をするとともに、ここでも多くの博士学生を育てました。ここでの彼の教え子たちがコンピューティングのアプリケーションを拓いていくことになります。その筆頭が、かの有名なアラン・ケイです。
ここまでの話からもわかると思いますが、魔法の世紀の基礎概念は、アイバン・サザランドの系譜をなぞっていくことで、読み解けるのです。しかし、実は1975年を最後に、アイバン・サザランドはコンピュータグラフィクスやこうしたインタラクティブなアプリケーションエリアを離れてしまいました。そして、当時のことについては、口を閉ざすようになりました。
僕の知る限りで、サザランドがこのことに触れたのは、まさに当時の業績で受賞した京都賞の講演の際のことです。1975年、サザランドは隠面処理のアルゴリズムに関するサーベイ論文を出版しました、その際に、彼は「隠面処理のアルゴリズムは一見違うアルゴリズムであっても、同種のソーティングの問題でしかない」と気づいたのだそうです。サザランドは、「それがグラフィクスにかける自分の情熱が消えていった瞬間だった」と言いました。また、彼が想像したようなインタラクティブシステムを行うには当時のコンピュータは貧弱であり、実現までの道筋も遠かったのだと思います。
1975年以降のアイバン・サザランドは、分散システムの研究に移っていきました。そして、こうしたユーザーインターフェイスにまつわる研究からは姿を消したのです。
「パーソナルコンピューティングの夜明け前」
しかし、サザランドが撒いた種は、その後のコンピュータの歴史の中で大きく育ち続けました。
とりわけ、コンピュータの使い方が積極的に議論された当時のユタ大学で、サザランドが指導に関わった学生たちからは、アプリケーションユースの歴史に名を残した人々が幾人も登場しました。
その中でも、ジェームス・クラーク、アラン・ケイ、ジョン・ワーノック、エド・キャットムルの4人は代表格です。コンピュータの歴史に詳しい人であれば、彼らが業務アプリケーションからハリウッドのCGまで、各分野において巨大な業績を残した人物であることを知っていると思います。アイバン・サザランドがユタ大学で教鞭を持っていたあの時代、そんな彼らが一つの時間を共有していたことは、まるで「トキワ荘」のようなものだと思います。それは、後のコンピューティングの歴史を切り開く一ページと言えるでしょう。
▲ジェームズ・クラーク
画像出典:ジェームズ・クラーク (事業家) - Wikipedia
まず、ジェームス・クラークは、後にシリコングラフィクスを起業して、ネットスケープを起ち上げた人物です。第一次ヴァーチャルリアリティブームや、黎明期のハリウッドのコンピュータグラフィクスソフトウェアのほとんどは、実はシリコングラフィクスのワークステーション上で動くものでした。コンピュータグラフィックス計算に特化したワークステーションを数多く輩出し、シリコングラフィクスは一時代を築きました。
ネットスケープのモザイクコミュニケーションズは、その上場益をもとに1994年、ジェームス・クラークが創業したものです。これは、みなさんが知っているネットブラウザの先駆けで、WWWへインターネットブラウザを用いてアクセスするというサービスでした。このようにクラークの業績は、インタラクティブグラフィクスや映画のテクノロジー基盤の提供を経て、インターネットの普及にまで渡ります。彼の存在は、この世界にコンピュータグラフィクスやインタラクティブアプリケーションのテクニックが普及していく原動力の、少なくとも一部をなしていたと言っても過言ではありません。
▲アラン・ケイ
画像出典:アラン・ケイ氏が描く未来のパソコン像(前編) - ニュース - nikkei BPnet
次にあげるのは、アラン・ケイです。既にこの連載でも取り上げている、コンピュータ史における最も有名な人物の一人です。「未来を予知する最も確実な方法はそれを作ることだ」という格言で、一般には広く知られているかもしれません。
彼もまた、ユタ大学でアイバン・サザランドの影響を受けた一人でした。アラン・ケイはパロアルト研究所の研究員時代に、グラフィカルユーザーインターフェースをもつコンピュータ(Alto)や、オブジェクト志向言語(Small Talk)をもつコンピュータなどの、現在のコンピュータに極めて近いコンポーネントをもつシステムを次々と発明しました。GUI付きのAltoを見たスティーブ・ジョブズが、それを真似してMacintoshを作ったというのは有名な話です。そして、いまや彼のDynabook構想はタブレットやスマホへと受け継がれています。ユーザーインターフェースという観点で、現在のコンピュータを作ったのは彼であると言っても過言ではないでしょう。
▲ジョン・ワーノック
画像出典:ジョン・ワーノックとは - コンピュータ偉人伝 Weblio辞書
ジョン・ワーノックについては、他の三人に比べるとご存知な方は少ないかもしれません。しかし、実は皆さんの生活に最も身近なところで活躍している人物です。というのも、彼はPostscriptの発明者であり、あのAdobeの創業者にして社長でもあります。そう、Illustrator、Photoshop、PDFリーダー、Flashなどの製品を生み出している、あのAdobe社の創業者なのです。彼の製品は生活のあちこちに溶け込んでおり、ソフトウェア的な面でデジタル世界でのクリエイションを支えています。
▲エド・キャットムル
画像出典:エド・キャットムル - Wikipedia
そして、最後の一人が、エド・キャットムルです。エド・キャットムルはルーカスフィルムでコンピュータグラフィクスチームを立ち上げ、その後チームで独立して、Pixarを創業した人物です。現在でも、キャットムルはPixar社の社長を務めています。
コンピュータグラフィクスを使ってどういうコンテンツを作るか、またディズニーコンテンツとデジタルコンテンツの親和性を用いてどうやって訴求していくか。彼の存在は、魔法の世紀のコンテンツを語る上で欠かせません。
さて、本当に今のデジタル世界の数多くのものが、この時代のユタ大学から芽吹いたものだとわかったと思います。サザランドが手放した研究テーマを引き継いだ彼の弟子たちは、VRブーム、ネットブラウザ、タブレットやGUI、オブジェクト志向言語の原型、CADCAMソフト、印刷出版、ハリウッド映画などを生み出し、やがてコンピュータ産業の花形を切り開く中心的人物となり、社会を大きく変革したのでした。
「旅の終わりと継承」
それにしても、こうした世界を変革した4人の源流にあるサザランドの研究テーマとは、結局のところ、どういうものだったのでしょうか。
僕が思うに、魔法の世紀という視点で最も重要なのは、サザランドが「創造性」や「リアリティ」のような、いかにも人間の領域の問題だとされてきたものを、コンピュータの補助によって巧妙に扱えるようにして、現実に解ける問題として捉えてきたことです。つまり、芸術や現実などの人間的知性を扱うような観点で、人間の価値観をアップデートしうる技術がコンピュータによって可能だということを明らかにしたのでした。
おそらく、サザランドには「適切なプログラミングを用いて魔法を実現する」ための自由な発想があったのだと思います。事実、サザランドの「究極のディスプレイ」に関する思想は、現在のVRの手法や、二次元画面のディスプレイに縛られたものではありませんでした。それは、究極的には物体の存在そのものをコントロールできる部屋を生み出すという思想にまで繋がっていました。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
▼PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は4月も厳選された記事を多数配信予定!
配信記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201504
-
落合陽一×宇野常寛「〈映像の世紀〉の終わりに――視覚イメージのゆくえ」(後編) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.296 ☆
2015-04-03 07:00220pt※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
落合陽一×宇野常寛「〈映像の世紀〉の終わりに――視覚イメージのゆくえ」(後編)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.4.3 vol.296
http://wakusei2nd.com
本日のメルマガは、現代の魔術師・落合陽一さんの好評連載『魔法の世紀』のスピンオフとして、宇野常寛との対談「〈映像の世紀〉の終わりに――視覚イメージのゆくえ」後編をお届けします。今回は会場から寄せられた質問に答えながら、落合さんと宇野常寛の二人が、「物理世界に染み出す」時代のインターネットと情報技術のありようを解説しています!
前編はこちら。落合陽一×宇野常寛「〈映像の世紀〉の終わりに――視覚イメージのゆくえ」(前編)
落合陽一『魔法の世紀』これまでの連載はこちらのリンクから。
■ 質問1.「物理世界に染み出す」
落合 ……会場がすごく盛り上がっていますね(笑)。
宇野 いいことだね。もう議論を再開できないくらい会場が盛り上がっていて、これは「魔法の世紀」に手応えがあるな。
落合 はい、じゃあ質問を受けます。一個目が来ましたね。「"物理世界に染み出す"という話を、もっとわかりやすくお願いします」という内容です。
この、「染み出す」という言葉は重要です。例えば、光源からスクリーンに光が当たって皆さんの目に届くとき、実はパソコンの中の情報がスクリーンに転写されて届いているわけです。とすれば、このときにコンピュータの中にある情報は、あらゆる場所からアクセスできるようになったとも言えます。データの実体は、インターネット世界にあるのかもしれない。でも、情報そのものはどんどん人間が触れられる場所に出てきている。その事実を、僕は「染み出す」と表現しているんです。
宇野 さっきの触覚の説明がわかりやすいと思いますね。例えば、僕らが生きている間に、おそらくほとんどのものにセンサーが入るでしょう。その行き着く先は、僕がセーターを着てチクッとするなと思った瞬間に、それをセンサーが感じとって肌触りが滑らかになる……みたいな状況です。ここで重要なのは、僕の脳神経ではなくて、素材の方がいじられていることなんですよ。これが、落合さんの研究の重要な問題提起です。
みんな情報技術というときに、インターネット上で行う自意識上のテキストコミュニケーションだと思っていますよね。つまり、多くの人はインターネットを、僕らの内面を変えるツールだとみなしている。でも、情報技術がディスプレイの中の映像と人間の自意識を変えるだけの段階は既に終わっている。
そうなってくると、もはやインターネットをバーチャルと呼ぶような話には、もう全く意味がなくない。実際、現状のコミュニケーションしか変えていない程度のインターネットでさえも、リアルと結託しているわけですよ。だって、「食べログ」やGoogleマップのお陰で、僕たちの都市生活は大きく変わりましたから。
こういうふうに、かつてのインターネットはユートピアをディスプレイの中に作り上げる発想だったけれども、既にリアル空間のコミュニケーションをより円滑にしていく方に発想が切り替わり始めた。ここから先の情報技術の展開というのは、おそらくインターネットという存在すら飛び越えて、センサー技術などと手を結びながら我々の実空間を情報化で書き換えていくというあり方なんだと思います。これが現在見えている、一つの大きな流れだと思います。
落合 伝わってるかな(笑)。情報の取得というときに、ついついTwitterのTLやメールのような目で見られるものを思い浮かべてしまうけど、五感のあらゆるものが情報を取得してるんですよ。極論すれば、あらゆるものは物性を介した情報のやりとりだといってもいい。
例えば、椅子が人間の体重を認識して、その体重に合わせて強度を変えたり、表面の材質を変えたりすれば、それは人間が情報に直接触っていると言える。いまや世界中に張り巡らされたコンピュータが、動物や車の動きを情報として読み取って、最適解を返し始めているわけです。物理空間が情報を媒介して、再び物理空間に戻ってくる。こういうことがあらゆる場所で起き始めているんです。それがこの世界にコンピュータでもたらされる魔法、情報の動的な物理実装です。
■ 質問2.原理主義と文脈主義
落合 次の質問です。「エクスペリエンスドリブンとは何でしょうか?」。
お、これはいい質問ですね。ネットでバズるコンテンツを見ると分かりますが、「ただ大きい」とか「無茶苦茶書き込みがある」みたいな、「ヤバイ」と言いたくなるものへの感動が大きくなる時代になっています。要は「わかりやすい表現」が強くなっているのですが、それって「ヤバイ」と思えることそれ自体に価値が見出され始めているという話なわけです。
昔は、もっと違いましたよね。今という時代をどう反映して、作家の生い立ちをどうこの作品は表現していて……というのを、誰もがコンテクストを重視していた。ピカソの「青の時代」みたいに、青い絵の具で塗るような感じですね。これは、よく宇野さんと話すことですね。
宇野 これは僕の言葉に置き換えると、「文脈主義」か「原理主義」かという話なんですよ。
さらに言えば、僕ならば「映像の世紀」に文脈を、「魔法の世紀」に原理を対応させますね。結局、「映像の世紀」というのは、特定の文脈をメディア装置で多くの人たちに共有させて、「美」の基準を作り上げたり、正しさが共有される空間を作ったりしていく世界だった。
しかし、その前提がどんどん壊れている。誰もが発信者になり、誰もがメディアを作っていけるようになったとき、もはや僕らはメディア装置を必要としていない。そのとき、人間の心を感動させる力を持ちはじめているのが、より原理的な表現になっているんです。
落合 ちょっと良い例を思いつきました。例えば、フェンシングの太田選手っているじゃないですか。彼がオリンピックの決勝戦で、超絶すごい突きで相手を倒したとき、「映像の世紀」であれば、きっと幼少期からの太田さんの生い立ちについて語って、「あの努力の高校生時代を過ごし、苦難の大学生時代を過ごして、今のあの突きにつながったんです」というのを、どうしても30分かけてやると思うんです。
だけど「魔法の世紀」には、より高精細なスローモーションビデオなんかで、その凄まじい一瞬を沢山語ることが出来る。「やっべえ、これ絶対よけられねえじゃん」みたいな映像が共有されて、どんどん盛り上がれる。そもそも重要なのは、コンテクストではなくて、その「突き」そのものですから。それが太田選手の文脈を理解してない人でも突きそのものの凄さとして理解される。
宇野 たぶん僕らが生きている間に、それをもっと別の手段で我々は感じることができるようになっていくのだろうと思いますね。「突きの鋭さ」だけのもつ圧倒的な体験だけがむしろ共有されていくような。
落合 例えばHMDを被って正面から突きを食らう映像が来たら、もうそれだけで「これはマジでヤバいな」となるじゃないですか。これが、「魔法の世紀」の重要な転換点なんです。
しかも、短くて済みますからね。俺たちはコンテクストを共有するには、情報が溢れすぎていて、一個のコンテンツと接する時間があまりに少ない。テレビをぼうっと口を開けて見て、30分長々と鋭い突きを繰り出した人間に時間を割くことは、もうなかなか出来ないでしょう。情報は希薄化され、溢れている。すぐに体感できるコンテンツが重要なんです。
宇野 もう一つ重要なのは、「文脈主義」の立場に立つ限り、あらゆるものが規模と距離の問題に還元されてしまうことなんです。結局、「文脈主義」というのは、自分にとって感動できるかどうかという問題にしかならない。
例えば、僕は全くスポーツには興味がないけど、自分が講演に行って生徒と仲良くなった高校が甲子園に出たりすると、一生懸命に応援するわけです。でも、ここで僕が彼らの試合から受け取る感動って、まさに講演に行って少し仲良くなったという事実にしかない。
とすれば、もはやソーシャルグラフを充実させるアーキテクチャと、その感情が維持できるような、頻繁に握手会をするだとかの近さだけが重要になる。つまりは、規模と距離のコントロールだけで、濃い文脈が発生する確率をどんどん引き上げられるというのが、おそらく現在のゲーミフィケーション的な存在の一つの回答です。
でも、これはもはやアーティストというよりも、プラットフォーマーの仕事になっている。両者の線引きは物凄く深い議論で、それだけで3時間くらいシンポジウムが出来ると思いますが。ただ、僕としては、もっと大きい形で個人の体験に還元されない価値のようなものを作ろうと思うと、おそらく文脈主義を捨てて、原理主義に回帰するしかないだろうとは思ってますね。
落合 例えば、昔は同じテレビ・新聞・教科書を見て生きていたから、福山雅治がビールを飲むだけで一気に説明されてしまうようなCM文化が存在していたわけです。福山雅治というコンテクストが一瞬で15秒の間で共有されることが可能だった。でも、その共通文脈が崩壊してしまえば、CM文化も同時に消滅してしまう。逆に言えば、コンテクストでウケを狙いたければ、まずはその説明から入る必要があるんです。
宇野 僕はエンターテイメントの評論家なので、そこに関してはあっさりとした回答を持っています。例えば、いま一番日本で支持を受けているエンターテイメントは、「300人くらいグループにいたら、1人ぐらい好みの女の子はいるでしょ。その子と1ヶ月に1回は握手させておけば、コンテクストが豊富になるので楽しいでしょ」という発想なわけです。
つまりは、コンテクストの感動というのはプラットフォームで完全に設計できる――これで、終了です。結局、そういう感動というのは、実はほとんど個人的なコミュニケーションの問題でしかないと判明してしまったんですね。あとは残っているのは、そのコミュニケーションの環境をいかに整えるかという問題と、個人の努力の問題だけでしょう。握手会で変なことを言って嫌われないとかね(笑)。
■ 質問3.ヒューマズムな表現とは?
落合 ここに質問が一個きているので読みます。
「『魔法の世紀』は文脈主義から原理主義へ移っていくというお話は、ヒューマニズムのような感動よりも五感に直接訴えかける感動の方が主流になるということでしょうか?」
はい。そう思います。ヒューマニズムというのもポイントですね。BBCなんかは、よく泣けるコンテンツをバズらせるんです。例えば、死ぬ直前の老婆が愛する馬と会った瞬間に死んだみたいな話です。ただ、それってヒューマニズムなのかというと、少し違う。「死」という直接的なコンテンツをバズらせているだけとも言えて、実は「原理主義」的な話なんだと思います。別に些細な心の機微があったわけではなくて、ガツンと人が死んだからええやろ、という発想ですよね。人間の心を直接に金槌でぶん殴るような表現なんだと思います。
それって嫌だなと思う部分もありますが、機微のある表現はコンテクストが重要である以上、どんなコミュニティの人間も共通して理解できる表現は減少しています。もちろん、あるアートのコミュニティ、SF好きのコミュニティ、何かの映画作品好きのコミュニティみたいなところに分断された表現は残っていくと思いますが。
宇野 繰り返すけれども、いわゆる狭義のヒューマニズムがもたらす感動というのは、プラットフォームによっていくらでも設計できると判明した。だって単純に、本当にシステムを作って多様な選択肢と近い距離さえ確保していけば、確率的に発生するともう証明されてしまったわけですよ。そうである以上、それはもうアーティストの仕事ではなくなっていく。おそらく、マーケッターやアーキテクトの仕事になっていくでしょう。
落合 感動の話だったら、前田敦子が転ぶ瞬間を捉えたらいいんだよね。しかも、それは確率の問題でしかない。
宇野 その感動の大きさというのも、前田敦子との距離の近さによって設計できるわけだからね。つまり、2005年の12月から劇場に通い続けたやつの感動は1億なんだけど、テレビで何となく「何だあの人」と思っている人間の感動はもしかしたら−3みたいなね(笑)。それって、ほとんど多様な選択肢と近さをどう設計するかという問題に、おそらく8割ぐらい還元されている。
ただ、今日の話について言えば、僕はそういう作業を馬鹿にする気は全くないけれど、もうちょっと別の回路があるんじゃないかという気がする。もう少し文脈主義に回収されない、「魔法の世紀」における「死」とはなにか、みたいなことは考えられると思う。人間と情報との関係が変わりつつある時代の絶対的なものとかね。
落合 それ、俺も連載で書こうかな。だって、外在的に俺たちは死ななくなってるもんね。死んだ後もブログは残っているわけで。
宇野 そうなんですよ。「認識できても触れられないものとは何か」みたいなものが、おそらくテーマになっていくんだと思う。
■ 質問4.ソニーについて
落合 次の面白そうな質問は、「ソニーに関して聞いていいですか」というものです。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
▼PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は4月も厳選された記事を多数配信予定!
配信記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201504
-
落合陽一×宇野常寛「〈映像の世紀〉の終わりに――視覚イメージのゆくえ」(前編) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.274 ☆
2015-03-04 07:00220pt※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
落合陽一×宇野常寛「〈映像の世紀〉の終わりに――視覚イメージのゆくえ」(前編)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.3.4 vol.274
http://wakusei2nd.com
本日のメルマガは、落合陽一さんによる好評連載『魔法の世紀』のスピンオフとして、昨年11月に行なわれた宇野常寛との対談をお届けします。落合陽一はいかにして「現代の魔術師」になることを志したのか、そして今改めて〈魔法の世紀〉というコンセプトを解説します。
落合陽一『魔法の世紀』これまでの連載一覧はこちらのリンクから。
初出:NICA プレオープニングクロスセッション「落合陽一 × 宇野常寛『魔法の世紀』21世紀のテクノロジーカルチャーを語り尽くす」(2014年11月16日開催)
宇野 僕が主宰しているメールマガジンで、いま落合さんに「魔法の世紀」というタイトルの連載をしてもらっています。僕はメールマガジンと紙の本と両方出しているのですが、正直に言って、この「魔法の世紀」は今手がけている全ての媒体の中でも目玉企画だと思っています。つまり、これは僕が今編集者として最も力を入れている連載であって、来年の目標の一つは、この「魔法の世紀」をベストセラーにして、日本の文化シーンと思想シーンに「一石」――どころか「大砲」を撃ち込むことです。
この「魔法の世紀」という言葉は、僕が落合さんにロングインタビューをしたときに対話の中で生まれたものです。研究内容かがアート作品にどう昇華されているのかを聞いたとき、「20世紀が『映像の世紀』だとすると、研究者にしてアーティストの落合陽一は『魔法の世紀』を表現しようとしているんですよね」と指摘したのがキッカケです。
連載では、そこから話を広げて、落合陽一の構想する「魔法の世紀」を思想的に定義づけ、アートやデザインにおいてどう展開するのか、そして人間と文化、情報の関係がどうシフトするかを考えてもらっています。まずは落合さんにその概要を話していただきましょうか。
■ CGの歴史はディスプレイからモノへ
落合 わかりました。僕の名前は、落合陽一といいます。名前をググると、TEDで喋ったり、ホリエモンとよくわからない8次元ディスプレイの話をしていたり、テクノロジー系の雑誌に載っていたりすると思います。
▲「これは幼少期の写真です(笑)」(落合氏)
そうそう、最近では「Time」誌と「Fortune」誌と「Forbes」誌がやっているワールド・テクノロジー・ネットワークの、今年のアワードノミニーになりました。渡航に23万円かかると言われて、授賞式に行くのはやめましたけど(笑)。
では、そんな僕が何をやっているか。普段はメディアアーティストと、コンピューターグラフィックス(注:以下、表記はCG)のリサーチャーをしています。
CGの技術が始まったのは1960年代です。基本的には、「コンピュータの中でどうやって絵を作るか」をずっとやってきたのですが、90年代にハリウッドで盛り上がったときに成熟してしまいました。そこで僕は「モニターの外でどうやって画像を作るか」を研究しています。口で説明すると、ちょっとアレですけどね。ただ、僕としては、2100年の情報技術をどう作っていくかを考えているつもりです。
例えば、138億年前、宇宙が誕生したときから物質はあるわけです。でも、CGが生まれたのは1963年です。138億年して,人間はコンピュータの中にもう一つの世界を作って操作できるようになったってことです。例えば、マウスでクリックするアイコンなんかがありますよね。ああいうふうなグラフィカルなユーザーインターフェイスを探求していく歴史が始まったのが、そのときです。90年代になると、今度はARをOSのアプリに入れて、触って操作できるユーザーインターフェイスや触って操作できるようなコンピュータも登場しました。ところが、2000年代になると、研究者たちはちょっとやることがなくなって来たんです。デジタル世界でできることが減ってきた。たとえば『ターミネーター2』の中に液体金属のロボットが出てきますよね。あんな感じで「形が変わるようなコンピュータってできるんじゃないの?」というような研究が始まったんです。
そこで今、僕が話しているのは、「分子サイズのコンピュータがたくさんあって全体の形が変わるコンピュータはなかなか大変なので、それを出来そうな範囲内に収めよう」ということです。そして、そうなると「物体自体よりもそれを包み込む環境、例えば物理場のほうが重要だよね」となる。僕が考えているのは、要は物理場をどうやってコンピュータでコントロールして、この物質世界を動かすかなんです。見た方が早いので、簡単にお見せします。
見ていただければわかりますが、実は上手く場を制御すれば、たとえCGの世界ではなかったとしても、物体はわりと自由に空中に浮かぶんです。そうしたら、今度はその場自体のxyzの位置、三次元位置を変えてしまえば移動できる。でも、簡単そうに話すのですがこの世界は「何だって出来てしまうCGの中の世界」とは違ってリアルの世界なのです。というのも、この世界には重力があって、そう簡単に物体は動かないんです。そこで、僕は移動させる場を重力よりも強い力で制御しようと考えました。そうすれば、コンピュータの外でも、コンピュータの中と同じように自由にものを動かしたり、飛ばしたり、浮かべたりできると思ったわけです。
▲「PIXIE DUST」
まさに、それが僕の研究者としてのテーマです。例えば、普通は重力があれば、粉は下に落ちますよね。でも、ある一定の秩序を持った「場」があれば、空中に降り注ぐ粉をその場に留めておける。すると、そこが一瞬で三次元のディスプレイになるわけです。これはつまり、コンピュータの中にある秩序をコンピュータの外に持ってきて、表現をしているということだと思うんです。しかも、今後は何百個ものモノをコンピュータの計算によって制御する、よりコンピュータの力を使ってコンピュータらしい振る舞いを考えるのが、ホットな分野になると思っていますから、今はそこをガリガリとやっています。
最近CNNから取材されたんです。実は来年、映画の中では『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に出てきたホバーボードが発売される予定らしくて、「レビテーション=空中浮遊」の特集をやってたんですよ。最近は、日本のメジャーな番組にも出させて頂くようになりました。僕が日本のメディアに出るひとつの理由としては、日本の研究者を増やしたいという目的もあります。研究者は英語で研究発表をするので、日本にリーチする機会があまりないので、メディアにでてなるべく研究の面白さを伝えようとしています。海外に優秀な研究者は沢山いるけど、日本には中々いないですから。
▲「アリスの時間」
研究以外にも作品作りもしています。たとえば、この「アリスの時間」という作品は物体が12個並んでいて、そこに光を当てて1個の映像を作ったものです。昔、プロジェクターが普及する前に、OHPという実物投影機がよく使われていたんです。その原理は、光を当てて、レンズで集めて、鏡ではね返すというものだったのですが、これも同じですね。LEDが当たった文字盤で反射した光が、上のレンズで一度変換されて、スクリーンに映像で映るんですよ。
言わば、モノをフィルムの代わりに並べてアニメーションを作ったわけです。宇野さんとよく話すのですが、かつてはマスに向けて表現する際には、印刷可能なフィルムや紙などの状態にするしかなかったんです。具体的には、映画や本ですよね。でも、今の時代は「魔法の世紀」だから、物体から物体へと表現を移せるのだと示したかったんです。それのコンセプトを物体を直接映像に変換する装置として表現しました。ちなみに、これは海外でウケました。ハリウッドがお金を出している「SIGGRAPH」という世界で一番大きいCGのカンファレンスで、テクニカルとアートのプレスが両方とも俺の作品で埋まったんです。あとで聞いたら、40年間やっていて、そんなことは初めてだったと言われました。そんな感じに毎日楽しく研究したり作品作ったりしています。
■ 「魔法の世紀」を貫く3つのキーワード
落合 さて、今日のテーマは、まさにこの「魔法の世紀」なんですが……ちょっといいですか?
連載を読んでいる人は手を上げてください……4人いますね。ということは、今日の人口の5%くらいは取っているわけですね、素晴らしい。じゃあ、軽く説明します。
まず、僕はこの「映像の世紀」から「魔法の世紀」へ、という流れを一つのパラダイムだと思っています。僕は本来、テクノロジーの研究者なので、「テクノロジーをどうやって我々、現代人が噛み砕いて考えていくのか」を誰かの代わりに考えているつもりです。でも、誰の代わりなんだろう……みんなの代わりに考えているんですかね(笑)。
宇野 昔だったら、思想家や哲学者や芸術家が語っていたようなことを、今やテクノロジーの担い手自身が語っているわけでしょう。この現実自体が「魔法の世紀」のコンセプトそのものだと思う。
落合 そうだと思うんです。それで話を戻すと、まさにフランシス・ベーコンが16世紀にテクノロジーの思想について考えていて、「自然を征服する」というコンセプトを掲げたんです。彼は、科学技術を用いて、いかに自然を加工して人間の意のままに操っていくのかを重視したんですね。彼の思想が象徴的ですが、この発想は西洋の至るところに現れているものです。例えば、噴水が好きな人は手を上げてください。噴水の好きさ具合を5段階で表してみましょう……"5"がふたりしかいない!!(笑)。
僕は「噴水」を西洋思想の一番の現れだと思っています。なぜならば、洪水を引き起こすような制御しづらい存在の象徴である「水」を、人間が作った庭園の真ん中に置いて、しかも重力に逆行して形を作っているからですよ。それは人間が自然を克服したことの一つの象徴だと思うんですね。西洋文化は、そういうふうにこの地球上のあらゆるものをいかに「神の御わざ」ならぬ「人間の御わざ」でコントロールしていくかをやってきたんです。僕が21世紀を「魔法の世紀」と呼んでいるのは、それがもっと爆発して、我々があらゆる存在にコンピュータ技術を用いて干渉できるようになってきたことを言っているに過ぎません。
では、そんな「魔法の世紀」とはどんな時代なのか。今のところ、重要なポイントは大きく3つあると思っていて、”Magically”、”Logically”、"Physically”です。
まず、”Magically”の意味は、「まるで魔法のように、それが何で起こっているかわからないし、何を使っていても関係ない」ということですかね。テクノロジーが秘匿されるってことです。
例えば、Twitterをつぶやくときに、スマホでもパソコンでもテクノロジーは何でも構わないわけです。なぜなら、僕たちが最終的にやりたいことは、自分の何らかの思いをWebに乗せていくことであって、その間にあるツールは別に関係がないからですよ。それって、魔法みたいでしょう。
魔法も何で動いているのかわからない。「炎よ出よ!」と言うと、なぜ炎が出るかわからないが、とりあえず炎は出る。この「わからないけどできる」というのが、「魔法の世紀」を説明する一つの大きなパラダイムですね。
二番目の”Logically”については、「論理的」という意味ではなくて、「コンピュータで動く」という意味です。コンピュータで一度ロジック化されているので、あらゆるものはコンピュータによって、プログラミングによって論理的に記述することで、コントロール可能になるわけです。
そして、最後に重要なのは、それらが”Physically”を志向していることですね。例えば、アイドルのプロモーションビデオがもし全て単なるCGとかだったら、きっとテンション下がりますよね。一方で、ライブではオタクがガンガン盛り上がるわけですよ。我々はもう、実際にあるもの以外にあまり価値を持たなくなっていると思うんです。
それはデジタル社会が繁栄して、コンピュータがこの世界をくるんでしまったからだと思いますね。かつてはコンピュータが希少だったから「デジタルすげえ」だったけど、ここまでコンピュータが豊富になってしまうと、もはや「フィジカルすげえ」に回帰してしていくわけです。
■ 魔法の世紀で何が変わるのか
落合 では、こういう特徴を持つ「魔法の世紀」への変化で何が起きるのか。ここでも俺は3つのキーワードを挙げたいと思います。それは、パーソナライズ、インタラクティブ、直接的な表現、です。具体的に説明しましょう。
例えば、僕たちは映画を観るとき、携帯電話の電源を消すように言われてしまって、Twitterでつぶやくことはできないわけです。ここに象徴的ですが、映画というのは全員で一つのスクリーンを見ている一方で、僕たち観客同士は互いの存在を意識していないんです。でも一方で、本来なら現在は、いつでも誰かに話しかけられて、相互にコミュニケーションがとれる時代のはずなわけですよ。映画監督のような一人の偉い人が情報を発信するんじゃなくて、僕たちは相互にコミュニケーションしながら、それをコンテンツとして咀嚼していく。相互ネットワークの「NtoN」の関係なわけです。これが「魔法の世紀」の一つのキーワードで、俺は「パーソナライズ」と名づけています。
あと、「インタラクティブ」ですね。昔は例えば、「黒澤明死ね!」とかつぶやいても、黒澤明には伝わらなかったわけじゃないですか。だけど、今Twitterでそんなこと言ったら、エゴサーチした黒澤明がへこむわけです(笑)。
宇野 実際に、作家も映画監督も毎日エゴサーチしてはヘコんでるからね。今、いい編集者というのは、いかに担当作家にエゴサーチを気にさせないかみたいな仕事になっている。
落合 みんなが「死ね死ね」言ったらその作家はへこむし、逆に褒めたら喜ぶ。まさに、この社会全体がインタラクティブになっていることを示してますよね。
あと、最後の一個がすごく重要で、昔は代理表象が可能だったんです。例えば、絵画や小説でもわりと直接的ではない表現を使って、伝えたいことを象徴させる。伝えたいことを何かに代理させて、表象していたわけです。だから、婉曲的で、コンテクストがあって、感情があって……という、そういう世界でした。
でも今って、わりと直接的な「キラキラして綺麗」とか「でかい」とか「すごい時間かかってそう」とか、そういうアートがYouTubeでバズったり、Twitterですごい勢いで流れたりする時代になっています。昔は間接的に表現してきたものが、今は直接的な表現になっている。しかも、フィクションの世界を表現するよりは、ライブやこの社会全体とつながっている表現自体が一番刺さるようになっている。こういうふうに、コンピュータが作った大きなネットワークや枠組みの中で、あらゆるモノや哲学が変わろうとしているわけです。そこで、この時代を「魔法の世紀」と名づけているわけです。
宇野 いやあ、説明が手慣れてきたね。この半年、いかに「魔法の世紀」と言い続けてきたかということだよね(笑)。
落合 そうなんですよ。あ、いつでもTwitterにリプライをくれていいですよ、僕はいつでも見てますから。意見やコンテンツに対して双方向的になる、それが魔法の世紀ですからね。
■ 戦後思想から見た「魔法の世紀」
宇野 僕は落合さんにロングインタビューをしたとき(『静かなる革命へのブループリント』に収録)に、「明確に一つの時代が終わろうとしているな」と思った。
色々なことに僕は手を出してるように見えるけど、究極的にはサブカルチャーの評論家なんですよ。だから、これまでアニメや漫画について議論することが多かった。その視点で言うと、戦後日本のアニメは、すごく特別な位置にある。村上隆が世界に出ていくときにアニメ的な意匠を用いたことには、まさに必然性があった。戦後アニメーションはまず戦後日本的なアイロニーの結晶であった。要するに近代国家としての精神的成熟を迎えないまま、経済大国化したネオテニー的主体としての日本の自画像が、もっとも如実に、そして批評的に出現していたのが戦後アニメーションだった。
そしてさらに同時に、アニメは完全な「虚構=作家が意図したもの以外に存在できない映像」でもある。ここには二重の「ねじれ」があって、第一に戦後アニメを形成する文化空間自体が「アメリカの影」によってネオテニー的に「ねじれ」ている。そして第二に、こうしたアイロニカルな文化空間はアニメのような完全な虚構を通してしか現実、つまり戦後的アイロニーの本質にアプローチすることができなかった。僕はここが重要だと思うんです。
と、いうのも結局、20世紀というのは、映像という虚構をマスメディアで広範に共有させることで、社会を形成するということにたどり着いた時代だったから。だからこそ、アニメーションという映像こそが戦後日本の精神性を代表するものであり得た。
落合 共通のコンテクストはテレビによって作られていましたからね。
宇野 そう、戦後日本の、とくに政治の季節の終わった70年代以降はテレビを中心としたサブカルチャーについて語ることが、もっとも効果的にこの国の文化空間を批評することだった。これは単純にメディア史を考えても必然的なことで、20世紀前半はラジオが普及した結果、あちこちにファシストが出てきて人類が滅びかけた時代だった。そこで後半は逆に、「じゃあ、マスメディアというのは政治からちょっと距離をとりましょう。とりあえず西側諸国ではそういう建前でいきましょう」ということになって、政治権力から切り離したテレビメディアを50年くらいやった結果、今度は政治漂流やポピュリズムを誰も止められなくなってしまった。
これが、20世紀というまさに「映像の世紀」の本質で、社会を形成する一つのビジョンを作り、それを極めて受動的に消費できるようなメディアを作り、それを社会全体が共有することで何かを維持してきた。
しかし今日はそんな時代が終わる、いや、すでに終わっているという話をする場です。
サブカルチャーの世界の人間として語るなら、その終わりはサイバーパンク的なものの終わりだと言い換えられるし、戦後日本の精神史的に言えば、連合赤軍〜オウム的なものの終わり言える。アメリカ的に言うとヒッピーカルチャーからカリフォルニアン・イデオロギーへの流れが一段落し、その果てにまったく別のものが台頭し始めていると言えるはず。
要するにこれは68年以降先進国が共有していた、革命が信じられなくなったとき、つまり社会を変えることが信じられなくなったとき、自分の脳内に何かを注入することによって、自分を変えようと、納得させようとする思想が台頭してきた。テレビが代表するような20世紀的な虚構がもっとも力を持ったのはこの時代だと思う。そして、いまこの時代が終わろうとしている。
落合 そうして変わった人間が、今度はマスメディアに乗って自分のメッセージを伝えれば、人間がどんどん変わっていくというわけですよね。でも結局、それって一人のトップ思想をコピーしただけで、彼らは一つの理念で動いているにすぎない。その人の脳みそが単に拡大しただけで、総体として大きな人間が生まれたに過ぎない。でも、今の時代はそうじゃなくて、本当は一人ひとりが個別に動くわけです。それは圧倒的孤独ともいえるけど、コンピュータのもたらしたつながりが逆に個別性を招いた結果です。
宇野 日本の場合、20世紀後半的な虚構が破綻してしまったのがオウム真理教だった。あれって元々は、信者にヘッドギアをかぶせ、『風の谷のナウシカ』と『機動戦士ガンダム』と『宇宙戦艦ヤマト』を組み合わせた架空歴史設定やカルト思想を注入していけば、いつの間にか悟りを開けて、特に社会に害を与えることもなく勝手に成仏できるという思想だったはずなんだよ。ところが、結局は自分たち自身がそれを信じられなくなって、「ガチに国務大臣やマスコミを暗殺して、地下鉄にサリンを撒かないと、俺たちはもう駄目だ」というところにまで行ってしまった。まさに虚構を自分の中に注入して自分を変える「虚構の時代」の敗北であったと思う。
じゃあ、どうすればいいか。それをインターネットに付き合いながら、世界中の人間が考えていたのが、実は世紀の変わり目前後の20年間だと思うんだよね。僕もずっとそのことについて考えていた。その中で僕は、落合さんの研究を見たときに、「ここにたぶん一つの答えがあるんじゃないのかな」ということを思ったわけです。
例えば、20世紀後半の人間は触覚を変えようと思ったときに、自分の脳の中で発生している電気信号を変えようとする。これまでは、少なくとも20世紀後半の人間たちは、たとえば本当はザラザラしたものを触っているのに、スベスベしているものを感じるように人間の認識の方をいじろうとしてきた。しかし落合君の研究というのは、むしろ板の表面をコントロールして、あるときはザラザラ、あるときはスベスベするように触感をいじっている。つまり、人間の脳内をいじるのではなくて、人間とモノとの関係をテクノロジーでいじろうとしている。
これは、なかなか僕くらいの世代までの人間は思いつけない。なぜなら、僕らの世代はやはり「虚構の時代」という「映像の世紀」の終わりに出て来た世界観に毒されすぎていて、社会全体を革命的に「大きな物語Aを大きな物語Bに変えることで変えてしまう」のか、あるいは「自分を納得させるようなロジックを脳内に注入する=ヘッドギアをかぶってしまう」のかの二択で考えてしまって、第三の道を考えられない。しかも、それがテクノロジー的に可能だとも、最近までは思っていなかった。そういう中で、まさに落合陽一の研究というのは、第三の道をかなりクリアなイメージで出していると感じたわけです。
落合 まさに、僕はHMD(ヘッドマウントディスプレイ)をかぶるのが嫌いなんです。どちらかというと、テクノロジーは完全に人間から秘匿されるべきだと思っていて、テクノロジーのことにはかまけずに生きていきたいんです。だって、インターネットに常時接続されて、インターネットでダベるために生きていたら、人間はインターネットに食われている状態じゃないですか。インターネットの恩恵を受けつつも、僕たちは僕たちらしく生きていくべきだと思うんです。コンピュータと我々どっちが主体的な存在なのかということです。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
▼PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は3月も厳選された記事を多数配信予定! 配信記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201503
-
(非)言語にとって美とはなにか――〈魔法の世紀〉をめぐって(落合陽一×石岡良治×宇野常寛) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.251 ☆
2015-01-29 07:00220pt※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
▼PLANETSのメルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」2015年1月の記事一覧はこちらから。
(非)言語にとって美とはなにか――〈魔法の世紀〉をめぐって(落合陽一×石岡良治×宇野常寛)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.1.29 vol.251
http://wakusei2nd.com
本日は、昨年末に行なわれた「PLANETS Festival 2014」から、メディアアーティスト・落合陽一さんと、おなじみ批評家の石岡良治さん、そして宇野常寛との鼎談の模様をお届けします。落合さんの提唱する「映像の世紀から魔法の世紀へ」というコンセプトを基点に、ジェームズ・キャメロンやディズニー、クリストファー・ノーラン、Ingressなどにも触れながら、〈メディア〉と〈アート〉のその先の表現の可能性について語りました。
▼当日の動画はこちらから。(PLANETSチャンネル会員限定)
▼プロフィール
落合陽一(おちあい・よういち)
1987年生まれ。名前の由来はプラス(陽)とマイナス(一)。小さなころから電気が好き。
コンピュータの未来をアートと研究の両面から追求するのがライフワーク。
日本の巷では現代の魔法使いと呼ばれている。
筑波大でメディア芸術を学び、2011年卒業、東京大学学際情報学府で修士号を取得(2013年)。米国MicrosoftResearchを経て、東大にて博士審査中(2014年)。情報処理学会新世代企画委員としてアカデミックの未来も考案中。
筑波大学非常勤講師。これまでに研究論文はSIGGRAPHを始めとして有名な国際会議に採択され、作品はSIGGRAPH Art Galleryを始めとして様々な場所で展示された。情報処理推進機構よりスーパークリエータの称号、LAVAL VIRTUALよりグランプリ&部門賞、ACEより最優秀論文賞。
HP: http://96ochiai.ws/
★PLANETSメルマガで好評連載中! 落合陽一『魔法の世紀』過去記事一覧はこちらから。
石岡良治(いしおか・よしはる)
1972年生まれ。批評家。跡見学園女子大学ほかで非常勤講師を務める。専門は表象文化論。著書に『視覚文化「超」講義』(フィルムアート社)がある。
◎構成:稲葉ほたて
宇野 ここからはメルマガPLANETSでも大人気で、最近ではテレビにも出ている現代の魔法使い・落合陽一さんと、日本最強の自宅警備員であり、表象文化論やメディアアートの問題にも非常に知識があり、間違いなくリテラシーも日本最強である批評家の石岡良治さんをお迎えし、落合陽一さんのメルマガ連載のタイトルでもある「魔法の世紀」という問題提起について掘り下げたいと思います。よろしくお願いします。
落合・石岡 よろしくお願いします。
宇野 と、いうことで今日は「自宅警備員 vs 魔法使い」というテーマでいきたいと思います。ところで皆さん、この中で「メールマガジンで落合陽一の連載を読んだことがある」という人はどれくらいいますか?(手を挙げてもらう)
さすが、かなり多くの人が読んでいますね。
落合 ここにいる人口の40%くらいですね。この前講演会(http://peatix.com/event/60459/)で聞いたら2%でしたよ(笑)。
宇野 一応、ここが本家本元ですからね。非常に反響の大きい連載であり、おそらく来年に本になると思うんですが、非常に大きなインパクトを持って迎えられるのではないかと早くも囁かれている連載です。この「魔法の世紀」という問題提起については、これまでの僕とのトークでは主にメディア論や面白い文化として、あるいは猪子さんと同じ括りのテクノロジーの問題として語られることが多かったと思うんですよ。
でも、今回は本業が美術批評家でいらっしゃる石岡さんをお招きすることで、メディアアーティスト・落合陽一という側面にスポットを当てながら、この「魔法の世紀」について考えていく1時間15分にしたいと思っています。
まず最初に、残り60%の観客のために、「魔法の世紀」という連載について、ご本人の口から軽く説明していただけますか。
落合 この連載は、そもそも20世紀が「映像の世紀」だったということとの対比関係において、21世紀は「魔法の世紀」だと、捉える連載なんですね。
例えば、21世紀になって、たくさんのコンピューターが溢れている世界になっていると思います。この中でスマホを持っていない人は?――1人ですか。みんなスマホを持っていますよね。5年くらい前だったらスマホを持っている人の方が少なかったわけで、どんどんコンピューターと我々の境界が変わってきている。その中で、どうやって文化が変わるのか、どうやって表現が変わるのか。そして、どうやって俺たちの考え方自体が変わっていくのか。それをコンピューターの歴史になぞらえながら語っていく連載です。
例えば、昔はテレビが流していることが絶対で、CMをバンバン打てば商品が売れた。でも今の時代では、インターネットでみんなが違った考え方を持っている。高倉健が死んだ日に、ニコニコのチャンネルで観られている番組といったら、囲碁をやっている人は囲碁を見ているし、ポケモンをやっている人はポケモンを見ている。だけど、テレビをつければ高倉健が死んだことばかり流している。ここにはすごい乖離があるのですが、僕は後者の方がより”今風”だと思います。なぜなら我々はすでに共通の文脈を持っていないし、文脈がなくとも小さなコミュニティをWeb上で形成して楽しく生きてゆける。そのようにコンピューターが我々の生活や思考様式を変えうる中で、21世紀に通じる文化がどんなものかを、現在の段階で読み解きながら思想を作っていこうという連載です。
宇野 そういった中で、この「魔法の世紀」をモチーフに、僕は石岡さんを落合くんにぶつけてみたかった。この連載を一言でいうと、「人々が平面のイメージ、その究極で言えば映像を共有することで社会を作っていく時代は終わる。なぜかといえば、情報テクノロジーというものが今どんどん画面の外に出てきているから」というものです。
その中で、逆に石岡さんはやっぱり究極の二次元擁護者なわけですよ。特に映像イメージというものをいまの日本で最も肯定している批評家の一人が石岡さんだと思います。その石岡さんから、この「魔法の世紀」がどう見えるのかを、ちょっと一回マジで聞いてみたかったんですね。
映像はモノの劣化コピーなのか
石岡 なるほど。差し障りのあることを言わずに何かをdisるのは難しいのですが、簡単に言いますと僕がずっと学んできたものは、メディアアートみたいなものに対して最もシビアな「ザ・人文」の本道みたいなところです。僕はその成果を基本的には全部尊重しているつもりですが、やはりメディアアート的なものなどのある種の雑多さを嫌うタイプの文化・芸術観というものに対しては、ずっと違和感があったんです。
▲石岡良治『視覚文化「超」講義』フィルムアート社、2014年
▲宇野常寛(編著)、落合陽一ほか(著)『静かなる革命へのブループリント この国の未来をつくる7つの対話』河出書房新社、2014年
『視覚文化「超」講義』は『静かなる革命のためのブループリント』と同時期に出たのですが、『ブループリント』を読んでいくつか後悔したところがありました。すごく雑に一ヶ所だけ言うと、僕は映像を映像だけで語ろうとは思わずに、ホビー――つまりおもちゃの趣味とか、SF映画のガジェット、例えば『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に出てくる車とか――そういう装置と映像の関わりについて語ったつもりだったのですが、『ブループリント』でレゴブロックやミニ四駆の話を読んだときに、タミヤのミニ四駆を忘れていたと気づきました。あそこで僕は「タミヤはスケールモデル、及びミリタリーのプラモを作っているところ」で、それに対して「ガンプラはかっこいい」という擬似的な二項対立を作ってしまったんです。
宇野 僕なりに、この『視覚文化「超」講義』という本を解釈すると、こうなるんです。いま世の中がどんどん情報ではなくて、体験にしか価値がなくなってきている。映像や音声といった情報は供給過剰に陥っていて、どんどん0円に近づいている。その結果、コミュニケーションというか体験にしか値段がつく時代になった。
そんな世の中で、映像というものを体験的に解釈し直すためのコードを設定した、というのがこの本なんです。つまり「エクスペリエンスドリブンで映像というものを見てみるにはどうしたらいいか」ということを考えたのがこの本です。普通同じことをやると、二次創作論になってしまう。要するにどんな映像も二次創作的に視聴者が打ち返せばインタラクティブに楽しめる、というのがこの手の議論の王道だった。でも石岡さんはそれを排して、たとえば映像が映し出してしまったモノなどに注目することで、エクスペリエンスドリブンの時代の「映像」の楽しみ方を提案しているのだと思うんですよ。
石岡 『ブループリント』に「革命」という言葉が入っていますよね。「革命」というと、マルクスは「世界の解釈を変えるんじゃなくて、世界を変えるんだ」と言ったみたいな話がある。そう考えて、「映像」と「魔法」と言ったときの落合くんのテーゼをそれに翻訳すると、映像というのはあくまでも「モノについてのイメージ」を色々いじってきたんだけれども、そうじゃなくて「モノそのもの」をいじってしまおう、ということになる。そうすると、モノとイメージの関係で言うと、モノを変えちゃうというのは、『ブループリント』の言葉だと革命になるし、「映像」と「魔法」の対比で言うと「魔法」の側になるかなという感じがしました。
落合 俺はよく講演会や論文、ネットで「ここ50年間、映像は映像の世紀として生きてきたけど、映像の外側でも映像と同じように自由度を上げるというのが今世紀の最も重要なことだ」ってよく言っているので、まさしくその解釈で合っています。
石岡 ただそれに関しては、僕は逆の言葉もちょっと言っておきたくて、そうするとやっぱり映像なんてものはただのペラい、現物に対する劣化コピーに過ぎないとかいう話になってしまう。これって多分、文化批評全般に対する大きな疑念とも結びつくと思うんですよ。社会的な批評と文化というものがどこかで分かれているとみなされ、文化が社会の劣化版とされている。僕がなぜ二次元派かというと、いま言った世界そのものを変化させるという話は、当然ながら文化の側にもダイレクトに結びついていると思うからです。
落合 僕はCGの人間なので、実はCGこそが、我々のイマジネーションをフルに使える場所なのだと思います。
なぜなら、コンピュータグラフィクスを生成するコンピューターのデータ空間には、重力もないし摩擦力もないし、何をやっても大丈夫だからです。だけど、こっちの現実世界の不自由さはすごいものがあって、いかに精巧な、リアリスティックな像を作ろうともCGの中の我々のイマジネーションの自由に比べたら大した表現にたどり着くことができない。ハリウッドの映画に見られるような画面の中のCGの方が表現としてやれることが圧倒的に多い。
ジェームズ・キャメロンは何が凄いのか
落合 現実世界での表現が不自由でコンピューターの中の表現が自由、しかもハリウッドには金がものすごいたくさんある。それが現状で、それをどうやって変えていくかを考えるのが、僕は一番良いと思うのです。そこで、今日、僕は一つ問題提起をしたいんです。
コンピューターというと、みんなコンピューターの革命者を想像して、ご多分にもれず「スティーブ・ジョブズすげえ」と思うわけですが、俺の中では最近は「ジェームズ・キャメロンすげえ」なんですよ。だって、ハリウッドの興行収入を上から数えていくと、一位『アバター』、二位『タイタニック』なんですよ。で、ちょっと下のほうに『ターミネーター2』がある。ハリウッドって、80年代からCG業界に金をバンバン突っ込んでいて、自分自身をどれだけイマジネーションから自由にするかっていうことを、実はすごい金を使ってやってきたんですよ。
確かにスティーブ・ジョブズはiPhoneを売ったかもしれないし、Macも売ったかもしれない。でも、ジェームズ・キャメロンは表現という世界で、『アバター』一発で2700億円ですよ。日本のAR(オーグメンテッド・リアリティー)産業を最初から最後まで積分しても、『アバター』一本に全然勝てない。ハリウッドは自分たちの末期、コンピューターによる自由表現が映画を変えていくし産業も変わっていくことを最初からわかっていたから、コンピュータグラフィクスという本丸の産業をあらかじめ買い取って、自分の金で育てておいたわけです。
石岡 今日、色々と準備しながらTwitterを見ていたら、「Ingressが東京でイベントをやっていたときに、緑色サイドの人たちが青島とグアム島と襟裳岬で巨大三角形を作って、日本全土を緑色サイドの陣地にした」という、まさに今日一番のアツい出来事があったんですよ。
Ingressというのは、スマホアプリを使って三角形で現実の地形を囲んでいくゲームなのですが、まず緑側がそういう三角形を作ってしまった。それに対して、青色サイドの廃人が襟裳岬に向かって、4時半とか5時くらいのイベント終了間際に破壊して、「崩れたー」とか「おおー」とか言ってイベントが盛り上がっていた。
僕が面白かったのは、その三角形に一個だけ襟裳岬という日本の場所が入っていたことですね。襟裳岬という一点がギリギリ行ける範囲にあったのが大事で、そうじゃなかったらただのチートです。本当に外から囲っていたらどうしようもない。僕はどちらかというと自宅派なんだけれども、そういうのを見ているとIngressをやりたくなってきますね。
宇野 この「キャメロン vs Ingress」は、結構面白い対比だと思います。それはつまり、「結局、映像の世紀の臨界点はどこなのか」ということなんです。さっきのキャメロンの話から導きだされるのは、「すべての映画はアニメになる」ということですね、これはもともとは押井守の言葉です。 -
【ほぼ惑ベストセレクション2014:第1位】現代の魔術師・落合陽一連載『魔法の世紀』 第3回:「心を動かす計算機をつくる」 ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 号外 ☆
2014-12-31 11:10220pt
【ほぼ惑ベストセレクション2014:第1位】現代の魔術師・落合陽一連載『魔法の世紀』 第3回:「心を動かす計算機をつくる」
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2014.12.31 号外
http://wakusei2nd.com
2014年2月より約1年にわたってお送りしてきたメルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」。この年末は、200本以上の記事の中から編集長・宇野常寛が選んだ記事10本を、5日間に分けてカウントダウン形式で再配信していきます。栄えある第1位は、現代の魔術師・落合陽一さんの連載『魔法の世紀』の第3回、「心を動かす計算機をつくる」 です!(2014年9月17日配信)
これまでのベストセレクションはコチラ!
▼編集長・宇野常寛のコメント
この『魔法の世紀』に関しては、うちの2015年の目玉企画になると思っています。
メディアについて語ることがイコール社会について語ることだった時代――つまり「映像の世紀」は、この先、情報技術がディスプレイの外に進出していくことによって終わっていく。そして今や我々が突入しつつある次の時代を、彼はここで「魔法の世紀」と呼んでいるわけです。
そしてこの落合くんの『魔法の世紀』という連載は、ビッグデータで記録される人間のライフログや、モノに仕込まれるセンサーといったかたちですべてのものが繋がっていく時代に、人間は何に感動し社会はどう形成されていくのか、という根本的な問いに対して、政治史や社会史ではなくコンピューター史から描き出していくところが非常にユニークな論考だと思います。
研究者としてではなく理論家としての落合陽一が考えていることは、あまりにも大きな示唆を僕らに与えてくれる。彼の初めての著作を世に送り出すということが、編集者としての宇野常寛の2015年の最大の仕事のひとつだと思っています。こちらもぜひ、続きを楽しみにしていてください!
▼落合陽一による『魔法の世紀』
前回までの連載はこちらから
■「流れよ我が涙、と計算機は言った」
前回の終わりに、ここからは「魔法の時代」における「メディア・アート」の変容について考えていくと宣言しました。ここまでは僕の作品や研究の紹介や、研究者的側面からコンピュータと人間の関わりについて論じて来ましたが、ここからは僕のアーティスト的な側面から、コンピュータとアート文化の関係について論じていくことになるでしょう。
いきなりですが、皆さんは計算機に心を動かされたことはありますか?
ギョッとする言い方かもしれませんね。「心を動かす絵を描く」や「心を動かす映画を撮る」なら普通の印象を受けるのに、「心を動かす計算機をつくる」には違和感を覚えるのはなぜでしょうか。計算機という言葉と、我々の感性がかけ離れている印象を持つからでしょうか。それとも計算機に心を動かされるということに抵抗感があるからでしょうか? 実は、ここでの計算機(コンピュータ)はメディアアートのことを指しています。ですから、僕は何度も計算機に心を動かされてきました。常に多感な年ごろの僕は、何度かコンテンツ装置(メディアアート)で泣いたことがあります。
例えば、以前「うなずきん」というおもちゃがありました。ダルマのような小さな人形に話しかけると、相づちを打つように頷いてくれるのです。このおもちゃで遊ぶためには、独り言を言い続けるしかありません。そうなると、独白装置として機能する訳です。懺悔をきいてくれる自動神父さん、みたいなものです。
▲うなずきん NatureVer. Rainbow
人間は、何を言っても肯定してくれる存在を欲する生き物です。しかし、そういう存在と出会うことは滅多にないでしょう。恋人でも夫婦でも男女に意見の相違はつきもので、完全にわかりあえる友だちですらも全てを肯定してくれることは少ない。でも、この小さな機械は全てを肯定してくれるのです。気がついたら真面目に話し込んで、なぜか機械に心を許して、そして泣き出す自分がいました。実に不思議な体験でした。
人はコンテンツで涙したり笑ったりしますが、メディアで笑ったり泣いたりはしないと考える人は多いでしょう。映画館に入った瞬間に泣き出す人、一眼レフを見て涙が止まらなくなった人、本の表紙に触ると泣き出してしまう人……そういう人は、だいぶおかしな人間と見られることだと思います。さすがに僕もそんな体験はありません。なぜなのでしょうか。
実際、例えば自分が乳幼児だったときのことを思い出してみましょう……いや、無理でしょうか。では、周りの乳幼児のことを思い浮かべてみてください。
おもちゃを使って大人が乳幼児をあやしているとき、乳幼児は簡単に機械に泣かされていると気づくはずです。彼らは、泣かされるだけでなく、機械に笑わされたりもします。しかし、乳幼児はテレビのコンテンツを見て笑ったり、泣いたりすることは少ないはずです。それは、乳幼児が文脈やストーリー自分の感情で涙するわけではなく、原初的な快/不快のような感覚で泣くことにあります。
僕は、現代の大人たちが乳幼児のようにメディアで涙したり笑ったりできないのは、彼らの生きてきた20世紀が「映像の世紀」だったからだと思います。「映像の世紀」とは、コンテンツとメディアが分離していた時代です。しかし、今世紀はメディアとコンテンツの境目がどんどん曖昧になって行く時代なのです。映像の世紀は本質的にメディアとコンテンツの関わり方を定めていきましたが、それがどう定められて、そして今どう変わろうとしているのか。
今回は、これを議論をしていきましょう。キーワードは、先程の乳幼児の例で出てきた「原初的な感覚」です。ここにはメディアアートの現在を巡る大きな問題が横たわっています。冒頭に記したように「魔法の時代」における「メディアアート」の変容について考えていく必要があるのは、このキーワードから見えてきます。
■「文脈のチェス盤の上から」
そのために、まずはメディアアートが登場した20世紀にメディアアートが置かれていたアート観を知る必要があります。それは、コンテンポラリーアートという潮流です。
コンテンポラリーアートとはなにか?
人によって意見は様々ですが、大枠のコンセンサスがとれるところは、さながら「文脈のゲーム」と化している点でしょう。例えば、日本の現代アーティストに村上隆さんという人がいますが、彼は国内芸術の文脈にある浮世絵やマンガ、アニメなどの平面性を再構成して、「スーパーフラット」という文脈を作り出すことで、世界的に評価されました。
奇麗な絵を見て「傑作だ!」と思う一般人の価値観に対して、コンテンポラリーアートはそうした感覚をゆさぶる作品に必ずしも高い評価を与えてきませんでした。一つには、写真技術の到来とともに、技巧的なもの(うまい絵、写実的な美しさ)が評価された時代は過ぎ去ったのが大きいでしょう。その結果として、従来の芸術観が崩壊してしまい、文脈による評価が高くなったとも言えます。これは20世紀美術の大きな潮流でもあります。
実際、美術史の教科書には、20世紀のコンテンポラリーアートを説明する際に、必ずマルセル・デュシャンの『泉』という作品が挙げられているはずです。男性用小便器を寝かせて置いただけのこの作品は、レディメイドの芸術の始まりだとか、現代アートの夜明けだとかと言われています。
なぜこんな作品が重要なのかでしょうか。それは、マルセル・デュシャンがこの作品を通じて、「これは芸術足るか」という問いを投げかけたからなのです。20世紀のコンテンポラリーアートとは「芸術の文脈そのもの」に対する問いかけそれ自体が文脈を形成する時代であり、この作品はその幕開けに相応しかったのです。
……少々、わかりにくいでしょうか。つまりは、「芸術表現とはなんだろうか」と考えた時代なのです。芸術表現のあり方それ自体を探求する試みこそが高く評価されていく流れが、20世紀には大きくあったのだと思っていただければいいでしょう。
その際に一つ大きな評価の基準となったのは、「西洋芸術史の中における文脈の構築」でした。例えば、アメリカの芸術家にジャクソン・ポロックという人がいます。彼は「抽象表現主義」と呼ばれる手法を代表する画家で、アクション・ペインティング(寝かせたキャンバスの上に絵の具を撒く)という独特の技法で、同時代にはモダンジャズのインプロビゼーションなどと比較されながら、ニューヨークのギャラリーを中心に高く評価されました。
この技法をコンテンポラリーアートの視点から見ると、彼の絵画は「絵を描く」という行為そのものの刷新になっています。それは「描くという芸術行為はキャンバスを打ち立てて、そこに描いて行くものだ」という「文脈」に対する大きな逸脱なのです。この立場からは、彼は独自の抽象絵画の世界を切り拓きながら、「文脈のゲーム」に新しいゲームを仕掛けてきた作家と言えるでしょう。
こうした世界では、やや単純化して言ってしまうと、「美しい絵を描くことなどよりも、新たな文脈を構築することの方が重要であり、感覚的なものは評価されにくかった」と言えます。そして、メディアアートも大きくはコンテンポラリーアートの一種として評価されることが多く、私たちが普段触れている映像装置というメディアに対する文脈への関わり方、つまり「文脈のゲーム」の中で評価されてきた面が強くあります。
以上が、美術史における教科書的な説明です。
しかし、別に写真の登場で不要になった技巧的な表現技術以外にも、心を動かすような表現は存在するはずです。とすれば、そうした軸が低く評価され、20世紀を代表的する潮流であるコンテンポラリーアートが「文脈のゲーム」になってしまったのはなぜなのかという新しい疑問が湧いてきます。
それに対する僕なりの解答は、まさに20世紀が「映像の世紀」、すなわちマスメディアの時代だったから、というものです。
そもそも、アートとアートでないものの境目を作っていたのは何だったのでしょうか。それは、美術館という制度の存在です。例えば、現代アートでは中心地にあるニューヨークのギャラリーが、現代アートの文脈を作り出しています。その周囲にいる専門家や画商のコミュニティの中で評価された現代アートは、高い値段でやり取りされます。彼らは、現在の資本主義市場の中心地である米国で、雑誌やテレビなどの様々なマスメディアと、その中で活動する批評家たちのような権威を上手に駆使しながら、アートの流れを生み出してきたのです。
もちろん、これもまた教科書に載っている程度の説明で、そもそも『泉』という作品の出展の中にその問いかけは含まれています。だから、ここではもう一歩踏み込んで考えます。そうした美術館の権威の源泉は、一体どこから生まれたのでしょうか。
結論から言えば、それは「鑑賞可能性」にあったと僕は考えています。
世界中でも限られた場所にしか存在していない美術館やギャラリーというスペースに、多くの人が鑑賞しにやってくる。その構造こそが、アートをアート足りえさせていたのではないでしょうか。つまり、一部の発信者の作品に注目が集まるような仕組みとしての「美術館」こそが、重要だったのではないかと思うのです。
しかも、その集客効果は、「映像の世紀」のマスメディア技術を抜きに語れません。ニューヨークのギャラリーの権威ある大きな声が、資本主義市場の中心地であるアメリカのマスメディアに乗せられて、世界中に届いてゆく。これによって、共通の文脈が共有され、権威の声は世界全体の文脈と合致することが可能になっていたのだと思います。
しかし、この「魔法の世紀」には、作品はそのようには受け取られません。なぜなら、インターネットが台頭してしまったからです。
■「島宇宙の共通言語を探して」
そこでは、誰もがあらゆるものを鑑賞できるようになりました。
例えば、現在TwitterやFacebookなどのメディアは、コンテンツに対する巨大な鑑賞装置――すなわち、大きな美術館として機能していると言えます。民主的かつ巨大なコンテンツ鑑賞空間がネットに広がっていていて、あらゆるコンテンツ(コンテンツ的なメディア装置も含む)が、万人によってキュレーションされ(=選び取られシェアされ)、万人によって鑑賞されているのです。
しかも、最近はメディアアートやインタラクティブ作品のプレゼンテーションに、映像が用いられ,それが広告などにも使われるようになっています。リアルな場でしか鑑賞できないスケール感、ディテイル、五感への表現などはあれど、やはり時間と空間を超えて誰もが鑑賞可能になったのも事実です。
何よりも重要なのは、これがメディアアートのみに留まる話ではないことです。最新のプロダクトもニュースもメディアアートも、メディア装置上のコンテンツを鑑賞する同様のプロセスで消化され、拡散されていくのです。世界中のありとあらゆるリアルの事物が、美術館に置かれた作品のような「鑑賞可能性」を持つ時代がやってきたのです。
その結果、たとえニッチな興味であったとしても、小さなコミュニティを保つことが可能になっています。
これまでメディアコンシャスの消失を語ってきましたが、それはマスメディアの相対化ももたらしたわけです。共通の文脈を展開するのは難しくなり、ニューヨークのギャラリーのような一部の権威者が文脈を制定することも、マスメディアがマスメディアとして機能しないために、不可能になりました。島宇宙としてバラバラになってしまった興味のコミュニティには、共通言語も共通文脈も存在しなくなり始めています。全員に受容される作品は、もはやつくりにくくなってしまいました。
こうした情報拡散を中心にした文化において、集約型である前世紀の権威者の威光は徐々に陰りつつあります。20世紀とは「代理表象」の時代でした。表現はマスメディアに乗る際に、感覚を代理する文脈に置き換えられ、文脈のゲームが戦わされたのです。しかし、魔法の世紀には、もう「代理表象」による文脈のゲームで戦うのは難しい。文脈のゲームプレーヤーは、実はロールモデルを失いつつある時代になっていると言えるでしょう。
■「人間という感覚装置の内と外」
こうした状況の中で、メディアアートは既存の芸術の枠組みから変わりつつあります。
具体的には、二つの道に分かれているように僕は感じています。一つは、「文脈のゲーム」として、20世紀の延長線上でメディア装置に関する文脈で戦う芸術。もう一つは、より「原初的な感覚」を対象とした芸術です。
1 / 2