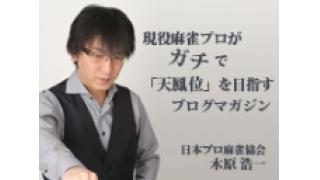-
九段坂奮闘記・158~159戦目
2015-02-18 12:00110pthttp://live.nicovideo.jp/watch/lv210274741本日はブログマガジン杯準決勝B卓、解説はタケオしゃんです。
話題の堀内本では、これを曲げるそうですね。一発裏祝儀1枚10000点相当の雀荘ならリーチします。でもほとんどのルールでは曲げないような気がしますが・・・・14、69待ちでリーチした時のアガリの比率、ツモ確率は同じとしても出アガリ確率は19の方が多くなるのは間違いないと思いますが、その比率は少し気になりますね。(1で出アガリ):(4で出アガリ)=6:4くらいの比率であれば「リーチ有利」といってもいいと思いますが実際はもう少し差がありそうな気がします。そのあたりも書いてくれると面白いですね。昨今はそういった戦略が支持を得ているのだとしたら僕のこういう打ち方は、完全に時代に逆行した打ち方ということになりますね。
-
九段坂奮闘記・154~157戦目
2015-02-17 12:00110ptラス目のリーチを受けて一発目、自分はクソ手、クソ受けのイーシャンテン見事なまでに安全牌はありません。さて、ここから何を切るか?全くその通りなのですが、テンパイ確率が低く、アガリ確率も低いその上点数状況的にも全く勝負するに見合わないような牌姿だと話は別です。この状況がまさしくその通り。ではここはどうするのかというと―― 無理やりベタオリを選択します。「困ったら2枚以上ある牌を打て!」「困ったら先に切ってある7sまたぎの無筋を打て!」これの複合技です。まだ7巡目と先は長いです。ここで3巡凌いでいる間に横移動や他の安全牌が増えることに期待する戦略が無理やりベタオリです。イーシャンテンを維持する価値が薄い場合「安全牌が無いから1pプッシュ」よりは幾分マシな選択でしょう。それでも手詰まりました。「困ったら2枚ある牌を打て!」作戦失敗の図です。こうなったらもう「一発で掴まされたよ~!」と負け惜しみでも -
鳳凰卓を斬る! vs仕掛けversion
2015-02-16 12:00110ptみなさまへお願い。記事の中で牌画を扱っているのですが 赤5m、赤5p、赤5s。機種によっては白抜きの長方形の空欄になり、表記されない場合があるようです。こういった件はニコニコヘルプに問い合せてみないとわからないのですがその際必ず聞かれるのが「お使いの機種名は?」です。機種がわかれば対応出来る場合もあるようです。同じように牌画が表記されない症状がある方は、お使いの機種名をできるだけ詳しく教えてください。ご協力のほどよろしくお願いします。仕掛けというのは、確実に一手進んだというサインでもあります。例えばトイツ落としやターツ落としは、不要なブロックを払ったというサインではありますが
-
危険牌先切りとその反例
2015-02-15 12:00110pt -
九段坂奮闘記・150~153戦目
2015-02-14 12:00110pt配牌がこうでした。ここから反射的にドラヘッド固定の打1sとしてタンヤオと役牌重なりの天秤に受ける人もいるのではないでしょうか?(牌図A)東が被ってしまうのは痛いです。しかしこのツモだって同じくらい痛いですよね?東と2s、引いてくる可能性は同じです。仕掛けられる牌姿のほうが価値が高いのは間違いないですが、1巡目この牌姿、このツモならば門前進行で十分いけそうです。短い時間で判断するのは難しいかもしれませんが裏目った時の牌姿をそれぞれ瞬時に思い浮かべて比較することですね。(牌図A)から打8mとする人もいるかと思いますが、それだけは止めましょう。8mと東が重なる可能性は同じです。8mが重なればタンヤオ本線で仕掛けるでしょう?つまり東と8mの重なりの価値は、この手牌においてほぼ同価値です。ならば現状ターツ不足の手牌では、重なり以外にも6m、7m、9m引きのターツ候補がある分、東と比較すると8mを残し -
九段坂奮闘記・147~149戦目
2015-02-13 12:00110ptカンチャン選択のシーンです。下家がマンズかもしれない、しかし断定はできないような捨て牌相。どちらを選択するにも一長一短あるのですが、ここは9mを打ってみた。2枚切れの8sですが、リーチで全く問題ありません。しかしこの時は下家に鳴かれそうだからと、一発抽選を受けるために1巡回してやろうかな――とまあホンの気まぐれ、心の贅肉ともいうべき行為が結果的に3枚目の8sを打たれる悲劇を生み、雀頭が暗刻になる幸運を呼び込んだ。ふ、今度は待つ理由が全くないぜ!ほんの小さな気まぐれが、こんな結果を生むこともある。ここが麻雀のつまらないところでもあり、面白いところでもあるのだけど。6000オールの次局、9sをポンして打4pの図。こんなことをしていたら、またまた渋川先生に怒られそうですがでも僕は思うんですよね。この点数状況でおいたをしたとしても、生涯成績には何らが影響ないのです。アガリ確率10%の1500点や2 -
第4回ブロマガ杯準々決勝結果!
2015-02-12 12:00第4回ブログマガジン杯は、準決勝進出者16名が決定しました!準決勝の予定は、随時この記事に追記していきます。準決勝A卓・16日21:00~ 解説者・どんよく(近藤千雄)http://live.nicovideo.jp/watch/lv210273845準決勝B卓・18日21:00~ 解説者・タケオしゃん(6代目天鳳位)http://live.nicovideo.jp/watch/lv210274741準決勝C卓・25日20:00~ 解説者・gousi(第1回ブロマガ杯優勝)http://live.nicovideo.jp/watch/lv210276067準決勝D卓・22日20:00~ 解説者・比嘉秀仁http://live.nicovideo.jp/watch/lv210387092以下準々決勝の牌譜とタイムシフトです。準々決勝A卓1回戦 D:goshikku(+43.0) A:伊咲(- -
九段坂奮闘記・144~146戦目
2015-02-11 12:00110pthttp://live.nicovideo.jp/watch/lv206719029本日はブログマガジン杯準々決勝C卓、D卓。19時からです。お間違えなく~。門前リーチ狙いで役牌から切り出します。234の三色願望を抱きつつ、打8mとしますがというわけで、これは少し3色成就は難しそうです。この時に考えることはそれだけではありません。少なくとも事前の準備 ツモ→打 ツモ→打これくらいのイメージは頭に描いておきましょう。まだあの程度ではオリませんね。当然勝負、両脇がオリ気味の状況での現物待ち。山にある可能性も十分にあります。即リーチでいいのですが、今回は3列目まで待ってみることにしますそれでも出なかったら山にいる、つまり――終盤になればなるほどツモ確率が高まってるとみて、ツモ切りリーチを発動します。あ・・・大事なオーラス。1pは既に4枚切れで、白も枯れている。形式テンパイを取る価値がある局面 -
九段坂奮闘記・139~143戦目
2015-02-10 12:00110pt -
鳳凰卓を斬る! vsリーチversion2
2015-02-09 12:00110ptチーして形式テンパイを狙い1pを切るのですがこれは完全に何かの悪い影響を受けているのではないかと思います。東1局に1500点を獲得した場合の最終着順は○%上昇するというデータ(データA)このデータに基づいて選択判断するのは一見正しそうに見えるのですが終盤リーチ、あの河の無筋に対して1pを切った場合の放銃確率データ(データB)VS親リーチの放銃素点のデータ(データC)この3つのデータを元に判断するとして、参考にすべきデータの優先順位は――(データB)>>(データC)>>>>>>>>(データA)ではないでしょうか?>顧客満足度を上げるサービスの向上。>射幸心を煽るような企画の立案。>快適な環境を提供するために店内清掃の強化。お店の売上を上げるためにはどうすればよいか?そりゃ掃除は大事ですよ。だからといって掃除に力を入れたところで売上向上には繋がらないでしょう?目的を達成するための手段選択の優先