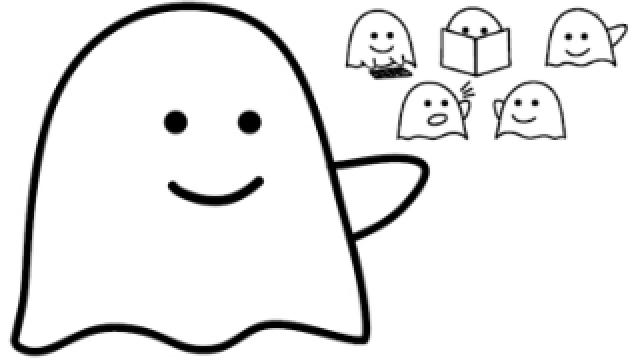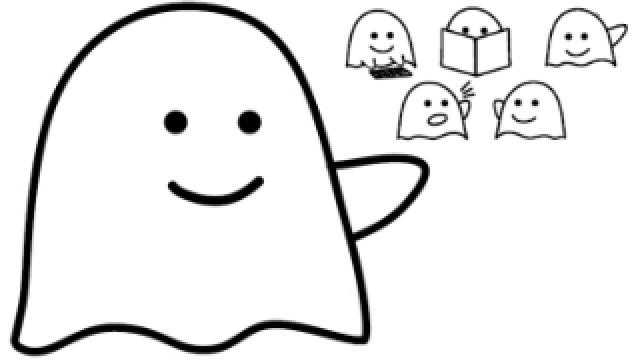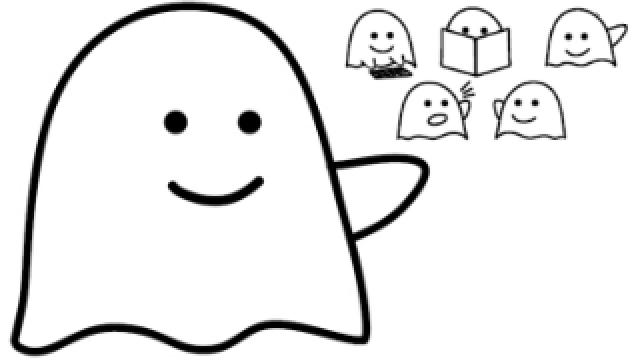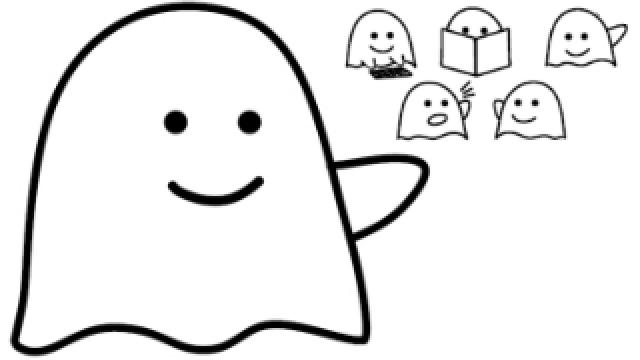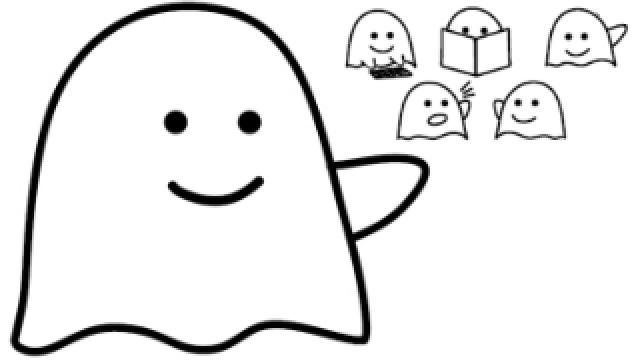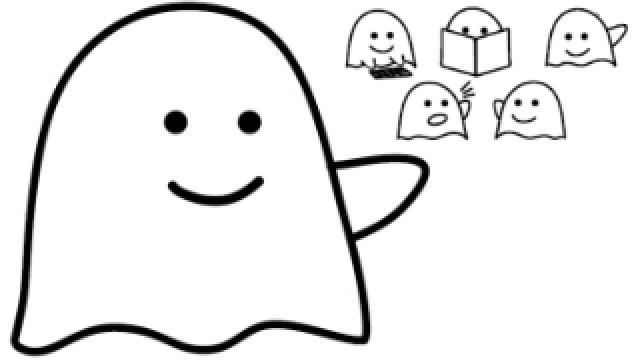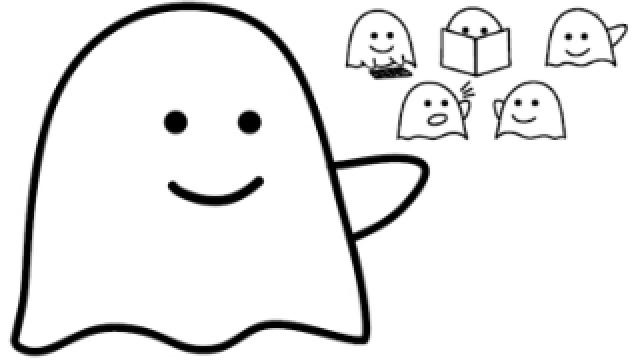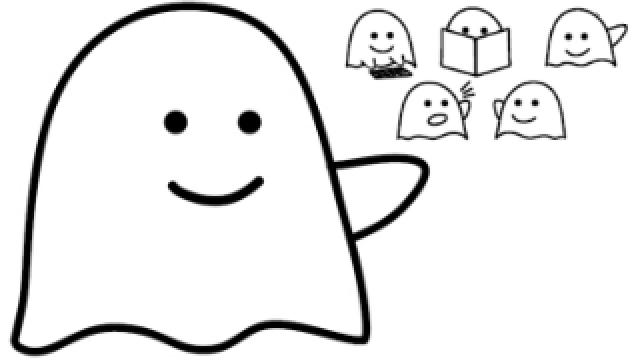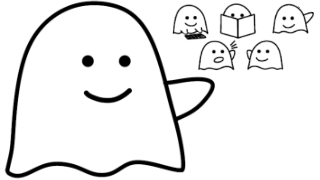-
Vol.283 結城浩/note(ノート)からの配信/クリエイタと独自ドメイン/中学生からのインタビュー/
2017-08-29 07:00220ptVol.283 結城浩/note(ノート)からの配信/クリエイタと独自ドメイン/中学生からのインタビュー/結城浩の「コミュニケーションの心がけ」2017年8月29日 Vol.283
はじめに
おはようございます。結城浩です。
いつも結城メルマガをご愛読ありがとうございます。
* * *
note(ノート)の話。
現在この「結城メルマガ」は、 「まぐまぐ!」と「ブロマガ(ニコニコチャンネル)」 という二つの配信プラットホームから配信しています。 内容と購読料金はどちらも同じです。
2017年の9月から新たに、 「note(ノート)の継続課金マガジン」 という形式でも配信を開始することにしました。 こちらも、内容・購読料金ともに同じです。
「まぐまぐ!」と「ブロマガ」での配信は、 これまでとまったく同じように継続されますので、 「結城メルマガ」をすでに講読してくださっている人には、 何の影響もありませんし、手続きも必要ありません。
新たに「note(ノート)の継続課金マガジン」 での配信も行おうと思った理由の一つは、 購読者さんの「選択肢」を増やそうと思ったからです。
(1)「まぐまぐ!」で講読する場合、 テキストメールと、epub(結城が作ったもの) で読むことができます。
(2)「ブロマガ」で講読する場合、 整形したテキストメールと、Webと、 epub(プラットホームが用意したもの) で読むことができます。
(3)「note(ノート)の継続課金マガジン」で講読する場合、 HTMLメールと、Webと、 epub(結城が作ったもの)で読むことができます。
同じ文章を読む場合でも形式が違えば雰囲気も違います。 多様な形式を用意しておけば、 購読者さんの読みやすい形式を選ぶことができます。 それが「選択肢」を増やすということの意味です。
また、note(ノート)で講読する選択肢を用意することで、 これまであまりリーチできていなかった方にも 「結城メルマガ」をアピールしたいという思いもあります。
試し読みのサービスとして、 「まぐまぐ!」では初月無料、 「ブロマガ」ではひと月分の料金で二ヶ月講読可能、 を提供しています。「note(ノート)」では、 「まぐまぐ!」と同様に初月無料という形式にします。 これは発行者(結城)の設定で決められます。
「note(ノート)」を初月無料にしましたので、 すでに「まぐまぐ!」や「ブロマガ」で結城メルマガを講読している方でも、
《note(ノート)でも、試しにひと月読んでみるか》
という選択が可能になります。 すでに購読者になっている方でも、ご興味がありましたら、 検討してみてください。
「結城メルマガ」が「note(ノート)の継続課金マガジン」 でも講読可能になるのは、2017年9月1日からです。 講読可能になったら、あらためて告知いたします。 現在は【プレ告知】として情報を公開しています。
◆【プレ告知】結城メルマガをnote(ノート)の 継続課金マガジンからも配信予定(2017年9月から) https://note.mu/hyuki/n/n0ae97288d626
なお、今回の継続課金マガジン対応と合わせて、 note(ノート)の「独自ドメイン対応」も行う予定です。 創作活動と関連させて、どんなことを考えているかは、 後ほどお話しいたします。
* * *
しゃれた言い回しの話。
数学者を機械にたとえた、
「数学者はコーヒーを定理に変える機械」
という言い回しがあります。
「数学者はコーヒーを定理に変える機械」 というのはしばしば数学者エルデシュの発言と思われていますが、 実際にはアルフレッド・レニイのものだそうです。 上原隆平先生にご指摘いただきました。
ともあれ「数学者はコーヒーを定理に変える機械」は、 数学者の仕事である「定理を証明する」という仕事をうまく表した言い回しだな、 と思います。
生物学的には「ブドウ糖を定理に変える機械」とも言えるかな、 と思いました。実際に頭を動かしているのはブドウ糖ですし……。 でも、「ブドウ糖」では表現としておしゃれじゃないですね。
そんなことをつぶやいていたら、戀塚昭彦さん(@koizuka)から、
「(A)は(B)を(C)に変える機械」みたいに色々適用できるなw (A,B,C) = (ハッカー, レッドブル, コード) みたいな
と一般化したリプライをいただきました。
なるほど!
あなたは、自分のことを、
「何を何に変える機械」
とたとえるでしょうか。
* * *
フィードバックの話。
最近できた新しいカフェに妻と二人でランチに行きました。
いつもいく店Aが近くにあるけれど、 せっかくなので新しい店Bに行こうと思ったのです。
ところが失敗。
美味しくなくて、しかも値段が高かったのです。 いつもの店Aの方が安くて美味しいので、 もうこの店Bには来ないよねえ…と二人で話しました。 残念。
そこで思ったのです。
おそらく私たち夫婦は、あの店Bには行かないでしょう。 でも、私たちは、
店Bにどうして行かなくなったかを、 わざわざ店主に伝えたりはしません。
「この店は新しくできたので期待したけれど、 美味しくないし、コスパ悪いのでもう来ないです」 そんなことをわざわざ伝えたりはしません。
多くの人がそうだと思います。 ある店が不味いからといって、わざわざ伝えたりしない。 ただ、その店に行かなくなるだけです。
味は人の好みがあるし、値段との兼ね合いも人によるでしょう。 私がイマイチと思っても、そうでない人がいるかもしれません。 でも、もしも、多くの人が「ここにはもう来ない」と判断したら、 早晩経営は苦しくなるでしょう。 そしてその来なくなった人のほとんどが、 「なぜ来なくなったか」という理由を店に伝えません。
経営者にとって、 フィードバックをもらうことは大事です。
フィードバックがなかったら、 お客さんが来ない理由を必死で想像するしかないからです。
サービスを提供する側にしてみれば、 「ほめてくれるお客さんの声」はありがたいものです。 ほんとうに励みになります。 でも、それにも勝るとも劣らない価値があるのが、 「不満を感じたお客さんの声」です。 「ここがよくない」や「ここが変わればいいのに」や 「こうしてほしかった」という不満の声は千金に値します。
必ずしもその声に反応する必要はありません。 またその声をうのみにする必要もありません。 しかし、そういう声があることを知るのは、 サービスを提供し続けていく上でとても大切なこと。 それは「顧客を知る」ことに直結しているからです。
結城は本を書いており、いわば読者に対するサービス提供者です。 ですから、毎日のようにTwitterでの反応を読んだり、 メールで送られてくる感想文を読んだりするのは当然の活動です。 応援メッセージはほんとうにうれしいものですが、 そうではない意見や感想や不満もていねいに読んでいます。 そこで提示された情報のすべてに従う必要はないと思っていますが、 その情報を知ること自体はとても大切だと思っています。 それは「読者を知る」ことに直結しているからです。
結城は本を書く上で、 《読者のことを考える》という原則を守ろうと思っています。 そして、そのためには「読者を知る」ことが必須なのです。
* * *
ドラマのようなシーンの話。
ある夜のこと。場所は駅のホーム。
背広男性と女性のカップルが、 いかにも別れがたい様子でシリアスにハグしている。
まるで恋愛ドラマの一シーンのようなので、 つい見とれてしまう。
ところが、あまりにも深く抱き合っていたため、 いざ離れようとしたら二人の傘とバッグとカバンが絡み合って、 ハチャメチャになってしまった。
ほぐそうとする二人は、 途中からゲラゲラ笑い出してコメディの一シーンへと場面転換。
何だか楽しい一幕でした。
* * *
それではそろそろ、 今回の結城メルマガを始めましょう。
どうぞ、ごゆっくりお読みください!
目次
はじめに
クリエイタが独自ドメインを持つ意味 - 仕事の心がけ
『数学ガール』執筆に関する中学生からの質問 - Q&A
おわりに
-
Vol.281 結城浩/おっくうな作業/結婚と子育てと - Q&A/
2017-08-15 07:00220ptVol.281 結城浩/おっくうな作業/結婚と子育てと - Q&A/結城浩の「コミュニケーションの心がけ」2017年8月15日 Vol.281
はじめに
おはようございます。結城浩です。
いつも結城メルマガをご愛読ありがとうございます。
* * *
Kindleセールの話。
先週の火曜日まで実施されていた、 「SBクリエイティブ50%ポイント還元セール」 は無事に終了いたしました。
今回の50%ポイント還元はたいへん大規模なものでしたし、 多くの注目を集めたようです。 アクセス解析をしていたのですが、 ふだんの数十倍から百倍のオーダーのアクセスがありました。
アクセスが特に多かったのはセールの初日とセールの最終日。 グラフの両端が大きな山になるほどでした。興味深いですね。
結城の書籍もたくさんお買い上げいただき、 また応援もいただきました。Kindle数学書ランキングで、 1位から14位までを占めるほどの人気でした。感謝です!
Twitterでの反応も多かったですね。 「ふだんから数学ガールが気になっていたけれど、 買うほどではなかった。 でも今回のセールをきっかけに購入してみようと思った」 という方がけっこうな人数いたと感じています。 つまり、セールが購入の「後押し」になったということでしょう。
そう考えますと、 普段からの宣伝や書籍紹介がとても大事だということがわかりますね。 たとえ宣伝した直後に売れなくても、 セールなどのきっかけによって購入に結びつくからです。
ともあれ、応援ありがとうございます!
* * *
Web連載の話。
cakes(ケイクス)でのWeb連載「数学ガールの秘密ノート」は、 新シーズン「関数を手がかりに」が始まっています。
◆第202回 最初に最後を考えて(後編) https://bit.ly/girlnote202
第202回(第1章後編)は関数の定義が題材です。
結城が高校生のとき、数学の先生から、 関数の定義を暗記させられたのをいまでも覚えています。 上の記事に書いたものとほぼ同じで、 「二つの集合があって……」から始まる定義です。
何でこんなものを暗記するんだろう、 と当時は思いましたが、 いまにして思えばありがたい教え方だったと思っています。
といっても、 機械的に暗記させられたのが嬉しかったわけではありません。 そうではなくて、
暗記するに値するほど、 《関数の定義》は大事なんだな
と学べたことがありがたいのです。
ここにはやや微妙な問題が絡んできます。 数学と暗記の関係です。
何かを丸暗記するのはいいけれど、 その意味内容をまったく考えないとしたら、 その暗記は意味がありません(数学の場合)。
でも丸暗記を忌避するあまり、 すべてを考えようとするのもいささか的を外しています。
むしろ、いったん暗記してしまうことで、 いちいち本を見なくてもその数学的概念について考えることができる、 その点に目を向けたほうがいいように思います。
もちろん、意識的に「暗記しよう」なんて思うのではなく、 その数学的概念について考えているうちに自然と覚えてしまうのが、 理想といえば理想なのかもしれませんけれどね。
結城が思うのは「暗記だから悪」や、 逆に「考えるのは時間の無駄だから暗記せよ」 のような極論に走るのはよくないなあ、ということです。 極論や、前提条件をすっとばした断言は危険です。
断言した方が教えやすいという一面はあります。 でも、まあ、それは教師の側の都合ですね。 生徒の側としては、教師のいうことを素直に聞きつつも、 「それは違うのでは」 という点はスルーするくらいがちょうどいいのかもしれません。 こういう日和見的な考え方は人気がないのですけれど。
学習と暗記の関係はそれほど単純ではありません。
* * *
自分の態度が自分の環境を決める話。
「人の良いところを見つけ出してほめる人」 のまわりには、 そういうことが好きな人が集まる。
「人の悪いところを見つけ出してけなす人」 のまわりには、 そういうことが好きな人が集まる。
自分のまわりを見渡して、 自分の環境がどうなっているかをチェックするのは大事かもしれません。 それはふだんの自分の態度をチェックすることにつながるからです。
世の中は○○だ!と呪詛する気持ちもわかるけれど、 もしもそれが自分のまわりだけだとしたら、 ちょっと恐い話です……
* * *
過度の一般化の話。
数学では「すべて」と「存在する」の区別が大切な場面がよく出てきます。
実は、人を評価するときでも、 その区別は大切かもしれません。 つまりそれは、
「あの人はいつも〇〇だ」と、 「あの人は〇〇なときがある」
とを区別するという意味です。
人というものはパターンを見つける能力が高く、 自分が体験したことを重要視してしまい、 しかも記憶を持っています。ですから、
「あの人が〇〇した」
という場面を《数回》見ただけで、
「あの人はいつも〇〇する」
と考えてしまうことが多そうです。 《数回》が《いつも》に変化しちゃうのですね。
でも、その推論は本当に正しいのでしょうか。 もしかしたら、誤った一般化ではないでしょうか。
逆も考えられます。 自分がうっかり〇〇したとき、 他人から「この人はいつも〇〇だ」と思われてしまわないだろうか。 そのような心配をすることもあるでしょう。 人の目を気にして自分の身を正す、 というくらいならば結構ですけれど、 人の目を気にし過ぎて活動が萎縮することはないでしょうか。
社会のあり方や組織論のような大きな話ではありません。 自分個人のこととして考えるのは意味があります。 誰かに対して評価を下すとき、
「自分は何を根拠にその評価をしたんだろうか」
と改めて考えるのは大切です。
「判断の根拠となった事象のサンプル数は何個か」
と問うのもいいですね。
そういえば友人の一人に、 この問いが大好きな人がいたのを思い出しました。 「△△な人は○○なんだぜ」という話を耳にするたびに、
「その話、サンプル数いくつ?」
と問い返すのです。いまにしてみると、 あの問いは大事だったんだな、と思い返します。
サンプル数が少ないのがすべて悪というわけではありません。 個人的な体験は多くの場合、サンプル数は《1》ですし。 でもサンプル数を確かめないのは賢明ではないですね。
* * *
ネギとオーダーの話。
先日、台所で細いネギを刻んでいました。 包丁を使って、ネギの端からトントントン……と。 わかりますよね。
家内はそんな私の包丁の使い方を見るに見かねて 「こうするのよ」と教えてくれました。
ネギを中央で半分に切り、 二つになった束を重ねる。 さらに中央で半分に切り、 二つになった束を重ねる。 それを繰り返していく。
あっという間に切り終わったのを見た結城は、 O(n)とO(log n)の違いに思いを馳せていました。
大ざっぱにいえば、 O(n)というのはデータサイズをnとしたとき、 十分大きなnに対して、たかだかnの定数倍以下の手間になるという意味です。 「端から順番にやっていく」という方針だとO(n)になることが多いですね。
それに対してO(log n)というのは、 たかだかlog nの定数倍以下の手間になるという意味です。 「二分割を繰り返していく」という方針だとO(log n)になることが多いでしょう。
結城の方法ですと、 ネギを端から1024個に等分割するためには、 1023回包丁を使う必要があります。 それに対して家内の方法では、 なんと、たった10回で1024個に等分割できるのです(!)
1→2→4→8→16→32→64→128→256→512→1024
このような「手間を見積もる」アイディアが、 アルゴリズム解析の根底にあります。 詳しくは以下の本をどうぞ!
◆『数学ガール/乱択アルゴリズム』 http://www.hyuki.com/girl/random.html
* * *
それではそろそろ、 今回の結城メルマガを始めましょう。
どうぞ、ごゆっくりお読みください!
目次
はじめに
再発見の発想法 - Checksum(チェックサム)
おっくうな作業に着手したときに要注意 - 仕事の心がけ
限界はどこにあるのか - 本を書く心がけ
結婚と子育てと - Q&A
おわりに
-
Vol.279 結城浩/読書感想文のテンプレート/「頭がいい人」について/これだけは負けないと思うこと/
2017-08-01 07:00220ptVol.279 結城浩/読書感想文のテンプレート/「頭がいい人」について/これだけは負けないと思うこと/結城浩の「コミュニケーションの心がけ」2017年8月1日 Vol.279
はじめに
おはようございます。結城浩です。
いつも結城メルマガをご愛読ありがとうございます。
もう八月ですね……「夏本番」といえる暑さがやってきました。
暑い日でも、できるだけ外を歩く時間を作るようにしています。 一つは健康のためで、もう一つは仕事のためです。
「身体を動かすことは文章を書くのに役立つ」 ということは経験上わかっています。 単に血行がよくなって、 頭に酸素がたくさんまわるからかもしれませんけれど、 理由はまあなんでもいいでしょう。
自分の身体に刺激を与えることで、 自分の仕事(特に文章)にも刺激が加わるのを感じます。
ということで、暑い中、汗を流しながら、 せっせと歩くように心がけているのです。
* * *
「ロバ耳」の話。
結城は「ロバ耳」というWebサイトを20年間運営してきました。
◆Webサイト「ロバ耳」 http://www.hyuki.com/roba/
◆Webサイト「ロバ耳」(スクリーンショット)
どうも調子が悪いというとき、 友達としゃべったり、メールを書いたり、 あるいはSNSに書き込んだりすると、 ちょっと気分がよくなることがあります。
誰かにメールを書いて送信した時点で (つまり、相手からのアドバイスや共感をもらう前に)、 気分がよくなっているという現象もよくあります。
だとしたら、もしかして
きちんと読まれることは保証されるが、 返事は絶対にこない
という形式のメールにも意味があるんじゃないだろうか。 そんなことを、結城はずっと昔から考えていました。
20年前のWeb日記で、 こういう企画には何という名前がいいだろうか、 という質問を提示したところ、複数人から、
「ロバの耳」
という名前がいいという案をもらいました。 そのような経緯を経て、 この「王様の耳はロバの耳」(ロバ耳)が誕生したというわけです。
「ロバ耳」で結城が定めたルールは以下の4個です。
ルール0.誰でも、何でも自由にお話しください ルール1.あなたが話すことを結城はていねいに聞きます ルール2.結城は返事をしません ルール3.あなたが話すことは公開されません
実際には「話す」というのは、 結城が用意したWebフォームに書き込むという意味で、 「聞く」というのは、 結城に送られてきたその書き込みを読むという意味です。
送られてきた書き込みを結城は読むだけです。 その内容は誰にも言わないし、 書き込んだ人にも返信したりしません。
ただ、それだけのサイトなのですが、 「ロバ耳」が誕生した1997年7月31日以来、 結城の想像を越えた多くの方から利用いただくこととなりました。
今回「ロバ耳」を終了するのは、 一つは結城自身のキャパをオーバーしているためで、 もう一つは20年目という機会を節目としたいためです。
正直、20年も続くことになるとは思っていませんでした……
流れとしてはここで「ロバ耳」の思い出話を書くところですが、 このWebサイトの性質上、それは不可能です。
ということで、ご利用くださったみなさん、 ありがとうございました。
* * *
留年と進捗遅れの話。
京都大学のカウンセリングルームのWebサイトに「留年について」 という文章があります。 以前も見たことがあるのですが、先日再読してとてもよかったのでご紹介。
特に「学生さんが一度留年して、それがさらなる留年を生むという悪循環」 について書かれた部分は、学生さん以外でも参考になると思います。
◆留年について-カウンセリングルーム(京都大学) https://www.gssc.kyoto-u.ac.jp/counsel/ryunen.html
項目だけ抜粋しましょう。 以下が「悪循環に陥るパターン」だそうです。
(1)留年を家族や友人に隠そうとする (2)一挙に挽回しようとする (3)日々の楽しみを自分に与えない (4)卒業しなければ生きていけないと考える (5)時期尚早に「来年からがんばろう」と考える (6)自分は他の学生より明確に劣っていると考える
先ほどのWebページには、 各項目について丁寧な解説が書かれています。
ところで、この「悪循環に陥るパターン」というのは、 進捗が進まないクリエイタが陥る危険性にも当てはまりそうです。 たとえば、以下のように読み替えてみましょう。
(1)遅れを編集者に隠そうとする (2)一挙に挽回しようとする (3)日々の楽しみを自分に与えない (4)〆切にまにあわなければ生きていけないと考える (5)時期尚早に「次の作品からがんばろう」と考える (6)自分は他のクリエイタより明確に劣っていると考える
そういえば、結城も最初の本を書いているとき、 これと似たような心境に陥りました。危険です。 とっても危険です。 そのときは担当編集者からのアドバイスに従うことによって、 危険を脱することができました。
クリエイタ系の人の中には、 繊細な心を持ち、潔癖な性格の方もいらっしゃいます。 その心とその性格のゆえに生まれる作品というものもありますが、 進捗遅れの「悪循環に陥るパターン」にはまる危険性も高いです。 ぜひ、ご注意していただきたいと思います。
* * *
高校生の活躍の話。
国際化学オリンピック、国際数学オリンピック、国際物理オリンピックで、 日本の高校生が活躍しているようすが記事になっていました。 以下、高校生新聞onlineの記事をご紹介。
◆国際化学オリンピック 日本代表全員がメダル 坂部圭哉君が2年連続「金」、3人が「銀」 http://www.koukouseishinbun.jp/articles/-/2028
◆国際数学オリンピック 髙谷悠太君(開成高)が世界1位 日本代表全員がメダル http://www.koukouseishinbun.jp/articles/-/2229
◆国際物理オリンピック 渡邉明大君が世界1位、3年連続金メダル 日本代表は金2銀3 http://www.koukouseishinbun.jp/articles/-/2230
* * *
表記法の話。
先日「サイゼリヤ」がネットで話題になったとき、 以前から気になっていたことを思い出しました。
気になっていたことというのは、 店名が「サイゼリ《ア》」ではなく「サイゼリ《ヤ》」になっていること。
日本には「そっちが正式名称なんだ!」と驚く名前がいくつかあります。
結城が気づいていたのは、
サイゼリヤ(サイゼリアじゃない) キヤノン(キャノンじゃない) 日経ソフトウエア(日経ソフトウェアじゃない)
くらいでしたが、 いろんな方から意外な表記をたくさん教えていただきました。 以下、その一部です。
オンキヨー(オンキョーじゃない) キユーピー(キューピーじゃないんだ!) シヤチハタ(シャチハタじゃないの?) 富士フイルム(富士フィルムだと思ってた…) 文化シヤッター(文化シャッターでもないし、文化シヤツターでもない!)
おもしろかったのは、
函館どつく
です。函館を「どつく」わけではなく函館ドックのようです(造船メーカー)。
* * *
そのアカウントはどんな人?の話。
Twitterを眺めていると、ときどき 「思わずリツイート(RT)したくなるようなおもしろツイート」 が流れてきます。でも、RTした後で、
「結城さん、さっきのは《パクツイBOT》による 《パクリツイート》でしたよ」
と教えていただくことがあります。
つまり、こういうことです。
(1)誰か(A)が非常におもしろいツイートをする。
(2)パクツイBOTなどと呼ばれるアカウント(B)が、 そのツイートの内容をパクって、 あたかも自分のものであるかのようにツイートする(パクリツイート)。
(3)パクリツイートを見た人が「これおもしろいな!」といって、 パクリツイートとは知らずにRTして拡散する。
(4)オリジナルのツイートをしたAではなく、 パクリツイートをしたBがフォロワーを増やす。
パクリツイートを拡散するのは好ましくありませんけれど、 自分が見ているツイートがオリジナルのツイートなのか、 それともパクリツイートなのかを見極めるのは難しいものです。
ツイート単体での見極めは難しいですが、 パクリツイートをしているアカウントを見分けることは、 それほど難しくないかもしれません。 少なくとも確信犯的にパクツイBOTを続けているアカウントはわかりそうです。 というのは、
そのアカウントが、 他の人からどんな「リスト」に入れられているか
を調べることができるからです。 多数の人から「パクツイBOT」や「パクリ」 などという名前のリストに入れられていたら、 パクツイBOTである可能性が高いでしょう。
確認方法はアプリで異なりますが、 iPhoneのTwitterクライアントの場合、 そのアカウントのプロフィールページから歯車をタップして、 →「リストを表示」→「追加されている」タブで調べます。
アプリでのUIの違いはありますが、 要するに「@ユーザ名」がどんなリストに追加されているかは、
https://twitter.com/ユーザ名/memberships
というURLにアクセスすればわかります。 たとえば、結城浩(@hyuki)の場合には
https://twitter.com/hyuki/memberships
というURLを表示すればいいですね。
ちょっと時間があったので、 そのアカウントのプロフィールページやツイートを表示した状態から、 「そのアカウントはどんなリストに追加されているか」 を調べるブックマークレットFameList.jsを作りました。
◆TwitterでパクツイBOTか否かを調べる方法 (FameList.jsで「そのユーザが登録されているリストページ」を確かめる) https://snap.textfile.org/20170725150257/
厳密には「パクツイBOTか否か」を調べているわけではないのですが、 当該アカウントが「他人からどんなリストに入れられているか」 は有益な情報になるでしょう。
ちなみに、 結城のアカウントが入っているリストを名前が多い順に並べてみました。 こんな感じです。
43 math 37 IT 34 science 30 tech 29 数学 27 famous 25 My 23 engineer 20 it 17 twizard-magic-list 17 programmer 17 dev 15 book 14 writer 13 programming 12 developer 12 celebrity 11 author 10 list 10 geek 10 fav (以下略)
https://gist.github.com/hyuki0000/43c35992a0b43761336f9542926bc1a8
なるほど。
* * *
親子の話。
よく晴れたある日のこと。
結城が駅に向かって歩いていると、 リュックを背負った親子(父と娘)らしい二人が前を歩いています。 これからきっと「プチお出かけ」なのでしょう。
はっきりとはわかりませんが、背丈から想像して、 娘さんは小学五年生くらいに見えます。
何ということもなしに二人が歩くのを後ろから見ていると、 お父さんの方の手が少しずつ娘さんの手に近づいていきます。 どうも、お父さんは娘さんと手をつないで歩きたい様子。
デートで手をつなごうとしている男女を見てるみたいに、 私のほうがどきどきしてきました。
娘と二人、手をつないで歩く休日へ……
お父さんが手を伸ばして、ようやく手が触れようとした瞬間。 娘さんに(うざいな)という感じに振りほどかれていました。 お父さんは再挑戦せず。
あのくらいのお年頃になると、 親と手をつないで歩くというのは難しいのかもしれませんね。
お父さんの失意の胸の内を想像して、
(お父さん、ガンバ…!)
とエールを送ってしまいました。
* * *
それではそろそろ、 今回の結城メルマガを始めましょう。
どうぞ、ごゆっくりお読みください!
目次
はじめに
読書感想文のテンプレート - 文章を書く心がけ
「頭がいい人」について
これだけは負けないと思うこと - Q&A
おわりに
-
Vol.278 結城浩/反実仮想と恋の歌/片思いを忘れる方法/歳を重ねていくごとに/
2017-07-25 07:00220ptVol.278 結城浩/反実仮想と恋の歌/片思いを忘れる方法/歳を重ねていくごとに/結城浩の「コミュニケーションの心がけ」2017年7月25日 Vol.278
はじめに
おはようございます。結城浩です。
いつも結城メルマガをご愛読ありがとうございます。
あいかわらず暑い毎日が続いています。
幸いにして結城は夏バテにもならず、 毎日規則正しい生活を送ることができています。
水分を多めに摂ることと、 夜はできるだけさっさと寝ることと、 あまり物事をくよくよ考えないことを心がけています。
今年の前半はとてもヘビーだったので、 そのバランスを取る意味でも、 無理せずがんばる方針で行きたいです。
* * *
『数学ガール6』の話。
現在の最重要課題は、 秘密ノートシリーズではない「数学ガール」シリーズ最新刊です。
ここしばらく、第4章をずっと書いています。 章を構成する素材としてはもう以前から準備が出来ているのですが、 どうしても章としてまとまりません。
先週は、カギとなる数学的内容について検討していました。 でも、どうも収まりが悪い。
結城が文章を書こうとしていてよく陥るのは、 以下のようなパターンです。
・とてもおもしろい題材がある。 うまく料理できればベストである。 しかし、難しすぎて料理できない。
・ちゃんと料理することは不可能ではない。 でも、そのための準備が大掛かりすぎて、 全体のバランスが大きく崩れてしまう。
短くいえば、 「手が届きそうだけど、なかなか届かない状況」 ということですね。木の上のリンゴに手を伸ばしていて、 指先は触れているのだけれど、つかめない。 そんなもどかしさがあります。
これはとても悩ましい状況です。 というのは、がんばって背伸びすれば、 バランスを崩さずに提示できる道が見つかるかも? と思ってしまうからです。
結城はそのために一生懸命勉強します。 参考書を読んだり自分で考えたりして、 一つの解法だけではなく、複数の解法を検討します。
正確さをできるだけ犠牲にせず、 わかりやすさもできるだけ犠牲にせず、 「なるほどね」に至るための細いルートを探索する。 そのような活動をしているつもりです。
そのような探索は悪いことではありません。 でも、危険性がないわけではありません。
一つは時間が掛かりすぎること。つまり、 「もうちょっと勉強しよう……」とか、 「もうちょっと調べよう……」を続けているうちに、 自分自身が深い森で迷い、疲弊してしまう危険性です。
もう一つはサンクコストの誤謬にはまること。 「こんなに時間を掛けてしまったのだから、 この題材はぜったいに使わなくては」 と考える危険性です。
どちらの危険性にも注意が必要です。 そしてそこから逃れるためには、 いつもの原則《読者のことを考える》 に立ち返る必要があります。
この章で読者は何を期待するだろうか?
この章で読者に伝えたいことは何だろうか?
ひとことでいうなら、何が大事なの?
それをしつこいほど自分に問わなくてはいけません。 学ぶことは大事だけど、 それが自己目的になってしまってはまずいですし、 自分が掛けた時間が惜しいからといって、 読者に生煮えのものを読ませてはまずいでしょう。
ということを頭に置きつつ、 今週も第4章に取り組む予定です。
* * *
マリアム・ミルザハニさんの話。
先日、ショッキングなニュースを知りました。
数学者のマリアム・ミルザハニさんの訃報です。
マリアム・ミルザハニさんは、 2014年にフィールズ賞を受賞した史上初の女性。 そして、フィールズ賞を受賞した初のイラン人です。 そのミルザハニさんがガンで亡くなったとのこと。
◆Iranian Math Genius Mirzakhani Dies of Cancer http://ifpnews.com/exclusive/iran-math-genius-die-cancer/
2014年のフィールズ賞受賞の時点では、 既にガンであると診断されていたとのことです。
◆Fields Medals 2014 - IMU http://www.mathunion.org/general/prizes/2014/
このようなニュースは、何ともいえず悲しくなります……
* * *
ペーシングの話。
実際に人に会った場合であっても、 ネットでのやりとりの場合であっても、 結城は相手に合わせる習慣があるようです。
コミュニケーションの用語でいえば「ペーシング」でしょうか。 相手の話すスピードや、テンションや、喜怒哀楽。 それに自分のペースを会わせて話す傾向があるのです。
フェース・トゥ・フェースの場合には「ペースを合わせる」 ことの意味はわかりやすいでしょう。でも、 文章でやりとりする場合に「ペースを合わせる」 とはどういう意味でしょうか。
簡単な例でいうと「文末を合わせる」というやり方です。 「!」で終わる文章には、「!」で終わる文章を返す。 「。」で終わる文章には、「。」で終わる文章を返す。 そして、「……」で終わる文章には、「……」で終わる文章を返す。 そのようにすると、 自然と相手のペースに合わせた文章になることが多いようです。
といっても、 それをマニュアル化してやりとりしているわけではありません。 まず、相手の文章を注意して読みます。 そして、そこに書かれた文章上の意味だけではなく、 文章のスピードや、テンションや、 喜怒哀楽をできるだけ感じ取ろうとします。 そして、その上で、自分の言いたいことをいい、 書きたいことを書くようにしています。
トランシーバーで交信をするときに、 まず相手と自分の通信する周波数を合わせます。 周波数が合わなければ通信は成り立ちません。 ちょうどそういう比喩が成り立つかもしれませんね。
* * *
クラウドファンディングの話。
不特定多数の人からネット経由で資金を集める 「クラウドファンディング」 という方法があります。Kickstarterが有名ですが、 日本にも多数のクラウドファンディングサイトがあります。
ところで「クラウドファンディング」という単語、 結城はつい先日まで、綴りを誤って覚えていました。
(誤)Cloud Funding (正)Crowd Funding
Webサービスでよく使われる「クラウド(Cloud)」と、 多くの人々(群衆)を意味する「クラウド(Crowd)」とが、 ごちゃまぜになっていたのですね。 「Crowd Funding」が正しい綴りです。
確かに「不特定多数の人からネットで資金を集める」 という意味を考えればCrowdになるのも理解できます。
ちょっと気になったので、 Twitterの投票機能を使って 「クラウンドファンディングの綴りを知っていますか」 と尋ねてみました。すると、 1012人のうち77%の人が「Cloudだと思っていた」とのこと。
自分だけじゃなかった……と謎の安堵感を得た次第です。
* * *
バズの話。
iPhoneでアプリのアップデートを行おうとしたら、 Tumblrアプリのリリースノートにおもしろいことが書かれていました。
-------- バグを退治しました。 バグは他のアプリに移動したようです。 --------
プログラムミスのことを「バグ(虫)」と呼びますから、 バグを退治するというのはまあわかります。 でも「他のアプリに移動」とは!
おもしろかったので、スクリーンショットを撮り、 「ちょっと待ってTumblrくん」という一言を添えてツイートしました。 まあ、いつも結城が行っている、軽口ツイートですね。
◆ちょっと待ってTumblrくん
https://twitter.com/hyuki/status/887266466591981568
ところが、思いも掛けないことが起こりました。
この何気ないツイートが、 結城のツイート史上最大数のRTといいねをもらうことになったのです。 RT数が10000を越えたのはこれが初めてのことでした。 軽くバズった感じですね。
RTがどんどん増えていくのを見ながら結城が最初に思ったのは、 「スペルミスしなくてよかった……」ということでした。 ツイートをする直前に、 「Tumblr(タンブラー)の綴りはこれであってるよな」 と確認をしたのを覚えています。 大量にRTされたツイートにミスがあったら恥ずかしい!
Twitterには「アナリティクス」という機能があり、 自分のツイートがどれだけのインプレッションになったか、 あるいはそのツイート経由で何人がプロフィールを見たか、 ……といった統計情報がわかるようになっています。
今回のツイートの場合、 驚くことに190万インプレッションにも達しました。
◆アナリティクス
自分ではまったく予想もしていなかったツイートが、 こんなに広まるとは。驚きです。
* * *
スーパーのレジの話。
ぼーっと考えごとしつつスーパーに行ったとき。
店員「お支払いは…?」 結城「ポイントを使ってください」 店員「はい、クレジットでよろしいですね」 結城「いえ、現金で」 店員「…」 結城「…」
そのあとレジのお姉さんと、 私たちは何をやっているのか!……と爆笑。 しかも、実際の支払いはSuicaになったのです(!)
ちなみに、こんな会話になったのは、 今回の支払いの末尾が3円になったため。 やりとりの途中で「あっ、財布に3円あったぞ!」 と気づいたので、現金に切り換えたためです。 でも、実際は2円しかなかったのですが……
また、別の日に、こんな出来事も経験しました。
結城「ポイントは全額を使ってください」 店員「わかりました。ポイントは?」 結城「全額を使って…」 店員「わかりました。113ポイントございますが、全額を使っても…」 結城「全額を…」 店員「わかりました。全額を使っても?」 結城「全額を…」 店員「使っても…」 二人「「よろしいですー」」
これじゃ、まるでミュージカルコメディです!
このあと、レジのお姉さんと大笑いしました。
* * *
それではそろそろ、 今回の結城メルマガを始めましょう。
どうぞ、ごゆっくりお読みください!
目次
はじめに
反実仮想と恋の歌
ニュートラルで検証可能なマスメディアを求む
片思いを忘れる方法 - Q&A
歳を重ねていくごとに
おわりに
-
Vol.277 結城浩/再発見の発想法/繰り返しに耐える/大学の数学を理解するには/
2017-07-18 07:00220ptVol.277 結城浩/再発見の発想法/繰り返しに耐える/大学の数学を理解するには/結城浩の「コミュニケーションの心がけ」2017年7月18日 Vol.277
はじめに
おはようございます。結城浩です。
いつも結城メルマガをご愛読ありがとうございます。
暑いですね……
とても、暑いですね……
毎日、とても、暑いですね……
暑いせいなのか、結城は最近、 夜中に目を覚ましてしまうことがよくあります。
ある日は午前二時十七分に。
ある日は午前三時十四分に。
ふと、目が覚めます。
そんな時間に目が覚めたとき、 結城はクーラーの温度調節をしたり、 水を飲んだりします。そして、それ以外に、
「眠れないでいる人のために祈る」
ことを習慣にしています。
夜中にふと目が覚めたときには、 眠れないでいる人のために祈る。
幸いにして結城は(少なくとも最近は) 悩みごとのために眠れないという夜はほとんどありません。 眠くなってコトンと眠り、朝になったら自然に目が覚めます。 目覚ましを掛けることもありません。
でも、世の中には「眠れない」という方はたくさんいらっしゃいます。 理由はさまざまです。悩みごとや心配ごとが心を満たすとき、 考えてもしょうがないとわかっていることでも気になってしかたがない。 そんなときはどうしても眠れないものです (結城もそういう時代を何回か過ごしたことがあります)。
眠れないというのはつらいものです。ほんとうにつらいものです。 ですから、夜中にふと目が覚めたときには、 眠れないでいる人のために祈るようにしているのです。
* * *
多様性の話。
結城は、朝起きると最初に聖書を読むようにしています。
先日はこんな箇所でした。
すべてあなたがたのうち、心に知恵ある者はきて、 主の命じられたものをみな造りなさい。 出エジプト記 35:10
この箇所の前後は、神さまに命じられて建物を建て、 インテリアを整える場面になっています。特にこの箇所の後には、 モーセが神さまから指示された「これを作りなさい」 という物品リストが列挙されています。 幕屋とか、柱とか、机とか、パンとか。 素材も大きさも種類も目的も、 多種多様なものがリストアップされています。
この聖書箇所を読むといつも、
全体として一つのものを作り上げるときでも、 多様なものが多数必要になるのだな
ということを思います。 あたりまえといえばあたりまえのことです。
ある程度以上の規模のものを作り上げるとき、 そこには構造があります。複数のもの…… 素材も大きさも種類も目的も異なるものが、 一つの意思の下で組み上げられて初めて、 大きな一つのものとなるのですね。
ばらばらのままでは、一つのものじゃない。 一つに組み上げられて初めて、一つになる。
それは、モノに限らない話でしょう。
プロジェクトを進めるとき、組織作りをするとき、 会社運営をするとき、旅行計画を立てて実行するとき、 勉強を進めるとき……どんな場合でも、 多様な要素をうまく組み合わせないとまとまりがなくなり、 収拾がつかなくなります。何か一つの旗印のもと、 多様な要素を組み合わせる必要があるのです。
自分という一人の人間を考えても、わかります。 自分の活動や意思や感情は単純ではありません。 複雑に絡み合った多様性を持っています。 その中の一つだけを伸ばして残りを殺すことはできない。 かといって、ばらばらのままではまずい。
自分の中の多様な側面を、うまく調和させ、 いい具合に組み上げたい。 そこにはきっと、 一つの意思が必要になるのじゃないかしら。
そんなことを思いました。
* * *
インタビューを受けた本の話。
昨年、結城は岡部晋典氏(同志社大学学習支援・教育開発センター助教) にインタビューを受けました。 今月末にそのインタビューを含む書籍が刊行されますのでご紹介。
書名は、
『トップランナーの図書館活用術 才能を引き出した情報空間』
というものです。タイトル通り、 この本のテーマは「図書館」。 さまざまな分野で活躍している人が、 図書館をどのように関わってきたのかが語られています。
インタビューイー一覧は次の通りです(掲載順)。
落合陽一/清水亮/前野ウルド浩太郎/ 三上延/竹内洋/谷口忠大/ 結城浩/荻上チキ/大久保ゆう/ 大場利康/花井裕一郎/原田隆史/
この本の中で、結城のインタビューは、 「小さな数学者たちの対話の場」というタイトルになり、 縦書きで24ページほどの記事になっています。
結城が子供の頃から図書館で体験したこと、 『数学ガール』と図書館との関わり、 登場人物同士の対話、図書館に自著が入ることの意味、 結城がこれからの図書館に求めるもの……そんな話題を楽しく話しています。
もしも機会がありましたら、ぜひお読みください。
◆『トップランナーの図書館活用術 才能を引き出した情報空間』(岡部晋典編) http://amzn.to/2upuO4z
* * *
note(ノート)の売上の話。
結城はnote(ノート)で読み物を公開しています。
多くは「投げ銭」スタイルになっています (全文無料で、おもしろかったらお金を払ってねというスタイル)。 前半は無料で後半が有料になっているものもあります。 また、PDFとして用意し、そのURLを売っているものもあります。
だいたいは、結城メルマガの過去記事として配信したものですね。
読み物は不定期更新で、 宣伝はほとんどTwitterでのツイートくらいです。
先日ふと「2014年4月から2017年6月までの売上」 のヒストグラムを作ってみようと思いつきました。 こんなふうになりました。
◆note(ノート)売上のヒストグラム
これは、月単位でおおよそいくらになっているか、 その分布を表したものです。
毎月の売上は平均すると「2418円」になります。 平均2418, 標準偏差2027ですから、 ばらつきがすごく大きいことがわかります。
ともあれ、読み物をご購入&サポートしてくださっている 読者さんに感謝いたします。
◆結城浩のnote(ノート) https://note.mu/hyuki
* * *
ビデオコンテの話。
新海誠監督が『言の葉の庭』テレビ放映の後に、 こんなツイートをしていました。
-------- 『言の葉の庭』テレビ放送、 遅い時間にもかかわらずご覧いただいた方、 ありがとうございました!お礼代わり(?)に、 制作に先立って作ったビデオコンテの一部です。 スマホ直録りですが……ちゃんとしたものは、 BD特典に入っていたかと思います。 --------
https://twitter.com/shinkaimakoto/status/883718188789145600
リンク先には『言の葉の庭』のシーンの動画が公開されています。 監督が「ビデオコンテ」と表現しているように、 絵は線画で、色も二色しかついていません。 長さも1分半ほどの短いものです。 でも、非常におもしろい動画なのです。
何がおもしろいかというと、コンテの形になっているがゆえに、 監督がイメージしている骨組みが見えるような気がするからです (結城は動画に関する知識がないので「気がする」だけですが)。
たとえば、主人公がグッと表情を変えるシーン。 また、主人公が料理をしながらふと振り返るシーン。 あるいはまた、ガラス窓を流れる水滴の方向を指示しているところ。
色も着けておらず、線もラフなのに、 上に書いたほんのちょっとしたところには細かい指示が入っている。 そこがおもしろいと思いました。
このシーンで表情を変えるところ、このシーンで振り返るところ、 そして水滴がこの方向に流れていくところ……それは、 きっと監督にとっては何かしら重要な意味を持っているのでしょう。 だって、かなりの部分が省略されているのに、 わざわざ、ビデオコンテでそこの部分を詳しく描いているのですから。
あたりまえですけれど、 監督にはいろんなことが見えているのだなあと思った次第です。
そして、このビデオコンテの状態から、 完成版としてのアニメーションに持って行くために、 どれほど多くの手間と時間が掛かっているかを考えると、 気が遠くなってきます。
アニメーション作品を見るときには、 その美しさや物語を楽しめばいいはずです。 でも、このビデオコンテのような制作途中の過程をチラ見すると、 あらためて、
どんな作品でも、 誰かが手を動かして作らなければ、 この世に生まれなかったのだ。
という事実を強く感じざるを得ません。
しかも、その作品は、 他の誰も気がつかないような微妙な箇所を骨組みとして持ち、 とんでもない時間を費やして肉付けされることで、 初めてこの世に生まれたのです。
そして、勝手ながら結城は、 「よし……私も、自分の書く本のためにがんばろう!」 と静かな闘志を燃やすのです。
* * *
索引の話。
先日購入して、楽しみにしていた本がようやく届きました。 書籍執筆の参考にしようと思っていた本です。 でも、ぱらぱらとめくって、がっかりしました。
その本には「索引」がなかったからです。
本のはじめに書いてあるのは「目次」(もくじ)。 本の最後にあるのが「索引」(さくいん)。
目次では、書かれている順番に従って内容が示されています。 索引では用語や人名がどこに出てくるかが五十音順などで示されています。 目次と索引は、本全体の姿を違った観点で見せてくれるのです。
個別の書籍をディスることが目的ではないので、 索引がなかったその参考書名は挙げません。 とても厚くて調べ物にも使える本なのに、 索引がないのはとても困りますね。
もちろん、きちんと構成してある本ならば、 本の初めに書いてある目次を読んで、 「このあたりに書いてあるかな」と予想はつけられます。
でも、ある用語が予想もつかない場所に出てくる場合には、 その用語を見逃してしまう恐れがありますね。 一つの用語が、目次からは予想もつかない場所に出てくるとき。 それは、しばしば大きな喜びにつながります。 というのは、一見無関係に思われる分野が《つながっている》 ことを示唆するからです。
言い換えるなら、索引をうまく使うことで、 目次からは読み取れない分野のつながりや、 概念のつながりを短時間で発見できるということです。
索引が用意されていなければ、 その発見の道は失われてしまいます。
結城の書籍『数学文章作法』では、 索引をつけることを以下のように強くお勧めしました。
-------- 索引を作る場合でも, 私たちの原則《読者のことを考える》は変わりません. まず何より,読者が調べるときに使う長い説明文なら, 索引は必須であると心得てください. (『数学文章作法 基礎編』第7章) --------
索引を用意するというのは、 読者の役に立つとはっきりわかっていて、 しかも著者にできることの一つです。
結城はLaTeXで目次と索引を作ります。 索引項目のピックアップは私がやります。 ただ、最終工程では編集部の方で総確認を行います。 そしてしばしば 「こちらのページの方が適切ではないですか?」 という指摘を編集部からいただきます。 一つ一つの索引項目を、結城は編集部と共に真剣に取り扱います。
いい索引を作るというのは、目立たず手間のかかる作業です。 しかし索引は、読者にとって非常に大事なものなのです。
近くにある本を手にとって、目次と索引を眺めてみてください。 意外な発見がありますよ!
* * *
それではそろそろ、 今回の結城メルマガを始めましょう。
どうぞ、ごゆっくりお読みください!
目次
はじめに
再発見の発想法 - Promise(プロミス)
ギャンブルコミックが好きな理由
繰り返しに耐えるということ - 本を書く心がけ
大学の数学を理解するにはどう学べばいいですか - Q&A
おわりに
-
Vol.276 結城浩/値は値 - 仕事の心がけ/文系の三年生に数学を教えたい - Q&A/
2017-07-11 07:00220ptVol.276 結城浩/値は値 - 仕事の心がけ/文系の三年生に数学を教えたい - Q&A/結城浩の「コミュニケーションの心がけ」2017年7月11日 Vol.276
はじめに
おはようございます。結城浩です。
いつも結城メルマガをご愛読ありがとうございます。
* * *
「あちはわー」の話。
最近、ほんとうに暑い!暑い!
とても暑いことを表現する顔文字として、
あちはわーU>△<U
というのがプチ流行していたので、 結城も便乗していました。
すると、湊川あいさんが、 結城のキャラクタ(スレッドお化け坊や)を使って、 「あちはわー」を描いてくださいました。感謝!
◆結城先生で「あちはわーU>△<U」
https://twitter.com/webdesignManga/status/881836763269914625
最近、ほんとうにこのイラストのように暑いです。
そして、別の日。
「あちはわー」を検索したら、 まったく関係がない「聖書の一節」が出てきてびっくりしました。
◆検索でみつかった「あちはわー」
おとめたちのうちに わが愛する者のあるのは、 いばらの中に ゆりの花があるようだ。 (雅歌二章二節)
確かに「あ・ち・は・わ」という文字は入っていますが…… コンピュータはおもしろいところにパターンを見出しますね。
ちなみに、上のツイートは2015年のもの。 縦書きツイートを作ったのは以下のツールで、 このツールの作者は『横浜駅SF』の柞刈湯葉さんです。
◆縦つい。 http://yubais.net/tatetwi/
* * *
新刊の話。
新刊『数学ガールの秘密ノート/積分を見つめて』は、 順調に読者さんの手に届いているようです。 みなさんからの「買いました」ツイートを見たり、 「読みました」メールを見ていると、感謝で胸がいっぱいになります。
先日結城が個人的に実施した《サイン本無料プレゼント》 の発送も無事に済みました。
今回の題材は「積分」です。 Web連載の順序では「指数・対数」でしたが、 Web連載記事を書籍化する書籍化の順序を入れ換えて、 「積分」を先に持ってくることにしました。
その理由はシンプルで、
《微積分セット》
を早く作りたかったからです。
すでに第5巻目で「微分を追いかけて」 という微分を題材にした書籍は出版されています。 第9巻目となる今回の「積分を見つめて」と合わせると、 微分と積分を扱った二巻セットができることになります。
微積分というと、三角関数と並ぶ「数学を象徴するキーワード」ですね。 人によっては「数学でつまずいたキーワード」かもしれませんが…… ともかく、数学といえば「微積分」を思い浮かべる人は多いでしょう。 ですから《微積分セット》を作りたいと思ったのです。
この《微積分セット》というコンセプトは、 結城の方から編集長に提案したものです。
もともと結城は、Web連載を順番に書籍化していこうと考えていました。 しかし、第8巻目を作るときに編集長から「統計を先にしましょう」 という提案をいただいたのです。その理由は、
・統計は注目をあびているので、早めに統計を出すのがいい。 ・これまでの「秘密ノート」の読者層と違う層にアピールするかも。
という二点でした。なるほど。
結城はそのアドバイスに従い、昨年「やさしい統計」を出しました。 そして、編集長の予想通り、たいへんな人気となったのです。 出版直後に増刷が掛かり、10カ月たらずで第3刷が決まりました。
今回の第9巻目を作るとき、 結城は編集長のアイディアを結城なりに咀嚼しました。 自分にこう問いかけました。
連載順にこだわらないとしたら、 次に出すべき書籍は何だろう?
そして、先ほどから述べている《微積分セット》 というアイディアに繋がったのです。
今回の「積分」というテーマの選択は、 編集長からもらった提案への 「結城なりにバージョンアップした返事」 といえるかもしれませんね。
《微積分セット》というコンセプトは、 書籍紹介の文章の中にも入れましたし、 営業さんがアピールするときにも使われているはずです。 書店さんも「微分を追いかけて」&「積分を見つめて」 がセットで売れた方がうれしいでしょう。 《微積分セット》はみんなが喜ぶ企画なのです。
「積分を見つめて」の刊行直前、 「微分を追いかけて」の増刷が掛かりました。 これはもちろん「積分を見つめて」の刊行に備えて、 《微積分セット》の体勢を整えるためです。
こんなふうにして、今回の「積分を見つめて」は、 多くの関係者が、
《微積分セット》
というコンセプトをとらえた状態での出版となりました。 たいへん感謝なことですね。
◆数学ガールの秘密ノート/微分を追いかけて https://note5.hyuki.net/
◆数学ガールの秘密ノート/積分を見つめて https://note9.hyuki.net/
そして、新刊が出るとシリーズの他の巻にもよい効果があります。 ちょうど2017年7月10日(月)に、 以下の三冊の《同時増刷》が決定しました!
『数学ガールの秘密ノート/式とグラフ』 『数学ガールの秘密ノート/数列の広場』 『数学ガールの秘密ノート/やさしい統計』
結城は書籍を出すようになって二十数年経ちますが、 三冊の本の増刷が同時に決まったという経験は、 おそらく初めてではないかと思います。
応援してくださる読者のみなさんに心から感謝します!
* * *
たなか鮎子さんの話。
表紙カバー絵を描いているのは、 イラストレータ&絵本作家のたなか鮎子さんです。
◆AYUKO TANAKA http://ayukotanaka.com
《微積分セット》の微分編の表紙モチーフはブランコで、 これは単振動のイメージです。
《微積分セット》の積分編の表紙モチーフは階段で、 これは区分求積法のイメージです。
毎回、書籍のカバーは結城と、編集長と、 デザイナーの米谷テツヤさんと、たなか鮎子さんで練ります。 説明にならないようにしつつ、内容と呼応するイメージを考え、 また他の巻とかぶらないように注意し、 あとは自由に描いていただきます。 毎回、すばらしいカバーになっていますよね。
ベルリン在住のたなかさんの、 すてきなインタビュー記事はこちらから読めます。
◆「女性目線のベルリン」 「アートで生計を立てていく」ためのヒント http://sekaistory.jp/2240/
海外で、好きなことを仕事にして生きていく人のための、 特にアートで生きる人のためのヒントが書かれています。
* * *
Inkdropの話。
Inkdropというのは、Markdownノートアプリです。 結城はユーザではないのですが、 先日見かけた以下の記事が気になりました。
◆MarkdownノートアプリInkdropで家賃の半分が賄えるようになりました https://blog.craftz.dog/3f30f4e1e479
タイトルを見たときには「へえ」と思っただけでしたが、 はてなブックマーク数が多かったので、中身も読んでみました。 読み応えのある面白い記事でした。
記事の中で特に印象に残ったのは、
-------- しかし僕はアプリをシンプルに保ちたいので、 ほとんどの意見を保留にしたり断ったりしました。 --------
というところです。
有料アプリをユーザに使ってもらうために、 ユーザからの意見を聞き、それを「取り入れる」ならばわかります。 「取り入れる」のではなく「保留にしたり断ったりした」 という点がすごいと思いました。
ここには「作者の判断」がありますね。
機能を実装してユーザに喜んでもらいたくなるのは人情です。 有料アプリならなおさらです。 お金払っている人からの意見を尊重しないで、 何を尊重しようというのでしょう。
ユーザに言われるまま機能を実装していき、 アプリをシンプルに保てなくなり、 やがて使いにくくなったら、 結局ユーザには喜ばれません。
機能を「実装する」判断ではなく「実装しない」判断は難しそうです。 その判断ができるということは、 きっと、このアプリの「あるべき姿」が見えているのでしょう。 つまり、それが「作者の判断」ということです。
しかし、言うは易く行うは難し。 たくさん課金してくれるユーザから熱心な要望が来て、 それが自分の考える「あるべき姿」からズレていたならどうするか。 そうなってくると「作者の判断」というよりは「経営者の判断」 に近くなってくるかもしれません。
価格に関しては、こちらにも文章がありました(英語)。
◆Why Inkdrop is a Subscription App https://hackernoon.com/beda29c507d5
ぜひ、あなたもお読みください。
ここでは、売り切りではなくSubscription model になっている理由が次のようにまとまっています (和訳は結城です。ずれていたらごめんなさい)。
・Going cheap is poor strategy (低価格勝負はまずい戦略) ・The most important thing is to make sure everything is sustainable (すべてを確実に持続させるのが最重要) ・The goal is not to catch ’em all (すべての人を得ることがゴールではない) ・If you try to please everyone, you won’t please anyone (みんなを満足させようとすると、だれも満足しない) ・Trusting the value (価値を信じる)
結城は、ここには非常に大事なことが書かれていると思いました。
結城は、自分が書く文章について思いながら、 この記事を読みました。 そして、このInkdropの作者TAKUYAさん(@craftsdog)をフォローしてみました。
https://twitter.com/craftzdog
価格については、後ほど「値は値」という別のお話をしましょう。
* * *
Web連載の話。
先日CakesでのWeb連載「数学ガールの秘密ノート」 が第200回目を迎えました。 継続的な応援をありがとうございます。
(と、落ち着いて書きましたが、 心の中では「200回!すごーい!」と叫んでいます。 数学のそれなりのクオリティの読み物を200回!……こほん、失礼しました)
ところでその第200回目は、予定よりも長くなってしまい、 饒舌才媛ミルカさんの話がいれられなくなってしまいました。 Web連載ではそういう場合に「メタ数学トーク」と称して、 舞台裏のおしゃべりというスタイルで書くのですが、 今回はそこにも入りませんでした。
せっかくなので、別途テキストに起こし、 数学部分だけを公開することにしました。 以下です。
◆フェルマーの小定理とオイラーの定理を見比べる https://story.hyuki.net/20170703011050/
オイラーの定理が証明できれば、 フェルマーの小定理はその「系」として一瞬で証明できてしまいます。 でも上では意識的にその二つの類似性を強調して書いてみました。
Web連載の第199回と第200回では、 「pを素数としたとき、p-1にはどんな意味があるだろうか」 ということがテーマになっていました。 p-1はもちろん「素数よりも1小さい数」ではあるのですが、 「pと互いに素であるp以下の正整数の個数」 という見方もできます。
オイラーの定理に出てくるオイラーの関数φ(n)は、 「nと互いに素であるn以下の正整数の個数」 ですから、フェルマーの小定理とオイラーの定理に 類似性があるのもよくわかります。
◆第200回の最終パート(二つの定理の比較部分)
数式や証明をじっと観察していて、 そのような類似性が見つかるのは楽しいものです。 数学に詳しい人には「あたりまえ」かもしれませんが、 それを自分なりに「見出す」ところに喜びがあります。
二つの「似ている」概念があったとして、 それが「似ている」ことをどのように表現すればいいでしょうか。 どのように表現したら「似ている」ことがはっきりと伝わるでしょう。
結城は、
概念上で似ているものを、 表現上でも似ているように表す
のが好きです。もちろん表層的に似た表現を使って、 無理矢理似せるわけではありません。 ほんとうに似ているものに、ふさわしい表現を与えて、 「確かに、見るからに似ている」 と読者に感じてもらいたいのです。
残念ながら、今回の第200回では、 フェルマーの小定理とオイラーの定理の類似性について、 そこまでは突っ込んだ書き方ができませんでした。
でもいつか(いつになるだろう)書籍化するときには、 その類似性が明確になるように書き表したいなと思っています。
結城が文章(読み物)を書くときには、 それなりの「目標」があります。 「全体としてどこまで書きたいか」ともいえますし、 「読み終えたときに読者に何をつかんで欲しいか」 ともいえます。
その「目標」が見えないと、 まとまった文章を書く意欲はなかなか出てきません。 「目標」が見えてくると、そこへ向けて材料を集めたり、 材料の取捨選択をしたりできるのです。
Web連載はしばらくお休みをいただき、 8月から新シーズンの再開となります。 次のシーズンの題材候補はすでにいくつか見つけており、 そこへ向けての準備も進めています。
ぜひ、ご期待ください!
◆Web連載「数学ガールの秘密ノート」 https://bit.ly/girlnote/
* * *
それではそろそろ、 今回の結城メルマガを始めましょう。
どうぞ、ごゆっくりお読みください!
目次
はじめに
値は値 - 仕事の心がけ
文系の三年生に数学を教えたい - Q&A
おわりに
-
Vol.272 結城浩/再発見の発想法/教えるときの心がけ/著者と出版社の販促活動/
2017-06-13 07:00220ptVol.272 結城浩/再発見の発想法/教えるときの心がけ/著者と出版社の販促活動/結城浩の「コミュニケーションの心がけ」2017年6月13日 Vol.272
はじめに
おはようございます。結城浩です。
いつも結城メルマガをご愛読ありがとうございます。
* * *
まずはご連絡から。
『数学ガールの秘密ノート/積分を見つめて』 《サイン本無料プレゼント》実施中です!
◆『数学ガールの秘密ノート/積分を見つめて』《サイン本無料プレゼント》 https://snap.textfile.org/20170612150529/
◆『数学ガールの秘密ノート/積分を見つめて』カバーイラスト
* * *
新刊の話。
2017年6月末に刊行される予定の新刊 『数学ガールの秘密ノート/積分を見つめて』の、 再校読み合わせが終わりました。
編集長との読み合わせのとき、 結城は出版社まで出向くのが普通です。 でも今回は直前に体調を崩してしまい、 近所のカフェまで編集長の方に出向いてもらいました。 何とか読み合わせをこなすことができましたけれど、 体調管理の点で猛省が必要ですね。
ともあれ、再校読み合わせが終わりました。 この本の内容に関して結城ができることは、 ほぼすべて終わったことになります。 あとは印刷して本ができるのを待つばかりという状態。
今回の本の執筆は、個人的にたいへんな時期と重なり、 難産だったイメージがあります。しかしながら、 長い時間が掛かった分、多様な視点での読み返しができたため、 いつもより品質が上がった可能性もありますね。 感謝なことです。
微分に関してはすでに、 『数学ガールの秘密ノート/微分を追いかけて』 という本が出ていますので、今回の積分と合わせて
《微分積分セット》
ができたことになりますね。
今回の新刊も、 この本を必要としている読者さんに無事届きますように!
◆『数学ガールの秘密ノート/微分を追いかけて』 https://note5.hyuki.net/
◆『数学ガールの秘密ノート/積分を見つめて』 https://bit.ly/girlnote09
後ほどQ&Aのコーナーでは、 本を書いているというメルマガ購読者さんからの、 「販促活動」に関する質問にお答えします。
* * *
執筆のようすをアニメーションGIFにして公開する話。
結城はMacBookを使っています。 Macでは、QuickTime Playerを使うと、 コンピュータ上での操作のようすを動画として記録できます。 いわば「録画」ですね。QuickTime Playerのメニュー項目名は、 「新規画面収録」です。
◆QuickTime Playerで「新規画面収録」
保存した結果はmovファイルになりますので、 それをYouTubeにアップロードすれば公開できます。 でも、ffmpegというツールでmovファイルをアニメーションGIFに変換すれば、 もっと手軽に公開することができます。
しかし、結城はffmpegというツールのオプションが複雑で覚えられません。 変換するたびに使い方を検索することになります(悲しい)。 そこで、mov-to-gifというスクリプトを作りました。 一度学んだ結果をスクリプトに覚えさせておけばいいのです! スクリプトは以下で公開しています。
◆mov-to-gif https://gist.github.com/hyuki0000/66990a8152e78eb48c38d31991383114
たとえば、結城が作ったWebサイトDraftで数式入力しているようすを、 QuickTime Playerで「録画」して、mov-to-gifでアニメーションGIFに変換してみました。 タイプしているようすをリアルタイムで見るのはたいくつなので、 タイプしたときの三倍速で再生するようにしています。
◆Draft https://draft.hyuki.net/
◆数式入力しているようす(アニメーションGIFへのリンク)
なお「動画をアニメGIFにしては?」という示唆は、 以下のツイートで @nnabeyang さんからいただきました。
https://twitter.com/nnabeyang/status/868800719062614016
結城が以下の動画をYouTubeにアップロードしたときに、 リプライで教えてもらったものです。
◆Draft - Distraction Free Editor with Math https://youtu.be/ADZj4pAD52c
ちょっとした動画なら、 YouTubeにアップロードするよりも、 アニメーションGIFにしてツイートする方が確かに手軽ですね。
* * *
スタティック・テトリスの話。
スタティック・テトリス(static tetris)というゲームの原案を思いつきました。
普通のテトリスはリアルタイムゲームですよね。 プレイヤーがじっとしていても、ピースはどんどん降ってきます。
でも、テトリスのおもしろさの一つは、 やってくるピースをどのような向きで、 どのように積むかというところにあります。
そこで、テトリスからリアルタイム性を除いたパズルゲームにするのです。 プレイヤーはじっくり考えて一手を進める。 一手というのは、左右に動かしたり、回転したりというアクションです。 プレイヤーが一手を進めたら、ピースが少し下に落ちる。
リアルタイム性がない分だけやさしくなっちゃいますから、 普通のテトリスよりも難しくしたほうがいいですね。 たとえば、同時に複数個のピースが落ちてくるとか。
結城はリアルタイムなゲームがあまり好きじゃないけど、 パズルゲームは好きなので、 どなたかおもしろいゲームとして実現してくれないでしょうかね。 名前に「テトリス」は使えないかもしれませんけれど。
* * *
比喩と説明の話。
プログラミング言語で「変数」のことを説明するときに、 「変数は箱のようなものです」ということがあります。 「変数に値を代入することは箱にものを入れるのに似ている」 のように使うことになります。
これは「変数」という抽象的なものを相手に教えるために、 「箱」という具体的なものの性質を借りていることになりますね。 つまり《比喩を使った説明》ともいえるでしょう。
比喩を使った説明は、うまくいけばとても強力です。 抽象的な概念はなかなか相手に伝えることが難しいものです。 具体的な事物を使って「完全にこれと同じというわけではないけれど、 これと似た性質を持っているんだよ」と説明すれば、 まずは理解のとっかかりとして有効です。
ただし、比喩を使った説明を行うときには、 教える側にも学ぶ側にも注意が必要です。 比喩はあくまで比喩であって、 概念すべてを説明するわけではありません。 つまり、比喩には自ずから適用できる限界があるのです。
たとえば「変数は箱のようなものである」といった場合、 「変数に値を代入すること」を「箱にものを入れること」 にたとえるのは、まあいいでしょう。 でも「変数の値を他の変数に代入すること」を、 「箱からものを取り出して他の箱に入れること」 と見なすのは正しくありません。 つまり「変数は箱」の比喩は、 その適用限界にすぐ至ってしまいます。
教える側も学ぶ側も、 比喩を使った説明でさっとイメージをつかんだ後は、 いさぎよくそれを捨てて、もっと正確な説明 (あるいはより正確な比喩)へと移るのがいいでしょう。
結局捨てることになるなら、 最初から「変数は箱」などといわない方がいいのでしょうか。 それは説明する内容と読者によります。
比喩を捨てるときも、相手に概念を伝えるいいチャンスになります。 つまり、こうです。
「変数は箱のようなものだから○○できるといったよね。 でも、変数は箱とは違って△△はできないんだ。 そこは箱とは違う点だから注意して」
このような説明を行えば、 「変数」という未知で抽象的なものが持つ性質を、 「箱」という既知で具体的なものが持つ性質を使って 理解を深めることができるのです。
・変数は○○できる。その点は箱に似ている ・変数は△△できない。その点は箱に似ていない
このように「できる」「できない」を知ることで、 学ぶ側は概念の姿をくっきりと理解できるようになるでしょう。
概念を的確に表す比喩を求めるのはいいことですが、 最適な比喩を求めすぎるのはよくありません。 概念との一致を求めすぎると、 わかりにくくてアクロバティックな比喩が生まれがちだからです。 大きな特徴がさっとわかるシンプルな比喩がいいですね。
比喩は道具の一つに過ぎません。 使いどころを間違えなければ、強力な道具となるでしょう。
* * *
gitとグラフ表示の話。
バージョン管理システムgitをコマンドラインで使っていると、
これからマージするんだけど、 コマンドラインだと不安なので、 ブランチの様子やリモートリポジトリの様子を グラフィカルに見ておきたい
という場面がよくあります。そんなときには、
open -a SourceTree .
を実行すると、カレントディレクトリで SourceTree(GUIアプリ)が開かれるので便利です。
◆SourceTreeでcommit historyを見ている様子
Macのopenコマンドはとても便利で、-a オプションで、 アプリを指定して起動することができるのです。
さて、こんな話をツイートしながら、 (ふふん、私ってgitやMacを使いこなしてるなあ) と心ひそかに思っていました。でもあるとき、 gitにはそもそもグラフ表示機能が付いていることを知り、 ショックを受けました。具体的には、
git log --oneline --graph
を実行するだけで、以下のような表示になるのです。 左側にテキストを使ってグラフっぽい形が描かれていますね。
◆gitでcommit historyを見ている様子
結城は、結城メルマガVol.270でこんなことを書きました。
ある技術を使って活動をしているとき、 「こういうことをしたいな」 と思ったらまずは公式ドキュメントを読むべき。 自分が考える「改良」や「応用」というのは、 すでに誰かが考えていて、 適切な対応方法が確立されていることが多い、 ということ。
今回の--graphオプションは、 まさにこれにぴったりあてはまる事例ですね。
* * *
それではそろそろ、 今回の結城メルマガを始めましょう。
どうぞ、ごゆっくりお読みください!
目次
はじめに
再発見の発想法 - DRY
還元論と全体論 - 教えるときの心がけ
著者と出版社の販促活動について - Q&A
おわりに
-
Vol.270 結城浩/数式混じりのメモ/「具合が悪い」ときのチェックリスト/執筆中の忘却/
2017-05-30 07:00220ptVol.270 結城浩/数式混じりのメモ/「具合が悪い」ときのチェックリスト/執筆中の忘却/
結城浩の「コミュニケーションの心がけ」2017年5月30日 Vol.270
はじめに
おはようございます。結城浩です。
いつも結城メルマガをご愛読ありがとうございます。
ここ数日、気持ちのいい天気が続いています。
やや暑いけれど、風が気持ちよく、空も青く澄み、 何だか遠くまで飛んでいきたくなるような、 そんな天気です。
あなたはいかがお過ごしでしょうか。
* * *
新刊の話。
『数学ガールの秘密ノート/積分を見つめて』の初校読み合わせが済みました。
初校読み合わせが終わると、 私の手元からゲラが編集部に渡ります(そのゲラには、 私がたっぷり朱入れをしているわけです)。 編集部はそれを使って組版を修正します。
再校が出てくるのはおよそ一週間後。 今週末にはおそらく再校ゲラが結城の手元にやってきます。
ではそれまで結城は暇になるかというと、 そんなことはありません。 今回の本の宣伝展開のためのメッセージカード作りや、 初校で積み残しになっていた修正点& 懸念事項を練る作業が必要になるからです。
現在のペースで行きますと、 新刊が書店に並ぶのは六月末くらいになるでしょうか。 それまでにはサイン本を作る作業も待っています。 いよいよ『数学ガールの秘密ノート/積分を見つめて』 作成も終盤戦です。がんばりましょう!
◆『数学ガールの秘密ノート/積分を見つめて』 https://bit.ly/girlnote09
* * *
陳腐化させない話。
Zack Kanter氏による以下の文章を読みました。
◆Amazonが「世界を食い尽くしている」理由を考える | TechCrunch Japan http://jp.techcrunch.com/2017/05/16/20170514why-amazon-is-eating-the-world/
この記事は、Amazonのビジネスのある側面について語っています。 要約することは難しいですが、結城はこんなふうに捉えました。
Amazonは、 自社が使っているサービスをAWSによってプラットホーム化している。
◆AWS(Amazon Web Services) https://aws.amazon.com/
それによってAmazonは利益を得ると同時に、サービスを進化させていける。 つまりAmazonは、自社が使っているサービスをプラットホーム化することで、 世界の水準にキープし続けることができている。そこに他社は追随できない。 要するに「究極のドッグフーディング」を行なっていることになる。
なるほど、と思いました。 この記事を読みながら結城は「陳腐化」について考えていました。
会社であれ、個人であれ、 誰しも仕事でライバルに遅れを取りたくはないでしょう。
そのため多くの人が考えるのは、 自分が持っているノウハウや技術を外から「隠す」ことです。 隠せばライバルに盗まれる心配はなくなりますから、 優位性が保たれる……といえそうです。
確かにそれはそうでしょうけれど「隠す」ことには危険性もあります。 それは隠すことによって陳腐化に気づかなくなる危険性です。 「ガラパゴス化する」や「レガシー化する」ともいえるでしょうか。
技術を「隠す」ということは、 自社の持っている技術の利用者を、自社に限定するということです。 自分が作って自分が使うのですから、注意しなければ整備が遅れます。 まがりなりにも使えているので、無駄をそぎ落とす努力が後回しになり、 文書化が遅れ、情報共有が先細りする恐れがあります。 「この技術については、社内のあの人に聞けばいいよ」 という状況は危険です。 知る人ぞ知る「秘伝のタレ」状態が生まれるということですね。
自社が使っているサービスを他社に使わせるというのは、 一見、秘密を外に漏らしているように見えます。 でも実は、厳しい目を持つコンサルタントを雇っているようなものです (しかもコンサルしている側がお金を払っている!)。
先ほどの記事を読みながら「なるほど」と感じたのは、 陳腐化を防ぐための工夫がそこにあると思ったからです。
何をオープンにし、何をオープンにしないか。 その判断は自身の陳腐化を防ぐために重要です。 そしてその判断を行うためには、 自分が生み出している価値が、 いったいどこから来ているのかを見抜く力が要りそうですね。
自分が持つ「秘伝のタレ」は価値を生み出しているのか。
「隠す」ことで自分をガラパゴス化させているのではないか。
そんなことを思いました。
* * *
探す/作るのバランスの話。
結城はプログラムが好きです。
プログラムの魅力の一つは、基本的な部品の使い方を理解したら、 それを組み合わせることでより複雑なものを作れる点にあります。 アイディア次第、というわけですね。
自分が「こういうものがほしいなあ」と思うものがあったときには、
「あっちとこっちを組み合わせれば、実現できるな!」 「ここの値を変えちゃえばできるじゃん!」
のように考えるのが大好きです。
ところで、結城が思うような工夫は、 すでに誰かによって考えられてることも多いものです。 つまり、結城が欲しいものを手に入れるとき、 プログラムを「作る」よりも「探す」方が楽なことが多いのです。
たとえば以前、バージョン管理ツールのgitを使っていて、 「このファイルをいったん脇に置いておきたいな」 と思ったことがあります。そのためのツールを自作しかけたのですが、 実は「ファイルを脇に置いておく」機能はすでにgitにあるのです (git stash)。
また、BootstrapでWebサイトを作っているとき、 「もっとページ全体を大きく使いたいな」 と思ったことがあります。widthを調整して……と思いかけたのですが、 実はcontainer-fluidというCSSのクラスが最初からありました。
あるいはまたMathJaxで数式表示するサイトを作るとき、 「数式表示がちらつかないようにしたいな」 と思ったことがあります。ダブルバッファリングを行い、 レンダリングが終わったところでvisibilityを切り換えれば…… と思ってコードを書きかけました。 でも、MathJaxの公式リポジトリには、まさにそのための例が、 test/examplesというディレクトリの下にたくさんあったのです。
つまり、こういうことです。
ある技術を使って活動をしているとき、 「こういうことをしたいな」 と思ったらまずは公式ドキュメントを読むべき。 自分が考える「改良」や「応用」というのは、 すでに誰かが考えていて、適切な対応方法が確立されていることが多い、 ということ。
安易に「作る」前に「探す」ことも大事。
だからといって、 自分が作ろうとする気持ちが無駄なわけではありません。 「こういうことをしたいな」と感じて、 「こうすれば作れる!」と気がつくということは、 その技術をよく理解している証拠といえるからです。
「作る」と「探す」の話は、また後でも出てきます。
* * *
流動床の話。
砂をたっぷり入れた容器を用意し、そこに空気を吹き込みます。 そうすると、砂がまるで水のような状態になるのだそうです。 「流動床」(りゅうどうしょう)が以下の記事で紹介されていました。
砂の上にカヌーを置いてスイッチを入れると、 いきなりカヌーがゆらゆらと揺れ出すのです。 まるで水の上に浮かんでいるかのように!
冒頭に動画へのリンクがありますのでご覧ください。
◆砂を液状に…カヌーもこげちゃう? 流動床、応用に期待 http://www.asahi.com/articles/ASK554TWKK55UTNB003.html
この動画を見ると、なぜかウキウキしてきますね。 砂場遊びと水遊びが一体化した感じがするからでしょうか。
もう一つ、空気を入れたり止めたりすることで、 固い床と柔らかい床を自在に行き来することができる点も魅力です。 つまりそれは、コンピュータを使って床の固さを 制御できることを意味するからです。
ふだんは固い床だけど、いざというときには水のような表面になる、 防犯用の「落とし穴」も作れそうです。
* * *
アイコンの話。
きっかけはもう忘れてしまいましたが、 最近、メールの設定を変更して「メール一覧でアイコンを表示する」 ようにしています。
あたりまえのことですが、単なる文字の羅列よりも、 アイコンを表示した方が視認性がよくなります。 メールの差出人は詐称しやすいのでアイコンだけで「本人である」 と判断するのは危険ですが、 少なくとも「いつもと違う人」からのメールの識別が簡単になりました。
◆メール一覧にアイコンを使う様子(スクリーンショット)
Macのメール.appでの設定は「メール>環境設定>表示」にあります。
◆メール一覧にアイコンを使う設定(スクリーンショット)
さて、この「改善」はあたりまえのことですが、 結城にはちょっと思うことがありました。 それは「小さな改善の積み重ね」についてです。
上で示したスクリーンショットには、
・Unsplash ・Instagram ・Evernote ・SparkPost ・bitly
からのメールが来ています。これからもわかるように、 これは、サービス利用専用のメールアドレスなのです。
数ヶ月前、結城は自分のメールアドレスを整理しました。 目的ごとにメールアドレスを分けて、使いやすくしました。 あのとき「メールアドレスを分ける」という改善をしていたから、 今回の「アイコンを表示する」という改善が生きたことになります。 なにしろメールアドレスを整理する前は、 spamがいっぱいでほぼすべてが知らないユーザからのメールでしたから。
ひとつひとつはちょっとした改善、あたりまえのことですが、 少しずつそれが積み重なっていくのだな、と感じた次第です。
* * *
それではそろそろ、 今回の結城メルマガを始めましょう。
どうぞ、ごゆっくりお読みください!
目次
はじめに
数式混じりのメモを書く環境について - 文章を書く心がけ
何となく「具合が悪い」ときのチェックリスト - 仕事の心がけ
執筆中の忘却について - Q&A
おわりに
-
Vol.255 結城浩/再発見の発想法/本を読むとき/図版作成/
2017-02-14 07:00220ptVol.255 結城浩/再発見の発想法/本を読むとき/図版作成/結城浩の「コミュニケーションの心がけ」2017年2月14日 Vol.255
はじめに
おはようございます。結城浩です。
いつも結城メルマガをご愛読ありがとうございます。
今週は後半に家庭の用事が入ってしまったため、 一週間の仕事を前半で終わらせるというスケジュールになりました。
「一週間の仕事を前半で終わらせられるなら、 いつもそうすればいいのでは?」 と、自分のどこかで声が響きます。
でも、そういうものじゃないんですよ。
ね?
* * *
情景を想像する話。
ある方が「物語を読むときに情景を思い浮かべられない」 という話題をツイートしていました。
結城の場合、物語を読むときの情景は「自分で作る」感があります。 作者が情景描写で書いている情報を参考にしつつ、 過去に自分が経験した情景を記憶から借りて使います。
それはちょうど、演劇で大道具を準備するのに似ています。 自分の経験と記憶を使って舞台を作るのですね。その結果、 シャーロックホームズが自分の居間でパイプをくわえていることも。
それはまた、夢を描くことにも似ています。 ほら、夢の世界って現実にはありえない構造になっていますよね。 都会の交差点を右に曲がったら自分の実家の裏通りになってたり。 自宅の階段をのぼったら、学校の屋上に出たり。 ちょうどあれと似ていることが読書中にも起きるのです。
私がこのような「読書中の情景は自分の経験を組み立てて作る」 ことを意識したのは、小学校低学年のころだったように思います。 たくさんの物語を読んでいたころですね。
と、いまこれを書いていて気付いたのですが、 このような情景の組み立てというのは実は「雑な読書」 なんじゃないでしょうか。 ほんとうは、作者が描いている場面をひとつひとつ味わって、 その文章に従って想像するべきなのでは?
当時の私は、細かいニュアンスはすっとばして、 対応物・類似物をてっとりばやく思い浮かべていたようです。 「階段」と書かれていたら知っている階段を、 「居間」と書かれていたら知っている居間を、 さっと想像して先に読み進める。 当時の私はものすごくたくさん本を読んだのですが、 それは、こういう「雑な読書」だったからできたのかもしれませんね。
あなたは、物語を読むとき、どんなふうに情景を想像しますか?
* * *
後悔の話。
先日、こんなアンケートを実施しました。 Twitterはアンケートが気軽にできて楽しいですね。
◆あなたが「後悔」するのはどちらが多い?(スクリーンショット)
選択肢は、
・あっ、やってしまった! ・ああ、やればよかった!
の二つですが、 801票のうち両者はほぼ半々となりました。 なかなか緊迫した状況ですね。 こんなに二つが拮抗するとは思っていませんでした。
ちなみに、結城自身はどちらのパターン「後悔」も嫌いです。 とてもとても嫌い。ほんとに嫌いです。 ですから、できるだけ早く気持ちを切り換えようとします。
「あっ、やってしまった!」に対しては、
・キャンセルはできるか? ・対策はあるか?
を大急ぎで考えます。対策を考えているあいだは、 後悔の感情に襲われずに済むからです。
そしてどうしても駄目ならば、
・時間は戻せない! ・現状で最善の次ステップは何か?
のように発想を切り換えます。 「時間は戻せない!」は真実なので、心を納得させやすく、 次ステップを考えることで、 後悔の感情が湧き上がるのを防ぐのです。
「ああ、やればよかった!」に対しても似たように振る舞います。
・そもそも「やる」という選択肢を過去の自分は持っていたか? ・そのとき「やらない」を最善手として選んだか?
そのように考えます。 それによって後悔という感情が大きく育たないように、 小さいうちにつぶしておこうと試みているようですね。
そもそも、後悔の感情は、 受け入れたくない現実にぶつかるときに生じます。 ですから、受け入れてしまうと後悔の感情は育ちません。
私、後悔しないように、必死ですね!(苦笑)
* * *
スーパーの話。
あるスーパーでは、お客様クーポン券(紙)をレジでときどき配ります。 決まった日にそのクーポン券をレジに出すと、割引してくれるのです。 当然のことですが、その日以外では、あるいは紙を忘れたら、 割引にはなりません。まあ、よくある話です。
結城は毎日のようにスーパーに行きますが、 そのクーポン券をよく忘れます。まあ、これもよくある話(かな)。 そして、私はそのことがおもしろくありません。
結城はそのスーパーで買い物をするとき、クレジットカードを使います。 支払いに使うのは、そのスーパーの関連会社と提携しているカード。 そのカードだと、ポイントが付くという特典があります。 それはぜんぜん悪い話じゃありません。 疑問なのは「だとしたら、なぜクーポン券を紙で配る必要があるのか」 という点。
買い物ごとに自動的にポイントがたまるということは、 スーパーは私を顧客として把握している。 だったら、そこから一歩進めば、 クーポン券の割引も自動的に行えそうだ。 なぜわざわざクーポン券を紙で配って、 その紙を特定の日に提示する必要があるのか。 顧客にわざわざ手間を掛けさせるのはなぜ。 そんなふうに不思議に思いました。
いや、まあ、細かい話といえば細かい話ですし、 そんなのスーパーの勝手でしょうと言われればその通りです。 でも、その理由がわからないのでモヤモヤしています。
自分の財布がクーポン券でごしゃごしゃするのが好きな人って、 そんなにいませんよね。いちいちクーポン券を持ち歩きたくはない。 でもその一方で、
「クーポン券があれば割引になります」
とレジで言われて、
「あちゃー捨てちゃったよ」
みたいなのは何だか損した気分になる。うーん……
結果的に、紙のクーポン券が配られると、 「ああ、またこれ、捨てたり忘れたりして、損した気分になるんだろうな」 という印象を受けてしまう。 せっかくの割引サービスなのに、 損した気分の予感があるってサービスとしてどうなんだろう、 なーんて思うのです。
オンラインで顧客の購買状況は把握しているんはずですから、 それに応じて自動的に割引して、 レジで「今回はXXX円分オトクになりました!」 と宣言してくれるだけでいいのになあ…… 毎日のことだから、気になるなあ……
と、ここまで考えてきたところで、結城はふと思いました。
果たして私の感覚はほんとうに一般的なんだろうか?
そこで、さっそくTwitterでアンケート取ってみました。 質問はこうです。
-------- スーパーなどの日常系買い物に関して、 ポイントやクーポンの割引適用を、 お店側にはどうしてほしい? A) 適用できる割引は尋ねることなく毎回適用してほしい。 レジでいちいち聞くな。 B) 適用するかどうかを顧客の私に選ばせてほしい。 レジで勝手に決めないで。 https://twitter.com/hyuki/status/830328902643904512 --------
さて、結果はどうだったでしょう。
◆アンケート結果(スクリーンショット)
このように350票でA)とB)はほぼ同じ結果となりました。 結城は当然A)が大多数になると思ったのですが、 そんなことはまったくありませんでした。
ちなみに今回のアンケートでは「クーポン券が紙かどうか」 についての要素は排除し、割引適用の選択に限定して尋ねました。 今回のようなアンケートでは、経験的に、状況をできるだけ限定し、 二つの選択肢から選んでもらったほうがわかりやすい結果になるようです (アンケート形式でクイズをするときには、選択肢を四つフルに使います)。
ともあれ、自分の感覚だけで考えちゃいけませんね。 考え方は人ごとにさまざま。
クーポン券の話を結城がツイートしたときの自分の心、 それを振り返ると、私は、個人的な気持ちを吐露しているふりをしつつも、
「そうだよね、結城さん、私もそう思うよ」
という声を期待していたようです。
アンケートを取ってみて、 自分の感覚を一般化して考えるのは危険だなと改めて思いました。
* * *
イミテーション・ゲームの話。
アマゾンプライムビデオに映画『イミテーション・ゲーム』が来ていました。 現在は無料で観れるようです(こういうとき、可能を表す「ら抜き言葉」は便利)。
『イミテーション・ゲーム』は、 ベネディクト・カンバーバッチ扮するアラン・チューリングが、 ドイツの暗号機「エニグマ」の暗号を解読する計算機を作る物語です。
ドイツ軍が通信に使っている暗号を解読すれば同胞の命が助かり、 戦争終結を早めることができるのだが…というストーリーですが、 これは、現実の歴史をもとにしています。
数学と暗号とコンピュータが絡み合う物語ということで、 結城がこれまで書いてきたほとんどすべての本に関わりますね。
◆『イミテーション・ゲーム/エニグマと天才数学者の秘密』(アマゾンビデオ) https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B015SAFOBG/hyam-22/
* * *
亜人(デミ)ちゃんの話。
毎週日曜日の夜、 アマゾンプライムビデオで「亜人(デミ)ちゃんは語りたい」を観ています。
先週の第6話「小鳥遊姉妹は争えない」もおもしろかった!
毎回、登場人物ひとりひとりを注目するのですが、 今回は小鳥遊姉妹にスポットが当たったようです。
双子の姉妹だけれど、人間と亜人の姉妹で、 性格も振る舞いもまったく違う。 しょっちゅうケンカばかりしているけれど、 お互いに深いところでは思いやりにあふれている。 そんな姉妹のあり方が描かれていました。
毎週「亜人ちゃんと語りたい」のことを書いていますが、 結城がこの物語を気に入っているひとつの理由は、 「悪人やいじわるな人がほとんど出てこない」 からです。基調として素直な流れで物語は進みます。 けれど、決して単調にならず、また予定調和になるわけでもない。 その微妙なところが気に入っているのです。
登場人物に毎回スポットが当たると書きましたが、 第5話でスポットが当たったのは雪女の雪ちゃんでした。 すると!今週の第6話オープニングでは、 雪ちゃんの登場シーンが変わったのです。 物語の進行に合わせてオープニングが変化するって、 楽しいですね。
来週も楽しみです!
◆『亜人ちゃんは語りたい』(アマゾンビデオ) https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B01N4KENHZ/hyam-22/
* * *
それでは、今回の結城メルマガを始めましょう。
どうぞ、ごゆっくりお読みください!
目次
はじめに
再発見の発想法 - アイコン
本を読むときのあれこれ
本の図版はどのようにして作りますか - Q&A
おわりに
-
Vol.193 結城浩/子育てと「夫婦の一致」/誤読は著者の責任か?/
2015-12-08 07:00220ptVol.193 結城浩/子育てと「夫婦の一致」/誤読は著者の責任か?/結城浩の「コミュニケーションの心がけ」2015年12月8日 Vol.193
はじめに
おはようございます。 いつも結城メルマガをご愛読ありがとうございます。
最近はすっかり「冬」になりましたねえ。 晴れた天気ならばよいのですが、 曇っていたり、風が強かったりすると、 ちょっと「ふにゃあ」とめげてしまいそうになります。
それに「朝のおふとん」の誘惑に負けないのは難しい。 つい「あと五分寝させて」という気持ちになってしまいます。 こんな絵を描きたくなるくらい。
◆あと五分寝させて(イメージ図。どら焼きではありません)
ま、まあ、それはそれとして、 毎日の生活の中に「小さな楽しみ」を見つけて、 元気に過ごしていきたいですね。
* * *
「よかった探しリース」の話。
結城は毎年、クリスマスシーズンに「よかった探しリース」 というWebの企画を行っています。 個人のサイトやブログなどをリンクでつなぐことを、 クリスマスの「リース」に見立てる企画です。
そしてそれぞれのページは、
「今年よかったことを探そう」
という共通のテーマで結ばれています。
毎年実施して、今年で19回目になりました。 もしよければ、あなたも参加してみませんか? こじんまりした企画ですので、どうぞお気軽に!
◆よかった探しリース http://www.hyuki.com/ring/
* * *
「もこもこ」の話。
最近、調子が悪いというのではないけれど、 あれこれ考え込んでしまい、 うまく言葉にならない「もこもこした気持ち」 になることがあります。イメージ図に描くと、 こんな感じ。
◆もこもこ(イメージ図)
Twitterで @tatesuke さんから、こんなリプをいただきました。 「スレッドお化けの触り心地はどんな感じなんでしょうね。 ふわふわなのかもこもこなのか。 個人的には中は空で、風で膨らんでいるカーテンみたいな感じを想像していますが」
◆ふわふわ?もこもこ? https://twitter.com/tatesuke/status/667525008156049409
結城は、スレッドお化け坊やのさわりごこちは、 「触れる相手によって感触が違う」んじゃないかな、 と想像しています。
おもしろいもので、誰か自分以外の人と、 こういうちょっとしたやりとり(おしゃべり)をするだけで、 何だか晴れやかな気分になりました。
ひとりで考え込みすぎるのは、 あまりよくないのかもしれません。 誰かと何ということもない対話をするのは、 意外に大事なことなのかも。
* * *
数学の話。
結城は、ときどき数学の問題を出します。 先日はTwitterのアンケート機能を使って、 こんな問題を出しました。
π度と1ラジアン、大きいのはどっち?
アンケートは24時間で締め切られ、 結果はこんなふうになりました。
◆π度と1ラジアン、大きいのはどっち?(スクリーンショット)
正解は、1ラジアンです。
πは3.141...という数ですから、 π度というのは3.141...度ということになり、 「3度」よりも少し大きい角度です。
ラジアンというのは、その角度に対する円弧の長さが、 円の半径の何倍になるかを表したものです。 ですから、360度は2πラジアンに等しく、 また、180度はπラジアンに等しくなります。 なので、1ラジアンというと「60度」よりも少し小さく、 約57度ほど。
ということで、1ラジアンの方がずっと大きいことになりますが、 先のアンケートでは意外にまちがいが多かったですね。
通常「ラジアン」という角度の単位は、πや2πやπ/2など、 πと合わせて使うことが多いものです。 なので「1ラジアン」はどれくらいかを考えることは少ない。
一方「度」という角度の単位は、30や45や90や180など、 整数で使うことが多いもので「π度」を扱うことは少ない。
結城はそれを考えてわざと「π度と1ラジアン」 を比較させる問題を出題しました。 でもそれは「引っ掛け」という意味ではなく、 「1ラジアン」のおおよその大きさを体感的に知っているかどうか、 それを確かめたかったからです。
実際、ある数学の先生からは「1ラジアンがだいたい何度か」を問うのは、 ラジアンを教えるときには定番の問題だとあとから教えてもらいました。
他にも数学の問題をいくつか出したので、 また、後ほどお話しします。
* * *
スクリーンショットの話。
ふだん仕事でコンピュータを使っているとき、
「いま見ているこの画面を保存しておきたい」
というのはよくあることです。 いわゆる「スクリーンショット」を撮るということですね。 先ほども、アンケート結果のスクリーンショットをお見せしました。
結城はMacでスクリーンショットを撮るツールを三つ使っています。
一つは、Gyazoです。これはスクリーンショットを撮影して、 即時にサーバにアップロードして共有できるというもの。 結城はこのツールの中に含まれているスクリプトを改造して使っています。
◆Gyazo https://gyazo.com/
もう一つはSimpleCapです。ドラッグして範囲指定することもできるし、 前もってサイズを定めておくこともできるので、たいへん便利です。
◆SimpleCap http://xcatsan.com/simplecap/
そしてもう一つはEvernoteクリップです。 スクリーンショットで撮った画像をすぐにEvernoteに保存できるので便利。
参考資料をMacで読んでいるとき、
「あ、ここ、あとで再読しよう」 「この部分はあの本を書くときに参考にしよう」
という部分を見つけたら、さくさくとスクリーンショットを撮り、 Evernoteに保存するようにしています。これは非常に有効。 Evernote上に自分専用の参考書を作るようなものだからです。
そういえば、先日「液晶画面をカメラで綺麗に撮る話」が話題になっていました。 ひとことでいえば「カメラを少し斜めにして撮る」のだそうです。 おそらく画面とカメラで、ピクセルが干渉しないようにするためなのでしょう。
◆液晶画面をカメラで撮るときに出るモアレを消す http://togetter.com/li/901190
* * *
日常生活の中での発見の話。
以下のリンク先は、高等学校の塚本浩司先生が、 生徒が発見したなにげない現象を解明していくという論文です。 まるで、探偵が犯人を追い詰めていくような、 そんなどきどきするお話になっています。
◆コーヒーカップとスプーンの接触音の音程変化 http://ci.nii.ac.jp/naid/110007491429
上のリンクに書かれていたアブストラクトを以下に引用します。
--------- マグカップでインスタントコーヒーを溶かしてかき混ぜるときに, ティースプーンとマグカップがぶつかり,音が生じる。 この音は,インスタントコーヒーが完全に溶解するまでの間, 音程が「くぐもった低い音」から徐々に甲高い音に変化する。 周波数特性を行ってこの現象の原因を解明し,その過程を教材化した。 この教材は,音波・音響や振動に入門する教材にもなりうるが, それ以上に,科学研究の手法を学び, 物理学を身近に感じるために最適の教材となりうる。 ---------
現象から仮説を立て、それを検証していくという、 まさに、科学的研究の王道を行くような論文です。
この論文は、以下の @qutrit_a さんのツイートで知りました。
https://twitter.com/qutrit_a/status/668247116477833216
* * *
文章を書く人が一人いると、 それを喜ぶ人が九九人いて、文句言う人が一人いる。 文句言う一人のために書くのをやめてはいけない。
人気が出て、喜ぶ人が九九万人に増えたら、 文句言う人は一万人に増える。 それでも、書くことをやめてはいけない。
* * *
CodeIQの話。
結城は現在CodeIQというサイトで、 「マヨイドーロ問題」というプログラミングの問題を出題しています。
先週の木曜日から公開されたのですが、 週明けの月曜の朝の時点ですでに300人以上の人が挑戦しています。 ありがたいことです。
◆結城浩の「マヨイドーロ問題」 https://bit.ly/c19mayoi
今回は一年ぶりの出題になるので、 少し趣向を変えて「自動採点問題」にしてみました。 つまり、解答者がプログラムを送信すると、 即座に正解/不正解が判定できるという方式です。
この方法だと、解答者は何度でも挑戦できますし、 自分の頭に情報が残っているうちにフィードバックを受け取ることになるので、 より楽しくチャレンジできますね。
それはそれでけっこうなことなのですが、 出題者としてはいささか緊張感が高まることになります。 つまり、自分が用意する「正解」がほんとうに正しいかどうか、 前もって確信を持って用意できなければいけないからです。
あたりまえのように聞こえるかも知れませんが、 実はあたりまえではありません。
昨年結城が使っていた方法では、解答者の投稿をすべて受け取り、 〆切が過ぎてからフィードバックを(半手動で)行っていました。 つまり、解答者がどんな解答を行ったかを、 フィードバック「以前」に見ることができたのです。 多数の解答者の答えを見ることで、 結城自身が用意した「正解」がほんとうに正しいかを確認できたという意味です。
しかし、今回のような自動採点の場合にはそれができません。 結城が一人で「私の用意する解答は絶対に正しい」と確信できるほど、 準備を整えなければならないのです。
それは、問題を出す立場としてはある意味当然の準備になるわけですが、 なかなか緊張するものではあります。 しかし、その反面、実際に問題がオープンされ、 多くの人が正解を出し始めると、 結城は出題者として大きな満足感を得ることになります。
プログラミングに慣れていない人は、 自分の書いたプログラムが「動くかどうか」が最初の課題となります。 でも、実はプログラムが動くかどうかというのは、 ある意味ではやさしい課題です。 なぜかというと、動かなければ、 動かないことが「すぐわかる」からです。 エラーになりますからね。
それに対して、それらしい結果が出たときに、 それが「ほんとうに正しいのか」を判断することは難しい。 とっても難しい。
その難しさというのは哲学的な意味合いも帯びる。 なぜかというと、プログラムを使って解く問題というのは、 おうおうにして、
「非常に規模が大きいため、 人間が実際に試すことができない問題」
だったりするからです。
人間が実際に(たとえば手計算で)試すことはできない。 プログラムを使ってはじめて得られる答えが目の前にある。 さてさて、これは、正しい答えだろうか。
そして、もしもプログラムを経ずして正しい答えだといえるなら、 プログラムを使う意味はどこにあるのか。
そういう意味で「プログラムの出す結果が正しいか」 という判定は非常に難しい問題をはらむのです。
そんなことを考えつつ、CodeIQの問題を作っています。
* * *
レトリカル・クエスチョンの話。
レトリカル・クエスチョン(修辞疑問)というのは、 疑問の形をしているけれど、その真意は疑問ではないという文です。
「どうして、こんなことしたの?」
というのは疑問の形をしていますが、 叱責であることも多いですよね。 答えを知りたくて聞いているのではなく、 怒っているだけ。
ちょっと意識すると、 レトリカル・クエスチョンは日常生活のあちこちで見つかります。 自分自身が使うときもあるし、 他の人が使っているのを耳にすることもあります。
先日ファミリーレストランで、 小さな子供が飲みものをひっくり返したとき、 親が、
「どうしてちゃんと押さえてないの?」
と叫んでいました。 これも、レトリカル・クエスチョンの一種ですね。 別に押さえていない理由を知りたいわけではない。 親は「ちゃんと押さえなさい」と怒っているのです。
レトリカル・クエスチョンは叱責になるとは限りません。 子供の歌で、
どうしてお腹が減るのかな? ケンカをすると減るのかな?
というものがあります。あの歌も、歌詞を注意深く読んでみると、 レトリカル・クエスチョンであることがわかります。 「お腹が減る理由」を知りたいというのは真意ではなく、
おかあさん、おかあさん。 お腹がすいたから、何か食べるものちょうだい!
という歌なんだよな、と思います。
仕事でレトリカル・クエスチョンが飛び交うのは考えものですが、 日常生活においては、微妙なニュアンスを出し、 ときにはいい効果を上げる場合もあります。
あなたのまわりには、 どんなレトリカル・クエスチョンがあるでしょう。
* * *
それでは、今週の結城メルマガを始めます。 今回は、いつもの読み物の他に、
「誤読は著者の責任か?」
というQ&Aをお届けします。そこでは、 『エンジニアとして世界の最前線で働く選択肢』 という書籍の著者、 竜盛博さんとのメールのやりとり全文を書きました。
◆『エンジニアとして世界の最前線で働く選択肢』(竜盛博) http://www.amazon.co.jp/gp/product/4774176567/?tag=gnk-22
どうぞ、ごゆっくりお楽しみください!
目次
はじめに
子育てと「夫婦の一致」
誤読は著者の責任か? - Q&A
数学の問題
おわりに