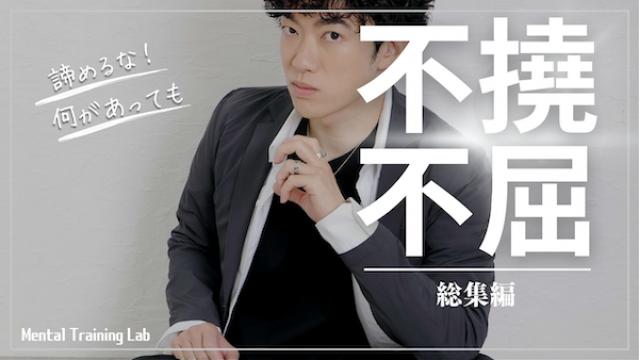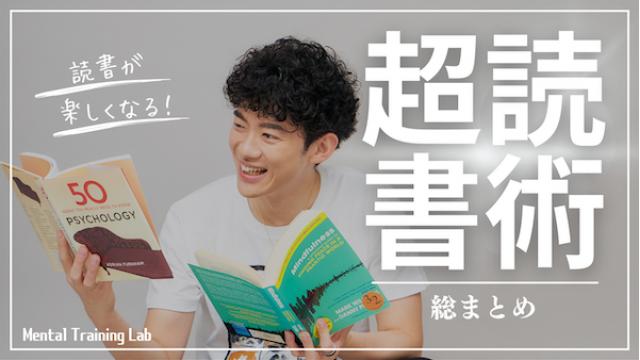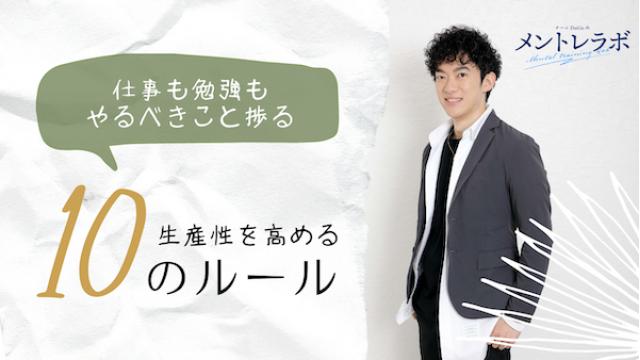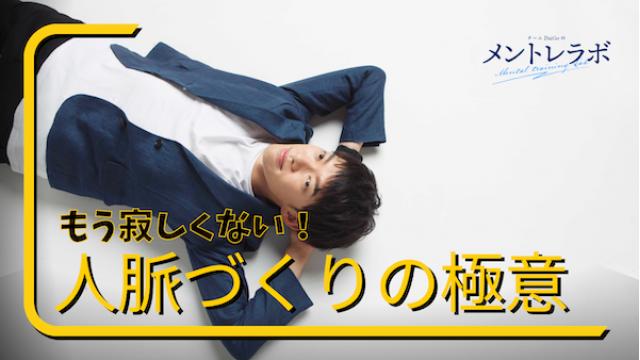-
一問一答「あなたが、絶対に諦めたくないことはなんですか?」【諦めない力】
2023-06-29 12:50330ptあなたが、絶対に諦めたくないことはなんですか?
今回は、挫けることなく諦めない力について纏めさせてもらいます。
諦めない人のための科学
行動できる人もいればできない人もいます。
リスクを恐れず挑戦することができる人もいればできない人もいます。
この勇気は性格特性です。
つまり、ある程度は生まれながらにして持っているものです。
まずは、勇敢さや勇気というものは生まれながらのものだという切ない事実を受け止める必要があります。
ですが、だからといって仕方がないと諦めないのが科学者です。
科学者は、勇気に満ち溢れて勇敢な行動をとることができる人をとことん調べて、その中でも普通の人が真似できる要素について明らかにした上で、それを後から身につければ結果的には同じだと考えます。
今の心理学では、人生を変えるためには性格ではなく行動を変えればいいと言われます。
性格を変えるのはなかなか難しいですが、内向的な人でも外向的な人のような行動をとることができればいいだけです。
人間の性格と行動は別だと考えてください。
それでは、ここからは具体的に必要な要素について3つのポイントを紹介させてもらいます。
要素①自己効力感
自己効力感というものは、自分が行動を起こすことによって少しでも未来が変わると信じることができる力です。
「やればできる」という感覚です。
目の前の困難に立ち向かって、自分の能力を発揮しながら少しずつ未来を変えていく信念のことです。
この自己効力感のために絶対にしてはいけないことは、「圧倒的に上の人と比べる」ということです。
現代において、スマホや SNS の普及によって皆さんの自己効力感はかなり下がっていると言われています。
お金を稼ぎたいと思っている男性が TikTok を見れば、美女とお金に囲まれた画像の男性が出てきます。
スタイルを良くしたいと思っている女性が Instagram を見れば、骨格的にどう考えても無理だと思えるようなスタイルの美女がいくらでも出てきます。
自己効力感は、自分が行動したことでほんの少しでも未来が変わるという感覚を積み重ねなければ身につかないものです。
ですが、そんな圧倒的レベルの人の生活を簡単に見ることができると、自分がコツコツと積み重ねることでのプラスが見えなくなってしまいます。
例えば、年収400万円の人が410万円になったとしたら、それも自分の努力の積み重ねで喜べるはずなのに、スマホを開くといくらでも年収2億円3億円の人が目に入ります。
そうなると、いつまでたっても自己効力感が養われないので、そこから脱出することも難しくなってしまいます。
要素②自尊感情
成功することが難しい問題やリスクがある課題に対して、立ち向かってそれをやり遂げようと思うと、自分の性格や自分の能力、自分のキャラクターなどをある程度認めることが必要になります。
自分を認めることができている人でなければ、自分の持ったものを活かして、目の前のことに向き合おうとすることはできません。
自分にはネガティブな部分もあり弱点かもしれないけれど、それ以外である程度いいところもあって、それを上手に使うことができれば前に進んでいくことができると覚える必要があります。
要素③開放性
困難や危機を目の前にした時に勇敢な行動を起こすためには、開放性や好奇心というものがとても重要になります。
好奇心がない人は基本的に新しい行動をとることが難しくなります。
つまり、諦めることなく行動できる勇気を持つためには、
①目の前の困難に立ち向かうための自己効力感
②自分の能力を発揮するために自分を認める自尊感情
③新しいものを求めて試すための好奇心
これら3つの特性を鍛えればいいということです。
これらは自らの訓練や周りからのサポートによって鍛えていくことができる特性です。
後から鍛えることができる勇気につながるポイントです。
あきらめない人の考え方:「まだ」の思考
挫けてしまう人と挫けない人の最も大きな違いとしては、達成するべき目標がひとつありそこにたどり着くことが全てであり、その目標にたどり着くまでの過程を軽視してしまうというのが挫ける人の特徴です。
そのため、挑戦してみたけれどうまくできなかったとか、自分の思っていたイメージと違うというだけですぐに諦めてしまいます。
これがすぐに挫けてしまう人の考え方です。
一方で、決して諦めない挫けない人の考え方は、常に「まだ・・・」という言葉を使います。
「もっと」ではなく、失敗した時には「まだうまくいかないだけ、きっといつかはできる」と考えますし、ある程度うまくいっている時には、もうこれぐらいで十分だと考えたりしてやめてしまうのではなく、「まだ自分はできるはず」だと考えます。
つまり、挫けない人ほど「まだ」という言葉を多用します。
これは英語では「the power of yet」という言葉になりますが、この「まだ・・・」という思考が重要です。
ですから、挫けそうになった時には「まだうまくいっていないだけ」だと考えるべきですし、諦めてしまいそうになったり妥協しそうになった時には「まだ自分はできる」とか「まだあと1回はできる」と考えるようにしてください。
もしある程度うまくいってもう十分かと思い始めた時には「まだ自分は成長できるはず」と考え、「まだ」を多様するようにしてみてください。
あきらめない人の考え方:「階段思考」
これは人間の成長に対して使われている思考です。
人は物事が常に右肩上がりで上がっていって欲しいと思うものです。
実際には当然ながら浮き沈みを繰り返しながら、それでも続けていれば長期的には成長していくはずです。
そんな中では、どうしても停滞することもあれば、そのまま続けても意味がないのではないかと思ってしまうときもあります。
挫けそうになるときは誰でもあるものですが、そんなときに使えるのがこの階段思考です。
人はどんな物事でもスキルでも常に右肩上がりで上がっていくことを期待しますが、実際にはそうではなく階段状に成長していくものです。
一度上達したり成長するとしばらく停滞する時期があり、そこで何かコツを見つけたりきっかけがあるとまた一段上がります。
これはどんなものでも同じで、例えば、YouTuber でも何かをきっかけにチャンネル登録者数が増えたりします。
そして、しばらく停滞してまた何かをきっかけに伸びます。
停滞しても怖がる必要はありません。
停滞しているというのは階段の平らなステップを進んでいるタイミングだからです。その平らなステップを耐えながら続けていれば必ず一段登れるときが来ます。
これが普通ですし、人生というものはこれと同じです。
皆さんの中にも、常に成長し続けないといけないと考えたり、毎日必ず進歩しないといけないと考える人もいると思いますが、その自分の進歩を感じることはとても重要です。
毎日どんな小さな進歩でもいいのでそれを感じることで僕たちのモチベーションというものは湧いてきます。
ですから、毎日の進歩を実感することは大切ですが、欲張りすぎないようにしてください。
常に右肩上がりに成長していかないといけないと考えてしまうと、それは大きなプレッシャーになってしまいます。
どんなものでも常に階段状で上がっていくものだということを理解していただければ、 あきらめない人の考え方を身につけることができるはずです。
人生というものは階段状に成長していくものです。
あきらめない人の考え方:「うまくいかない時は10%だけ変える思考」
人は行き詰まったときに同じことを繰り返そうとしてしまいます。
なぜうまくいかないのかと考えながら、ずっと同じ方法を続けていることがよくあります。以前はこの方法でうまくできたのになぜうまくできないのかと行き詰まります。
失敗したりうまくいかないと「以前はうまくできたのになぜできないのだろう」と考えがちですが、これが危険な考え方です。
以前うまくいった時と何が違うのだろうと悩んだりしますが、人間は以前と同じことをしているつもりであってもどうしても少しずつ違っています。
体調や周りの環境によっても少しずつ変わりますし、ビジネスなどの場合にはトレンドというもっと大きな動きにも左右されてしまいます。
ですから、以前はこの方法でうまくいったはずだと考え同じことを繰り返すのではなく、気づかないうちに何かしらの条件が変わっている可能性もあるわけですから、一旦その考え方をリセットする必要があります。
うまくいかないときほど少しだけ変えてみることを意識してください。
うまくいかないときにその方法を少しでも変えてしまうと、余計にうまくいかなくなってしまうと考える人もいるかもしれませんが、少しだけ変えてみてうまくいかないのであれば、その方法が間違っているということを理解できるだけです。
とはいえ、あまりに大きく変えてしまうと、それもプレッシャーになってしまうので、お勧めとしては10%変えるということを意識してみてください。欲張ったとしても20%ぐらいまでにしてください。
少しだけ方法を変えてみるということが重要になります。
これはビジネスであってもスポーツやスキルであっても同じです。
今の方法がうまくいかなくなっているのは皆さんの周りの環境や条件が変わっているからです。
ですから、自分もそれに合わせて変わっていく必要があるわけですが、大きく変える必要はなく、ほんの少しだけでいいので変えてみるということをうまくいかない時ほど試してみていただけるとスランプを抜け出しやすくなります。
皆さんの求めていることや目標も色々とあると思います。
もっと自由な生活をしたいとか、仕事の効率を上げたい、もっと友達を増やしたい、今年こそはダイエットをしたいなど色々とあると思いますが、それも突然多くのことを求めてしまうとなかなか難しいことですし、プレッシャーになりかえって何も出来なくなってしまいます。
今の生活より10%だけ自由な生活を手に入れるには?
仕事の効率を10%だけ上げるためには?
友達の数を10%だけ増やすためには?
運動やトレーニングの量を10%だけ増やすためには?
このように10%だけ変えるには? と考えてみていただけると、くじけない人の考え方を身につけて、目標に向かって進むための糸口を見つけることもできると思います。
ちなみに、自分が調子がいいときには10%ではなく10倍にすることを考えてください。
10%というのは少し頑張ればできるような数字だったりもします。
10%変えようと思うと、仕事であれば少し無理をしたりいつもより長めに働くことで、それができたりもします。
そうなると新しいアイデアも生まれなくなってしまいます。
ですから、自分の調子が悪かったりスランプを感じているときには10%だけ変えてみるということを意識してもらい、逆に、自分の調子が良くて自分を大きく変えようと思ったときには、「10倍にするにはどうすればいいのか?」と考えてもらえると、それにより思考の幅が広がりますので、新しいアイデアを生み出すことにもつながります。
この使い分けを覚えておいてください。
あきらめない人の考え方:「トライした回数をカウントする思考」
人はどうしても結果に縛られてしまいがちです。
自分が調子がいいときや目標に向かって頑張っている時というのは、自分が成功した回数をカウントしていれば、それによりどんどんモチベーションが湧いてきて進むことができます。
ところが、その結果としての数字にとらわれていると、その数字が下がった時に自分の心が耐えられなくなってしまいます。
成果が出なくなったときであっても、そんな中、常に挑戦し続けている自分を誇りに思ってもらいたいので、トライした回数をカウントするようにしてください。
例えば、YouTube でチャンネル登録者数が増えなくなってしまったというのであれば、登録者数が増えなくても、毎日欠かさず動画を投稿し続けているということを誇ればいいわけです。
これは、さらに言うと、伸びていないときであれば今までよりも投稿回数を増やすとか考えてみてください。
伸びていないときには色々なことを試すことができるタイミングだと考えます。
うまくいっていないのであれば、回数を増やしたり、今より工夫してみたりして、そのトライする回数をカウントしてください。
それにより挫けることなく続けることができて、いつかは先ほど紹介したように階段状の一段ステップを登ることができます。
あきらめない人の考え方:「Why ではなくHow で考える」
うまくいかないときには、人は、なぜうまくいかないのだろうとか、こんなに頑張っているのにどうしてうまくいかないのかと悩んでしまうものです。
この「どうして?」「なぜ」:Why? という思考になると、人はどんどん自分を責めてしまいます。
うまくできることが前提になっているので、なぜそれができないのかと自分を責めてしまうわけです。
そうではなく、「どうすれば?」「どのような方法を新しく試せばいいのか?」:How? という考え方にしてください。
うまく数字が伸びていないのであれば、今まで試していないことでどんな事をすれば伸びるだろうかとか、どのような変化をさせてみればうまくいくだろうというようなことを考えます。
Why? という質問は常に過去に向いてしまいます。
これは仕事でも人生でもどんなことでも同じです。
「なぜ自分はこんなにも苦しいのだろうか?」
「なぜ収入が低いのだろうか?」
「なぜ自分は集中力が低いのか?」
ということを考え始めると、過去に対して目がいくようになります。
そうなると、自分はいい大学を出ていないからだとか、自分は家庭環境に恵まれていなかったから、子供の頃に一生懸命勉強しなかったから・・・というように、Why?:なぜ? を考え始めると、全て過去に目が向いて後ろ向きな思考になってしまいます。
一方で、How?:どうやって? を考えると、これからどのようにすれば学歴を乗り越えるような能力を身につけることができるのか?、どうすれば新しいことを習慣化できるのだろうか?、どうすればこの苦しい状況を乗り越えることができるだろうか? というように、思考が前に向きます。
これは無駄にポジティブ思考になるべきだというわけではありませんが、あきらめない人やくじけない人はほとんどの場合その思考が「How?」です。
だから、思考が後ろ向きにならず挫けることなく頑張ることができるわけです。
粘り強く物事に取り組む能力
人生の成功に必要なスキルに関するロンドン大学の研究を見てみると、52歳以上の男女8119人を対象に11年間にわたり追跡調査したというものですが、この研究でも、やはり、ひとつのことに諦めないで粘り強く取り組む力が成功のためには重要だということがいわれています。
この粘り強さとは学習可能なものです。つまり、後から身につけることができる能力です。
粘り強さを測る方法
1940年にハーバード大学の研究チームが行なった実験で、健康な男女を対象に角度のついたトレッドミルで5分間走ってもらうようにお願いしました。
かなりの角度がついて、よほどきつかったようで、5分間走るように指示したにもかかわらず大抵の被験者は4分間までで脱落しました。
そのトレッドミルでどれくらい走り続けることができるのかということをチェックした上で、その後数十年経ち参加者が60代になった時にもう一度集めて、彼らの収入や仕事に関するキャリア、社会的な活動や仕事に対する満足度、結婚しているかどうかということや夫婦関係の満足度からメンタルの状態というようなことまで調べました。
それにより、若い時にトレッドミルで5分間走り続けることができていた人たちと、走りきることができず途中で諦めてしまった人たちで、人生に何かしらの違いが表れていたのかということを調べようとしたわけです。
要するに、若い時の粘り強さが将来に何かしらの影響を与えるのかということを調べています。
その結果、粘り強さが強くトレッドミルで5分間走り続けることができた人は、収入やキャリアも、社会的な活動や仕事に対する満足度も高く、結婚状態もメンタルの状態も良かったということです。
ここまででは、トレッドミルで走り続けることができた人はただ単に運動能力が高かっただけではないのかと考える人もいると思います。
運動能力が高かったので歳をとってからも良い人生を歩んでいただけなのではないかという議論が、最初にこの論文が出た頃には起きました。
ところが、被験者たちの肉体能力を調整した上でも同じ現象が確認されました。
ですから、体力があるかないかということにかかわらず、若い頃から目の前のことに粘り強く取り組むことができる能力を持っていると、歳を重ねれば重ねるほどその差は大きく開いていくということです。
もちろん、歳をとってからでも鍛えるに越したことはありませんが、できるだけ若いうちに身につけておくと、人生の成功に対して大きく影響してくる可能性があるということがいえます。
ひとつのことに取り組んで心が折れそうになっても粘るという体験を重ねれば重ねるほど、諦めない力は鍛えられ人生にとってもメリットは大きくなるということです。
例えば、読書をしている際になんとなく内容が難しくなってしまったので、ちょっと LINE でも見てみようかと思い、自分が粘り強さを発揮できない状況に気付いたら、そこで粘り強く頑張ればそれは将来のためになるはずだと考えて諦めない力を発揮していくことが大切です。
お勧めとしては、そんな心が折れそうな作業を1日に1回や2回でもいいのであえてするようにしてみてください。
例えば、1日30分でもいいのですぐに心が折れてしまいそうな難しい本を読むようにしてみてください。難しくて心が折れそうになっても30分間は頑張って読むようにします。
本ではなく、筋トレやスポーツでもいいと思います。HIITのような心が折れそうになる運動を毎日続けてもいいでしょうし、筋トレであれば、あげられる限界ぐらいまで変化をつけながら体を追い詰めていくというのもいいと思います。
習慣化のテクニックを使って、継続的に新しい習慣を身につけていくというのもいいと思います。
粘り強さを鍛えることによって、それは人生の後半で大きな差として影響してくるものだということを覚えておいてください。
過去を乗り越える力も身に付く
2019年のフィンランドアカデミーの研究で、2018人の学生を対象に全員の粘り強さを調べる実験を行いました。
その上で、全員を6年生から9年生まで追跡調査して、学業の成績との相関を調べました。
要するに、粘り強い人は学校の成績もいいのかということを調べようとしたものです。
その結果わかったこととして、8年生の時点における粘り強さが9年生になったときの学業の成績と相関しているということでした。
この結果は、その人の誠実性や過去の成績を調整した上でも同じ傾向が確認されました。
つまり、過去の自分の成績が悪かったとしても、性格としての誠実性が低かったとしても関係がないわけです。8年生の時点で粘り強さをちゃんと発揮することができていれば、1年後になった時にはちゃんと成績として結果がついてくるということです。
ですから、過去の成績や成果が今ひとつだったとしても、今から粘り強さを身につけることができれば、1年や2年のスパンでも確実に結果として現れるということがこの研究から見えることです。
ちなみに、6年生の時点での粘り強さもゴールへのコミットメントに相関していたということもわかっていますので、粘り強さを身につけることができれば、将来の成果はもちろん、その時点でもゴールへのコミットメントも強くなるということも言えます。
過去は関係がなく、今から粘り強さを身につけることができれば、僕たちの人生は短いスパンでも変わっていくということを覚えておいてください。
ここから先は、実際に粘り強さを身につけるための方法について解説していきます。
人生も、これからの可能性も、諦めることなく挑戦していくためにぜひ続きもチェックしてみてください。
-
【総集編】あなたが勇気を出して行動したいことはなんですか?【現状打破の心理学】
2023-06-15 12:00330ptあなたが勇気を出して行動したいことはなんですか?
今回は現状を変えるための勇気の出し方についてまとめさせてもらいます。
新たな一歩を踏み出したり、日々変化し成長していくために参考にしてください。
臆病になることで安全を確保することもできますが、多くの人が臆病すぎます。
僕たちには間違う自由があります。
間違った場合にも他人にとやかく言われる必要はありませんし、万が一法律に引っかかった場合には、法律に従って処罰を受けるというだけです。
ですが、特に今日本は失敗した人を批判したり叩いたりします。
失敗した人を笑い続ける人生は、失敗する人生よりもはるかに惨めです。
それに気づくことがなく、自らの幸せを諦めた人間が他人の不幸を望む状態になっています。
皆さんは臆病にどんどん追い詰められています。
今回はそんな追い詰められた臆病を追い払い、自分の人生を手に入れるための方法を解説させてもらいます。
極度のストレス状況でも勇気を出す方法
とはいえ、失敗が怖いとか周りからのプレッシャーが気になって挑戦できないという人も多いと思います。
これは芸能界でも同じだと思いますが、今はこのような悩みを抱えている人が増えているような気がします。
芸能界であれば、タレントさんも俳優さんも昔はかなり無茶苦茶な人が多くいました。
それがいいかどうかは別として、そんな無茶苦茶なことが許された世界でも、人はこうあるべきだというような周りからの圧力が強くなっています。
皆さんも感じていませんか?
この会社の社員であれば〜あるべき
旦那としては、嫁としては、〜あるべき
社会人としては〜あるべき
男なら、女なら、〜あるべき
この「べき思考」が日本中で蔓延しています。
この考え方を受け入れてしまった瞬間に、皆さんは他人の人生を生きることになってしまいます。
自分らしさを失って、自分以外の誰かの人生を生きろと強制されています。
こんなにも強烈なストレスは他にありません。
このストレスは挑戦をしなくなる方向に働いてしまいます。
皆さんに対してこのべき思考をぶつけてくる人がいると思います。
ただ、彼らは新しい変化が怖いだけです。
新しいものが次々と現れてくる中で、それを受け入れると自分たちの人生を否定されたように感じています。
自分たちの人生を否定されないために、「常識」「普通」「レッテル」などを使って、これからの若い世代や挑戦し続ける人にストレスを与えます。
人はストレスを感じると勇気が出なくなります。
彼らはストレスやプレッシャーを与えて皆さんをコントロールしようとしています。
時代の変化にもついていけないし、新しいことができない人がいます。
このような人は、ヤフーコメントに夢中になって他人の足を引っ張ろうとしています。
ネット上の嫌な奴は実生活でも嫌な奴である可能性が高いです。
アメリカ陸軍も採用している勇気を出す方法
勇気に関する研究はたくさんあります。
どうすれば多くの人が思うようなリスクを取れたり、勇気ある行動を取れるのかということについて研究している人は結構います。
そんな中でも、今回はアメリカの陸軍でも採用されている勇気を出す方法についてです。
軍隊になってくると当然ですが命が関わってきます。 そんな命が関わる状況においても勇気を出す方法ということですから、人間にとって最も強い勇気を出す方法と言えます。
彼らがどのようにして勇気を奮い立たせているのかということを調べてみると、興味深いことが見えてきます。
これは日本とは違うところでもありますが、アメリカでは軍隊や国の機関であっても科学的な知見がしっかり取り入れられています。
例えば、軍隊であれば、悲惨な状況を目の当たりにしてトラウマを抱えて国に帰ってくる人もいます。 そのような人に向けてメンタルを改善するプログラムも結構使われています。
大事なのは、自分が何を手に入れるために戦っているのかということを明確化することだと思います。
リスクと向き合えないとか、勇気を出せないという人もいると思います。 自分の人生の中で大きな挑戦はできないという人もいるでしょうが、それがどのようなことが原因になっているのかということが明確になれば、そこから具体的に前に進んでいくことができると思います。
勇気ある行動と言われても、人それぞれ様々な考え方があります。 人によっては、自分が信じたことを貫くことと考える人もいますし、みんなが否定しているものをあえて踏み込んでリスクを取ることと考える人もいます。 人によって考え方が違う部分があるので、「勇気」は定義するのが難しいです。
そんな様々な「勇気」がある中、自分に必要な勇気を見つけたり、足りない勇気に気づいていただける内容になるかと思います。
それを見つけて補っていただけると、皆さんの勇気はブーストしていくと思います。
自分は他人の意見も気にしないし、リスクも取れるし勇気がある方だと思っている人もいるでしょうが、本当の勇気とは何なのかということを知ってください。
ポイント1:経験に対する寛容さ
勇気がある人は創造力がある人です。
いいアイデアを作るためには、ひとつのことに集中するのではなく、一見無駄だと思えることに対しても思考を巡らせる拡散的思考が必要になります。 無駄に感じるような時間に対しても心をオープンにしてもらい、自分の思考を広げていかなくてはなりません。
この拡散的思考と創造性の高さが上がれば上がるほど、自分の無駄に思えるような経験や行動に対しても寛容になれて、経験に対する寛容さを持つことができます。
人間は自分の知っているものばかりを認めるようになってしまいます。 冷静に考えると、これは勇気ではありません。
勇気がある人は自分が認められないものに対してもオープンに心を開いて受け止めます。 その受けたものが、仮に自分の今までの人生の中での経験を否定するものであったとしても、それを受け入れることができるかどうかということが重要になります。
ないものを受け入れる勇気です。 このないものを受け入れる勇気とは創造力です。
創造力のない大多数の人が否定するものに対して、自分の創造力によって可能性を見いだす人が勇気がある人です。 勇気がある人は無謀に手を出したり余計なリスクを取っているわけではなく、周りの誰もが否定していても、その可能性やメリットに気づく人です。
つまり、勇気とは「気づくこと」です。
気づくためには、普段から様々な可能性に目を向ける必要があります。 そのために必要なのが創造力です。
勇気を持つためには創造力を高めて人生の選択肢を広げる必要があります。 選択肢をたくさん持っている人は、自分の外側からもたらされる多くの人が否定することに対しても興味を持つことができます。
ですから、創造性やクリエイティビティを高めていかないと勇気を持つことはできません。 自分が想像できない未来を受け入れることができる人はほとんどいません。 経験に対する寛容さが重要になります。
人は年齢を重ねる度に、自分とは違う経験や考えを受け入れられなくなります。 普段から創造性を鍛えることで、自分とは違う価値観や新しいものを受け入れる力を養っておいてください。 自分に思いつかないアイデアに普段からどれぐらい向き合っているかです。
ポイント2:誠実性の高さ
勇気を出すために必要な特性として、誠実性の高さもあります。
勇気は自分の内側から湧いてくるものだと考えている人が多いと思います。 確かに、勇気を出せるかどうかは、その半分ぐらいは生まれもったもので決まりますが、残り半分は「義務感」で決まります。
自分以外の人間からどれくらい義務感を感じるかということが重要なポイントになります。
例えば、皆さんも誰にも伝えることなく自分だけでダイエットをしようとすると、ついつい誘惑に負けたり挫折してしまいがちだと思いますが、自分が本当に尊敬している人や一番大切な人と約束したら、そこに責任や義務感が生まれると思います。
自分だけであればいくらでも先延ばしすることができますが、尊敬している人との約束があったり、大切な人と一緒に取り組んでいるとなると、それを行うしかなくなります。
これが義務感です。
誠実性が高い人は、自分に対しても他人に対しても義務感を感じやすい人です。 自分をちゃんと保たなくてはならないという義務感もあれば、他人との約束は守らなくてはならないという義務感もあります。
この義務感があればあるほど、人はくじけそうになった時にも勇気を発揮することができます。 辛い状況に陥ったとしても勇気を出して乗り越える確率が高くなります。
誠実性が高い人は、人と関われば関わるほど自分と相手との間に義務感を感じるようになります。 その結果、自分をコントロールすることができて勇気を出すことができます。
ポイント3:コア・バリュー(核となる自己評価)
自分をどう評価するかということは、勇気を作り出すために重要なことです。
皆さんは、嫌なことがあった時にそれを自分のせいだと思いますか? それとも、環境や周りのせいだと思いますか?
どちらかだけということはないでしょうが、多くの人は嫌なことがあった時に、自分のせいだと考える前に他人のせいを疑います。
少し相手の態度が悪かったら、嫌われてしまったのではないかと疑い、仕事がうまくいかなかったら、上司の伝え方が悪かったのではないかと疑います。
この良いことが起きたり悪いことが起きた時に、その責任をどこに置くかということを統制の所在と言います。
良い事が起きたり悪いことが起きた時に、その責任や原因を自分の内側に置く人もいれば自分の外側に置く人もいます。
この特性がかなり重要で、自分がその状況をどうにかできると思えるかどうかが核となる自己評価です。
短期的にみると、他人に責任を押し付けることができる人の方が楽に生きることができます。
ですが、勇気を持って戦うためには長期的な視点が重要になります。 勇気を持って行動した結果うまくいかなかった時に、それを改善していくことができるのは統制の所在が内側にある人だけです。
自分のせいだと考えると、自分を責めたり最初は辛いかもしれません。 ですが、自分が悪かったのであれば、自分を改善すれば未来は変わります。 だから勇気を出すことができます。
全てが自分のせいではないとしても、自分で改善できるポイントに目を向けることができるかどうかです。 自分を責めたとしても、それを乗り越えることができれば、改善することで開ける未来が見えます。
ですが、統制の所在が外部にある人は、自分が本当に向き合わなければならない問題を他人のせいにしてしまいます。 この人は他人が変わるまで変わりません。 他人に人生をコントロールされています。
統制の所在が自分の内側にある人は、自分を改善すれば未来は変わると思えるようになります。 それを積み重ねていけば勇気を持てるようになります。 自分が行動すれば未来が変わると思えるわけです。
自分を責めるのは良いことではありません。 自分を責めるのではなく自分に起きた結果を受け止めて、その中で自分がコントロールできるところに目を向けてください。 自分がコントロールできるものとできないものを見極めることができれば、自分を改善して人生を変えていくことができます。
世の中では自分でコントロールできないところに対して文句を言ったり批判している人が大勢います。
自分の生まれや置かれた状況を嘆いてばかりで行動できない人もいます。
ですが、同じような苦しい過去や状況があったとしても、そこにどう向き合うかで人生は変わります。
ポイント4:自己効力感
自分の望む未来や結果を、自分の能力でどれぐらい手に入れることができると思っているかです。
やればできる感覚が勇気を出すためには必要です。
当然ですが、自分が行動してもうまくいかない気がすると行動なんてできません。
自己効力感を高めるためには、どんなものでも構いませんので何かしらの専門的なスキルを習得してみてください。
自分はそれについての専門家だと言い切れたり、自分を表現できるようなスキルを持っているかどうかが重要です。
自分を表現する際にアピールできるスキルや技術がないのであれば、勇気を出して行動するために、まずはそこから始めてみるのもいいと思います。
もちろんスキルや技術がないからダメということではありません。
今現在の自分の置かれた状況や問題点、何かしらの苦難を違う形に再解釈できるかどうかも重要になってきます。
特に専門的なスキルがなくても、何とかなるだろうと考え行動できる人もいます。
例えば、心理学の知識があるから、何かしら問題やトラブルが起きても、とりあえず対応策を考えることができるだろうと考えることができる人もいれば、特にその根拠はなくても同じように行動できる人もいます。
このように考えることができる人は、自分の置かれた状況や課題に対して、異なる目線で見ることができる人です。
例えば、借金10億円を抱えて人生終了だと考える人もいれば、それを違う目線で見て、逆に考えると10億円も借りることができる信用があるわけだから、それだけの信用を使って別のことができるのではないかと考えられる人もいるわけです。
人は行き詰まることもあります。
その状況を再解釈できるかどうかです。
自信を持って自分をアピールできるスキルや技術を身に付けること、そして、自分の置かれた状況を再解釈すること、この2つが重要になります。
要するに、物事に挑戦したり、逆境に直面したときには、それを乗り越えることができるだけのスキルを持っていると思えるか、あるいは、その状況を再解釈して前に進むことができるかです。
このどちらかで自己効力感は高まります。
どちらかといえば、何かしらのスキルを高める方が考え方も変わります。
それを続けていると目の前の問題も再解釈できるようになります。
目の前の問題や状況を自分なりの言葉で解釈できるかどうかで、自己効力感は変わってきます。
問題が起きて突破できなかったり、解決策を見出せなかったりしたときに、自分を無駄に責めてしまったり卑下してしまう人もいます。
自分が悪いのではなく、その状況や問題に今の自分の考え方が合っていないだけです。
違う考え方を見つけられればそれでいいだけです。
ところが、ほとんどの人が自分の過去の成功体験や失敗体験にとらわれて、同じ目線で見てしまいます。
そのために必要なのが専門的なスキルとクリティカルシンキングです。
想像力や発想力を鍛えることが大事です。
自分が今まで絶対に付き合わなかった人にも会って話をしてみたり、今までやりたいけれどやってこなかったスキルや技術を身に付けてみてください。
順番としてはまずはスキルを身に付けてから発想力を身に付けてください。
どんなに良いアイデアが生まれたり素晴らしい発想力を身に付けたとしても、スキルがなければそれを形にすることができません。
アイデアだけでは無価値です。
行動してそれを形にした人だけが利益を得ることができます。
思いつくだけでは何の意味もありません。
どんなものでも構いません。
まずは何かしらのスキルを手に入れてみてください。
仮にそれによって成果が出なかったとしても、そのスキルによって自分という人間を評価できて、やればできる感覚が生まれて次のスキルがついてきます。
それと同時に、突飛なアイデアを表現しても周りは受け入れてくれると感じられるようになると、自分は人と違っても問題ないという感覚が生まれ、これも自分の自信につながります。
つまり、スキルは次のスキルにつながり、アイデアは次のアイデアにつながります。
これが成功につながります。
他人と違うことをやって認められたら、その成功が次の成功につながります。
目の前の問題を乗り越えたり、今皆さんがしていることをどうすれば効率化できるかを考えることも重要ですが、本来は次のどんなことにつながるのかを考えることが重要です。
スキルは次のスキルに、アイデアは次のアイデアにつなげていきましょう。
スキルを身に付けて次のスキルをまた身に付けようと思うと、どうしても時間が必要です。
アイデアも同じで、アイデアが出るのは一瞬だったとしても、それを出せるようになるまでは時間がかかります。
ですから、スキルもアイデアも同時に育てるものだと考えてください。
自分のスキルがまだ熟さないうちは、アイデアが支えてくれます。
アイデアが出ない時はスキルが支えてくれます。
人が稼ぎ続けるためにはスキルとアイデアを交互に使う必要があります。
スキルを身に付けて稼げるようになったら、その間にアイデアに自分のリソースを投資することができるようになります。
そのアイデアが形になり走り始めたら、そのアイデアが稼げなくなったら、どんなスキルが自分を助けてくれるだろうかと考え学びます。
これは個人のビジネスだけでなく企業でも一緒です。
1つの成功が形になったときに、次を考えてアイデアを練ることができるかどうかです。
勇気とは、自分が恐れて不安に感じるところを支えてくれる何かを作ることです。
スキルを身につければ他人に何を言われても自分に自信を持つことができます。
そのスキルが必要とされなくなる前に、次のアイデアを考えます。
そのアイデアが形になり評価されたら次のスキルを考えます。
どうすればそれを継続できるのかを考えることが勇気につながります。
勇気とは無謀なものではありません。
計画的かつ戦略的な生き方が勇気につながります。
それこそが決して奪われることがない僕たちの大切な資産になります。
ポイント5:手段効力
手段効力とは、自分が目の前のタスクをこなすために必要なツールや知識など必要なリソースを持っている感覚のことです。
目の前のことに勇気を出して取り組むためには、やればできるという感覚だけでなく、自分がそれをやるためのスキルやツールを持っているという感覚も重要になります。
この手段を自分が持っている感覚を得るために、多くの人が資格をとったり何かしらのお墨付きをもらおうとします。 手段効力を高めるためには、もちろん新しいスキルを身につけてもいいですが、それよりも自分が使い込んだツールに注目した方がいいです。
そのツールを使いこなすことによって、自分の知識や経験やツールが効果があると自信を持つことができるようになります。
目の前に難しい課題や問題があったとします。
それを大きくざっくりと捉えてしまうと、難しさや恐ろしさばかりを感じてしまいます。
ですが、実際には注意深く観察すると、確かに難しいところがあったとしても、自分でなんとかなる気がする部分もあったりします。
多くの人は怖いものや勇気が必要なものに目を向けません。
見て見ぬふりをしようとしてしまいますが、より細かく見ていけば手段効力を発揮することができます。
例えば、部分的には自分で解決できる部分があるのであれば、今の自分では対応できないところを助けてくれる人を探すこともできます。
すべてを自分でこなす必要はありません。
すべてを自分でこなすことができる人なんてそういません。
一部だけでも自分でできれば構いません。
その一部を見つけることができるかどうかが重要です。
世の中にはこの自分でできる一部分を理解している人と理解していない人がいます。
多くの人は自分が何ができるか理解していません。
しかも、多くの人は自分が全部できる人だと見せたいので、自分ができないことをわかっていない人も多いです。
手段効力の考え方を持っていると、誰を仲間にすればいいかもわかります。
自分が何をやればいいかもわかるので、無理にリスクを取りすぎたり責任を抱える必要がなくなります。
だからこそ勇気を持てるわけです。
例えば、コンサルタントの仕事がしたいとして、コンサルタントがどんなことを勉強するのかを調べて、スキルを身に付けようとする人もいます。
ですが、手段効力の考え方を持つと、コンサルタントだけがコンサルティングの仕事をできるわけではないと考えることができます。
コンサルタントがしている仕事は、どんなタスクを解決することなのかを調べると、企業を良くすることや組織を動かすことなどが中心です。
これについてDaiGo師匠は、コンサルタントの仕事がしたいと思った当時、これらは自分が持っているツールで解決することができる問題だと考えました。
当時から既に身に付けていた心理学の知識で解決できる問題がほとんどでした。
当時は、その問題が心理学で解決できる問題かどうかが仕事を受ける基準でした。
その答えがYesであれば、手段効力としてタスクをこなすための必要なツールを持っているということです。
自分は人間の心理に関するタスクをこなすために必要な心理学の知識を持っている信念を持つことができて、テレビ業界をやめてコンサルタントの仕事なんてしたことがないのに、自信を持って仕事を受けることができました。
手段効力は皆さんにとっても大切です。
皆さんが今もっている特定のツールや、これから身に付けるスキルが、どんな特定のタスクをこなすために活かすことができるのかを考えると勇気が湧いてきます。
与えられた仕事だけに目を向けていると、自分のできないことばかりに意識が向いてしまいます。
そうではなく必要なツールから考えていただけると、自分にできることは意外と多いということに気づきます。
できることの幅が広がり勇気を持つことができます。
瞑想でも断食でも、HIITでも続けていれば必ず成果が出ます。
1つでもうまくいくツールを見つけることができれば、人はやればできるという感覚が強くなります。
まずは自分のツールを1つ決めます。
ゴッホであれば、黄色の使い方が上手だということがあったので、黄色の絵の具を使うとどこかのタイミングで決めたのだと思います。
そのツールを様々なタスクに対して使っていきます。
どんな問題を解決できるのかが見えてきます。
DaiGo師匠の場合は、心理学の知識を様々な分野に使ってみましたが、ビジネスの世界で使うのが最もうまくいったと感じました。
使えば使うほど心理学の知識に自信を持つことができるようになりました。
皆さんも自分のツールを1つ決めて使い続けてみてください。
ある程度使い続けていると効果を実感できて、最悪のことがあったとしても、そのツールを使って突破することができると考えることができるようになります。
それによって最強の手段効力を得ることができます。
ポイント6 :状態の希望
目の前にやらなければならないことやタスクがある時に、それを自分が実行可能なものだと信じて、それを実行する必要がある時には実行するための方法を見出せるに違いないとと思える信念のことです。
これは成長マインドセットに近い考え方ですが、ただそれをやればできるという感覚ではなく、必要であればそれをやることもできるし、困難にぶつかっても乗り越えることができる方法を見つけられるという感覚です。
例えば、仕事で自分が一度もしたことがないタスクを任せられたとしたら、自分が一度もしたことがないことだからと不安を抱えて手をつけられない状態になるのは状態の希望がないということです。
逆に、それをしたことがないけれど、なんとなく今までしてきた近い仕事を思い浮かべながら、多分やればなんとかなるだろうと考えることができるのは、状態の希望があるということです。
できないことやわからないことがあっても、誰に聞けばいいとか、なんとなく解決の糸口を思い浮かべることができます。
これは生まれつきの要素のように思われがちですが、認知行動療法によって高めることができます。
目の前のできるかどうかはわからないけれど、物理的に絶対に不可能ではない問題に向き合ったときに、状態の希望を持っていない人は、自分にとってできないところばかりに目が向いてしまいます。
その助けになる方法や経験、困った時に助けてくれる人などを思い浮かべることができるかどうかです。
つまり、状態の希望は、統制の所在と同じように、自分の認知を変えて帰属を変えることができれば、誰でも手にすることができるものです。
勇気がある人は、自分の勇気が報われるようになる状況や状態を見つけることができる人です。
勇気が出せない人の中には、勇気を出そうと思えば出すことはできるけれど、それは今ではないと考えてしまう人もいます。
勇気は使えば使うほど発揮しやすくなるものです。
先延ばしせず勇気を出せるようになるためには、先延ばし対策も効果があると思います。
勇気を出したりリスクを取って成功した人はたくさんいますが、努力は成功するためのものではありません。
仕事でもスポーツでもどんなものでも同じですが、努力している間は楽しさを感じることができます。
皆さんも感じたことはあると思いますが、スポーツでもどんなことでも、何度も何度も失敗してうまくいかないことが、うまくいった時の気持ちの良さや感動はとても大きいものです。
できなかったことができるようになる感覚は、僕たちの人生に大きな喜びをもたらしてくれます。
それは成長と呼ばれますが、人間の本能に刻まれた感覚です。
成長や進歩が人間のモチベーションを作り出してくれます。
それが小さな成長であっても、努力する人生の方が絶対に楽しいのは間違いありません。
それが経済的に報われたり誰からも見てわかる成功でなければ、そもそも努力する意味はないという考え方は間違っています。
自分の成長や進歩に目を向けることができなければ、勇気を出すことができなくなり変化も受け入れることができず、日本のように30年間も停滞し続けることになってしまいます。
皆さんにも日本にも素晴らしいものがたくさんあります。 努力は報われなかったとしても、人生を楽しくしてくれるものです。
人生を楽しくして勇気を出して向き合いたいという方は、ぜひ続きもチェックしてみてください。
-
【総集編】読書が楽しくなる心理学
2023-06-10 12:00前回の記事では、DaiGo師匠がこれまで紹介してきたおすすめ本やおすすめのアイテムをイッキ見で紹介させてもらいました。
まだまだごく一部ではありますが、読んでみたい本もたくさんあったと思います。
【総集編】DaiGoおすすめ!人生を変える神アイテム総まとめ
そこで、今回はどうせ本を読むのであれば、楽しく読んで実践につながる知識として身につけてほしいので、読書術について纏めさせてもらいます。
ぜひ気になる部分だけでも参考にしてみてください。
理解力を高めるための6つの読書術
理解力を高めるための読書術は、どんなものがあるのかという研究は色々と行われています。
2013年にハジェテペ大学が、過去に行われた様々な読書術研究の中から信頼性が高い研究を15個選び出して、本の理解力を高める方法を徹底的に調べたレビュー研究があります。
そこから、本の理解力を高める読み方がわかっています。
大きく分 -
一問一答「あなたが毎日続けたいけど、続けられないことはどんなことですか?」【習慣化の原則】
2023-06-06 12:00330ptあなたが毎日続けたいけど、続けられないことはどんなことですか?
今回は、物事を続けることができず諦めてばかりという方の相談をもとに、習慣化のための原則について解説させてもらいます。
「Q. 何事も続けるのが大事だとわかっていても、いつも飽きっぽくて続けることができません。自分にはどうせ…という言葉が頭に浮かんで諦めてばかりです。アドバイスをお願いします。」
多くの人は自分の才能に気づく前にそれをやめてしまいます。
例えば、皆さんも子供の頃に自転車に乗れるようになるまでには何度も転んだはずです。
もし 、皆さんにお子さんがいたとして、その子供が自転車を練習しようとして、2度や3度転んだだけで自分には自転車の才能がないと言って諦めたらどう思うでしょうか?
大人になると、この子供と同じことをしてしまいます。
ですから、自分に向いている向いていない、才能があるないを判断するのは、少なくとも習慣化ができてからにしてください。
習慣化できて、ほとんど考えることもなくそれができるようになってから、それが上手にできるかどうかを客観的に見ることができるようになります。
習慣化して流れ作業のようにできるようになってから、その仕事を続けるべきかどうか考えてください。
そう考えていただけると、とりあえずどこまで続けるべきなのかということもある程度はっきりしますし、同じことをするとしても様々な方法や選択肢が見えてきます。
ちなみに、習慣化は自分の好きなことよりも嫌なことに発揮した方がいいです。 ですが、当然自分の嫌なことよりも好きなことを習慣化する方が楽です。
人生の序盤や若い頃に、嫌なことでも必死に続けて習慣化したけれど、結局転職して無駄だったと感じることがあるかもしれません。
ですが、人生の序盤で嫌なことを習慣化する技術を身につけておくと、人生の後半では好きなことを習慣化することがいくらでもできるようになります。
ですから、習慣化の技術を身につけるためだと考えて、特に人生の序盤や若い頃にはいろいろなことに手を出してみてください。
結果的に自分に向いていなかったことであれば、習慣化の技術を身につけるために役に立ちますし 、自分に向いていることだったとしたら 、それがそのまま天職になります。
あっという間に過ぎてしまった!の正体とは?
カンザス大学の研究で、時間があっという間に終わってしまう原因は何なのか調べたものがあります。
今年に起きた出来事と似た過去の出来事を思い出した場合と、今年起きた出来事とは異なる過去の出来事を思い出した場合を比較し、どちらが時間感覚が伸びるのかということを調べています。
その結果、似た過去を思い出した場合の方が、時間が過ぎるのを早く感じました。
つまり、今自分がやっていることや最近やったことと近い出来事を思い出したら、あっという間に時間が過ぎたと感じるけれど、異なることを思い出すとその感覚を感じづらかったということです。
これらは、人間がチャンキング(chunking:小さなかたまり・断片)という性質を持っているからです。 チャンキングというのは、たくさんある情報をひとつに纏めることです。
過去数日の記憶と過去数年の記憶を比べると、同じ過去でも数年の方が大きいですから、過去の自分の出来事があっという間に纏められたように感じてしまいます。 それにより、あっという間に過ぎてしまったと感じてしまうわけです。
今年起きたことと似た出来事が去年も一昨年も起きているとなると、それらが同じくくりで纏められてしまいます。
僕たちが毎年毎年、歳をとればとるほど1年が過ぎるのを早く感じるのがなぜかというと、新しいことをしていないからです。
新しいことをせずに自分が今までしたことがあることと同じような慣れたことをし続けて、さらに、自分がやっているひとつひとつのことを細かくマインドフルに見ることをせず、かたまりで考えてしまうがために、チャンクがまとまっていて、いつもと同じことしかしていないし、自分は進歩していないと考えてモチベーションも上がらず実際に挑戦もできないとなってしまいます。
前々回で、今年も残り半分かと、目標に対して焦りを感じている人が改めて目標を再設定する方法について解説させてもらいました。
一問一答「あなたの、今年の目標の進捗はどんな感じですか?」【目標の再設定】
そして、前回は、その目標に向けて毎日やるべきことに向き合うための行動力の高め方を解説させてもらいました。
一問一答「あなたが、毎日やるべきと思っていることは何ですか?」【超行動力】
とは言え、モチベーションだけでは毎日やるべきことを続けるのも難しくなります。
そこで今回は習慣づくりの大切なポイントについて解説させてもらいます。
習慣作りに欠かせない6つのポイント
今回は、非常に優秀な実業家や科学者を数多く輩出しているカリフォルニア大学バークレー校が示してくれている習慣化の6つのポイントについて解説させてもらいます。 人生において、自分の健康を大切にして、人生の目的を達成できるような習慣をどうすれば身につけることができるのか調べたレビュー論文があります。
習慣化ポイント1. 習慣は目標に依存しないが、最初は強い目標が欠かせない
ダイエットをしようとか腹筋を割ろうとか、年収1,000万円を超えるとか、習慣は強い目標で最初は始まります。
ですが、この目標が必要なのは最初だけです。
逆に言うと、目標をベースにした習慣というものは、それを達成すると続けることができなくなります。 リバウンドがおきるのもこれが原因です。
これは目標に依存しすぎているからです。
目標に依存している習慣は簡単に挫折して元に戻ります。
そして、もう一度そこに戻るのは大変です。
最初は憧れの自分を目指していたから頑張ることができたわけですが、次は一度失ったものになってしまいます。 2回目にもう一度目指した目標は挫折しやすくなります。
ですから 、目標に依存しすぎないということが重要なわけですが、多くの人が気にしていません。 みんな目標に依存して、まるで目標設定が全てかのように考えています。
習慣化ポイント2. 習慣は自分の文脈を知るところから始まる
習慣を身につけるためには一貫性を保つことが欠かせません。
毎回同じタイミング、かつ、同じシチュエーションで習慣的な行動ができるかによって決まります。
ですから、続かない人のほとんどは「気まぐれ」のせいです。
その時間帯に、それをするときもあればしないときもあるとなると、まるで自由かのように感じるかもしれませんが、実際には一番不自由な状態です。
なぜかと言うと、毎回迷ったり考えなくてはならないからです。 それによって脳に余計な負荷をかけてしまいます。
それが結局続かなくなる理由です。
自分自身の文脈を知って、どんなタイミングでどんな習慣を身につければいいのか知る必要があります。
DaiGo師匠は、朝起きてからすることの順番を必ず守っています。 これも余計なことを考えなくていいからです。
習慣化するためには、その習慣的な行動をしている時に、「いかに余計なことを考えないか」がとても重要です。 それによって習慣の継続性は決まります。
習慣化ポイント3. 習慣化には事前のトラブル対策が必須
習慣を身につけるためには必ずトラブル対策が必要です。
習慣を邪魔したりネガティブな影響を与えることに対しては、あらかじめ対策をしておく必要があります。
これがとても重要なポイントで、多くの挫折する人は、大抵気合と根性で何とかなると考えています。 自分はそれを続けると決心したから、必ずやり遂げることができると下手に自分を信じています。
習慣化する際に、気合いでなんとかなると考えたり自分を下手に信じる人はまず続きません。
なぜかと言うと、その時の気合や自分を信じる感情というものは長く続かないからです。
習慣を身につけることが得意な人は、最初から自分を信じていません。
信じていないから習慣にします。
逆に言うと、自分は意志力がないとか自制心がないと思っている人ほど、習慣化のテクニックを学ぶとその効果は大きくなります。
なぜかと言うと、習慣化のテクニックは意思が弱い人のためにあるものだからです。
意志が強い人は、どんなタイミングで何をするにしても全力で取り組むことができます。
それが意思が強いということですが、ほとんどの人は意志が弱いです。
いつどんな時でもやるべき行動が取れるとは限りません。
1日の中でランダムで突然アラームが鳴って、今から筋トレの時間だと言われて続けることができる人はほとんどいません。
毎日続けることができている人も、それをする時間や状況が決まっているからできるだけです。
人はそもそも怠け者な生き物ですから、よほど自分に自信がある人以外は、事前にトラブルが起きたり習慣ができなくなる状況を想定しておく必要があります。 トラブルが起きることを想定して計画を立てていた方が習慣は続きます。
習慣化が上手な人や結果を出し続けている人は、このトラブル対策が上手な人です。
トラブルがなければ多くの人が続けることができます。 ですが、何かしらのトラブルが必ずあるので習慣が途切れてしまうわけです。
ちなみに、「自分は意志力が弱い人間だ」と自分の意志力をディスっている人ほど習慣を身につけることが上手だという研究があります。 自分の意思の力に頼らないから、続けるための工夫をします。
ところが、意思の力に頼ったり自分を信じすぎる人は、気合と根性で何とかなると思っていますが、結局何とかなりません。
DaiGo師匠も意思の力が弱いから、心理学を勉強しています。 もともとメンタルが強いわけでもありませんし、人間の心もよくわからなかったので、心理学を勉強して人の心を理解しようとしたわけです。
習慣化ポイント4. 習慣は自動的である
習慣的な行動を続けるのが面倒だと感じる人もいるでしょうが、その面倒だと感じる感情がある時点で習慣化に失敗しています。
習慣的な行動を始めることは、意識を必要とせず、習慣的な行動が始まったとすら思っていないことが多いです。
例えば、皆さんが朝起きて歯磨きをするまでに、自分がしている行動というものは毎日ほとんど同じです。 全ての行動が気にせず毎日同じようにできています。
つまり、習慣的な行動のスタートに気づいている時点で、まだ習慣が身についていないということです。
皆さんは、昨日の夜にご飯を食べたり歯磨きをしたりしたと思いますが、何がきっかけでその行動をしたかまでは覚えていないと思います。 なんとなく自動的にその行動を始めているからです。
これが完全な習慣化できた状態です。
行動を始めたことにさえも気づかないレベルが習慣です。
例えば、お風呂に入ってぼんやりとしている時に、「髪洗ったっけ…」と考えたことはありませんか? 髪を触って洗ったことに気づきます。 これがまさに習慣的な行動です。
その行動の開始を意識していないので、抵抗なく始めることができます。 ですが、ほとんどの人は習慣的な行動をこれから始めようと意識して気合で取り組もうとします。 習慣的な行動は開始を意識した時点でまだ習慣として身についていません。
習慣化ポイント5. 習慣は報酬によって促進される
これは当たり前ですが、ご褒美のタイミングや量にコツがあります。
それを押さえておくと習慣が身につきやすくなります。
習慣化ポイント6. 習慣を変えるには時間がかかる
習慣を変えるにはかなりの時間がかかりますので、その間耐えるための工夫をする必要があります。
習慣というものは、先ほど紹介したとおり行動の開始を意識しないレベルで自動的にできるようにするものですから、一度身についてしまえば何も考えなくても行動できるようになります。
ただ、何も考えなくて行動できるようになるまでの日数やレベル、達成率を意識している人はほとんどいません。 これを意識していないと、ゴールがないマラソンのように思えてしまいます。
死ぬまで自分が続けなくてはならないことを絶対に続けると考える人はほとんどいません。
おそらく皆さんは死ぬまで歯を磨き続けると思いますが、それは習慣になっているので意識せずできているからです。
死ぬまで物事を続けようとすることは難しいですが、習慣化すればそれを実現することができます。
ゆえに習慣というものは運命を操ると言われています。 習慣というものは僕たちにそれほどの大きな力を与えてくれます。
人によっては8割だそうですが、皆さんの人生の6割は習慣的な行動によって決まります。
良い習慣を身につけることは、皆さんの人生の6割から8割を思い通りにコントロールすることです。
ここから先は、これら6つのポイントをより具体的に掘り下げて解説していきます。
ぜひ続きもチェックしてみてください。
-
一問一答「あなたが、毎日やるべきと思っていることは何ですか?」【超行動力】
2023-06-03 12:00330ptあなたが、毎日やるべきと思っていることは何ですか?
今回は、将来の不安を感じながらも挑戦することができないという方の相談をもとに、行動力を上げて毎日を充実させるための心理学を解説させてもらいます。
「Q. 将来が不安で少しでも早くいろいろと始めておくべきだとわかっていても行動できません。なおさら不安になって落ち込んでしまいます。アドバイスをお願いします。」
誰でも人は悩むわけですが、いくら悩んでも前に進むことはありません。
後から振り返って、「あの時悩んでよかった 」「あの時立ち止まってよかった」という人はいないと思いませんか?
これは歴史に名を残した偉人たちでも同じです。
行動できないときはこの言葉を思い出してください。
行動こそが、悩みに効く唯一の薬である。
同じような名言がたくさんあります。
偉人たちが残した名言や教えの中には、「悩み」「迷い」「苦しみ」に関するものがいろいろとあります。
偉人たちも成功者もそうでない人もみんな悩むのに、後から悩んだことをよかったと思う人は誰一人いないはずです。
要するに、人間は失敗を恐れたり不安でいろいろと悩むわけですが、その先のルートは2つです。
悩んで悩みまくって結局行動しない人と、散々悩んだ結果、「これ以上考えても仕方がない」と、悩み尽くしたと、考え尽くしたと思ってとりあえず行動する人です。
大抵の場合、過去を後悔しない人は行動した人です。
もちろん、立ち止まる時間も考える時間も大切ですが、結局、人は悩みを解決したいのであれば、とにかく行動するしかありません。
例えば、有名な名言では、トーマスエジソンも同じようなことを言われています。
悩みの解決には、仕事が一番の薬だ。
同じような名言を残してくれている偉人はたくさんいます。 とにかく行動しない限りは何も変わらないと考えるようにしてください。
以上がDaiGo師匠からのアドバイスでした。
未来は与えられる物ではなく、獲得する物
将来起業して自分の力で仕事を作って成功したいとか、今ある仕事で成功したいと思うのであれば、自ら行動してそれを形にするしかありません。 創造力もあってアイデアは思いつくけれど形にすることができない人は結構多いですが、それは自分の未来と結びついていないからです。
自分の創造性を現実的な方向に向けることができていないので、だから形にならないということです。
自分がアイデアについて思いつきたいのであれば、自分の思考を遠い未来に飛ばしてください。
一方で、アイデアを形にするために行動したいと思うのであれば、半年や1年以内の自分の計画に対して思いを巡らせてください。
これにより創造性と行動力につながるモチベーションを手に入れやすくなります。
皆さんは自分の未来を自分で選んで手に入れてください。 重要なのは、できるだけ早く決断して、その決断が正しかったと思えるような行動を繰り返すことです。
先延ばしにして決断が遅くなればなるほど、もしその決断が間違っていた時にはそれを巻き返すチャンスも減りますし、修正することもできなくなってしまいます。
先延ばしをなくす後悔先回り法とは?!
意志が弱い人ほど使える自分をコントロールするための画期的なテクニックを紹介させてもらいます。
後悔先回り法と呼ばれるテクニックですが、これは上手に使っていただけると、普段から後悔することが多いとか、自分の意志の力が弱いと思っている人ほど、自分をしっかりコントロールすることができて、素敵な未来を掴むことができるようになると思います。
参考にしている研究では、ジムに通って定期的に運動している人を対象にしています。
多くの人が目標を掲げて取り組む中でも、最も目標達成が難しいことのひとつが定期的な運動を続けたりダイエットすることです。
参加者たちにジムに通って運動を行ってもらうわけですが、当然その中には途中で挫折してしまう人もいます。
その挫折しそうになった時に、研究者はあることを試してもらっています。
「ジムに行かなかった場合、後でどれくらい後悔するだろうか?」と考えてもらいました。 これによってジムに通い続けることができる確率が高くなったということです。
自分の意識と感情を未来に飛ばす!
これが後悔先回り法と呼ばれるテクニックで、自分がやろうと思っているけれど、ついついダラダラとしてしまい諦めそうになっている状況で、自分の感情をもっと先の未来に飛ばします。
僕たちは「やることがめんどくさい」と思っているときには、やるべき行動の前段階に意識が向いています。
そうではなく、「行動しなかったらどれぐらい未来で後悔するだろうか?」と考えると、自分の意識や感情の時間軸を変えることができて、それによって圧倒的にやるべき行動を取れるようになります。
これは仕事でも勉強でも同じです。 やるべきことがわかっているけれど面倒だと感じることは誰でもあります。
それをしなかった時の後悔やマイナスについて考えると、人は行動できるようになります。
目の前にあることを考えるよりも、その目の前のことをやらなかった時の後悔を考えてください。 これだけで行動力は圧倒的に上がります。
行動力を上げる手帳の使い方
人は自分が過去にやってきたことややり遂げたことを見ると満足度が高まります。
一方で、未来の計画を見るとモチベーションが高まります。
つまり、意識をどこに向けるかだけで人は変わります。
スケジュール帳には過去に自分が頑張ってきたことややり遂げてきた仕事など過去の記録も残っていますし、将来的に挑戦したいことや予定しているプロジェクトやプレゼンが書いてあると思います。
自分の心理状態に合わせて、過去を見るのか?未来を見るのか?を変えてください。
例えば、自分の気持ちが落ち込んでいるときや仕事のやりがいを感じないとき、自分の人生に満足感が足りないときや落ち込んでいるときには過去を見るようにしてください。
過去の予定を見て、自分がこれまで頑張ってきたことや、小さな成功も含めて積み重ねてきたことに目を向けてください。
それによって今の自分や生活に対する満足度が高まります。
そうすれば前向きに物事を考えることもできるようになります。
逆に、モチベーションが上がってきて、新しいことをやりたいとか行動力を高めたいと思うときには、過去ではなく未来に目を向けるようにしてください。
将来やりたいことや新たに挑戦したいことについて計画を練ってみたり、今後控えているプロジェクトや未来の計画を見ることによって人はモチベーションが上がり、今この瞬間の行動力を最大化することができます。
落ち込んでいるときは過去、行動力を上げたい時は未来。
些細なことですが、毎日の気分や行動力を最大化できます。
決断麻痺「それをやらなかったときにどれくらい後悔するか?」
人は迷った時には「それをやらなかった時にどれくらい後悔するか」ということを考えると行動できるようになります。
ところが、多くの人は心理的に真逆のことをしてしまいます。 ほとんどの人は「やって失敗したらどれくらい後悔するか」と考えてしまいます。
そうすれば当然ですが行動するのが怖くなります。
自分が行動しなかったことによって、どれくらい後悔するのかということに目を向けてください。
それだけで大抵のことには行動する勇気が湧いてきます。
現代人には完璧主義が増えています。 多くの人が完璧にこだわったり失敗を極度に恐れています。
なぜ現代人にこのような人が増えたのかということについては、科学的にも諸説ありますが、例えば、SNS の普及によって他人との比較が容易にできるようになったということがあると思います。
この完璧主義がひどくなると決断麻痺という状態になります。 結局のところ、やるということを決めているわけでも、やらないということを決めているわけでもない状態です。 無意味に保留している状態が増えてしまいます。
例えば、転職するかしないかで迷ったときに「今は転職しない」を選んでいる人は多いと思います。
それが「今転職をするか」「一生転職しない」の2択の場合には、ほとんどの人は「今転職する」を選ぶことができます。
これは選ぶのが怖いだけです。
完璧主義に陥ると人は物事を選べなくなります。
そんな決断麻痺の状態のなくし方については、セルフコンパッションが効果的です。
オーストラリアンカソリック大学の研究で、完璧主義の対策としてセルフコンパッションがどのように効果があるのかということを調べたものがあります。
541人の若者を対象に実験を行なっており、全員に完璧主義の度合いを測る心理テストを行い、その程度をチェックしました。
その後に、全員の自尊心やメンタルの強さ、セルフコンパッションのレベルなどを調べました。
その結果、セルフコンパッションのレベルが高い人は、完璧主義の悪影響がかなり和らげられているということがわかりました。
つまり、自分に自信を持とうとか、自尊心を育もうとするよりも、自分に思いやりを持ち失敗した自分を許すことの方がはるかに効果が高いということです。
この研究では、さらに515人の成人の方を対象にした実験を行っていて、やはり、セルフコンパッションのレベルが高い人ほど、うつ病になりづらく、完璧主義の人にありがちなメンタルの低下が少なかったということです。
コンパッション日記
完璧主義の傾向があり行動できない人にぜひ実践してもらいたい簡単なワークを紹介しておきます。
エクスプレッシブ・ライティングに近いテクニックで、1日の終わりに、自分を許すためのテクニックをどれぐらい実際に使ったかということを記録します。
そして、つらい体験や自分を責めてしまうような思考に苛まれたときには、寝る前など後からでも結構ですので、そんな自分に対してどんな優しい言葉をかければ良かったのかということを考えて日記のように書き出してください。
これにより、自分を許しても結果的にうまくいっているし、自分を慰めたことで人生がうまくいっているということが見えてくるようになります。
記録が溜まっていくことで、自分が自分を許せる人間だということを理解できるようになります。
1日の終わりにその日の悩みをGoogle カレンダーに記録してみるのもいいと思います。
記録していくことで、過去の自分が悩んでいることも結果としては些細なことであったりすることが理解できて、今の自分を許すことができるようになります。
自分を許すことができて、自分を責めることから感じるストレスが軽減され、その結果として、行動できるようになり、自分が望む方向にどんどん進んでいくことができるようになります。
記録するときは反省点を書くのも結構ですが、それに対する優しい言葉も同時に残してください。
自分を許すことができた記録が溜まっていけば溜まっていくほど、自分を許すことができる確率は上がっていきます。
これによりセルフコンパッション能力を高めていただけたらと思います。
おすすめとしては、防水のスマホなどを使ってお風呂の中で実践してみてください。
お風呂の中で体が温まり血行が良くなり副交感神経が優位になっているときには、自分を責めづらくなります。
ぜひ実践してみてください。
人間の後悔の9割以上は「やらなかったこと」に対する後悔
とはいえ、誰でも間違った決断をしたくないはずです。
人間は「やらなかったこと」に対して多大な後悔を持つということが様々な研究でもわかっています。 人間の後悔の9割以上は「やらなかったこと」に対する後悔だと言われています。
それがわかっているのになぜ多くの人が行動できないのでしょうか。
これは自分の決断が正しいかどうかがわからない不安があるからです。
これについては、はっきり言いますが正しい決断なんてどこにもありません。 後悔しづらい決断はありますが正しい決断というものはありません。
自分の決断や決定に正しさを求めたら、ほとんどの人が選べなくなります。
人間は自分が選んだ道を「あれは正しかった」「自分は間違っていなかった」と考えられる「後悔しない選択」に自分の決断を変えていくことができます。
選ぶ前にそれが正しいかどうかなんて誰にもわかりません。
考えすぎを防ぐマキシマイゼーションテスト
どうすれば後悔しづらい選択をできるようになるのかということについては、マキシマイザーテストを行ってみましょう。
とても当てはまる:7点
当てはまる:6点
まあまあ当てはまる:5点
どちらとも言えない:4点
やや当てはまらない:3点
あまり当てはまらない:2点
全く当てはまらない:1点
全部で6問の質問がありますので、それぞれ直感で採点して点数を合計してください。
質問1 :音楽を聴くときには、今流れている曲がそこそこ気に入っているにも関わらず、もっといい曲がないかとついほかのプレイリストを探してしまう。
質問2 :今の仕事に満足していようがいまいが、常に良い職場を探そうとするのは当然のことだと思う。
質問3 :友達や恋人にあげるプレゼントに悩むことが多い。
質問4 :映画を見ようとすると最高の1本を選ぶためにいつも苦労する。
質問5 :何をする時にでも自分に対して最高の基準を定めている。
質問6 :2番目に良いもので妥協したことは一度もない。
以上です。
それぞれの点数を合計したら6で割って平均点を出してください。
5.5以上:全人口の上位10%に入るマキシマイザーです。
この場合には、ベストな選択肢を考えすぎて悩みすぎているのではないかということを意識してみてください。
それによりストレスを抱えている可能性もあるので、ストレスケアもちゃんとした方がいいと思います。
4.75〜5.4:全人口の上位30%に入るマキシマイザー
このレベルでもかなりストレスフルな状況かと思いますので、もう少し肩の力を抜いてベターな選択肢で妥協することも考えてみると良いのではないでしょうか。
あるいは、自分が本当に大切で譲れないことにだけマキシマイザーであり、それ以外に関しては妥協してもいいと考えるようにするのがいいと思います。
3.25〜4.7:どちらとも言えないほどほどなマキシマイザー
2.6〜3.24:全人口の下位30%ほどに入る人で、サティスファイザーに近い
この辺りからはサティスファイザーの傾向が強くなりますので、そのままでいいのではないかと思います。
2.5以下:全人口の10%程に入る人で、マキシマイザー要素はほぼないサティスファイザー
こちらに含まれる方は、意思決定においてはストレスがあまりない人生を送れるのではないかと思います。
いずれにしても、自分がどんなタイプなのかを自覚することが大切です。
自分がマキシマイザーだということがわかったら、自分がストレスを抱えすぎてしまうからダメだと考えるのではなく、自分はマキシマイザーだから、考えすぎてしまうこともあれば選択肢にこだわりすぎてしまうこともあるということを意識して、判断に迷ったりした時にはそれを思い出してください。
それに気付いたらベターな選択肢を選ぶように心がけてください。
それにより、バランスよく考えすぎることもなく人生を送れるのではないかと思います。
そして、後悔しない選択をするためには、 自分がマキシマイザーになりこだわるところを限定的に絞るようにしてください。
今目の前にある意思決定や選択というものは、自分がマキシマイザーになるべきところなのかということを考えてください 。
おすすめとしては 、自分がマキシマイザーになるべきところは 、促進系マキシマイザーで徹底的に調べて後悔しない選択を心がけてください。
その上で、それを決めたらもう迷わないようにしてください。
そして、それ以外に関してはこだわりを捨ててもいいと思います。
ここから先は、学校や会社からの帰宅後のやる気も高めて、人生を変えるための目標に対する行動力を上げていく方法を解説させてもらいます。
ぜひ続きもチェックしてみてください。
-
一問一答「あなたの、今年の目標の進捗はどんな感じですか?」【目標の再設定】
2023-06-01 21:00330ptあなたの、今年の目標の進捗はどんな感じですか?
今回は、今年はもう6月になり、このタイミングで今するべきことについての質問をもとに、目標の修正と再設定を行い成長していくための方法について解説させてもらいます。
「Q. 半年ほど経った今するべきことはありますか?」
目標の修正をしましょう!
1年の始まりにどんな目標を立てたのか?それを振り返ってもらい、もしそれができていないのであれば、なぜできていないのか?どんな挫折をしたのか?を考えてください。
その失敗や挫折の対策も行った上で、次の3ヶ月を過ごしてください。そのタイミングでもう一度見直して修正と対策を行い、残りの期間を過ごすのが1番良い過ごし方だと思います。
以上がDaiGo師匠からのアドバイスでした。
目標の決め方・基準は?
目標やノルマを設定する時に、自分の100%の力や120%の力で設定することはおすすめしません。
変化が激しく何が正しいのかわからない時代においては、余力を残しておくことが一番の目標になります。
ですから、皆さんが仕事で成功しようと思うのであれば、自分の全力の8割から7割ぐらいで成功するにはどうすればいいのかと考えてください。
2割から3割ぐらいの余力は必ず残すようにしてください。
それができないと、新しいことを考えたり状況に応じて修正したりする時間を作る事もできません。
人は100%の力で頑張っていると、「自分は頑張っているから報われるべきだ」「自分は評価されて当然なんだ」というわけのわからない幻想を抱いてしまいます。
僕たちがやるべきことは成果を出すことであり頑張ることではありません。
ですから、常に7割から8割ぐらい、できれば6割ぐらいでメインの仕事の部分が終わるようにしてください。 残りの部分を使って新しいことをやるということを常に考えておいてください。
目標を作る時には、自分の力の7割から8割ぐらいでどこまでできるかということを考えてみてください。 普通に目標を立ててもらい3割ぐらいがちょうどいいです。
実際にDaiGo師匠もテレビに出ていた頃から2割から3割ほどの余力を残すことをしていました。 これによって今のDラボにつながる活動を始めることができました。 この2割から3割の余力を残すということが成功するためのコツです。
世の中に出ている成功体験や起業家の方々の本などでは、120%の力を出さないと成功できないと言われている人が多いです。
それで成功できるほど世の中は甘くないと思います。
7割から8割ぐらいの力で、手を抜くのではなく工夫を続けながら仕事をして、残りの2割から3割で新しいことに挑戦し続けるということが成功のための第一条件になると思います。
これは仕事やビジネスだけではありません。
例えば、受験に向けて頑張っているけれど伸び悩んだり上手くいっていない学生さん、年始に立てた目標に対して諦めを感じ始めているすべての方に言えることです。
自分が手が届かないレベルの目標を作ってはいけません。 大学受験などでは手の届かない目標を立てる人が結構多いですが、指先さえもかかっていないようなレベルの目標を立てることは現実逃避です。
例えば、年収400万円の人がいきなり年収1億円を目指そうとしてもまず無理です。 まずは500万円を目指して、それを達成したら600万円、段階を経て徐々に上の目標を目指して行くべきです。
目標を作るのは「何から手をつければいいのか」ということを明確にするためです。 自分の目指す理想を決めれば今何をすればいいのかが明確になります。 だから目標が大事になります。
「今何をすればいいのかが分からない」そんなレベルの目標を立てる意味はありません。 今の自分には無理なレベルの大学の合格を目標にしても、今何をすればいいのかがわかりません。
今目標に対してモチベーションが落ちている人もいると思います。
それはモチベーションが落ちているというよりは、目標設定が間違っていると思います。
自分が10%から20%ぐらい背伸びしたら届くところをまずは目標にしてください。 それは着実にクリアしていくのが一番良い目標設定の方法だと思います。
これぐらいの背伸びをしたところにある目標が一番モチベーションを上げてくれます。 頑張ってそこにたどり着いたら、もっと欲しいと思えるようになります。 ところが、いきなり1.5倍とか2倍の目標を立ててしまうと、自分の力だけではどうにもなりません。
相当ラッキーなことがない限りはそんな成長はありえません。
20%ぐらいまでの成長であれば自力でできますので、自力で上がっていくことができるレベルの目標を立てて着実に成長していってください。
その過程でラッキーなことがあれば1.5倍や2倍の成長もあり得るかもぐらいに考えておいてください。
達成率を上げる目標の立て方
皆さんが来年の目標を立てる時に気をつけてもらいたい5つのポイントを紹介していきます。
2010年のイリノイ大学の研究で、目標に対する行動を動機づける要素について調べてくれています。
内省的なセルフトークを通じて目標指向の行動を促進することを調べてくれています。
具体的には、研究者は、被験者に対して将来の目標を達成するために疑問形でセルフトークを行うように指示しました。
例えば、自問自答の形で「私はこの仕事を終えることができるだろうか?」などの疑問を立てるという方法です。
研究者は、疑問形のセルフトークが目標指向の行動を促進する効果があるという仮説を立てています。
実験を通じて、被験者の動機づけやタスクパフォーマンスにどのような影響を与えるかを調査しました。
その結果、疑問形のセルフトークが目標指向の行動を促進し、被験者の動機づけとタスクパフォーマンスを向上させることを示しています。
セルフトークによる自問自答は、被験者に自身の能力や意欲について考えさせ、行動につなげる助けとなるとされています。
この研究は、自己内省と自己調整のプロセスに関連する心理学的な要素が、目標達成のための実用的なアプローチになると提案しています。
全ての目標に対して「〜だろうか?」という疑問を付け加えるということがこの研究の一番の肝になります。
自分に向かってポジティブな目標を立てて「〇〇になるんだ!」ということを考えるよりも、
「〇〇になれるだろうか?」
「〇〇な人生を歩めるだろうか?」
「この目標を達成することができるだろうか?」
というように、自分に対して疑問を与えていくことで、自分の思考を疑問形に変えるテクニックが重要だということです。
疑問形で考えることによって、それは具体的な思考に結びつきます。
ほとんどの人が計画や目標というものを立てますが、それがただ単に夢や理想と結びついています。
理想になると、それは行動につながりません。
ですから、そもそも目標の立て方がおかしいということです。
目標というものは疑問形で立てるというのがこの研究からわかることです。
自分がどのようなことをするべきなのかということが見えてくるので、疑問形で考えることがとても重要になります。
この目標というものは常に疑問形で立てるということを前提として、次に紹介する5つのステップを理解していってください。
目標の5つのステップ
ステップ1:目標設定
自分がどのようなゴールを達成したいのか、どのような目標を作りたいのかということをまずは考えてください。
これがもし思い浮かばない場合には、そもそも目標とは何だろうかと考えても結構です。
例えば、特に仕事に対しての目標があるわけではないけれど、もっと自由な時間が欲しいという欲求があるということであれば、それを目標にしようと考えてもいいわけです。
目標を作るときも疑問形で自分に問うようにしてください。
そうすると具体化されやすくなりますので、特に目標がはっきりしないという場合には、自分に対して自問自答していくことが大切です。
その際には、できれば声に出すか紙に書くようにしてください。
自分の頭の中でひたすら考えているのも難しいものですし、声に出すか紙に書くかアウトプットすることによって、目標は明確になりやすくなります。
目標は現実的に立てるべきだとよく言われますが、現実化するのは後でも結構です。
一番最初に自分が目標を立てる時には、できるだけポジティブに考えてみてください。
自分はどんなことでもできると思って目標を立てることが大事です。
少し無理かもしれないけど頑張れば何とかできそうというぐらいの目標を設定しておくのがいいと思います。
まずは自分がどのような目標を達成したいのかということを、自分に対して疑問形で問いかけて考えてみてください。
ステップ2:現実化
目標を決めたら、それに対してひたすら疑問を投げかけるようにしてください。
ステップ1で遠い目標に対してポジティブに考えたら、それに対してどんどん疑問を投げかけていって、それを細かく砕いていきます。
細かく砕いてステップを作っていくことが大切ですが、この際の、近い目標や現実的なプロセスを考える場合には、少しネガティブに考えた方がうまくいくということがわかっています。
ポジティブに考え続けていくと細かいところに目が行かなくなってしまいますが、「できるだろうか?」というようにネガティブに考え込むステップを作って考え抜いた場合には、具体的な手法が生まれるので、自分に疑問を投げかけながら現実化していく方法は上手くいきやすくなります。
この疑問を投げかけるステップは10分ぐらいは行うようにしてください。
目標は5分ぐらいで決めても結構ですが、この疑問を投げかけるステップは最低でも10分ぐらいは行なってもらい、30分くらい続ければかなりステップが見えてきます。
もうこれ以上疑問が出てこないというぐらいまで行うのがコツになります。
ステップ3:挫折と対策
先ほどのステップで疑問を投げかけていくと、越えられないような壁や失敗した心当たりがある挫折のルートが見えてきます。
このような挫折や失敗に対して、少なくともその対策法を3つずつ考えるようにしてください。
今のタイミングで上手くいっていない場合も同じです。
上手くいかない点や挫折しそうなポイントが見えてくるので、それに対しての対策を考えていきます。
この対策をそれぞれ3つぐらい考えるようにしておいてください。
その対策がどうしても思い浮かばない場合には、今までやって上手くいった方法、本や YouTube で他人が提供している情報や他人の過去の経験に頼るのももちろんありです。
ただし、その場合は、自分で試してうまくいくかどうかということをチェックする必要もあります。
このような挫折や失敗に対する対策を考えたときの方が、人間は具体的な行動に結びつきやすくなります。
モチベーションが下がったりやる気が出てこないというときにも、人間はやろうかどうしようか迷っている時にやる気がなくなってしまうものですから、そのための対策としても使うことができます。
ステップ4:進歩の記録
人間のやる気というものは、「自分がどれぐらい前に進んでいるかがわかる」ことがとても大事です。
自分が前に進んでいるとか成長しているという感覚がなくなると、あるいは、それがわからなくなると人間はやる気がなくなってしまいます。
この前に進んでいるという感覚は、ボーナスやご褒美よりもはるかに強力なやる気に繋がります。
ですから、ほとんどの人はやる気の問題ではなくて、自分の目標達成までのフェーズのうち今どこにいるのか、どれくらい自分は進んでいるのかということが原因でモチベーションを保てなくなっているだけです。
これがわかるようになるためには、進歩しているものを数字で計測できるようにするのがいいと思います。
例えば、DaiGo師匠が紙の本をおすすめしている理由のひとつでもありますが、どこまで読んだかがわかりやすくなります。
ステップ5:定期的な修正
問題の修正が行われないことが原因で、一度決めた計画は絶対にやり遂げないといけないと考えてしまう完璧主義の人もかえって失敗しやすくなります。
問題が起きてしまった時には、目標をかたくなに決めすぎていて過去のやり方に固執してしまったり、あるいは、問題が起きたら自分の考えた計画通りにいかないということで投げ出してしまったり、これにより計画倒れが起きるわけです。
計画を立てる時に最悪の状況を想定しておいてください。
最悪こうなる可能性があるということを決めておかないと、少しでも進捗が悪くなると、その分だけモチベーションも下がってしまいます。
最悪な状況をあらかじめ決めておけば、少し進捗が悪くなったとしても、まだ最悪な状況というわけではないと考え立て直す意欲も湧いてきます。
最悪な状況を想定しておいた方が、計画倒れをしそうになった時も持ち直すことがしやすくなります。
まだ最悪な状況までには至っていないので、ここからまた取り返してやるというモチベーションが湧いてきます。
未達成の目標の修正
目標にしがみついたり、これまで達成できなかった目標をもう一度立てるのはやめましょう!
だからといって諦めるわけではなく、修正もしくは再定義します。
うまくいかなかった目標を、これまでと同じ形で目標設定するのはやめましょう。
過去にうまくいかなかったり挫折した目標は、それをそのまま目指すと無意識のうちにストレスを感じてしまいます。
その結果として達成できなくなってしまう可能性が高くなります。
過去に失敗した目標を同じ形でリトライするだけは、失敗しやすくなるので避けた方がいいです。
1.目標の修正
例えば「英語をしゃべれるようになる」と目標を立てたけれどうまくいかなかったとしたら、それは曖昧でわかりにくいことが原因だったかもしれません。
それであれば、「海外のレストランに行ったときにウェイターの方と5回会話のキャッチボールができるようになろう」とすればわかりやすくなります。
漠然としてわかりにくかった目標であれば、それを達成したかどうかがわかりやすい目標に修正します。
2.目標の軽量化
「英語をしゃべれるようになる」では、英語がペラペラになるような状況をイメージする人が多いです。
それは重過ぎる目標です。
目標を達成できていない、進捗が悪いのは、皆さんの意思が弱いのではなく目標が重過ぎただけです。
もっと軽くできる目標に落とし込むことを考えてみてください。
英語の目標であれば、例えば、とても簡単な英会話の本を1冊買ってきて「この英会話の本を3ヶ月で使えるようになる」とすることもできます。
それを達成したら次のステップに進んでいけばいいだけです。
逆に3ヶ月後にそれも難しかったのであれば、その時点でもう一度見直すだけです。
目標を立てて階段を1段飛ばしでがんばっていたつもりでも、夢や理想によって、いつの間にか10段の階段を飛ばすことを考えていたかもしれません。
1歩ずつ足元を確かめながら階段を上っていくために、目標を見直すのが軽量化です。
3.目標の再解釈
目標の再解釈は「そもそもその目標を達成して何をしたかったのか?」と自分に問い直す方法です。
英語をしゃべれるようになりたいとしたら、そもそも英語をしゃべれるようになったとして何がしたかったのかまで考えます。
仮に海外で仕事をしたいから英語をしゃべれるようになりたいと思っているのであれば、そもそも英語をしゃべれるようになってから海外に行くのではなく、海外に行ってから英語を学びながら働く方法もあります。
目標の再解釈を行うと別の方法があるのではないかと気づけます。
自分が本当に求めていたのはその目標なのか?それとも、その目標の先にある別のことなのか?と考えます。
この再解釈を考えると意外といい道が見つかります。
皆さんも、目標は定期的に修正したり軽量化したり再解釈することを忘れないでください。
重要なのはモチベーションを維持することです。
失敗したりうまくいかないのであれば解釈を変えなくてはなりません。
目標の数字を変えるのではなく形を変えなくてはなりません。
モチベーションを保ちやすくするために、目標自体の形を変える必要があります。
ここから先は、目標を立てる際にも見直す際にも使える考え方や、達成率を飛躍的に高めて、今からでも今年を目標達成の年にする方法を紹介させてもらいます。
ぜひ続きもチェックしてください。
-
一問一答「あなたが、どうしても捨てられないものはなんですか?」【片付けが捗る心理学】
2023-05-30 12:00330ptあなたが、どうしても捨てられないものはなんですか?
今回は、やるべきことを先延ばししがちな方の相談をもとに、片付けを邪魔してしまう心理的障害について解説させてもらいます。
「Q. 運動や勉強など、なかなかやる気が出ず後回しにしてしまい、いつも追い詰められてから焦ってしまいます。どうすればいいでしょうか?」
先延ばしというものは、習慣化と同じで癖になってしまうものです。
ですから、先延ばしをする人はあらゆることに対して先延ばしをするようになってしまいます。
そのような人は、プライベートでも仕事でも、家の片付けでも勉強でも、人生の備えに対してもお金に対しても、恋愛でも人生の夢でも、あらゆることに対して先延ばしをしてしまいます。
そうならないためには、先延ばししてしまう原因を知る必要があるわけですが、ほとんどの人は自分の意志の力を先延ばしの原因と考えています。
先延ばし対策も技術です。技術ですから誰でもすればできるものです。
先延ばしが起きてしまう原因と、その原因に対する対策を知る必要がまずはあります。
Dラボ▶即断即決即行動!すぐやる人になれる「先延ばしの心理学」
上記の動画を参考にしてもらえれば、あらゆる物事がサクサク進むようになります。そうなれば進めることが楽しくなりますので、当然ですがやるべきことがどんどん捗ります。
以上がDaiGo師匠からのアドバイスでした。
人がものを捨てられない本当の理由とは?
人はなぜものを捨てることができないのでしょうか?
あるいは、捨てようかどうしようかと迷ったときに、一旦置いておこうとするのはなぜでしょうか?
人がなぜ捨てることができないのか、その本当の理由を知っておかないと、ものはどんどん増えていきます。
これは皆さんの自制心によるものではありません。
これは企業が皆さんに対して行っている戦略が心理的に影響を与えている可能性が高いです。
その戦略を理解しておけば、ものをあっという間に捨てることもできるようになります。
捨てられない理由その1:企業のマーケティング戦略
PixiesDidIt社の心理学者ケリー・マクネミン氏が、過去の様々な文献をレビューして人がものを捨てられない理由についてまとめてくれています。
結論としては、企業のマーケティング戦略に僕たちの脳が踊らされているからです。
毎年、断捨離や片付け、ミニマリストなどの本が出版されています。
本当にその本を読んで整理整頓できたりシンプルライフを実現できるのであれば、当然ですが、そんな本が毎年出版されるはずがありません。
英語の本もダイエットの本も同じです。
英語の本もダイエットの本も毎年のベストセラーに必ず含まれています。
みんなできないから毎年売れるわけです。
これも消費者心理をついたマーケティング戦略によるものです。
人がものを買ったり消費する心理としては、ポジティブな感情を増やしてネガティブな感情を減らすためです。
ポジティブな感情を最大化して、ネガティブな感情を最小化するために人はものを買います。
例えば、お掃除ロボットを買うのは、掃除の手間をなくすことでネガティブな感情を減らして、掃除をする時間で自由なことができて、そこでポジティブな感情を増やすことができるからです。
企業のマーケティング戦略として、人の感情のコントロールをベースに設計されています。
どうすればユーザーや消費者のポジティブな感情を増やして、ネガティブな感情を減らすことができるかを考えています。
捨てられない理由その2:自尊心と結びついたパーソナル・アイデンティティーと社会的帰属感
実験ではTOMS(トムス)という靴の例が挙げられています。
このブランドは、自分が靴を一足買うと、恵まれない誰かにもう一足靴がプレゼントされるキャンペーンを行いました。
人はものを買うとそれを所有できて良い気分が手に入ります。
それだけでなく、その消費によって社会的に良いことをしているとなるとポジティブな感情は増します。
この靴を買った人たちは、自分たちが社会的に意味がある素晴らしいことをしていると感じていました。
自分が慈善的な人間だというアイデンティティーを作り、それと同時に、自分だけのことではなく世の中全体のことを考える素晴らしいグループに所属している感覚がありました。
人はものを買って手に入れると、自分の中に何かしらのアイデンティティーが生まれます。
それによって価値ある仲間も生まれます。
ものにそれが付随しているから捨てることが難しくなります。
自分のいい人と思えるイメージを捨てたくないからものも捨てられないわけです。
ブランド品ばかりを買って捨てることができない人は、そのものに価値を感じているだけでなく、自分はそのブランドにふさわしい価値ある人間だと思っています。
ブランド品をたくさん買えるだけの経済的成功をしている人たちのグループに所属していると思いたいからです。
ですから、その商品によって引き起こされる感情の問題と、それを持っていることによって生まれるアイデンティティー、そして、それを持っていることによりグループに所属している感覚を持つことができる帰属性の3つが僕たちがものを捨てられない理由です。
この3つに対処しないと、ものを捨てられません。
人は感情を満たしたいからものを買います。
アイデンティティーを保ちたいから、グループに帰属していたいから、それを捨てられなくなります。
これがものを捨てられない原因ですし、次々にものを買ってしまう原因でもあります。
研究では、この3つの要素を満たしていると感じた場合、それにお金を使う確率が30倍も高くなりました。
企業はこれを理解してマーケティング戦略を考えています。
感情とアイデンティティーと帰属を満たした上で、それなりに機能が備わっていれば、その商品が買われたり試される確率が30倍も高くなるわけです。
高級ブランドのパーティーで有名人や芸能人が呼ばれるのも同じです。
そのブランドがこれだけの芸能人が来てくれるだけの素晴らしいブランドだと伝えています。
それはアピールすることによって、感情もアイデンティティーも帰属性も満たされます。
実際の機能性としては大差ありません。
感情とアイデンティティーと帰属性を理解して、それを拒否することが大切です。
僕たちがものを捨てられないのは企業がマーケティング戦略として、僕たちの脳をハックしているからだと認識するだけでも、余計なことに惑わされる確率は減ります。
その上で、なかなか捨てられないものや、ついつい買ってしまうものについて考えてみてください。
その商品が自分のどんな感情を満たそうとしているのか?
その商品がどのように自分のアイデンティティーを作っているのか?
その商品を持つことによってどんなグループに所属している意識につながっているのか?
最近、自分が買ってしまったものについて、この3つのポイントで再評価してみてください。
これを理解しておくと、種がわかった状態でマジックを見ている感覚を持つことができます。
それによってものを捨てることもできるようになりますし、そもそもものを買わなくなります。
自分がいかに必要のないものを抱え込んでいたかも理解できます。
片付けを邪魔する5つのメンタルブロック
2019年に社会心理学者のアリス・ボイズ氏が、先行研究をベースにして、人がものを捨てられない5つの原因と対策についてまとめてくれています。
①他人の散らかりは目に入るが、自分の散らかりは目に入らない
自分の一緒に住んでいるパートナーや家族について考えてみてください。
他人の部屋が散らかっていたり乱雑になっていると、やたらと気になったり目が行くと思います。
ところが自分のことにはあまり目が行きません。
他人の部屋は散らかっているように思え、自分の部屋はきれいに思えるバイアスがあります。
自分はきれいにしていて相手が散らかしているので、相手が片付けるのを待つスタンスになってしまいます。
その結果自分の片付けが疎かになります。
他人と比較して安心しているような状態です。
この問題を解決するためには、マインドセットを変えてください。
周りと比較して片付けをするかしないかを考えるのではなく、自分がお手本になると考えてください。
自分が周りの人のためのお手本になると考えます。
これは片付けだけでなく、仕事でもスキルを学ぶ場合でも同じです。
職場の雰囲気を変えたいとか、人生を変えるための習い事をしたいという場合でも、自分がお手本になろうと考えれば勇気を持って自制心を発揮することができます。
それによって他人に見られている感覚を持つことができます。
自分が周りの人のお手本になるマインドセットを持ってください。
それによって実際に片付けをしてみると、意外と家全体がきれいになったりすることがあります。
結局のところ周りが片付けをしていないのではなく、自分が片付けをしていなかっただけだったと気づくこともあります。
どちらかが悪いのではなく、お互い様だったことに気づけることもあります。
②片付けに必要な認知リソースを過小評価する
人は片付けをしようとしたときに、すっきりと片付いた部屋を想像します。
ところが、実際に片付けをするとなると様々なプロセスが必要になります。
片付けはひとつのプロセスで終了するものではなく、小さな意思決定の連続です。
小さな意思決定を大量に行うのが片付けという作業です。
人はそれを過小評価しています。
ビジネスでも副業でも、成功するためにはそのプロセスは容易ではありません。
自分がそれをやりきって成功したところをイメージすると、達成した気分だけ高まりやる気がなくなります。
ダイエットでも、かっこいい肉体だけを想像しているとだんだんやる気がなくなってきます。
人はやろうと思っただけでやる気がなくなります。
結果ばかりを見て、その結果にたどり着くためのプロセスを疎かにして、小さな意思決定の連続を過小評価しています。
多くの人は片付けが簡単だと思い込んでしまうせいで、片付けをしようと思った瞬間に、大変さを感じてやる気が失われるわけです。
この問題を解決するためには、次のポイントに留意してください。
ポイント1:「どこに収納するか?」よりも「捨てるべきかどうか?」の質問を優先する
片付けは多くの意思決定の連続です。
捨てるべきかどうかは、YES/NOで答えられる質問です。
それに対して、どこに収納するかは、自由回答ができるオープンクエスチョンです。
そうなると認知的負荷が大きくなります。
ですから、まずは簡単に意思決定ができる2択で片付けをしてください。
どこに収納するかよりも捨てるか捨てないかで考えてください。
特に危険なのが、「これは何かに使えないだろうか?」と考え始めることです。
これも自由回答なので脳が疲れてしまいます。
それによって片付けができなくなります。
自由回答の質問を自分に投げかけることを避けてください。
ポイント2:中間ボックスを作る
捨てるか捨てないかだけでは迷って決められない人も多いと思います。
その場合は、中間ボックスを作って、その箱に3カ月先の日付を書いてください。
迷ったら全てそこに入れます。
その3カ月後の日付になったら、その箱を見てまだあったものは捨てます。
人はそのものが本当に必要かどうかを予測することが苦手です。
迷ったものは全て3ヶ月後の日付が書かれた箱にとりあえず入れておきます。
必要であればその箱から取り出すはずです。
3ヶ月後にもそこに残ったままのものは使わないものです。
これにより決断のプレッシャーを減らすことができます。
片付けのコツは、いかに決断のプレッシャーを減らすことができるかです。
ちなみに、YES/NOと中間ボックスの考え方は人間関係にも使えます。
自分のスケジュールや予定を見ながら、それを続けるべきか?止めるべきか?を考えて、中間ボックスも作っておきます。
3ヶ月後にも中間ボックスにあった予定や人間関係は、少なくとも当面は必要ないと考えることができます。
残りの解説については続きで解説しています。
自分にとって本当に大切なことに集中するために、ぜひ続きもチェックしてみてください。
-
一問一答「あなたは、毎日をどんな行動で満たしたいですか?」【焦りをなくす時間術】
2023-05-27 12:00330ptあなたは、毎日をどんな行動で満たしたいですか?
DaiGo師匠の質疑応答でも、結局時間の使い方に行き着く相談は多いです。
今回は、将来死ぬのがもったいないという方の相談をもとに、毎日の焦りをなくし、有意義な時間で満たすための心理学を紹介させてもらいます。
「毎日楽しく幸せですが、将来死ぬのがもったいないと思ってしまいます。」
将来死ぬのがもったいないというのは、要するに、自分の生きている時間を最大化したいという意味だと思います。
であれば、そんなことを考えて悩む時間を行動することに使ってください。
人間関係でも仕事でも物でも何でも同じですが、無駄なものを捨ててみてはどうでしょうか?
捨てれば捨てたぶんだけ時間が手に入った感覚を得ることができます。
自分の時間を最大化したいのであれば無駄をなくすことをしてみてください。
以上がDaiGo師匠からのアドバイスでした。
時間に追われて生きていくのか、時間を追い越すのか。
時間に対して常に余裕を持って生きている人たちがいます。 時間に余裕を持っているか、時間に追い立てられているか、この違いはただ単に暇かどうかということではありません。
お金にどれだけ余裕を持っている人であっても、いつも忙しい忙しいと追い立てられていて幸福度が低い生活をしている人もいれば、お金に決して余裕はなくても、自然の中で家族とのんびり幸せに暮らしていて、時間に余裕がありながらも生産性が高い人もいます。
時間に追われていると、一瞬自分が有意義に時間を使っているような気になります。
ところが、実際に長期的に幸福度や健康度を測定してみると、時間に追われている人の方が圧倒的に不幸で不健康です。
今回は時間に余裕を持って生きていくことができる方法についてです。
時間に追われながら毎日仕事をするのではなく、ある意味時間を追い越して仕事するにはどうすればいいのかということを解説します。
1日24時間という時間は変えられませんが、時間の使い方と働き方を変えるだけで、はるかに時間に余裕を持って生きることができるようになります。
ハードワーカーで成果を出すことができるのはごく一部の天才だけ
多くの人が思ってるほど、時間に追い立てられている人は実際には仕事ができていません。 毎日時間がない時間がないと言いながら忙しく仕事をしている人は、仕事を頑張っているようには見えます。
ところが、実際にはこのような人が大した成果をあげることもできていません。
ごく一部のミリオネア達は確かにハードワーカーです。
そんな人達を見て、忙しく働いている人はかっこいいというようなイメージを持つ人が多いですが、それはごく一部の限られたミリオネア達だけの話です。
そういう人達は特別なだけで、僕たちのような普通の人がそんな部分だけを真似しても意味はありません。
1日の労働時間を普段の倍にしても集中力も生産性も下がらないような特別な人たちが、大企業のトップになったり何かで大きな成功を成し遂げてミリオネアになったりします。
普通の人たちが同じようなことをしようとすれば、健康被害が出たり集中力が落ちて、むしろ生産性は普通に働くよりも落ちてしまいます。 余計なミスをして被害が大きくなったり、そのようなデメリットが必ず出ます。
そんな被害が起きないごくごく一部の天才たちが輝いて見えるだけです。
野球でもテニスでもゴルフでも同じですが、そんなスポーツを趣味にしている人は多いと思います。 そういったスポーツをしていて、そのスポーツのプロの選手と同じレベルの練習をしようとはしないはずです。
ところが、これが仕事になると、多くの人がこれをしようとしてしまいます。 トップレベルの天才たちが1日10時間働くと聞くと、自分も同じぐらい働いて頑張らないといけない、週末も休んでいる暇なんてないと考えてしまいます。
時間に関してはこの問題が起きてしまいやすいです。
スポーツの場合は、プロと同じ練習をしようとしてもできないことに気づくでしょうが、時間の使い方に関しては、ただ10時間働くだけであればだらだらと仕事をすることはできてしまいます。
実際には、眠い目をこすりながらほぼ机の前に座っているだけであっても、何の成果も出ていなくても、10時間働くということはできてしまいます。
仕事でも人生でも成果というものは後からついてくるものです。
スポーツやゲームのように成果はすぐ出るものではありませんので、時間を長く使うことによって、多くの人が一部の偉大な人たちに近づいているような錯覚を持ってしまいます。
これは地獄につながる道です。
皆さんにもDaiGo師匠にとっての読書と同じように、これであれば何時間でも続けることができるということはあるかもしれません。
それが自分の仕事に対して向いているごく一部の人たちだけが、それをしても生産性や集中力が下がらないだけです。
にもかかわらず、なぜか世の中では仕事をガンガンする人たちがかっこいいと思われたり、ハードワーカーは素晴らしいと思われているので、皆さんもその方向に強制されてしまっています。
そんな一部の限られた天才ではない普通の僕たちが、どのような時間感覚を持って仕事と向き合えば、生産性を下げることなく成果も出て幸せに生きていくことができるのでしょうか。
人は住む場所によって年収が変わるが時間感覚は?
住む場所によって僕たちの年収が結構変わるという話は皆さんもご存知だと思います。
年収は「住むところ」で決まる 雇用とイノベーションの都市経済学
人は周りの人達や環境から多くの影響を受けています。
住む場所によってお金に対する感覚が変わるというのは皆さんもなんとなくわかると思います。
では、住む場所によって僕たちの時間の感覚や時間に対する価値というものは変わるのでしょうか。
それについて調べた研究も実はあり、これによると、皆さんの周りの人間がどれくらい働くかで皆さん自身の労働時間がかなりの部分決まってきます。
周りにハードワーカーが多くて朝から夜まで毎日ガンガン働いているような人たちが多い所に行くと、そんな周りの人たちに影響を受けて時間感覚が歪み、時間が足りない時間が足りないと言いながら時間に追われている生活をするようになってしまいます。
地方ののどかな島に行ったりすると、島の人たちはみんなのんびりと暮らしているような感じがするでしょうし、皆さんもなんとなくわかることだと思います。
実際に研究では、仕事に執着する人が多い地域とそうでない地域を比較すると、仕事にあまり執着していない地域に住んでいる人の方が、自分の時間をちゃんと大切にしているという傾向が確認されていて、その結果として幸福度も高い傾向があったということです。
仕事に執着している地域の人たちの方が、仕事を一生懸命しようと思っているわけなので、隙間時間も仕事を一生懸命しようとしますから、そういう人たちの方が時間の使い方に関してはシビアな感じもします。
時間を大切にしそうな気もしますが、この研究を見ると、どうやら逆のようです。
仕事に執着している人達は実は時間をあまり大切にしない傾向があったということです。
そして、結果的に幸福度が低くなってしまいます。
一方で、あまり仕事に執着することなく、ほどほどに稼ぐことができればいいという考え方をしている人が多い地域に住んでいる人の方が、時間を大切にする傾向があり、結果的に幸福度も高かったというわけです。
忙しい時ほど余計な事に時間を使ってしまう
これは考えるとわかるような気もします。
港区や六本木のあたりに行くと秒刻みのスケジュールで動いているビジネスマンがいたりします。 彼らは毎日仕事に執着して、秒単位のスケジュールで動いていることを自慢する起業家たちが、なぜか西麻布のバーで明け方まで飲んでいたりします。
朝まで飲んでいたりすれば、睡眠時間が削られて当然生産性は落ちるでしょうし、そんなに忙しいのであればその時間働いていた方がいいはずです。
秒刻みのスケジュールで働いていてそんなに仕事が大事なのであれば、その時間も働いていた方がいいのは間違いないはずですが、なぜか彼らはそんな行動をしてしまいます。
仕事に執着が強くてガンガン働くというところまでは問題ないわけですが、やはり働きすぎると生産性の低下やストレスの影響がどうしても出ますので、働き続けることができずどこかでギブアップしてしまいます。
その時に、すぐに家に帰ってゆっくり休めばいいはずなのに、ストレスの影響により判断能力も低下していますので明け方まで飲んでしまうという悪循環が起きる愚かな行為をしてしまうわけです。
仕事に執着すると、確かに仕事に一生懸命向き合っている時はかっこいいとは思います。 時間をうまく使っているように見えます。
ところが、それにより仕事を離れたところで時間を無駄にしやすくなってしまうということが、この研究から見えてくることです。
これは結構多くの人が思い当たることなのではないでしょうか。
仕事が立て込んでいて忙しい時ほど、家に帰って早く寝ればいいのに Netflix を見てしまったり、テストの2日前で追い込みをかけて今日は2科目を頑張らなければいけないと思っている時に、なぜか北斗の拳をイッキ見してしまったりします。
これも全く同じで、人が切羽詰まった状況にいるとろくでもないことに時間を使いやすくなります。
プライベートな時間から幸せを感じづらくなる
他の研究でも、同世代の周りの自分と同じレベルの人達がめちゃめちゃ働いているという認識が強い地域に住む人達は、人付き合いやボランティア活動や休日の余暇の活動から幸せを得にくくなるという傾向が確認されています。
周りの人達が一生懸命働いていると思うと、そんな中で自分だけ遊んでいて差をつけられているような気がするとか、周りの人が一生懸命働いているし、この時間に仕事をしたり副業をすればもっと稼ぐことができるのではないかと頭によぎってしまいます。
そうなると、せっかく家族と楽しく過ごしていたり、ボランティア活動や自分の趣味の活動をしていても、そこから幸せを感じづらくなってしまいます。
時間に切羽詰まっている人は、せっかくの休日にも休むことができず、そのためその状況のまま仕事に戻ってしまいます。
そして、自分は仕事が趣味でもあるから、逆に休んでいるとストレスになってしまうというようなことを言ってしまうビジネスマンもいますが、それは寝られない自慢をしている同じようなビジネスマンに囲まれているからです。
そんな人達が住んでいる地域に住んだり、そういう同僚が周りにいると、普段の趣味や休日を楽しむこともできなくなってしまうということです。 こんなにも住む場所から影響を受けてしまうわけです。
仕事に対する考え方もかなり影響を与えます。 仕事に対しては勤勉さが何より重要で、仕事は真面目にコツコツとガッツリとするものだと考えている人が多い地域に住んでいる人は、やはり同じように休日や余暇を楽しむことができなくなるようです。
住む地域によってこんなにも人は影響を受けるわけです。
時間に追われる生き方をしたくないと思うのであれば、最近であればリモートをできるようになっている会社も増えてきているでしょうから、できるだけそういう仕事を選んで郊外でのんびり暮らすことができる場所に住む方が良いのではないのかということになります。
そういう意味でも、これからはますます地方に移住するような人たちも増えるのだろうと思います。
豊かな時間の使い方の方程式とは?
では、豊かな時間の方程式というものはあるのでしょうか。
余裕を持って過ごすことができて、仕事でも成果を出せて幸せにもなれる、そんな方法はあるのかということについても調べられていますが、これによると、それは人によるので色々と試してみるしかないとされています。
これは時間の使い方というものが人間の価値観に依存するものだからです。
つまり、自分の価値観に合った仕事ができるかということが重要になるということです。
人の価値観はそれぞれです。
一生懸命働くことよりも自由な時間が確保できる方がいいという人もいるでしょうし、自由な時間はほどほどでもいいけれど、一生懸命働いていい生活がしたいという人もいます。
これはその人の人生のステージによっても変わってきます。 30代前半まではガンガン働いて休んでいる場合ではないと思っているけれど、それは過ぎて結婚して子供もできたら家族との時間を優先したいと考える人も結構いると思います。
その人の価値観
人生のステージにおけるニーズ
優先順位
これらはその人と時々によって変わるものですから、それにより時間をどのように使うのかということに対する心の反応は大きく変わってきます。
ですから、多くの人が使える絶対的な法則というものはありません。
自由な時間を得ることができる感覚の違い
プリンストン大学などの先行研究によると、フリーになって働くことで自由な時間が増えたという感覚を覚える人もいれば、毎日必ずオフィスに行って一定時間そこで働くことにより時間が増えた感覚を得ることができる人もいたということです。
最近はリモートワークも一般化してきたので、なんとなくわかる人も多いでしょうが、DaiGo師匠のように自由な仕事の仕方をしていると仕事とプライベートのオンオフがはっきりしなくなるということはあります。
それでもかまわないという人は良いのでしょうが、このオンオフがつけられない人はオフィスに入って働いた方が会社から帰った後に余計に仕事のことを考えなくてすみます。 その結果自由な時間が増えたような感覚を覚えるわけです。
ですから、自分がこのオンオフを気にしないタイプなのか、それとも、しっかりと切り替えた方がいいタイプなのかということにより結構変わってくるわけです。
万人に通じる最適解というものはないわけですから、今まで紹介してきた時間に関するアプローチが色々あったと思いますので、それらを試してもらい自分が共感できるものを探してみてください。
そんな中で試行錯誤しながら自分の最適解を見つけるしかありません。
例えば、家事代行サービスを使うことで時間をお金で買う方法もありますが、他の人に自分の家を触られることが嫌だという人もいると思います。 そんな人も、できれば一度試してみてください。
そして、意外と良かったと思うのであれば続ければいいし、やはり嫌だったというのであればその理由を考えてみてください。
その理由を考えれば上手に時間を買うこともできますし、自分の時間感覚を変えていくこともできます。
どうすれば時間に余裕を持てるようになるだろうかということを常に考えて試してみてください。 実際に余裕を感じたらそれを採用し続けてください。もし感じられなかったらやめてまた次を試せばいいだけです。
時間の豊かさチェックリスト
時間のストレスを感じる度に、これから紹介する6つのチェックリストに沿ってチェックしてください。
それにより皆さんの時間ストレスを軽減することができます。
これを手帳などにメモしてもらい、最近なんだか忙しい気がするとか時間に余裕がなくなってきたと思ったら、ちょっと時間を作ってこれを見直してみてください。
これについては、続きで解説していきます。
自分の時間感覚が狂っている気がする人も結構いると思います。
なんだか忙しく働いてはいるけれど、今ひとつ成果も出ないという人や、何年もガンガン働いてきたけれど全く成果も出ないし給料も上がらないという人もいると思いますが、時間の使い方というものは矯正することができるものです。
時間に余裕を持つことができれば、新しいことを思いつく可能性も高くなります。
それにより今抱えている問題に対する解決策も出てきやすくなります。
まずは時間の余裕を作ることです。 時間に余裕のない人には新しいことはできません。新しいことができなければ現状を変えることはできません。
まずは時間の豊かさチェックリストを試してもらい、時間の余裕を持っていただけたらと思います。
ぜひ続きもチェックしてみてください。
-
一問一答「あなたが、つい注意を持っていかれてしまうのはどんなことですか?」【生産性を高めるルール】
2023-05-25 12:00330ptあなたが、つい注意を持っていかれてしまうのはどんなことですか?
今回は、人間関係が原因で退職することになったものの、残りの期間が怖くてしょうがないという方からの相談をもとに、注意力をコントロールして、仕事や勉強、運動や自分のやるべきことの生産性を高める方法を解説させてもらいます。
「Q. あと1ヶ月半で会社を退職します。退職理由は人間関係によるものです。残り1ヶ月半で何かミスをしないだろうかとか、先輩たちに陰口を言われないだろうかと毎日が怖いです。もっと堂々としていたいのですが、何かアドバイスをいただけないでしょうか?」
1ヶ月半ぐらいであれば普通に我慢できると思うので頑張ってもらいたいですが、おすすめとしては新しいことを何か始めてみてください。
人間関係でもどんなことでも同じですが、人間の人生というものは何に注目するかで決まります。
会社の人間関係で悩んで退職を決意したとなると、自分の注意力はほぼ全てが人間関係に向いています。そうなれば当然ですが人間関係が怖くなります。
怖いからずっとそればかりを考えて何度も確認するようになってしまいます。
一方で、自分が新しい習い事を始めて、それが毎日楽しくて仕方がないとなると、もっと楽しくて注意を向けることがあるので人間関係は気にならなくなります。
退職までの1ヶ月半の間に仕事に関わることでも趣味でもどんなことでもいいので、何か自分だけの目標を作ってもらい、そちらに全力で取り組んでみて下さい。
そうすれば、多少職場で何か言われたところで些細なことだと気にならなくなります。
自分の退職日を目安にゴールを設定してもらい、そこに向かって何か新しいことにチャレンジしてみましょう。
以上がDaiGo師匠からのアドバイスでした。
集中力と注意力と生産性
仕事でも勉強でも毎日の生産性を高めることが大事だと言われますが、そのための集中力や注意力というものは実は微妙に違います。
例えば、お医者さんが手術をするときには集中力が必要になりますが、日常的に行う事務作業やそれほど集中力を必要としない作業にまで、常に集中力を発揮していると疲れてしまいます。
科学的な集中力と注意力は、いくつかの異なる要素に基づいた異なる概念です。
集中力は、一定の課題や活動に意識を集中させる能力を指します。
集中力が高い人は、長時間にわたって注意を散漫にせず、特定の目標に向けて思考や行動を集中させることができます。
集中力は、タスクの達成や問題の解決において重要な要素です。
一方、注意力は、外部からの刺激に対して注意を向ける能力を指します。
注意力が高い人は、周囲の情報や刺激に敏感であり、それらに適切に反応することができます。注意力は、情報の処理や環境の把握において重要な役割を果たします。
ですから、集中力は内的なプロセスに焦点を当てており、特定の課題や目標に向けて思考と行動を統合する能力を示します。
一方、注意力は外的な刺激に対する感受性と、それに対して適切に反応する能力を指します。
これらの能力は相互に関連しており、高い集中力を持つ人は通常、注意力も高い傾向があります。
ただし、注意力が高いからといって必ずしも集中力が高いわけではありません。
集中力と注意力は、独自の特徴を持つ能力です。
もちろん集中力を鍛えることも大事ですが、注意力をコントロールすることが生産性を高めることにつながるのではないかと最近の様々な研究で言われています。
集中力は、注意を一点に向ける能力です。
注意力は、自分が注意を向けたい一点に注意を向けて集中モードになることもあれば、逆に、今は注意を向けたくないところから注意を背けることもあります。
例えば、仕事に行く前に奥さんと喧嘩したとして、そのことにずっと注意を向けていると仕事の生産性も上がるはずがありません。
つまり、自分が注意を向けたいところに向けることができて、今は向けるべきではないところに注意を向けない力が注意力です。
生産性を高めたいのであれば注意力のコントロールが重要になります。
集中力という言葉を生まれ持った才能かのように使う人がいますが、実際にはそんなことはありません。
注意をコントロールする力と切り替える力が重要です。
そんな注意の切り替え方も含めて、注意力を高めるための10のルールを解説させてもらいます。
注意力を高めるための10のルール
研究者が論文の執筆の生産性を向上させるための方法についてまとめてくれた文献があります。
論文を書く作業には緻密で面倒な作業と興味の湧く作業が混在しています。
その注意を上手に切り替えることができなければ良い論文を書くことができません。
普通に仕事をしている人も、普段の仕事の中には楽しい仕事もあれば面倒な仕事もあると思います。
そこから注意力が必要なタスクに対しての生産性を高める方法を解説させてもらいます。
注意力のコントロールとしては勉強にも家事にも子育てにも使えると思います。
家事や子育てに忙しい人もいると思いますが、子供ややるべきことに対して注意を向けるときもあれば、リラックスして自分の楽しみに上手に切り替えることができなければ疲れてしまいます。
毎日の注意を上手に切り替えて、生産性を高める方法として役に立つと思います。
ルールその1:必ず確保できる時間で習慣化する
大抵の人は、仕事でも家事でも毎日ある程度決まった時間に決まったタスクをこなしていると思います。
習慣化する際には、毎日必ず確保できる時間帯を決めて、それを絶対に死守するというところから始める必要があります。
人間の脳は習慣的な行動に支配されています。
注意力のコントロールも習慣にコントロールされています。
例えば、うつ病や気分障害になって、気分のアップダウンが激しくなってしまった人であればわかると思いますが、いつもダウンする時間は大体決まっていると思います。
落ち込んでしまい仕事に手がつかなくなる時間帯が決まっています。
人は自分も気づかないうちに注意力に対して習慣化を行ってしまいます。
逆に言うと、それを脳に教え込めば注意力を上手にコントロールできます。
そのためにはまず必ず確保できる時間帯を決めてください。
例えば、仕事から帰ってきて新しいスキルを身に付けるための勉強をしたいのであれば、仕事から帰ってきて、どの時間帯にどれぐらいの時間であれば必ず確保できるかを考えます。
30分であれば必ず確保できるのであればそれでも構いません。
仕事から帰ってきてからの時間では疲れていて無理だと言うのであれば、朝起きてからの30分でも構いません。
寝る前の30分でも構いません。
必ず確保できる時間を決めて、そこで新しいスキルのための勉強をしたり読書をしたりとやることを決めてください。
時間が多い少ないではなく、必ず毎日その時間を死守することによって、脳に教え込むことができるようになります。
それが徐々に習慣化され、勝手に注意がそこに向くようになります。
自分のモチベーションを上げて勉強しようと思わなくても、気合を入れて読書をしようと思わなくても、やりたいと思っている行動ができるようになります。
副業を始めたりYouTubeやSNSの投稿でフォロワーを増やすのも同じです。
まずは時間を決めて注意力を向ける癖をつける必要があります。
それができないといつまでたってもツラいまま続けるしかなくなります。
人は普段とは違うところに注意を向けるときに大きなエネルギーを必要とします。
習慣化が苦手な人は、この注意を向ける時間帯がバラバラであることが多いです。
気が向いたらやるのでは、いつも大きなエネルギーが必要になります。
自分がやりたいと思っている作業に使う時間を決めてください。
できれば毎日、最低でも週に4日は確保するところから始めてください。
最初は短い時間でも構いません。
2ヶ月ほど経ってくればかなり慣れてきます。そこから徐々に時間を増やしていくことも難しくはありません。
ルールその2:集中できる環境をつくる
人の注意力は環境に依存しています。
行ったことがない場所や知らない土地に行くと、人はいろんなところに注意を向けて警戒します。
慣れた場所や自宅ではぼんやりとしたりリラックスしたりします。
人の注意力は環境に支配されています。
とは言え、わかっているけれど難しいという人も多いと思います。
環境を整えるためには以下の5つのポイントだけは留意してください。
①気が散る要因を排除する
スマホや漫画など、人の注意力を引きつけまくるものが溢れています。
その気が散る要因を必ず排除してください。
Netflixが気になってしまうのであれば、リモコンを遠ざけて目に入らないようにしてください。
②集中できる場所をつくる/見つける
注意力をコントロールしやすい場所は人によって違います。
自分の部屋が適している人もいれば、カフェが適している人もいます。
家族もいるリビングが適している人もいます。
これは人によって違うので、自分が最も注意力をコントロールしやすい場所を探してください。
DaiGo師匠の場合であれば、ホテルや旅館などに行って、自分の所有物がなければないほど注意力をコントロールできると気づきました。
これは自分なりに試して見つけてください。
③通知をオフにする
スマホの電源や通知をオフにしてください。
通知をオフにしても見れるものがたくさんありますので、電源を切る方がいいと思います。
おすすめは電源を切った上で袋に入れて見えないところにしまってください。
それでもダメな場合は、緊急時だけは使うことができるこのようなアイテムを使ってみるのもいいと思います。
タイムロッキングコンテナ 禁欲ボックス スマホ依存対策 ゲーム中毒
④後でやるメモ
やるべきことに注意を向けているのに、その注意が切れる瞬間としては、スマホなど余計なものが気になってしまうこともありますが、他のやらなくてはならない仕事が気になったときがあります。
急に他のタスクが気になって注意がそれてしまいます。
緊急なタスクと感じても、緊急なことが重要ではないことの方が多いです。重要なことは緊急でないことの方が多いです。
他のタスクを思い出しても、それに注意力を奪われないように、後でやるメモに書き出すようにしてください。
メモに書き出しておくだけで注意力を奪われることがなくなります。
人は短絡的な生き物です。
すぐにやって結果が出るものや簡単に終わる仕事を優先してしまいます。
見た目で成果を感じられる筋トレを3ヶ月続けることよりも、やってすぐに結果が出る机の片付けを優先してしまいます。
人は目先の欲求に弱いです。
短期的な欲求に支配されそうになったときには、後でやるメモに書き出してください。
それができないと、人は永遠にどうでもいい仕事ばかりを続けて、本当に大事なことを先延ばしして、何も残らないということになります。
⑤「今集中してやらなければならない作業をしているので、終わってから声をかけてもいいですか?」
職場などではこれを使うようにしてください。
同僚や上司に質問されたり話しかけられて、やむを得ず中断しなくてはならないときもあると思います。
そんな場合にはできるだけ早く作業に戻れるように、どうしても今は集中しなくてはならないことがあるので、終わったら声をかけさせてもらってもいいでしょうかとお願いしてください。
自分のデスクの横にホワイトボードを用意して、そこに「今は全力で集中しているので、何か用件があればここに書いておいてください」と見えるようにしておくのも良い方法です。
ルールその3:まず手をつけて、後で評価/修正する
人は先延ばしするときには、手をつけるかどうかを考えると同時に評価をしています。
それに手をつけようかと考えたときに、それを今やる必要があるかと考えます。
どれぐらい時間がかかるだろうかといろいろ考えます。
やる前から結果や評価を考えて先延ばししてしまうわけです。
手をつけてダメだった場合の心配もします。
これでは先延ばしばかりになります。
評価や修正は後でやればいいことです。
まずは手をつけてください。
仕事でも運動でも論文の執筆でもどんなことでも同じです。
あれこれと考えて最初から最高のものを作ろうとする人ほど、手をつけることなく先延ばししてしまいます。
完璧なものどころか何もできなくなります。
まずは取り組むことが大事です。
しかも、手をつけたとしても、その作業を進めることと、それがうまくいっているかどうか?本当にそれをやるべきかどうか?ということを同時に考えると、注意力は分散しています。
目の前の作業に注意力100%で向き合えばうまくいくのに、その作業に対する評価や価値に注意力が分散していてはうまくいくはずはありません。
人にとって評価はとても難しい作業です。
評価を同時に行おうとすると注意力は分散します。
習慣化も完璧な習慣を作るよりも、まずは手をつける習慣が大切です。
それをどれぐらい続けてどう発展させていくかは後から考えるべきです。
習慣化できてから評価や修正を行えばいいだけです。
ルールその4:トリガーを活用する
何をするべきかタスクに注目する人がいても、そのタスクの前のトリガーに注目する人はあまりいません。
ハビットチェーンの考え方に近いですが、「Aの行動をとったらその後にBを行い、BのあとにC…」とすると習慣を積み重ねていくことができます。
日常の中に違和感を設置するのも良い方法です。
例えば、「明日は朝起きてHIITをしよう」と決めたとします。
夜寝る前に、自分のお気に入りのワインの空のボトルをなぜかリビングに置いておいたりします。
普段とは違う日常があると、人の注意力は一気にそこに向けられます。
それによって、昨日の夜に決意したことを思い出すことができます。
人の注意力は一気に向けるところを決めて、そこから次のやるべきことに行動をつなげると、注意力の分散を防ぐことができます。
そのために違和感があるものをいつもとは違う場所に置いてみてください。
ルールその5:プリコミットメント
やるべきことを習慣化して注意力のコントロールができるようになりたいのであれば、やるべきことをする前に、友人や家族にこれから始めると公言してください。
一緒に取り組む仲間でLINEのグループを作って、そこで公言してもいいと思います。
人は公言すると自分の発言に責任を感じるようになります。
最初に必ず確保できる時間を死守することと組み合わせてください。
必ず死守すると決めた時間が近づいてきたら、5分前に公言してそれから始めるという感じです。
いつもとは違う時間に公言していたらダラダラしていたのがバレてしまいます。
ここから先は後半の残り5つのルールを解説していきます。
ぜひ続きもチェックしてみてください。
-
一問一答「あなたは、人間関係づくりにどんなイメージを持っていますか?」【人脈づくりの極意】
2023-05-23 12:00330ptあなたは、「人脈づくり」にどんなイメージを持っていますか?
今回は寂しい感情についての相談をもとに、新しい人間関係を最速でつくるための心理学について解説させてもらいます。
「Q. 寂しい感情を感じたときにどうすればいいか教えてください。」
寂しさを感じたときに過去に答えを求めないでください。
人は寂しさを感じたときに昔の方が良かったと思ってしまいますが、昔の方が良かったと思ってしまうと人間関係や恋愛関係でも昔の関係に頼ってしまいます。
そうなると人はいつまでたっても未来に向かって進むことができなくなります。
寂しい原因は、自分の人間関係が全く成長していなくて新しい関係を作ることができていないからです。
だからといって、過去に戻っていては未来は遠ざかっていきます。
寂しさを感じたときには、その寂しさを埋めてくれる過去に頼るのではなく未来に手を伸ばすことが大切です。
会ったことがない人に出会える場に行ったり、行ったことがない場所に行ってみましょう。
それが僕からできるアドバイスです。
以上がDaiGo師匠からのアドバイスでした。
人間関係の5つの思い込み
人間関係は作っても意味がないし面倒なものだと考えている人も多いと思いますが、その考え自体が思い込みです。
人間関係は面倒だと感じたとしても、それはどんな人間関係を作るかによって違ってきます。
僕たちは人間関係を作らなければ生きていくことができません。
どうせ作るのであれば良い関係を作った方がいいはずなのに、人間関係は面倒だとか苦手だと思い込んでしまうために、結果的に抱えざるを得ない嫌な人間関係だけを抱えていることが少なくありません。
これは自分のキャリアだけでなく人生においても大きなマイナスになります。
それを防ぐために人間関係における5つの思い込みについて解説させてもらい、価値ある関係を作るための方法まで紹介させてもらいます。
人間関係を作ることが苦手な人について調べたレビューがあります。
人間関係を作る上で必要なのは、才能や生まれつきのコミュ力、生まれ持った性格によるものだと考えている人も多いと思います。
ですが、このレビューによると、人間関係を作る上で最大の壁は、大抵の場合スキルではなく考え方の問題だとされています。
人間関係が苦手だったり下手なのはスキルの問題ではありません。
人間関係が下手になる思い込みや考え方、誤解を持っているからです。
誤解その1:人間関係づくりは時間の無駄だと思っている
定期的に新しい人間関係を作る場に出かけたり、親密さを増すために適切なコミュニケーションを取ったり、様々な人間関係づくりのやり取りがありますが、多くの人はこのような人間関係づくりは時間の無駄だと考えています。
皆さんには仕事上の関係や必要な人間関係がいろいろあると思いますが、実際には、必要のなさそうな人間関係も持っていなくてはなりません。
研究によると、皆さんの現在の仕事や職場などに直結する関係ではなかったとしても、長期的に見ると皆さんの人生やキャリア、パフォーマンスの改善に役立っていることが多いそうです。
つまり、今はそれほど興味がないかもしれません、特に仕事に役にたつわけでもないかもしれません、それでも軽くつながっておいた方が、本当に必要な人間関係だけつながっておくよりも、長期的に見るとプラスになるわけです。
人はだれでも変わりますし成長していきます。
人も変われば環境も変わるし、職場も変わると思います。
そうなったときに、それまで必要な人間関係しかなかったとしたら、自分の新しい状況で必要な人間関係をまったくのゼロからつくる必要に迫られます。
これが多くの人が人間関係づくりが面倒だと感じる大きな原因です。
普段から幅広く人間関係をつくっておけば、自分の状況や環境の変化が起きたときに、それまで付き合ってきた人間関係の中で変化させることができます。
ところが、小さな限られた関係の中だけでしか付き合わないとなると、自分や状況が少し変わっただけで、その人間関係に対して何か違う気がしたり不満を持ってしまいます。
しかもゼロから新しい関係を開拓しなくてはならないので、当然面倒ですしストレスを抱えます。
今直接関係のない人であっても、長期的に見ると自分を支えてくれる人かもしれません。
とは言え人間関係を広げすぎると面倒なのは当然です。
とりあえずは自分が重要視するテーマや戦略的な人生計画から見たときに重要だと思える相手にまずは接触してみてください。
そこから徐々に範囲を広げるようにしてみてください。
今自分にとって1番重要な関係や、つながりたい人との関係をまずは大切にします。
その自分が必要だと思う関係からの紹介で、その人の友達と会う機会を増やすようにしてください。
つまり、自分が必要だと思っている人とのつながりだけでなく、その人の友達とゆるくつながっておくと、その人間関係が先々活きてくる可能性があります。
無作為に人間関係を広げる必要はありませんが、今自分が必要だと思っている関係の一歩先まではつながっておくようにしてください。
誤解その2:人間関係の才能は生まれつきで変えにくいと思っている
人脈づくりは生まれつき外向的な人にとっては楽でうらやましいと思っている人が多いと思います。
内向的な人には人脈作りは向いていないと思っていると思います。
この考えも思い込みです。
この思い込みを持つと、当然人間関係をつくるために自分のリソースを使わなくなります。
使わなければ増えるはずがありません。
キャロル・ドュエック博士によると、対人スキルのような個人の属性は、生まれつき決まるものだと思っている人よりも、練習を重ねると伸びるものだと思っている人の方が、より多くの対人スキルを身に付けるための練習を重ねて、結果的に人間関係からの見返りを得ることが多くなるとされています。
生まれつき決まるものではなく練習によって伸ばせるスキルだと思うことができれば、当然その練習の量は増えていきます。
その結果多くの人間関係を得ることができて、その練習をしない人たちよりも人間関係から多くのリターンを得ることができます。
練習をした人の方が結果的に得をします。
これはお金の面でも時間の面でも仕事の面でも言えることです。
人間関係のスキルは生まれつきのものではありません。
筋肉と同じで、練習によって伸ばすことができるスキルです。
内向的な人には内向的な人の戦い方があり、外向的な人には外向的な人の戦い方があるだけです。
生まれつき決まるものという思い込みは捨てましょう。
誤解その3:人間関係は自然にできあがるものと思っている
友達というものは心と心がつながって自然とできるものだと考えていませんか?
人間関係は気の合う人同士の間で自然と生まれ、育っていくものと考えている人が結構いますが、これは完全に誤解です。
この考え方を持っている人にとっては、自分の人生やキャリアにとって必要な人間関係を戦略的に作ろうとする人は非倫理的な人のように感じると思います。
そんなことで出会った関係は本当の友達ではないと言うわけです。
この考え方を持っている人は似たもの同士の関係しかできません。
同じような人ばかりが周りに集まってしまいます。
同じような人が何度集まってどれだけコミニケーションをとったところで同じような結論しか出ません。
その結果、自分にも相手にも大した結果をもたらすことがありません。
これはお互いに傷を舐め合うだけの関係です。
自分にも相手にもメリットはなくただの時間の無駄で終わります。
何十年にもわたる社会心理学の研究によると、大抵の人は特に意識しないと、自分に似た相手や頻繁に会う相手としか交流しなくなります。
このような人間関係を心理学では「自己愛的で怠惰な人脈」と呼びます。
戦略的に考えて人間関係を広げるのは何の問題もありません。
意識しないと同じような人としか会わなくなります。
例えば、自分がしてみたいビジネスに必要な人間関係、何かしらの問題を抱えたときに必要だと感じた人間関係、そんな関係を新たに作ろうとするのは大切なことです。
仕事上必要な関係を求めるのは良いことです。
プライベートな関係だけでは自己愛的で怠惰な人脈になってしまいます。
そうならないためのスパイスとして仕事上の関係が活きてきます。
そこから一生の友達ができることも珍しくありません。
人間関係は自然とできるものではなく恣意的に作っていくものです。
誤解その4:人脈づくりは利己的なものだと思っている
人間関係づくりに努力をしない多くの人たちは、人間関係づくりは不誠実な行為だと思い込んでいます。
人脈やコネで物事をなんとかしようとしているズルい人だと考えています。
そんなのは実力ではないと批判しています。
それは人間関係における努力を怠っている人です。
人間関係づくりの努力をしている人は、人間関係というものは互恵関係であり、お互いにメリットをもたらすものだと考えています。
互恵関係がなければ長い関係は成り立ちません。
ですから、何十年も付き合っている良い関係がある人は、お互いにメリットをもたらす関係を保つことができる人です。
人間関係をつくろうと努力している人は、お互いにメリットをもたらす互恵関係を作ろうと努力している人です。
そんな人と付き合う方がメリットが大きいです。
この思い込みから脱却するためには、実際にやってみるのが効果的です。
実際に作ってみた人間関係が、自分だけでなく自分のチームや家族、友達など自分の身近な人にとっても価値があることだと実感すれば思い込みから逃れることができます。
人間関係づくりは利己的で自分のためだけのものと思い込んでいても、実際に人間関係をつくれば、自分の大切な人も幸せになります。
自分のチームや組織にもメリットがあると理解できると思います。
誤解その5:強い絆ほど価値があると思っている
多くの人は強い絆で結ばれた相手との関係こそが最も重要だと考えています。
これも誤解です。
強い関係で結ばれた相手が重要ではないということではありませんが、その関係こそが最も重要だというのは間違いです。
信頼感で満ちた長い関係も大切ですが、一方でデメリットもあります。
自分が長く付き合っている重要な人たちを大切にすることで、新しい関係を過小評価してしまう人が多いです。
つまり、確かに長く付き合っている大切な人たちとの関係は重要なものですが、だからといって弱い関係が必要ないわけではありません。
どちらも大切ですし、どちらにもメリットがあります。
上下関係があるわけではなく、その目的が違うだけです。
皆さんが今持っている人間関係の輪があるとして、その一番端っこにいる関係も重要です。
世の中を変えるようなイノベーション、皆さんの人生を変えるターニングポイントなど、新しいきっかけや知見を与えてくれるのはその人たちです。
強い関係は今を維持したり心を支えてくれるために必要です。
人生におけるイノベーションやターニングポイントを与えてくれるのは弱い関係です。
この2つは両方を大切にして、両方を使いこなせるようにしてください。
新しい出会いや弱いつながりがないと、新しいことを学ぶことも少なくなります。
今の自分から遠く離れたリソースにアクセスする機会も減ります。
そうなると人生が煮詰まります。
強いつながりと弱いつながりには同じように価値があります。
その両方を大切にしていきましょう。
短期間で人間関係を作る5つの方法
人間関係づくりの大切さが実感できたと思いますが、それがなかなか面倒だと感じている人も多いと思います。
それが簡単にできる5つのポイントを解説しておきます。
これがわかれば引っ越しをしたり転職や転勤をして環境が変わったとしても何の不安もなくなります。
そんな方法については、続きをチェックしてみてください。
1 / 38