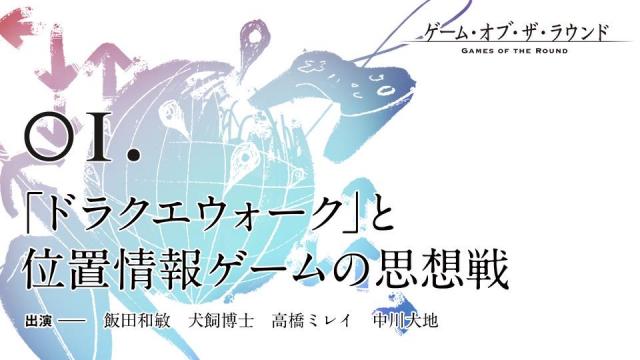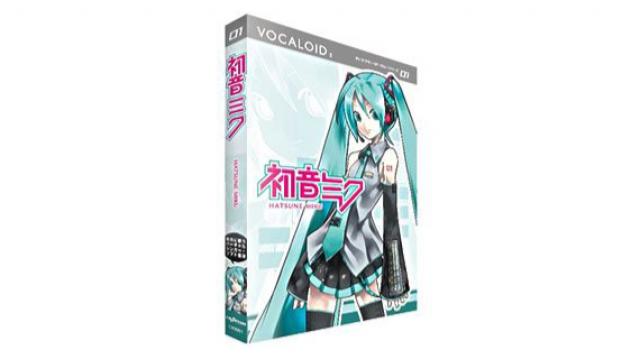-
丸若裕俊 ボーダレス&タイムレス――日本的なものたちの手触りについて 第8回 渋谷の街から考える〈見立て〉と〈閒〉(前編)
2019-10-21 07:00
工芸品や茶のプロデュースを通して、日本の伝統的な文化や技術を現代にアップデートする取り組みをしている丸若裕俊さんの連載『ボーダレス&タイムレスーー日本的なものたちの手触りについて』。茶筒の老舗と家電メーカーの協業は、丸若さんの演出する「茶」に何を寄与するのか。千利休的なストイシズムと古田織部なラグジュアリーの対比、さらにGEN GEN ANが渋谷にある理由と、そこから生まれる「見立て」について語り合います。
開化堂とパナソニックが共同開発した「響筒」が表現するもの
丸若 今日は最初に見てもらいたいものがあるんです。茶を入れるための茶筒をつくっている老舗に、明治時代から続く開化堂というお店があるんですが、宇野さんも以前、行ってくれていましたよね? その彼らが、何とも乙な取り組みをパナソニックと組んで面白いものをつくっていて。「響筒」という製品で、見た目は開化堂の伝統的な茶筒なんですが、フタを開けると内部はスピーカーになっていて、音楽を再生できる。フタを閉じると音は完全に消えます。開化堂の茶筒は気密性がハンパないから。
宇野 本当だ。すごい。
丸若 「次の世代にも渡したくなる家電」がコンセプトなんだけど、開発者の皆さんのスイッチが入ったらしくて、採算度外視でつくっちゃって。ワイヤレス充電にまで対応してる(笑)。これは、パナソニック的にはむちゃくちゃチャレンジだったらしいです。開化堂の茶筒は時間を経ると色合いが変わったり味わいが出てくるんですが、経年変化する家電は技適に通らないんですよ。
宇野 でも、むしろ経年変化しないと開化堂の茶筒とはいえないわけですよね。
丸若 そもそも茶筒を売って儲けを出すという開化堂のビジネスモデル自体、よく考えると一見、不可思議なところがありますよね。茶筒ってなければなくてもいいものですから。だけど、ある種の美意識に気づかせてくれるアイテムのような気もするんです。この響筒を今度の茶会のときに出してみようと考えているんですが、そこで伝えたいのは、「閒」を使って、いろんなことに気付いてほしいということ。気付くというのは本当は怖いことで。周囲に気付いた人間がいると、みんな怖くなって、その人を潰そうとすることすらある。でも、子どもの頃は、気付くというのはめちゃくちゃ楽しい遊びだったはずで。そういうことを伝えていきたい。
宇野 この10〜20年、工業社会から情報社会に移り変わる中で、僕らはラグジュアリーなものを手放してきた。もともと工業製品は生活に足りないものを満たし、生活水準を上げるためのものだったのだけれど、必需品が一通り行き渡って消費社会になると同時に自己表現の手段になっていったわけですよね。モノを所有することが自己表現になっていった。このとき、モノの「過剰さ」や「余剰」が、心に余裕を持って世界を見つめ直すための回路として機能した。ラグジュアリーなモノの批判力ってここにあったわけです。ところが、情報社会下ではモノではなくコトが価値の中心になる。そうなると、モノを通じた自己表現自体がかっこ悪くなっていって、モノは可能な限り余剰を削ぎ落としてミニマルにしていく。確かに、工業社会時代の手垢を落としたことで楽になった部分はある。モノからコトへ、他人事から自分事へと軸足を移したことで、シンプルでスマートになったのはいいんだけれど、シンプルでスマートになった分の欠落を、どう埋めればいいのか、わからなくなっているところがある。余剰が最適化されたその先に、僕らはどこに向かうのか。もちろん、モノを削ぎ落としたその分、豊かなコトを追求するのが基本になる。じゃあ、その「コト」ってなんなのか。今はとりあえずFacebookに自分の豊かなソーシャルグラフを誇ることとか、Instagramにリア充で「映え」る休日を載せることになっている。でも、ちゃんと考えている人はどこに向かうのかというと、それはやっぱり「閒」なんじゃないかと思っていて。余計なものを削ぎ落として、無駄なくスマートにシンプルにまとまっている。そこからラグジュアリーな過剰さに戻るのではなくて、「閒」を取り入れてみよう。もうちょっと物事に対する距離感や進入角度を自由に取れるようにしてみよう。時間ではなくて「閒」を獲得してみよう、という流れをつくっていけると思うんですよね。
モノが促す思考によって「閒」を楽しむ
宇野 今年の夏休みに漫画『へうげもの』を改めて読み返したんけど、あの時代の茶人たちは、茶器や茶そのものと同じくらいパフォーマンスを重視していましたよね。茶を飲むシチュエーションや、もてなしというかたちでの関係性の構築に、すごくこだわっていた。変な場所に茶室を建てたり、インテリアの配置に工夫を凝らしたり。あれは建築やモノを通じて体験そのもののをデザインしていたわけですよね。情報社会下のモノのデザインはこれに近くなると思う。情報技術の発展によって、体験そのもののデザインはより容易に、そして細かいところまでできるようになる。チームラボの空間演出がいい例だよね。さっきの響筒にしても、すごく実験的な企画だから、ある種のネタ感というか、サプライズ的な要素の方にみんな興味がいっちゃうのかもしれないけど、本当はこういう製品が出てくるのは自然なことだと思う。開ければ音が鳴る茶筒が流行るという意味ではなくて、茶を飲むという体験そのものをどうデザインするか。そういう方向に向かうと思うんですね。だからこそ、茶をつくっている丸若さんが幻幻庵をやるし、茶筒をつくっている開化堂がKaikado Cafeをやる。昔はあまりなかったことかもしれないけど、この先はそれが当たり前になっていくと思う。茶や茶筒をつくるなら、それがどう使われてどんな体験をもたらすかまで、しっかりプロデュースしたいと考える作り手が増えるし、お客さんもそれを望むようになる。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
稲葉ほたて×宇野常寛 『パズドラ』をプレイしていたのは誰なのか?――ソーシャルゲームの歴史と運営思想(PLANETSアーカイブス)
2019-10-18 07:00
今朝のPLANETSアーカイブスは、大ヒットアプリゲーム『パズル&ドラゴンズ』を巡る、稲葉ほたてさんと宇野常寛の対談です。GREE・DeNAというソーシャルゲーム2強の牙城を崩すべく、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが繰り出したこのゲームから、ゼロ年代以降のゲーム史の流れを議論します。(構成:稲葉ほたて 初出:「月刊サイゾー」2014年2月号) ※本記事は2014年2月24日に配信された記事の再配信です。
宇野 僕が『パズル&ドラゴンズ』をやったのは実質1カ月くらいなんだけど、やっている時期は結構ハマったんだよね。自分の周囲でもやっている同年代が多かった。
パズドラで一番意外だったのは、ゲーム自体がソーシャルではなかったことなんだよね。使っている人間もソーシャル性を求めてというより、むしろリアルの人間関係まで含めた「ソーシャル疲れ」みたいな状態の人が、黙々と遊んでいた印象がある。
稲葉 僕も基本的には、サラリーマン時代に、会社帰りの電車で何も考えずに楽しめる娯楽としてやってましたね。ネットでゲリラダンジョンの時間割【1】が公開されてたので、間に合うように退社を早めたりして(笑)。
パズドラに限ったことではないですが、ソーシャルゲームはガラケービジネスの隙間時間を奪い合う文化の中で、発展してきたものです。基本は暇つぶしなので、ソーシャル性なんて本質的には要らないんですよね。「ひとりでできる暇つぶしこそ最強」ですよ。
宇野 少し大きい話をすると、いまはコンテンツが2極化していて、1年に一度のAKB48総選挙とか4年に一度のワールドカップ、数年に一回の宮崎駿の大作みたいな祝祭的な大花火か、リアルタイムで小刻みに更新されていくものという2つになってる。人間が生理的なところで求めている娯楽はこの二通りでしかないということが、社会の情報化によって明らかになってきた。そのうちのひとつの究極の流れがソーシャルゲームなんじゃないかと思う。
ソーシャルゲームについて語るときって結局、お金の問題の文脈でしか見られていない。でも僕はソーシャルゲームのようなものが流行ってるっていうのは、「ゲームとは何か」「遊びとは何か」という問いを突きつけてる気がする。
2010年頃に「PLANETS」VOL.7【2】で話したことなんだけど、「結局、ゲームはネットに負けた」と。人間にとって一番面白いゲームとは、LINEみたいに知り合いとダラダラ話したり、ツイッターみたいに不特定多数と戯れることなのではないか。予定調和の安心感としても乱数供給源としても、そちらのほうが優れている。そうして、せいぜいバグと戯れるのが限界だったゲームから訴求力が決定的に落ちた。その後にそこで勝ったのも、『ポケットモンスター』や『モンスターハンター』のような、社会のネットワーク性を逆手に取って、自分たちの作りたいゲームに活かしたアクロバティックな作品だけだった。その流れがケータイ機に移っていったというのが、近年のゲームの歴史だと思う。
この流れにソーシャルゲームもあるんだけど、もともとこの手のゲームって、プラットフォームに人を置いておくために始まった経緯があるじゃない?【3】 ゲームのためにネットワーク環境を利用する、つまりコンテンツのためにコミュニケーションを利用するのではなくて、むしろコミュニティを維持するため、コミュニケーションのためにゲームを利用するというふうに逆転していた。
そういう時期が何年かあった後で、『パズドラ』みたいなソーシャル性の弱いものが出てきた。その背景には、以前ほどSNSが単純な暇つぶしの娯楽じゃなくなってきてることがあると思う。不特定多数のネットワーク上のコミュニケーションは面白いけど、実はこれって結構アクティブな行為なんだよ。人間はスイッチがオフに近い状態だと「見知らぬ相手との出会い」なんでウザくて、頭を使わずにひとりでできるシンプルなゲームのほうがいいと思う。
稲葉 少し歴史を整理しつつ話すと、確かに、09年の夏頃には『サンシャイン牧場』【4】のような、コミュニケーション要素の強い、農園系ゲームの存在感は大きかったんですよ。一方で、宇野さんが指摘されたようなSNSの活性化という当初の狙いはすぐに置き去りにされたんじゃないでしょうか。『ドリランド』のおかげで、毎日GREEで日記を更新するようになった人って、そんなにいない気がする(笑)。そもそも、SNSを活性化してもせいぜいmixi程度の収益ですが、ゲームのアイテム課金のそれは桁違いです。
実際、『サンシャイン牧場』が流行っていたその年の秋には、米国のZyngaの『マフィアウォーズ』【5】にインスパイアされて、DeNAが『怪盗ロワイヤル』【6】を出してます。これで「ロワイヤル系」の波が来る。一応、互いにバトルを仕掛け合うもののコミュニケーション要素は希薄で、ソーシャル性は後退していました。さらに、翌年の秋口からは、GREEが「カード系」のゲームを本格展開してDeNAの業績を一気に追い上げていく。その象徴が、単に穴を掘って宝を集めるゲームだった『探検ドリランド』【7】の大リニューアルです。気がついたら、ビックリマンカードでバトルするような内容になっていた(笑)。こうした遊び方には、もちろん自分のカードを見せびらかして「俺TUEEEE」【8】をしたくなるような類いのソーシャル性はありますが、人間の収集欲に根差したデータベース消費の側面が大きい。
このカード系のソーシャルゲームは、巷間言われる海外のSNSゲームの文脈とは全くの別物です。これはどちらかというと、ハンゲーム【9】が牽引することで、日本で独自に高度な発展を遂げた、バーチャル世界のアバターに課金させるビジネスから流れてきたもの。一時期激しく問題視されたコンプガチャも、アバターサービス周りで発達してきた手法だと聞きます。
宇野 なるほど。ソーシャルゲームがゲーム批評の文脈で語られにくい理由のひとつとして、アバターサービスのようなところから発展していった歴史がある、と。つまり、いわゆるコンシューマーゲームの中心ユーザーだった20~30代男性カルチャーから切れた、もっと言えば文化というよりは風俗に近いところのサービスから始まっている。そこに後から、コンシューマーをやっていたソフトハウスが合流した。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
與那覇潤 平成史ーーぼくらの昨日の世界 第7回 コラージュの新世紀:2001-02(後編)
2019-10-17 07:00
今朝のメルマガは、與那覇潤さんの「平成史ーーぼくらの昨日の世界」の第7回の後編をお届けします。「9.11」で幕を開けた2000年代。政治・言論の領域では「歴史の失効」と「運動への回帰」が進行します。インターネットの大衆化と2ちゃんねるの隆盛にともない、変化する社会の力学。それを利用したのは、昭和期には非主流派だった「異形の父たち」でした。
崩壊するアソシエーション
2001年9月11日、イスラム原理主義のテロ組織がハイジャックした旅客機を世界貿易センター(ニューヨーク)とアメリカ国防総省(ワシントンDC)に激突させた事件は、日米関係においても大きな転機となりました。報復として翌月からアフガニスタン空爆に踏み切ったアメリカを、小泉政権は全面的に支持、後方支援のためのテロ対策特措法を一か月で成立させます。あえて軽薄にいうなら、目下の事態への対応という「イシュー・ドリヴン」なプロセスが、憲法に照らした際の整合性という原則論をすり抜けて進行してゆく。そこから2003年末、名目上は非戦闘地域に限ってのイラク戦争への自衛隊派遣までは一直線でした。
換言すると、それは「現在」の存在感が突出し、すでにやせ衰えていた「歴史」(連載第5回)の形骸化を確認する儀式だったとも言えます。大東亜戦争を肯定的にとらえ、欧米の植民地主義と戦った日本の戦争を評価せよと唱えてきた「保守論客」が、次々と親米路線(対テロ戦争支持)を表明して現状追認に転じる姿に失望し、2002年春に小林よしのり・西部邁の両氏が「つくる会」を去りました。運動体が掲げた「新しい歴史教科書」がじっさいのところ、反左翼・反戦後を示す記号にすぎず、そこで語られている物語を本気で生きている人はほぼいなかった[19]。平成後半の西部・小林は、戦後を否定し憲法改正を唱えながらも、目下の自民党政権による対米従属(とその現れとしての立憲主義の空洞化)を批判する、ややこしい反米保守の隘路へと入ってゆきます。
そして小林氏の『ゴー宣』とほぼ同時に始まり、左派かつ高等的な形で平成の新しい言論を担ってきた『批評空間』も(連載第2回)、対をなすかのように現実の政治情勢のなかで翻弄され、終焉を迎えてゆきました。きっかけは、中心人物だった柄谷行人が2000年6月末に立ち上げた社会運動NAM(New Associationist Movement)の失敗でしたが、物語論的には翌年頭の文芸誌での村上龍(作家)との対談で、同氏がこんな発言をしていることが目に留まります。
柄谷 台湾の候孝賢の『非情城市』〔1989年。日本公開翌年〕を見たときに、このひとははっきり主題をもっていて、この映画で台湾の運命を描いている〔のに……〕パンフレットみたいなのを見たら、蓮實重彦が、ここのアングルは小津の引用だとか、そういうことしか書いていないんですよ。村上 本当ですか。柄谷 監督はあきらかに、そのような主題なしにこの映画をつくらなかっただろう。〔……〕しかし、蓮實重彦は主題などを見るのは素人だ、俺はそんなバカではないという感じで書いていた。[20]
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
今夜20:00から生放送!飯田和敏×犬飼博士×高橋ミレイ×中川大地「『ドラクエウォーク』と位置情報ゲームの思想戦」2019.10.16/GAMES OF THE ROUND
2019-10-16 13:00
今夜から、新番組「ゲーム・オブ・ザ・ラウンド」がスタートします。話題の最新タイトルから懐かしの名作、xRやAIといったテクノロジーや社会的・学術的なトピックまで、あらゆる話題を縦横無尽に語り合う〈ゲーム円卓会議〉。『現代ゲーム全史』の評論家/PLANETS副編集長の中川大地を進行役に毎回豪華ゲストをお迎えしながら、ゲーム・カルチャーの真髄をえぐるクリティカル・トークを繰り広げていきます。記念すべき第1回のテーマは、『ドラゴンクエストウォーク』と位置情報ゲームの最新動向について。『テクテクテクテク』や『ハリー・ポッター:魔法同盟』なども含め、『ポケモンGO』以降の3年間で何が変わったのか?ゲームクリエイターの飯田和敏さん、運楽家/ゲーム監督の犬飼博士さん、ライター/モリカトロンAIラボ編集長の高橋ミレイさんとともに、各タイトルの“思想対決“の諸相に迫ります!▼放送日時2019年10月16日 -
與那覇潤 平成史ーーぼくらの昨日の世界 第7回 コラージュの新世紀:2001-02(前編)
2019-10-16 07:00
今朝のメルマガは、與那覇潤さんの「平成史ーーぼくらの昨日の世界」の第7回の前編をお届けします。2001年、小泉純一郎が内閣総理大臣に就任します。新自由主義の潮流に乗り、高い支持率を背景に構造改革、規制緩和を推し進めたその政策の伏線は、90年代にありました。
エキシビジョンだった改革
元号が替わったいま、遠からず各種の入試でも平成史から出題される事例が増えてゆくのでしょう。それは同時代が「過去」になることの徴候ですが、せっかくですので本連載でもひとつ、問題を出してみようと思います。
問い 以下のA・Bそれぞれについて、発言者である平成の政治家の名前と、いかなる状況での発言であったかを簡潔に答えよ。 【A】もちろん改革には痛みがともなう。痛みのない改革は存在しない。しかし、人はなぜ痛みを覚悟で手術台に横たわるのであろうか。生きて、より充実した明日を迎えるためである。明日のために今日の痛みに耐え、豊かな社会をつくり、それを子や孫たちに残したいと思うのである。 【B】いままでの自民党の党内手順というのは、調査会とか部会でまず全会一致で了承を得る、政審も全会一致、そして総務会も全会一致、これで初めて正式の党議となったわけです。しかし、今度の……にかぎっては、どこでも了承を得られていない。それを『これには××内閣の命運がかかっている』と言って無理やり国会に出そうとしている。
多くの方が連想するのはやはり、Aは平成13(2001)年4月に組閣し、5年半におよぶ長期政権をスタートさせた小泉純一郎首相。Bは2005年の郵政政局で、彼に自民党を追われた亀井静香氏あたりでしょうか。たしかに「……」に郵政民営化、「××」に小泉と入れれば、それでもとおります。
しかし正解は、Aは小沢一郎で、細川非自民政権への引き鉄を引く直前だった1993年5月に刊行され、ベストセラーとなった『日本改造計画』の末尾の一節[1]。むしろBが小泉純一郎で、「……」に入るのは小選挙区比例代表制、××はその小沢氏が(自民党幹事長時代に)担いでいた「海部〔俊樹〕内閣」です。1991年10月の『文藝春秋』誌上、田原総一朗さんの司会で小選挙区制導入の可否を論じる座談会での発言でした[2]。このとき反対で歩調を合わせたのが、YKKと呼ばれた加藤紘一・山崎拓(ともに、のち自民党幹事長)。逆に推進派を代表したのは、小沢の盟友でやがてともに新生党を創る羽田孜でした。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
今夜20:00から生放送!南章行×宇野常寛「人生100年時代のサバイバル仕事術」2019.10.15/PLANETS the BLUEPRINT
2019-10-15 07:30今夜20時から生放送!「PLANETS the BLUEPRINT」では、 毎回ゲストをお招きして、1つのイシューについて複合的な角度から議論し、 未来の青写真を一緒に作り上げていきます。 今回のゲストは、株式会社ココナラ代表取締役社長・南章行さんです。
自分のスキルを売り買いできるサイト「ココナラ」や、NPO法人「二枚目の名刺」など、
個人の自立・自律や副業をサポートする活動を実践されている南さん。ご自身の新著『好きなことしか本気になれない。
人生100年時代のサバイバル仕事術』と合わせて、
現代を生きる私たちの仕事術を考えます。
▼放送日時2019年10月15日(火)20時〜☆☆放送URLはこちら☆☆https://live.nicovideo.jp/watch/lv322006467▼出演者南章行(株式会社ココナラ代表取締役社長) 宇野常寛(評論家・批評誌「PLANETS」編集長)フ -
【特別寄稿】成馬零一 2019年の「現実 対 虚構」ーー史実の暴力に、どう向き合うべきか?(中編)
2019-10-15 07:00
今朝のメルマガは、成馬零一さんによる寄稿の中編です。溶解する現実と虚構を素材とした映像作品は、海外からも次々と登場していますが、そこには歴史改変につながる危うい欲望が見え隠れしています。タランティーノ、スパイク・リー、フィンチャーの最新作から、虚構と作家性の関係について掘り下げます。 ※本記事の前編はこちら
クエンティン・タランティーノの最新作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(以下、『ワンス』)は1969年のハリウッドを舞台にした映画だ。 テレビの西部劇スターだった落ち目の俳優リック・ダルトン(レオナルド・ディカプリオ)と、リックの親友で専属スタントマンのクリフ・ブース(ブラッド・ピット)、リックの家の隣に引っ越してきた、映画監督・ロマン・ポランスキー(ラファル・ザビエルチャ)の妻で若手女優のシャロン・テート(マーゴット・ロビー)。カメラはこの三人の姿を交互に追っていく。 俳優として行き詰まり、酒に溺れながらも西部劇ドラマの撮影に挑むリック。リックが撮影している合間にフラフラしていると、ヒッピーの少女に連れられてマンソン・ファミリーのコミュニーンに足を踏み入れてしまうクリフ。そして、自分が出演した映画『サイレンサー第4弾/破壊部隊』を鑑賞するシャロン。 三人の姿を描いた後、物語は半年後の1969年8月9日へと飛ぶ。イタリアの西部劇(マカロニ・ウエスタン)に出演したリックはイタリアで成功を収めた後、イタリアで結婚した妻を連れて帰国。契約を解消するクリフと最後の晩餐を過ごしていた。一方、シャロン・テートはポランスキーの子を妊娠していた……。
▲『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』
本作は1969年のハリウッドを、落ち目の西部劇俳優の視点から描いたノスタルジックな映画だ。劇中では当時の風景やファッションや車が忠実に再現されており、ブルース・リー(マイク・モー)、シャロン・テート、ロマン・ポランスキーといった実在する映画監督や俳優が登場する。主人公の二人、リックとクリフは架空の人物だが、モデルとなった人物は複数いるようで、タランティーノの映画に出演したある老俳優が専属スタントマンと共に行動する姿を見て、二人の関係に魅力を感じたことがきっかけだったという。 劇中でかかるラジオ番組も実際に流れていたものらしく、本作の魅力は1969年のハリウッドを忠実に再現した箱庭的な楽しさだと言える。その意味で『全裸監督』にも通じる実話をもとにした偉人伝系の作品だが、そこはタランティーノらしい虚実の入り混じった巧妙な仕掛けが施されている。
引用と編集と暴力
90年代に『レザボア・ドックス』や『パルプ・フィクション』といった作品で注目されたタランティーノの作風は「引用(サンプリング)と編集(リミックス)と暴力(バイオレンス)」だ。 ビデオショップの店員だったという出自が伝説化しているタランティーノは、過去の映画や音楽、あるいはジョン・トラボルタのような過去に活躍した俳優を自由自在に引用して、物語の時系列を巧みに組み替えることで、どこにでもありそうで、どこにもなかった物語を作り上げた。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
稲葉ほたて「彼女たち」のボーカロイド――"初音ミクの物語"からは見えない世界(PLANETSアーカイブス)
2019-10-11 07:00
今朝のPLANETSアーカイブスは、ライター・編集者の稲葉ほたてさんによるボーカロイド文化論です。ネットのアングラ文化の一つとして登場したはずが、いつの間にかガールズカルチャーの最先端になってしまったボーカロイド。その市場とそれを巡る言説のねじれについて論じます。(初出:文化時評アーカイブス2013-2014) ※本記事は2014年5月29日に配信された記事の再配信です。
■日本文化の象徴になった初音ミク
ボーカロイド、中でもとりわけ初音ミクは現在、単にネット上の創作文化にとどまらない、現代日本の文化におけるイコンになっている。特に10年代に入ってから、初音ミク関連のビジネスやグッズ展開は著しい。かつてはテレビにミクが登場するだけで事件になっていた時代があったことが、懐かしくさえ思えるほどだ。
たとえば、ボーカロイド関連のニュースを毎日紹介している「初音ミクニュース」【注1】を見てみよう。毎日のようにボカロ関連の新製品やイベントが登場していることがわかるはずだ。その内容も、もはやフィギュアやCDなどのオタク関連商品にとどまらない。昨年で言えば、少女マンガ誌「りぼん」(集英社)にボカロとコラボした付録が挟まれ、前年のearth music & ecologyにつづいてMILKのようなガールズブランドもボカロとコラボしている。一方で、ボカロPや歌い手出身の歌手がアニメのテーマに抜擢されるのも、もはや珍しくない。近年は“ぐるたみん”や“りぶ”、伊東歌詞太郎などのような多くの人気の歌い手が商業進出を果たし、オリコンでも好調な成績を上げた。音楽業界における歌い手への注目は、ある意味でボカロP以上に高まる一方である。
こんなふうにボカロ関連が商業とのコラボを華々しく展開していく状況は2007年、初音ミクの登場したあの夏【注2】から人々が見てきた夢が、まさに実現した状況といえる。
何らのフィクショナルな物語に裏付けられていないバーチャルなキャラクターが、あたかも身体を持つ我々のごとき実在感を獲得して、市場やマスメディアで氾濫する。それはさまざまな人々の無数の創作やつぶやきの膨大な記憶を背負った「集合知」そのもののキャラクターであった。しかも、その過程でメディアに評価されずに来た数々の才能が表に出ていって活躍を始めていったーーそんな物語の全てがたかだか数年で実現したのだから、これは現代における痛快事と言ってよいだろう。ゼロ年代の参加型キャラクター文化は、ここにおいて一つの達成を見たとさえ言えるのではないだろうか。
しかし一方で、2012年頃からだろうか。「ボカロの熱気が終わった」という声が、現場の空気をよく知る人々の間でささやかれ続けている。【注3】
こうした問題に、決定的な形で定量的な回答を出すのは極めて難しい。新規投稿数はともかく、動画の総再生数や市場規模で言えばボカロは拡大の一途だからである。だが、10年代に入っての商業化が、2007年に始まった初音ミクを象徴としたボカロの物語に「上がり」の空気をつくりあげたのは、このシーンを追いかけてきた多くの人の体感ではないだろうか。
そうした状況の中で、ついに2013年はハイカルチャー側からの接近も始まった。渋谷慶一郎のような現代音楽の作り手が初音ミクでオペラ(『THE END』)を上演したり、六本木ヒルズの森美術館での「LOVE展」に、初音ミクが展示されるということもあった(そこで皇后陛下が「これが、ミクちゃんですか」と口にするという「珍事」もあった)。
ボカロ文化の商業的隆盛とハイソな人々からの接近が進行する一方で、足下でボカロ離れは着実に進行している――そんなふうに祝祭的な時間の「終焉」「衰退」を物語る声は、いまさまざまな場所でぽつぽつと上がり始めている。
だが、その「物語」というのは、果たして「誰の」物語なのだろうか。
■「彼女たち」のボーカロイド
一昨年の冬、筆者はボカロ小説について、mothy_悪ノP氏に取材したことがある。ボカロ小説というのは、人気のボーカロイド楽曲の歌詞を小説化【注4】したもので、近年驚異的な売上をあげているジャンルである。mothy_悪ノP氏は、自身の楽曲『悪ノ娘』の小説化によって、このブームの端緒を切り拓いた人物であった。この取材中、とても印象的だったのが、彼とその編集者が「いざ出版してみたら、読者は中高生の女子だった」という話をしていたことだ。当時(2010年)はまだ、ニコニコ動画は主に大学生以上の男性オタクのサイトというイメージが強く、ボカロもまたそのイメージで捉えられていた。そもそも数々の歌い手がステージに上がったドワンゴの「ニコニコ大会議」ツアーで、会場に多くの女子中高生が詰めかけていることが話題になったのが、やっとこの時期のことである。
この頃に顕在化したリスナーの低年齢化(と、女子)へのシフトが、実際にいつ頃から起きていたのかを特定するのは極めて難しい。だが、こうしたユーザーたちに話を聞いてみると、ryoの『メルト』などの比較的初期に投稿されていた楽曲の思い出が語られるのが興味深い。彼女たちの話を鑑みるに、実は極めて早い段階からボーカロイドには低年齢層のリスナーがついていたのではないかと筆者は考えている。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
10月31日(木)まで限定冊子つき・先行予約を受付開始!猪子寿之×宇野常寛『人類を前に進めたい チームラボと境界のない世界』
2019-10-10 19:30
チームラボ代表・猪子寿之氏と、評論家・宇野常寛との4年間に及ぶ対談が、ついに書籍化! 10月31日(木)まで限定で、冊子つき・先行予約を受付中です。
▼書籍紹介 チームラボはなぜ「境界のない世界」を目指し続けるのかーー?
2015年からの4年間、チームラボ代表の猪子寿之氏は、評論家・宇野常寛を聞き手に、展覧会や作品のコンセプト、その制作背景を語り続けてきました。
ニューヨーク、シリコンバレー、パリ、シンガポール、上海、九州、お台場……。共に多くの地を訪れた二人の対話を通じて、アートコレクティブ・チームラボの軌跡を追う1冊。 さらに、猪子氏による解説「チームラボのアートはこうして生まれた」も収録!
【目次】 CHAPTER1 「作品の境界」をなくしたい CHAPTER2 デジタルの力で「自然」と呼応したい CHAPTER3 〈アート〉の価値を更新したい CHAPTER4 「身体」の境界を -
今夜20:00から生放送!竹下隆一郎×宇野常寛「あいちトリエンナーレから何を持ち帰るか」2019.10.10/PLANETS the BLUEPRINT
2019-10-10 07:30今夜20時から生放送!「PLANETS the BLUEPRINT」では、 毎回ゲストをお招きして、1つのイシューについて複合的な角度から議論し、 未来の青写真を一緒に作り上げていきます。 今回のゲストは、ハフポスト日本版 編集長・竹下隆一郎さんです。2019年9月26日、文化庁は「あいちトリエンナーレ2019」への補助金の全額不交付を決定。対して主催者側は10月8日より「表現の不自由展・その後」を含む全作品の展示を再開し、大きな議論を巻き起こしています。実際に現地の様子を体感してきた竹下さんのホットなレポートを踏まえ、「あいちトリエンナーレ2019」を取り巻く一連の問題について、いまわたしたちが考えるべきことを話し合います。▼放送日時2019年10月10日(木)20時〜☆☆放送URLはこちら☆☆https://live.nicovideo.jp/watch/lv322244681▼出演者