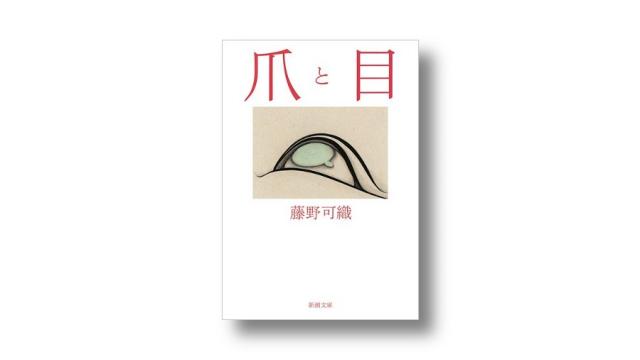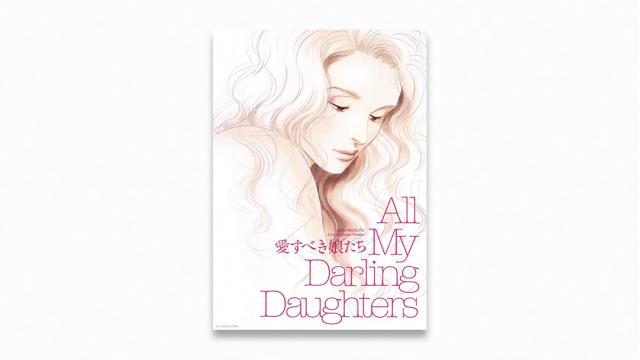-
藤野可織――自覚する娘|三宅香帆
2022-09-26 07:00
今朝のメルマガは、書評家の三宅香帆さんによる連載「母と娘の物語」をお届けします。東日本大震災の後、2012年以降に増え始めた「母娘」の対立を描いた諸作品。「父と息子」のように単純な構図では捉えきれない関係を象徴する作品として、藤野可織の『爪と目』を考察します。
三宅香帆 母と娘の物語第十一章 藤野可織――自覚する娘|三宅香帆
1.年齢を重ねてからも続く
前章では、東日本大震災以後の2012年に『ポイズン・ママ 母・小川真由美との40年戦争』(小川雅代、文藝春秋)、『母がしんどい』(田房永子、KADOKAWA/中経出版)の二冊が出版されたことがきっかけで、「毒母」という言葉が流行し、母娘問題が注目されるようになったことを扱った。平成の文学作品について文芸評論家の斎藤美奈子と高橋源一郎が対談した『この30年の小説、ぜんぶ 読んでしゃべって社会が見えた』(高橋源一郎・斎藤美奈子、2021年、河出書房新社)においては、2012年に注目すべき文芸作品の変化についても以下のように指摘されている。
斎藤 母なんですよ、3冊とも。『東京プリズン』『母の遺産』、芥川賞の『冥土めぐり』。どれも虐待する母とその母に抗う娘というか、母親によって抑圧された娘の話で、もっとザックリ言うと母殺しなんですよね。これまで近代文学はずっと父殺しをやってきたわけだけれども、今年はここにきて急に母殺しという。 高橋 そう、しかも、全部書いてるの女性だしね。女の子の母殺しですよね。 斎藤 そうなの、母と娘なんですよ。父と息子という構図がずうっと続いてきたわけですけど、なぜか今年は母と娘の葛藤の話が重なった。 高橋 だから父と息子の話なんかないんだよねえ。 斎藤 そうですね。もう父と息子はね――。 高橋 終わったの?(笑)。 斎藤 終わったでしょ(笑)。 高橋 ほんとにそう思いました。だって男性の書いてる小説もあるけど、父と息子の話なんか出てこない。っていうか父いないし(笑)。 斎藤 かつては近代の父が立ちはだかってたわけじゃないですか。特に文学をやろうなんていう人はさ、父は絶対に反対するもんね(笑)。けど、母と娘の対立は近代文学の誕生から150年たってやっとテーマになったって感じがする。 (『この30年の小説、ぜんぶ 読んでしゃべって社会が見えた』p89-90)
『冥土めぐり』(鹿島田真希)が芥川賞を受賞した2012年、同年に『東京プリズン』(赤坂真理)、『母の遺産 新聞小説』(水村美苗)という母娘関係をテーマにした小説が続けて刊行されていた。エッセイやノンフィクション作品のみならず、小説においても「母娘の主題」が注目された年だったのである。2022年現在においては文芸誌『文藝』の2022年春季号で特集「母の娘」が組まれるなど、小説のテーマとして珍しいものではない。が、当時は斎藤が「やっとテーマになった」と述べるなど、新鮮な主題として受け取られていたことが分かる。 高橋は「父と息子の場合だったら、ある程度わかりやすい対決がある」と述べる。母を奪い合ったり、何かを得ようとする同士で対立が図られる。だからこそ「それを得ようとしない」という手で逃げることも可能である。だが、母と娘のほうは「逃げちゃえばいいじゃんと思うんだけどさ、そうはいかないんだよね」と語る。斎藤も「そこが母娘の難しさ」と頷く。
斎藤 そう、共依存みたいになってるとこがある。父の要求って「おまえは出世しろ」とか「家を継げ」とかさ、シンプルでしょ。でも、母から娘への要求は複雑。ここに出てくる母は一応みんな近代人ですが、がんばって勉強しろって言ったかというと「早く結婚しろ」と言ったりする。矛盾するふたつの要求の中で娘は混乱するっていうのがまず基本で、さらに母はみんなお金持ちの娘だったりするので、強権的なんだけど、お嬢さんみたいなところがあって、庇護しないとダメっていう。そのへんが面倒くさい。受けた教育の差も反映している。 高橋 どうなんだろうね、母には、ある程度自分のことも投影されてるのかな。つまりさ、父と子の場合には他者であると同時に自分を投影している部分があるけど、母娘の場合、今の自分は若い頃の母親、あるいは母は何十年後かの自分みたいな、そういう感じはあるんですか。 斎藤 さあ、関係はあるんでしょうけど、もっと現実的で切実な問題が大きいと思う。この3冊についても言えることですけど、40~50代になって初めて、母娘問題に目がいくんですよ。介護問題とかが浮上するからです。今までこういう小説が少なかったのは、若い頃は女性が書く小説って、女性の自立や男との葛藤とかのほうがずっと大きな関心事だったからだと思うのね。20世紀はそっちが重要だったわけですし。それが少子高齢化社会になって母との葛藤が始まる。父と子の葛藤はもっと若いわけじゃない。 (『この30年の小説、ぜんぶ 読んでしゃべって社会が見えた』P91-92、太字と傍線は筆者が付した。)
たしかに傍線部の斎藤の指摘の通り、小説に限らず、母娘問題をテーマとした作品は、30歳を超えている作者が書いていることが少なくない。前述した母娘のエッセイ『ポイズン・ママ 母・小川真由美との40年戦争』『母がしんどい』もまた同様である。本連載で扱ってきた『イグアナの娘』(萩尾望都)や『シズコさん』(佐野洋子)もまた、作者がキャリアを積み年齢を重ねた時期の作品である。 一方で父と息子の対立は、フロイトの言葉を参照するまでもなく、息子が大人になる通過儀礼――つまり思春期から青年期にかけての葛藤として描かれることが多い。父殺しの物語として著名である『スター・ウォーズ』シリーズや『海辺のカフカ』(村上春樹)の主人公はやはり、少年あるいは青年期までの年齢である。 娘にとって母の支配から逃れることは、どうやら思春期のテーマというよりも、もっと年齢を重ねた時期に重視される問題なのではないか。そこが父と息子との違いのひとつであることは確かだろう。 しかし一方で、斎藤が引用した対談においての太字部分で述べる通り、「出世と結婚、矛盾するふたつの要求の中で娘は混乱する」ことが母と娘の葛藤の本質であるならば、それは青年期までのテーマではないのだろうか。もちろん年齢を重ねてもなお出世や結婚を望まれることはあるだろうが、前述した作品たちは30歳を超えた作者によって、どちらかというと青年期以後のテーマとして描かれているのだ。そこに斎藤の述べるような「矛盾するふたつの要求にこたえること」以上の葛藤があるからこそ、父と息子のような若い時代に終わらない対立となっているのではないだろうか。 斎藤自身は、それについて「40~50代になって初めて、母娘問題に目がいくんですよ。介護問題とかが浮上するから」と説明している。が、挙げられた『冥土めぐり』を読んでも分かる通り、どちらかというと「若いころから年齢を重ねてなおずっと続く母の支配」というテーマが描かれており、年齢を重ねて突然浮上した、という形とも言い切れないのである。つまり斎藤の述べるような中年期に初めて目がいったというよりも、思春期や青年期から、そして中年期になってなお残っている、という言い方のほうがより実情に近いのではないか。そして2012年に出版されたエッセイや小説は、前章で語った通り東日本大震災等を通して、その問題を一気に取り上げ始めたのだろう。
高佐一慈『乗るつもりのなかった高速道路に乗って』PLANETS公式ストアで【オンラインイベントのアーカイブ動画&ポストカード】の特典付で販売中!
-
川上未映子――保守化する娘(後編)|三宅香帆
2022-08-12 07:00
今朝のメルマガは、書評家の三宅香帆さんによる連載「母と娘の物語」をお届けします。今回取り上げるのは川上未映子の作品です。母を愛し、自らも母となる「保守化」した娘が諸作品で描かれていた1990年代。一転して川上未映子が2008年に描いた『乳と卵』には、母を愛しながらも、「母性」の暴力性に自覚的であるがゆえに葛藤する娘の姿がありました。(前編はこちら)
三宅香帆 母と娘の物語第十章 川上未映子――保守化する娘(後編)|三宅香帆
3.母性の暴力性―『乳と卵』
2008年、信田・斎藤の著作出版とともに『シズコさん』が佐野洋子の手によって出版された。これは本連載冒頭でも見た通り、「母に愛されない娘の話」ではなく、「母を愛せない娘の話」だった。佐野は戦前生まれの女性なので、むしろ彼女の世代にあってはじめて、母娘問題の口火を切れたのかもしれない。 しかし同時に、2008年、団塊ジュニア世代の作家である川上未映子が『乳と卵』で芥川賞を受賞していた。まさしく母性と母娘の関係をテーマとした小説だった。 娘を産んだことで減った胸を気にして豊胸手術を受けたいと言う母・巻子と、彼女に連れられて大阪にやってきた娘・緑子の関係性が、巻子の妹・わたし(夏子)の目線から描かれる。
あたしな、かわいいなあ、思ってさ、ときどきちゅうしたりするねんよ、寝てる緑子に、と箸の先をひらひらさせながらわたしに向かって云った。すると巻子がそれを云った瞬間に、緑子の顔の色と硬さがぎゅんと変化してそれからものすごい目で真正面から巻子を睨んだ。わたしはそれを見て、あ、と思いつつ言葉が出ず、その目は緑子の顔の中でますます強く大きくなるよう、それを見た巻子は、一瞬顔をこわばらせて、なにやの、と小さく静かに云って、なにやのその目、と巻子は静かに続け、あんたいったい、なにゃの。 緑子は目をそらして、それからメニューが掛かってある壁のあたりを見つめ、しばらくしてから、小ノートに〈気持ちわるい〉と書き、それをテーブルのうえに開いて見せて、ペンで〈気持ちわるい〉の下に何度も何度も線を引いた。 (川上未映子『乳と卵』2008年、文藝春秋)
緑子をかわいがろうとする母に対し、緑子ははっきりと嫌悪を向ける。「気持ちわるい」という言葉は、愛情が重たく感じられるという意味にもとれるし、母性の愛情そのものを拒否しようとする姿にも見える。緑子は生理が来ることや胸を大きくなることに嫌悪感を抱く娘であり、自らの母性を否定する娘である。同時に、母の母性も拒否しようとする。 このような娘のあり方――母の愛情を拒否しようとする娘の姿――は、2000年代前半には見られなかった描き方だった。 しかし緑子は、母のことを拒否したままでは終わらなかった。緑子にとって母はやはり「大事」な存在なのである。
あたしを生んで胸がなくなってもうたなら、しゃあないでしょう、それをなんで、お母さんは痛い思いしてまでそれを、(中略) あたしは、お母さんが、心配やけど、わからへん、し、ゆわれへん、し、あたしはお母さんが大事、でもお母さんみたいになりたくない、そうじゃない、早くお金とか、と息を飲んで、あたしかって、あげたい、そやかってあたしはこわい、色んなことがわからへん、目がいたい、目がくるしい、目がずっとくるしいくるしい、目がいたいねんお母さん、厭、厭、おおきなるんは厭なことや、でも、おおきならな、あかんのや、くるしい、くるしい、こんなんは、生まれてこなんだら、よかったんとちやうんか、みんな生まれてこやんかったら何もないねんから、何もないねんから、と泣き叫びながら今度は両手で玉子をつかんでそれを同時に叩きつけた。 (『乳と卵』)
高佐一慈『乗るつもりのなかった高速道路に乗って』
PLANETS公式ストアで【オンラインイベント&ポストカード付】の特典付で販売中!
-
川上未映子――保守化する娘(前編)|三宅香帆
2022-08-08 07:00
今朝のメルマガは、書評家の三宅香帆さんによる連載「母と娘の物語」をお届けします。団塊ジュニア世代の漫画家の多くが「母殺しの困難」「重みとなる母」を描いていたのに対して、1990年代には素直に母を愛し、自らも母性を獲得していく娘が諸作品でみられるようになりました。そうした娘の「保守化」が生じた1990年代の作品史をたどります。
三宅香帆 母と娘の物語第十章 川上未映子――保守化する娘(前編)|三宅香帆
1.保守化する娘―団塊ジュニア世代の娘たち
本連載でも冒頭から見てきたように、信田さよ子が母娘問題について提起した『母が重くてたまらない──墓守娘の嘆き』(春秋社)、斎藤環が『母は娘の人生を支配する──なぜ「母殺し」は難しいのか』(NHK出版)を出版し、母娘問題が注目を浴びたのが2008年。同年『ユリイカ』(青土社)でも「母と娘」特集が組まれた。この現象について、信田と齊藤の対談において二人は以下のように語っている。
斎藤:「母の重さ」について、僕自身は本を書いたときも今もさっぱりわかりません。ただ、当時30代の女性編集者が「母娘関係について書いてほしい」と熱心に依頼してきて。 信田:私の本もまったく同じ。30代後半の女性編集者から「母親との関係で苦しむ女性たちをテーマに執筆してほしい」と。彼女自身も母の存在に苦しみ、その思いが依頼につながったのです。「団塊母」が「教育熱心」という形で娘を支配し、その期待に応え高学歴を経てメディアで仕事をするようになった娘たちが、一斉に声を上げ始めた。それが「母が重い」というムーブメントに火をつけたと見ています。 (「信田さよ子×斎藤環 根深い「母娘問題」に共存の道はあるのか?」『AERA dot.』2018/2/5掲載 https://dot.asahi.com/aera/2018020200049.html?page=1)
当時2008年段階で30代半ばだったと仮定すると、1970年代前半生まれのいわゆる「団塊ジュニア」世代が、大人になったからこそやっと声を上げられたのではないか、と信田は述べる。 第七章以降で扱ってきたよしながふみ、小花美穂、芦原妃奈子、高屋奈月は、1970年代前半生まれのちょうど団塊ジュニアと呼べる世代の漫画家である。彼女たちは1990年代後半から2000年代前半、すでに「母と娘」がテーマのひとつとなる漫画をヒットさせていた。それらの漫画に熱狂した少女たちは、精神科医たちが分析を綴る前に、少女漫画というフィクションの中で母娘問題に触れていたのである。 しかしよしなが、小花、芦原、高屋の描いた母娘像とは、「母から離れない娘」の在り方だった。つまりはどの作品も、娘が母を好きなのである。精神的な母娘の密着。そのような在り方こそが、団塊ジュニアの漫画家たちが描いた母娘像であった。 これは萩尾望都、山岸凉子といった団塊の世代の漫画家たちが描いた「母が弱いからこそ支配されてしまう」在り方とは異なる。萩尾や山岸の描く母娘密着においては、娘が母を嫌悪するさまが描かれていた。たとえば『イグアナの娘』において娘のリカは自分を呪ってくる母を嫌悪し、家から離れた(第一章参照)。あるいは『日出処の天子』において厩戸王子は母の性を嫌悪した(第二章参照)。 一方『愛すべき娘たち』においてまさに団塊ジュニア世代の雪子は、母の麻里とともに暮らし、そして「ずっとあたしだけのお母さんだったのよ」と呟く。『こどものおもちゃ』の紗南は、自らを育てた血の繋がっていない母も、自らを捨てた血の繋がっている母も、どちらのことも受け入れる。『フルーツバスケット』は亡くなった母を慕う主人公が描かれる。さらに『砂時計』においては自分を置いて自殺した母に対して、母と同じ道を辿ろうとする娘が描かれた。娘の杏は、作中において基本的に母を好きなことは疑わず、「自分が愛されていたかどうか」に論点を置くのである(第九章参照)。 こうして並べると、団塊ジュニア世代の漫画家の描く娘たちは「自分が母を愛していること」にはほとんど疑いを入れず、「自分が母に愛されているかどうか」に注目していることが分かる。これは団塊世代の描く、母を嫌悪していた娘とは真逆のあり方である。さらに氷室冴子、松浦理英子といった1950年代後半生まれ世代の、母を受け入れるか迷っている描き方ともまた異なる。 つまりそれ以前の世代に比べて、団塊ジュニア世代の娘たちのほうが、母を好きなことを疑わない「娘の保守化」が見られるのだ。 信田さよ子や齋藤環は2008年当時、娘の「母が重い」という感情について『イグアナの娘』(萩尾望都、1992年)や『光抱く友よ』(高樹のぶ子、1984年)といったフィクションを援用して解説するが、これらは基本的に娘が保守化する前の、母に嫌悪感を示せていた世代の物語だったことは否めない。
高佐一慈『乗るつもりのなかった高速道路に乗って』
PLANETS公式ストアで【オンラインイベント&ポストカード付】の特典付で販売中!
-
芦原妃奈子――なぞる娘|三宅香帆
2022-06-28 07:00
今朝のメルマガは、書評家の三宅香帆さんによる連載「母と娘の物語」をお届けします。今回取り上げるのは芦原妃奈子の作品。少女漫画における母による娘の支配と、その克服はどのように描かれていたのかを考察します。
※7月から、リニューアル準備のためメールマガジンの配信日を「月曜日と金曜日」に変更とさせていただきます。今後とも各媒体での記事・動画の配信や書籍刊行を含め、さらなるコンテンツの充実に務めてまいりますので、引きつづきPLANETSをよろしくお願いいたします。
三宅香帆 母と娘の物語第九章 芦原妃奈子――なぞる娘|三宅香帆
はじめに―芦原作品のテーマ
芦原妃奈子の作品の主題は「少女の成熟」である。少女はどうしたら大人になることができるのか。その主題をさまざまな角度から描いているのが作風となっている。たとえば『砂時計』においては母の呪いを解くこと、『Piece』においては父の呪いを解くこと、『Bread & Butter』においては家族をつくることによって、少女の成熟は達成される。芦原作品において、少女が大人になるためには家族という通過儀礼を通らなければならなかった。 特に母親という主題について切り込む『砂時計』の連載が開始されたのが、2003年。よしながふみの『愛すべき娘たち』の刊行と同年のことだった。2000年代前半のほぼ同時期に、両作家によって母との絆を断ち切る物語が描かれているのは注目すべき事象だろう。 本章では芦原作品にみる母娘像から、2000年代に描かれた母娘の主題を読み解きたい。
1.『砂時計』の母娘像
『砂時計』は母の自死から始まる物語である。 主人公の杏は、12歳のとき母の離婚をきっかけに島根の田舎へ引っ越してきた。最初は厳しい祖母や田舎の空気に馴染めなかった杏だが、同い年の大悟、藤、藤の妹・椎香と出会い、仲良くなってゆく。そしてとくに大悟との仲を深めてゆくが、ある日突然母親が自殺してしまう。 大悟は杏を支え続けると言い、ふたりは一緒に成長することを誓う。しかし杏が父に引き取られ東京に引っ越すことになり、ふたりの距離は離れることになる。 杏の母は、もともと精神的に不安定なところがあった。とくに東京で鬱病になり、アルコール依存症にもなっていたという。故郷に帰ってからも、過労で倒れ、精神的にもさらに疲れ切ってしまう。娘の存在を見て自分を奮起させようともするが、母親に「情けない、しゃんとせえ」と言われたことをきっかけに、発作的に自殺してしまう。 杏の祖母は、母について以下のように杏に伝える。
「…昔っから 弱い子だったけん 気ばっか強いくせに どっかもろくて だから心配で ずっと手元においておきたかったんよう…私が殺した…! 言っちゃいけんのわかっとって はがゆくて…! “がんばれ”て…!」 (『砂時計』1巻)
杏は祖母の発言を「おばあちゃんのせいじゃない」と否定するが、祖母の罪悪感は杏にうつることになる。杏は過去に母親へ「がんばれ」と言ってしまった経緯もあり、「ママはきっと最初からこうするつもりだったんだ この村に戻ると決めた日から きっと」「あたしはとめられなかった」と思うようになる。 『砂時計』において、杏は母の死をトラウマとして何度も反芻するが、中でもとくに顕著なのが、杏は母の死に対して罪悪感を持つ点である。たとえば偶然出会ったシングルマザーが「この子たちは私の希望だわ」と言うのに対し、杏は「あたしは母の希望になれなかった」と発言する。母の死を止められなかったという罪悪感から、杏は母の存在に囚われ続けて生きることになるのである。 そんな杏に対して、幼馴染であり恋人である大悟は何度も支えようとするが、うまくいかずに二人は別れてしまう……というストーリーが『砂時計』の概要となっている。
2.『砂時計』と『成熟と喪失』の主張の相似
実は『砂時計』のテーマは、1988年に出版された江藤淳の批評集『成熟と喪失 ―“母”の崩壊―』の主張と似通うところがある。 江藤は戦後文学を批評しながら、「今後、日本は前近代的な『母性』の庇護も失い、同時に欧米的で個人主義の規律である『父性』を得ることもできないままになるだろう」という主張を行う。女性は母性を引き受けることを拒否し、そのような母性に逃げ込む場も喪失される。かといって代わりに父性が台頭するわけでもないまま、子供は成熟できずにさまようのだろう、と。 『砂時計』のタイトルにもある「砂」のモチーフとは、杏たちの住んでいた島根県に砂丘があることに由来する。大悟は砂丘に足を踏み入れた時のことを以下のように話す。
「オレさ 昨日一人で行ったんだ 小雪がちらついてシーズン・オフで人もおらんで なんちゅーか 砂丘の真ん中に立ってるとすげー不安になるんだよ 目指す指針が何も見えなくて 自分がどこに立ってるのかもわからない 足元砂にさらわれておぼつかんし」 「答えが見えなくて 目的も見えなくて 本当にこっちに進んでいいんか道を間違ったんじゃねえかとか 焦って 迷って 結局どこにも行けなくて 訳もなく不安になって どつぼに陥って ああ こぎゃん状態の時ってあるよなって 杏は多分ずっとこぎゃん状態なんだろうなって 12の冬からずっと」 (『砂時計』7巻)
砂に足をとらわれ、どこに向かっていいかわからない。杏は母を喪失してから、ずっとそのような状態にある。かといって父が新たな指針になるわけでもなく、ただ砂丘をさまよっているのではないか、と大悟は言う。 これはまさしく江藤の主張する「母性が喪失された後の状態」そのものであった。 とくに杏の母が、思春期のころから前近代的な田舎からずっと出たがっており、しかし離婚を契機に田舎に帰ることになったことが自殺のトリガーだったことは注目すべき点である。杏の母にとって、田舎の閉鎖的で情緒的な、つまり前近代の日本的な空気がなによりも耐え難いものであった。しかし杏の母として、田舎で母親として生きることを選ばざるをえない。それは江藤の言う「女性が前近代的な母を引き受ける」ことそのものだった。 杏の母は、田舎で母の役割を担うことを拒否する。前述したように杏は「ママはきっと最初からこうするつもりだったんだ この村に戻ると決めた日から きっと」と述べており、まさしく江藤の言う拒否の構造を直感的に理解している。杏の母が拒否したのは、『成熟と喪失』で説明された「母性」そのものだった。 杏と母は距離の近しい母娘だった。母が自殺しに行く前日、出かける際に杏が「私も一緒に行っていい?」と言ったことが象徴的である。しかし母は杏が一緒に来ることを拒否する。そして杏は母を喪失することになる。 また江藤は母を喪失した子のことを以下のように表現する。
「母」の拒否は子のなかにかならず深い罪悪感を生まずにはおかない。つまり自分が「母」にあたいしない「悪」の要素を持っているからこそ、「母」は自分を拒んだと思うのである。 (『成熟と喪失』)
これもまた『成熟と喪失』の主張と『砂時計』が同じ話をしている点である。前述したように杏は母が自分の母であることを拒否し、自ら命を絶ったことに、自分に原因があると罪悪感を持ち続けていた。母の希望になれなかったことにずっと罪悪感を抱えているのである。『成熟と喪失』は俊介を、その罪悪感から「彼のなかにほとんど処罰されたい欲求がある」と評するが、『砂時計』の杏もまた母への罪悪感から自らの幸福を許さない傾向がある。 そして杏は、罪悪感を抱えたまま、母の人生をなぞることになる。母と同じように結婚相手を見つけるが、結局結婚は破談となり、杏は無意識に自殺を図る。妻となろうとし、しかしそれを拒否する、という母のルートをなぞるのである。これは江藤が日本の女性たちについて説明した「母になることの拒否」という行動を杏は母と同じく実行したのだ、という点も強調したい。
3.喪った母をなぞる「娘」と、その成熟
しかし『成熟と喪失』と『砂時計』のもっとも異なる点は、ほかでもない子の性別だ。
-
小花美穂・槇村さとる──憧れる娘(後編)|三宅香帆
2022-05-10 07:00
今朝のメルマガは、書評家の三宅香帆さんによる連載「母と娘の物語」をお届けします。1990年代の少女漫画に登場するようになった「自由な母親」は母娘関係にどんな変化を与えたのか。1994年に連載が始まった『イマジン』などの作品から考察します。
前編はこちら。
三宅香帆 母と娘の物語第八章 小花美穂・槇村さとる──憧れる娘(後編)
3.家父長制を境界にした母娘シスターフッドー『フルーツバスケット』
『こどものおもちゃ』において、紗南にとって実紗子は母というよりも、良きメンターのような役割を担う。つまり、母娘として自己投影や同化の欲求を抱くというよりも、母はあくまでアドバイザーであり監督者であるという距離を保つのである。そのため実紗子と紗南の関係は、母と娘というよりも、叔母と姪のシスターフッド的関係性に近しいような距離感となっている。実紗子と紗南はたしかに母娘関係ではあるのだが、どちらかというと、家父長制の内部に留まる娘と外部に飛び出した母のシスターフッドに見えてくるのだ。前編で論じた藤本論は「自由な母親像はシングルマザー家庭の物語に多い」と述べていたが、たしかに『こどものおもちゃ』以外にも、同じく1990年代に始まった『フルーツバスケット』(高屋奈月、白泉社)もまたシングルマザー家庭の自由な母親像が登場する。主人公透の母は、ヤンキー的キャラクターでありつつ、やはり透とは仲が良く、よきメンターのような存在であった。そして『フルーツバスケット』もまた、血縁ではない家庭的連帯を重視しながらも、最終的には結婚し子供を産むラストになっていることも『こどものおもちゃ』と共通している。透の母である今日子は、親と縁を切っていたり夫の実家から悪口を言われたりと、家を否定するキャラクターなのだが、娘である透はむしろ家庭に肯定的である……という点も同じである。 この「自由な母親」系譜について、前編で論じた藤本論は『明るい家庭のつくり方』等を挙げ、しっかり者の娘が破天荒な母の世話をする「逆転親子像」として整理していた。しかし1990年代の「自由な母親」系譜の物語を見てみると、どうやら自由な母は家父長制の外部に逃げ、しかし娘は家父長制の内部に留まって幸福を得るという、その双方の生き方を提示しなおかつ肯定するシスターフッド物語に見える。『こどものおもちゃ』も『フルーツバスケット』も、母と娘は決して呪いを掛け合ったり自己投影したりする存在として描かれていない。それは母と娘の問題を超えた、女性同士のユートピアのような家庭像なのではないか。つまり読者にとって、「子供を産めという呪いをかけてこない母親」こそが、幸せな恋愛をするとか居心地の良い繋がりをつくるとかいったことと同じくらい夢物語なのだろう。 時代はかなり下るが、2013年のディズニー制作『アナと雪の女王』もまた、この物語の系譜ではないかと考えられる。家父長制を境界線として、外部に逃げる母(姉)と、内部に留まる娘(妹)のシスターフッド。それはおそらく日本では1990年代に少女漫画で描かれていたテーマではなかっただろうか。 日本の少女漫画は、血縁のない家庭像や自由なひとり親像について身近に取り扱ってきた。たとえば『こどものおもちゃ』と同じ雑誌である「りぼん」においては、1992年から始まった『ママレード・ボーイ』(吉住渉、集英社)が「父母を入れ替えてW再婚する」という破天荒ともいえる父母像を描いていた。あるいは『Papa told me』(榛野なな恵、集英社)や『カードキャプターさくら』(CLAMP、講談社)において、シングルファザー家庭を理想的に描くこともあった。1990年代になって、本連載でも扱った『イグアナの娘』(萩尾望都、小学館)や『鬼子母神』(山岸凉子、小学館)といった母娘間にある苦悩が漫画の主題となる一方で、伝統的な価値観から外れた家庭をユートピアとして登場させる漫画も生まれていたのである。 日本の漫画で「自由な母親像」がシングルマザーとして描かれやすいのは、それが一度家父長制の外部に逃走している合図だったからなのだろう。夫の不在によって、従来的な「母」をまずは脱ぎ捨てることができる。それが少女漫画においてまず必要な記号だったのだろう。
4.理想のメンターとして登場する「母」―『イマジン』
『こどものおもちゃ』と同じ1994年に、槇村さとるは自由なシングルマザーを主人公格に置いた『イマジン』を連載開始した。『イマジン』は、OLとして働きつつ炊事洗濯を引き受ける娘の有羽と、建築家として破天荒に生きて家事はまったくしない母親の美津子の物語である。美津子は自分の欲望がはっきりしているキャラクターで、仕事も恋愛もアグレッシブに楽しんでいる。一方で有羽はまだ彼氏もいたことがなく、大人しく仕事と家事をまわす毎日。そして美津子はテレビディレクターの本能寺と、有羽は最近転勤してきた同僚の田中と、恋が始まってゆく。
-
小花美穂・槇村さとる──憧れる娘(前編)|三宅香帆
2022-05-02 07:00
今朝のメルマガは、書評家の三宅香帆さんによる連載「母と娘の物語」をお届けします。小花美穂・槇村さとるの作品から見出せる、少女漫画における「理想」の女性像の変遷とは? ユートピアとしての「家父長制の外部」をキーワードに、1994年に連載開始した『こどものおもちゃ』について分析します。
三宅香帆 母と娘の物語第八章 小花美穂・槇村さとる──憧れる娘(前編)
1.少女漫画の「自由な母」像が指差すもの
本連載では、これまで伝統的な家庭像のなかで描かれる母娘表象に注目し分析してきた。特に少女漫画の分野では、母に抑圧される娘の物語が繰り返し描かれてきたが、それは家父長制の伝統に則った母親の在り方ゆえのものであった。しかし一方で、少女漫画や女性漫画といったジャンルが、家父長制の要求に対抗するかのように、「自由な母親像」を求め続けてきたのも本当である。 少女漫画でしばしば描かれる、自由奔放な母親像。常識から外れていて、まったく親らしくなくて、時には主人公である娘のほうがハラハラしてしまうような母親像。このような描写について、藤本由香里は「この二作品に共通している「子どもっぽくて常識はずれな親と、しっかりして大人びた子ども」という組み合わせは、八〇年代後半から目立ってきたパターンである。そこでは、家事無能力の母親に代わって、娘がてきぱきとたち働いている。とくに明るい母子家庭にはこの描き方が圧倒的に多い」と説明する[1]。藤本はこの例として、『明るい家庭のつくり方』『新・明るい家庭のつくり方』(くぼた尚子)を挙げ、さらに『ミステリー・ママ』(森本梢子)、『したたかな女達』(秋本尚美)、父はいるが存在感が薄いパターンとして『フルーツ果汁100%』(岡野史佳)、『じゃりン子チエ』(はるき悦巳)を紹介する。またその源流として、一条ゆかりの描く母親像──例として『ママン・レーヌに首ったけ』──を参照する。一条は、少女のような母と15歳の息子の物語を描くことで、母の欲望をポップに描くことに成功した作家であった。 藤本論の注目すべき点は、「自由な母親像を描く舞台は、圧倒的に母子家庭が多い」という点である。シングルマザーであればこそ、家父長制の要求から外れた「自由」な母親を描くことができる。当時の漫画家たちがもしもそこに、従来の少女漫画が描くことのできていなかった「脱・母親」への道筋を見つけていたのだとしたら、それはおそらく母娘の関係を考察するうえでも重要な点になるだろう。 少女漫画が少女あるいは女性を主人公に据えることが多く、彼女たちは「いつか母になるのか・ならないのか」という問いを抱えることになる。もちろんそのような問いを持たずに生きることも可能だが、とくに藤本の著作が世に出た1990年代以前において、その問いから完全に自由であった女性は少ないと言ってもよいのではないだろうか。勿論、今もその状況はあまり変わっていないと筆者は感じる。だとすれば物語に登場する母親像は、自分の実際の母親を重ねる存在であると同時に、自分の未来の姿を重ねる存在でもあり得る。少女漫画で描かれる母娘関係は、母娘問題を映す鏡でありつつ、同時に娘にとって将来の姿を重ねるロールモデルとの葛藤の表象でもあるのだから。
-
よしながふみ──許されない娘|三宅香帆
2022-04-08 07:00
今朝のメルマガは、書評家の三宅香帆さんによる連載「母と娘の物語」をお届けします。今回取り上げるのは漫画家・よしながふみの短編連作集『愛すべき娘たち』です。謙虚であることを要請されてきた女性を描いた本作品は、時代とともに変化してきた女性への抑圧を描いていると読み解く三宅さん。2000年代初頭の、ポストフェミニズム思想の過渡期ともいえる時代性についても指摘します。
三宅香帆 母と娘の物語第七章 よしながふみ──許されない娘
1.傲慢をめぐる『愛すべき娘たち』
よしながふみによる短編連作集『愛すべき娘たち』は、傲慢を許されない、許さない女性たちの物語である。 母娘をテーマとした漫画というと、第一章で取り上げた『イグアナの娘』(萩尾望都)のほかに、『愛すべき娘たち』を思い浮かべる人も多いのではないだろうか。実際、本稿でも参照した斎藤環の『母は娘の人生を支配する なぜ「母殺し」は難しいのか』は、『イグアナの娘』と『愛すべき娘たち』を同時に取り上げている。『イグアナの娘』は短編漫画であり、『愛すべき娘たち』は短編連作集であるという違いはあるが、たしかに似たテーマを扱っていることは確かである。 とくに斎藤環が扱った『愛すべき娘たち』最終話は、外見のコンプレックスを母が娘に与える物語である。母が娘にコンプレックスを植えつける構図は『イグアナの娘』とほぼ同じと言ってよい。しかし一方で、『イグアナの娘』の母が抱えていたコンプレックスは、「自分は本当はイグアナであること」という、外見に限らない特性にあった。『愛すべき娘たち』の場合は、外見に特化しているのである。本章では、この外見というひとつの能力をめぐる母娘の葛藤を扱いたい。
2.なぜこれが母娘の物語なのか
群像劇ともいえる短編連作集『愛すべき娘たち』の中で、第一話と最終話に登場する母娘の物語がある。簡単にあらすじを説明する。 実家に住む三十代の独身女性である雪子は、突然母・麻里が再婚すると聞き、驚く。母の年齢は五十歳を過ぎており、しかも相手は雪子よりも年齢の低い男性だというのだ。しぶしぶ会ってみると、彼は俳優の卵でありながら、美しい容姿の元ホストだった。 彼は麻里に繰り返し「美人だよ」と説く。麻里はとても美しい女性なのだが、それを彼女自身は頑なに否定する人物なのである。母が否定することを厭わず、彼は繰り返し母に「美人だよ」と述べる。彼と母の関係を見た雪子は、実家を出て、彼氏と結婚することを決めるのだった。 そしてある日雪子は、母の容姿に対する頑なさの理由を知る。麻里は、彼女の母にいつも「不細工だ」と言われて育っていたのだ。
「おばあちゃんに大した悪気は無かったと思うわ 無神経な人だから自覚無しに人を傷付けるような事を平気で言うのよ」 「他人に言われたのならこんなに気にしてないわよ 身内の言う事特に親の言う事ってものは胸に突き刺さるものなんですよ …許せなかった」 (『愛すべき娘たち』p190-191)
宇野常寛 責任編集『モノノメ #2』PLANETS公式ストアで特典付販売中!『モノノメ 創刊号』+ 「『モノノメ #2』が100倍おもしろくなる全ページ解説集」付
-
角田光代──嫉妬される娘|三宅香帆
2022-03-07 07:00
今朝のメルマガは、書評家の三宅香帆さんによる連載「母と娘の物語」をお届けします。今回は小説家・角田光代の作品で描かれる母娘関係について考察します。母親から娘へ、または娘から母親へ注がれる同化の視線が交差して描かれる角田光代の小説『銀の夜』。各々の登場人物が持つ嫉妬の感情について考察します。
三宅香帆 母と娘の物語第六章 角田光代──嫉妬される娘
1.母と娘の嫉妬の関係
前章で母と娘の関係には、同化のまなざしがあることを指摘した。母から娘への独占や同化という欲望は、母息子の関係と比較すると社会的抑圧がない状態でおこなわれることが多い。とくに日本では、母息子となると「マザコン」などの言葉が社会的に広まっていたり、異性であることが壁となっているため、母側に欲望することの規制がかけられていると考えられる(母と息子の関係については次章で詳しく扱う)。そのため母から娘へ独占・同化というまなざしは抑圧の少ない状態で向けられ、娘がそれを「許す」ことによって支配が達成される、という構図になっている。自分と同じ存在であってほしい、あるはずである、という視線が母から娘には向けられる。前章では、母から娘への同化の視線が、他人の侵入を許さない独占欲(『最愛の子ども』)のような形で発露される様子を見た。 しかし同化の視線は、おそらく独占欲という形のみに出るわけではない。たとえば一章で扱った萩尾望都の『イグアナの娘』においては、自分がイグアナであるというコンプレックスを抑圧した母親が、娘にも同じコンプレックスを見出すことによって「イグアナ」という呪いをかける、という物語を見た。ここにはたしかに同化のまなざしの負の側面が存在する。つまり、母→娘の自分と同じ存在であるはずだというまなざしこそが、自分と同じコンプレックスを持つはずだという思い込みに転換しているのである。 それでは他にどのようなパターンがあるだろうか。角田光代は、『銀の夜』という小説において、母から娘へ向けられる嫉妬というかたちでそれを描く。 母は娘に嫉妬する。父は息子に嫉妬しないのに。 ──と言い切ってしまうと、おそらく反論が出てくるのだろうが、親子を描いた小説を読んでいるとその傾向はたしかに存在しているのではないだろうか。そう思えてならない。有名な物語を考えてみても、娘の美しさに嫉妬して鏡を割り、娘を殺そうとした白雪姫の継母の物語を知る人は多いだろう。なぜあのふたりは「母娘」という関係だったのだろうか。単に若さと美しさに女性間で嫉妬する物語というよりも、母娘の関係性の物語として伝承されるのはなぜなのだろうか。もちろんもはや使い古されたテンプレート的構図ではあるのだが、だからこそ、なぜそのようなテンプレートが存在するかは考えてみても良いのかもしれない。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
松浦理英子──同化する娘(後編)|三宅香帆
2022-02-04 07:00
今朝のメルマガは、書評家の三宅香帆さんによる連載「母と娘の物語」をお届けします。今回は松浦理英子の小説をめぐる考察の後編です。短編小説「肥満体恐怖症」は、肥満体質の母を病気で亡くした主人公・唯子が肥満体の同級生たちから持ち物を盗む話です。主人公を通して、母から娘だけでなく、娘から母への感情にも同性愛的な愛情が存在することを示唆していると指摘します。(前編はこちら)
三宅香帆 母と娘の物語第五章 松浦理英子──同化する娘(後編)
4.侵入を許す娘 ──「肥満体恐怖症」
作者の松浦理英子は「肥満体恐怖症」という短編小説において、母から娘だけでなく、娘から母への感情も、同性愛的関係と同じ場に配置する。 「肥満体恐怖症」は、肥満体の女性が嫌いな女子大生・唯子が主人公である。一緒の空間にいると、肥満が伝染しそうでぞっとするのだと言う。彼女が入った学生寮の同室には、三人の女性がいた。彼女たちは皆巨体であった。唯子は三人に嫌がらせをされるが、なぜかそれを受け入れてしまう。そしてある日から唯子は、三人の私物をそっと盗み始める。 唯子は、肥満体の女性を苦手とするが、肥満体の男性の存在はとくに気にならない。唯子の肥満体恐怖症の根底には、太っていた母親の存在が関係しているからである。 小学生の時、唯子は歳を重ねるにつれ母の体型を嫌悪していった。たとえば当時の日々を、唯子は「バスに乗った時に、一つ空席があると唯子を坐らせて自分は吊革に縋りついて喘いだりする姿は、苛立ちと苦痛を湧き起こさせ」たのだと振り返る。とくに母親と入浴するとき、その乳房を見ると吐き気を感じるのだった。いつの間にか母の体型に対して怨恨めいたものを感じるようになった唯子は、徐々に母親から離れ始め、無視しようとするようになる。
見るからに人が好さそうなせいか、他の父兄たちにおだて上げられ、危くPTAの役員をやらされそうになったことがあるらしい。それをまた無邪気に得意がって話す母親に向かって、とうとう唯子は言ってしまった。 「もう学校になんか来ないでよ。おかあさん太ってるんだもの。恥しくって。」 その時の母親の表情を思い出すと、今でも声を上げたくなる。言った瞬間後悔したがすでに遅く、母親は金縛りにでもあったかのように大きな体を硬直させた。いたたまれなくなった唯子が部屋を出ようとしても、顔を向けもしなかった。罪悪感で眠れぬ一晩が過ぎた。翌朝母親は平生と全く変わらず、唯子の失言も忘れたかのように見えた。しかし、その後母親は一度も授業参観にやって来なかった。乳ガンで死んだのは次の年の秋である。唯子は十歳だった。 (松浦理英子「肥満体恐怖症」『葬儀の日』所収、河出文庫p192-3、1993年(「肥満体恐怖症」発表は1980年)
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
松浦理英子──同化する娘(前編)|三宅香帆
2022-02-03 07:00
今朝のメルマガは、書評家の三宅香帆さんによる連載「母と娘の物語」をお届けします。同性であるがゆえに娘に強い同一化を求める母娘関係は、これまで様々なフィクションで描かれてきました。今回は小説家・松浦理英子の作品で描かれる母娘関係を手がかりに、同一化欲求を超えた「愛情」を望む母娘関係について、前後編で考察します。
三宅香帆 母と娘の物語第五章 松浦理英子──同化する娘(前編)
1.母娘と「ヘドロのような」同一化欲求
母と娘の関係と、父と息子の関係の何が最も異なるのか。 もちろんその答えはひとつに限らないし、これまで「母の弱さ」が注目されてきたことは本連載でも追いかけた通りである。しかしそれ以外の点で気になっているのが、フィクションにおいて母と娘を描く際に、同性愛的な描かれ方をすることがしばしばあるところである。 たとえば『ユリイカ』2008年12月号(特集:母と娘の物語 母/娘という呪い)で信田さよ子と上野千鶴子が現代の母娘像について対談する中で、信田が以下のような指摘をする。
信田 私はもっと同性愛的なものを感じるんです。 上野 それはちょっと言い過ぎかも。 信田 やっぱり同じ女として「好きだ」というか……。 (『ユリイカ』2008年12月号「スライム母と墓守娘 道なき道ゆく女たち」信田さよ子、上野千鶴子p83)
ある種の母親は娘に対し、思慕を抑圧しようとしない。垂れ流した、底なしの愛情を向けてしまう。あれは分身への自己愛でもなく、同性愛的なものではないか、と信田は述べる。 たしかにこの表現は上野の指摘通り「言い過ぎ」ではあると感じる。なぜなら同性愛にもさまざまな愛情の形があり、一概にこのような形が同性愛であるとは定義できない以上、母娘の関係を同性愛に近いと指すことはできないだろう。しかし同時に、フィクションで母娘の関係を描く際、同性愛に近いものとして描かれることがあること、そして似たような描き方が父息子においてはほとんど見られないことは、たしかに一考に値する。 引用した信田・上野の対談は、以下のように続く。
(引用者注:上野)たとえば息子だったら、あたりまえですけど息子としての達成しかできないわけです。ところが娘という「女の顔をした息子」たちは、息子としての達成+女としての成功という代理満足を同時に与えてくれるから、母である自分にとっては最高の作品でしょう。同一化という概念を使うのならば、これまでは子供の側から「同一化」と言ってきたわけですが、今度は母親の側から娘に対して同一化が起きるというほうが、同性愛と言うよりもわかりやすいと思います。同一化は、同一化する側の機制であって、される側には関係ない一方的なものですから。 信田 それを同一化と言ってしまうとちょっと明晰すぎる気がするんだよなあ。なんでわたしがそこに違和感を感じるかというと、彼女たちの意識自体が自覚的でないという部分においてそぐわない感じがあるからなんです。「同性愛的なもの」とわたしが言うときには、そうして自覚されてないが故に彼女たち自身もそれほど明晰に語り得ないものについて、そういう風に明晰に語ってしまっていいのかなという戸惑いがあるんですよ。被害者である娘側にとっては、明晰にすることに意味があるし明晰に語って欲しいと思っているから、そういう上野さん的な表現はぴったりくるんですけど、母の側には何とも言語化し難い、スライムのような、あるいはヘドロのような感じがあって、本当にああいう人たちをどういう風に言ったらいいのかわからないというところで、「同性愛的」というタームが浮かんだと。 (『ユリイカ』2008年12月号p83-84)
上野が指摘する、母にとっての「息子としての達成+女としての成功という代理満足」という枠組みは、まさに前回の氷室冴子が抱えていた葛藤そのものだった。女性の社会進出が進む中で、息子としての(仕事をして社会的成功を収める)自分と、娘としての(結婚して子を産み家庭で成功する)自分の双方が、娘に求められるようになる。氷室の場合は後者のみを母から求められる葛藤を主に描いていたが、多くの「働く娘」がこの両軸を求められる物語は枚挙に暇がない。 しかし信田は、それだけではないのではないか、と述べる。母にとって娘は作品であるというだけでなく、母にとって娘は同性愛的な思慕がある場合があるのではないか、と。 たしかに上野の述べる「作品としての娘」という構図は、母が専業主婦で、子どもを自分の家事育児の結果として見る時代だったからこそ成り立つ図式かもしれない。母にとって子が自分の成績通知表ならば、たしかに子は母の作品だろう。一方で、母が子を通して評価されたいと思っていなくても、母が子を手放せないと感じる場合もある。 今回解説する松浦理英子の『最愛の子ども』は、信田の指摘にも通じるような、母娘関係を同性愛的関係の中に入れ込んだ小説である。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
1 / 2
次へ>