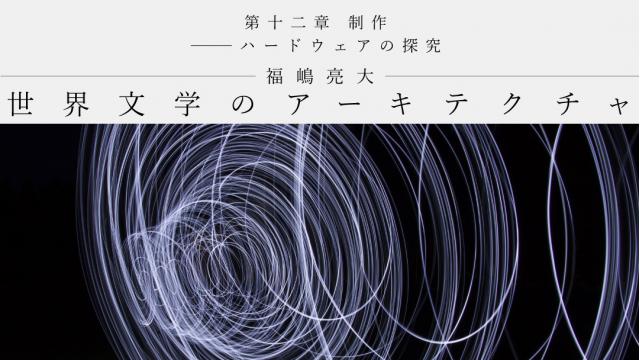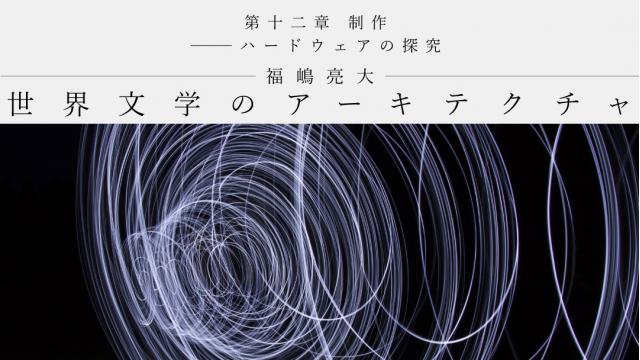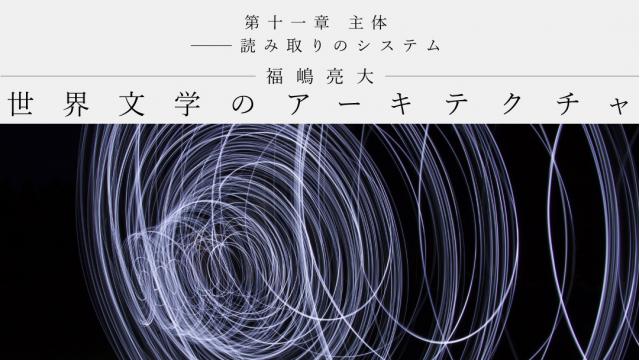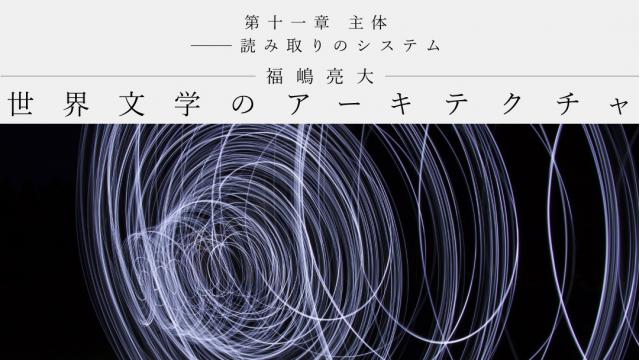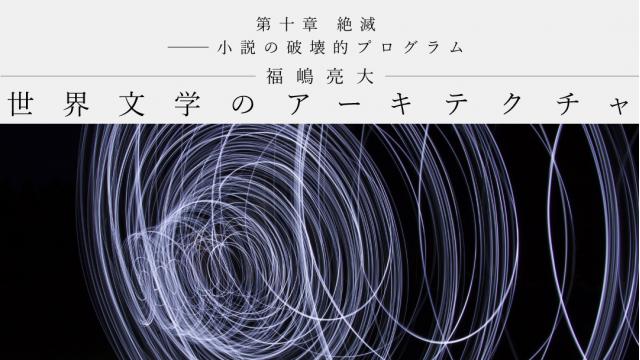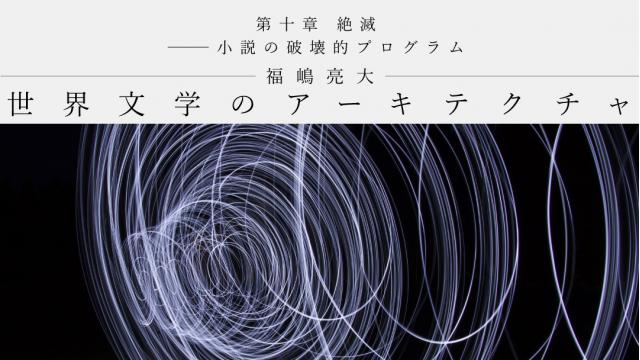-
世界文学のアーキテクチャ 終章 時間――ニヒリズムを超えて|福嶋亮大
2024-08-27 21:00
1、近代小説に随伴するニヒリズム
一八八〇年代に書かれた遺稿のなかで、ニーチェは「ニヒリズムが戸口に立っている。このすべての訪客のうちでもっとも不気味な客は、どこからわれわれのところへ来たのであろうか」と書き記した。ニーチェによれば「神が死んだ」後、人間の基準になるのはもはや人間だけである。しかし、神の死によって生じたのは、神のみならずあらゆる価値を崩落させ、意味の探究をことごとく幻滅に導く「不気味」な傾向であった。ニヒリズムとはこの「無意味さの支配」を指している。
ハイデッガーの解釈によれば、ニーチェの哲学において「意味」は「価値」や「目的」とほぼ等しい。つまり、意味は「何のために」とか「何ゆえに」という問いと不可分である。意味を抹消するニヒリズムが支配的になるとき、世界の「目的」や「存在」や「真理」のような諸価値もすべて抜き取られる。ニーチェが示すのは「諸価値を容れる《位置》そのものが消滅」したということである。われわれは世界に価値や意味を嵌め込んできたが、今やそれを進んで抜き取っている――このようなニヒリズムの浸透は、世界に「無価値の相」を与える[1]。目的をもたなくなった世界で、人間は確かに価値の重荷から解放されるが、それは幸福を約束しない。
ここで文学史を回顧すれば、すでにニーチェ以前に「ニヒリズムという不気味な客」の来訪する予兆があったことが分かる。宗教が世界に意味や価値を嵌め込んだのに対して、デフォーの『ペスト』やスウィフトの『ガリヴァー旅行記』を筆頭とする一八世紀の近代小説は、意味の探究を超えた不確実性に傾いてきた。小説は安定した意味のシステムを自らくり抜き、一種の「壺」として自らを造形したが(前章参照)、特に絶滅やジェノサイドへのオブセッションは、小説という壺に底なしの空虚をうがち続けてきた。小説にとって、ニヒリズムは不意の来客というよりも、むしろ長期にわたって共生してきた伴侶なのである。
そう考えると、ニヒリズムがニーチェに先立って、まずロシア文学において結晶化したことも不思議ではない。ツルゲーネフは一八六二年の『父と子』で若き医師で唯物論者のバザーロフをニヒリストとして描き、この概念を広く普及させた(第十章参照)。宗教的な救済のヴィジョンを内包したロシア文学は、人生の意味の飽くなき希求によって、かえって世界の無意味さの深淵に足を踏み入れた。その後もロシア文学は、哲学とは異なるやり方で、ニヒリズムに応対したように思える。その興味深い例として、一八六〇年生まれのアントン・チェーホフを取り上げよう。
2、二〇世紀最初の文学――チェーホフの『三人姉妹』
生粋の一九世紀思想家ニーチェは一九〇〇年に亡くなるが、その翌年の二〇世紀最初の月すなわち一九〇一年一月に、チェーホフの戯曲『三人姉妹』がモスクワ芸術座で初演された(以下、チェーホフの作品の引用は松下裕訳[ちくま文庫版全集]に拠り、巻数と頁数を記す)。その第二幕に、雪の降る日に父をなくした三人姉妹の一人マーシャが、正教徒の軍人トゥーゼンバッハとやりとりをする場面がある。もう一人の軍人ヴェルシーニンが、未来の新しい幸福な生活のために働くべきだと言うのに対して、トゥーゼンバッハは百万年後にも生活の法則は変わらないと断言する。マーシャは、世界を無意味と見なす彼の態度に懸念を示す。
マーシャ それでも意味は?
トゥーゼンバッハ 意味ねえ……。こうして雪が降っていますがね。どんな意味があります?
(間)
マーシャ わたしはこういう気がするの。人間は信仰を持たなくてはいけない、すくなくとも信仰を求めなくてはいけない、でなければ生活はむなしくなる、むなしくなる、って……。生きていながら知らないなんて、なんのために鶴が飛ぶのか、子どもたちが生まれるのか、空に星があるのか……。なんのために生きているのか知らねばならないし、さもないと何もかもがつまらない、取るにたらないものになってしまうわ。
(間)
ヴェルシーニン それにしても残念でたまらない。青春の過ぎ去ったのが……。(第二巻、二四七‐八頁)
トゥーゼンバッハはここで、生の意味を否定するニヒリストのように振る舞う。雪が降るように、人間が生まれ死ぬだけなのだとしたら、人生に意味や目的を求めるのは無益だろう。ここで思い出されるのは「雨の降るごとく死が降る」と記した哲学者のドゥルーズである。ドゥルーズはたんに雨が降るという「非人称的」な出来事を人間的な意味づけに優先させたが[2]、トゥーゼンバッハの考え方はそれに近い。
逆に、マーシャは世界に意味や目的がなければ、人間の生が取るにたらないものになることを恐れている。ただし、このマーシャの発言は誰かに賛同されたり反論されたりするわけではない。ひとしきりの「間」があってから、話題は別の方面に移り変わる。トゥーゼンバッハもマーシャも、この件で口角泡を飛ばして議論しないし、自説に固執もしない。彼らの思想は、ティータイムの前の退屈しのぎとして語られるにすぎない。
ツルゲーネフの『父と子』における若い男性知識人たちの熱っぽい会話とは対照的に、およそ四〇年後の『三人姉妹』では、意味と無意味に関する問いは、空白やためらい、退屈や倦怠の気分のなかに控えめに浮かんでいる。すでに青春を過ぎた彼らの口調は、決然とした強さをもたない。彼らは他者を声高に説得しようとする意志を欠いたまま、会話の「間」に滑り込んで、つぶやくようにして自らの考えを語る。
この慎ましさにおいて、チェーホフは明らかに反ドストエフスキーないしポスト・ドストエフスキーの作家である。ドストエフスキーの登場人物は、経験的にはふつうの人間と何ら変わらないが、その存在には「形而上学的な次元」が随伴している。ドストエフスキーを特徴づけるのは、経験的なレベルと形而上学的なレベルの「神秘的な一体化」である[3]。逆に、チェーホフは生と思想をむしろ乖離させる。自己の思想を論文や文学を動員してまで述べようとするラスコーリニコフやイワン・カラマーゾフのような熱意を、チェーホフ的人間は初めからもちあわせていない[4]。
二〇世紀最初の文学である『三人姉妹』が「意味」の問題を提示したこと、これは非常に示唆的である。ただ、チェーホフの独自性は、人生の意味ないし無意味というテーマを、ニーチェやドゥルーズのような「哲学」としてではなく、人間の頭上を鳥のように通過するあいまいな思念や気がかりとして示したことにあった。トゥーゼンバッハに言わせれば「渡り鳥、たとえば鶴などは、ただひたすら飛んで行くだけで、高遠な思想やちっぽけな思いが頭のなかに浮かんだとしても、飛んで行きながら、やっぱりなぜ、どこへ飛んで行くかを知りはしない」(第二巻、二四七頁)。彼にとっては、いかなる思想も人間の頭脳には根づかない。チェーホフ的人間は、思想の所有者ではなく、思想の一時的な止まり木なのだ。
アメリカの哲学者コーネル・ウェストは、チェーホフの文学の根幹に「世界との不一致」があり、それが彼の喜劇性の源泉になっていると指摘した。「彼は最も洗練された知性的なやり方で、知性の失敗と不十分さについて語る」[5]。『三人姉妹』の人間たちは、彼らにとって価値あるものが過ぎ去った時点にたたずんでいる。このuntimelyな――反時代的で時機を失した――チェーホフ的人間たちは、世界に対して遅れてやってくる。思想と生とが乖離してしまう、このチェーホフ的な「不一致」の情景においては、世界は有意味とも無意味とも断定されない。ニヒリズムは文字通り「客」であり、人間の生に定住はできない。
-
世界文学のアーキテクチャ 第一四章 不確実性――小説的思考の核心|福嶋亮大
2024-08-27 21:00
1、不確実性を思考する
本連載もそろそろ終わりに近づいている。私はここまで、世界文学の中心を占める小説を、広義の人類学的対象として捉えてきた。人類の諸文化がそれぞれ世界理解の型をもつように、小説もいわば特異な人工知能として、世界を思考し、解釈し、再構成する力をもつ。人類と小説はドン・キホーテとロシナンテのように、異質な隣人として共生関係を結んだ。人間は小説を利用して、世界を了解し直す。その一方、小説は人間の利用を利用して、その流通の版図をグローバルに拡大してきたのである。
小説とは、隣人である読者=人間の心を巻き込みながら、思考を引き延ばす装置である。それは人間の心そのものではないが、人間の心の諸機能(知覚、想像、情動、想起、予測……)を擬態する能力をもつ。私は小説を、人間の心の動きを言語的なレベルに翻訳した《心のシミュラークル》と考えたい。この心の似姿は、ときにかえって本物の心以上に複雑怪奇な多面体として現れるだろう。心と言語を結合させた小説が、ウイルスのように流行し、人間の思考の不可欠の隣人になったのは、それ自体が人類学的現象として注目に値する。
心のシミュラークルとしての小説の流行は、ヨーロッパ近代において、思考の意義が更新されたこととも関わる。その指標として、思考そのものを思考した一七世紀のパスカルの『パンセ』を挙げておこう。
パスカルは「人間の尊厳のすべては、考えのなかにある。だが、この考えとはいったい何だろう。それはなんと愚かなものだろう」と記した。彼によれば、思考は人間の尊厳の根拠になるほどには偉大であり、それでいて非常に愚かで卑しいものである。思考は確実なものや堅固なものは何一つ与えない。ゆえに、人間が多くの不確実なもの、具体的には「航海」や「戦争」に賭けるのは当然である。「人が明日のため、そして不確実なことのために働くとき、人は理にかなって行動しているのである」[1]。デカルトが懐疑の果てに、思考しつつある我(コギト)という根源にたどり着いたのに対して、パスカルは存在の根源にいわば「賭け続ける我」を発見した。
もとより、パスカル自身は小説家ではないが、彼の洞察はその後の小説の時代の予兆になっている――近代小説の歴史はまさに航海と戦争という「賭け」によって導かれたのだから。思考はもはや確実な地盤に到る技術ではなく、不確実性の海における賭けの連続に等しいのではないかというパスカル的な問いに、小説というジャンルは新たな活力を与えた。小説とは、さまざまな不確実性を織り込んで思考し続けるための装置なのである。
では、小説という特異な思考装置は、いかなる進化史をたどって構成されたのか。それが私の取り組んできた問いである。この問題にアプローチするにあたって、私は文学史をさまざまな角度からリプレイし、得られた結果を多層的に重ね書きするようにして記述してきた。この作業を世紀の区切りを基準として、もう一度実行しておきたい。
2、《場を超える場》としての海――ダンテからメルヴィルへ
一四世紀のダンテの『神曲』地獄篇第二六章で語られるオデュッセウス(ユリシーズ)の物語は、強い印象を与える。「この世界を知り尽くしたい」という知の欲望に駆り立てられたギリシアの英雄オデュッセウスは、家族を捨てて仲間たちと禁断の航海に出るが、地中海をめぐり、スペインやモロッコを横目にジブラルタル海峡を越えようとしたとき、神意によって船を転覆させられる。「やがて私たちの上には海がまたもと通り海面を閉ざした」[2]。不確実性への賭け=航海は、神の力によって封印されたのである。
西に向かう「狂気の疾走」を強制終了され、神の禁止を破った罪によって地獄の火で焼かれるダンテ版のオデュッセウス――その苛酷な姿は、不吉とされた西方にあえて旅立ったコロンブス以降のヨーロッパ人の存在様式を、見事に先取りしている。ダンテはここで、未来の探検の時代を明晰に「予言」しつつ、峻厳に「拒否」したのだ[3]。のみならず、『神曲』のオデュッセウスは後の文学上の冒険者たち、特に『白鯨』のエイハブ船長の先駆けにもなった。ボルヘスが指摘したように、両者はともに「刻苦と豪胆さによってわが身の破滅を招く」のであり、その最期の言葉まで似通っているのだから[4]。
ただ、『神曲』の場合、世界=海への欲望は、地獄・煉獄・天国から成る三位一体の神学的構造のなかに拘禁された。ダンテは〈世界〉への欲望を予告しつつ、それを厳しく断罪した。オデュッセウスの船が沈められ、海が閉ざされたとき、世界もまた閉ざされたのだ[5]。
逆に、およそ五〇〇年後の一九世紀の『白鯨』になると、海=世界はもはやこのようなリジッドな構造に収容されず、むしろ不確実性に満ちた不定形の時空として現れる(第六章参照)。海をワープするように移動する鯨の出現は、確率的に推測するしかない。鯨を追跡するエイハブは、オデュッセウスのように特定の場(地獄)に束縛されず、船員たちもろとも《場を超える場》、つまり脱領土化された海に没入してゆく。『白鯨』には土台を失った〈世界〉における、ほとんど愚かしいとも言える賭けの連続が記録されている。不確実性を思考するメルヴィルは、尊厳と愚かさが「賭け」において両立するというパスカル的問題を、小説の核心に据えたのである。
3、〈世界〉に響くダイモンの声――ラブレーと海
ここで、ダンテとメルヴィルのあいだに一六世紀のフランソワ・ラブレーを挿入してみよう。ラブレーの奇想天外な小説『ガルガンチュアとパンタグリュエル』の「第四の書」(一五五二年)では、巨人族のパンタグリュエル一行が神託を求めて航海に出る。彼らは後のガリヴァーのようにさまざまな部族の住む国を巡り、その奇妙で珍しい習慣や暮らしぶりを記しながら、当時の反動的な教会や医者に対して、強烈な批判を浴びせてゆく。
この文化人類学的な探検は断片的なエピソードの連続であり、『神曲』のような厳格な構造をもたない。大船団を組織したパンタグリュエルらは「出エジプト」の詩編の朗誦に見送られ、暴風雨にさらされながら未知の島に気安く上陸し続けては、ときに巨大な鯨を退治し、ときに派手な戦争も引き起こす。この聖書のパロディのような多産多死の航海は、陽気であり、しかも危険に満ちている。パンタグリュエルの考察によれば、航海者は「死にながら生きており、生きながらも死んでいる」[6]。ラブレーの海は生にも死にも属さない別の人間、オルタナティヴな人間を浮上させる。そして、この生と死のあいだを放浪する航海の終わりに、パンタグリュエルの心に突然謎めいた声が響く。
「ううん、なにやら」と、パンタグリュエルがいった。「急に、後ろから引っぱられるような気持ちがしてきたぞ。〈この場所に上陸するなかれ〉と命じる声が、遠くから聞こえてくるような気がするのだ。心のなかで、そのような気持ちの揺れを感じるたびに、わたしは、こうやって引き止められた方向に進むのをあきらめて、その場所を立ち去ったことを、それでよかったのだと思ったし、あるいは反対に、わが心が勧めた方向に従って進んでいった場合もあるけれど、それもまた、それでよかったと思っているのだ」
パンタグリュエルは祝祭的な船旅の終わりになって〈この場所に上陸するなかれ〉という禁止の声を耳打ちされる。興味深いことに、彼の部下は、この不思議な声を「ソクラテスのダイモン」として説明する[7]。プラトンの『ソクラテスの弁明』によれば、ダイモンはソクラテスが間違いを犯しそうになったとき、それに「反対」する神霊の声として現れた。この不可視の霊的な声は、ソクラテスに「何をすべきか」は一切教えず、その代わり「何をしてはならないか」を告げたのである。
『神曲』のオデュッセウスを束縛した神の厳格な禁止とは違って、「ソクラテスのダイモン」の唐突な声は、内的であり謎めいている。だが「その行為は間違っているから引き返せ」という内なる否定の力は、パンタグリュエルの旅の性質を劇的に変える。この宣告に従うようにして、世界を陽気に航海してきたパンタグリュエルの物語は、慌ただしく閉じられる。そのとき、快活な探検の旅は終わり、進むべきとも退くべきとも決められない根源的なあいまいさが立ち現れてくる。
世界進出に反対する「ソクラテスのダイモン」の声をきっかけとして、パンタグリュエルの心に未知の揺らぎや迷いが生じること――この奇妙な展開は、ラブレーとほぼ同年に生まれたラス・カサスが、新世界の悪を批判したことを思わせる。ラス・カサスはヨーロッパの言論空間に「その行為は間違っているから引き返せ」というダイモンの声を、キリストの霊とともに響かせたと言えるだろう。この見地から言えば、陽気なパンタグリュエルをあいまいな心境に導くダイモンの声は、新大陸でのジェノサイドを引き起こした黒い歴史への応答ではなかったか。
この内的な禁止の声を振り切るには、ときに常人離れした異常な意志が要求される。現に、ダンテ版のオデュッセウスの狂気を引き継いだ『白鯨』のエイハブは、慎重さを求めるスターバックの声を無視して、決然と海に乗り出した。裏返せば、狂気の力なしには、自己はただちにあいまいさや不確実性に呑み込まれてしまう。それが〈世界〉との接触の帰結である。
一四世紀のダンテは神学的な構造のなかで、不確実な〈世界〉への誘惑を断ち切った。しかし、ポスト神学時代になると、〈世界〉は「ソクラテスのダイモン」のような不可解な力、禁止を発する超自我の声を呼び覚ます。小説は確かに人間を中心にするが、その人間は自己とは別の力によってあらかじめ規定されてもいるのだ。私は先ほど、小説を「さまざまな不確実性を織り込んで思考し続けるための装置」と呼んだが、その思考は人間を超えた霊的な声に先行されている。
-
第十三章 人間――悪・可塑性・人種|福嶋亮大(後編)
2024-05-28 07:00
6、可塑性を利用する芸術家――オーウェルの『一九八四年』
架空の全体主義国家オセアニアを舞台とする『一九八四年』では、戦時下の党を率いるビッグ・ブラザーが、テレスクリーンを用いて社会の全体をくまなく監視している。真理省記録局に勤務するウィンストン・スミスは、過去の文書の改竄に従事しているが、やがて魅力的な女性ジュリアと出会ったことをきっかけに党の禁を破る。彼女との性的関係だけが、この息苦しい社会での唯一の避難所となるのだ。しかし、それは本人があらかじめ予想していたように、破局を迎える。逮捕されたウィンストンは、オブライエンの狡猾な拷問によって、心から党への愛を誓う人間に作り変えられてゆく。
もとより、このような常時監視システムにどれほどリアリティがあるかは、検討の余地がある。例えば、アンソニー・バージェスはオーウェルを批評した『一九八五年』のなかで、アメリカがベトナム戦争を遂行しながら、同時にそれを娯楽的なテレビ番組として国民に消費させたことを皮肉っぽく指摘し、オーウェルの社会像の限界を言い当てている[16]。実際、物質的窮乏を国民に強いる架空のオセアニアと異なり、戦後の現実の先進国は、むしろ豊かさや娯楽を統治の手段とした。この点に限っては、同じイギリス人作家オルダス・ハックスリーの『すばらしき新世界』(一九三二年)の描いた管理社会――人間を生物的次元で巧妙にコントロールする快適なユートピア――のほうが、『一九八四年』よりも明らかに予見的であった。
ただ、『一九八四年』にはもう一つの重要なテーマがある。それは、思考および言語の可塑性に関わる問題である。オーウェルが描いたのは、人間を単一のイデオロギーに盲目的に従わせる単純なメカニズムではない。ウィンストンやオブライエンを含めて、オセアニアの人間たちは二重思考(doublethink)の実践者として描かれる。それは党の支配のもとでは民主主義はないと知りながら、党が民主主義の擁護者であると信じる思考様式である。嘘をつくことと信じることを、何ら矛盾なく両立させるアイロニーが浸透したとき、ひとびとは自ら進んで思考を柔軟に調整し、全体主義社会に適応するようになる。
オーウェルはこのアイロニカルな思考様式を、「ニュースピーク」と呼ばれる新しいタイプの人工言語と連携させた。言語が単純化されて、繊細なニュアンスを失えば、思考を社会にあわせて調整し、過去の出来事を都合よく訂正することも容易になるだろう。ウィンストンはまさにそのことに強い恐怖を覚えている。「もし党が過去に手を突っ込み、この出来事でもあの出来事でも、それは実際には起こっていないと言えるのだとしたら、それこそ、単なる拷問や死以上に恐ろしいことではなかろうか」(五五頁)。「歴史は止まってしまったんだ。果てしなく続く現在の他には何も存在しない。そしてその現在のなかでは党が常に正しいんだ」(二三九頁)。
こうして、思考も言語もまさにその柔軟な可塑性ゆえに、党への抵抗力を奪われる。ウィンストンを執拗に虐待するオブライエンは、この仕組みを正しく理解していた。彼の振る舞いは、ある意味ではきわめて洗練されている。かつてスペイン人の征服者が多数のインディオを「破壊」したとすれば、オブライエンは一人の人間のもつ多数の思考を入念に滅ぼした後、別の形態に作り変えるのだ。彼がウィンストンら囚人を閉じ込め、徹底的に洗脳する密室は、まるでゾラ的な実験室のグロテスクなヴァージョンのように見える。そして、このような思考の実験的なジェノサイドが可能なのは、オブライエンが人間の可塑性を熟知しているためである。
われわれが人生をすべてのレベルでコントロールしているのだよ、ウィンストン。君は人間性と呼ばれるような何かが存在し、それがわれわれのやることに憤慨して、われわれに敵対するだろうと思っている。だがわれわれが人間性を作っているのだ。人間というのは金属と同じで、打てばありとあらゆるかたちに変形できる。(四一七‐八頁)
哲学者のリチャード・ローティは『一九八四年』を分析するなかで、オブライエンに「オーウェルの青年時代におけるイギリス知識人の典型的な特徴のすべて」が与えられていると見なし、そこにオーウェルの世代の知的アイドルであったジョージ・バーナード・ショーの面影を認めている。洗練された知識人オブライエンは、その美的な趣味と知的な能力を最大限に発揮して、犯罪者を矯正する卓越した拷問官になった。ローティによれば、オブライエンが知的でありつつ残酷であることは、何ら不思議なことではない。なぜなら「知的な天分――知性、判断力、他への関心、想像力、美への趣味――は性的な本能と同じように可塑的で柔軟なもの」であり「人間の手と同じように、多種多様な形をとりうる」からである[17]。そのことを最も明瞭に自覚していたのがオブライエンなのだ。
そもそも、『一九八四年』は最初から、人間の感情を可塑的なもの、つまり抽象的で無軌道なものとして描いていた。テレスクリーンから定期的に流れる「二分間憎悪」という奇妙なイベント――「人民の敵」とされるエマニュエル・ゴールドスタインへの糾弾が二分間続けられる――のもたらす群衆の熱狂のなかで、ウィンストンの怒りの感情の向かう先は「鉛管工の使うガスバーナーの炎のように」めまぐるしく転換する。
ウィンストンにしても、ある瞬間の怒りはゴールドスタインには少しも向かわず、それどころか、〈ビッグ・ブラザー〉や党や警察に向けられる。そして、そうしたときにはスクリーンに映っている孤独で皆の嘲笑の的である異端者、虚偽の世界における真実と正気の唯一の守護者へと気持ちが傾くのである。ところがその次には、あっという間にまわりの人間と同化し、ゴールドスタインについて言われていることはすべて真実だと思えてくる。そうした瞬間には、彼が密かに抱いている〈ビッグ・ブラザー〉への嫌悪感は敬愛の念へと変化し、〈ビッグ・ブラザー〉は恐れを知らぬ無敵の擁護者として辺りを睥睨する存在であり、アジア人の大群に立ちはだかる巌のように思えてくる。(二六頁)
ここには、ドストエフスキーの登場人物を思わせる二日酔い的な混乱がある。ウィンストンはオブライエンに拷問される前に、すでに変わりやすい感情に支配されていた。「二分間憎悪」においては、ただ感情の激しいアップダウンだけがあり、怒りの矛先は瞬時に切り替えられる――しかも、このアドレス変更はほとんど当人の自覚なしに生じるのだ。この場面は架空の全体主義社会の描写にとどまらず、現実の大衆社会の集合的感情を絵解きしたものにも思える。怒りは群衆の連帯を支える。しかし、それは短時間のイベントに回収され、その怒りの軌道も簡単に変わるのである。
われわれはここで、オーウェルが『ガリヴァー旅行記』についての優れた批評家であったことを思い出そう(第十章参照)。スウィフトが人間の可塑性を強調したように、オーウェルもアイロニカルな二重思考と単純化されたニュースピークという装置のなかで、人間性がいかに変わりやすいかを示した。オブライエンは自らの思考を一切傷つけることなく、きわめて繊細なやり方で党のイデオロギーに順応する。そして、彼はまさにその同じ技術を用いて、ウィンストンの思考を計画的に訂正した。
オーウェルはもともと、原案では『一九八四年』を『ヨーロッパ最後の人間』と題していたが、この形容はウィンストン以上にオブライエンに当てはまるのではないか。オブライエンは知性的であることと残酷であることを、良心の呵責なく両立させる「最後の人間」(ニーチェの言う末人)である。ローティが言うように、人間の「知的な天分」はそれほどに「可塑的」なのであり、そしてこの可塑性を知り尽くした知識人こそが不正を遂行するのだ。このような暗いヴィジョンをもつ小説家にとって「人生にたいする純粋に美学的な態度」はもはやあり得ない。晩年のオーウェルが「政治による文学にたいする侵犯」を積極的に招き寄せようとしたのは、そのためである[18]。文学もまた、政治による介入を受け入れざるを得ないのだ。
7、可視的な透明人間――オーウェルからラルフ・エリスンへ
ところで、テレスクリーンという装置に象徴されるように、オーウェルは社会の全面的な可視化を想定していた。ウィンストンとオブライエンもまた、お互いの姿をしっかり視認している。そして、このあらゆる私的な秘密を視覚的にあばく透明社会のメカニズムが、思考や言語の管理とコントロールを徹底し、全体主義体制からの逃走を失敗に終わらせる。
しかし、『一九八四年』からまもなくして、一九五二年に刊行されたアメリカの黒人作家ラルフ・エリスンの『見えない人間』では、オーウェル的監視社会とは正反対の状況が描かれている。ウィンストンやジュリアが全面的な可視化にさらされていたとしたら、エリスンの捉えたアメリカ社会の黒人は、むしろ不可視(invisible)だと見なされる。『一九八四年』と『見えない人間』のこの興味深いコントラストは、アフリカ系アメリカ人がヨーロッパの白人とは異なる文学的課題を背負ってきたことを示唆している。
トマス・ピンチョンが『一九八四年』に関する評論で注目したように、オーウェルの描く近未来の国家ではすでに人種差別は撤廃されており、ユダヤ人や黒人、インディオにも入党の資格が与えられていた。ただ、ピンチョンによれば、この「ありそうもない人種的寛容」は、小説のリアリティをいくぶんか損なっている(四九八頁)。逆に、エリスンはアメリカの人種差別の存在を前提として、そこで生じる認識の偏向を問題にした。『見えない人間』の主人公のブルー(憂鬱)な黒人青年――その名は最後まで明かされない――は、その語りの冒頭から白人の「内的な眼」の歪みを批評する。
僕は見えない人間である。かといって、エドガー・アラン・ポーにつきまとった亡霊のたぐいではないし、ハリウッド映画に出てくる心霊体(エクトプラズム)でもない。実体を備えた人間だ。筋肉もあれば骨もあるし、繊維もあれば肉体もある。〔…〕人は、僕の近くに来ると、僕の周囲のものや彼ら自身を、あるいは彼らの想像の産物だけを――要するに、僕以外のものだけを見るんだ。(上・二九頁)
ルイ・アームストロングの歌(どうしておれはこんなに黒くて/こんなにブルーなのか)を聴き、マリファナを吸いながら、彼は「時間の裂け目」に滑り込む。「言いわけになるが、不可視性のせいで僕には人と少し違った時間の感覚があって、完全にリズムにのるというわけにはいかない。進みすぎる時もあれば、遅れすぎる時もある。気づかないほどの時間の速い流れではなく、僕には節目が、つまり時間がぴたりと止まったり先にサッと進んだりする瞬間が分かるのだ」(上・三五頁)。
ときに加速し、ときに遅延する主人公の語りは、人生の時間に麻薬的な抑揚を与えている。この不安定なアゴーギク(テンポの変動)のもとで、『見えない人間』は黒人青年の語る長大な「自伝」の様相を呈する。彼はもともと南部のアラバマ州の大学――ツタで覆われ、スイカズラやマグノリアの花の咲く美しい田園として描かれる――の学生であったが、北部出身の白人理事ノートンをうっかり旧奴隷地区、さらには戦争神経症を患った黒人帰還兵の集う酒場に案内するという失態のせいで、大学を追放され、ニューヨークに移住する。ここには大学の欺瞞的なあり方とともに、聖書の「楽園追放」が意識されているのは明らかだろう[19]。
その後、彼はちょうど拷問を受けるウィンストンのように、病院で電気ショックを与えられるという苦難を経て、『一九八四年』の地下抵抗組織「ブラザー同盟」ならぬ「ブラザーフッド同盟」――黒人の自由と能力を解放するために民衆運動の組織をめざすサークル――に参加し、演説の才能を発揮する。しかし、警官に不当に射殺された黒人を弁護したことで、彼とブラザーフッド同盟の関係は悪化してしまう。やがて白人警察に追われるうちにマンホールのなかの黒い石炭の山に転落した彼は、白人専用ビルの地下室の人間、つまり孤独な「見えない人間」となり、ドストエフスキーの『地下室の手記』の自意識過剰な主人公のように、自らの人生を回顧するノートを書くのである。
エリスンはニューヨークの無名の黒人青年を、いわば可視的な透明人間(The visible invisible)として描いた。黒人はその肌の色、つまり可視的・表面的な情報で差別される。そして、まさにそのことによって黒人の状況そのものが不可視化されるというのが、エリスンの提示した逆説であった。それは、全面的な可視化を恐怖と見なすオーウェルの『一九八四年』には欠けていた問題である。
-
第十三章 人間――悪・可塑性・人種|福嶋亮大(前編)
2024-05-24 07:00
1、悪の発明――ラス・カサス的問題
文学にとって世界とは何か。私は歴史的な見地から、その問いを初期グローバリゼーションと紐づけた。世界とはたんに空間的な広さを指す概念ではなく、異質なものとの接近遭遇がたえず起こる場である。異なる歴史、異なる習俗、異なる人間との関係の集合体としての〈世界〉――その成立に欠かせなかったのが、アメリカ大陸へのヨーロッパ人の進出であり、「万物の商品化」を加速させる資本主義のプログラムであった。「世界文学とは新世界文学である」(第七章)という私のテーゼは、異質なものとの関係の無尽蔵の発生を、その根拠としている。
その一方、グローバリゼーションの発端にはおぞましい暴力がある。一六世紀スペインの神学者ラス・カサスの『インディオの破壊についての簡潔な報告』は、まさにその暴力を告発した文書である。先住民――ヨーロッパ人の誤認のせいで「インディオ」と呼ばれた――の虐殺のカタログと呼ぶべきその記録は、ヨーロッパの発明した「世界」が、他者との対話や競合ではなく、搾取と破壊から始まったことを証言している。
ラス・カサスによれば、コロンブスがアメリカ大陸に到着した一五世紀末に「まったく新しい、過去のいずれにも似ても似つかない」時代の扉が開いたが、それはただちに黄金に目のくらんだキリスト教徒たちによる、先住民のインディオの殺戮へと到った。スペイン領植民地におけるエンコミエンダ制(先住民を労働力として使役する権利を征服者に認めた制度)を神への違反として厳しく批判した他のドミニコ会士とともに、ラス・カサスは「人間の破壊」という激越な言葉を使って、スペインの植民地政策の非合法性を訴えた。彼が批判したのは、インディオを「絶滅」させることも厭わない残酷さであり、それを促した数々の社会的不正である[1]。
ラス・カサスは新大陸で受けた精神的な衝撃を、神学的かつ法学的な枠組みのなかで厳密に思考し直した。二〇世紀ペルーの神学者グスタボ・グティエレスによれば、ラス・カサスの企ては「掠奪と不正の上に築かれた社会で福音を宣べ伝えること」にあった。彼は聖書の教えに従い、断固として貧しきものたち、つまり先住民(インディオ)の側に立った。本来、キリストの教えでは、神と富に同時に仕えることはできない。キリスト教徒たちはインディオを、異教の神々をあがめる偶像崇拝者として蔑んだが、ラス・カサスに言わせれば、富(マモン)を行動の基準とし、富にすべてを捧げた自称キリスト教徒たちこそが、本物の神をフェイクの神に取り替えた最悪の偶像崇拝者にほかならない[2]。
黄金という「偶像」に惑溺したキリスト教徒が、おぞましいジェノサイドに駆り立てられる――この植民地でのトラウマ的な「人間の破壊」は、悪の新たな形態の出現、つまり悪の発明と呼ぶにふさわしい。ラス・カサスは大部の『インディアス史』において、この数々の邪悪な行為を歴史家として緻密に再現する一方、『インディアス文明誌』では非ヨーロッパ人のインディオがいかに理性的な人間であるかを、主にアリストテレスの哲学に拠りながら論証しようとした。そこには、人類社会のさまざまな差異とその深層の同一性をスキャン(走査)する文化人類学的な要素がある[3]。
アリストテレスの考えでは、あらゆる人間は政治的動物である。ラス・カサスが論証したのは、それはインディオも例外ではないということである。ラス・カサスに続いて、ホセ・アコスタの驚異的な著作『新大陸自然文化史』(一五九〇年)になると、アリストテレス哲学の限界が厳しく指摘され、あわせてアメリカ大陸の自然誌(気象、動植物、鉱物等)およびインディオの多様な文化についての詳細な分析が記された。それは、ヨーロッパ人に根強くあった新世界=怪物の住む土地という迷信を解体し、理性的な人間の住む範囲をヨーロッパ以外にも広げる企てであった[4]。《世界》に直面したスペイン人は、人間を破壊する暴力と、人間を発見する体系的な知を、ともに進行させたのである。
2、リハビリテーションの技法としての小説
ところで、新世界が「まったく新しい時代」を開いたと言われるのは、それが「旧世界」にも無数の変化をもたらしたからである。スペイン史の泰斗ジョン・エリオットによれば「アメリカを発見したことによって、ヨーロッパは自らを発見した」。アメリカは大量の新しい事実を、ヨーロッパの人間に示した。アメリカはたんに「新しい」世界であるばかりか、自然や文化に関してもヨーロッパとは「違った」世界であった[5]。ゆえに、ヨーロッパ人は新世界の人間や風土を理解するのに、自らの認識の土台――聖書やアリストテレスの哲学も含めて――に遡り、理性や信仰の問題を根本的に再検討するように強いられたのである。
新世界との出会いは、旧世界=ヨーロッパの自己認識に少なからぬ影響を及ぼした。そして、このヨーロッパにおける自己の再発見は、小説の認識の基盤にも重大な作用を及ぼしたように思える。繰り返せば、新しい「世界」の成立は、新しい「悪」の発明でもあった。それは人間――というより人間以下とされた存在――を組織的に破壊するという悪であり、富の増進のために貧者を資源として酷使するという悪である。
このようなジェノサイドの光景は、ヨーロッパの近代小説において変奏された。デフォーの『ペスト』やスウィフトの『ガリヴァー旅行記』、そしてサドの一連のリベルタン小説から、ドストエフスキーの『死の家の記録』、コンラッドの『闇の奥』、ソ連の強制収容所(ラーゲリ)を告発したソルジェニーツィンの『収容所群島』等に到る小説は、人間のシステマティックな「破壊」というラス・カサス的問題を執拗に反復してきた(第十章参照)。ここからは、近代ヨーロッパの発明した「世界」および「世界文学」が、人間の脆弱さや傷つきやすさへのオブセッションを抱いてきたことがうかがえる。
その反面、近代小説はラス・カサスの言説と同じく、富の発明した悪への批判、つまり富の有害さの暴露という一面をもった。われわれはここで、小説が悪からのリハビリテーションという仕事を自ら背負い込んだことに、注意を払っておこう。
現に、ラス・カサスの告発からほどなくして、フェリペ二世の統治時代(一六世紀半ば)のスペインではピカレスクロマンが流行し、無一物の「貧しきもの」の視点から、社会の富める主人たちの欺瞞があばかれた(第十一章参照)。スペインは新大陸から膨大な富が流入していたのに、財政的には赤字が膨らみ、苦境にあった。この繁栄のなかの危機を背景として、当時のスペイン社会では上から下まで、貧しきピカロの精神が浸透し、スペイン人の「人生哲学」を形成するまでになった[6]。財貨を軽蔑し、名誉を求める遍歴の騎士ドン・キホーテは、まさにこの哲学の延長線上に位置している。新世界に最初に進出したスペインが、小説の原初的なプログラムとして富=偶像への批判を明確化したことは、その後の小説の進化を方向づけるものであった。
さらに、『ロビンソン・クルーソー』や『ブーガンヴィル航海記補遺』で新世界と旧世界の対話的なつながりを創出した一八世紀のデフォーやディドロの言説は、アメリカ大陸におけるスペインの暴虐、いわゆる「黒い伝説」への厳しい批判を含んでいた。異文化の人間との友好的な対話を描いたデフォーやディドロは、スペインの悪魔的な「進出」と自らを差異化しようとする――そのとき彼らの小説は、ヨーロッパ人の発明したトラウマ的な悪からのリハビリテーションの場になった。
-
第十二章 制作――ハードウェアの探究|福嶋亮大(後編)
2024-04-30 07:00
6、制作の哲学――他者性のオン/オフ
制作者は、素材=ハードウェアとしての他者を象る。これは他者性の創設である。しかし、この被造物が制作者と合一するとき、他者性はむしろ打ち消される。制作者にとって、素材の他者性はときにオンになり、ときにオフになる。さらに、制作者自身も自らの制作物の魅力や恐怖に屈するとき、自己がオンの状態とオフの状態が重なりあう。『フランケンシュタイン』と「ピュグマリオン」が示すのは、まさにこの量子状態である。
ここで議論の補強のために、哲学的な観点も導入しておこう。「制作的態度」を現象学的に分析したハイデガーは、およそ次の二点を指摘している。
(α)制作的態度において、制作されるものはそれ自身に引き渡される。材料や素材がそれ自体として自立したものとして了解されるのは、作るという態度によってである。「材料や素材といった概念の起源はまさに、制作に定位した存在了解にあるのです」[13]。もう一歩進んで言えば、制作的態度こそが制作を必要としないもの、制作不可能なもの、つまり「自然」を浮上させる。
(β)制作者の狙いにおいては、制作物は「できあがれば自由に使用されるもの」として把握される。この態度において、制作物は「引き離して置かれるもの」ではなく「こちらへ招き立てられるもの」[14]、つまり手元で自由に扱える存在となる。ここには、技術の本質を自然の駆り立て=徴発(Gestell)と見なしたハイデガーの見解の反響が認められる。
ハイデガーによれば、制作者は素材=ハードウェアをそれ自身の権利において確立し、自立的なものとして了解する。つまり、自己とは異なる他者が創設される。その一方、制作物は完成したとたん、使用者の手元へと招き立てられる。つまり、隔たった他者ではなく、むしろ自己に近接的な他者として現れ直すのだ。他者を創設する一方、その他者と自己が限りなく近づいてゆくというパラドックスがここにはある。ルソーとシェリーはこの制作のパラドックスを的確に把握していたように思える。
ただ、一八世紀半ばの「ピュグマリオン」からおよそ半世紀後の『フランケンシュタイン』に到ったとき、制作のテーマがより厄介な問題を含むようになったことも見逃せない。フランケンシュタインと彼の制作物は、ピュグマリオンとその彫像が和解するのと違って、お互いを最大最強の敵と見なす。呪われたカップルとなった二人には、もはや相手を殲滅する選択肢しか残されていなかった。制作物が制作者を圧倒するような怪物として現れること――それがシェリーのつかんだ新たな問題なのである。
7、社会に先行する悪夢へのアクセス
イギリスのメアリー・シェリーとフランスのルソーはともに神話的な制作者(プロメテウス/ピュグマリオン)を参照しながら、散文的な現実に回収されない素材=ハードウェアの制作をテーマとしたが、『フランケンシュタイン』が示すように、その制作物は制作者自身を破局に追いやる怪物へと変身した。この制作物の怪物化という問題を探究するには、ヨーロッパだけでなくアメリカ大陸の文学も考慮に入れなければならない。
もとより、アメリカという国家そのものが、フランケンシュタインの怪物のような合成物である。アメリカの作家たちは総じて、自らの社会的現実が、稠密に組織されたヨーロッパとは異質だと考えていた。アメリカ的現実には穴があいていて、あちこちに飛躍や断絶がある。そのため、アメリカ文学は安定的な居住ではなく、踏破(メルヴィル、ジョン・ミューア)、探索(ヘンリー・ソロー、レイモンド・チャンドラー)、放浪(ナボコフ、ジャック・ケルアック)のような落ち着かない心情に由来する行為に導かれてきた。二〇世紀半ば以降は、これらのモチーフはSFに受け継がれる。特にロシア系移民のアイザック・アシモフの作品には、銀河帝国のファウンデーション(創設)からロボットまで、既存の社会や人間の限界を超え出る「制作」のテーマが息づいていた。
この安息を振り切ったアメリカ文学の系譜のなかで、一八〇四年生まれのナサニエル・ホーソーンは枢要な位置を占める。彼はE・A・ポーと並んで、ゴシック小説の陰鬱な想像力を駆使しながら、人工物の「制作」の問題に取り組んだ作家である。クリス・ボルディックが言うように、ホーソーンの一連の芸術家小説――「イーサン・ブランド」「美の芸術家」等――では「被造物は、きまって自律的な力を持つようになり、やがては自らを生み出した創造者を圧倒するに至るのである」[15]。ホーソーンには、制作者が制作物に食いつぶされるというモチーフがある。
ただ、これだけならば、ホーソーンの小説は、およそ半世紀前の『フランケンシュタイン』の亜流に留まるだろう。ホーソーンやポーの創意は「制作されたもの」に過去の悪夢的な重さを与えたことにある。ゴシック小説研究者のデイヴィッド・パンターによれば「ヨーロッパの過去の重圧は、美であると同時に恐怖を意味した。この過去の重圧によってヨーロッパは窒息死する危険にさらされていたのだ。ホーソーンやポーの全体にわたって存在しているのは、この窒息状態である」[16]。ホーソーンとポーの「制作」は、過去の呪縛のせいで「窒息」しかかっている社会や人間を浮かび上がらせる。そのため、彼らの小説はたいてい陰鬱で安らぎを与えない。
特に、マサチューセッツ州のセイラムを拠点としたホーソーンは、散文的な「ノヴェル」を希求しつつも、それ以前の古い文学形態である「ロマンス」をあえて戦略的に選び取った作家である。彼の企ては、散文的な現実との和解を拒み、社会に先行する悪夢にアクセスすることにあった。しかも、そのあらゆる安息を奪う悪夢を、制作された物質=ハードウェアに結びつけたところに、彼の真骨頂がある。
-
第十二章 制作――ハードウェアの探究|福嶋亮大(前編)
2024-04-23 07:00
1、読むこと、見ること、作ること
私は前章で、近代小説の主体性の源泉が「読むこと」の累積にあることを示した。一八世紀の書簡体小説では、登場人物たちが大量の手紙を送受信し、相手のテクストにエントリーし続ける。手紙はいわば瞑想用のアプリケーションであり、心(主観)の状態をその揺らぎも含めて、きわめて詳細に書き込むことができた。さらに、近況を報告しながら、知識や感情を親しい相手とシェアする手紙は、速報性と共同性を兼ね備えた媒体でもある。書簡体小説はこのアプリケーションに支援されながら、主観とコミュニケーションを文学の中心に据えた。
この文学的発明によって「読むこと」はたんなる情報の獲得ではなく、相手の心を深く了解するための没入的なコミュニケーション行為となる。他者の書いたテクストへの反復的なエントリー(学習)によって、書簡体小説の主人公たちは、心的な一貫性をもつ主体として組織された。しかも、彼らのプライヴェートな送受信の記録は、なぜか読者に漏洩し、覗き見されることになる。ゆえに、書簡体小説には「読むこと」そのものがテクストの内から外に転移するという構図がある[1]。
書簡体小説を含め、近代小説は『ドン・キホーテ』から二〇世紀のハードボイルド探偵小説に到るまで、《読む主体》を核として進化してきた。日本文学でも、ダンテやセルバンテス、ポーを読み解く大江健三郎からレイモンド・チャンドラーを翻訳した村上春樹まで、このタイプの主体性が継承された。村上の『街とその不確かな壁』(二〇二三年)という曖昧模糊とした小説になると、読む行為が何のてらいもなくロマンティックに美化されている。
もともと、ヨーロッパ小説で「読むこと」の進化を促したのは、宗教的権威からの離脱の動きであった。メキシコの作家カルロス・フエンテスによれば、『ドン・キホーテ』の母胎となったのは「ローマ教会とその一義的な世界の読みとりに背を向けたヨーロッパ」である[2]。世界の解読の方法がもはや一つの絶対的な規範=信仰に従属しなくなったとき、セルバンテスは「読むこと」を小説の中心的問題に引き上げた。一義的な読みへの圧力が弱まれば、読むことはいつなんどきエラーや暴走を起こし、主体=読者を狂気や誤解に導くか分からなくなる――それが二一世紀のインターネット時代にも通じる『ドン・キホーテ』の教えにほかならない。セルバンテスにとって「読むこと」は、信仰とも理性とも異なるやり方で世界を学習する行為であり、それゆえに危険かつ魅惑的であった。
ただ、《読む主体》を抽出するだけでは、小説のアーキテクチャを解明するにはまだ不十分だろう。われわれは「読むこと」に回収されない問題を把握せねばならない。例えば、ゲーテは『若きウェルテルの悩み』で書簡体小説の時代の終わりを告げる一方、自然科学者として「見ること」の価値を高めた。彼にとって、科学は深遠な自然にアクセスし、感覚を豊富化する学問的アプリケーションであった。自然のもつ無尽蔵の生成力に沿いながら、文学者ゲーテは『イタリア紀行』では火山の測量のような調査を含めて、自らの視覚的体験を詳しく再現した(第九章参照)。
言うまでもなく、自然の旺盛な生成力は凶暴な破壊力にも転じる。少年時代にリスボン大地震の惨状を何度も聞かされたゲーテは、自然の過剰さに心を揺るがされた作家であった。リスボン大地震は哲学者や神学者による世界の説明を疑わしいものとし、前例のないスピードで恐怖を蔓延させた。彼の自伝『詩と真実』によれば「恐怖の悪霊がかくも迅速に、かつ強力に、その戦慄を地上にくり広げたことは、おそらくかつてないことであった」[3]。このメフィストフェレスのような悪魔じみた自然に対しては、もはやテクストを「読む」だけでは太刀打ちできない。ゲーテの《見る主体》は、科学というアプリケーションに支援されながら、生成=震動する自然にアクセスしようと試みた。
さらに、「読むこと」のちょうど対になる行為として、「作ること」や「書くこと」が挙げられるだろう。私はそれを「ハードウェアの制作」というテーマとして論じたい。まずは、このテーマが浮上してくる文学史的背景を整理しよう。
2、フィクションとノンフィクションを区別しない言説
ヘーゲルは『美学』の叙事詩を論じたくだりで、近代的な小説(Roman)の前提となるのは「すでに散文的世界として秩序づけられた現実」だと述べた。散文と化した現実は、神々や英雄の非凡な業績ではなく、取るに足らない日常的・偶然的な事柄によって構成される。ヘーゲルによれば、小説家の個性はこの平凡で、散発的で、とりとめのない現実の「捉え方」に現れるが、そこには二つの手法があった。一つは散文化した現実を承認し、それと和解すること、もう一つは平凡な現実をより美的・芸術的な現実に置き換えることである[4]。ごく大雑把に言えば、これは「日常系」と「非日常系」の差異に対応する。
近代小説はまず、前者に力点を置いたジャンルとして現れた。「散文」となった現実を承認した小説は、平凡な人間の心理および社会の状況を描くことに、エネルギーを注いだ。小説家が関心を向けるのは、前もって何が起こるか予測できない、社会という偶然の場である。イギリスの古典的な文学や批評(とりわけシェイクスピアやジョン・ドライデン)を吸収した明治日本の坪内逍遥が「小説の主脳は人情なり、世態風俗これに次ぐ」(『小説神髄』)と的確に評したことも、ここで思い返しておこう。
特に書簡体小説は、まさに坪内逍遥の言う「人情」(心)と「世態風俗」(社会)を記述する散文的なリアリズムを前進させた。サミュエル・リチャードソンやモンテスキューに始まり、ルソーの『新エロイーズ』やゲーテの『若きウェルテルの悩み』に到るまで、手紙の記述はもっぱら身辺の出来事の報告に向けられ、超自然的な現象は排除された。加えて、書簡体小説は自らが本物の手紙の集まりであり、創作されたフィクションでないことを強調した。現に、ルソーやゲーテは創作家ではなく、ジュリやサン゠プルー、ウェルテルの書いた実在の手紙の編集者として自己演出したのである。
ゆえに、一八世紀の書簡体小説は自らを「フィクション」として規定しない――というより、当時はフィクションとノンフィクションの区別そのものが厳密ではなかった。テリー・イーグルトンによれば「リチャードソンの特異な文学生産様式は、言説を「フィクション」と「ノンフィクション」に厳密に分節化しない社会、つまり私たち自身の社会とは異なる社会において、はじめて可能な様式であった」[5]。現代のわれわれは、小説とはフィクションであると無造作に考える。しかし、一八世紀ヨーロッパの作家たちにとって、小説はむしろ「人情」や「世態」を高精度で再現するハイパーリアルな書式であり、その言説をわざわざ虚構の文書と宣言する意味はなかった。同じく、中国でも小説は歴史書、つまり事実の文書を擬態して書かれたのである(第四章参照)。
フィクションとノンフィクションをボーダーレスにつなぐ言説の形態は、書簡体小説に限ったものではない。リチャードソンより約三〇歳年上のデフォーは『ロビンソン・クルーソー』や『ペスト』を、出来事を忠実かつ詳細に記録したfactual(事実的)な文書として読者に差し出した。デフォーにとって、文書の価値は巧みな虚構の創作にではなく、いわばfactfulness(事実に満ちていること)にあった。二〇世紀のヴァージニア・ウルフが『ロビンソン・クルーソー』について「この本は個人の労作というよりはむしろ、民族が生み出した作者不明の所産の一つに似ている」と評したように[6]、作家デフォーはクルーソーの島を覆う無数の「事実」の影に隠れている。一八世紀の作家は、ノヴェルという新しい高精細の記録装置によって、散文化=日常化した世界と和解したのである。
-
第十一章 主体――読み取りのシステム|福嶋亮大(後編)
2024-03-19 07:00
6、教師あり学習――ゲーテのビルドゥングスロマン
もっとも、セルバンテス以降もピカレスクロマンの影響力は持続し、一八世紀のヨーロッパではときに女性のピカロも登場した。デフォーの『モル・フランダース』にせよ、サドの『ジュリエット物語あるいは悪徳の栄え』にせよ、その主人公はいわば不良の女性である。特に、悪の快楽に染まったジュリエットは、美徳を象徴する妹ジュスティーヌとは対照的に、ヨーロッパの各地を旅して破壊の限りを尽くす。ジュリエット一行が道中で目の当たりにしたイタリアの火山は、まさにその放埓なエネルギーの象徴であった。
その反面、ピカレスクロマンの主人公には成長や発展の契機は乏しかった。一人称の視点を備えたピカロは、さまざまな社会環境を遍歴するが、それはしばしば単調でパノラマ的な反復に陥った。場面が劇的に変化しても、主人公はそこをサーフィンするだけで内面的な成長にはつながらない――それはピカレスクロマンだけではなく、クルーソーやガリヴァーのような一八世紀型の主人公全般に当てはまる傾向である。
この限界を超えるようにして、一八世紀後半以降になるとドイツ語でビルドゥングスロマン(Bildungsroman/「教養小説」や「成長小説」と訳される)と総称されるジャンルが、精神的な「発展」のテーマを浮上させた。人間の隠れたポテンシャルを探り当て、生物のように成長させて自律的な存在に到らせること――それがビルドゥングスロマンの企てである。その中心地のドイツでは、一七世紀のグリンメルスハウゼンの『阿呆物語』をはじめ、一八世紀後半にヴィーラントの『アガトン物語』やノヴァーリスの『青い花』が現れた。なかでも、ゲーテの『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』(一七九六年)は、ビルドゥングスロマンの標準的形態として評価されてきた。
ジャンル論的な観点から言えば、ゲーテが『ヴィルヘルム・マイスター』以前に、書簡体小説からの離脱を促したことが重要である。彼の初期のベストセラー『若きウェルテルの悩み』(一七七四年)は、形式的には書簡体小説であるものの、その内容は激情型のウェルテルの一方的な語りによって占拠されており、書簡相手とのコミュニケーションを欠く。ウェルテルは他者の書簡を読む代わりに、たとえ話をたびたび用いて、自らの語りの意味を重層化することを試みる。つまり、彼の手紙はあくまで自己内対話の記録なのである。
ゆえに『ウェルテル』は「書簡体構造の崩壊」を鮮明にする一人称の告白小説に近づく[25]。書簡体小説の時代の終わりを、これほどはっきり示した作品は他にない。加えて、ウェルテルはピカレスクロマンを導く下層のアウトサイダーでもなかった――ルカーチが言うように、ウェルテルはむしろ「高貴な情熱」を純粋化した挙句に、社会の法体系と矛盾してしまうのだから[26]。要するに、ゲーテはウェルテルに、それまでの文学形式には収容しきれない人間像を託したと言えるだろう。
この『ウェルテル』の実験の二〇年後に現れたのが、大作『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』であり、そこで後にビルドゥングスロマンと称される文学形式が開示された。ウェルテルが自己破壊的な情動に囚われたのと違って、ヴィルヘルムはむしろ世界に沿って記憶や経験を組織的に蓄積し、それを自己形成のプログラムとして利用する。コンピュータ・アルゴリズムの比喩を使えば、ビルドゥングスロマンとは「教師あり学習」(supervised learning)のプロセスを再現した文学として理解できる。ヴィルヘルムはまさに世界=教師から学習し、精神を段階的に建設してゆく「教養(ビルドゥング)」の企てに自らを差し向けた。
もとより、教養とはまばらな知識の集まりではなく、自律性の獲得に向けた組織的で終わりのない知的運動を指す。バフチンによれば、ゲーテにとって、この教養的な人間形成のモデルになったのが、自然環境に含まれる「有機的」な「歴史的時間」であった。「空間のなかに時間を見るゲーテの驚くべき能力」は、生き生きとしたリズムで脈動する自然を捉える[27]。ゲーテ的な人間は、この自然のダイナミックな時間と共鳴するようにして、自らのうちなる生成力を発見する。教養とは死んだ知識の収蔵ではなく、世界に内在する生成力の発見に等しい。
主人公の自律性の獲得を描くビルドゥングスロマンは、ふつうに見れば「一」の文学である。しかし、主体が世界=教師とペアリングされて成長するという意味では、そこには潜在的な「二」の文学の要素がある。バフチンが言うように、ゲーテはこのペアリングを「見ること」つまり鋭敏な視覚の力によって可能にした。
7、教養の廃墟からの成長――ブロンテの『嵐が丘』
それにしても、なぜドイツでビルドゥングスロマンが発達したのか。そこにはドイツ特有の政治状況がある。フランスと違ってドイツには革命がなく、しかも多くの領邦国家が分立していた。ゆえに、ドイツの統合に向けては、精神的な次元での「文化国家」のアイデンティティに訴えるしかなかった。そのとき、未成熟な状態からの成長を描くビルドゥングスロマンは、一つの成熟した精神的=文化的共同体に向かうための格好の道標になった[28]。
このような政治的動機を潜ませたドイツの文芸を中心にするとき、ビルドゥングスロマンはきわめて男性的なジャンルとして現れてくる。ただ、この見方がジェンダー的な偏向を含むのは明らかだろう。
そもそも、小説的主体の歴史が男性に還元されないことは、スペインの『セレスティーナ』をはじめ、デフォーやサドらの描いた女性のピカレスクロマンからも分かる。彼女らは社会的規範を出し抜く戦略家であり、モル・フランダースのように、大西洋を渡ることも辞さない旺盛な活動力を備えていた。その一方、リチャードソンやルソーの書簡体小説も、女性の心理という豊饒な鉱脈の発見なしにはあり得なかった(この両者が幼少期から女性との接触の機会が多かったことは興味深い)。近代小説の原史において、女性の関与が不可欠であったことは、改めて思い出されるべきである。
ビルドゥングスロマンの進化についても、すでにゲーテ以前に女性作家が関わっていた。女性作家による女性を主人公とするビルドゥングスロマンの先例としては、フランスのラファイエット夫人の『クレーヴの奥方』(一六七八年)やイギリスのイライザ・ヘイウッドの『ベッツイ・ソートレス嬢の物語』(一七五一年)等が挙げられる。その後、アメリカではルイーザ・メイ・オルコットの『若草物語』(一八六八年)からマーガレット・ミッチェルの『風と共に去りぬ』(一九三六年)まで、広義のビルドゥングスロマンに数え入れられる小説が、商業的にも大きな成功を収めた。
ただ、私はここであえて、女性作家の書いた変則的なビルドゥングスロマンを、特異な事例として導入しておきたい。それはエミリ・ブロンテの『嵐が丘』(一八四七年)である。
周知のように、この小説はもはやふつうの意味でのビルドゥングスロマンの可能性が崩壊した、荒涼とした丘陵と渓谷を舞台にしている。孤児ヒースクリフの形象はアイルランド大飢饉の惨禍に通じるが(第五章参照)、この亡霊的なヒースクリフ自身も、同じ魂をもつ死んだ恋人キャサリン・アーンショウの亡霊に憑かれる。ヒースクリフの狂気は、望まない結婚を経て死に到った不幸な女性の狂気と重なりあう。その意味で、『嵐が丘』とは「二」の小説、つまりきわめて荒々しく凶暴な男性が、実は女性にハイジャックされているという両性具有的な作品である。
そして、この二乗された亡霊は暴風のように吹き荒れ、人間どうしの絆を断ち切り、幼い家族を虐待し、ついにヒースクリフ自身の破滅へと到る。彼の前代未聞の過剰なドメスティック・ヴァイオレンスは、ゴシック小説の伝統に即しつつも、それをはるかに超えるような不可解な印象を与える。語り手の家政婦ネリー・ディーンは、本名も年齢も不詳のヒースクリフについて「いったいあの人は、どこから来たのだろう?」と夢うつつでつぶやく[29]。ヒースクリフにはいかなる社会的属性もない。彼は、社会に場をもたない異邦人であり、彼の住まう「嵐が丘」はいわば亡霊たちのアセンブリ(集会)の場なのである。
キャサリンの亡霊と一人対話するヒースクリフの表情は「極端な楽しみと苦痛」にさいなまれ、苦しみのなかで恍惚としている[30]。このぞっとするような光景には、いかなる出口もない。内面的な成長の可能性をもたないヒースクリフは、ビルドゥングスロマンの枠組みから完全に外れた存在である。
煽情的なゴシック小説の流行を嫌った一九世紀初頭のワーズワースは、湖水地方のなめらかな自然の運動を教師としながら、自らの詩(特に『序曲』)に一種のビルドゥングスロマンの性格を与えた。The Tables Turned(形勢逆転)という詩では、書物を捨てて、光を浴びて鳥のさえずりを聴き、自然を先生にせよというまっすぐなメッセージが発せられる[31]。ワーズワースにとって、自然は書物を超えた書物、学校を超えた学校であった。しかし、その半世紀後の『嵐が丘』になると、自然=教師はその暴力的な顔をむき出しにする。ヒースクリフ(ヒースの茂る荒野の崖)という名前そのものが、破局的な自然の記号にほかならない。
しかし、ここで注目に値するのは、ヒースクリフの異様な暴力と謀略の支配のなかでも、自らの精神的な独立をめざした女性がいたことである。それが亡きキャサリンの娘キャシーである。一八歳のキャシーは二三歳のヘアトン(キャサリンの甥だが、同居するヒースクリフに虐待されてまともな教育を受けられず、すっかり退嬰的な気分に沈み込んでいる)を抱き込み、「嵐が丘」という屋敷――ゴシック小説を特徴づける不気味な「城」の等価物――でのサバイバルを企てる。その際、キャシーとヘアトンを結びつけるのは、ヒースクリフの忌み嫌った書物である。
「本があったときには、いつでも読んでいたわ」とキャシーは言いました。「でも、ヒースクリフさんは本を読まないの。だから、あたしの本も捨てちゃうような真似をするのよ。〔…〕それにねヘアトン、あたし、あなたの部屋に隠してある本を偶然見つけたのよ……ラテン語やギリシャ語の本に、物語や詩の本。みんな、あたしの昔の友達だったわ〔…〕」。[32]
キャシーはヘアトンに本をプレゼントし、二人で仲良く読書する。この自己教育によって、二人の敵対性は消滅し、親密な同盟関係が設立され、ヒースクリフの暴力の防波堤となる。ここで重要なのは、二人がともにキャサリンの亡霊を背負っていたことである。ネリーの報告によれば「二人の目はほんとうにそっくりでございますよ。亡くなったキャサリン・アーンショウの目なのです」[33]。キャサリンの亡霊はヒースクリフに苦痛に満ちた恍惚を味わわせる一方、若いカップルには連帯の可能性を与えた。ヒースクリフを過去に閉じ込める亡霊は、キャシーとヘアトンにとっては、むしろ唯一の活路として現れる。ブロンテがここに世代的な差異を導入したことは明らかだろう[34]。
こうして、キャシーは「嵐が丘」という恐るべき紛争地帯において、読む行為をヘアトンに感染させながら、自己を戦略的に立て直そうとする。ビルドゥングスロマンを粉砕するほどの過剰な暴力の吹き荒れる閉域で、いかなる成長の物語を描くか――ブロンテはこの難題に「読む主体」の複数化によって応じたのだ。
-
第十一章 主体――読み取りのシステム|福嶋亮大(前編)
2024-03-14 07:00
1、一か二か
ルソーが自伝文学『告白』の冒頭で「わたしひとり。わたしは自分の心を感じている。そして人々を知っている。わたしは自分の見た人々の誰とも同じようには作られていない」と大胆不敵に宣言したことを典型として、近代ヨーロッパの文学は唯一無二の創造物である「私」の探究に駆り立てられてきたように思える。故郷喪失に続く冒険を小説の基本的なテーマと見なしたジェルジ・ルカーチも、結局は「一」なる主体をその核に据えていた。
柄谷行人が指摘したように、近代小説の根幹には「内面の発見」がある[1]。これは、他者や環境から区切られた内面が、小説の探究すべき対象になったことを意味する。ルソーの『告白』は、まさに「私」を他に依存しないスタンドアローンな存在に仕立てあげた一種の独立宣言である。
古代文学と比較すると、ルソーの宣言の意義はいっそうはっきりするだろう。例えば、古代のホメロスの叙事詩では、英雄たちの心は閉じた自我のなかに格納されず、環境の作用を強く受けていた。ホメロス的人間とは「周囲のあらゆる力の影響から人間を隔絶する境界をもたない、いわば「開かれた力の場」」なのだ[2]。逆に、カメラ・オブスクラのモデルに近似する近代小説のリアリズムは、自我の感覚の部屋(=カメラ)を、この種のボーダーレスな「力の場」から切り離した。それによって、小説は唯一無二の「私」の自己認識を深める装置として進化してきた。
ルカーチも柄谷も、「一」なる主体を近代小説の主人公の標準的形態として捉えたことに変わりはない。しかし、このモデルには修正の余地がある。というのも、小説的な主体性は実は純粋な「一」ではなく、早期から「二」への傾きを備えていたからである。
その具体例には事欠かない。『ドン・キホーテ』(ドン・キホーテ/サンチョ・パンサ)、『ペルシア人の手紙』(ユズベク/リカ)、『新エロイーズ』(ジュリ/サン゠プルー)、『ラモーの甥』(ラモー/哲学者)、『ロビンソン・クルーソー』(クルーソー/フライデー)、『闇の奥』(クルツ/マーロウ)、『ロリータ』(ハンバート/ロー)、日本文学で言えば夏目漱石の『こころ』(先生/K)、大江健三郎の『万延元年のフットボール』(蜜三郎/鷹四)、村上春樹の『風の歌を聴け』(僕/鼠)等では、単一の主体ではなくカップルが中心化される。さらに、ルソーの『ルソー、ジャン゠ジャックを裁く』、ドストエフスキーの『分身』、E・A・ポーの「ウィリアム・ウィルソン」、E・T・A・ホフマンの『砂男』、オスカー・ワイルドの『ドリアン・グレイの肖像』をはじめ、自己を二重化する分身(ドッペルゲンガー)のテーマも、特にロマン主義以降に何度も反復されてきた。
だとすれば、小説の主体性を「一」に還元するのは妥当ではない。小説はいわば「二」のウイルスに感染しており、それが折に触れて症状として顕在化するのだ。この「一」と「二」のあいだの振幅は、小説そのものの特性と切り離せない。なぜなら、小説における「私」は他者との接触なしにはあり得ないからである。「小説は演劇ではないのだから、すべての人物を厳密にいって同時に、読者に《見せる》わけにはいかない。小説においては、人物は相互に他の人物を通してみられるのである」(ジャン・プイヨン)[3]。小説の自我(ego)は他我(alter ego)の介入を必要とする。そこに、「一」なる主体が潜在的に「二」への分裂を含む要因がある。
ミハイル・バフチンは、小説における他者の介入に「対話的」という形容を与えた。バフチンの理論では、小説は複数の声の遭遇や衝突の場として了解される。ただ、私は「二」を「対話的」というより「読解的」な問題として考えたい。結論から言えば、近代小説は他者や世界を読むことの発明と不可分だからである。以下では「一」と「二」のあいだをさまよう主体の歴史を整理しながら、小説的主体を《読み取りのシステム》として把握することを試みる。まずは「二」の問題から始めよう。
2、書簡体小説の啓蒙的機能――近況報告あるいは権力のホログラム
一八世紀ヨーロッパを代表する小説が書簡体で書かれたことは、コミュニケーション(自我と他我のカップリング)が近代小説の基盤にあることを示唆する。もともと書簡文学の伝統は、医師ヒポクラテスの名を冠した古代の架空の書簡集(ヒポクラテス・ロマン)や中世の『アベラールとエロイーズ』等にまで遡れるが、一八世紀になるとそれは啓蒙思想の有力な手段として再創造された。
書簡体小説の金字塔と呼ぶべきモンテスキューの『ペルシア人の手紙』は、ヨーロッパとアジアのあいだの異文化コミュニケーションを主題としながら、開明的な貴族ユズベクと若く生気に満ちたリカという二人のペルシア人を対比的に登場させた(第三章参照)。モンテスキューはここでペルシアとフランス、年長者と若者という二組のカップルを交差させたが、それを手紙というテレコミュニケーション・メディアで実行したところに彼の創意工夫がある。
モンテスキューの創作した手紙は、カップルを結びつける一方、その両者の差異や異質性も浮き彫りにする。モンテスキューは異邦人の仮面をかぶり、フランス社会に対してわざと無知のふりをすることによって、その体制に加担せず、悪しき因習を暴露した。バフチンによれば、この「変わり者」の人物像の「分からない」という態度こそが、モンテスキューの発明であった[4]。小説とは分からないこと、不可解であること、愚かであること、変わり者であることを積極的に利用して、社会の自明性を懐疑するジャンルである。『ペルシア人の手紙』の大量の通信は、まさに変わり者=異邦人の態度に根ざしながら、見慣れた社会を見慣れないものに変えた。
さらに、モンテスキューの書簡体の採用には、明確な方法論的な企図があった。彼自身、書簡体小説の利点を具体的に説明している。
そもそも、この種の小説は、たいてい成功を収めるものだ。なぜなら、人物がみずから近況を報告するからである。このやり方は、人が語ることのできるどんな物語よりも、きちんと情念を伝えてくれる。〔…〕書簡集の形式では、役者たちは決まっておらず、扱われる主題は前もってあたためられたどんな意図や計画にも左右されないため、一つの小説に哲学や政治や道徳を盛り込み、全体を秘密の鎖で、ある意味では未知の鎖で束ねるという特権を著者は手に入れたのだ。(「『ペルシア人の手紙』に関するいくつかの考察」)
現代のEメールやインスタントメッセージでも、そのやりとりはほぼ「近況報告」によって占められている。この種の報告では、語りの首尾一貫性や事前の入念の計画性よりも、相手にそのつど情報や感情を伝える即興性が優位に立つ。モンテスキューは架空のペルシア人たちがパリの異文化に出会ったときの新鮮な驚きを擬態し、脱線もおおらかに許容しながら、哲学や政治の話題にフレッシュな生命を与える。思想をその誕生の瞬間に差し戻すこと――それが書簡体小説の効果である。
その一方、モンテスキューは書簡が届くまでの「時差」も巧妙に利用していた。フランスとペルシアの遠さゆえに、ユズベクが故郷に手紙で発する命令は遅延し、有効に機能しない。そのため、彼は絶対的な権力者であるにもかかわらず、ペルシアのハーレムで起こった女たちの叛乱を制御できない。この無力さは、彼が手紙の通信のなかでのみ立ち現れる、いわばホログラム的なヴァーチャル・リアリティ(VR)であることに起因する。
そもそも、パリでアイドルとなった若いリカとは違って、年長のユズベクは消費社会の見かけ(仮象)に騙されないように警戒している。つまり、ユズベクにはオーセンティックなもの(本物)への意識がある。しかし、手紙で語られる自己とは、むしろ記号的な「見かけ」しかないホログラムに似た存在ではなかったか。手紙は他者を操作し、望ましい状況を作り出そうとするが、その戦略はたやすく誤解されたり改竄されたりする。いかなる強大な専制君主であっても、見かけだけの《手紙内存在》として現れるときには、そのリスクを回避できない。ここには本質的な脆弱性がある。
要するに、手紙は権力の増減、権力のキャンセル、権力のねじ曲げの発生する戦場であり、書簡体小説とは権力を乱高下させるゲームなのである。テリー・イーグルトンはそれをうまく説明している。
手紙は、主体の秘密をあかすもっとも生々しい記号であるがゆえに、干渉を受け、捏造され、奪われ、失われ、書き写され、引用され、検閲され、パロディにされ、曲解され、書きなおされ、からかい半分の注釈にさらされ、別のテクストに織り込まれることによって意味の変質をこうむり、書き手が予想だにしなかった目的のために使われる。[5]
現代でも、流出したメールは週刊誌的なゴシップの格好のネタになる。手紙は人間の隠された秘密を生々しく語る一方で、他者によってたやすく曲解されパロディにされ、権力者の威厳を失墜させる。一言で言えば、手紙とは神経過敏なメディアであり、限りなく「私」に近いのに、同時に「他者」の干渉にさらされている。
このような手紙の特性を踏まえると、モンテスキューが書簡体小説を啓蒙のプロジェクトに利用したのも、当然と言えば当然のことに思える。改めてポイントを二つにまとめよう。
第一に、手紙はよそもの(他者)の目から見た即興的でタブーのない近況報告によって、フレッシュな社会批評となる。比較人類学的な思想書『法の精神』の著者らしく、モンテスキューは『ペルシア人の手紙』でも法や文化の相対性を読者に強く意識させる[6]。ヨーロッパからペルシアを観察し、ペルシアからヨーロッパを観察する『ペルシア人の手紙』は、他者に自己を映し出すプロジェクトの記録にほかならない。しかも、このプロジェクトを支える手紙は、しばしば接続不良に見舞われ、混乱を助長するのだ。
第二に、手紙はその送信者を脆弱なホログラムに変える。権力者ですら、その例外ではない。書簡体小説では、他者がいなければ自己もない。つまり、送信者も受信者も、他者の地平のなかに、自己を出現させなければならない。相手からの返信によって、自己がどんな人間かがはじめて了解される。だからこそ、発信者は受信者の思想を占拠し、望ましい自己をそこに出現させようとする。他者を支配することと他者に支配されることが、次第に見分けがたくなること――そこに書簡体小説の特性がある。
-
第十章 絶滅――小説の破壊的プログラム|福嶋亮大(後編)
2024-02-20 07:00
6、倒錯的な量的世界――スウィフト『ガリヴァー旅行記』
『ロビンソン・クルーソー』への自己批評と呼ぶべき『ペスト』からほどなくして、一七二六年にスウィフトの『ガリヴァー旅行記』の初版が刊行される。この奇怪な旅行小説は、一八世紀の初期グローバリゼーションを背景として、人間の可変性や可塑性を誇張的に示した。
イングランドの政治を批判する一方、故郷のアイルランドをも罵倒した非妥協的な著述家らしく、スウィフトはまさにルカーチ流の故郷喪失者としてガリヴァーを描き出した。海に出ることを「運命」と感じて、医者として船に乗り込んだガリヴァーは、何度も冒険と漂流を繰り返し、そのつど新たな国家に接触しては、ヨーロッパとは異質の文化的習慣を「ありのまま」に記録しようとする。そこには、人間はいかようにも変化し得る動物だというスウィフトのクールでシニカルな認識があった。
周知のように、ガリヴァーは第一部では小人国リリパットに漂着し、自身の十二分の一サイズの王侯貴族に歓待されるが、第二部では大人国ブロブディンナグで、十二倍の巨人に小さな玩具のように扱われる。第三部では、飛行島ラピュタ(ラプータ)から日本の長崎に到る多くの土地が登場した後に、第四部では奇怪な「馬の国」が舞台となる。そこでは「フウイヌム」と呼ばれる理性的な馬たちが特定の支配者をもたず「集会」によって政治を進める一方、人間は下等な「ヤフー」として使役されている。馬の国にすっかり魅せられたガリヴァーは、ヤフーの皮(!)でカヌーを製造して帰国し、妻子と再会した後も、人間の体臭に耐えられず馬たちと暮らす。
人間の象徴的な優位性をさまざまな手口で失墜させること――それが『ガリヴァー旅行記』を貫く明晰な悪意である。それは究極的には、ジェノサイドの構想にまで到るだろう[26]。馬の国のフウイヌムは理性の命令に従って、人口を完璧にコントロールする一方、醜悪で悪辣きわまりないヤフーを地上から絶滅(exterminate)させるべきか否かを議論する(第四部第九章)。ちょうどデフォーの『ペスト』と同じく、スウィフトの馬の国でも固有名は蒸発し、生物は操作可能な量に還元される。『1984』の著者ジョージ・オーウェルは『ガリヴァー旅行記』の第三部に相互監視的な警察国家のモデルを認める一方、第四部の「馬の国」を順応主義がすみずみまで行き渡った全体主義体制の予告編と見なし、ヤフーをナチス・ドイツ統治下のユダヤ人になぞらえたが[27]、それもあながち突飛な解釈ではない。
そもそも、『ガリヴァー旅行記』は子供向けにも思える前半から、すでに人間の量的操作を実行していた。『ペスト』や『ソドムの百二十日』がいわばエクセルのように犠牲者の数値的データを記録したとすれば、『ガリヴァー旅行記』はいわばフォトショップのように図像のサイズを伸縮させた。リリパットでは人間と動植物の「比率(proportion)」が正確に決められている(第一部第六章)。ブロブディンナグでは万物のサイズが大きくなった結果、その図像の解像度も変わり、シラミが異様に拡大され、女性の皮膚の気味悪くでこぼこした様子がクロースアップされるのだ(第二部第五章)。
かつて批評家の花田清輝が鋭く指摘したように、『ガリヴァー旅行記』の認識と論理は「量的把握という一事につきる」。ガリヴァーの旅行は「量的変化をみちびきだすための力学的位置変化」であり、そこには「人間の質のみを強調するルネッサンス以来の人間主義にたいする批判」が含まれる[28]。この比率の操作された量的世界においては、シラミや皮膚のような平凡なものが平凡なままで吐き気や嫌悪感を催させる[29]――それがフォトショップ的な比率変更の効果なのだ。スウィフトはある意味ではデフォーやサド以上に徹底した悪意によって、倒錯的な量的世界を描き出した。
さらに、第三部では、テクノロジーの進歩への夢が批評される。天然磁石の力で飛ぶラピュタの住民は、数学と音楽に熱中して周囲を顧みず、ガリヴァーの存在には無関心である。この冷淡なラピュタを去ってバルニバーニの首都ラガードに赴いたガリヴァーは、さまざまな新規プロジェクトを推進するグランド・アカデミーを見学する。そこで「思弁的学問」の自動化を企てる教授は、まるで二一世紀の生成AIの研究者のように「どれほど無知な人間でも、費用も手ごろ、多少の肉体労働を行なうだけで、天賦の才や勉強の助けをいっさい借りずに、科学、詩、政治、法律、数学、神学に関する書物を著すことができるのです」と豪語し、百科全書を自動生成する機械を披露する。
表の面には、おおよそ骰子の大きさの――ただし一部はもう少し大きい――木片が並び、細い針金でたがいにつながっています。どの木片も、すべての面に紙が貼られ、それらの紙に、この国の言語の全単語が書いてあります。あらゆる時制、語形変化、直接法や仮定法等々すべての叙法も網羅していますが、ただし順番はバラバラになっています。[30]
この木片の並んだ装置を弟子たちが回転させると、そのつど新たな文が出力される。単語を網羅的にデータ化し、その膨大な順列組みあわせを試して、あらゆる分野の書物を自動生成する機械――それはAIの夢を先取りするものだろう。
この教授をはじめ、ラガードの学者たちは人間の労力を減らすための「進歩」に駆り立てられているが、それをスウィフトは諷刺的に描いている。オーウェルが注目したように、第三篇で描かれるプロジェクトが、言語の全体主義的なコントロールに通じることは確かだろう。『ガリヴァー旅行記』では、人間のみならず言語も量的なものであり、いかようにでも操作され変形される。
その後、ガリヴァーは降霊術を用いるグラブダドリッブ島で、偉人の亡霊(ホメロス、アリストテレス、デカルト……)に出くわした後、ラグナグ島で「ストラルドブラグ」と呼ばれる不死の人間たちを目撃するが、彼らは老醜をさらけ出し、身体も思考能力もむざんに衰え切っている。死ぬに死ねない不気味なゾンビのような不死人間たちは、長寿のおぞましさをその全身で表現していた。『ガリヴァー旅行記』において、ポストヒューマンな人工知能と不死の身体は、ときに滑稽で、ときにグロテスクなものとして描き出される。
すでに『ガリヴァー旅行記』に先立って、ライプニッツとニュートンが近代科学の礎を築いていた。スウィフトの驚くべき先進性は、この科学の欲望の帰結――人工知能からアンチエイジングまで――を見通し、諷刺の対象にしたことにある。後にゲーテが『ファウスト』で描いたように、近代の知的冒険はいずれ、人間の枠組みを超越したポストヒューマンな存在を生成するだろう。世界の量的操作をアカデミックな「プロジェクト」に仕立てた『ガリヴァー旅行記』の第三部は、この超越の運動が希望のない世界に到ることを暗示していた。
こうして、『ガリヴァー旅行記』の読者は馬の国で悪辣なヤフーに出会う前に、身体・知能・言語が可塑的なものであり、いかようにでも作り変えられるというクールでシニカルな認識を何度も突きつけられる(この人間の可塑性を全体主義的支配の前提と見なしたのが、後のオーウェルの『1984』である)。人間の象徴的な優位性をしつこく転覆するスウィフト的な教育――その極限に、ヤフー=人間を物理的に「絶滅」させようとする忌まわしい議論が現れるのだ。
-
第十章 絶滅――小説の破壊的プログラム|福嶋亮大(前編)
2024-02-16 07:00
1、冒険の形式、絶滅の形式
小説をそれ以前のジャンルと区別する特性は何か。この単純だが難しい問いに対して、ハンガリーの批評家ジェルジ・ルカーチは『小説の理論』(一九二〇年)で一つの明快な答えを与えた。彼の考えでは、小説とは「先験的な故郷喪失の形式」であり、寄る辺ない故郷喪失者である主人公は「冒険」を宿命づけられている。
小説は冒険の形式であり、内面性の固有価の形式である。小説の内容は、自らを知るために着物を脱いで裸になる心情の物語であり、冒険を求めて、それによって試練を受け、それによって自らの力を確かめながら、自らの固有の本質性を発見しようとする心情の物語である。[1]
ルカーチによれば、近代小説の主人公は「神に見捨てられた世界」でさまざまな試練をくぐり抜けながら、固有の魂を探し求める存在である。今でも多くの小説は、欠損を抱えた主人公の冒険の物語として書かれる。揺るぎない根拠を喪失し、世界とのギャップ(疎隔)を抱えた「ホームレス・マインド」(社会学者ピーター・バーガーの表現)が、冒険によって固有の何かを獲得したり、あるいは獲得し損ねたりする――このような精神の運動が小説というジャンルには刻印されている。
ゆえに、近代小説は安定した意味の宇宙をあてにできない。ルカーチが言うように、神に見捨てられ、世界との「疎遠さ」を宿命づけられた小説的冒険は「絶対的に解消されない不協和」を内包している。いかなる「生」も世界とぴたりと意味的に一致することはない。この本質的なギャップゆえに、ルカーチの言う「冒険の形式」はセルバンテスの『ドン・キホーテ』以降、デモーニッシュな狂気と不可分であった[2]。絶対的な根拠=故郷をもたないまま、自己を脱ぎ捨てて冒険に乗り出す試みは、それ自体が狂気じみたエネルギーを要求したのだ。
精神的なホームをもたない小説の主人公は、自己の魂の探究と再創造という冒険に向かう――ルカーチがこの仕組みを理論的に明示したことの価値は揺るぎない。ただ、彼の力点はあくまで冒険者の「生」(主観)の側にあり、冒険のなされる「世界」の様相については深く考察されなかった。第一次大戦とロシア革命という大事件の後、祖国ハンガリーからの亡命直後にルカーチが刊行した『小説の理論』は、確かに「世界の崩壊とその不完全さ」や「世界構造の脆弱性」に言及するものの[3]、この黙示録的なテーマはあくまで理論の周縁に留め置かれた。
この弱点を修正するために、私は冒険の形式の裏面に、もう一つの別の形式を想定したい。それを今「絶滅の形式」と呼ぼう。その前駆的形態はやはりセルバンテスの作品に認められる。
アルジェでの捕虜生活から解放された帰還兵セルバンテスは、『ドン・キホーテ』で名声を得る以前の一五八〇年代に、紀元前二世紀のスペインを舞台とする歴史劇の傑作『ヌマンシアの包囲』を書いた。小スキピオ率いるローマ軍に包囲されたスペインの都市ヌマンシアは、飢餓と病気が蔓延し、すでに勝利の見込みをなくしている。そのとき、占領の恥辱を受けることを潔しとしないヌマンシア人は、すべての財産を燃やし、家を焼き払い、街の全員を自ら殺戮し、統治者も自ら火中に身を投じることを決断した。その結果、スキピオ将軍の部下の報告によれば「ヌマンシアは赤い血の湖と化し、みずからの苛酷な決断によって殺された無数の死骸に埋まっています。彼らは恐怖をかなぐり捨て、迅速な大胆さを発揮して、他に類を見ないほど重くも辛い隷属の鎖から逃れることができたのです」[4]。
これはまさに自分自身に対して行使されたジェノサイドである。後の『ドン・キホーテ』は汲めども尽きぬ旺盛な語りの力によって、幻想の解体と再生産を推し進めた。逆に、古代ギリシア演劇にも通じる風格をもつ『ヌマンシアの包囲』は、そのようなアイロニカルな「語り」そのものを殲滅する過酷な暴力性を前景化する。ヌマンシア人の迅速にして徹底した自己破壊は、ローマ軍の勝利すら空虚な敗北に変えてしまう。「ヌマンシア人は、みずからの敗北から勝利を引き出しました。驚嘆すべき意志と志操の固さを発揮して、将軍の手から勝利を奪い去ったのです」[5]。つまり、この作品の根幹には、都市の絶滅だけが解放=勝利につながるという恐ろしい逆説がある。
この勝利と敗北の反転は、後の『ドン・キホーテ』では狂気とユーモアによって遂行される。ラマンチャの憂い顔の騎士は、語りによって事象を引き延ばしながら、外見的にはみじめな敗北を勝利として解釈する。他方、戯曲『ヌマンシアの包囲』のジェノサイドは、一切の遅延や躊躇なしに、既定のプログラムとして粛々と実行された。『ドン・キホーテ』が近代小説の祖だとしたら、『ヌマンシアの包囲』で作動する自己破壊のプログラム(フロイトふうに言えば「死の欲動」)は、近代小説に先立つおぞましい原風景と呼べるものである。セルバンテスにおいて、冒険と絶滅はコインの裏表の関係にあった。
1 / 7
次へ>