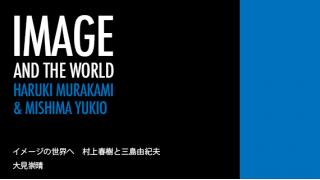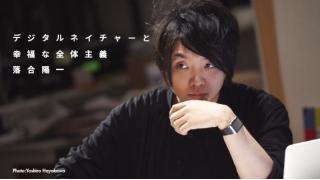-
加藤るみの映画館(シアター)の女神 2nd Stage ☆ 第4回『小さな園の大きな奇跡』『マダム・イン・ニューヨーク』【毎月第4木曜配信】 ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.690 ☆
2016-09-15 07:00チャンネル会員の皆様へお知らせ
PLANETSチャンネルを快適にお使いいただくための情報を、下記ページにて公開しています。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/ar848098
(1)メルマガを写真付きのレイアウトで読む方法について
(2)Gmail使用者の方へ、メルマガが届かない場合の対処法
(3)ニコ生放送のメール通知を停止する方法について
を解説していますので、新たに入会された方はぜひご覧ください。
加藤るみの映画館(シアター)の女神 2nd Stage第4回『小さな園の大きな奇跡』『マダム・イン・ニューヨーク』【毎月第4木曜配信】
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2016.9.15 vol.690
http://wakusei2nd.com
今朝のメルマガは、加藤るみさんの連載『加藤るみの映画館(シアター)の女神 2nd Stage』第4回をお届けします。今回取り上げるのは女性が活躍する2本。るみさんが涙、涙の感動作と語る香港映画『小さな園の大きな奇跡』と、NYを舞台にしたインド映画『マダム・イン・ニューヨーク』です。
▼執筆者プロフィール
加藤るみ(かとう・るみ)
1995年3月9日生まれ。岐阜県出身。サンミュージックプロダクション所属のタレント。映画鑑賞をはじめ、釣り、世界遺産、料理、カメラ、アニメと多趣味を活かしてマルチに活躍中。インターネットラジオK'z Station『おしゃべりやってま~すRevolution』にレギュラー出演中。雑誌『つり情報』でコラムを連載中。
本メルマガで連載中の『加藤るみの映画館(シアター)の女神』、過去記事一覧はこちらのリンクから。
前回:加藤るみの映画館(シアター)の女神 2nd Stage ☆ 第3回『ショート・ターム』『マン・アップ 60億分の1のサイテーな恋のはじまり』【毎月第3木曜配信】
どうも! 加藤るみです。
夏が終わり、秋の始まりを告げようとしている今日この頃
皆さん、いかがお過ごしでしょうか?
この夏は、日本中が『シン・ゴジラ』に興奮した夏だったと言っても過言ではないでしょう。
2回劇場に行ってみて気づいたのは、上映後、
「なんかわからないけどスゴイ」という声が四方八方から聞こえてきたこと。
私の持論ですが、映画って「面白い」「面白くない」と言う前に
「スゴイ」という言葉が出たらもうOKな気がするんですよね。
それは、私が『マッドマックス 怒りのデス・ロード』を初めて観た時に思ったことで、
この『シン・ゴジラ』の凄まじさは日本映画の歴史に残ると思います。
今回『シン・ゴジラ』を観た人と何回か『シン・ゴジラ』談義をしてきましたが、
私の周りでは、「この映画を観ればもう今年の邦画は何も観なくていい」
というほどの、大絶賛の声ばかりでした。
「今の日本に本当にゴジラが現れたら……」
日本映画の一流のスタッフ陣が本気で描いた『シン・ゴジラ』は、
もはや現代のアイコンになりつつある映画だと思います。
そんな『シン・ゴジラ』に始まり、
『ゴーストバスターズ』や『ジャングル・ブック』『ペット』など 、
今年の夏映画は豊作祭りでしたね。
今回紹介する映画は、そんな大作に引けを取らない、
私が得意なミニシアター系の感動作、女性が活躍する香港映画とインド映画です!
11月公開の新作映画『小さな園の大きな奇跡』と、
インドのマダムに勇気をもらえる映画『マダム・イン・ニューヨーク』。
日本ではまだまだ馴染みの薄いアジアの映画、ぜひたくさんの方に観ていただきたいです。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は今月も厳選された記事を多数配信します! すでに配信済みの記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201609
-
橘宏樹『現役官僚の滞英日記』最終回「イギリスから何を学ぶか」【毎月第2水曜配信】☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.689 ☆
2016-09-14 07:00チャンネル会員の皆様へお知らせ
PLANETSチャンネルを快適にお使いいただくための情報を、下記ページにて公開しています。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/ar848098
(1)メルマガを写真付きのレイアウトで読む方法について
(2)Gmail使用者の方へ、メルマガが届かない場合の対処法
(3)ニコ生放送のメール通知を停止する方法について
を解説していますので、新たに入会された方はぜひご覧ください。
橘宏樹『現役官僚の滞英日記』最終回「イギリスから何を学ぶか」
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2016.9.14 vol.689
http://wakusei2nd.com
今朝のメルマガは橘宏樹さんの『現役官僚の滞英日記』最終回をお届けします。今回は、約2年にわたった連載の総まとめとして、マネジメント手法、外交戦略、コミュニケーションにおける日英の違いから何を学ぶべきかについて論じます。
▼プロフィール
橘宏樹(たちばな・ひろき)
官庁勤務。2014年夏より2年間、政府派遣により英国留学中。官庁勤務のかたわら、NPO法人ZESDA(http://zesda.jp/)等の活動にも参加。趣味はアニメ鑑賞、ピアノ、サッカー等。
本メルマガで連載中の橘宏樹『現役官僚の滞英日記』これまでの配信記事一覧はこちらのリンクから。
※本稿の内容(過去記事も含む)に関して、皆様からのご質問や、今後取材して欲しいことを受け付けたいと思います。こちらのフォームまたはTwitter(@ZESDA_NPO)にお寄せいただければ、できるかぎりお応えしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
前回:ブリティッシュ・ドリームの叶え方――英国版「わらしべ長者」と3つのキャピタリズム(橘宏樹『現役官僚の滞英日記 オクスフォード編』第10回)
おはようございます。橘です。早いもので今号が本連載の最終回となります。帰国して1か月が経ち、僕は官庁の通常業務に復帰しております。2年前と同じ建物のなかで同僚との日々を再開しておりますと、離任する前と時間が急に接続するようで、あれれ、僕はずっとここに座っていたのではないか、という思いが一瞬去来することがあります。
しかし、ロンドンやオクスフォードで出来た友人たちとは、それぞれ母国に帰ってもちょこちょことしたやり取りが続いています。SNSでは世界中の友達の近況がわかるのは素晴らしいですね。オリンピックのときはLSEでのブラジル人クラスメイトと長いことチャットをしました。また、最近は、オクスフォードのクラスメイト(アメリカ人)が日本に遊びにきて、拙宅に1週間泊まっていきました。一緒に『ガンダムUC』を毎晩一話ずつ観たり、『シン・ゴジラ』を観に行ったりしました。ほかにも日本で職を得ようと長期滞在している友人もいて、ちょくちょく遊んでいます。やはり夢ではなかったわけです。背景画像がオクスフォードから東京に差し替わっている違和感を楽しんでいます。
さて、今回は、2年間の留学の総括として、イギリスから日本が学べることをまとめてみたいと思います。
まず、昨今日本への導入が進んでいる「コーポレート・ガバナンス」というアングロ・サクソン的経営手法のルーツや必然性をイギリスで目の当たりにする中で、善し悪しについて思うところがあったので、それについて書きます。それから、個人的に日本がイギリスから学ぶべきだと思う点について、やや具体的な提案も含めて述べてみたいと思います。
▲国会議事堂と皇居。戦場に戻ってきました。
▲戻ってきました霞が関の官庁街。みんな遅くまで働いています。
■コーポレート・ガバナンスと貴族支配
まず、いわゆる「コーポレート・ガバナンス」と呼ばれるアングロ・サクソン流意思決定・経営手法の根本的な特徴は、ざっくり言ってしまうと「経営と執行の完全な分離」、そしてそれを前提にした「トップ・ダウン形式」だと思います。方向性や戦略など組織の意思決定を行い、執行過程を管理するのが「経営」、決定内容通りに実行するのが「執行」です。コーポレート・ガバナンスではこの二つをしっかり切り離すことが要諦とされています。経営者は、執行過程をしっかりウォッチして、評価したり次の行動を思案したりします。ですから、適切な経営判断を支える情報を確保するために、売上やコストなどのあらゆるデータ、各種判断や実行の根拠などを、執行者に明らかにさせます(透明性・説明責任)。説明要求と経営指示を繰り返すことによって「PDCAサイクル」を徹底的に回すわけです。株主や投資家は取締役会に対して、取締役会は執行役員以下の高級労働者に対して、ホワイトカラーはブルーカラーに対して、このような管理を行う階層構造があります。
ポイントは、経営者と執行者(労働者)では、持っているスキルも生き様もまったく違うということにあります。
経営者は、利潤追求が至上命題です。上から俯瞰し要所を突いて指示を与えます。情報収集、分析、計画立案能力が重要です。どういう数値を提出させればよいか。それらをどう読み解くか。数値の精度をどのように担保するか、アメとムチをどう設計するか、などが問われます。他方で、極端に言うと、素晴らしい何かを自分の手で創り出す実力、従業員を鼓舞したり共に汗して先導したりするリーダーシップ、職場のコミュニティの中で信頼される人間力などは要らないのです。要するに「上から目線で」「情報を見ているだけ」だけれども、「正鵠を得て」、「他人に」目的を達成「させる」能力が問われるのです。そのために、競馬場や晩餐会の機会に、閉じられたコミュニティの中で決定的な情報交換をして、前号で描写したように、「コネ」と「チエ」を「カネ」に変える算段をするところで、勝負をしています。
ブリティッシュ・ドリームの叶え方――英国版「わらしべ長者」と3つのキャピタリズム(橘宏樹『現役官僚の滞英日記 オクスフォード編』第10回)
そしてそれは、出自や学歴を大きく共有するなど、高い同質性を前提にした、お互いの知性やコネクションの広さ、秘密に対するモラルを信頼しあえる関係があるから成り立つのです。さらに言うと、たとえば英国議会ではオープンな空間で、大人数が同時に参加し、徹底した高度な議論が闘われており、熟議型議会政治の最高峰として世界中の羨望を集めていますが、あの場のディベートの成員もみなオックス・ブリッジ出身で、批判能力・議論能力を徹底的に鍛え上げられた高い同質性を有した者同士だからこそ可能なのです。
僕の目には、むしろ日本の国会議員の方が出自に多様性があり、英国議会に比して国民全体を箱庭的に代表しているように思います。だからこそ、持てる能力や性質が千差万別となります。そうした人々の集団内で合意形成を図るためには、密室で少人数が集まり、相手によって説明方法や言葉すら変えながら、皆に信頼される「調整役」が汗をかいて、一貫性を保つというごまかすようなスキルを駆使する「根回し」を展開することで、コミュニケーション・コストを贖(あがな)う必要がどうしても大きくなってきてしまいます。
これを「不透明だ」と(特に、根回ししてもらえなかった人々が)非難することにも理はあると思いますから、なかなか難しいところです。もちろん、こうした「根回し」は英国でも行われている思いますが、なるべくオープンな議論の場を使うことで、コミュニケーション・コストを抑えていると思います。
▲オクスフォード街中のバー。屋上テラスで夜更けまで楽しめました。
▲聖メアリー教会とラドクリフ・カメラ。オクスフォード大学を象徴する2トップです。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は今月も厳選された記事を多数配信します! すでに配信済みの記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201609
-
大見崇晴『イメージの世界へ 村上春樹と三島由紀夫』補論 記号と階級意識(後編)【不定期連載】 ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.688 ☆
2016-09-13 07:00チャンネル会員の皆様へお知らせ
PLANETSチャンネルを快適にお使いいただくための情報を、下記ページにて公開しています。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/ar848098
(1)メルマガを写真付きのレイアウトで読む方法について
(2)Gmail使用者の方へ、メルマガが届かない場合の対処法
(3)ニコ生放送のメール通知を停止する方法について
を解説していますので、新たに入会された方はぜひご覧ください。
大見崇晴『イメージの世界へ 村上春樹と三島由紀夫』補論 記号と階級意識(後編)【不定期連載】
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2016.9.13 vol.688
http://wakusei2nd.com
今朝のメルマガでは大見崇晴さんの『イメージの世界へ 村上春樹と三島由紀夫』の補論、「記号と階級意識」の後編をお届けします。
永山則夫から加藤智大に至るまで、現代の無差別殺人の特徴は、そのあまりの「凡庸さ」にあります。昭和から平成まで断続的に発生している「メッセージなき犯罪」。その根底にある、コミュニケーションの不全性について論じます。
▼プロフィール
大見崇晴(おおみ・たかはる)
1978年生まれ。國學院大学文学部卒(日本文学専攻)。サラリーマンとして働くかたわら日曜ジャーナリスト/文藝評論家として活動、カルチャー総合誌「PLANETS」の創刊にも参加。戦後文学史の再検討とテレビメディアの変容を追っている。著書に『「テレビリアリティ」の時代』(大和書房、2013年)がある。
本メルマガで連載中の『イメージの世界へ』配信記事一覧はこちらのリンクから。
前回:大見崇晴『イメージの世界へ 村上春樹と三島由紀夫』補論 記号と階級意識 〜消費・要請・演技・自意識・幸福・アルゴリズム〜【不定期連載】
3.演技と消費
消費社会が訪れたことを、若者批判を介して明らかにしようとしていた人物がいる。その人物もまた、寺山修司だった。
当時すでに『書を捨てよ、町へ出よう』や『ドキュメンタリー家出』などで知られていた寺山修司は、若者たちの「自立」や「反抗」を代弁する人物に思われがちだ。しかし、よく読めば彼は一貫して新左翼によるテロリズムに対して疑いを持ち続けていた。社会主義・共産主義の激戦地域だったベトナムに向かわず、アラブや北朝鮮に亡命していった日本赤軍派の宣伝主義的な疚しさを寺山修司は視界に収めている。若者たちは自己実現のために反抗的な若者を演じ、それにふさわしい舞台を探しているのではあるまいか? 寺山修司の評論は当時の若者たちが抱えていた疚しさを見逃さない。引用魔として知られた寺山は経済学者ヴェブレンの言を引いて論じる。
(略)爆弾を投げて戦死した奥平剛士の死は、政治的にだけ解明しようとしても解明できるものではない。彼には、表現したい願望があり、それが彼の参加の理由でもあった。「もはや消費が自己顕示の手段として有効ではありえない時代では、あとはじぶんの命を浪費することによって自己顕示する手段がのこされる」(ベブレン「有閑階級の理論」)。
日本赤軍は自己顕示のために自らの命を浪費した部分が存在すると、寺山は分析する。つまり、日本赤軍に属した奥平の死に、政治によって社会を変革する以外のことが強く存在すると看る。寺山は自死も厭わぬテロに消費主義を見出す。「持つこと」、所有のための対価を支払うことを超えた消費である。言うなれば、何者かを演技するために必要な衣裳の所有することをも超越した消費主義である。消費の対象は自らの生命に達する。そこにあるのは、演技の果てに、依頼もなく死地に向かう人間である。永山と同時代に、階級や階層を無くそうとした(共産主義に熱中した)若者の末路には、こうした消費主義の極限が待ち受けていた。
顧みれば、これほどまでに消費に飽き足らなかった若者たちが、消費のない世界を思い描いて行動することでしか、消費というエクスタシーの享受が不可能だったのが、昭和元禄(一九六四)と呼ばれた高度成長期を迎えた日本だったのである。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は今月も厳選された記事を多数配信します! すでに配信済みの記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201609
-
月曜ナビゲーター・宇野常寛 J-WAVE「THE HANGOUT」9月5日放送書き起こし! ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.687 ☆
2016-09-12 07:00チャンネル会員の皆様へお知らせ
PLANETSチャンネルを快適にお使いいただくための情報を、下記ページにて公開しています。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/ar848098
(1)メルマガを写真付きのレイアウトで読む方法について
(2)Gmail使用者の方へ、メルマガが届かない場合の対処法
(3)ニコ生放送のメール通知を停止する方法について
を解説していますので、新たに入会された方はぜひご覧ください。
月曜ナビゲーター・宇野常寛J-WAVE「THE HANGOUT」9月5日放送書き起こし!
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2016.9.12 vol.687
http://wakusei2nd.com
大好評放送中! 宇野常寛がナビゲーターをつとめるJ-WAVE「THE HANGOUT」月曜日。前週分のラジオ書き起こしダイジェストをお届けします!
▲先週の放送はこちらからご覧いただけます!
■オープニングトーク
宇野 時刻は午後11時30分を回りました。みなさんこんばんは、宇野常寛です。そして松岡茉優さん、今夜も生放送お疲れ様でした! 松岡さん、こうやってガラス越しに話すのも、今日を入れてあと4回になってしまいました。はい、「THE HANGOUT」は終わります! 超終わります。僕が出なくなるだけではなくて、月から木までの全部が終わります。いきなり大告白してしまいました。
こうやって松岡さんとガラス越しに会えなくなるのは本当に悲しいですけれど、僕はいつまでもあなたのことを応援しています。僕のことも忘れないでくださいね。いつか「スッキリ!!」にも来てください。まあ、来てくれる頃には、僕が「スッキリ!!」の方もクビになってるかもしれないですけれどね。絶対に木曜日に来てくださいね。
ということで。まあ終わっちゃいますね。どこから話したらいいのかな。8月の頭ぐらいに、日浦プロデューサーにちょっと呼ばれて「番組が終わります」と言われたんですね。2014年の10月から始まっているので、もう2年やってますからね。まあ、早くもなく遅くもなく、おそらくは通常のJ-WAVEの番組サイクルだと思います。だから終わりが来るということ自体は、正直次の改編か、次の次か、ぐらいに僕は思っていました。実際は思っていたよりも若干早かったかなという感触はありますけれどね。僕が非常に悔しかったのは、こう言うのもなんですが、月曜ってそこそこ人気があったんですよ。他の曜日が人気ないわけじゃないですよ。ただ、特にインターネットの人気に関して言えば、たぶん月曜日がダントツだったと思います。それはYouTube Liveのアーカイブの再生数だったりとか、メールの数だったりとか、あとはTwitterのハッシュタグがよくトレンドに入っていたんですよね。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は今月も厳選された記事を多数配信します! すでに配信済みの記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201609
-
京都精華大学〈サブカルチャー論〉講義録 第8回 富野由悠季とリアルロボットアニメの時代(後編)(毎週金曜配信「宇野常寛の対話と講義録」) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.686 ☆
2016-09-09 07:00チャンネル会員の皆様へお知らせ
PLANETSチャンネルを快適にお使いいただくための情報を、下記ページにて公開しています。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/ar848098
(1)メルマガを写真付きのレイアウトで読む方法について
(2)Gmail使用者の方へ、メルマガが届かない場合の対処法
(3)ニコ生放送のメール通知を停止する方法について
を解説していますので、新たに入会された方はぜひご覧ください。
京都精華大学〈サブカルチャー論〉講義録第8回 富野由悠季とリアルロボットアニメの時代(後編)(毎週金曜配信「宇野常寛の対話と講義録」)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2016.9.9 vol.686
http://wakusei2nd.com
今朝のメルマガは「京都精華大学〈サブカルチャー論〉講義録」をお届けします。今回は『ガンダム』以後のロボットアニメについてです。ガンダムが開拓した「リアルロボットアニメ」という可能性からは、『超時空要塞マクロス』や『装甲騎兵ボトムズ』『聖戦士ダンバイン』といった作品が生まれます。ここから、80年代に起きた時代感覚の変化や、新しい社会に対する批評性の萌芽を読み解きます。(この原稿は、京都精華大学 ポピュラーカルチャー学部 2016年5月13日の講義を再構成したものです)
毎週金曜配信中! 「宇野常寛の対話と講義録」配信記事一覧はこちらのリンクから。
前回:京都精華大学〈サブカルチャー論〉講義録 第8回 富野由悠季とリアルロボットアニメの時代(前編)(毎週金曜配信「宇野常寛の対話と講義録」)
■「三角関係のBGM」としての最終戦争――『超時空要塞マクロス』
『超時空要塞マクロス』(TV版は1982年放映開始/劇場版『超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか』は1984年公開)は今に続くマクロス・シリーズの第1作で、宇宙戦争ものであると同時に宇宙人との「ファーストコンタクト」を描いた作品でもありました。地球人と「ゼントラーディ」という宇宙人が遭遇して戦争が起き、主人公の一条輝(いちじょうひかる)はパイロットとして活躍していくという物語ですね。
ところが『マクロス』の本題はそこじゃありません。宇宙戦争でもなければファーストコンタクトでもなく、主人公と二人の女性との三角関係です。ヒロインの一人目は、もともと輝の近所の友達で、やがてアイドルデビューしていくリン・ミンメイ。放送当時の80年代前半、松田聖子や中森明菜などに代表されるアイドルブームがあって、それを背景に設定されたキャラクターです。声を当てていたのも飯島真理というアイドルでした。もう一人は、輝の上官である早瀬未沙という歳上の女性キャラクターです。そして主人公の輝くんは、延々と「アイドルデビューした友達と仕事で知り合った美人上司のどっちと付き合うか?」という、まあ、端的に言って極めてどうでもいいことについて悩むことになります。でも、この「どうでもいいこと」が真面目な話を押しのけて本題になる感じが、1980年代にはクールだったわけです。「政治の季節」の反動ですね。「意味のない」ものをでかでかと掲げることが、一番批評的な態度だった。
現在まで続くマクロスシリーズはすべてこれを基本にしています。最近の『マクロスF(フロンティア)』もそうでしたし、今度の『マクロスΔ(デルタ)』もおそらくそうなっていくだろうと思います。だいたいの場合、メインヒロインがフラれるパターンが多いんです。この第1作でも、輝は結局上司の早瀬未沙と付き合うことにして、メインヒロインのはずのリン・ミンメイがフラれてしまう。まあ「アイドルは恋愛しちゃいけない」という事情もあるんでしょうね(笑)。
『マクロス』にはもうひとつ面白い側面があります。そもそも敵として出てくるゼントラーディは文化を失った戦闘民族なんですね。だからアイドルの歌を聴くと感動して戦争するのをやめてしまう。これはマクロスシリーズを知らない人には突飛な設定に見えるかもしれませんが、80年代当時の若者たちの感覚をよく表していると思います。
これ、さっき説明した「意味のない」ことを追求することこそが意味がある、という当時の世相と関係しています。80年代の若者は「戦って世の中を良くしていく」ということに対して醒めていた。というか、それが知的であることの条件ですらあった。だからアイドルやアニメのようなサブカルチャーに「あえて」耽溺してみせること、がクールだったわけですね。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は今月も厳選された記事を多数配信します! すでに配信済みの記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201609
-
落合陽一『デジタルネイチャーと幸福な全体主義』第2回 デジタルネイチャー時代の『人間機械論』(後編) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.685 ☆
2016-09-08 07:00チャンネル会員の皆様へお知らせ
PLANETSチャンネルを快適にお使いいただくための情報を、下記ページにて公開しています。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/ar848098
(1)メルマガを写真付きのレイアウトで読む方法について
(2)Gmail使用者の方へ、メルマガが届かない場合の対処法
(3)ニコ生放送のメール通知を停止する方法について
を解説していますので、新たに入会された方はぜひご覧ください。
落合陽一『デジタルネイチャーと幸福な全体主義』第2回 デジタルネイチャー時代の『人間機械論』(後編)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2016.9.8 vol.685
http://wakusei2nd.com
今朝は『デジタルネイチャーと幸福な全体主義』第2回の後編をお届けします。今回は、ノーバート・ウィーナーの『人間機械論』をベースに構想するデジタルネイチャーの社会論です。単一のコンピュータが人間を支配するディストピア的な社会観を超えて、各人向けにカスタマイズされたコンピュータを仲介に集合知と繋がる、新しい社会構造の仕組みを考えます。
【発売中!】落合陽一著『魔法の世紀』(PLANETS)
☆「映像の世紀」から「魔法の世紀」へ。研究者にしてメディアアーティストの落合さんが、この世界の変化の本質を、テクノロジーとアートの両面から語ります。
(紙)/(電子)
取り扱い書店リストはこちらから。
▼プロフィール
落合陽一(おちあい・よういち)
1987年東京生まれ。東京大学大学院学際情報学府博士課程を飛び級で修了し、2015年より筑波大学に着任。コンピュータとアナログなテクノロジーを組み合わせ、新しい作品を次々と生み出し「現代の魔法使い」と称される。研究室ではデジタルとアナログ、リアルとバーチャルの区別を越えた新たな人間と計算機の関係性である「デジタルネイチャー」を目指し研究に従事している。
音響浮揚の計算機制御によるグラフィクス形成技術「ピクシーダスト」が経済産業省「Innovative Technologies賞」受賞,その他国内外で受賞多数。
◎構成:長谷川リョー
『デジタルネイチャーと幸福な全体主義』これまでの連載はこちらのリンクから。
前回:落合陽一『デジタルネイチャーと幸福な全体主義』第2回 デジタルネイチャー時代の『人間機械論』(前編)
▼ニコ生放送時の動画はこちらから!
http://www.nicovideo.jp/watch/1467959618
放送日:2016年6月28日
◼︎人間知性をコンピュータの知性が補完する新しい協業関係
前編では、「コンピュータが〈人間の補集合〉を作るようになる」というところまで、議論を進めましたが、これは一体どういう意味を持つのでしょうか。
我々の知性には限界があります。一人の人間が知り得る物事は、この世界全体の持っている情報量からすると、あまりにも少なすぎます。しかし、もしAさんが知らないことの全てを代わりにコンピュータが把握してくれるようになれば、それは、Aさんが考えつかないアイディアを提案する装置になっていく。
この〈人間の補集合〉としてのコンピュータは、現実化しつつあります。たとえば、日立製作所はウェアラブル技術で「幸福度を測る装置」を発表していますし、あるいはFacebookが開発していると噂される「自殺しそうな人を特定するシステム」も、(ややディストピア的ではありますが)そのひとつかもしれません。
これらが意味するのは、我々自身について、すでに自分よりもコンピュータの方が詳しくなりつつあるということ、自分の知らないことまでコンピュータが把握しているという状況です。たとえばスマホもそのひとつです。昨日の朝食に何を食べたか、スマホに残っている写真を見て思い出したなら、それはすでにスマホの方が自分に関する記録をより多く持っているということです。
これは、生まれたときからスマホに全情報を蓄積している世代が大きくなったときに、より大きな意味を持つでしょう。誕生以降のすべての記憶をクラウドにバックアップすることで、生涯の全記録をいつでも取り出せるようになる。それは、人間の記憶よりも遥かに巨大な容量のメモリを用いた、過去へと向かうタイムマシンのようなものです。
先日、講演を行ったある中学校では、生徒の全員が21世紀生まれで、99%がスマートフォンを持っていました。彼らが大人になったとき、特定の日時の情報を引っ張り出して、自分がそのとき何をしていたのかを容易に振り返ることが可能になるはずです。
このように、人間と機械が新しい関係の元で対峙したときに、これまでの人類社会ではありえなかった価値観が生み出されつつあります。
たとえばTwitterには、Botと変わらないような行動をしている人間がたくさんいます。特定の有名人に粘着してリプライする、その人の「ツイート検知器」みたいになっている人もいますね。そんな人と、Microsoftが開発した女子高生AIの「りんな」を比べれば、後者の方がはるかに人間的でしょう。これは人間が機械的になり、機械が人間的になりつつある状況の一例だと思います。
もちろん、人工知能の「人格」をいかに定義するかについては、様々な議論があると思いますが、そこで行われている入力された情報に対する処理は、人間並みに複雑になっているはずです。逆にいえば、我々人間も、ある統計的な情報に基いて、言葉や行動の形で情報を出力しているに過ぎない。統計的な情報であれば、コンピュータにも人間と同様に蓄積できるはずです。その出力手段としての「言語」は、確かに複雑な体系を持っていますが、有限個の組み合わせである以上、人格の存在を推測しうるレベルの高度な情報の伝達が、いずれ行えるようになるのではないか。そういうことが明らかになりつつあるのが2016年の世界です。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は今月も厳選された記事を多数配信します! すでに配信済みの記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201609
-
猪子寿之の〈人類を前に進めたい〉第12回「自分と〈世界〉を一体化させたい!」【毎月第1水曜配信】 ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.684 ☆
2016-09-07 07:00チャンネル会員の皆様へお知らせ
PLANETSチャンネルを快適にお使いいただくための情報を、下記ページにて公開しています。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/ar848098
(1)メルマガを写真付きのレイアウトで読む方法について
(2)Gmail使用者の方へ、メルマガが届かない場合の対処法
(3)ニコ生放送のメール通知を停止する方法について
を解説していますので、新たに入会された方はぜひご覧ください。
猪子寿之の〈人類を前に進めたい〉第12回「自分と〈世界〉を一体化させたい!」【毎月第1水曜配信】
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2016.9.7 vol.684
http://wakusei2nd.com
今朝のメルマガは、チームラボ代表・猪子寿之さんによる連載『猪子寿之の〈人類を前に進めたい〉』の第12回です。今回は『Pokemon GO』や『シン・ゴジラ』などのヒットコンテンツを分析しながら、チームラボ作品がいかにしてそれらの作品と闘えるかについて話しました。新作『カラス』や表参道の展示を通じて考えた、「展示方法」と「作品」の概念の拡張とは――?
▼プロフィール
猪子寿之(いのこ・としゆき)
1977年、徳島市出身。2001年東京大学工学部計数工学科卒業と同時にチームラボ創業。チームラボは、プログラマ、エンジニア、CGアニメーター、絵師、数学者、建築家、ウェブデザイナー、グラフィックデザイナー、編集者など、デジタル社会の様々な分野のスペシャリストから構成されているウルトラテクノロジスト集団。アート・サイエンス・テクノロジー・クリエイティビティの境界を曖昧にしながら活動している。
47万人が訪れた「チームラボ 踊る!アート展と、学ぶ!未来の遊園地」などアート展を国内外で開催。他、「ミラノ万博2015」の日本館、ロンドン「Saatchi Gallery」、パリ「Maison & Objet」など。2月からシリコンバレー「teamLab: Living Digital Space and Future Parks」、イスタンブール「Borusan Contemporary」、5月はバンコク「Central World」、また3月からシンガポールで巨大な常設展「FUTURE WORLD: WHERE ART MEETS SCIENCE」開催中。
http://www.team-lab.net
◎構成:稲葉ほたて
本メルマガで連載中の『猪子寿之の〈人類を前に進めたい〉』配信記事一覧はこちらのリンクから。
前回:猪子寿之の〈人類を前に進めたい〉第11回「身体でアートへ没入し、世界との境界を無くせ!」
■ジョン・ハンケと猪子寿之の違い
宇野 猪子さん、『Pokemon GO』やってる? 僕はまだレベル8くらいで止まっているんだけど。
猪子 いや、リリースされた直後は超やってたんだけどね……。宇部市ときわ公園で「呼応する森」という展示をしてて、ちょうどその出張中に始めたの。
▲山口県宇部市ときわ公園で開催された「呼応する森」
宇部市って彫刻が多い街なんだけど、『Pokemon GO』をやっていると「あ、こんなところに彫刻が!」という発見がたくさんあってすごく楽しかった。それで、東京に帰ってきてからもその勢いでやっていたんだけど、よくよく考えたら俺の東京の生活って自宅と会社の往復ばかりで、本当につまらないわけ(笑)。もはや『Pokemon GO』がつまらないのか俺の人生がつまらないのか……という問題に直面してしまったわけだよ。
宇野 俺は『Ingress』のときもハマってたんだけど、やっぱり2〜3か月でやめちゃったんだよね。奇しくも『Ingress』のおかげで「こういうものに気をつけて歩くと面白いスポットが見つけられる」という散歩のコツがわかってきて、要するにゲームという支援装置が要らなくなってしまったんだよね。
でも、『Ingress』と『Pokemon GO』を作った元Google副社長のジョン・ハンケは「ゲームの力で人を外で歩かせることが目的なんだ」というようなことを言ってて、両作ともそれ自体は達成されてはいるんだよ。
▲『Ingress』プレイ画面
【参考】
宇宙の果てでも得られない日常生活の冒険――Ingressの運営思想をナイアンティック・ラボ川島優志に聞く ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.246 ☆
猪子 でも、その後が続かないってことだよね。『Pokemon GO』はひたすらアイテムやポケモンをとるのみで、街とか全く見なくなっちゃった。周りを見ていても、みんな途中からAR機能は切っているしね。
宇野 へー、僕はまだ切っていないけどね。あのビジュアルはやっぱりいいと思うから。
猪子 それは珍しいね。結局ゲームって、ある種の報酬制度を使った中毒性でできていると思うんだけど、それが目的化しちゃうとパチンコと一緒でひたすらその報酬を求めるのみになっちゃうんだよ。ただの中毒患者としてやらされてる感じで、今はプレイするのが嫌だもん(笑)。
宇野 ただ、まずは世界中のゲームとか全くやったことのないおばちゃんとかにARゲームをやらせるということが彼らの目的だったと思うんだよ。『Ingress』は敷居が高くて、暇なインテリしかやってなかったけれど、『Pokemon GO』でその敷居を下げることには成功したとは思う。この先、封印していた機能もどんどん解放されるだろうしね。プレイヤー同士のモンスター交換とか。
なんで『Pokemon GO』の話をしたかというと、最近のチームラボの作品って、ジョン・ハンケとは違うかたちで、テクノロジーの力を使って「人間が世界を眺める視線」に介入していると思うんだよね。
猪子 どういうこと……?
【ここから先はチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は今月も厳選された記事を多数配信します! すでに配信済みの記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201609
-
『ドラがたり――10年代ドラえもん論』(稲田豊史)最終回 人生はチョコレートの箱 ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.683 ☆
2016-09-06 07:00チャンネル会員の皆様へお知らせ
PLANETSチャンネルを快適にお使いいただくための情報を、下記ページにて公開しています。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/ar848098
(1)メルマガを写真付きのレイアウトで読む方法について
(2)Gmail使用者の方へ、メルマガが届かない場合の対処法
(3)ニコ生放送のメール通知を停止する方法について
を解説していますので、新たに入会された方はぜひご覧ください。
『ドラがたり――10年代ドラえもん論』(稲田豊史)最終回 人生はチョコレートの箱
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2016.9.6 vol.683
http://wakusei2nd.com
今朝は稲田豊史さんの連載『ドラがたり』の最終回をお届けします。藤子・F・不二雄が生涯をかけて追い求めたテーマ「世界の創造」と「運命の改変」。そこには、思い通りの世界を創造する「箱庭作り」と、配偶者を再選択する「人生のやり直し」という、作者の直裁的な願望が見え隠れします。大人になった私たちは、Fが残した物語から何を学べるのか。不本意な「チョコレートの箱」のフタを開けてしまった、かつての「のび太」たちへの、Fからのメッセージとは――?
▼執筆者プロフィール
稲田豊史(いなだ・とよし)
編集者/ライター。キネマ旬報社でDVD業界誌編集長、書籍編集者を経て2013年にフリーランス。『セーラームーン世代の社会論』(単著)、『ヤンキーマンガガイドブック』(企画・編集)、『パリピ経済 パーティーピープルが市場を動かす』(構成/原田曜平・著)、『ヤンキー経済 消費の主役・新保守層の正体』(構成/原田曜平・著)、評論誌『PLANETS』『あまちゃんメモリーズ』(共同編集)。その他の編集担当書籍は、『団地団~ベランダから見渡す映画論~』(大山顕、佐藤大、速水健朗・著)、『成熟という檻「魔法少女まどか☆マギカ」論』(山川賢一・著)、『全方位型お笑いマガジン「コメ旬」』など。「サイゾー」「アニメビジエンス」などで執筆中。
http://inadatoyoshi.com
PLANETSメルマガで連載中の『ドラがたり――10年代ドラえもん論』配信記事一覧はこちらのリンクから。
前回:『ドラがたり――10年代ドラえもん論』(稲田豊史)第13回 『ドラえもん』のルーツ/偉大なる縮小再生産
●藤子・F・不二雄と村上春樹
前回【第13回】で、『ドラえもん』は藤子・F・不二雄による偉大な縮小再生産の産物である、と結論づけた。こちらの連載を大幅に加筆修正した書籍が発売中です!
『ドラがたり のび太系男子と藤子・F・不二雄の時代』☆★Amazonで詳しく見る★☆ -
月曜ナビゲーター・宇野常寛 J-WAVE「THE HANGOUT」8月29日放送書き起こし! ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.682 ☆
2016-09-05 07:00チャンネル会員の皆様へお知らせ
PLANETSチャンネルを快適にお使いいただくための情報を、下記ページにて公開しています。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/ar848098
(1)メルマガを写真付きのレイアウトで読む方法について
(2)Gmail使用者の方へ、メルマガが届かない場合の対処法
(3)ニコ生放送のメール通知を停止する方法について
を解説していますので、新たに入会された方はぜひご覧ください。
月曜ナビゲーター・宇野常寛J-WAVE「THE HANGOUT」8月29日放送書き起こし!
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2016.9.5 vol.682
http://wakusei2nd.com
大好評放送中! 宇野常寛がナビゲーターをつとめるJ-WAVE「THE HANGOUT」月曜日。前週分のラジオ書き起こしダイジェストをお届けします!
▲先週の放送はこちらからご覧いただけます!
■オープニングトーク
宇野 時刻は午後11時30分を回りました。みなさんこんばんは、宇野常寛です。そして松岡茉優さん、今夜も生放送お疲れ様でした! 昨日の『真田丸』も観ましたよ。春ちゃんの意外な性格があらわになって、あれはあれで可愛いですよね。松岡さんにひとつ言っておきたいことがあります。三成は確かにあなたに気を持たせただけだったかもしれない。でも僕のあなたへの愛は本物です。だから僕のことを覚えておいてください。石田三成よりも信じるに値する男、それが宇野です。
ということで、昨日の『真田丸』を観ていないと全く意味のわからないトークから始まりましたが、それはちょっと置いておいて、僕の夏休みの話を聞いてください。実は先週いっぱい夏休みを取っていたんですよね。この番組と「スッキリ!!」だけは調整できなかったので休めなかったんですが、細かくブラブラと国内旅行とかをしてそれなりに楽しんでました。それで、そのうちの火曜日いっぱいをつかって、湘南のあたりを歩いていたんです。この番組を聞いてくれている人は知っていると思いますけれど、僕はあのエリアがなんだか好きで、よく行くんですよ。朝から1人で高田馬場の自宅から山手線で品川まで行って、東海道線に乗り換えて鎌倉とかに行ってきたんですよね。海を見ながらゆっくりこれからのことを考えようかなとか思って、夏の暑い日に1人きりで行ったんですよ。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は今月も厳選された記事を多数配信します! すでに配信済みの記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201609
-
京都精華大学〈サブカルチャー論〉講義録 第8回 富野由悠季とリアルロボットアニメの時代(前編)(毎週金曜配信「宇野常寛の対話と講義録」) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.681 ☆
2016-09-02 07:00チャンネル会員の皆様へお知らせ
PLANETSチャンネルを快適にお使いいただくための情報を、下記ページにて公開しています。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/ar848098
(1)メルマガを写真付きのレイアウトで読む方法について
(2)Gmail使用者の方へ、メルマガが届かない場合の対処法
(3)ニコ生放送のメール通知を停止する方法について
を解説していますので、新たに入会された方はぜひご覧ください。
京都精華大学〈サブカルチャー論〉講義録第8回 富野由悠季とリアルロボットアニメの時代(前編)(毎週金曜配信「宇野常寛の対話と講義録」)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2016.9.2 vol.681
http://wakusei2nd.com
今朝のメルマガは「京都精華大学〈サブカルチャー論〉講義録」をお届けします。今回は富野由悠季(当時は富野喜幸名義)の初期作品が登場します。衝撃的な結末を迎えた『無敵超人ザンボット3』、そして、リアリズムを持ち込むことでロボットアニメに革命を起こした『機動戦士ガンダム』について語ります。(この原稿は、京都精華大学 ポピュラーカルチャー学部 2016年5月13日の講義を再構成したものです)。
毎週金曜配信中! 「宇野常寛の対話と講義録」配信記事一覧はこちらのリンクから。
前回:京都精華大学〈サブカルチャー論〉講義録 第7回 〈鉄人28号〉から〈マジンガーZ〉へーー戦後ロボットアニメは何を描いてきたか(毎週金曜配信「宇野常寛の対話と講義録」)
■ロボットアニメにリアリズムを持ち込んだ『無敵超人ザンボット3』
『マジンガーZ』で男子児童文化の主役に踊り出たロボットアニメは、様々なかたちで発展を遂げていきます。たとえば1974年放映開始の『ゲッターロボ』では合体ロボが登場します。合体ロボットの初出はおそらくは『ウルトラセブン』(1967年放映開始)に登場したキングジョーという宇宙人の合体ロボットだと思うのですが、『ゲッターロボ』は同じ永井豪を原作とする(作画を担当した石川賢のカラーが強い作品ですが)『マジンガーZ』の「乗り物としてのロボット」というコンセプトにこの「合体」という要素を取り入れたわけです。3機のマシンが合体し、空戦用には「ゲッター1」、陸戦用には「ゲッター2」、海戦用には「ゲッター3」というかたちで3種類の形態に変形するんですね。『ゲッターロボ』は、この変形がカッコいいということで人気を博したんですが、同時に「おもちゃできちんと再現できない」という壁にもぶつかりました。
ここを突破したのが1976年放映開始の『超電磁ロボ コン・バトラーV』で、劇中のイメージに近い変形合体が再現できるおもちゃを作ることに成功して、これが大ヒットします。ちょっとオープニングの映像を見てみましょうね。はい、『コン・バトラーV』は5体の戦闘メカ、戦闘機や戦車が合体してひとつのロボットになります。『マジンガーZ』と同じ水木一郎さんが主題歌を謳っています。そしてやっぱり、内蔵している武器の名前をずっと叫んでいます(笑)。
70年代半ばから後半にかけてのロボットアニメブームはおもちゃの進化とともに拡大して、ジャンルとして完全に定着します。基本的には30分の玩具コマーシャル的なロボットプロレスが反復されるのですが、ジャンルの拡大の中でその制約を逆手にとってアニメの表現の可能性を広げよう、という動きも出てきます。
『コン・バトラーV』の翌年、1977年に『無敵超人ザンボット3』というアニメが登場します。この少し前に、手塚治虫の設立したアニメ制作会社「虫プロダクション(通称:虫プロ)」が倒産してしまい、その残党たちが設立したのが「サンライズ(当時は日本サンライズ)」という制作会社です。そのサンライズが初めての自社企画として制作したのがこの『ザンボット3』でした。さっそくオープニングを見てみましょう。
▲『無敵超人ザンボット3』
『ザンボット3』はいとこ同士3人が合体ロボットに乗って戦うアニメです。ザンボットに乗る神勝平(じんかっぺい)・神江宇宙太(かみえうちゅうた)・神北恵子(かみきたけいこ)の3人とその家族を「神ファミリー」と呼ぶんですが、彼らは江戸時代に地球に逃げてきた宇宙人「ビアル星人」の子孫であるという設定です。なぜ逃げてきたかというと、ガイゾックという別の宇宙人に自分の星が攻め滅ぼされてしまったからです。逃げてきたはいいけど、そのうち地球もガイゾックに襲われる可能性が高いから、ビアル星人たちは300年のあいだに戦闘用ロボットを開発しながら戦いに備えていた。そんななかで、ついにガイゾックが地球侵略を開始します。そこで神ファミリーの3人は地球を守るために、ロボット「ザンボット3」に乗って戦います。
ここまではいいでしょう。これまで見てきた作品に比べて多少複雑な設定かな、と思う程度だと思います。
しかしここからが面白い。なんと、地球人たちは自分たちのために戦ってくれている神ファミリーを「お前たちが地球に逃げ込んできたせいで俺達が襲われるんだ」と言ってとことん迫害するんですね。
神ファミリーからすると「地球を守るために戦っているのに、なんでいじめられなきゃいけないんだ」と思いますよね。もともと友達だった奴らからもいじめられて、石投げられるどころか家代わりの移動要塞に爆弾を仕掛けられたりするんです。ザンボット3が地球を守るために敵のロボットと戦っていると、お巡りさんがやってきて道路交通法違反で取り締まられたりもします。全23話の話ですが、15話くらいまでずっとそういう話で、非常に陰湿な印象を受けると思います。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は今月も厳選された記事を多数配信します! すでに配信済みの記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201609