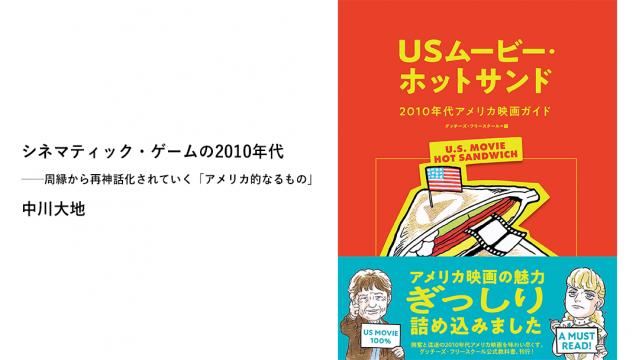-
【特別掲載】ホモ・ルーデンスの夏休み、夏の夜の夢──アートとゲームの野生を解放する二つのドリームタイム|中川大地
2023-08-22 07:00
本日のメルマガは、PLANETS副編集長・中川大地がコンセプト監修を務める、現代アートとインディーゲームの今を発信する展覧会「art bit – Contemporary Art & Indie Game Culture- #3」(会期:2023年7月5日〜9月2日)の開催を記念し、前回につづき同展をめぐる解説論考をお届けします。 20世紀における現代アートとビデオゲームの発展をリマインドしながら、その歴史を打ち返すようなコンセプトを掲げて展示作品を選定してきた前2回のart bit展。その文脈を踏襲しながらも、2023年はコロナ禍による行動制限が緩和されたことを受け、〈ホモ・ルーデンスの夏休み、夏の夜の夢〉と題して、さらに多様かつダイナミックなキュレーションが試みられています。遊びやゲームの奥底にある「野生の思考」との再会を期した同展のコンセプトの模索過程とは? (初出:「art bit – Contemporary Art & Indie Game Culture- #3」展示フライヤー(ホテルアンテルーム京都、2023年))
【告知】 ■art bit - Contemporary Art & Indie Game Culture - #3 会期:2023年7月5日(水)〜9月2日(土) 会場:ホテル アンテルーム 京都 GALLERY9.5 入場料:無料https://www.uds-hotels.com/anteroom/kyoto/news/17075/ 2011年の開業以来、「常に変化する京都のアート&カルチャーの今」を発信してきたホテル アンテルーム 京都と、2013年より続く日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit」との出会いから生まれた本展では、現代アートのゲーム性とインディーゲームの芸術性という、合わせ鏡のような魅力とクリエイティビティのルーツに注目。互いのカルチャーの垣根や、アーティストやクリエイター、研究者といった立場を超えた人と人との交わりから、アートとゲームの新たな可能性を追求しています。 3年目となる本年は「ホモ・ルーデンスの夏休み、夏の夜の夢」をテーマに、わたしたち人間の持つクリエイティブな野生や遊び心を解き放つ多彩な作品を展示します。 ■ギャラリートーク&レセプション 「アート&ゲームの最前線 〜BitSummitとart bit から考える2025への道筋〜」 日時:2023年8月27日(日)19:00〜20:30 会場:ホテル アンテルーム 京都1F 出演(予定):村上雅彦、石川武志、尾鼻崇、中川大地、豊川泰行 11年目に踏み出したBitSummit Let’ GO、およびart bit #3の運営の舞台裏とゲームカルチャーをめぐる最新動向を振り返りつつ、大阪万博2025を控えた関西の地でアートとゲームに何ができるのかを展望します。
ホモ・ルーデンスの夏休み、夏の夜の夢──アートとゲームの野生を解放する二つのドリームタイム|中川大地
現代アートのゲーム性とインディーゲームの芸術性を合わせ鏡のように展示することをコンセプトに掲げた展覧会「art bit – Contemporary Art & Indie Game Culture- 」も、今年で3回目を迎える。新型コロナウイルスのやり過ごし方に日本社会が一応のガイドラインを示した2023年の展示テーマは、当初は〈再会(Reunion)〉を軸に検討されていた。人と人とが集うことの制限がおおむね緩和された現在の状況を意識しつつ、異なる文化ジャンルとして発展を遂げながら、今ふたたび呼応しあっているアートとゲームの関係を改めて見つめ直そうというわけである。 その底意をもうすこし展開するなら、アートとゲームそれぞれの営みの根源にある「遊び」という共通の因子に溯りながら、それが現代の情報環境のもとで再び強固に結びついているさまを炙り出そうということに他ならない。かつて歴史家ヨハン・ホイジンガが「ホモ・ルーデンス(遊ぶ人)」という語で示したように、遊びこそが人間の文化や社会を形成する原動力をなしているという立論は今日でも遊び/ゲーム研究の古典として参照され続けているが、20世紀後半から始まった情報技術とビデオゲームの相互発展は、まさにそんな文明の遊戯史観を圧縮して現代人の目の前に差し出すかのような経験だった。 そしてビデオゲームを差し出された現代人の側はと言えば、最初期の『ポケットモンスター』に出会った当時の人類学者・中沢新一の洞察を信ずるなら、かつてクロード・レヴィ=ストロースが見出した「野生の思考」──すなわち、長らく近代社会が「未開」だと見做してきた世界各地の狩猟採集民をはじめとする自然民族の精神性に通底する、原初的な神話的・芸術的思考を再活性化させつつある。 このようにしてホモ・ルーデンスたる人間が、パンデミックや現在進行中の戦争、それにグローバル資本主義の帰結としての富と力の非対称化といった世界の様々な分断をいずれ乗りこえ、せめて想像的にでも遊びの因子と野生の創造力のもとに「再会」を果たすイメージを思い描こう──そのような契機としてアートとゲームが出会い直す祈りのかたちを、「art bit #3」では浮き彫りにしようと考えた。
アートとゲームの「再会(Reunion)」をめぐって
さらにその「再会」のモチーフをアート史の脈絡に求めるなら、一昨年の初回展でもリマインドしたように凄腕のチェス・プレイヤーでもあった現代アートの祖マルセル・デュシャンが、盟友の前衛音楽家ジョン・ケージとともに1968年にカナダ・トロントで行ったチェス対戦イベントでのコラボレーション・パフォーマンス《REUNION》こそが、より直接的なイメージ源となっている。ケージが企画したこの伝説的なライブは、二人の対局するチェス盤に音響装置が仕掛けられており、両者の駒の動きによって会場に設置されたスピーカーから即興的にサウンドが発生し、勝敗を競うゲームとしてのチェスのゲームプレイの境界を内破して、より高次元に展開する一回性のアート体験を現出させようというものだ。 そのコンセプト性は、ちょうど同時代にケージも呼応するかたちで展開していたジョージ・マチューナスの主宰による同時多発的な芸術運動フルクサスとも呼応するもので、同運動に参画していたナム・ジュン・パイクやオノ・ヨーコらが1960〜70年代の世界的なカウンターカルチャーの機運のもとに模索していた「境界のない世界」を指向するモーメントとも軌を一にしている。このように2度の世界大戦の戦禍とも密接にかかわりながら発展した写真や映像といった「網膜的」なテクノロジーとの対峙の中で、既存の芸術文化の制度に対する「頭脳的」な価値転倒ゲームを創始したデュシャンから、音楽ライブや演劇などより「身体的」な回路での前衛を追求したフルクサスまでに至る前世紀の戦後現代アートの史的展開は、「現代アートとビデオゲームの父と母に捧げる展覧会」を掲げた昨年の「art bit #2」の大テーマとしても強く意識していた文脈であった。
《REUNION》と1968年の「革命」
したがって、〈再会(Reunion)〉を起点に3年目のart bitのキュレーション・コンセプトを起草しようということになったとき、〈理想の時代〉(1945〜59年)の代表的なムーブメントだった抽象表現主義への応答として「規則性・ミニマル」を筆頭に四つのテーマで現代アートとインディーゲームを接続した1年目、〈夢の時代〉(1960〜74年)を体現するフルクサス的な祝祭性・体感性を中核に据えた2年目から続く流れとして、いよいよ本格的にコンピューターの一般普及やビデオゲーム産業が興り、社会・文化と直接的に切り結ぶようになった〈虚構の時代〉(1975〜89年)の精神性とそのアート的な脈絡を振り返ってみる過程が、まずは必要だった。 そこからすると、デュシャンとケージが《REUNION》を実演した1968年という年は〈夢の時代〉の折り返し点にあたり、アメリカでの黒人公民権運動やパリの五月革命、日本での全共闘運動など、主に若い世代が主体となって既存の政治体制を覆そうと志した世界的な反体制ムーブメントがピークを迎える、いわゆる「政治の季節」の転換点とされている。この年の挫折を境に、西側先進国ではイデオロギーに基づく革命闘争によって人々が現実をドラスティックに塗り変えようと志した〈理想〉は破れ、政治運動への大衆的機運が徐々に退潮して経済成長による繁栄を目指す〈夢〉に呑み込まれつつ、やがて人々は高度消費社会のもたらす様々な〈虚構〉に淫するようになった──というのが、かつて社会学者・見田宗介が批判的なトーンで素描した第二次世界大戦後の社会心性史をめぐる時代区分の要諦だ。 ただし、その一方で1968年はその年末、サンフランシスコで行われたコンピューター会議の場で、情報工学者ダグラス・エンゲルバートが当時のコンピューターにまつわる様々な発明を集積して先駆的なGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)システムのデモンストレーションが披露された年でもある。「すべてのデモの母」とも呼ばれるこのインパクトが、アラン・ケイなどを触発して1970年代のパーソナルコンピューターの登場や、その先のインターネットの普及といったIT革命につながっていく。その意味で、いわば現実社会の構造を変えていくための回路が政治革命から情報技術上の革命にシフトし、〈虚構の時代〉への変遷が始まる象徴的タイミングとして、1968年を捉え直すという見方も可能だろう。
1980年代を再照射する出展アートたち
そのように俯瞰してみると、ロジカルな完全情報ゲームとしてのチェスのゲーム性をテクノロジー・ガジェットの介入によって別種の遊びへと組み換えてみせた《REUNION》は、まさに先端的なコンピューター技術とプリミティブな遊びの感性とが結びつき、多種多様なビデオゲームが爆発的に世に出ていく〈虚構の時代〉の風景の本質を先取りしていた営みだったという構図が見えてくる。特にオイルショック後の日本では安定成長を背景に様々なポップカルチャーが開花し、バブル景気に向かって消費社会を謳歌する「遊び」のモードが全面化していたこともあり、そうした気分をインテリ層が知的に正当化するためのエクスキューズとして、当時のフランス現代思想を輸入したニューアカデミズムのようなムーブメントが起きたりもした。本展が依りどころにしているホモ・ルーデンスや野生の思考といったキーワードもまた、実のところは当時のそうした浮き足だった気分の中で広く知られるようになった概念でもある。 それゆえ、今回のキュレーション過程で現代アート側の出展作が具体化していくにつれ、しだいに1980年代的な玩具ガジェットをフィーチャーしながら、その行為性を現代的な観点や問題意識から組み換えようとするタイプの作品群が肩を並べるようになってきたのは必然だった。ともに1982年から発売されている動力付き自動車模型「ミニ四駆」を素材としつつ、片や資本主義的な速度と競争の原理への価値転倒を図ったやんツーの《遅いミニ四駆》、片や擬似プリミティブアート的な造形で直截に人類学的な土俗の現出に挑むFunny Dress-up Labの《Mask Series》の両作は、まさにそんな姿勢のストレートな顕れと言える。スケートボードにエレキギターの弦を張るなどの工夫を凝らした創作楽器《滑琴(かっきん) + 響筐(きょうきょう) + 擬似耳(ぎじじ)》および動力付き鉄道玩具「プラレール」の挙動を音源化する《ぼくのDTM》で生活空間との予測不能なインタラクションを可聴化するおおしまたくろうの2作品、かつてのファミコンがRF(高周波)変調方式で電波ジャックするかのようにテレビの映像に介入していた本質性を今日のゲーム実況のように可体験化する毛原大樹の《ビデオゲーム傍受者の受像機「Telephono Scope」》とあわせ、子供たちには愉しさを、大人たちには童心に立ち返る懐かしさを呼び起こすだろう、過年度に増してキャッチーかつ遊戯性の高いラインナップが固まってきたのである。
やんツー《遅いミニ四駆》 Funny Dress-up Lab《Mask Series》 おおしまたくろう《滑琴 + 響筐》 おおしまたくろう《ぼくのDTM》 毛原大樹《ビデオゲーム傍受者の受像機「Telephono Scope」》 こうなってくると今回のart bit展には、もはやアートとゲーム、野生とテクノロジーの「再会(Reunion)」といった広漠とした描像よりも、さらに輪郭のはっきりしたアグレッシブなイメージが宿りつつあるのではないか。インディーゲームの祭典「BitSummit」の併催イベントとして恒例化し、日々の責務を離脱して毎年の夏ごろに泊まりがけで手ずから味わうことのできる、ノスタルジックなホビーや自由研究の工作のような遊びと創造性の解放。そう、多くの人々の記憶の奥底に原体験として刻まれる、「夏休み」のイメージが。
-
【特別掲載】art bit展が投げかけるもの ──世紀をこえた「20年代」のリフレインに向き合うために|中川大地
2023-08-15 07:00
本日のメルマガは、PLANETS副編集長・中川大地がコンセプト監修を務める、現代アートとインディーゲームの今を発信する展覧会「art bit – Contemporary Art & Indie Game Culture- #3」(会期:2023年7月5日〜9月2日)の開催を記念し、同展をめぐる解説論考を2週連続でお届けします。 世界中のクリエイターが集う日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit」の関連イベントとして、ホテルアンテルーム京都にて2021年から毎年開催されている「art bit」展。COVID-19のパンデミック下で延期された東京五輪2020とともにはじまった初回展につづき、ロシアによるウクライナ侵攻や安倍元首相の銃殺事件といった衝撃が社会を揺さぶる中で開催された翌2022年の第2回展では、何が問いかけられていたのか。 映像と戦争の世紀だった20世紀における現代アートとビデオゲームそのものの成り立ちに立ち返りながら、その展示キュレーションに込められたアクチュアルな文脈を読み解きます。 (初出:「art bit – Contemporary Art & Indie Game Culture- #2」展示フライヤー(ホテルアンテルーム京都、2022年))
【告知】 ■art bit - Contemporary Art & Indie Game Culture - #3 会期:2023年7月5日(水)〜9月2日(土) 会場:ホテル アンテルーム 京都 GALLERY9.5 入場料:無料https://www.uds-hotels.com/anteroom/kyoto/news/17075/ 2011年の開業以来、「常に変化する京都のアート&カルチャーの今」を発信してきたホテル アンテルーム 京都と、2013年より続く日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit」との出会いから生まれた本展では、現代アートのゲーム性とインディーゲームの芸術性という、合わせ鏡のような魅力とクリエイティビティのルーツに注目。互いのカルチャーの垣根や、アーティストやクリエイター、研究者といった立場を超えた人と人との交わりから、アートとゲームの新たな可能性を追求しています。 3年目となる本年は「ホモ・ルーデンスの夏休み、夏の夜の夢」をテーマに、わたしたち人間の持つクリエイティブな野生や遊び心を解き放つ多彩な作品を展示します。 ■ギャラリートーク&レセプション 「アート&ゲームの最前線 〜BitSummitとart bit から考える2025への道筋〜」 日時:2023年8月27日(日)19:00〜20:30 会場:ホテル アンテルーム 京都1F 出演(予定):村上雅彦、石川武志、尾鼻崇、中川大地、豊川泰行 11年目に踏み出したBitSummit Let’ GO、およびart bit #3の運営の舞台裏とゲームカルチャーをめぐる最新動向を振り返りつつ、大阪万博2025を控えた関西の地でアートとゲームに何ができるのかを展望します。
art bit展が投げかけるもの ──世紀をこえた「20年代」のリフレインに向き合うために|中川大地
「あれ、今って21世紀だよね……?」 2022年に入ってからの衝撃的な出来事の連続に、そのような思いにとらわれている人も少なくないのではないだろうか。およそ100余年前のスペイン風邪が2度の世界大戦をまたぐ20世紀の世界史ドミノの倒列の端緒近くにあったことと同様、COVID-19のパンデミックで幕を開けた2020年代の世界は、各国での対策をめぐる社会の分断、ロシアによるウクライナ侵攻、金融危機化を懸念されながら進む世界同時株安、そして日本社会を震撼させた先の安倍元首相の惨劇と、これでもかというほどに前世紀への先祖返りを志向しているかのようだ。 昨年、現代アートのゲーム性とインディーゲームの芸術性を合わせ鏡にするという趣旨で初めて開催されたart bit展では、マルセル・デュシャンが同時にチェス・プレイヤーでもあったという脈絡のリマインドから、そのコンセプトの図解きが始まっていた。そしてデュシャンがレディメイドの小便器を使った《泉》を1917年のニューヨーク・アンデパンダン展に出展しようとした騒動が現代アートのスタート地点となったこともまた、目下の情勢の変化から振り返ると、1世紀前の時代状況との奇妙な符合の一つだったようにも思えてくる。 とはいえ、一見「かつて来た陰惨な道」をリフレインしているかのようにもみえる現在の世界の展開も、螺旋を描くようにして未知のベクトルを進んでいる。未曾有の世界大戦に翻弄された人類の危機へのニヒリスティックな抵抗が、あらゆる権威や既成概念を疑うダダイスムにつながり、そして現代アートという価値転倒のゲームを産み出したように、いま世界を覆いつつある巨大な不安と無力感を受け止めながら、そこに少しでもハッキング余地を見つけていくという芸術表現の役割が、これよりは改めて切実化してゆくことになるだろう。そうした現在進行中の時代変化のベクトルの正体と、そこに付けいる隙を見つけていくための営みとして、2年目を踏み出すことにしたart bitに何が問われているのかを見定めていきたい。
「現代アートのゲーム性」と「ビデオゲームの芸術性」
デュシャンをメルクマールとする現代アートが何を成し遂げたかを改めて言い直せば、写真や映像技術、あるいは工業製品の氾濫といった産業革命以降の表現にまつわるテクノロジーの発展が、絵画や彫刻といった従来の伝統的な芸術表現の存在意義を脅かしていく中で、それでも人間が創造する「美」とは何かという規範を様々なイズムの更新闘争として展開してきた近代美術のモーメントを徹底させ、高純度の「文脈のゲーム」(落合陽一)を抽出したことだ。 そこでは、従来の「美」における自明の前提だった人の目に心地よく感じられる「網膜的」な快楽の要件は相対化され、むしろ不快や困惑すらもたらす認知負荷の高い「頭脳的」な鑑賞体験を通じて、従来の美をめぐる既成概念をいかに揺るがしたかという問題提起性こそが、作品価値の根幹となるシーンが現出していくことになる。 言い換えればこれは、それまでの美術史の脈絡や流通マーケットでの慣習というゆるやかな「ルール」の存在を前提に、個々の「プレイヤー」としての作家や鑑賞者がそれぞれに能動的な参加意識をもって制作や読み解きに「挑戦」し、コレクターやギャラリスト、批評家たちが形成するアートワールドの文脈での評価や影響力を勝ち取ることを「競う」という近代芸術の「ゲーム」としての側面が、デュシャン以降は特に先鋭化したことを意味する。とりわけ第二次世界大戦後のアメリカが発展の中心地となったことで、アートの流通価値の形成がグローバルな金融資本主義という定量的な評価システムと結びつき、現代に至るまで巨大化していったことが、「文脈のゲーム」としての現代アートの本質に他ならない。 他方、今日のビデオゲームのあり方が、現代アートの合わせ鏡のように位置づけられるとすれば、どのような意味においてか。そのルーツをやはり1世紀前に溯るのであれば、コンピューターゲームの最初の先駆例とされる、人間を相手にチェスのエンドゲーム(終盤局面)を指せる自動機械「エル・アヘドレシスタ」が1912年に発明されたことを思い起こさないわけにはいかない。これは奇しくもデュシャンが裸婦の連続写真から受けたインパクトのもとに人体運動のイマジナリーをキャンバスに定着させた絵画《階段を降りる裸体 No.2》を制作したのとも同年にあたり、彼が生涯をかけてチェスがもたらす「プレイ中に思考されている、不可視の方向へと広がる、実際には指されなかった局面の総体」(中尾拓哉)にインスパイアされた芸術制作を追求していったこととの見事な照応があるからである。 そして、このような「実際には指されなかった局面の総体」を数学的にシミュレートしていく知の追求こそが、第二次世界大戦期のコンピューター技術やゲーム理論の発展を促進。そうした論理機械の性能を検証するためのテストベッド・アプリケーションとして、ニムや三目並べといった相互手番制の論理ゲームがコンピューターに導入されていくことから、ディスプレイ装置を盤面表示に使うインタラクティブなビデオゲームの原型が生まれていくことになる。 このことは、デュシャンの芸術に始まる現代アートがテクノロジーとの対峙によって「網膜的」なものから「頭脳的」なものへと向かったのとは逆に、テクノロジーの側は、純然たる「頭脳的」な産物としての論理処理のエレメントを複合させていくことで、人間の認知と情緒に作用する「網膜的」な芸術としての原初性を獲得していったのだとも言えるだろう。 -
Pokémon LEGENDS アルセウス、タコピーの原罪、カムカムエヴリバディ、冬アニメ総括……4月のカルチャー番組のお知らせです
2022-04-03 17:15
こんにちは。PLANETS編集部です。新年度になりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
本日はPLANETSチャンネルのカルチャー関連番組についてお知らせします。
※どの番組も生放送に加え、タイムシフト・アーカイブでの配信を予定しています。
【新番組】「現代ゲーム通信」
現代のエンターテインメントとして、今なお進化を続ける〈ゲーム〉。今月から、話題のゲームタイトルとその背景を徹底批評する新番組「現代ゲーム通信」がスタート。有料ゲームメディアとして国内随一の購読者数を誇るnote「ゲームゼミ」を主宰するゲームジャーナリスト・Jiniさんと、『現代ゲーム全史』著者でPLANETS副編集長の中川大地のコンビで、既存のゲームマスコミや実況動画では絶対に味わえないゲーム論を展開します。「気にはなっているけど、自分でプレイする時間が取れそうにない」「いまゲーム分野で何が起きているのかだけでも知 -
ゲームAIは〈人間の心〉の夢を見るか(後編)|三宅陽一郎×中川大地(PLANETSアーカイブス)
2020-12-11 07:00
今回のPLANETSアーカイブスは、先週に引き続き、ゲームAIの開発者である三宅陽一郎さんと、評論家・編集者の中川大地さんの対談をお届けします。日本のゲームとゲーム批評は、なぜダメになってしまったのか。圧倒的な技術力と資金力で成長を続ける欧米のゲームに、日本のゲームが対抗しうる方策とは?『人工知能のための哲学塾』『人工知能が「生命」になるとき』の三宅さんと『現代ゲーム全史』の中川さんが、日本のゲームと人工知能に秘められたポテンシャルについて語ります。(構成:高橋ミレイ)※本記事は2016年10月18日に配信した記事の再配信です。
本記事の前編はこちら
ゲーム論壇の衰退とゲーム実況の登場
三宅 近年、日本のゲームが衰退していると言われています。その責任はもちろん開発者自身にありますが、ゲームを批評する言論の力の弱さも、原因の一端にあると思います。ゲーム産業が盛り上がった時期には、ゲームを語る文化も同時に盛り上がるのが常で、そうした時代には、ゲーム批評を担うスターが現れます。当時、『ゲーム批評』という雑誌がありましたが、今の時代にもそういうメディアや批評家の存在は必要です。
その点、中川さんの『現代ゲーム全史』は、コンピューターの黎明期から現代の『Pokemon GO』までを網羅した、ゲームの歴史を俯瞰するマップとして使うことができる。僕はこのマップを足がかりに、ゲーム批評を再興できるのではないかと期待しています。批評が盛り上がって言論が面白くなると、ゲーム開発の現場もエキサイティングになります。そうしてユーザーとゲーム開発者が高いレベルで応答できるようになれば、もう一度、「文化としてのゲーム」を取り戻せるかもしれません。今のメディアは売り上げばかりを報じていて、商業色が濃すぎますからね。
中川 ありがとうございます。ゲームがコンテンツカルチャーとして伸びていった2000年前後は、批評の文脈でゲームを語る人たちが、テキストサイト界隈で記事を書いていました。ところが、ちょうど三宅さんがゲーム業界に入った頃から、そういった論壇がどんどん弱くなっていった。日本のゲーム産業の停滞と共に、ゲームを批評的に語るモチベーションも衰退していって、2000年代後半に、その隙間を埋めるものとして現れたのが「ゲーム実況」でした。ニコニコ動画内で、ゲームをプレイしている動画を実況付きで放送する。このゲーム実況の登場によって、かつて批評の対象だったゲームが、ネット上のおしゃべりのネタとして共有されていきました。
ゲーム実況でプレイされるゲームは、すでに多くの人が共通体験を持っているレトロゲームとか、あるいは『青鬼』や『ゆめにっき』といった「RPGツクール」などで制作されたフリーゲームです。あの辺の作品は、スーパーファミコン時代のゲームシステムを踏襲しながら、ストーリーテリングの部分に工夫を加えたものです。基本的にファンコミュニティが有する共通のコミュニケーションコードに即したかたちでプレイヤーの心情を揺さぶる手法で、ゲームそのものの本質としては新しい体験が生み出されていないし、求められてもいないように見えます。
三宅 批評の役割のひとつは、その分野を他の分野とつなぐことです。例えば、ゲームと16世紀頃の絵画、あるいはゲームと別の産業のプロダクト、といったように、開発者が気付いていないような、他分野の事柄と関連づけることで新しい可能性を開拓します。確かに、ゲーム実況もこれはこれで興味深い文化なのですが、内輪の盛り上がりだけで終わってしまうのが難点です。
なぜ日本のゲームは衰退したのか
三宅 日本のゲームの衰退の背景には、コンピューターサイエンティストの少なさがあるように思います。ゲームプログラマーとして一流の人はたくさんいますが、ハイパフォーマンスのマシンに向けたゲームを制作する際に、コンピューターサイエンスの土壌の弱さが露呈してしまいます。その結果、相対的に欧米のゲームが伸びて、国内のゲームとその批評が衰退してしまうという連鎖が起きています。
中川 日本のゲーム文化がピークに達した2000年代初頭ぐらいまでは、それまで蓄積したシステムを使って、いかに先進的な表現ができるかを突き詰めていくような試みがありました。ところが本格的な3Dエンジンを使う時代に入ると、技術力の不足も相まって、日本のゲーム業界全体が目的や発想力を失ってしまい、語るべき新しさを持ったゲームが現れなくなってしまったように思います。
【12/15(火)まで】オンライン講義全4回つき先行販売中!三宅陽一郎『人工知能が「生命」になるとき』ゲームAI開発の第一人者である三宅陽一郎さんが、東西の哲学や国内外のエンターテインメントからの触発をもとに、これからの人工知能開発を導く独自のビジョンを、さまざまな切り口から展望する1冊。詳細はこちらから。
-
ゲームAIは〈人間の心〉の夢を見るか(前編)|三宅陽一郎×中川大地(PLANETSアーカイブス)
2020-12-04 07:00
今回のPLANETSアーカイブスは、ゲームAIの開発者である三宅陽一郎さんと、評論家・編集者の中川大地さんの対談をお届けします。デカルト以降の近代西洋哲学はどのように人工知能を定義するのか。欧米と日本のゲームの背景にある思想的な差異とは。『人工知能のための哲学塾』『人工知能が「生命」になるとき』の三宅さんと『現代ゲーム全史』の中川さんが、ゲームとAIについて徹底的に論じ合います。(構成:高橋ミレイ)※本記事は2016年10月18日に配信した記事の再配信です。
実験物理学の研究からゲームAIの世界へ
中川 今回、三宅さんとの対談をお願いしたのは、『現代ゲーム全史』をまとめてみて、ゲームと人工知能(AI)は車の両輪のような関係にあるなと感じたからなんですね。拙著の序盤の章でも述べたように、ゲームの数学的解析から始まるデジタルゲームとAIは、同じ起源を共有しています。以来、基本的には何か実用的な目的のために使うのではなく、純粋に人間がコンピューターで何ができるかの可能性を追求していくジャンルとして発展してきました。それが2012年あたりからAIではディープラーニング(深層学習)のブレイクスルーがあり、ゲームではOculus Riftなどが出てきてVRへの流れが全面化して、2016年現在はそれぞれに大きな歴史的転機が訪れています。
そんな時流の中で、三宅さんはまさにゲームに活用するAIの専門家として、『人工知能のための哲学塾』と森川幸人さんとの共著『絵でわかる人工知能』を立て続けに出版され、AIという概念についての非常に本質的な思索を展開されていたのが印象的で、ぜひ深くお話をうかがってみたいと思ったわけなんです。
それで、もともと三宅さんは物理学の研究をされていたそうですが、そこからどういう関心を持ってAIの研究に進まれたのかを、まずはお聞きかせ願えますでしょうか。
三宅 最初は京都大学で数学と理論物理を勉強していました。修士課程で大阪大学に移って地下にある半径数kmという巨大な加速器でデータを取るような研究をやっていたのですが、装置を自分で作ってみたくなって、博士課程で東京大学に移り電気工学を学びました。そのうちに装置を自律的に動かすことに興味が出てきて、そこが人工知能の研究のスタートですね。「ひとつの知能を丸ごと作る」というのが僕の目標で、そういった技術はゲーム業界でこそ必要とされているはずだと思って、2004年頃にゲーム業界に入ったんです。でも、当時のゲームで使われていた人工知能は完全なものではなかった。今でも世間で人工知能と呼ばれるものの90%は、人工知能の一部を利用したものです。たとえばAmazonのレコメンドシステムやGoogle検索、ディープラーニング、画像認識などで、こういった単機能のAIの方がサービスにしやすいんですね。でも、僕が作りたいのは、ゲームの世界で本当に生きている、完全な人工知能でした。完璧でなくていいですが、知能として最低限必要な一揃いが作っているという意味で完全な人工知能です。そのためには、ゲームの中に「世界」そのものが存在しなくてはいけない。
中川 なるほど。2000年頃といえば、ゲーム史的には2Dのドット絵の時代から、プレステ革命を経てポリゴンを用いた3DCG表現への主流の移行が完了したくらいの時期ですね。ゲーム世界が3D化すると、物理演算エンジンによって、現実の三次元空間に近い世界を作れるようになる。理念としてのAIは、特定の専門分野での用途に特化したものではなく、人間のような汎用的な問題解決のできる知能を目指すわけだから、知能に対して課題を与える環境の性格が人間のそれに近づくことが大きな意味を持つわけですね。言うなれば、AIがAIとして活動するための最も純粋なフィールドを用意しうる分野が、「世界」や「環境」を生成するテクノロジーとしてのゲームだったと。
三宅 おっしゃる通りです。人間も含め、知能というのは外部の環境に合わせて相対的に生成されるので、単純な世界では知能を複雑にする必要がない。ゲームデザインが複雑になれば、人工知能もゲームを理解するために高い知能を持たなければいけなくなります。僕がゲーム業界に入ったのは、森川幸人さんがプレステで『がんばれ森川くん2号』(1997年)や『アストロノーカ』(1998年)を出した、そのちょっと後くらいでした。
【12/15(火)まで】オンライン講義全4回つき先行販売中!三宅陽一郎『人工知能が「生命」になるとき』ゲームAI開発の第一人者である三宅陽一郎さんが、東西の哲学や国内外のエンターテインメントからの触発をもとに、これからの人工知能開発を導く独自のビジョンを、さまざまな切り口から展望する1冊。詳細はこちらから。
-
【特別寄稿】シネマティック・ゲームの2010年代──周縁から再神話化されていく「アメリカ的なるもの」|中川大地
2020-11-26 07:00
今朝のメルマガは、PLANETS副編集長・中川大地の寄稿をお届けします。「映画」と「ゲーム」が接近していった2010年代、メディアの境界を越えた物語体験を目指したシネマティック・ゲームの数々は、「アメリカ」という主題をいかに描いたのか。ジャンル全体の動向と『The Last of Us』『Detroit: Become Human』『DEATH STRANDING』の3作品のレビューを通じて浮き彫りにしていきます。※本記事は、2020年2月発売の『USムービー・ホットサンド 2010年代アメリカ映画ガイド』(フィルムアート社)所収の同名記事を採録したものです。
ゲームにとって、先行の総合芸術メディアである映画は、1970年代末のエンターテインメント産業としての成立以来、ずっと憧れであり挑戦対象であった。その野心は、1990年代半ばに2Dピクセル表現からポリゴンによる3DCG表現に移行することで、顕著なモード・チェンジを起こす。「映画的」たらんとするゲーム作品の数々は、『バイオハザード』(1996)や『メタルギアソリッド』(1997)などの成功を機に、いよいよ実写映画のそれを目指したフォトリアリスティックに漸近するためのビジュアル表現のレースを始動。そして2006年発売の「PlayStation 3」の世代に入ると、コンソールゲーム機の3DCG技術が個人の容姿や芝居を判別可能なレベルに到達し、2010年代には実在の俳優をキャスティングしたAAA級のタイトルが世界的なヒットを遂げていくようになった。 一方で、映画の側も同じくVFXの中核をなすCG技術の発展を背景に、2000年代後半以降のハリウッドの業界構造そのものが大きな変動を遂げている。すなわち、『トイ・ストーリー』(1995)で世界初のフルCGアニメーションによる長編映画を劇場公開したピクサー・スタジオをウォルト・ディズニー・ピクチャーズが2006年に完全子会社化したのを機に、2009年にはマーベル・エンターテインメントを、2012年にはルーカスフィルムを傘下に収めていく。こうしたディズニー一強の環境が、2010年代のメジャー映画の方向性を大きく決定づけていたのは周知の通りだ。 あるいは『アバター』(2009)以降の3D・4Dブームによって映画興行が体感アトラクション化し、その環境を前提にした『ゼロ・グラビティ』(2013)のような作品も登場。同作監督のアルフォンソ・キュアロンの盟友であるアレハンドロ・G・イニャリトゥが手がけたVR作品『Carne y Arena』がアカデミー監督賞を受賞するなど、xR技術の普及とも相まって、いまや20世紀型の映像表現そのものが、ゲームによって培われた没入型のインタラクション体験によって変質を遂げつつある。 このように、3DCGという共通の基幹技術を土台に、ゲームと映画(さらにはNetflixなどの伸張で影響力を増した連続ドラマ)の関係がはっきりと連続性のある隣接領域として並び立つようになったのが、2010年代だったと言えるだろう。
では、そのような環境下で、“シネマティック”を謳うタイプのゲームは、どのような体験の器として映画そのものとの距離感を築きつつ、その表現内容を確立していったのか。
【12/15(火)まで】オンライン講義全4回つき先行販売中!三宅陽一郎『人工知能が「生命」になるとき』ゲームAI開発の第一人者である三宅陽一郎さんが、東西の哲学や国内外のエンターテインメントからの触発をもとに、これからの人工知能開発を導く独自のビジョンを、さまざまな切り口から展望する1冊。詳細はこちらから。
-
『ダンガンロンパ』は「バトルロワイヤル的想像力」をどう更新したのか?──西尾維新、ゲーム的リアリティ、“ダークナイト以降”のキャラ造形から考える (井上明人×中川大地)【PLANETSアーカイブス】
2020-06-19 07:00
▲『ダンガンロンパ』生誕10周年記念トレーラー
今朝のPLANETSアーカイブスは、第1作発売から10周年を記念し、ゲーム研究者の井上明人さんとPLANETS副編集長・中川大地が、人気ゲームシリーズ『ダンガンロンパ』を語った対談記事をお届けします。2010年の第1作『ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生』(以下『1』)、2012年発売の続編『スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園』(以下『2』)はともに20万本を超える堅調な売上を記録し、2013年にはテレビアニメ化。若い世代のコスプレや二次創作シーンにも定着し、2010年代の家庭用ゲーム発の国産IPとしては特異な存在感を誇るタイトルになった本作。「ゲーム」の範囲にとどまらないこの作品の文化史的/批評的ポテンシャルを改めて語り尽くします。※この記事は2014年10月10日に配信した記事の再配信です。
※ネタバレが重大なゲームですので、ゲーム未プレイ/アニメ未視聴の方は注意してお読みください。
※この記事は、2014年9月3日にPLANETSチャンネルで放送されたニコ生番組を加筆・再構成したものです。
▼『ダンガンロンパ』とは
学級裁判の中で相手の矛盾を論破し、殺人事件の犯人を暴いていくゲーム。ハイスピードでテンポよく展開する学級裁判の中、捜査パートで集めてきた証言や証拠を弾丸としてトリガーにセットし、相手の主張の矛盾をアクションゲームのように撃ち抜くことで論破する。推理とアクションの融合により、これまでにない。まったく新しいエキサイティングなゲーム体験を表現。(公式サイトより)
▼ストーリー
舞台は、あらゆる分野の超一流高校生を集めて育て上げる為に設立された、政府公認の特権的な学園「私立 希望ヶ峰学園」。国の将来を担う希望を育て上げるべく設立されたこの学園に、至極平凡な主人公、苗木誠もまた入学を許可されていた。 平均的な学生の中から、抽選によってただ1名選出された超高校級の幸運児として……。入学式当日、玄関ホールで気を失った誠が目を覚ましたのは、密室となった学園内と思われる場所だった。「希望ヶ峰学園」という名前にはほど遠い、陰鬱な雰囲気。薄汚れた廊下、窓には鉄格子、牢獄のような圧迫感。何かがおかしい。
入学式会場で、自らを学園長と称するクマのぬいぐるみ、モノクマは生徒たちへ語りはじめる。──今後一生をこの閉鎖空間である学園内で過ごすこと。外へ出たければ殺人をすること。──主人公の誠を含め、この絶望の学園に閉じこめられたのは、全国から集められた超高校級の学生15人。生徒の信頼関係を打ち砕く事件の数々。卑劣な学級裁判。黒幕は誰なのか。その真の目論見とは……。
(『1』のAmazon商品説明より)
ポスト「逆転裁判」の系譜と「西尾維新」的文芸センスの融合
中川 今回は、PLANETSチャンネルで連載中の「中川大地の現代ゲーム全史」の番外編として、新作『絶対絶望少女』が発売されたばかりの人気ゲームシリーズ『ダンガンロンパ』について、ゲーム研究者の井上明人さんをお招きして、いま改めて語ってみようという企画です。井上さん、よろしくお願いします。
井上 よろしくお願いします。
中川 この『ダンガンロンパ』シリーズですが、まず第1作が発売されたのは2010年末ですよね。2010年といえば、ソーシャルゲーム市場が急激に成長して、家庭用ゲームがどんどん不振に陥っていった時期です。つまり『怪盗ロワイヤル』などが登場して一般のゲームユーザーの可処分時間を圧迫していった時期に、この『ダンガンロンパ』はクラシックなパッケージゲームの新作シリーズとして登場しつつ、比較的若い世代のライトオタク層を掴んで健闘したタイトルだった点が特徴です。井上さんが最初に『ダンガンロンパ』に注目されたきっかけは何だったんですか?
井上 実は体験版が出た最初の段階で、ちょっと話題になっていたのでやってみたんですよ。僕はプレイステーション・ネットワークのストアで体験版を漁る習性があるんです(笑)。それでプレイしてみたら「あっ、これは『逆転裁判』をすごく意識して、変種を打ち込んできたぞ」と思いました。体験版のときは難易度調整に若干失敗気味だったんですが、非常に野心的な試みだと思いましたね。
中川 やっぱり僕らのような30代ゲーマーからすると、まず思い浮かぶのが『逆転裁判』からの脈絡ですね。あれは第1作が出たのが2001年ですが、ゲームボーイアドバンスを代表する最初のオリジナルヒットシリーズでした。殺人事件の聞き込みや証拠品集めなどをする捜査パートと、容疑者や証人の証言の矛盾を指摘したり証拠を突きつけあったりする論争を通じて真相がつまびらかになる裁判パートの繰り返しで進行していくという構成のルーツは、ここから来ています。実際には「裁判」というよりも、ミステリーの王道の真犯人当ての形式的な趣向を置き換えただけだったわけですが、推理アドベンチャーゲームの作劇と体感性を大きく変えました。
▲『逆転裁判123 成歩堂セレクション』(発売元:カプコン/ニンテンドー3DS)
その後、『逆転裁判』のフォロワーがなかなか出てこなかった中で、10年を経てようやく新しい意匠とシステムで出てきたのがこの『ダンガンロンパ』シリーズなのかなと思うんですが。
井上 いや、『逆転裁判』のフォロワー的なタイトルは、売れていなかっただけで実はあるにはあったんです。たとえば、『有罪×無罪』『遠隔捜査 真実への23日間』なんかですね。少し離れたところでは『銃声とダイヤモンド』なんかはすごく良かった。『銃声とダイヤモンド』は、『街 〜運命の交差点〜』『かまいたちの夜』の麻野一哉さんがシナリオを手掛けていて、ゲームシステム自体もよくできていたんだけど、主要登場人物がおっさんが多めというのもあり(笑)やや渋めで、あんまり売れなかった。でも、『銃声~』はほんとにすごい作品でした。そういう作品も過去にはあったんですが、それらと『ダンガンロンパ』が何が違ったかといえば、『ダンガンロンパ』はシステム、キャラ、シナリオ、グラフィックなど多面的にK点越えをしていてグイグイ引っ張れる要素が本当にたくさんあった。ほんとに、いい作品なので、売れてよかったなぁという感想を持ちましたね。
中川 そんな中、『ダンガンロンパ』は推理パートと裁判パートで進むゲームシステムを『逆転裁判』から継承しつつ、そこに2000年代初頭から大きく盛り上がった講談社BOXや西尾維新の一連の作品のような、フリーキーなキャラクターたちが常識ではありえないフィクショナルな状況での推理を繰り広げる、いわゆる「新伝綺」と呼ばれるミステリーとライトノベルの中間領域のような文芸センスを導入してみせたことで、それまでのフォロワータイトルとは一線を画する支持を獲得した。
井上 『ダンガンロンパ』ですごいなと思ったのは、非常にアイロニカルで批評性があって問題意識がグネグネしたものなのに、『1』『2』ともそれぞれよく売れて、マニアックなサブカルっ子以外にもちゃんと受け入れられたことですね。それは素晴らしいことだと思う一方で、『ダンガンロンパ』や、その先駆者である西尾維新もそうだけど、グネグネしたことをやっていそうでいて、実はそんな難しい問題意識を持っていなくても楽しめるようにもなっている。そこの両立の仕方というのがすごいな、と。
中川 単純にキャラクターコンテンツとして秀逸です。男性と女性両方のファンがついていて、ノーマルなカップリングを喜ぶ層もいるし、男どうしあるいは百合カップルでの組み合わせの要素もあるし、全方位に向いていて、10代から20代までの若い層にも受けていますよね。それに加えて、ムダに豪華な声優陣の存在もありますよね。
井上 これは本当に豪華ですよね。
中川 やっぱりなんといっても特筆すべきは、マスコット兼悪役で、生徒どうしのコロシアイを操るモノクマ役への大山のぶ代さんの起用。ドラえもんの声に新たなイメージを付け加えたのは、この『ダンガンロンパ』シリーズの功績(?)ですよね。
井上 今のドラえもんの声優は水田わさびさんに代わっていて、今の子どもたちは大山のぶ代のドラえもんを知らない可能性もあるぐらいですよね。
▲ゲームを操る「モノクマ」中川 そう。別格感あふれる大山さんをはじめ、声優陣は豪華は豪華ながら、実は懐かしい感じのラインナップだった。たとえば『1』の主人公の苗木誠くんを演じたのは『新世紀エヴァンゲリオン』の碇シンジ役の緒方恵美さんだし、『2』の主人公の日向創役はコナンで有名な高山みなみさん、メインキャラの一人である十神白夜役は同じく『エヴァ』の渚カヲルとか『ガンダムSEED』のアスランで有名な石田彰さん等々、主に1990〜2000年代のヒットアニメを代表作とするベテラン勢が中心。かろうじて現役の声優ヲタの文脈に訴求する若手と言えるのは、霧切響子役の日笠陽子さんや『2』の七海千秋役の花澤香菜さんくらいですかね。
でもこういった今時の深夜アニメ等での旬よりは一回り年齢層高めなレジェンドクラスが起用されたことで、われわれ団塊ジュニア世代のオタク教養的なものと、近年の10-20代のニコニコ世代というか、ジュブナイルライトオタク層との共通言語ができた側面もある気がします。かつてのアニメやマンガなどの小ネタを縦横無尽に引用して詰めこみながら、それを若い世代向けに届けることに成功しているという意味では、やはり西尾維新とも通ずるところがありますよね。
「学級裁判」が体感させる“推理”と“理不尽”の詐術
井上 『逆転裁判』との比較をさらに掘り下げてみましょうか。『逆転裁判』の場合は、単に選択肢を選ぶのではなくて、選択肢を選ぶことに対して「なぜこの選択肢の方がいいのか」という合理的推論をする仕組みが提供されてましたよね。これは、ものすごい発明だったわけです。
まず第一に現実のコミュニケーションを簡単なゲームシステムに変換するということが難しいわけです。で、とりあえずアドベンチャーゲームは、選択肢で会話をするという方式をだいぶ初期につくりだしたわけです。ただ、その次にどの選択肢が正解か、ということについて、納得感をどう演出するか、というのが難しい。すごいゲームデザインというのは、ここの納得感の演出というのが神がかっているわけです。
たとえば今僕はこうやって中川さんと話していますが、僕が「中川さん、最近どうですか」とか言ったときに中川さんからいきなり「ボンッ! 不正解だ!」みたいなことをバシッと言われたら困るわけです。中川さんがそれを言ったら「この中川さんって人はちょっと、イっちゃった人だな」って感じがしますよね?
中川 なるほど(笑)。裁判ならそれを言ってもいい、という。
▲『ダンガンロンパ』の学級裁判パート
井上 そうです。そこまでが『逆転裁判』が切り開いた地平です。
さらにその上の第三の地平があるわけです。『逆転裁判』との違いは、『ダンガンロンパ』って学級裁判パートがリアルタイム制であることですね。リアルタイムで議論しているなかで議論の進め方のおかしな点を指摘しないといけなくて、それがゲームとしての緊張感を生んでいた。ちなみに『逆転裁判』も最初はリアルタイム制にしようとしていたらしいんですが、ただし、さすがにそれだと難易度が高すぎるということで実装しなかった。『ダンガンロンパ』はそれをある程度、なんとか遊べる形にしてしまった。
中川 まあ、ミスをすれば同じ議論が再びループするので、厳密な一回性という意味でのリアルタイムではなく、静的な『逆転裁判』のテキストメッセージに比べ、『ダンガンロンパ』の方が、1ターンの中のタイミング演出が動的になったというだけのことではあるんですが、アクション性が大きく高められたのは間違いない。こういう難易度調整の考え方って、基本的にアクションRPG的だと思うんですよ。ターン制のRPGは静的なパラメータに規定されていて、レベル上げやアイテム収集などプレイヤー本人の腕前によらず根気があれば誰でもできる反面、臨場感に欠ける。対して、ただのアクションゲームの場合は本人にアクションの腕前がないとゲームを進められない。
アクションRPGはその中間で、パラメータ管理とプレイヤー本人のアクションの腕前をミックスしたゲームデザインになっている。この折衷性が、2000年代以降は『モンハン』シリーズやオープンワールド系RPGでの標準になっていますよね。それと似たようなことを、ストーリーゲームの領域でやったのがこの『ダンガンロンパ』のシステムだったんじゃないのかな。
捜査パートで他のキャラクターと親しくなると、学級裁判でのアクションを有利にできるアイテムをもらえたりするあたりとかも含め。
井上 今まで混ざっていなかった「アクション」と「謎解き」のふたつの要素を混ぜて、何とかいい感じに納めたのは偉業と言っていいと思います。
中川 あと学級裁判パートで面白いのは、推理のプロセスを別種のミニゲームで置き換えていることですね。つまり、いくらプレイヤーに自分の頭で推理するリアルタイム論争に近づけると言っても、所詮は与えられた選択肢から正解を選んで一定のストーリーをなぞっていくAVGとしての本質は変わらない。そのお仕着せ感を軽減すべく、本来なら主人公が能動的な思考をするところを、パズルゲームや音ゲーなどの異なるゲーム的障壁を乗り越えていく体感性で代替して疑似体験性を補っているわけです。
コンシューマーゲームでは、『ファイナルファンタジー』シリーズぐらいから全体のゲームシステムと関係ないさまざまなミニゲームを入れ込む流れがあって、特に『レイトン教授』シリーズは、大きな推理ストーリーの骨格の中に「脳トレ」的なクイズを組み込むことで、自分が謎解きのプロになった気分を味わえるロールプレイングの詐術を使ったのは大きかった。ああやってゲーム内にミニゲームの多様性を入れ込み「体験を体験で置き換えていく」手法は、ストーリー演出のエフェクトとは無関係なゲーム的要素をすべて取り払っていく方向にAVGシステムを特化させていった1990〜2000年代のPCノベルゲームの台頭に対する、コンシューマーならではのリアクションでもあったのかなと。
井上 あー、ただ学級裁判のミニゲームに関してはちょっと僕は悩ましい気持ちになりましたね。特に『2』で出てきた「ロジカルダイブ」と称したスノボゲーム(下図参照)とか、さすがに「これは推理のスキルと関係が何もないのでは?」というところがありますよね。
▲『ダンガンロンパ2』に登場するゲーム内ゲーム、「ロジカルダイブ」の画面
ゲームデザインにおいて、プレイ中にずっと同じことをしていると飽きるので、刺激の多様性は必要なんだけど、そこの多様性の与え方って難しいポイントなんですよね。完全に別ゲームにすると、「関係ないことをやらされるストレス」が発生しやすくなってしまう。経験としては連続していて、かつ多様な展開というのが重要なわけですが、『ダンガンロンパ』に関しては、そこは少し振り切りすぎてしまって、もう完全に別のミニゲームになっているな、とは思いました。もちろんトータルで素晴らしいゲームであることは前提として、ですがこのゲーム設計はちょっとダメなストレスの与え方だな、と感じました。
中川 なるほど。ただ、あのスノボゲームに関して無理やり深掘りすると(笑)、『FFⅦ』でヒロインのエアリスが死んだあと、ものすごい衝撃を受けて悲しい気分になっているときにスノボゲームをやらされましたよね。それを彷彿とさせるところがあって。で、『ダンガンロンパ』ってそもそも理不尽なゲームをやらされているゲームですよね。
井上 ああ、なるほど、あれも含めてモノクマの陰謀であると。たしかにそれなら、一貫性がとれてますね(笑)。
『ダンガンロンパ』に埋め込まれたゲーム史的な自己言及性
中川 『ダンガンロンパ』って、ゲーム内で『ジョジョの奇妙な冒険』や『るろうに剣心』など、団塊ジュニア以降の世代が親しんできたサブカルネタをちょくちょくぶっこんできているわけですが、その中でゲーム自体の言及もすごくあったりするので、あのスノボゲームも『FFⅦ』のオマージュなんじゃないか、なんてことも思ったりするんですよね(笑)。
これがあながち邪推すぎるわけでもないかと思うのは、『2』に『トワイライトシンドローム』っていう妙なサイドビュー画面のゲーム内ゲームが出てくるじゃないですか。実際、本作を制作したスパイクの前身の会社が同名のシリーズをちょうど1990年代後半にPSで出していて、さらに後には『夕闇通り探検隊』という伝説的な後継作品にもなっていますが、そういうセルフオマージュを入れてきているわけです。
▲ゲーム内ゲームとして登場する『トワイライトシンドローム』の画面。
ここにはちょうど、『FFⅦ』までのPS第一世代的なローポリゴンの不気味の谷(3D表現の進化過程で人間の造形が中途半端に再現されると妙に不気味に感じられる段階があること)や構成のチグハグさ、操作系の未洗練さなどが結果的に恐怖や理不尽さの表現として独特の味わいを醸し出していた時代のゲーム史的な記憶を、意識的に埋め込む姿勢が感じられるんですよ。
井上 『moon』(1997年にラブデリックが開発しアスキーが販売したPS用ゲームソフト。王道RPGやゲームそのものを批評的に捉え返した名作とされる)と同じく、ゲーム内ゲームを構築して、その中でゲームに対する批評性みたいなものをちゃんと獲得していくというやり方ですよね。
中川 そもそも『ダンガンロンパ』という作品全体が、ゲーム内で登場人物たちが理不尽なデスゲームをやらされているという二重構造になっていて、それに対する言及が1作目のときからキモだったんだけど、それをさらにメタ視点で捉え返すかたちで2作目がつくられていますからね。
プレイしていて思い出したのが『メタルギアソリッド』の1、2の関係です。メタルギアは第1作の主人公・スネークがシャドーモセス島事件でああいう経験をして、2作目の主人公の雷電はその1の体験のコピーを仕組まれたゲームとしてやらされていて、それを1の主人公だったスネークが最後に解き明かして導いていくという構造があった。これはまさに『ダンガンロンパ』の1、2作目の作劇構造と同じですよね。
井上 なるほど。ただ僕としては、中川さんとは少し違う感想を持っていて。『ダンガンロンパ』は1作目の時点ですでにリアリティショー(台本や演出なしで素人の出演者がさまざまな状況に直面するさまをドキュメンタリー形式で放送するテレビ番組の一形態)として、中のコロシアイの様子が全世界に中継されていたわけですよね。続く『2』ではそのリアリティショーをさらにバーチャルリアリティに嵌め込んでいるというわけのわからないことをやっていて、これは「お約束をことごとく覆していく」という意味で、すごく西尾維新的な構造だなと思ったんですよ。
中川 たしかにそうですね。『1』では、閉鎖空間でコロシアイをさせられている学園内がディストピアだと思っていたら、実は世界全体のほうがすでに絶望病に冒されていて『北斗の拳』みたいな終末的な世界になっていて、むしろ学園のなかのほうが守られていた、というどんでん返しがあるわけです。そこにさらにモノクマが登場して学園をコロシアイの舞台にしてリアリティショーとして外の世界に中継していた、という。
『ダンガンロンパ』に結実した「バトルロワイヤル」な想像力の系譜
井上 これは『ダンガンロンパ』に限らない話ですが、バトルロワイヤルとリアリティショーはなんでこんなに相性が良いのか、というのも論点の一つかもしれないですよね。
中川 2000年代以降に台頭してきたバトルロワイヤル的な想像力って、学校やクラスの狭い人間関係の持つ日常の残酷さの表象として、クローズド・サークルのなかで疑心暗鬼になってコロシアイをさせられるというようなものですよね。で、そもそもバトルロワイヤル系の語源である『バトル・ロワイアル』(高見広春による小説。1999年刊で2000年に映画化され大ヒットした)がまさに、「少年たちがバトルする様子を大人たちが見て楽しむ」という構造でしたよね。僕の考えでは、00年代前半の時点ですでにゲームの体験がある程度、人々のリアリティに刷り込まれていたからこそ、殺し合いとリアリティーショーを結びつけるバトルロワイヤル系の想像力が出てきたのかな、と。その感覚が映画や小説に波及して、それをもう一回ゲームのほうに持ち帰ってきたのが『ダンガンロンパ』だったとも位置付けられるんじゃないでしょうか。
井上 なるほど。ゲーム発だったどうかかは、はっきりと断言できないですけど、その説明は説得的だと思います。
ちなみに僕の知り合いの20代前半の子が『ぼくらの』とか、バトルロワイヤルものがすごい好きで「こういうものにこそ人間の真実があると思うんですよ」ということをずっと言っていたんですよ。で、案の定『ダンガンロンパ』にはドハマりをしていました。20代前後の子が「ここにこそ人間の真実が!!」という感想を持つのは、頭では理解できなくはないけど、直感的には今ひとつピンとわからない。おそらく、僕が1990年に生まれていたら理解できたのかもしれませんけれど、そこの感覚が今ひとつ腑に落ちる感じがありません。中川さんはどうですか?
中川 やっぱり1970年代生まれの自分自身のリアリティとして、そういう感覚はないですよ(笑)。でもそれこそ、宇野君が『ゼロ年代の想像力』で書いていたように、『新世紀エヴァンゲリオン』以降の世代にとっては、ある種のバトルロワイヤル的な想像力が身の周りの社会をイメージする上での前提的なリアリティになっていて、まだ引きこもる余裕のあった『エヴァ』以前に思春期を過ごした世代にはその感覚があんまりわからない、というのはあるんじゃないですか。
80年代に実現された高度消費社会って、あくまで誰かに構築された偽物で、これはいつ壊れてもおかしくないものであるという感覚があり、それは『トゥルーマン・ショー』のような「この平和な日常は本当は存在しない、仕組まれたバーチャルなものなんだ」という想像力を生み出しましたよね。その一方で、旧ソ連が崩壊する前までは「核戦争が起こって世界が終わる」ということにリアリティがあって、そういった終末世界を描くフィクションもたくさんありました。
つまり『ダンガンロンパ』を規定している構造として、子供たちの2000年代以降のリアリティ(教室内でのバトルロワイヤル)を、大人が構築した1980年代的リアリティ(トゥルーマン・ショーと終末的な世界)が取り巻いている、という重層的な構造があるとも言える。
井上 ただ、今日び「終末後の世界」をそこまで気合を入れて描く気はないのだろうなっていう感じもしませんでした? 「人類史上最大最悪の絶望的事件」って、えらくざっくりとした表現ですし……。
中川 まあ、そこにはリアリティはないですよね(笑)。ポスト『エヴァ』の想像力としてバトルロワイヤル系と比肩される、いわゆるセカイ系的な想像力の流行って、新海誠のアニメやノベルゲームのような個人レベルのミニマムな制作環境と親和性が高かったと思うんですよ。他方、集団制作を前提としたコンシューマーゲームだと、もうすこし大勢のキャラクターを表現できるという事情もあって、教室レベルのクローズドな人間関係を主題化するリアリティサイズが表現できた。
しかし、その外側は後景としてボンヤリとせざるをえないあたりは共通している。それでも2000年の『高機動幻想ガンパレード・マーチ』なんかは、教室外のマクロな世界の戦争状況をうっすらとパラメータ化して関連させていたわけですけどね。
井上 セカイ系という物語形式って、要は「世界が滅ぶ/滅ばない」という大きなスケールの話が、主人公の周りのローカルな人間関係と直結するというものでしたよね。で、同学年の同じ部活の友達だけで楽しく過ごす日常を描いた『けいおん!』のようなものを「空気系」というわけですが、実は近場の人間関係だけ選んでいるという意味ではバトルロワイヤルものもそうで、この二つは近い関係にあるのかなと思ったりするんですけど。
中川 まさに、その二つは表裏一体ですよね。近場の人間関係のユートピア感だけを取り出すと空気系のぬるい世界になり、逆に残酷な面を戯画化して描くとバトルロワイヤル系になるという。『2』は最初に、(後でモノクマの妹という設定に無理やりされる)「モノミ」というキャラが出てきて、「みなさん、この南国の島で、修学旅行を永遠に楽しみまちょうね〜」って言っていて、実際に本編とは別にモノクマが登場しない平和な日常を楽しく過ごす「アイランドモード」というモードもありますが、それはまさに空気系的な世界観が表裏一体の構造として、この作品に埋め込まれているということの証左でもありますよね。
2010年代的なキャラクター造形とゲームの形式的必然が生んだ「黒幕」
井上 ……と、裏のほうから「キャラの話をしてくれ」というオーダーがきているので、すこし強引な振りになりますが(笑)、『ダンガンロンパ』が空気系的な構造すらも取り込んでいるとすると、空気系においてやっぱり重要なのはキャラ描写ですよね。『ダンガンロンパ』は本当にキャラづけが強いゲームだということがあると思いますが、
中川 『逆転裁判』の頃から成歩堂くんとか真宵ちゃんみたいな感じで記号的かつフリーキーにキャラを立てていく流れがありましたが、『ダンガンロンパ』はその傾向をさらに押し進めつつ、2010年代のボカロ世代や「カゲロウプロジェクト」好きなどにも通ずる、ジュブナイルライトオタク層の感性に適した元ネタをぶちこんだキャラクター造形へとアップデートできた点に勝因がありました。ちなみに井上さんが一番好きなキャラは?
井上 僕は『2』に登場する超高校級の飼育委員・田中眼蛇夢くんが、ペットであるハムスターを「破壊神暗黒四天王」と呼ぶ、あのパッケージングが好きですね。ハムスターだけ出されてもげんなりですが。
中川 なるほど(笑)。まさに彼なんかは、「厨二病」という2000年代後半以降のライトオタク層が自嘲的に共有するに至った属性を取り込んだ典型例ですね。実際人気も高いですし。僕は男性キャラでは、やはり『2』の狛枝凪斗くんの造形に度肝を抜かれました。狛枝くんは名前が1作目の主人公の苗木誠のアナグラムで、声優も同じ緒方恵美さんだし「超高校級の幸運」というところも同じなのに、第1話でいきなり前作の記憶のあるプレイヤーの予期を覆してみせる攪乱者ぶりが見事すぎました。彼のクライマックスである第5話でもそうだけど、彼の能力をああいうかたちでトリックに活かすというのも狂っていたし。
井上 たしかに狛枝くんのあのトリックは、本当にゲームデザインとシナリオを融合させた非常に素晴らしい、歴史に残したいトリックといってもいいですね。
中川 シナリオ自体が強烈にキャラクター性を引っ張っていましたよね。このシリーズを手がけている小高和剛さんのシナリオライターとしての力をすごく感じさせられたキャラだった。
一方、女性キャラでインパクトが強かったのは『1』の大神さくらちゃんですね。明らかに『北斗の拳』のラオウや『グラップラー刃牙』の範馬勇次郎みたいな格闘マンガのラスボスをムリヤリ女子高生化したネタキャラ枠なのに、それをシナリオの力で最後にはあれだけ可憐な乙女っぽく思わせたのも圧巻でした。
井上 さくらちゃんはすごい露骨ですけど、超高校級のアイドルとか、超高校級の野球選手とか、超高校級の文学少女とか、全部マンガ違いのキャラですよね。そういうジャンル違いのキャラクターを一同に会させてバトルロワイヤルさせるというのがこのゲームのコンセプトでもあった。
中川 キャラクターの話が出たので、重大なネタバレですが、ここからはあのキャラクターの話をしましょうか。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
もはやサブカルチャーは「本音」を描く場所ではなくなった――『バケモノの子』に見る戦後アニメ文化の落日(宇野常寛×中川大地)(PLANETSアーカイブス)
2020-03-06 07:00
今朝のPLANETSアーカイブスは『バケモノの子』をめぐる宇野常寛と中川大地の対談をお届けします。『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』などでヒットを飛ばし、ポストジブリの最右翼と目される細田守監督とスタジオ地図。その期待作であったはずの本作が逆説的に示してしまった戦後アニメ文化の限界とは? 初出:「サイゾー」2015年9月号(サイゾー) ※この記事は2015年10月7日に配信した記事の再配信です。
Amazon.co.jp:バケモノの子
大作化で発揮されなくなった細田守の批評性
中川 どうしても面白いとは思えない作品でした。「“夏休み映画”を作らなければ」という形骸的要請ばかりが先だって、ワクワク感が全然なくて。異世界ファンタジーとしての体裁が、ほとんど機能してなかった気がします。
宇野 僕はちょっと評価が複雑で、観ている間はそんなに気にならないんですよ。でも、観終わったあとに何か言おうと思うとまぁ、誰も傷つけずによくできていたな、ということしか浮かばない。
中川 基本的には、シングルマザーの子育てを描いた前作『おおかみこどもの雨と雪』【1】と対の構造になっている。つまり、親が一方的に子を導くのではなく、親の側が子から教えられる相互性とか、熊徹【2】だけではなく、友人の多々良と百秋坊【3】らにも子育てのタスクを分散させるとかで、細田守監督なりの新たな父性や家族像を追求しようとしたわけですね。そのメッセージ性自体にはなんら異論はないのだけれど、『おおかみこども』とセットだと「母にはあれだけ苛酷な運命を押しつけといて、父はここまでユルユルに免責すんのかよ!」という見え方になってしまう(笑)。
【1】『おおかみこどもの雨と雪』
公開/12年7月
細田守のオリジナル長編2作目。
“おおかみおとこ”と結婚し子どもを産んだ女性と、その娘と息子の“おおかみこども”の物語。シングルマザーとなった主人公の花を通じて描かれる母性信仰の強さが、一部から批判を集めた。
【2】熊徹
熊の容姿をした半獣人で、武道家。バケモノの世界で次期宗師の座を猪王山と争っている。人望が厚い猪王山に比べ、荒くれ者で我が強い。蓮を拾い、名前を名乗らなかった9歳の彼を「九太」と名づける。
【3】多々良と百秋坊
どちらも熊徹の幼なじみで、多々良はヒヒの半獣人、百秋坊は豚の半獣人で僧侶。多々良は大泉洋、百秋坊はリリー・フランキーが声を当てている。
宇野 『おおかみこども』では「女性賛美の形をとった女性差別」の典型例みたいなことをやってしまって、ちょっと過剰に叩かれすぎた面もあるけど、まあ、さすがにあれは今の40代男性の自信のなさと、屈折した男根主義が悪い形で全面化して作品を狭くしていた側面は否めない。その反省か、今回、現代的な家族観・コミュニティ観を最小公倍数的にきれいに描いていて、こういう関係が美しいという美学はわからなくもないけれど、今度はその分、批判力のあるファンタジーではなくなってしまった。
中川 まぁ『おおかみこども』での批判に誠実に対応した結果、たまたま男性側の免責に見えてしまっただけかもしれないからジェンダー論的な批判は留保するとして。もっと問題なのは、「渋天街」のイメージの弱さでしょう。『千と千尋の神隠し』的な、この世とは違う理で動く摩訶不思議な異界としての設定も映像的快楽も希薄で、ただステレオタイプな都会としての渋谷に対比させるためだけの、素朴な共同体社会でしかなかった。
宇野 あそこで描かれているものって、完璧に正しくてそこそこ美しいと思うんですよ。でも、いま期待をかけられているスタジオ地図【4】の新作アニメーションで、夏休みの最大のごちそうとしてみんなが観に行って、この作品が出てきた時の物足りなさは否めないと思う。ポスターから想像できるストーリーの半歩もはみ出ていない。
結局細田さんって、美少年というモチーフに一番興味があると思うんですよ。『サマーウォーズ』【5】を観ると明らかじゃないですか。一番思い入れがあるのはカズマだったでしょう。カズマは脇役だったのが『おおかみこども』で“雨”を経て、『バケモノの子』では完全に少年が主役になっている。モチーフレベルでは正直になってきているんだけど、その間に細田守の社会的地位が上がって、表現レベルではどんどん丸くなってしまって、とうとう誰も傷つけない代わりに何もない作品になってしまった。
特に九太が青年になって以降、後半のシナリオが完全に“段取り”になってしまっている。一郎彦【6】が実は人間の子どもだというのは観ていればすぐにわかるし、クライマックスのアクションシーンが必要だからという理由だけで渋谷に出るのも……。あと、九太の社会復帰が、勉強して高認をとって大学に行くことを決意する【7】って展開に到っては、だったらなんのためにファンタジーが存在するのかよくわからなくなってしまう。異世界で修行をすることで、大学では学べないような世界の豊かさを学んできたんじゃなかったのか、と(笑)。この映画の中でいちばん豊かに描けているのって、少年期の修行時代の擬似親子+2人の傍観者(多々良・百秋坊)というあのコミュニティですよね。
【4】スタジオ地図
『時をかける少女』『サマーウォーズ』を手がけたプロデューサーが、細田守と共にマッドハウスから独立して設立したアニメ制作会社。
【5】『サマーウォーズ』
公開/09年8月
17歳の健二が、ふとしたことから憧れの先輩の田舎に共に帰省し、
大家族の仲間入りをする。同時進行でインターネット上の仮想世界「OZ」ではサイバーテロが発生。田舎の大家族とネット上の仮想世界での出来事がリンクしながら進んでゆく。
【6】一郎彦
熊徹と宗師の座を争う猪王山の長男。実は拾われてきた人間の子ども。少年期はさわやかで聡明な子どもだったが、成長するにつれて心に闇を宿し、最後に暴走する。
【7】勉強して高認をとって~
17歳になってから人間社会に再び足を踏み入れた九太は、図書館で出会った楓(後述)の存在をきっかけに勉強を始め、楓の勧めもあって大学受験を考えるようになる。結果、熊徹とぶつかり、渋天街を飛び出してしまう。
中川 映像的には、細田さんが自分の本当に得意な表現を純粋抽出して組み合わせることで構築されてますよね。要は『サマーウォーズ』でも好評だった対戦格闘アクションを核に、『おおかみこども』での人獣のメタモルフォーゼの要素を盛り込むなどの手法で、ドラマの軸線を作った。熊徹からの見取り稽古をアニメーションのシンクロで示した修行時代や、猪王山とのバトルなどは、すごく良かった。
渋天街のイメージの弱さも、肯定的に捉えるなら、これまでの細田作品における現実社会と異世界──『デジモンアドベンチャーぼくらのウォーゲーム!』【8】や『サマーウォーズ』ならデジタル空間だったり、『おおかみこども』なら狼たちの自然世界だったり──とを等価に描く表現の延長線上に発想されたがゆえの帰結ともいえる。渋天街って、設定上は人間界の渋谷の地形と対応している〈拡張現実〉的な世界ということなので。そういう感じで、異世界を人間社会とフラットに捉えて特別視しない点が、自然/空想賛美的なジブリ作品に対する、細田守の現代的な作家性だったわけです。
しかし今作については、画面を見ていても2つの世界の対応が全然伝わらないし、作劇上も活かされていない。結局、世界観構築に際しての批評性が弱いので、前半と後半でファンタジー世界と現代社会を対置するプロットが作劇意図ほどには機能していないんですよ。それが“段取り”感につながっているのだと思う。
【8】『デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!』
公開/00年3月
細田守監督作品。ネットに出現した新種のデジモンの暴走を止めるべく、少年たちが戦いに乗り出すストーリーで、『サマーウォーズ』公開当初から類似性が指摘されていた。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
中川大地 タンポポの綿毛を追って ~『この世界の片隅に』ファンムーブメントの軌跡~(PLANETSアーカイブス)
2020-01-17 07:00
今朝のPLANETSアーカイブスは、映画『この世界の片隅に』とそのファンムーブメントの考察です。2016年11月、わずか63館で封切られた本作は、熱烈なファンムーブメントの後押しを受けて公開規模を拡大、異例のロングランヒットとなりました。公開前のクラウドファンディング当時からファンムーブメントに参加してきた評論家の中川大地が、その軌跡を追いながら、作品と現実が呼応する本作の意義を改めて問い直します。(初出:『ありがとう、うちを見つけてくれて「この世界の片隅に」公式ファンブック』双葉社)※本記事は2018年4月1日に配信された記事の再配信です。
【告知】 1月21日放送予定のPLANETS the BLUEPRINTに『この世界の片隅に』の監督・片渕須直氏がゲスト出演します。ご興味のある方は以下のリンク先から、ぜひご覧ください。片渕須直×宇野常寛「(さらにいくつもの)片隅から描かれた世界とはなにか」
▲『ありがとう、うちを見つけてくれて 「この世界の片隅に」公式ファンブック』(双葉社)
2017年6月16日、映画『この世界の片隅に』の累計動員数がダブルミリオンを突破した日の翌朝、テアトル新宿での凱旋上映で200万100人目くらいの観客として祝福する時間を、筆者は来場者たちと共有していた。
各地のファンミーティングや広島でのロケ地巡り等で知り合ったその面々は、古参の原作ファンから、アニメ化に際してのクラウドファンディングの支援者、主演女優の応援団まで、それぞれまったく異なる背景から参入してきた人々だ。しかしながら、みなSNSでの発信や勝手イベントの実施・参加など、並外れた能動性をもって自ら作品にコミットし、“自分事”としての使命感をもって意識的にムーブメント化しようとする人々の割合が非常に高いという点だけは、不思議と一致していた。
そうしたファンムーブメントは、どのように触発され、本作を異例のロングランヒットへと押し上げたのか。本稿では、筆者が本作をめぐる折々の縁に目の当たりにしてきた軌跡を辿り直しつつ、その意味を改めて問い直してみたい。
こうの漫画が誘う「昭和越しの戦争体験」
2005年、初夏。右手を失ったすずさんが激昂した玉音放送から干支が一巡りし、終戦60年の節目を偲ぶ企画が様々に登場していたおりのこと。
駆け出しのライターだった筆者は、戦後日本の漫画やアニメ等の歴代のサブカルチャーが、いかにあの戦争を描いてきたかを検証する雑誌特集に携わっていた。その前04年には、こうの史代の『夕凪の街 桜の国』が刊行されて大きな話題を呼んでおり、双葉社の担当編集である染谷誠氏を訪ね、同作の反響について訊かせていただいたことがあった。
取材の席上、広島での被曝体験に端を発する3世代の戦後史を繊細な筆致で描いた同作に続いて、呉軍港空襲を題材に、いよいよこうのが戦中の時代そのものを描く新作を準備中であるとの話を聞いた。それが、筆者が『この世界の片隅に』という作品の存在を知った、最初の機会だった。
その呉ではこの年、大和ミュージアムこと呉市海事歴史科学館がオープンしている。同館が協力した映画『男たちの大和/YAMATO』の公開とも相まって、戦後長らくタブー視されてきた「軍都」としての歴史を直截に見据えていこうとする機運が熟してきつつあったわけだ。
だから筆者の目には、『この世界の片隅に』の登場は、まさに『夕凪の街』から『桜の国』への変遷で描かれたような語り手世代の交代によって、ようやく左右のイデオロギーの呪縛を脱したフラットな視点から、日本人の戦争の語り継ぎ方が様々な意味で更新されていく大きな流れとして見えていた(実際、大和ミュージアムの施設や関係者たちの人脈は、後述する映画化に際しての現地支援ムーブメントでも中核的な役割を果たしていく)。
直接の戦争体験者たちからの語り継ぎを得る機会は、やがて完全に失われていくほかはない。だとするなら、私たちはいかにして風化と忘却に抗いながら、しかも押しつけがましい教条に陥ることなく、大切な記憶を後生に遺していくことができるのか。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
『この世界の片隅に』――『シン・ゴジラ』と対にして語るべき”日本の戦後”のプロローグ(中川大地×宇野常寛)(PLANETSアーカイブス)
2020-01-10 07:00
今朝のPLANETSアーカイブスは2016年の映画『この世界の片隅に』をめぐる宇野常寛と中川大地の対談です。戦時下の一人の女性の視点を通して個人と世界の対峙を描き、大好評を博した本作。しかし、その出来の良さゆえに逆説的に明らかになった「戦後日本的メンタリティの限界」とは?(構成:須賀原みち/初出:「サイゾー」2017年1月号)
【告知】 1月21日放送予定のPLANETS the BLUEPRINTに『この世界の片隅に』の監督・片渕須直氏がゲスト出演します。ご興味のある方は以下のリンク先から、ぜひご覧ください。片渕須直×宇野常寛「(さらにいくつもの)片隅から描かれた世界とはなにか」
中川 本作は、『シン・ゴジラ』と対にして語るのに今年一番適した作品だと思いました。『シン・ゴジラ』は日本のミリタリー的な想像力が持ってきた最良の部分をリサイクルして、従来日本が苦手といわれてきた大局的な目線での状況コントロールに対する夢を描いていた。一方で、『この世界の片隅に』は『シン・ゴジラ』で一切描かれなかった庶民目線での大局との向き合い方を描ききった。この両極のコンテンツが2016年に出てきたことは、非常に重要です。
すでに多くの人が語っていますが、雑草を使ってご飯を作るような戦時下の生活を“3コマ撮りのフルアニメーション”に近い手法で丹精に描くことにより、絵として表現できる限りの緻密さと正確さで日常描写を追求するという高畑勲の最良の遺産を、見事に現代的にアップデートしていた。そうした虚構の力によって、劣化していく現実へのカウンターを打てていたのは、素晴らしいと思う。
宇野 片渕さんは高畑勲的な「アニメこそが自然主義的リアリズムを徹底し得る」というテーゼを、一番受け継いでいる人なんだと思う。高畑勲が前提にしていたのは、自然主義とは要するに近代的なパースペクティブに基づいた作り物の空間であるということ。だからこそ、作家がゼロから全てを生み出すアニメこそが自然主義リアリズムを貫徹できるという立場に立つ。対する宮﨑駿は、かつて押井守が批判した「塔から飛び降りてしまうコナン」問題が代表する反自然主義的な表現、彼のいう「漫画映画」的な表現こそがアニメのポテンシャルであるとする。
片渕さんの軸足は高畑的なものにあるのだけど、『アリーテ姫』【1】や『マイマイ新子と千年の魔法』【2】がそうであったように「アニメだからこそ獲得できる自然主義リアリズム」をストレートに再現するのではなく、常に別の基準のリアリズムと衝突させることでアニメを作ってきた。比喩的に言うと、本作はその集大成で、“高畑的なもの”と“宮﨑的なもの”がひとつの作品の中でぶつかっていて、しかもそれがコンセプトとして非常に有効に機能している。そういう意味で、戦後アニメーションの集大成と言ってもいいんじゃないかと思いますね。
【1】『アリーテ姫』:01年公開の、片渕監督の出世作。制作はSTUDIO 4℃。
【2】『マイマイ新子と千年の魔法』:09年公開。片渕監督の代表作。制作はマッドハウス。
中川 そうした大前提の上で、原作が持っていたコンセプトとのズレや違和を語るなら、こうの史代の幻想文学性とでもいうべきものが、映画では児童文学性に置き換えられて失われてしまった部分もある。片渕さんは「子どもだから見ることのできる世界」といった児童文学的なものへのこだわりが非常に強く、これはむしろ“宮崎的なもの”に近い。
『この世界の片隅に』は、周りから大人になることを押し付けられて嫁に行ったすずさんの日常の鬱憤が、最終的に戦争という理不尽さの受け止め方につながる構造になっている。映画では周作と水原哲に対するすずさんの目線は、子どもでいたかった人が大人の性愛関係を拒絶するように描かれている。それは、片渕さんがすず役の声優として、『あまちゃん』以来ユニセックスなイノセンスを持ち続けているのんという女優にこだわったことにも表れています。でも、こうのさんはミニマムな人間関係の中で表出する世界の残酷さに対する感性が非常に高い人で、『長い道』【3】でも描かれたように、こうの作品のヒロインは大人の性愛関係を前提に織り込んだ上で、男性との間の丁々発止のバーター関係を築いている。その違いが、片渕さんによるこうの史代解釈の限界とも感じました。
【3】『長い道』:訳ありで結婚した夫・壮介と妻・道の、穏やかだが奇妙な生活を描いた短編連作集。01~04年連載。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
1 / 12