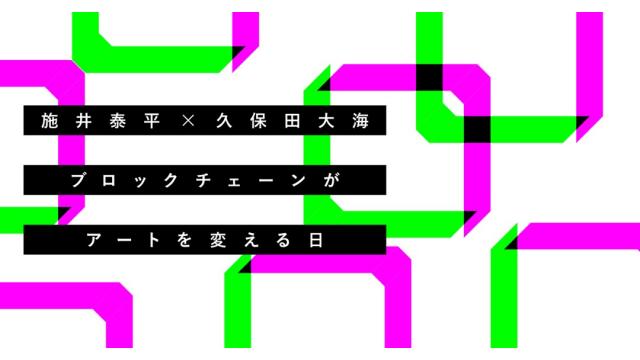-
【特別対談】ブロックチェーンがアートを変える日(後編)|施井泰平×久保田大海
2020-12-02 07:00
21世紀になってからのグローバル資本主義の加速で、ますます一握りの富裕層の金融ゲームになりつつあるアートマーケットの世界。誰もが発信者になれるウェブ2.0の熱狂と挫折を経て登場してきたブロックチェーン技術を、どのように用いればアートという営みを「民主化」していくことができるのでしょうか? 前編に引き続き、アート×ブロックチェーンの可能性を最前線で追求する二人に、withコロナのテクノロジー環境の変化も踏まえながら、さらなる未来像を思い描いてもらいました。(司会:中川大地 構成:小池真幸)※この記事の前編はこちら
暗号資産とアートの共通点──ロマンティシズムが生み出す“交換不可能”性
──ここで久保田さんにお伺いしたいのですが、いま施井さんにお話しいただいたようなアート業界の動きに近いかたちでブロックチェーン技術が活用されているケースは、別の領域にもあるのでしょうか?
久保田 施井さんのお話を聞きながら、僕が普段携わっている暗号資産と比較すると、すごく面白いと思いました。たとえば、「いかにして市場全体の母数を増やしていくか?」という問題が共通しているように見える。2018年12月に金融庁が仮想通貨の呼び名を「暗号資産」と定めたことが象徴的ですが、ビットコインは通貨ではなく「ゴールド」になっています。通貨には「価値交換の媒介」「貯蔵」「尺度」の三大機能がありますが、ビットコインは交換できる場所が増えていない。いくらビットコインを持っていても、コンビニで何も買えないじゃないですか。ここが分散型ネットワークの一番のボトルネックになっているわけです。だからといって、営業に強いソフトバンクが使える店舗を開拓したPayPayのようなトップダウンの手法を取ると、ビットコインの価値を成り立たせている分散性が失われてしまう。 それどころか、ビットコインに価値の貯蔵を求める人が大半です。「わたしも持っておこう」という心理で“ガチホ”する人は多いですから。そして、その背景には現状のビットコインの価値を担保している、「参加者数が増えれば価格が上がる」仕組みがある。これを施井さんの話に置き換えると、スタートバーンはアートを買う人の数を増やす、つまりアートマーケットの母数を増やすことで、価値を高めようとしているともいえると思うんです。
施井 おっしゃる通りだと思います。アートは、誰が何を目的に買っているのか、よくわからない側面もある。これは恋愛と似ています。恋愛対象者に求める要素を、一つだけ切り取るのは難しいですよね。「顔だけで選んでいる」と言う人でも、実際には喋り方や性格、出会い方等々といった多角的な要素が絡み合っている。アートも同じで、ビジュアルやモノとしての存在感はもちろん、買った場所や勧めてくれた人、コンセプト、そして将来的な価値の上昇見込みといった要素が合わさって、価値が作り上げられていくんです。 その意味では、暗号資産のエコシステム全体像も含めて似ているかもしれません。ビットコインのようにメジャーなコインだけでなく、「草コイン」「アルトコイン」と呼ばれているようなマイナーなものも含めると、かなりアートマーケットに近いところがある。相対取引がなされており、なおかつ一回で終わらずに、一定期間持っていることで価値が爆発的に上がるかもしれない点で、かなり共通性がありますよね。ビットコインは始祖であるからこそ得ている先行者優位を享受しているともいえますし、世の中にある数千種類の暗号資産の、一つひとつをアーティストと捉えることもできます。 ICO(新規仮想通貨公開)のムーブメントを見ていても、有名な人が立ち上げたり、それこそ「CoinDesk Japan」のような有名なメディアに取り上げられたりしたプロジェクトは、評価が高まりやすい。一方で、「技術が好きだからこのコインを買う」といった人もいれば、「ヴィタリック・ブテリンが好きだからイーサリアムを買う」といった人や「NEM信者」のような存在もいます。こうして多角的な評価軸がある点も、アートに似ています。
久保田 暗号資産には、すごくロマンティシズムがあり、ある意味、宗教になっていますよね。ビットコインが強いのは、もちろん先行者優位もありますが、提唱者とされるサトシ・ナカモトが喚起する謎めいた物語性が、想像力を膨らませているからです。その神秘性ゆえに、ビットコインそのものに対する愛着が湧いている。こうしたインターネットによるストーリーの共有が、暗号資産の特徴だと思います。この愛着が、100年後も生き続けるのか。そうした問いを喚起する点では、国家とも近いところがあるでしょう。 一方で、最近はそのロマンティシズムが薄れて、より資本主義の中に取り込まれつつある動きもあって。リーマンショック以後、金融工学の専門家が暗号資産の領域に流れてきたという点はよく指摘されますが、金融工学を導入してブラックボックス化することで価値を膨らませる、「DeFi」(Decentralized Finance:分散型金融)というムーブメントが起きているんです。イーサリアムをはじめ、多くのコインの価値が跳ね上がっています。
施井 すごいムーブメントですよね。金融商品であるにもかかわらず、脱中心性をすごく巧妙に利用して金商法が適用できないようになっており、誰にも刺されようがない構造になっている。
久保田 また、暗号通貨とアートが似ている点は他にもあります。通貨には「ファンジブル」(交換可能)なものと、「ノンファンジブル」(交換不可能)なものがある。たとえばアートは、さまざまな人が異なる価値の感覚を持っているので、ノンファンジブルとみなされますが、法定通貨は単位あたりの価値が誰にとっても同じなのでファンジブルです。ただ、暗号資産は少し話が違い、ノンファンジブルなアートと近いところがあると思っていて。たとえば、ビットコインの中でも、最初に刻まれて誰の手にも渡っていない「ヴァージン・ビットコイン」は価値が高い。先ほどの施井さんのお話にあったように、来歴が価値を左右しているんです。
施井 ヴァージン・ビットコインなんて概念があったのですね。人間はデジタルで交換可能なものであっても、ちょっとしたデータや情報の違いで唯一性を見出すことがありますが、ビットコインにもあてはまるとは驚きです。 これはアートにおける限定作品と似ていますね。「アンディ・ウォーホルの『キャンベルのスープ缶』の絵を100枚だけ発行します」というように、限られた点数だけ発行し、エディション番号が記載されている作品に近い。
また、ブロックチェーン技術の導入コンサルティングを行うBlockBaseが、ネットレーベルのMaltine Recordsと一緒に、ノンファンジブル・トークン(互いに代替することができない独自性を備えたトークン)を活用して、原盤権が含まれるかたちで音楽を配信する取り組みもありました。金融庁に当該プロジェクトが適法かを確認したときに、当時の担当者から「まったく同じものが何個かあるなら、ノンファンジブル・トークンであれど仮想通貨とみなされる」と言われたと言います。最近では決済性があるかどうかが判断基準になってきているというけど、このエピソードで当時はいろんなことを考えさせられました。もし同形態のノンファンジブル・トークンが仮想通貨と同様ならば、下手したらアーティストのエディション付き作品がすべて独自通貨と捉えられかねない世界が見えてきて、パンドラの匣を開けてしまった感覚もあります。先ほど「ブロックチェーンはデジタル革命のラストパンチになる」と言いましたが、こうして技術の解像度が高まり過ぎたことに起因して「曖昧」な存在が許されなくなってきているからこそ生じている事例もあり、アートの価値構造を問い直さないといけないタイミングであると感じています。
ブロックチェーンとxR技術との掛け合わせでバーチャルと現実の区別が消滅する
久保田 前編の「ブロックチェーンがデジタルに実存を与える」という話につながりますが、あらゆる領域で、デジタル空間と現実空間が融合しはじめるタイミングに差し掛かっていますよね。たとえばVTuberにおいては、コロナ禍に伴って、ライブ空間が急速にバーチャルに移りはじめています。米津玄師が『フォートナイト』の空間内でライブをしていたことが象徴的ですが、ギフティングをすることで、バーチャル空間に花火が上がったり、お金が降ってきたりする演出がなされるようになった。これまでリアル空間でグッズを買ってタオルを振り回すことで同時性を楽しんでいたのと、ほぼ同じですよね。
【12/15(火)まで】オンライン講義全4回つき先行販売中!三宅陽一郎『人工知能が「生命」になるとき』ゲームAI開発の第一人者である三宅陽一郎さんが、東西の哲学や国内外のエンターテインメントからの触発をもとに、これからの人工知能開発を導く独自のビジョンを、さまざまな切り口から展望する1冊。詳細はこちらから。
-
【特別対談】ブロックチェーンがアートを変える日(前編)|施井泰平×久保田大海
2020-12-01 07:00
「ブロックチェーン」と聞いて、どんなことを思い浮かべますか? 仮想通貨に使われている技術、分散型のしくみ、改ざんできない……どれも間違いではありませんが、実はもっと本質的で重要な特徴を秘めてます。たとえばアートの世界に、「数百年に一度の変化」を起こすかもしれない──? アート×ブロックチェーンを最前線で追求する二人が、そんな可能性を徹底的に考えます。(司会:中川大地 構成:小池真幸)
ブロックチェーンは人工的なアウラを創出し、デジタルに実存を与える
──久保田大海さんは現在、NHK出版で編集者としてテクノロジー領域の書籍を多数手がけたのち、現在はブロックチェーンと暗号資産を軸にテクノロジーが作り上げる新しい金融・産業・経済のかたちを考えるニュースメディア「CoinDesk Japan」の創刊編集長からコンテンツプロデューサーを務められていますが、実は前職のNHK出版時代にプライベートで『PLANETS vol.8』(2012年)の制作も手伝っていただいてたんです。その後も、宇野のネット番組で仮想通貨について語っていただく機会などもあったんですが、そんなご縁の中で「とても面白い人がいるので、ぜひ紹介したい」ということで、施井泰平さんをご紹介いただいたんですね。 施井さんは、ご自身も美術家として活動されているだけでなく、「アート×ブロックチェーン」を掲げるスタートバーン株式会社を2014年に創業されて、2020年8月にアート作品の流通・評価のためのブロックチェーン・インフラ「Startrail」をイーサリアムメインネット上に公開されています。こうした動向について、テック系やビジネス系のメディアではよく取り上げられてるんですが、この施井さんの事業がアートという営みにとってどんな意味があるのか、もっと本質的な話を伺いたいと思ったんですよ。ということで、今日はお二人に「ブロックチェーン技術がアートの価値創造をどう変えるのか」というテーマについて、ぜひ掘り下げていっていただければと思います。 まず最初に、お二人が知り合われた経緯からお伺いできますか?
久保田 はい。NHK出版を辞めて『CoinDesk Japan』編集部に移った直後の2019年1月、「ブロックチェーンから考える ゲームとアートで〈価値〉を創る方法」というイベントを開催しました。そこに施井さんに登壇いただいたのが、出会いでしたね。当時はブロックチェーンの活用法が模索されはじめたばかりで、2020年現在と比べても、まだまだ先が見えない状況でした。そんな中、ゲームとアートという切り口から社会実装の方法を考えるイベントを開催することになり、スタートバーンでアート領域の変革に取り組まれていた施井さんにお声がけしたんです。
施井 そうでしたね。知人から突然「久保田さんという信頼できる人が手がけるイベントだから、面白いはずだ」と連絡が来て、参加することになりました。そうしたら、登壇前の打ち合わせの段階から「あれ、なんかこの人ちょっと違うぞ」という感覚があって。モデレーターをしてくれたときも、トークやコミュニケーションの勘所が圧倒的に鋭くて、「この人は何者なのだろう」という第一印象を抱いたことを覚えています。
──そのイベントでは、どんな議論が展開されたのですか?
久保田 最も印象に残っているのが、「ブロックチェーン技術によって、デジタル空間上の“現実感”が変わっていく」という話です。よく言われているブロックチェーンの技術特性のひとつに、「改ざんできない」点があります。つまり、デジタル空間上に、複製できないものを作ることが可能になる。一般的には、デジタル空間の特性は情報を無限に複製可能なものとして捉える点にあるわけですが、それとは真逆の発想になっているのが面白いと思いました。ゲームとアートが複製できないものになったとき、デジタル空間が現実空間に近づいていく。デジタル空間の中にも、土地の権利やそれを保証する管理者のような概念が生まれてきて、セカンドライフ的なメタバース(現実の機能を代替する仮想共有空間)が実現するのではないか、といった話をしましたよね。
施井 そうでしたね。僕なりの言葉でいえば、「デジタルに実存を与える」ということです。たとえば、ゲームに出てくる勇者の剣は、誰もが皆同じように主人公の気持ちになれるよう、いわば無限に複製されているといえます。でも、ブロックチェーンによって一意性と来歴が保証されると、固有の剣になる。現実世界と同じように、何十個、何百個と量産されてはいるけれど、それぞれの来歴が、ゲームを横断したかたちで、数百年後まで歴史として記録されることが可能になる。そうすれば、現実空間における「豊臣秀吉が使った刀」のように、「あのプレイヤーが使った剣」といった“実存”を与えられるのではないかと盛り上がりました。 また、競走馬育成シミュレーションゲーム『ダービースタリオン』の例についても議論しましたよね。従来の育成ゲームは、クリアしたらその成果がリセットされてしまいます。しかし、一回育てたものが他のゲームに引き継げるようになると、現実世界における実存に近づいていきます。複製可能なデジタル空間ではアウラが消失していく、といった議論とは、まるっきり逆のかたちで実存が与えられていく。
──これは面白いですね。2000年代から2010年代にかけての社会では、インターネットをはじめとした情報技術の普及に伴って複製可能な「情報」の価値が目減りし、相対的に一回性の高い「体験」の価値が高まっていくという変化の潮流が顕著でした。典型的には、音楽産業で言えば、CDのようなパッケージメディアでのコンテンツの売り上げが激減する一方で、現場と紐づいた体験型消費が高まり、音楽フェスやライブアイドルの隆盛につながっていった。 しかし、ブロックチェーンをそれまでの情報技術とはまったく違ったかたちで活用することで、体験価値が生む一回性とは、さらにまた別の唯一性が生まれてくる。ベンヤミンが論じていた「複製技術時代のアウラの喪失」を、ある意味で反転させる方向で、人工的なアウラが創出されるということですね。
施井 はい。すごく大きな話をすると、ブロックチェーンは、脈々と続いてきたデジタル革命のラストパンチ、言ってみれば究極的なピースになりうるのではないかと思っています。当初はただのサブ空間だったデジタル空間が、閾値を超えてメインの空間に取って代わるきっかけになりうる。インターネットは登場以来、その技術的な解像度を高めていく方向で発展してきましたが、その全体的な流れにおける最後の大きな革命が、ブロックチェーンなのではないかと思っています。
ウェブ 2.0時代のクリエイティビティはどこへ向かったか
──そうした構想を練り上げるに至るまでの、施井さんのアーティストとしての来歴もお伺いしたいです。アートワークを拝見すると、メディア技術を主題とした作品も多いですが、どのようにそうしたモチーフにたどり着いたのでしょうか?
施井 もともと美大の油絵科に通っていて、その頃からアーティストを目指していました。油絵科は音大でいえばピアノ科のような、西洋美術のメインストリームとみなされている専攻なので、アーティストを目指す人が行く傾向にあります。卒業後は死ぬまで価値のある創作を続けていきたいと思っていたので、「長いキャリアの中で登るべき山は何なのか?」を考えていました。そして美術史を振り返っていくうちに、技術革命によって社会が大きく変わるときに、象徴的なアーティストやムーブメントが生まれていることがわかってきたんです。そこで僕もアート活動を続けていくうえで、大きなテクノロジーの変革を象徴するような創作を手がけていきたいと思うようになりました。
【12/15(火)まで】オンライン講義全4回つき先行販売中!三宅陽一郎『人工知能が「生命」になるとき』ゲームAI開発の第一人者である三宅陽一郎さんが、東西の哲学や国内外のエンターテインメントからの触発をもとに、これからの人工知能開発を導く独自のビジョンを、さまざまな切り口から展望する1冊。詳細はこちらから。
1 / 1