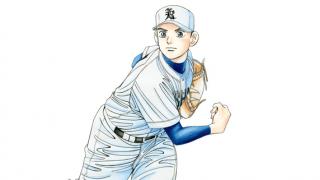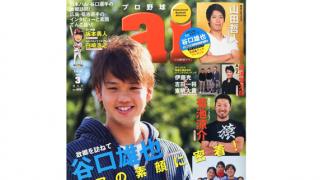-
いま野球界の構造はどうなっているのか? 選手育成過程と、今夏の「女子マネージャーと硬式球」問題(「文化系のための野球入門――ギークカルチャーとしての平成野球史」vol.3)☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.665 ☆
2016-08-12 07:00チャンネル会員の皆様へお知らせ
PLANETSチャンネルを快適にお使いいただくための情報を、下記ページにて公開しています。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/ar848098
(1)メルマガを写真付きのレイアウトで読む方法について
(2)Gmail使用者の方へ、メルマガが届かない場合の対処法
(3)ニコ生放送のメール通知を停止する方法について
を解説していますので、新たに入会された方はぜひご覧ください。
いま野球界の構造はどうなっているのか?選手育成過程と、今夏の「女子マネージャーと硬式球」問題(「文化系のための野球入門――ギークカルチャーとしての平成野球史」vol.3)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2016.8.12 vol.665
http://wakusei2nd.com
2016年は清原元選手の逮捕、巨人選手の野球賭博問題、プロ球団の試合前後の金銭授受など、野球界で様々な問題が噴出しました。またアマチュア野球においては、この夏も女子マネージャーの高校野球への参加をめぐって「炎上事件」が起きています。本記事では、野球界が抱える構造的な問題を、より俯瞰的な視点から解説します。
▼執筆者プロフィール
中野慧(なかの・けい):1986年生、PLANETS編集部。文化、政治からスポーツまで色々な書籍・記事を担当しています。過去の構成担当書籍に『静かなる革命へのブループリント』(宇野常寛編、河出書房新社)、『ナショナリズムの現在』(著・小林よしのり他、朝日新聞出版)、『「絶望の時代」の希望の恋愛学』(宮台真司編、KADOKAWA/中経出版)等。
過去の配信記事一覧はこちらから。
前回:「高校野球カルチャー」の本当の問題点とは?――高野連、坊主頭、夏の大会「一票の格差」を考える(「文化系のための野球入門――ギークカルチャーとしての平成野球史」vol.2)
本記事に関するご意見、ご感想等は、こちらまでお送りください。
■野球文化の問題点は「特別扱い」「異常なことを異常だと感じられなくなっていく構造」
久しぶりの配信になりますが、最初に宇野編集長より与えられたこの連載のミッションは「いま文化系にとって野球とは?」を語っていくことでした。野球文化にはまだ明示的に語られていない面白い要素があるのでそこをメインにしたい――と思っているのですが、前回の記事を配信した際に様々な方から感想をいただいて、野球に詳しくない人にはまだまだ不親切な部分があったと感じました。
今、野球界は様々な問題を抱えています。まずは、「現状のプロ、アマチュア含めた野球界の全体像はどういうものか?」「いま騒がれている問題の根源はどこにあるのか?」について、野球に詳しくない人に対してもわかりやすく見取り図を整理したいと思います。そこで今回の記事は編集担当者でもある僕(中野)の発表パートにして、その後にこれまで座談会に参加してくれた皆さんも含めて、討議形式で考えてみたいと思います。この発表パートでは、野球に詳しい人であれば「そんなの当たり前でしょ」と思うような部分も詳しく解説していきます。
結論から言うと、野球文化の問題点は「特別扱い」「異常なことを異常だと感じられなくなっていく構造」にあると思っています。
まずは、現状メディアに出ている問題の数々を順番に整理してみることにします。今年(2016年)、元プロ野球選手の清原和博が覚醒剤で逮捕され、巨人選手が野球賭博に関与していた事件の詳細もより明らかになりました。さらにプロ12球団中8球団で、試合前に各選手が現金を拠出し合い、試合前の円陣で声出しを担当した選手に、勝った場合には「ご祝儀」と称して金銭を与え、負けた場合には当該選手が現金を支払うという慣習が定着していたことも発覚しました。
基本的に刑法の賭博罪において、「ゴルフで勝負して負けた人が勝った人にジュースをおごる」というような行為は、その場で消費できる少額のものであるので許容されています。「声出し金銭授受」に関しては数万円と金額が大きくなるので賭博罪に該当する可能性も高くなってくるのですが、まだグレーゾーンの範囲のため、プロ野球を統括するNPB(日本野球機構/プロ野球の統括団体)は選手たちに処罰を下しませんでしたし、刑事事件に発展する可能性も低いとされています。
ただ、巨人選手の賭博行為に関しては、そもそも野球賭博は公営ギャンブルではないため関与すると賭博罪に該当します。また、NPBが制定している「野球協約」というルールでは野球賭博に関与することが明確に禁止されているため、NPBは3選手を永久追放、1人を1年間の出場停止という処分を下しました。この件については警察も動いており、主犯格の1人が今年4月に逮捕されています。
そしてこの問題と前後して、西武・巨人・オリックスで活躍したスーパースターである清原和博が覚醒剤取締法違反で逮捕されています。保釈時に報道陣が大挙して押し寄せるなどメディアスクラムが加速した一方で、「覚醒剤のような依存症に対しては『刑罰』ではなく『治療』によって対処すべきだ」という意見も出ています。
(参考)
薬物依存症は罰では治らない(松本俊彦/精神科医)SYNODOS-シノドス-
薬物問題、いま必要な議論とは(松本俊彦×荻上チキ)SYNODOS-シノドス-
清原事件と巨人選手の野球賭博問題に関しては、「タニマチ」の存在がクローズアップされました。タニマチとはもともと相撲界の言葉で、スターと私的に付き合い、金銭的なバックアップをするお金持ちの支援者のことです。相撲、芸能界、野球界など比較的古い世界では、こうしたインフォーマルな関係はよくあることだとされています。
ただ、タニマチは必ずしも善人ばかりではなく、中には裏社会と繋がりのある人たちもいたりします。そういった「悪い人」の中には野球賭博を開帳している人もいたりしますし、芸能界との繋がりのなかでスターを薬物使用に引き込んでいくような文化もあるわけです。
プロ野球界においては、巨人・阪神という伝統的に人気のある2球団の選手にタニマチがつく場合が多いとされています。また巨人・阪神に限らず、アマチュア時代から人気のある選手にもタニマチがつく場合があります。そういったインフォーマルな付き合いのなかで、清原も、そして巨人選手たちも悪事に手を染めていったのではないか、というのが現状出ている議論ですね。
また、今年7月になって「ハンカチ王子」こと日本ハムの斎藤佑樹選手も、個人的につながりのあるベースボール・マガジン社の社長に「ポルシェをねだる」ということをしていた疑惑が「週刊文春」によって報じられました。これに関しては基本的には違法性はない(あるとすれば車庫証明違反等)わけですが、「高い年俸を貰っているプロ野球選手である以上、ポルシェに乗りたいなら自分で稼いだお金で買うべきだ」という批判も出ています。ここでは違法かそうではないかというよりも、スポーツ選手としてのイメージが問題になっているわけです。
こうした数々の問題に、深いところで共通するものが、「野球の特別扱い」と、「異常なことを異常だと感じられなくなっていく野球界の構造」だと思っています。たとえば「出版社の社長にポルシェをねだるとお金を出してもらえる」というのはとても普通の感覚ではありえないことですが、そういった異常なことを「異常だと感じられなくなっていく」構造が野球界には深く根付いています。
■「高校球児のコスプレ」をする野球エリートたち
なぜそうなってしまったのか。様々な要因が考えられますが、社会と野球との関わりということで言えば「戦後社会で野球があまりにも特別扱いされすぎてきた」、そして野球界内部の問題で言えば「野球エリートの育成課程に問題がある」ということだと思います。
先に結論を言ってしまうと、サッカーのJFA(日本サッカー協会)のように、プロ・アマを総合的に統括するような組織が野球にはないことが最大の要因です。これはしばしば色んな人が言及していることですが、もっともっと強調されていいことです。
日本の野球界はアマチュアとプロがずっといがみ合ってきた歴史があります。さらにアマチュア野球界内部でも高校と大学では統括する組織が違いますし、大学野球界ではさらにひどい縄張り争いが繰り返されてきました。そういった歴史の積み重ねと、日本社会における「野球」というものの独特のプレゼンスの大きさが歪みを引き起こし、ここに来て様々な症状として噴出しているのだと思っています。
まずは、「野球エリートの育成課程」の特殊性について説明していきたいと思います。基本的にプロ野球選手になる人の多くは、小学生のときに野球やソフトボールを始めている場合が大半です。学童野球はゴムでできていて安全な「軟式球」を使うことが多く、軟式野球の場合は、年代別に小学校低学年なら「D球」、高学年は「C球」、中学は「B球」、高校〜一般は「A球」とそれぞれサイズと重さが違う球を使います。軟式球は日本発祥の規格です。
しかし、特に才能がありそうな子はプロと同じ「硬式球」を使う「ボーイズリーグ」「リトルリーグ」「ヤングリーグ」といった組織に所属するクラブチームでプレイします。「将来にわたってトップレベルでプレイし続け、プロ野球選手を目指すのであれば、早めに硬式球に慣れていたほうがいい」というわけです。ちなみに「本場」であるアメリカでは野球といえば硬式球を使うものなんです。アメリカ人は軟式球の存在すら知らないことが多いですね。日本における軟球の代わりとしてソフトボールがすごく人気があったりします。
▲下段左が硬式球、真ん中が軟式球。硬式球はコルクの周りに糸を巻き付け牛革で覆っているが、軟式球は内部が空洞になっており外皮はゴム(ちなみに一番右のボールは準硬式球と呼ばれ、内部構造は硬式とほぼ同じだが外皮が軟式と同じゴムでできていて、中間的な球。準硬式球のプレイヤー数は硬式・軟式と比べるとかなり少ない)。硬式球はほとんど石のような固さで、投球や打球が直接身体に当たるととても痛く、骨折の危険性も高いが、軟式球が当たって骨折するケースは非常に少ない。(画像出典)野球図鑑|ホームメイト・リサーチ
【ここから先はチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は今月も厳選された記事を多数配信します! すでに配信済みの記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201608
-
人間の「伸びしろ」を測定することは可能か? ――統計学的思考の教育への応用可能性 鳥越規央(統計学者)×藤川大祐(教育学者) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.439 ☆
2015-10-28 07:00チャンネル会員の皆様へお知らせ
PLANETSチャンネルを快適にお使いいただくための情報を、下記ページにて公開しています。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/ar848098
(1)メルマガを写真付きのレイアウトで読む方法について
(2)Gmail使用者の方へ、メルマガが届かない場合の対処法
(3)ニコ生放送のメール通知を停止する方法について
を解説していますので、新たに入会された方はぜひご覧ください。
人間の「伸びしろ」を測定することは可能か? ――統計学的思考の教育への応用可能性 鳥越規央(統計学者)×藤川大祐(教育学者)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.10.28 vol.439
http://wakusei2nd.com
今朝のメルマガでお届けするのは、統計学者でセイバーメトリクスの専門家でもある鳥越規央さんと、教育学者の藤川大祐さんの対談です。
8月末、藤川先生の携わるNPO「企業教育研究会」及び「日本メディアリテラシー教育推進機構」の主催で、ロッテ×オリックス戦(QVCマリンフィールド)にて鳥越先生のセイバーメトリクス観戦講座が開催され、PLANETS編集部も参加してきました。今回の記事ではその講座のレポートに加えて、その後行われた「セイバーメトリクスや統計学的思考の教育への応用可能性」についての鳥越先生と藤川先生の対談の模様を掲載します。
▼プロフィール
鳥越規央(とりごえ・のりお)
1969年 大分県生まれ。現在の研究分野は数理統計学、セイバーメトリクス、スポーツ統計学。各メディアにて、確率や統計に関する監修を行う傍ら、AKB48じゃんけん大会の監修を行なうなどアイドル・エンターテイメント業界にも精通。著書に『スポーツを10倍楽しむ統計学』(化学同人DOJIN選書、2015年)『勝てる野球の統計学――セイバーメトリクス』(岩波科学ライブラリー、2014年)、『9回裏無死1塁でバントはするな』(祥伝社新書、2011年)などがある。
藤川大祐(ふじかわ・だいすけ)
1965年、東京生まれ。千葉大学教育学部教授(教育方法学・授業実践開発)、教育学部副学部長。NPO法人企業教育研究会理事長。メディアリテラシー、ディベート、ゲーミフィケーション等を含めた新しい授業の開発を研究。著書『授業づくりエンタテインメント!』(宇野常寛氏やAKB48村山彩希さんとの対談も収録)、『いじめで子どもが壊れる前に』、『教科書を飛び出した数学』など。AKB48や乃木坂46のファンで、PLANETSチャンネルの関連番組に出演し、編集長をつとめる『授業づくりネットワーク』には「AKB48の体験的学校論」というコーナーを設け、これまで茂木忍さん、岩立沙穂さんに登場してもらっている。また、千葉ロッテマリーンズのファン。
◎聞き手・構成:中野慧
【お知らせ】本日、鳥越先生をお迎えしてプロ野球日本シリーズ 福岡ソフトバンクホークス vs 東京ヤクルトスワローズ 第4戦をテレビ実況します!
前回のクライマックスシリーズ実況ニコ生から引き続き、統計学者でセイバーメトリクスの専門家・鳥越規央先生による解説を軸に、アイドルグループPIPきっての野球好きである空井美友さん、そしてお笑いコンビ「カオポイント」石橋哲也さんをお招きしてお送りします。
▼ニコ生番組ページはこちらから。
http://live.nicovideo.jp/gate/lv239966175
■ 鳥越先生の「セイバーメトリクス観戦講座」レポート
鳥越先生による観戦講座が行われたのはまだ夏の暑さの残っていた8月29日。あいにくの曇り模様のなか、急造のPLANETS野球取材チームはたくさんの人でごった返す海浜幕張駅に到着しました。
千葉ロッテマリーンズのチームカラーは白・黒・赤・グレーですが、駅で周りを見渡すと、もっとカラフルな出で立ちの人ばかり。色は、赤・黄・緑・ピンク・紫……これはもしや、ももクロ……!? 調べてみると案の定、ももクロのファンクラブ会員限定イベントが幕張メッセのイベントホールで行われていたようです。やはり現代は、アイドル一強時代なのか……?
アイドルに負けない21世紀的な「野球2.0」はいかにあるべきかを構想しながら歩くこと15分、ようやくQVCマリンフィールドに辿り着きました。
モノノフに席巻されていた海浜幕張駅とうって変わり、QVCマリン周辺は少し落ち着いた雰囲気。ロッテファンは昭和からの伝統的な野球応援スタイルと決別し、Jリーグのサポーターを参考に独自の応援スタイルを築き上げたと言われていますが、やはり若い人が多め。
球場そばの「マリーンズ・ミュージアム」には球団の歴史を振り返る展示があり、単なるグッズ売り場というよりは、メジャー球団のボールパークに併設されている博物館のようでした。
グッズショップには、写真のように球団の正式ユニフォームとは違う、オリジナルデザインのNEW ERAキャップが並んでいました。ただ単にユニフォームと同じキャップだと昭和の野球少年になってしまう恐れがありますが、それとわからないさりげないデザインで主張するところに、現代のファンを掴もうという工夫が感じられます。実はこうした取り組みは現在多くの球団が行っているのですが、特にロッテのグッズデザインは洗練されているようです。
▲グッズショップには様々なデザインのグッズが並んでいます。かつて野球場のグッズ売り場といえば掘っ立て小屋やプレハブのようなイメージでしたが、今はまるでセレクトショップのような雰囲気。文明はどんどん発達していく…
▲さっそく試合開始! 先発投手はロッテが左の古谷拓哉(ふるや・たくや)投手、オリックスが昨年ブレイクした西勇輝(にし・ゆうき)投手でした。
▲Macbookでデータを見ながら参加者に解説する鳥越先生。右下にはマリーンズのユニフォームに身を包んだ藤川先生の姿も。
この日の参加者は30人ほど。鳥越先生の解説は、手渡されたトラベルイヤホンで聞くことができます。一緒に来た人と解説の感想をわいわいと言い合ったり、鳥越先生ご本人に直接質問したりすることができます。
▲(株)エアサーブの提供するトラベルイヤホン。普段は美術館の音声ガイドなどに使っているそうですが、球場で生観戦しながら解説を聞けるというわけです。他にもいろいろ応用できるかも……?
また、ゲストとして鳥越先生のご友人というプロ野球選手のモノマネ芸人さんたちも登場。
▲左からニセ勇輝さん(西勇輝投手のモノマネ芸人)、伊藤ピカルさん(伊藤光選手)、小谷野ええ位置さん(小谷野栄一選手)。一般的にそれほど有名とはいえないオリックス選手のモノマネを選択されることに男気を感じます。ただ小谷野ええ位置さんは坂上忍のモノマネで定評を得るなど、みなさんレパートリーは豊富なよう。
▲そして、あれは、く、桑田さん……? 元メジャーリーガーも幕張に駆けつけました
オリックス選手以外にも、巨人〜ピッツバーグ・パイレーツで活躍した桑田真澄さんのモノマネ芸人・桑田ます似さんが1イニングだけでしたがゲスト解説に登場し、桑田そっくりの語り口で参加者の笑いを誘っていました。
試合は1回にいきなり糸井が2ランホームランを放ちオリックスが先制するも、その後ロッテ先発の古谷がオリックス西に負けじと好投。ロッテがじわじわと追い上げて6回に逆転に成功し、9回は守護神・西野が危なげなく試合を締めました。(試合結果はこちら http://baseball.yahoo.co.jp/npb/game/2015082905/top)
鳥越先生はデータから古谷の好投を予想、打球方向の傾向から8回のヘルマンの左中間二塁打を的中させるなど、プロ野球OBの解説にはない語り口が新鮮でした。
▲地元ロッテが勝利し全身で喜びを表現する藤川先生
■ 「現場で解説を聞く」という新しい観戦スタイル――メディア論的観点から
――今回は鳥越先生と藤川先生のお二人に、「セイバーメトリクスや統計学的思考の教育への応用可能性」というテーマでお話を伺っていければと思うのですが、まずは今回の観戦講座について振り返ってみたいと思います。藤川先生はいかがでしたか?
藤川 いや~、楽しかったですよ。「楽しい」って色々な意味があるんでしょうけれど、まず野球場で野球を見るということは基本楽しいわけですが、耳元で鳥越先生が解説してくれてこちらから質問できて、データに着目していくと目の前に起こっていることも確率的に説明がつくことが多かったじゃないですか。フィールドの雰囲気プラス知的な楽しさが重なって、本当に楽しい時間を過ごすことができましたよね。
――鳥越先生は「左投手の古谷に合わせてオリックス打線は右バッターを並べてきたけれど、それは逆効果だ」とおっしゃっていましたよね。
鳥越 先発投手としての格で言えば古谷よりも西の方が上なわけで、戦前の予想もオリックス有利と出ていました。しかしスタメンが発表されたとき「おや?」って思ったんです。というのもオリックスのスタメンが糸井を除いてすべて右バッターだったんです。それまで調子のよかった左の小田裕也や駿太をはずして。たしかに古谷は左投手ですが、データを見ると右バッターに対する被打率が1割7分3厘(当日までのデータ、シーズン通算。185)と、じつは右打者のほうが得意な投手なんです。野球界では「左投手は左打者が得意」という定説があって、それは統計的にもある程度正しいのですが、古谷に関してはそれが当てはまらない。なので右バッターを並べるというオリックスの選手起用はよくなかった。それがオリックスの敗因のひとつでしょうね。
あと、今日の試合をセイバーメトリクス的な観点からみていて良いと思ったのが、ロッテが角中(勝也)を2番に置いているということでした。日本野球ではとかく2番に出塁率がいいわけではないけども、バントは上手いという選手を置きがちですが、序盤のノーアウト1塁で送りバントをするのって統計的には悪手なんですよ。
角中は以前首位打者を取っていて非常にシュアなバッティングをするバッターですが、彼を3番ではなく2番に置く。同じようにヤクルトでは川端慎吾(かわばた・しんご)という3番を打っていてもおかしくない打者を2番に置いていましたよね。こういったことは非常に良い傾向だと思います(その後、川端はセ・リーグ首位打者のタイトルを獲得、所属するヤクルトはセ・リーグを制覇した)。
藤川 「2番は送りバント」っていうのはだいぶ廃れつつあるんじゃないですか?
鳥越 いえ、たとえば今年のソフトバンクはまだ2番は打力のそこまで高くない選手を起用しています。ただソフトバンクには圧倒的な戦力がありますから、2番の起用に関しては相手チームにハンデを与えているものと思ってみています(笑)。本来なら柳田(悠岐)のような強打者を2番に置いたほうが得点はもっと増えますよ。(注釈:ただ2番に起用される選手の守備力はリーグ随一なので、そういう意味では必要不可欠な選手です、ただ打順が……。)
藤川 おそらくデータを見ずにただグラウンドで見ていたら今日の試合も、「ロッテが逆転して逃げ切った」というストーリーにしかならないんですけど、データがあることによってどこにドラマがあるのかがわかるから、より深く楽しめるんですよね。
鳥越 野球って「左ピッチャーには右バッターを当てろ」みたいなステレオタイプがたくさんあるんですけど、そういう「思い込み」に惑わされないようになるというのが、データで野球を観ることの面白さのひとつですね。
――藤川先生は教育学者として「エンタテインメントの方法論をどう教育に生かすか」や、メディアリテラシー教育について発言していらっしゃいますが、メディア論的な視点からみて今日の観戦講座の試みをどう感じましたか?
藤川 鳥越先生の解説で面白かったのは、オリックスのヘルマンというバッターが左中間に打つ確率が高いというのと、守るロッテ外野陣の荻野・岡田・清田の守備範囲がすごく広いので、そのせめぎあいが見どころとおっしゃっていたところ、ヘルマンが本当に左中間にツーベースを打ったんですよね。もしテレビで見ていてそういう解説があったとしても、テレビはピッチャーとバッターを主に映すから、外野陣の守備位置までは見ることができないじゃないですか。その意味で、球場全体を見渡すことのできる視点から解説を聞くことの面白さを感じましたね。
――「予言を当てる」といえばジャイアンツ戦での江川解説なんかがありますけど、江川の場合は経験知とカンに基づいた「神がかり」のようなものであるのに対し、鳥越先生の解説は統計的な根拠に基づいたものなのでより身近に感じることができますよね。
藤川 やっぱりテレビの画面にとって野球場って広すぎるんですよね。これは球場などのいわゆる「大箱」でやるAKBのコンサートでも感じるんですけど、200人とかのメンバーがウロウロしていても、スクリーンの画面に映るのって1人2人なんですよ。常に99%の人が映っていない。たとえば、私の推しメン(村山彩希さん)はそこまで推されているわけでもないので会場のビジョンに映る機会も少なく、肉眼で探すのが大変なんです(笑)。
サッカーなんかはテレビでもフィールド全体を映すので選手の位置はよくわかりますけど、野球はテレビ中継では投手と打者以外に球場で他の選手が何をやっているのかよくわからない。球場だったらネクストバッターズサークルで「次は誰が代打に出てきそうだ」とかわかるじゃないですか。その意味で、自分で見る場所を選べる現場観戦は非常に価値がありますね。
鳥越 もしマスメディア的に野球を盛り上げるんだったら投手と打者の「一対一勝負」をクローズアップしてドラマ性を盛り上げていくことになるんですが、データは一対一勝負以外の様々な場面で使えるので、テレビだけだとどうしても解説できることが制限されてしまうというのはありますね。
――数年前から楽天や横浜DeNAのようなIT系球団を中心に主催試合をニコ生やSHOWROOMなどでネット中継していて、ネタコメントが流れたり、アナウンサーのフリーダムな実況が面白かったりして非常に人気があります。横浜の場合、1試合のニコ生視聴者は20万人以上になることもあるんですが、無料公開だから球場に来なくなるんじゃないかと思いきや、スタジアムへの来場者も右肩上がりなんですよね。
藤川 やっぱりメディアとスポーツってすごく重要な関係があるわけですけど、まずメディアで見て現場に行きたくなって、現場で楽しんで行けないときはメディアで楽しむというかたちですよね。で、従来は現場に行くと解説を聞けなかったんですよ。やっぱり今の時代は本当に楽しみたければ自分でデータ見たりしながら人の話も聞いていたい。ところが今回は鳥越先生が全部その場で調べてくれて、しかもそれをリアルタイムで教えてくれるわけですからね。
鳥越 昔は横浜スタジアムや神宮球場で球場内FM放送といって、案内されたFMの周波数に合わせると誰でもDJのトークを聞けるというものがあったんですが、「ラジオ聞きながらだと集中してしまってファールボールに気づかないから危険」という理由で廃止になってしまった。でも今回は2階席からだったからそこまでファールボールの危険性もなかったですね。
球場にラジオを持ち込んで実況中継を聞きながらみるのもいいのですが、「第1球投げた!」という、映像を見ていない前提の細かな実況が煩わしく感じてしまったり、radikoで聞くと5秒のズレが生まれてしまったりするんですよね。
藤川 球場でピッチャーが投げたのを見た5秒後に「ピッチャー投げた!」っていう実況が流れてくるのは許しがたいですね。
鳥越 そういう意味では、エアサーブさんのイヤホンガイドによる実況解説は聴講されたみなさんにもストレスを感じさせることはなかったと思います。
藤川 誰でも聞けるというかたちではなく、特定のゾーンの人だけが聞けるシートを設けるなどしてプレミア感を出したほうがいいですよね。
――いまIT系の球団を中心に、様々なプレミアを付けたシートを少し高い値段で売り出していますが、それが当初の予想以上に売れているようです。砂かぶり席(球場のファールゾーンに新たに客席を設置してより臨場感が楽しめるようになっている。来場者にはファールボールの危険に備えてヘルメットとグローブが貸与される)が代表的ですが、スタジアムの上の方の座席を改造してパーティーができるような席種も販売されています。普通なら「チケットを値上げしたら売れないだろう」と思うのですが、むしろ様々な付加価値を乗せて高く売ることで全体の売上は増える。そういうビジネスモデルのひとつとして考えてみてもいいかもしれないですね。
▲広島カープの本拠マツダスタジアムに設置された内野パーティーデッキ。
http://www.carp.co.jp/ticket/zaseki/partyfloor.shtml#deck
▲横浜スタジアムに今年から新設された「ベースボールモニターBOXシート」。居酒屋のような席配置で友人たちと飲み会をしながら観戦できる。テーブル中央にはタブレットPCが設置されており、選手の成績やリプレイ、実況映像なども見ることが可能。
https://www.baystars.co.jp/ticket/2015/regular/seat.php
――もうひとつ今日の観戦講座で感じたのが、「鳥越先生の今の解説面白かったよね」というように、一緒に来た人や隣の席の人とコミュニケーションするきっかけになるということなんです。
鳥越 そういうエリアシートって今までになかったわけですから面白いですよね。その場に集まった人でも仲良くなれるでしょうし。ほんと、そういうシートを売り出して欲しいですね。一消費者として(笑)
実は今、アプリ開発を考えているんです。どういうものかというとスマホで音声が聞けて、そこに文字情報を入力してもらってニコ生のコメントみたいに実況者側が拾っていくというものです。ただスマホだけだと入力が大変なんですけどね。
こういうことは野球だけではなく色んなスポーツで試せると思っていて、もちろんサッカーもそうですし、大相撲なんかでできたら面白いはず。
藤川 大相撲こそ、現場で解説があったらものすごく楽しいでしょうね。解説なしで見てると何が何だかわからない。現場にいたら間合いも長いですし、立ち合いで力士が何回立ったかとか、そういう情報もあったらいいですよね。
鳥越 チケットの売り方にしても、いろいろとデータを活用すれば見えてくるものは多いはずです。そういう意味でオリックスは集客にデータ解析を使ってるんですよ。ファンクラブサイトに書き込まれる文字をデータマイニングして、「今はこの選手が注目されてる」ということを弾き出して、その選手のグッズを強化して売りだしたりしています。
もともとオリックスは観客動員数が少ないチームだったんですが、女性ファンにアピールするために「オリ姫」企画なんかをやっていますよね。実は関西の女性野球ファンって母数が非常に多いんですよ。もちろん阪神ファンを中心にですが。で、阪神の試合が甲子園で開催されていない日にオリ姫企画をやると、阪神ファンの女性が「じゃあ今日は私、オリ姫になる」と言って来るんですよ。
――昔は関西といえば南海ホークスや近鉄バファローズがあったりして競合が多かったけれど、パ・リーグでは在阪球団がオリックスだけになったから関西の野球好きは「セは阪神、パはオリックス」がひとつのかたちになるという。近年プロ野球チームが地方展開していったことの副産物かもしれないですね。
■ 集団には「均質性」と「多様性」のバランスが必要
――ここからは今日のテーマでもある「データや統計学的手法を教育にどう応用するか」を伺っていきたいと思います。まず基本的なところを藤川先生にお聞きしたいのですが、現代の教育現場では先生が持っている生徒一人一人のデータというのはどういうものなんでしょうか?
藤川 教師によるというところはあるんですが、基本的には文部科学省が策定した学習指導要領に基づいて、教師が「評価基準」を設けます。これは、「知識・理解ができているか」を測るというものがあり、それに加えて「関心・意欲・態度」や「思考・判断・表現」といったものが加わります。到達目標を時間や単元で決めていって、どの子が目標に到達しているか/していないかを評価するというやり方です。こうしたことは、教師はまず義務としてやらなければなりません。
一方でユニークな指導をしている先生のなかには「意外な発見を書く」ということをやっている方もいます。子供を見ているときに、予想通りの発見や予想通りの気付きだったら別に記録しておかなくてもよいですよね。しかし、「おとなしいと思っていた子が意外なところでリーダーシップを発揮している」とか「普段はすごく自信を持っている子が逆に物怖じしてしまっている」とか、そういう姿を見つけたら書く。これはその子を発見的に見ていくために有効なんです。
さきほど鳥越先生は「人は人を思い込みで見てしまう」とおっしゃっていましたが、人間は多様な側面を持っているものですし、そもそも小中学生ぐらいの時期って人間はめまぐるしく成長するんです。一番気をつけるべきなのは、教師が子供のことを第一印象で決めつけてしまって、そうではない姿を見ても見ぬふりをして指導にあまり活かさないということ。固定観念というのはスポーツにかぎらず教育においてもとても怖いものなんです。
鳥越 教育の評価基準について僕が感じているのは、ある2つの評価基準があったらそれを単純に足して2で割るような発想をしてしまっているということです。でもそうではなく5〜6個の要素をベクトルと見て、それを5〜6角形のマトリクスにしてその面積の大きさで評価する、そういうやり方のほうがいいのではないか。
藤川 多元的に評価するということですね。
鳥越 それと、昔は評価って相対評価だったじゃないですか。平均を3として、そこからどれだけ離れているかで成績を判断する。でも今は絶対評価で、「ここまでできたら4」「これが完璧にできたら5」というように判断する。そうなるとみんなが4とか5を取ることが可能で、差別化が難しくなってくると思うんですが、いまの実際の教育現場ではどういうふうに運用しているんですか?
藤川 実際は「みんなが5にはなる」というのはなかなかないですね。教師が評価基準をきちんと作らなければいけないというプレッシャーがあって、みんなが簡単に到達できるような目標ばかりを設定することはありません。現実には、「やっぱりこの子はちょっと無理だよな」という子もいる。だからみんなが一番上の評価を取るというふうにはなりにくいのが現実ですね。
鳥越 なるほど、絶対評価が相対評価に近づいてしまっているわけですね。しかしそれも学校ごとに微妙に違うものになってしまう。そうなるとやはり、推薦入試などで活用可能な統一的な指標としては成り立ちづらくなっていきますよね。
藤川 だから高校・大学では、内申点を入試で使うことは難しくなっていますね。
鳥越 その意味で、かつて批判された偏差値って本当は公平なシステムだったんですよね。偏差値って実は統計学的に非常に素晴らしい発明で、平均が50でそこからどれだけ離れているかを一律に測ることができた。個人の主観抜きに、自分が相対的にどこにいるかを冷静に判断することが可能だったわけですから。
でも、なぜか偏差値だけが一人歩きして、評価が高ければ人格的に評価できる、というようなことになって批判の対象になってしまった。僕は偏差値の良さを再評価してもいいんじゃないかとは思うんですよね。
藤川 ただ、入試で学生を選ぶ側からすると、偏差値はどうしても一元的な評価になりやすいし、何度も繰り返しやったらブレがなくなっていく。それで上位だからって本当にいいのかということはずっとあります。言い換えると、入試についてはもう少し偶然性があってしかるべきという部分があるんですよ。
これは言い方がなかなか難しいのですが、入学者選抜のような場合にも、スポーツぐらいの確率論的な見方を持ち込んでみてもいいのではないかということなんです。これは決して、「適当に選べばいい」というわけではありません。
そもそも学校教育って個人で学ぶものではないので、ある程度の幅の多様性を確保しておきたい。基本的に学校でも企業でもそうですが、均質的すぎる集団は脆いもの。ある程度の質を担保しつつも、ちょっと違うタイプの人もいるぐらいのバランスが、集団での指導をしやすいんです。
――学ぶときの共同体というものを考えたとき、多様性があったほうが共同体全体の活性化につながるということですか?
藤川 多様であればあるほどいいというわけでもないんです。あんまりにもみんながバラバラだと何も一緒にできないですけど、均質的過ぎると発想が貧困になったり、均質さゆえにお互いが潰しあったり、一人ひとりの良さが発揮されにくくなる。だから多様性と均質性のバランスをとるという意識がすごく大事だと思いますね。小学校の学級経営や中学校の部活指導もそうです。均質すぎると異質な人が排除されていじめられてしまうということもあるので、逆に異質な人を活かすように集団を作っていくというのが教育をしていく上では常に課題ですよね。
決定論的に緻密な評価を行って集団の構成を決めるのではなく、確率論的なブレを担保しておくということ。スポーツというエンタテインメントにしても、どっちかが有利だから必ずその通りになるというのではなく、確率論的に結果が覆ることがあるのが面白いわけですよね。
■ ランダム指名はなぜ有効なのか――「偶然のチャンスをモノにする」ということ
藤川 確率論ということでいえば、私はよく授業で「ランダム指名」をすることの有効性を言っています。どういうことかというと、先生から指名されたら、どんなにその課題が苦手であっても、他の子に助けてもらってもいいから全力で発表する。そのかわり、当たっていないときは自分のペースでゆっくりやってもいい。当たったときは集中してやって、そうでないときは無理せずというように、メリハリをつけるんですよ。たとえば算数の授業とかってどうしてもずっと活躍する子と、ずっと活躍しない子に分かれてしまう。そうなると先生はできそうな子にばっかり当てるんですよ。
鳥越 50分で終わらせるという授業運営のことを考えるとどうしてもそうなってしまいますよね。
藤川 でもそれでは、できない子はずっとできないままになってしまう。一方で、できない子にばっかり当ててしまうのも辛いわけですよ。
――「完全にランダムである」ということが重要なわけですよね。先生が、例えばあまりできない子に対して「これぐらいの簡単な問題だったらできるだろうな」という意図を持って指名するのもよいことではないと。
藤川 やっぱり、先生の意図どおりに動かされていると思った瞬間、白けちゃう子はたくさんいます。そうではない運営をするというのが、授業技術的に大事なことなんですね。そういう意味で、ランダムで、時々自分が主役になる場が巡ってくることにすごく意味があるわけです。
子供ってやっぱり突然目覚めることがあるんですよ。逆に言えばチャンスが来なければなかなか目覚めない。かといって毎回チャンスを与えられると辛く感じる。スポーツってよくそういうことがあるじゃないですか。たまたまチャンスを与えられたら偶然に打ってしまって、それで一皮むける、というような。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は今月も厳選された記事を多数配信します! すでに配信済みの記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201510
-
弱者なら「守り抜く」のではなく「打って勝て!」――高校野球文化と「散る美学」(『砂の栄冠』完結記念・三田紀房インタビュー) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.415 ☆
2015-09-24 07:00チャンネル会員の皆様へお知らせ
PLANETSチャンネルを快適にお使いいただくための情報を、下記ページにて公開しています。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/ar848098
(1)メルマガを写真付きのレイアウトで読む方法について
(2)Gmail使用者の方へ、メルマガが届かない場合の対処法
(3)ニコ生放送のメール通知を停止する方法について
を解説していますので、新たに入会された方はぜひご覧ください。
弱者なら「守り抜く」のではなく「打って勝て!」
――高校野球文化と「散る美学」
(『砂の栄冠』完結記念・三田紀房インタビュー)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.9.24 vol.415
http://wakusei2nd.com
今朝のメルマガは、「週刊ヤングマガジン」で好評を博した高校野球漫画『砂の栄冠』の完結を記念し、作者・三田紀房先生へのインタビューをお届けします。『ドラゴン桜』『インベスターZ』などのビジネス・教育漫画で著名な三田先生が高校野球を描き続ける理由とは? そして日本独特の「高校野球文化」について、たっぷりと語ってもらいました。
▼プロフィール
三田紀房(みた・のりふさ)
1958年生まれ、岩手県北上市出身。明治大学政治経済学部卒業。代表作に『ドラゴン桜』『エンゼルバンク』『クロカン』『砂の栄冠』など。『ドラゴン桜』で2005年第29回講談社漫画賞、平成17年度文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞。現在、「モーニング」「Dモーニング」(http://app.morningmanga.jp/)にて “投資” をテーマにした学園漫画『インベスターZ』を連載中。
三田紀房公式サイト mitanorifusa.com
公式ツイッター @mita_norifusa
◎聞き手・構成:中野慧
▲『砂の栄冠』最終第25巻は全国の書店やAmazonで好評発売中!
■ 唯一絶対の存在である「高校野球の監督」
――今回は、ヤングマガジンで大人気を博した高校野球漫画『砂の栄冠』の完結記念ということで、三田先生にいろいとお話を伺っていければと思います。
まず三田先生といえば、ドラマ化などもされた『ドラゴン桜』『エンゼルバンク』、そして現在モーニングで連載中の『インベスターZ』といったビジネス漫画のイメージが一般には強いかもしれませんが、『ドラゴン桜』以前からずっと野球、特に『クロカン』(1996年〜2002年にかけて週刊漫画ゴラクで連載)や『甲子園へ行こう!』(1999年〜2004年に週刊ヤングマガジンで連載)のような高校野球をテーマにした漫画を描いてきていらっしゃいますよね。
そこで最初にお聞きしたいのですが、そもそも三田先生が高校野球漫画を描こうと思ったきっかけは何だったんでしょうか?
三田 直接のきっかけというのはあまり思い当たらないんですけど、父の友人で高校野球の監督をやっていた人がいたんです。僕の地元は岩手県で、その人はご実家のお仕事をされていたんですが、仕事のほうはそこまで熱心にやっていたわけではなく、日中はわりとブラブラしていて、午後になると高校に行って野球部の監督をやっていた。「仕事はそこそこで、好きなことをやって生きていける」って、なんかいいじゃないですか(笑)。で、その人は甲子園も3回ぐらい行っていて県内では有名人で、高校行くと監督ですから国の王様みたいな感じだったのも印象的でしたね。その人をなんとなくベースにして、高校野球の監督を主人公にしたいと思って描いたのが『クロカン』です。
――それ以前から、三田先生は野球を好きで見ていらっしゃったりしたんですか。
三田 いえ、高校野球もプロ野球もそこまでちゃんと見ていたわけではないんです。岩手県なんで巨人戦しか見れなかったり、そもそも中継があんまりなかったので、関西や関東の野球好きの人のように「野球が生活の一部になっている」という感じではなかったですね。
『クロカン』連載当時は漫画家デビューして2〜3年目ぐらいだったんですけど、やっぱりまずは自分が企画として考えた『クロカン』を描きたいという思いがあって、いろんなところに持ち込んだんです。でも、「主人公がプレイヤーじゃないからダメだ」「監督がベンチに座ってサイン出してるだけの漫画なんて成り立たないよ」と言われてなかなか採用されなかったですね。それでようやく「週刊漫画ゴラク」で企画が通って、本格的に高校野球漫画を書き始めていって、それからですね。
――今でこそ主人公が監督という漫画は珍しくなくなりましたけど、当時の漫画誌はそういう雰囲気だったんですね。
三田 高校野球って、特に監督の存在が非常に大きいじゃないですか。そこを描いたら絶対に面白いと思っていたんですけど、90年代半ば当時はなかなか理解されなかったというのはありますね。
――僕も高校野球をやっていたんですが、たしかに高校野球って監督の良し悪しがチームの強さをかなり左右しますよね。監督5割、ピッチャーが5割なんて言われたりも。
三田 監督って一球ごとのサインを出したりしますし、そもそもベンチのなかで唯一の大人なんですよね。だからどうしてもおっしゃるような関係性になってしまうということはあります。
■ 「正しい投球フォーム」なんてない!〜『甲子園へ行こう!』
――『クロカン』や『甲子園へ行こう!』を描いていらした時期は、高校野球の現場をたくさん取材されたりしたんですか? 他にも、参考にされた漫画があったりしたんでしょうか。
三田 うーん、それはあまりないですね。取材もあまりしていないですし、漫画にしても水島新司さんの作品はいろいろ読んだりはしてましたけど、基本的に自分でいろいろ考えて描いています。
『甲子園へ行こう!』の頃は「ピッチング理論をちゃんと描こう」というのが企画のコンセプトとしてあったので、牛島和彦さん(80年代〜90年代初頭にかけて中日・ロッテで抑え投手として活躍。引退後は横浜(現:横浜DeNA)の監督なども務め、現在は野球解説者)にお話を聞きにいったことはありました。
「誰でもこれをやればすごいピッチャーになれる」というような”正しいフォーム”の理論のようなものがあるんじゃないかと期待して行ったんですけど、牛島さんからは「正しいフォームなんてない。良い球が行けばそれでいいんだ」とキッパリ言われてしまって(笑)。
――なるほど。牛島さんといえば投球術や「試合への向かい方」のようなメンタル面で鋭い解説をされていて理論派として知られていますが、その牛島さんでさえも投球フォームについては「正しいフォームはない」という考え方なんですね。
以前、長嶋茂雄さんがバッティングに関して「正しいフォームなんてない、来た球にタイミングを合わせて、前に強い打球が飛ばせればそれでいいんだ」「日本人選手はフォームの綺麗さを気にしすぎている」とおっしゃっていました。長嶋さんが言うと「天才だからでしょ」なんて言われてしまうんですが、最近のスポーツ科学でも「人間は意識の指令だけで自分の身体を思い通りに動かすことはできない」っていう知見も出てきていたりしますね。
三田 『甲子園へ行こう!』ではピッチャーが少し前傾姿勢になって「まっすぐ立つ」というテクニックを紹介していますけど、あれも「強いて言えば、いいピッチャーのフォームにはこういう共通点があるかもしれない」というぐらいのものなんですよ。
やっぱり、単に「正しいフォーム」で投げたからといって、打たれたら意味がないわけです。逆に言えば変なフォームでも打たれなければそれでいい。そう言われればそうか、という感じですよね。
たとえば「怪我しにくいフォーム」というものも描きましたけど、それはあくまでも確率論であって、変な投げ方してても怪我しない人はしないし、いい投げ方してもする人はする。身体のつくりも人によってまったく違いますし、何が合っているかは人それぞれなんです。
要は「正しく投げる」ということは野球にはまったく当てはまらない、と。それはそれで描いていて新鮮だなと思いましたね。「こうすれば正しいに違いない」と思い込んでいたものが、意外と大した価値がなかったりするわけです。
――なるほど、フォームのような「過程」ではなく、打ち取れるかどうかという「結果」から逆算していくわけですね。
ちなみに『甲子園へ行こう!』では神奈川の県立高校が舞台でしたが、地区予選のブロック大会から描いていましたよね。神奈川の地区大会って、秋と春は最初は地区ごとに、抽選で4チームずつに分かれて総当りでリーグ戦をやるわけですが、良いグラウンドを持っている「会場校」というシステムがあってそれに基づいて組み合わせが決まる。つまりどんな弱小校でも必ず強豪校と一回当たらなければいけないんですが、その独特の緊張感を描いているのがとてもリアルだなと感じました。
三田 「なるべくリアルに再現しよう」というのは、ひとつのこだわりでしたね。神奈川って私立の強豪校がたくさんあるのもそうですし、県立高校もレベルが高くて他県と全然違うんです。
『甲子園へ行こう!』でも舞台を県立高校にしていますが、非・強豪校が勝ち抜いていくには一番ハードルが高くて、そこでもがいて頑張っていく感じが出しやすいんですね。そういう高いハードルにチャレンジしていくところを描きたかったということがあります。
――神奈川県予選では準々決勝からすべて横浜スタジアムで試合が行われるわけですが、お客さんもたくさん入りますし、甲子園とはまた違った独特の雰囲気がありますよね。ベスト8ぐらいだとどこが甲子園に出てもおかしくないぐらい強くて、横浜・東海大相模・慶應・桐蔭・桐光……挙げればキリがないですが、お互いよく知っていて毎年当たるからライバル意識も強い。横浜スタジアムには独特の高校野球文化があるように思います。
三田 やっぱり高校野球って地域ごとに全然違う文化があるんですよね。逆に大阪府なんて、開会式こそ大阪ドームでやりますけど、準決勝と決勝はわざわざ「舞洲ベースボールスタジアム」という海沿いの不便なところで開催しています。これってわざとそうしているらしいんですよね。
――もし大阪大会決勝で大阪桐蔭 VS PL学園のような好カードが実現したとして、甲子園球場自体は兵庫県(西宮市)なのでできないかもしれませんが、せめて大阪ドームとかでやればいいのにと思ってしまうんですが……。
大阪府は47都道府県で唯一、夏の大会でのシード制を採用していなかったりしますけど、要は「甲子園以前」の大阪府予選にあまり注目を集めたくないんでしょうか(笑)。
三田 大阪はやっぱり、ちょっと変わったこだわりがありますよね(笑)。
■ 『砂の栄冠』で描かれた、本当にいる「高校野球オタク」な人たち
――『甲子園へ行こう!』までは高校野球のドキュメントというか、選手一人ひとりの頑張りのドラマであったり、練習やそれ以外の時間を含めてチームの結束をどう固めていくかという部分に焦点が当たっていたと思うのですが、今回の『砂の栄冠』は高校野球全体の「文化論」になっていると感じました。このコンセプトはどういう経緯で生まれたんでしょうか?
三田 『甲子園へ行こう!』の後も、「ヤングマガジン」が取材のパスを毎年用意してくれていたので、高校野球のマンガを描いてなくてもちょこちょこ甲子園を見に行ったりはしてたんです。で、『砂の栄冠』でも描いたことでもありますが、甲子園のバックネットって開場時間に来て毎日観戦しているようなおじさんたちがたくさんいるんですね。
たとえばバックネット裏で試合前のシートノックを見ながらカウンターをカチャカチャやっている人がいて、プロ野球のスカウトが近くにいたんで「あの人って何やってるんですか?」って聞いたら、「ああ、あれは制限時間内に監督が何本ノックを打ったかを数えているんですよ」と言っていて。
――「制限時間内にどれだけノックを数多く打てるか」という指標で、そのノッカーの技術を測っているわけですよね。
三田 そうなんです。そういったことをたくさん目の当たりにして、自分がそれまで思っていた「高校野球」とちょっと違う一面を感じたんですね。「こういう人たちがいてこそ甲子園なんだな」と。だから高校球児そのものと、プラスそれを取り巻いてる人間模様を描いたら面白いんじゃないかと思っていました。
▲『砂の栄冠(20)』より。濃い高校野球ファンたちは、それぞれ独自の視点から試合を観戦している。
――言ってしまえば「高校野球オタク」の人たちですよね。雑誌でいうと『野球太郎』(廣済堂出版)――昔だったら『野球小僧』(白夜書房)ですが――というものがありますが、プロ野球選手ではなくまだ高校生〜中学生の注目選手の情報を集めて、他県での練習試合まで遠征して追いかけるような人たちが実はたくさんいるんですよね。あの文化って、野球をやっている人間としては存在は知ってはいたものの、身近にそういう人が全然いないので「なんだろう?」と思っていたんです。でも『砂の栄冠』を読んで「ああ、こういう人たちなんだ!」と具体的なイメージが湧きました。
三田 高校野球って、たとえば伝統校だと毎日バックネット裏とかに練習を見に来るおじいさんっているじゃないですか。「練習を見に来る」というのは、ひとつの高校野球の特徴だと思いますね。
たとえば静岡高校なんて、毎日20〜30人ぐらい、90歳近いおじいさんたちが来ていたりするんですよ。これは他の競技にはない特徴なんじゃないかと思います。他にも高校野球部ってOB会だったり、父母会だったりといろんなものがくっついている。そういう外側のことも描いたら面白いんじゃないか、と思っていました。
▲『砂の栄冠(18)』より。高校野球ファンのなかには、お気に入りの選手を追いかけるため遠方まで観戦に出向く人も。上のシーンの人物は、静岡からわざわざ埼玉まで地方予選を観戦しに来ている。
■ 無能な監督、眉毛戦争、父母会の権力争い……高校野球を取り巻くディープな人間模様
――『砂の栄冠』では父母会で(なぜか)起こる主導権争いも描かれていましたが、元高校球児からすると「あるある」とすごく共感してしまいました。選手と関係ないところで無駄にドロドロしていたりしていて……子どもの側からするとたまったもんじゃないんですけど(笑)。
三田 高校野球は父母のみなさんもすごく熱心ですから。やっぱり地域や父母と一体となって取り組むというのがひとつのポピュラーなかたちですね。
――他にも主人公の高校の監督(作中では「ガーソ」というあだ名で呼ばれている)が典型的な無能上司だったり、「眉毛戦争」と言われるチーム内での太眉派VS細眉派の対立があったり、強豪校野球エリートの嫌な感じだったりとか、ああいった綺麗事ではないリアルな側面も描かれていましたよね。
三田 高校野球漫画って「みんなで頑張ろう」という話は書き尽くされている部分があるので、なにかしら作品の特徴というか、今までにないもの描きたいとは思っていました。あと、話を聞いていると意外とガーソみたいな監督って多いんですよね。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は今月も厳選された記事を多数配信します! すでに公開済みの記事一覧は下記リンクから。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201509
-
学校から解き放たれたスポーツ教育――古田敦也が語る未来の野球文化(無料公開) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 号外 ☆
2015-09-23 17:00
学校から解き放たれたスポーツ教育――古田敦也が語る未来の野球文化(無料公開)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.9.23 号外
http://wakusei2nd.com
2020年の東京五輪計画と近未来の日本像について4つの視点から徹底的に考えた一大提言特集『PLANETS vol.9 東京2020 オルタナティブ・オリンピック・プロジェクト』(以下、『P9』)。その『P9』の中から、特に多くの人に読んでほしい記事をチョイスし、10日連続で無料公開していきます。
最終回となる今回は元プロ野球ヤクルトスワローズ選手・監督の古田敦也さんへのインタビューです。
『PLANETS vol.9』連続無料公開記事の一覧はこちらのリンクから。
※無料公開は2015年9月24日 20:00 で終了しました。
2020年のオリンピックが、一過性の熱狂で終わる大会になってはつまらない。五輪とい -
「高校野球カルチャー」の本当の問題点とは?――高野連、坊主頭、夏の大会「一票の格差」を考える(「文化系のための野球入門――ギークカルチャーとしての平成野球史」vol.2) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.387 ☆
2015-08-13 07:00【チャンネル会員の皆様へお知らせ】
PLANETSチャンネルを快適にお使いいただくための情報を、下記ページにて公開しています。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/ar848098
(1)メルマガを写真付きのレイアウトで読む方法について
(2)Gmail使用者の方へ、メルマガが届かない場合の対処法
(3)ニコ生放送のメール通知を停止する方法について
を解説していますので、新たに入会された方はぜひご覧ください。
「高校野球カルチャー」の本当の問題点とは?――高野連、坊主頭、夏の大会「一票の格差」を考える(「文化系のための野球入門――ギークカルチャーとしての平成野球史」vol.2)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.8.13 vol.387
http://wakusei2nd.com
今日は好評の野球シリーズ第2弾をお届けします。今回のテーマは、現在も甲子園で熱戦が繰り広げられている「高校野球」。ここ数年、毎年夏になると高校野球にまつわるネット炎上騒動が繰り返されていますが、そもそも高校野球カルチャーの何が本当に問題なのか? 元高校球児でもある3人が自らの経験を踏まえつつ、「既存の高校野球論に足りないもの」について語りました。
▼この座談会の参加者
かしゅ〜む:92年生まれ。PLANETSチャンネル「朝までオタ討論!」でおなじみ。アイドルだけでなく野球にも一家言持つ生まれながらの論客。高校まで軟式野球をやっていた。巨人ファンだが、最近は推し(PIPの空井美友さん)の影響でロッテにも心が動いている。
石丸:84年生まれ。『弱くても勝てます』で有名な某日本一の進学校・K高校の元4番・主将。現在は東京で会社員。横浜ファン。
中野:86年生まれ。PLANETS編集部。野球歴は10年ぐらい。連勝→連敗のジェットコースターロマンスを展開するDeNAベイスターズを生暖かく見守っている。
◎構成協力:かしゅ〜む
前回記事:野球にとっての〈1995年〉とは? 野茂、イチローと阪神淡路大震災
■「埼玉のヌンチャク君」は制限速度をオーバーしただけだった
中野 この連載はせっかく月刊化されたので、時事ネタについても扱ってみたいと思います。7月〜8月は高校野球の季節ということで、ここ数年「カット打法」「おにぎりマネージャー」「超スローボール」等、高校野球関連の炎上ネタが投下されるのが恒例行事になってますけど、今年話題になったのは「埼玉のヌンチャク君」でした。
今夏の埼玉大会で、代打で登場した選手がバットをヌンチャクのように振り回すキレ味のあるパフォーマンスを披露したこと、そして埼玉県高野連(高等学校野球連盟)が注意をしたことで話題になり、その後ダルビッシュがツイッターで言及したことで海の向こうMLBのサイトでも紹介されました。
▲ダルビッシュがツイッターで言及し、その後MLBのサイトでも紹介された。
https://twitter.com/faridyu/status/624223502988480512
石丸 2人はあれについてどう思いました?
かしゅ〜む 僕は別に彼のことを注意したり、批判する必要はないんじゃないかと思いますけどね。彼に対する批判を見てると「実力が伴ってないからだめだ」的なものも見受けられましたが、そもそも論点としてずれているなという感じです。去年のスローボール騒動の時もそうでしたけど、こういった選手に対しては「実力が」的な論調が常につきまといますよね。実力云々の話ではなく、彼らなりに工夫をした結果のプレイスタイルですから、尊重すべきなのかなと。僕は単純な話、明らかに試合の進行に影響が出るほどパフォーマンスの動きが長いとかでなければ問題ないと思いますよ。
中野 まったく同意なんですけど、僕はちょっと別の角度で今回の件って面白いなと思って。というのも甲子園ではあんまり目にしないですけど、地方予選レベルだとああいうパフォーマンスする選手ってけっこういるじゃないですか。僕が高校生のとき、東東京地区で最近甲子園に初出場したある高校と練習試合をしたんですけど、そこの3番打者がヌンチャクパフォーマンスをやっていて、あまりのキレ味だったのでうちのベンチも「おお〜っ!」ってなぜか盛り上がった(笑)。
かしゅ〜む たしかに、ヌンチャクパフォーマンスに近いことをやってる選手はいますね。なんならチーム全体でヌンチャクをやっているところもありましたよ。
中野 アマチュア野球全体では、ヌンチャクパフォーマンスってそんなに突飛なものではなくて、謎にずっと受け継がれているんですよね。何でやねんって感じだと思うんですけど。埼玉のヌンチャク君も他校のいろんな先達を見て進化させていったんじゃないかなぁ。だいたい、他の人があんなカッコイイ中二病的なパフォーマンスやってるのを見たら、試合で実際にやるかどうかは別として、真似したくはなるでしょ。なんなら僕もちょっと練習したことがありますよ。みんな忘れているけど、高校球児は基本的に全員中二病ですからね。
かしゅ〜む 投球テンポの早いピッチャーに対しては、そのテンポを崩すために打席に入るときに余計なパフォーマンスをするときがありますけど、これもその類のものだったりするんじゃないですかね。
石丸 試合の流れが悪いと、それを止めるために、ほどけていないのにタイムをかけて靴紐を結び直したりとかね。
中野 あとパフォーマンスということでいうと、僕の先輩で、打席に立つと毎回ピッチャーにバットを向けて「ターッ!!!!!!」って奇声を発する人がいたんですよ。こっちのベンチからは毎回失笑が漏れつつも「(恥ずかしすぎて)俺たちにできない事を平然とやってのけるッ!そこにシビれる!あこがれるゥ!」となってちょっと盛り上がるし、相手チームをドン引きさせる効果もあった。味方ベンチが勢いづくきっかけになって、相手は「え……なにこれは……」となってペースを乱されるわけですよね。あ、別に推奨はしてないですよ。
石丸 野球は「流れ」とか「ムード」みたいなものが本当に大事なスポーツなので、戦略的にそういうことをやる場合もあるよね。
中野 このヌンチャク君もそうだと思うけど、学生野球においてこういうパフォーマンスは、ガッツポーズも含めある程度は黙認されているわけですよ。現に今やっている甲子園を見ればわかると思いますけど、選手たちはがんがんガッツポーズしていますよね。あれ、高野連は一応、公式見解としては「慎むように」って言ってますから(笑)。
ただ、今回のヌンチャク君のパフォーマンスに関しては、ちょっと「長かった」かもしれない。あれは審判から遅延行為と言われても不思議ではない。その分、ヌンチャクパフォーマンスとしては今までに見たことがないぐらいに高いレベルに到達しているんですけど。
かしゅ〜む たしかにそうですね(笑)。
中野 ネット上では、高野連というと「はい個性入ったー!今個性入りましたー!」みたいに、地獄のミサワのキャラ(参考:惚れさせ871 「はい主観ー!」 : 地獄のミサワの「女に惚れさす名言集」 )のごとく「個性は厳しく取り締まっていく」というイメージがありますけど、現実にはそんな戦前の特高警察みたいな組織というわけではない。
そりゃあ体罰やいじめ、飲酒・喫煙・窃盗などの不祥事が起こったら出場停止処分を下したりしますけど、試合中のパフォーマンスや髪型・眉毛などはほとんど大目に見ているわけですよ。今回に関しては、制限速度100kmの高速道路で120kmぐらいなら黙認されるところを、140km出してしまって警察(高野連)に捕まったっていうぐらいじゃないですかね。
かしゅ〜む こういう、ちょっと尖ったプレースタイルの高校球児が批判される時って、叩いている人は、野球経験者と言うより、あんまりプレイ経験のない野球大好きおじさん・高校野球ファン、意識高い系の教育関係者が多い気がするんですけど、僕だけでしょうか?
プレイヤーの側から見たら、「チームのために一芸(ヌンチャク、カット打法、超スローボール等)を磨く姿勢がかっこいい」くらいに感じると思うんですけどね。
石丸 この件や「カット打法」「超スローボール」事件にも言えることだけど、「高校野球はこうあるべき」という時代遅れの意見がまず投げられ、それに対して「こんなに時代遅れなことを言っている奴はけしからん→したがって高校野球もけしからん」と批判する人たちがネット上にたくさん出てくるという構図だよね。どちらにしても高校野球の現場からの視点がなく、単なるネット炎上の燃料にされているだけで、生産性のある議論はほとんどないよね。
中野 僕はそれに加えて、既存の高校野球論って、強豪校や野球エリートしか見ていないのがダメだと思いますね。はっきりいってあれは超特殊な世界ですよ。99%の高校球児は野球留学とかしないし、普通に高校受験して入ってきて野球をやっているだけ。
かしゅ〜む 全くその通りだと思います。人数が足りなくてそもそも試合が出来ない高校だって普通にあるわけですしね。
(参考リンク)「最強の帰宅部が現る」野球部員1人の文理開成、助っ人が連続ホームラン
中野 一方で野球エリート校にしても、野球部員が授業中に寝ていても例外的に許されるという話はありふれていますし、基本的に彼らはほとんど勉強していない。今「モーニング」で連載中の、PL学園野球部の内幕を描いていると言われる漫画『バトルスタディーズ』では、現代国語の授業でテレビのニュース番組(関口宏の「サンデーモーニング」がモデルと思われる)を見るという描写があったりしましたね……。いや、基本的には笑い話として描かれているんですけど、人権派の人たちが目にしたら激怒しかねないですよ。
▲なきぼくろ『バトル・スタディーズ(1)』モーニング KC
そもそも、普通科ではなく体育科にいて、将来的には体育の先生や指導者になるとしても、本当はスポーツ科学や身体学、栄養学、もしくは教育学やその他の一般常識もしっかり勉強しないといけないはずです。
いや、僕が何でこんな説教臭いことを思うようになったかというと、桑田真澄さんが早稲田の大学院で「野球界の発展」についての修士論文を書いたときに、プロ野球選手270人にアンケートを取っていて、これが本当に衝撃的な内容だった。体罰を「必要である」「時には必要である」と答えた選手が、なんと83%にも及んでいたんです。この数字は発表当時ちょっと話題になりましたけど、いやいや、市民社会の感覚からしたらとてつもなく常識はずれの数字じゃないですか。当然、プロ野球選手のほとんどが野球強豪校の出身ですけど、やはり強豪校→プロ野球という野球エリートの世界は、市民社会からかなり遊離した、閉鎖的で独自のルールで動いている場所だと言われても仕方がない。
多くの野球エリートたちが競技としての野球しか知らないし、大人も外側の世界を教えないようにしている。よく高校野球を正当化する論理として「人間形成になる」って言われますけど、これって特に学術的な根拠もないわけですよ。そして「高校野球は教育の一貫」などと言われるにもかかわらず、野球エリートは事実上、多くの高校生が受けているような「教育」を受けさせてもらえず、「お前らは野球だけやってればいいんだ」という状態に置かれている。こういう状態を世論がどうみるのか、これだけの国民的興行になっている以上は、今からでもちゃんと議論しないといけないと思います。
■ そもそも「高校野球=坊主」は個性の抑圧ではないのか?
中野 「高校野球はこうあるべき」という点では、「高校球児はなぜか坊主にする」という風習がありますよね。世間の人が、これについてあまり何も言わないのが不思議なんです。「個性を抑圧するな!」というなら、坊主が最大の問題じゃないですか。ここにいる三人は野球部に所属してたわけですが、高校のとき坊主にしてました?
石丸 僕の母校は、知る人ぞ知る話なんだけど、学校全体が5月の運動会に命をかけていて、そこで負けると坊主になる。なので別の理由で夏は坊主になっていた(笑)。
それはさておき、世間では勘違いされていることが多いみたいだけど、そもそも坊主って、別に高野連が強制しているわけじゃないし、今どき部則で強制されているところも少ない。甲子園に出るような強豪校でないかぎりは、大半の高校では髪型はルール上自由でしょう。それでも自主的に坊主にするということがあるけれど。
かしゅ〜む 僕は中学では坊主にしてましたけど、高校では軟式野球部に入っていて、軟式野球界は坊主にする風習はほぼなかったですね。むしろ坊主にすると、「お前なんで硬式の真似してるんだよ、調子乗ってんのか?」と怒られる(笑)。
中野 なるほど。坊主にする理由は様々だし、高野連の登録生徒数18万人のうち約1万人を占める軟式野球界では同じ高校野球でも坊主カルチャーがないわけですね。
僕は強豪校とかではなく普通の高校で、野球部でも髪型に関する決まりはなかったので高1ぐらいまでは普通の短髪でしたけど、高2ぐらいから坊主にしていました。でもよく考えると不思議なのが「なんで誰からも強制されていないのに坊主にしてたんだろう?」ということで。
かしゅ〜む まあ、やってる側からすると気合入れようと思って坊主にするというよりも、帽子をかぶってもムレなくて涼しいし、暑い日に水を頭からかぶれるという機能的なメリットがあるだけですよね。そもそも熱中症になりそうなぐらい暑い夏の昼間に練習や試合を積極的にやるという高校野球のカルチャーが異常とも言えますけど。プロ野球選手は髪型は自由ですし、ナイターやドーム球場で試合することも多いですからね。
石丸 大学野球だと公式戦は夏を避けて、秋と春にやるしね。そもそも高校野球だって秋・春・夏と3つの大会があるけど、逆にいうと夏以外は秋と春にやってるわけだ。
中野 夏真っ盛りかつ日中の最高気温になるような時間帯に試合をやるのは、それこそ夏の甲子園ぐらいですよね。まあ、現実的に大規模な全国大会をやるとなると、学校も夏休みにあたる8月くらいしか開催できないので仕方ない部分もありますけど、それだって学制が改革されて二期制とかになったら変わるかもしれない。
■ 高校球児のコスプレを〈自発的〉に強要される球児たち
中野 たとえば甲子園に出るような強豪校で坊主でなくてもOKな高校だと、仙台育英と慶應があります。仙台育英はいまちょうど甲子園にも出ているけれど、ある時期から坊主に戻ったみたいです。監督は何も強制していないけど、選手たちが自主的に坊主にし始めたらしい。やっぱり高校野球って、「坊主にしないと相手チームにナメられる」というのがあると思うんですよ。ほとんどの強豪校が坊主にしているから、普通の髪型をしていると悪目立ちして敵意を集めやすい。「あいつら坊主にもせずチャラチャラしやがって、俺達のほうが野球に本気だから負けるわけがない」という心理的なアドバンテージを相手に与えてしまう。あとはオールドな高校野球ファン――たとえば甲子園のバックネット裏に陣取って朝から夕方まで試合を見るような――にも評判が悪いわけですよ。
僕自身は高校時代は坊主にしてましたけど、普通の高校なので、頑なに坊主にしない選手も何人かいた。で、彼らは野球部内ではなく周囲から「高校球児なのになんで坊主にしないの?」って言われるんですよ。
かしゅ〜む 野球部内の規律ではなく、外からの目線が大きいわけですね。さっき石丸さんが言っていた「高校野球こうあるべき」というものに外部の人たちが洗脳されてしまっていて、その視線に耐え切れずに高校球児が坊主になっていく――誰も強制していないにもかかわらず。
中野 僕は心が弱いのでその外部の目線に負けて坊主にしてしまった。要は、高校で硬式野球をやるには「高校球児のコスプレ」を〈自発的〉にしないといけないという謎の不文律が出来上がってしまっているんですよね。
一時期、高校球児の眉毛の細さが話題になって、高野連が「校則違反の指導を徹底するように」と各校に通達を出したりしていましたけど、そもそも坊主という「高校球児コスプレ」を社会的に事実上強制されているせいで、眉毛ぐらいしかファッションにこだわれるところがないからああなるわけじゃないですか。
かしゅ〜む 甲子園の中継で、眉毛をバッチリ整えてるエースとか見ると「ああ、こいつは確実にスクールカーストの頂点にいるな」とか思っちゃいますけどね(笑)。
中野 まあ、強豪校の球児のやたら細い眉毛は、実はDQN性を高める――つまり「俺は不良である、したがって学校内でも地位が高い」というアピールとして機能している部分はあるんでしょうね。こう言葉にしてみると、すごくしょうもないことですけど。
僕が思うのは、高野連は坊主を禁止にすべきではないか、ということです。眉毛をヤンキーみたいに細くするのが「高校生らしくない」という理由で良くないのであれば、そもそも五厘刈りとかスキンヘッドみたいな頭が若者らしい爽やかな髪型だと思う人は別にいないでしょう。高校野球と同じく「若者らしさ」が求められる就職活動に、スキンヘッドで臨む人ってほとんどいないじゃないですか。むしろ「高校球児の坊主は軍隊的で野蛮なんじゃないか」という感覚のほうが一般的なはず。
かしゅ〜む たしかに、坊主って一般的にはガラ悪いイメージを受けますよね。
中野 もちろんオシャレとか色んな理由で坊主にする人はいますし、価値観は人それぞれでいいと思うんですけど、五厘刈りとかスキンヘッドのような坊主ってどちからというとタトゥーみたいなもので、高校野球以外の一般社会ではあまり積極的にはできない髪型ですよね。
今のように「高校球児は全員坊主」という一般社会からかけ離れた状況を高野連が放置しているから、よく知らない人から「高校野球は野蛮」というレッテル貼りが行われてしまう。「高校野球は教育の一貫」というのであれば、高野連はああいった「一般社会から遊離した独自の論理」で動く前時代的な風習を放置せず、髪型の指導をしっかりやるべきだと思います。
石丸 でも、さっきかしゅ〜む君も言っていたけど、坊主ってやっぱり機能的じゃない。汗かいてもサッとひと拭きできれいになるし、シャンプーもリンスも不要で、石鹸でそのまま洗えるというメリットがある。
中野 いや、それは僕も坊主になってたのでわかりますよ。何なら家にバリカンがあったのでそれを学校に持って行き、率先して坊主希望者の髪を刈っていたりした。
僕が高校生だった2000年代前半ってサッカー日本代表の小野伸二も坊主にしていたりと謎のオシャレボウズブームが起きていて、サッカー部やバレー部にもそれが波及しており、これって文化的にも象徴的なムーブメントだったと思います。学校に一個のバリカンが持ち込まれ、かつ男子校だったので「ウェーイ」みたいな集団心理も合わさって、ねずみ算式に坊主が増えていった。
石丸 アウトブレイクみたいだな(笑)。
▲『アウトブレイク』:一匹のサルが持ち込んだウィルスにより全米が滅亡の危機にさらされていく恐怖を描いた、ダスティン・ホフマン主演のパニック・アクション。1995年作品。公開当時はとても話題になった。
中野 これはあくまでも一例ですけど、要はこの頃から「坊主は逆にカッコイイ」という意識が生まれ始めていた。だから今の高校球児が坊主にしている背景には昔の「強制だから」というのと違って、「高校球児を演じるコスプレ」と「坊主が逆にカッコイイ」という2つの転倒した論理があると思うんですよ。
【ここから先はチャンネル会員限定!】PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は今月も厳選された記事を多数配信します!
-
野球にとっての〈1995年〉とは? 野茂、イチローと阪神淡路大震災(「文化系のための野球入門――ギークカルチャーとしての平成野球史」vol.1) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.368 ☆
2015-07-17 07:00【チャンネル会員の皆様へご案内】
PLANETSチャンネルのニコ生放送をあまりご覧にならない場合は、放送開始時のお知らせメールの配信を停止することができます。
(設定方法)
・ニコニコトップ(http://www.nicovideo.jp/)を開く
・画面右上の「メニュー」から「アカウント設定」を開く
・ぺージの左下にある「メール配信サービス」の「変更」をクリック
・「ニコニコ生放送」をクリック
・「【ニコニコ生放送】ニコ生アラート(メール)チャンネル版」の「変更する」クリック
・PLANETSチャンネルの「変更する」をクリック
・「停止」が表示されていることを確認
野球にとっての〈1995年〉とは?野茂、イチローと阪神淡路大震災(「文化系のための野球入門――ギークカルチャーとしての平成野球史」vol.1)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.7.17 vol.368
http://wakusei2nd.com
本日のメルマガでは、今年の春に公開され好評だった野球企画の続編が登場します!
マスメディアと巨人戦を中心に盛り上がってきた戦後日本の「野球」。それが2000年前後を境に大きく変貌を遂げ、メインカルチャーからサブカルチャーへ、巨人一極集中から多極型の地域コンテンツへ、マスメディアからネットへとその重心を移してきました。
この連載では、その変化が始まった90年代半ばを起点に、現代までに至る「文化史としての野球」を考えていきます。
▼この座談会の参加者
かしゅ〜む:92年生まれ。PLANETSチャンネル「朝までオタ討論!」でおなじみ。アイドルだけでなく野球にも一家言持つ生まれながらの論客。高校まで軟式野球をやっていた。巨人ファンだが、最近は推し(PIPの空井美友さん)の影響でロッテにも心が動いている。
石丸:84年生まれ。『弱くても勝てます』で有名な某日本一の進学校・K高校の元4番・主将。現在は東京で会社員。横浜ファン。
中野:86年生まれ。PLANETS編集部。野球歴は10年ぐらい。最近好きな選手は小林誠司(巨人)、西川遥輝(日本ハム)、森友哉(西武)、関根大気(横浜DeNA)。
◎構成協力:かしゅ〜む
■ 今こそ物語としての「野球の歴史」を語るべき!
中野 前回記事(いま文化系にとって野球の楽しみ方とは?――「プロ野球ai」からなんJ、『ダイヤのA』、スタジアムでの野球観戦、そしてビヨンドマックスまで)が好評だったため続編をやることになったのですが、まず、そもそもなぜPLANETSが野球に関する記事を始めたのかという説明が何もなかったので、改めて説明したいと思います。
最初は宇野編集長から編集部スタッフである僕(中野)に「その無駄な野球知識を活用して記事をつくれ!」という指令が下ったのがきっかけでした。
なのですが、文化史的な意義を踏まえてやっている部分もあります。たとえば現在、ネット上で「ンゴwww」「ぐう◯◯」「(震え声)」「あっ…(察し)」「ファッ!?」などの「なんJ語」がネットスラングの代表格になっていますよね。
なんJとは言うまでもなく、ニュー速VIPなどに並ぶ2ちゃんねるの人気板(なんでも実況ジュピター)のことで、野球を中心とした雑談が日夜行われています。その雑談の内容がたくさんのまとめブログによってネット上に拡散されたことで、なんJ語がすっかりネットスラングの主流の地位を占めるまでになってしまいました。
かしゅ〜む 確かにこの辺りはネタが先行して,元ネタを知らない人が多かったりしますよね。「え?その用語って野球関係だったの?」みたいな。まあ「ンゴ」がまさか外国人投手が元ネタだとは思わないですよね。
中野 ネットカルチャーの歴史を紐解くと、初期2ちゃんねらーやその後のVIPPER、そして2000年代後半以降のニコ厨など様々なトライブが生まれてきましたが、「なんJ民」は2010年代に表舞台に登場した種族ではないかなと思います。そしてそのネタとして、古くて新しい文化である「野球」があった。こうした2010年代特有の文化状況がなぜ生まれたのかを色々な角度から考えてみようというのが前回の趣旨でした。
今回は、90年代以降の野球の「歴史」をテーマに話していきたいと思います。なぜ90年代以降かというと、それ以前だと我々(座談会出席者)がリアルタイムで経験していないということもあるんですが、やはりこの時期、90年代から2000年代にかけて、巨人戦中継を中心とする「マスメディア型興行」としての野球の時代が終わったと言えるからです。この時代的なインパクトを中心に据えて、野球の歴史というのを語ってみたいと思います。
もう一点、なぜ歴史を振り返ってみるのかというと、最近ネット上での様々な野球談義を見ていると、「そんなことも知らないのか」「にわか乙」というような、2000年代にネット上の様々な趣味の場でよく見た風景が繰り返されていると感じたからです。ちなみに2000年代初頭の初期2ちゃんねるで僕が最初に覚えた言葉は「はい論破」でした。
かしゅ〜む 僕は92年生まれなので初期2ちゃんねるの雰囲気はよくわからないですが、たしかに「はい論破」をやっていると、あんまり生産的な議論はできなさそうですね。ネタでやってるならいいんでしょうけど(笑)。
野球の歴史ってYouTubeやWikipediaなども充実しているし、NPB(日本野球機構)のサイトやスタメンデータベースなどもあるので、後からいくらでも振り返ることができそうですけど、でもそれぞれの出来事の重み付けはわからないですよね。
中野 はい。というわけで、プロ野球だけでなく、メジャーリーグやアマチュア野球、その周辺文化も含めて、我々なりの「歴史観」そして「物語」を作ってみようと思います。ではさっそく、すべての変化の起点となる90年代半ばから行ってみましょう。
■ 「昭和最後の日」は、1994年の「10・8決戦」!?
石丸 90年代のどこから話を始めるかだけど、僕は1994年の「10.8決戦」がいいんじゃないかと思う。これは前回話した「巨人戦、セ・リーグを中心にしたマスメディア的興行」としてのプロ野球がピークを迎えた時期だと言える。日本プロ野球史上初めて、リーグ戦の勝率が同率首位で並んだ巨人と中日が、最終戦で直接対戦する優勝決定戦だった。社会的にも大変な注目を集めた「伝説の試合」だよね。
桑田真澄・槙原寛己・斎藤雅樹という巨人史上でも屈指の先発三本柱がいて、特にこの日は松井秀喜・落合博満・原辰徳という(名前だけ見ると)超強力なクリーンナップだった。ちなみに甲子園での松井の5打席連続敬遠事件が92年で、この94年頃に彼は巨人で不動のレギュラーになっていた。
中野 その10.8決戦が注目された1994年ですが、もうひとつ社会的な事件としてイチローの登場とブレイクも大きいですよね。打率.385で210安打(当時史上最多)を放つというとんでもない記録を、弱冠20歳にしていきなり打ち立てたわけです。
イチローは当時、注目の少ないパ・リーグの弱小球団であったオリックスから出てきたスーパースターだったわけですが、20世紀的な野球と21世紀的な野球を分かつものがあるとすると、松井はちょうどその端境にいる存在で、イチローは「アフター」というか、新時代の野球を象徴する存在ではないかなと思います。
石丸 年齢的にはイチローの方が1個上ではあるんだけど、松井はイチローよりも早い段階で話題になっていたから、松井が中間でイチローが「アフター」というのはたしかにそのとおりだろうね。
中野 前回も話しましたが、僕は90年代半ば当時は小学生で、日テレ土曜9時のドラマ『家なき子』『金田一少年の事件簿』『銀狼怪奇ファイル』『透明人間』『サイコメトラーEIJI』『プライベート・アクトレス』などを楽しみにしていたので、巨人戦が延長して食い込んでくるのがすごく嫌でした。「野球、早く終われ!」と思っていた。
原辰徳が引退したのが1995年で、当時の小学校の同級生たちはすごく話題にしていましたが、「ケッ」と思ってましたね。でも、そういう野球と〈マスコミ的なもの〉の結託に対しての反感抜きに、イチローはあっという間に好きになった。
石丸 そこで言うと、「巨人の4番としての原辰徳が昭和最後のスターだ」というのは歴史観としてありかもしれないね。原と同時期のスター選手としては落合博満が挙がると思うんだけど、落合はロッテ・中日の選手というイメージが強いし、巨人にいたのも一時期だけで、その後日本ハムに移籍もしている。
中野 落合は、位置づけの難しい人物だと思っています。そもそも高校・大学と体育会系的な上下関係が嫌で、一度完全に野球からドロップアウトし映画ばかり見ているような文化系の人だった。そこから社会人野球チームに入りなおしてプロ入りしたという異色の経歴で知られている。
2000本安打を達成した打者、200勝or250セーブ以上を達成した投手だけで構成される名選手のサロン「日本プロ野球名球会」への入会も拒否しているんですよね。つまり、戦後日本的な「世間」とは距離を置いて個人主義を貫いているわけです。だから彼を「昭和」的な人物と位置づけるのは難しいし、むしろ「プレ・平成」型の人物だと思います。これは後で述べる権藤博にも共通して言えることです。
ちなみに落合はガンダムオタクとしても知られており、好きなガンダムは『ガンダムW』に登場するウイングガンダムゼロカスタムだそうです。ご子息で最近声優デビューした福嗣さんの影響もあると思いますが、近年では『ガンダム00』を高く評価しているらしいですね。
▲MG 1/100 XXXG-00W0 ウィングガンダムゼロ (エンドレスワルツ版) (新機動戦記ガンダムW Endless Waltz)
かしゅ~む だいぶ話がそれてますけど(笑)、落合さんは、「長嶋茂雄はひまわりの花、私は月夜にひっそりと咲く月見草ですよ」と言ったノムさん(野村克也)に近いものがありますよね。人気よりも実力に誇りを持っているというか。
中野 “スター性"って明確な基準はないんだけど、原辰徳よりも落合博満はやや地味な印象があるかもしれない。原さんは巨人軍の4番で、その後巨人の監督やWBC日本代表の監督も務めて大変な好成績を残している。落合もそれに負けず劣らずというか、選手としての成績は圧倒的に落合の方が上なはずなんですけど、なんとなく原さんのほうが「スター」として扱われるというのはありますね。
石丸 「人気のセ、実力のパ」と言われていたパ・リーグで三冠王を獲得してセ・リーグに移籍していった落合と、アマチュア時代から超エリートコースを歩み巨人軍一筋で常にスポットライトを浴びてきた原さんとはここが大きく違うとこだろうね。
■ 野茂のメジャー挑戦と「VS日本的世間」
石丸 1994年ってなかなか面白くて、イチローと10.8決戦があった一方で、メジャーリーグでプロスポーツ史上最長のストライキが起こり、アメリカ国内でのメジャー人気の低迷が誰の目にも明らかになったんだよね。
中野 今はメジャーって日本のプロ野球よりも国内的な人気も高いし年俸もバカ高いしで、「成功しているリーグ」という印象だけど、当時のメジャーリーグは「しょうもないことやってんな……」という感じだったんですよね。日本プロ野球が盛り上がっていたので余計にそうだった。この時期、巨人で活躍したシェーン・マックが代表的ですが現役バリバリのメジャーリーガーが日本プロ野球に活躍の場を求めるケースも多かった。
ちなみに1994年には映画『メジャーリーグ2』が公開されています。前作からの主人公チャーリー・シーンを中心としたインディアンスが低迷するなか、とんねるずの石橋貴明演じる日本からの助っ人選手「タカ・タナカ」らの活躍で復活していくという内容です。ちょうどこの年の後半から現実のメジャーでストライキが起こり、人気が低迷していったところを翌95年の野茂英雄の登場で持ち直したことを考えると、『メジャーリーグ2』ってなかなか予言的な映画なんですよね。
内容自体は、後年の『マネーボール』とは違って昔ながらの「人情が勝つ」というものなんですが、野球コメディ作品としてはなかなか痛快な作品だと思います。当時、貿易摩擦でアメリカ国内で反日感情が高まっていたにもかかわらず、タカ・タナカのキャラクター造形は(もちろん類型的な日本人キャラクターとしてギャグテイストで描かれているものの)なかなか繊細なコントロールが効いていて素晴らしかったですよね。
▲ホームランになりそうな当たりをフェンスによじ登ってキャッチし、大歓声を受けるタカ・タナカ役の石橋貴明(映画「メジャーリーグ2」 | 一番星みつけた(歯科学生の日常) より)
石丸 そして94年の冬から翌95年の初めにかけて野茂英雄のメジャーリーグ移籍騒動があり、野球の日米関係がより密接かつ複雑になっていったわけですね。
中野 そう、これもみんな忘れかけているし「そもそも知らない」という人も多いと思うんですが、野茂のメジャー移籍に対して当時のマスコミやプロ野球のOBたちはものすごいバッシングをしていて、それはもう「非国民」のような扱いでした。
野茂がメジャーに挑戦したのは、もちろんメジャーでやる夢を持っていたというのもあるんですが、当時所属していた近鉄の鈴木啓示監督の前時代的な方針(走りこみのような根性練を重視する、故障しても投げろと指令される等)に反発したからだと言われていますよね。
石丸 日本球界からメジャーに挑戦した選手だと、それ以前はサンフランシスコ・ジャイアンツの村上雅則がいるけど、彼もメジャーでプレーしたのはほんの偶然で、たまたまマイナーリーグに野球留学していたところを「メジャーで投げない?」と声がかかり昇格してしまって日米間で大問題になった。それ以来30年間、「日本人選手はメジャーでプレーしてはいけない」という不文律ができてしまった。
中野 そこを当時の日米間の協約の穴を突いて、半ば亡命するようにメジャーに移籍したのが野茂英雄だった。当時の野茂への風当たりの強さは、96年に野茂が日米野球で凱旋したときにスポンサーであるナイキがつくったポスターがよく表しているんじゃないかと思います。
▲1996年の野茂英雄 - agehaメモ より
これは野茂が出て行くときにメディア上で展開された大バッシングの文言をまとめたものだそうですが、要は野茂英雄という「自由」を重んじる個人主義者と、「不文律」や「空気」を重んじる「日本的世間」が鋭く対立していた。
かしゅ〜む これはすごいですね。「日本のプロ野球のしきたりをめちゃくちゃにした男がアメリカに行って成功できるか」というフレーズなんて、『八つ墓村』の「祟りじゃ〜!」と叫ぶ老婆を彷彿とさせる勢いがある。古き因習の残る山奥の、村落共同体の息苦しさそのものですね。字体もなんか市川崑っぽいし(笑)。
▲市川崑監督・豊川悦司主演による1996年版『八つ墓村』のひとコマ(2005年09月23日の記事: 『ブタネコのトラウマ』 Blog版 より)
石丸 で、実際に野茂がメジャーで投げたらバッタバッタ三振を取って、日米で「NOMOマニア」という言葉が生まれるほどの人気を得た。ほぼ同じぐらいの時期にFA制度やポスティング・システムなど、日本プロ野球からメジャー移籍するための制度が整い、日本人選手が続々とメジャーに移籍するようになる。この頃から野球ファンの興味がメジャーにも行くようになったんだよね。
【ここから先はチャンネル会員限定!】PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は今月も厳選された記事を多数配信します! 配信記事一覧はこちらから↓
-
いま文化系にとって野球の楽しみ方とは?――「プロ野球ai」からなんJ、『ダイヤのA』、スタジアムでの野球観戦、そしてビヨンドマックスまで ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.293 ☆
2015-03-31 07:00※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
いま文化系にとって野球の楽しみ方とは?――「プロ野球ai」からなんJ、『ダイヤのA』、スタジアムでの野球観戦、そしてビヨンドマックスまで
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.3.31 vol.293
http://wakusei2nd.com
本日のメルマガは、「いま文化系にとって野球の楽しみ方とは?」をめぐる座談会です。文化系の野球好きが集い、腐女子的な楽しみ方から「体育会系と文化系」の関係、野球人気低下の真相、マンガやネットカルチャーとの関連、そして参加型スポーツとしての野球の可能性やビジネス的視点まで、(なぜか)2万字の大ボリュームでお届けします!
※本記事は好評につき全文無料公開しています。
▼座談会出席者
野条:82年生まれ。世を忍ぶ仮の姿とし -
統計学者・鳥越規央インタビュー(後編)「ゲームデザインはポピュリズムとどう向き合うか――スポーツからAKBまで」 ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.263 ☆
2015-02-17 07:00※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
統計学者・鳥越規央インタビュー(後編)「ゲームデザインはポピュリズムとどう向き合うか――スポーツからAKBまで」
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.2.17 vol.263
http://wakusei2nd.com
本日は、日本における「セイバーメトリクス」の第一人者、統計学者・鳥越規央さんへのインタビュー後編をお届けします。前編ではセイバーメトリクスの日本ローカライズ事情について語ってもらいましたが、今回はセイバーメトリクス的な思想を応用した先にある、普遍的な「ゲームデザイン」とマスメディア的公共性の関係について聞きました。
前編はこちらのリンクから。
▼プロフィール
鳥越規央(とりごえ・のりお)
1969年生。現在の研究分野は数理統計学、セイバーメトリクス、スポーツ統計学。各メディアにて、確率や統計に関する監修を行う。著書に『勝てる野球の統計学――セイバーメトリクス』(岩波科学ライブラリー、2014年)、『本当は強い阪神タイガース: 戦力・戦略データ徹底分析』(ちくま新書、2013年)、『プロ野球のセオリー』(仁志敏久との共著、ベスト新書、2012年)などがある。
Facebookページ
https://www.facebook.com/torigoenorio
Twitter
http://twitter.com/NorioTorigoe
■ゲームデザインはポピュリズムとどう向き合うか
宇野 鳥越さんは48グループのペナントレースの設計にも関わられていますよね。セイバーメトリクスの歴史は、可視化できない、しにくいものをどんどん可視化、数値化していったことでその射程距離を伸ばして来た歴史だと思うのですが、ああいった主観的な評価がからむ演技や表現を評価するというのは、まだまだ難しいんでしょうか。
鳥越 誰もが納得できる採点基準を作れるかという意味で大変難しいと言わざるを得ない。いい例がフィギュアスケートでしょう。昨年のソチオリンピックのフリーで浅田真央は6種類8回の3回転ジャンプを飛び、ファンのみならず世界のフィギュア関係者からも絶賛を受けたのですが、そんな彼女でも技術点は全体の2位。そのからくりはGOE(Grade of Execution)という各演技要素に対して、その技がきれいに決まったかどうかを審査員がプラス3からマイナス3までの幅で加減点するポイントにあります。技術点は基礎点とGOEで構成されていまして、難しい技を組み込めば基礎点は上がります。浅田の基礎点は全選手の中で最も高く、次に高い選手よりも5点以上差がついていました。ご存知のとおり、浅田はフリーをノーミスで演技を終えました。しかし浅田の12個ある演技要素に対するGOEでプラス1を超える評価は2つしかありませんでした。それに対し技術点1位の選手のGOEは11個。過去5人しか成功させたことないトリプルアクセルに果敢にチャレンジし、結果成功させても「それきれいじゃない」と判断されたら高得点が期待できないシステムなんです。このGOEがプラスに評価される基準ですが、正直ガイドラインには抽象的な表現が多く客観性があるとは言いづらい。
さらに言えば、演技構成点(いわゆる芸術点)に関してはもう何が何やらです。だって選手ですらどうすれば高得点になるかわかってないようですし。
先程宇野さんもおっしゃったように、私はAKB48グループのペナントレースの設計に携わりまして、AKBに関してどんなものが数値化できるかということに関して運営のみなさんと議論を重ねてきました。残念ながら諸事情があってペナントは中止となってしまいましたが、私の中ではAKBに限らず、アイドルを評価するための基準を作るために必要なデータって何だろうってことを常々考えていました。そこで提案なのですが、『朝までオタ討論!』で論客の皆さんに自分の知っている色んなデータを挙げてもらい、それについて議論してみたいと思っていまして。
いま、『クイズいいセン行きまSHOW!』っていうボードゲームが巷で来ているらしいんですが、これはまず――例えば「48グループの卒業適正年齢は何歳?」っていうお題を出したとします。それに対して5人、もしくは7人の回答者に答えてもらい、その中央値をそのお題の適正とするという遊びです。
平均値だと、各人のポイントにものすごく格差がある場合、その極端な数値に引っ張られるという特性があるので、感覚的にどうかな?と思うものが出てしまう場合があります。でも中央値ってそういうことが起きにくいので、この方が「代表値」として我々にしっくりくる値になることがあるんです。で、ゲームとしては、その中央値を出した人に100ポイントを与え、最大値と最小値の人はマイナス50ポイント。これをいろんなお題で何回か繰り返していって、ポイントが最も多い方がAKBマイスターの称号を得られるというルールにしてみる。そんな感じで「AKB48グループに関する事象の数値化」というのを、ゲーム性を織り込んで議論してみると面白いんじゃないかと思っています。
宇野 情報技術の発展が生んだものの一つとして、コミュニケーションや「空気」といったこれまで数値化できなかったものの数値化が可能になったことが挙げられると思うんです。たとえばFacebookの「いいね!」数やTwitterのリツイート数だったり、トラフィック数だったりと色んなものが数値化されている。ああいった情報化以降に新しく生まれた数値を使うのも、セイバーメトリクス的な思想の延長線上の可能性としてあるんじゃないかと思うんです。
鳥越 いわゆる「テキストマイニング」というものですね。Twitterとかウェブ上に流布してる大量のテキストデータから、情報を取り出していくわけですよね。ただ問題は、取り出した情報が、人気や実力にどれだけ寄与するものかを判断する術をどうするかってことですよね。天気予報を例に挙げれば、昔は気圧や風の変化といった地上で取れるデータで行っていたものが、今は衛星からの画像だったり、上空の気温だったりとさまざまなデータから推測していくわけです。テクノロジーが増えるごとに見るべきデータも増えていって、より予測性能が上がっていく。だから、どういうテクノロジーを開発すればより精度が高くなるのかを考えていかないといけない。
宇野 この議論でいちばん出てきやすいのって、選挙制度だと思うんですよね。データをどう活用すれば、より民意に近いものを選挙結果に反映させることができるのか。でも、選挙制度を考えるときにこういったアプローチってあんまり聞かないですが、これはなぜなんでしょうか?
鳥越 だって民意を反映させることによって、政権与党が不利になるような制度にしないでしょう(笑)。ドント式(日本の比例代表選挙で用いられている議席配分の方式)ですら大政党に有利なゲームデザインですし。
宇野 つまり、民意を反映させようと思ったらもっと公平性のあるゲームデザインが可能なんだけど、それだと政権与党にとって不都合になりかねないという問題が大きいということですか。
鳥越 いちばん良いのは、比例代表で自民党が18%取ったら、100議席の18%だから18議席を配分する、とやれば簡単ですけど、おそらくそれでは最大政党に不利ですよね。少数政党でも議席が獲得しやすくなりますし、今のように選挙のタイミングでの趨勢で議席が大きく動くようなことにはなりにくいですから。
宇野 つまり今のやり方は、おそらくプレイヤーの側の充実感や納得感を優先して、現実的なフェアネスを犠牲にしているような仕組みになっている、と。
鳥越 あとゲームデザインを考える上で、テレビの存在は非常に大きい。たとえば今年度のJリーグがまた2ステージ制に変わることになって、ファンの多くは「それはゲームデザインとして悪すぎるんじゃないか」と大反対している。でもJリーグ側が2ステージ制にこだわったのは、結局プロ野球のクライマックスシリーズが興行的に大成功しているからですね。
――クライマックスシリーズは12球団のうち6チームが出場できて、リーグ戦の3位でも日本一になれるという明らかにダメなゲームデザインですけど、興行としては上手くいっていますよね。
鳥越 そう、Jリーグも2ステージ制にすれば、「チャンピオンシップ」でお客さんをたくさん集められるし、テレビの放映権料もしっかり入ってくる。リーグ戦だけだとどの試合で優勝が決まるかわからないけど、チャンピオンシップがあればそこで優勝が決まるので、テレビ的な注目を集めやすいわけです。
テレビを意識するという意味では野球やサッカーだけでなく他の競技も同じ問題に直面していて、たとえば今のバレーボールは実はあんまり良いデザインではないんです。バレーボールってサーブを受ける側のほうが点数を取りやすい。だから昔はサーブ権を持っているチームがラリーに勝ったら一点というルール(=サイドアウト制)だったんですが、そうなると試合時間が4時間とかかかってテレビサイズに合わなくなってしまう。だから今のようにラリーポイント制(サーブ権の有無に関わらず、ラリーに勝ったチームに点数が入る)になったんです。
でもそうなると、24対21ぐらいになった時に勝っているチームがサーブ権を持っていると、わざとサーブを外して24対22にしてからサーブを受けたほうが先に25点を取れる確率が高くなる。実際にラリーポイント制になった当初はそれをやっているチームが多かったですね。本当はサーブ側と受ける側で得点の重み付けを変えたりできたらいいんですが、そうなると別の問題も出てくるし、何よりわかりづらいルールになるでしょう。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は2月も厳選された記事を多数配信予定です!(配信記事一覧は下記リンクから順次更新)
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201502
-
統計学者・鳥越規央インタビュー(前編)「セイバーメトリクス以降の優雅?で感傷的?な日本野球」 ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.259 ☆
2015-02-10 07:00※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
統計学者・鳥越規央インタビュー(前編)「セイバーメトリクス以降の優雅?で感傷的?な日本野球」
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.2.10 vol.259
http://wakusei2nd.com
いよいよ発売となった『PLANETS vol.9 東京2020 オルタナティブ・オリンピック・プロジェクト』。スポーツを情報化やテクノロジー以降の視点から考えたこの『P9』をさらにフォローアップすべく、日刊メルマガでも新たな切り口でスポーツ文化を考える記事をお届けします。
今回は、映画『マネーボール』などでも脚光を浴びた「野球を統計で分析する」手法=「セイバーメトリクス」の歴史と現在について、日本における第一人者である統計学者・鳥越規央さんに聞きました。スポーツだけでなく、AKBのような文化興行や政治にまで射程を及ぼすセイバーメトリクス、その本当のポテンシャルとは――?
※後編はこちらのリンクから。
セイバーメトリクス――この聞き慣れない単語が徐々に広まり始めたきっかけは、やはりブラッド・ピット主演で映画化された『マネーボール』(2011年)だろう。米オークランド・アスレチックスの敏腕GM(ゼネラルマネージャー)として弱小球団を強豪に育て上げたビリー・ビーン。彼はそれまでのアナクロなスカウティングシステムを拒否し、徹底的なデータ活用(=セイバーメトリクス)によって、強豪球団から声のかかることのない一見実力のない選手たちを安価な給料で集め、アスレチックスを強いチームに育て上げていく。そのビリー・ビーンを描いたこの映画は、「弱者の一撃」という古典的なストーリーラインに加えて、脚本のアーロン・ソーキン(『ソーシャル・ネットワーク』他)らによる、人情話に重きを置きがちだったそれまでの野球映画と異なる冷徹な描き方が、野球好きのみならず映画ファンのあいだでも高く評価された。
▲『マネーボール』2011年/ブラッド・ピット(主演)ベネット・ミラー(監督)アーロン・ソーキン(脚本)他
しかしこの「セイバーメトリクスによる革命」はアメリカに限ったものではなく、まさに「耐用年数を過ぎた戦後文化の象徴」たる日本のプロ野球にも2000年代以降導入され、それによって球界の勢力図も急速に塗り変わりつつある。
今回は日本におけるセイバーメトリクスの第一人者で(実はAKBオタでもある)統計学者・鳥越規央先生をお招きし、セイバーメトリクスの歴史や日本におけるローカライズ、そして他分野への応用可能性についてお話を伺った。
▼プロフィール
鳥越規央(とりごえ・のりお)
1969年生。現在の研究分野は数理統計学、セイバーメトリクス、スポーツ統計学。各メディアにて、確率や統計に関する監修を行う。著書に『勝てる野球の統計学――セイバーメトリクス』(岩波科学ライブラリー、2014年)、『本当は強い阪神タイガース: 戦力・戦略データ徹底分析』(ちくま新書、2013年)、『プロ野球のセオリー』(仁志敏久との共著、ベスト新書、2012年)などがある。
Facebookページ
https://www.facebook.com/torigoenorio
Twitter
http://twitter.com/NorioTorigoe
▲鳥越規央,データスタジアム野球事業部『勝てる野球の統計学――セイバーメトリクス』 (岩波科学ライブラリー、2014年)
◎聞き手・構成:中野慧
■オタクとインターネットがセイバーメトリクスを作り上げた
――「セイバーメトリクス」というものはこれまでのような打率や打点、投手なら勝利数や防御率のようなわかりやすい指標ではなく、「もっと細かく色んな数字を組み合わせることで、選手の能力をより精緻に数値化することができる」ということを打ち出し、それらのデータをもとに選手を集めチームを強くしようという手法ですよね。このセイバーメトリクスは、そもそもどのようにして生まれてきたんでしょうか。
鳥越 もともと「データで野球を見る」という観戦文化はアメリカでも一部のマニアのあいだで昔からあったのですが、セイバーメトリクスそのものは、1970年代前半のビル・ジェームズという退役軍人が始祖であると言われています。彼は友達の靴屋でバイトをしながら野球を見ていて、もともと野球好きだからとデータを取っていった。そうしたら面白いことが分かってきて、それらをまとめて自費出版したんですね。
最初は全然売れず、一説には75人しか購入しなかったといわれてます。ですが、これまでの野球のセオリーに反するような分析結果もデータから証明できるという面白さが、だんだんマニアの口コミで広がっていったんですね。版を重ねるに連れ、購読者も増えその結果、スポーツ・イラストレイテッドのライターの目に留り、1982年に出版社から販売されるとたちまちベストセラーになったのです。ただやはりというか、日本と同じようにアメリカでも「野球の素人がこんなこと言っても俺たちは騙されないぞ!」みたいな感じで現場ではなかなか受け入れられなかったようです。
セイバーメトリクスが面白いのは、「思い込みを是正する」という部分です。たとえば、野球の世界だと「ノーアウト満塁は点数が入りにくい」というのがありまして。
――「大チャンスに見えるけど、実は得点するのが難しい」という野球界の定説ですよね。ノーアウト3塁やノーアウト2・3塁に比べると内野ゴロをホームでフォースアウト→一塁に転送でダブルプレーを取られやすいですとか、スクイズしても走者へのタッチでなくホームベースへの触塁だけでアウトにできるからとか、いろんな理由が言われていますよね。
鳥越 でも、ノーアウト1塁、ワンナウト1・3塁、2アウト2塁……等々、状況別に整理したデータを見ると、得点が入る期待値が一番高いのってノーアウト満塁なんです。
なぜ野球界で「ノーアウト満塁では点が入りにくい」という説が流布するかというと、一番点数が入りやすそうなチャンスであるにも関わらず、自分のひいきのチームがノーアウト満塁で無得点に終わったらそのショックが大きすぎて、実際は点が入ってる場面が多いにもかかわらず心の中で「ノーアウト満塁は点が入りにくい」という思い込みを形成してしまうからですね。
セイバーメトリクスって、そういう「人間の思い込みを是正する」というのがテーマなんです。「思い込み」はプレイヤーの方にもあるようで、これはロッテのコーチから実際に聴いた話なのですが、自分はコントロールが悪いと思い込んでいる投手がいて、「いや、君の三振率とフォアボール率の比率(K/BB という指標)を見ると平均よりも高いんだから、自分でノーコンと決めつけることないよ」と諭したりできる。余計な悩みだったことがわかれば、選手自身も自分が本当に改善すべきポイントが見えてきますよね。
――なるほど。ちなみに、セイバーメトリクスの始祖であるビル・ジェームズや、その後この手法を発展させていったのってどういう人たちだったんですか? 『マネーボール』でも描かれていましたが、必ずしも元プレイヤーだったりするわけではないわけですよね。
鳥越 それは「野球オタク」のみなさんですね。セイバーメトリクスの語源となったアメリカ野球学会(Society for American Baseball Researchのこと。頭文字を取った「SABR」をセイバーと発音する)というものがありまして、僕は2007年に参加したんですが、とにかく参加者すべて「オタク」臭を漂わせている人たちばかり。会場のロビーでは野球カードに興じる人達もいれば、オールドスタイルのユニフォームを身にまとう人もいたりで、まさに「野球版コミケ」ですよ。参加者の内訳ですが、いわゆるアナリストと言われる人は4割ぐらいで、あとは企業の社長だったりお医者さんだったり、作家さんだったり、本当に野球が大好きで趣味でデータ分析をしている人たちの集い、という感じでしたね。
コンピュータやネット環境が発達したことによって、そういう人たちが自分なりの分析を発表できる時代になった。その分析を見て、さらにいろんな人たちが考えて改良を重ねていくわけです。
――ソフトウェア開発でいうならオープンソースのように、ボトムアップで作られていったんですね。
鳥越 そういうことですね。例えばピッチャーの評価法に、DIPS(Defense Independent Pitching Statistics)という概念があります。これは「失点のピッチャーによる責任ってどこまでなんだろう?」ということを考えたときに、運とかチームの守備力といった「投手自身ではコントロールできない」部分の影響はできるだけ排除してあげたいと思うわけです。でも一方で、例えば「ホームラン打たれるのは投手の責任だよなぁ」とか、「フォアボールを与えたりするのは明らかにピッチャーの責任」とか「逆に三振を取るのはピッチャーの力量のみに依存する」といった考えから 「じゃあこの3つの指標だけでピッチャーを評価してみるのはどうか?」ということを誰かが提起するんです。この場合の「誰か」というのはボロス・マクラッケンという人なんですけど。そうすると、色んなセイバーメトリシャンがそれに基づいて「自分はこう考える」といろんな意見を出し合って、一番理に適い、しかも計算が容易な指標が普及していくんですね。DIPSの中で今一番普及しているのはトム・タンゴが提唱したFIP (Fielding Independent Pitching) という指標です。ちなみにこのFIPという指標は先発・中継ぎ・抑えも同様に評価できるので、今では主要な指標のひとつとなっています。
さらには、野手も投手も究極的に同じ指標で評価することのできるWAR(Wins Abobe Replacemnt)が出てきたり、これまでセイバーメトリクスの中でメジャーな指標だったOPS(出塁率+長打率。打率などよりもより得点貢献への相関が高いとされる)よりもRC (Runs Created) や XR (eXtrapolated Runs) 、さらにはwOBA(Weighted On-Base Average)というように、どんどん新しい指標が提案されていくんですね。
――野球には「この選手は打率や打点とかではあんまりパッとした数字は出ていないけれど、なぜかいつも強いチームにいる」ということがよくありますよね。そういったかたちで、これまではっきりとした数字は出ていなかった「なんとなく」だったり「空気感」のような部分を、より細かな指標で可視化させるというのが、セイバーメトリクスの大きな意義ですよね。
鳥越 その意味では最近、「運」というものを数値化しようという考え方が出てきています。選手本人の調子が悪くなくても、不運が重なって思うように成績を残せないことがよくありますが、たとえばバービップ(BABIP)という指標はその「運」「不運」を可視化しようというものです。
投手が投げた球を打者に打たれて、それがフェアゾーンに飛んだとき(ホームランを除く)にそれがヒットになる確率って、ほとんどの投手で3割付近に収束するという理論があるんです。たとえば今季、ある投手の調子が悪いなと思ったときにBABIPを見たら3割5分だった、と。そうなると、その選手の調子が悪いというよりも、チームの守備がまずかったり、たまたま転がったところが悪かっただけである可能性が高いと考えられる。なので翌年は本来の数字に戻せるのではと推測する。逆に成績がよくてもBABIPが2割5分だったら運に助けられている部分が大きいから、次のシーズンは成績がよくないかもしれないと予想できる。
――そのセイバーメトリクスが一部のマニアだけでなく、アメリカで少しずつ世の中に広がり始めたきっかけってなんだったんでしょうか? やはりビリー・ビーンの登場が大きい……?
鳥越 いや、大きなきっかけになったのは『ファンタジーベースボール』でしょうね。ビリー・ビーンがチーム編成にセイバーメトリクスを取り入れ始めたのは90年代前半以降ですが、ほぼ時を同じくして『ファンタジーベースボール』がネット上で爆発的に普及し始めました。
『ファンタジーベースボール』というのは、オンラインゲームの一種で、サラリーキャップ(選手の総年俸額を制限すること)の中で自分たちの夢のチームを作るというものです。実際のメジャーリーガーを題材にしていまして、彼らの現実世界での活躍がゲームでの加点対象になるのです。サラリーキャップですからオールスター級の選手を集められるわけじゃないですよね。だから実際の成績を見て、コストが安いけど良い成績を残している選手を集めていく。これはまさにビリー・ビーンのやっていることと同じですね。プレイヤーがデータを見て年俸の安い若手を雇った結果、その選手が実際に活躍してチームに大きなポイントをもたらしたとき、プレイヤー冥利につきるのでしょうね。
■パ・リーグを中心にセイバーメトリクスが普及した2000年代
――セイバーメトリクスの日本での受容についても伺っていきたいのですが、そもそも「野球にデータを導入する」という意味では、日本では90年代ヤクルト・野村克也監督の「ID野球」もありましたよね。鳥越さんの著書では、要するにID野球というのは野村監督の経験知に負う部分をデータ化・定式化していたものだったという分析も書かれていました。そうなるとID野球とセイバーメトリクスはまったく別物ということなんでしょうか?
鳥越 セイバーメトリクスのスタート地点では対極にあるものだったと考えています。僕は「ミクロの視点」と「マクロの視点」というふうに整理していますが、ミクロの視点で「次のノーアウト1,2塁でボールカウント2-1で、ここからはこう投げたらいい」という一瞬一瞬の判断をする際に、野村ID野球の経験知が使えるんだと思います。ですがセイバーメトリクスはミクロな判断というよりは、「この選手は科学的に見るとこういう成績だったから、この人の評価はこうですよ」というマクロな視点を与えるものなんです。
――なるほど。では、アメリカ流のセイバーメトリクスが日本で本格的に受容され始めたのは、いつぐらいなんでしょうか。
鳥越 一番最初に導入したと言われているのは、ロッテの監督を二度にわたり務めたボビー・バレンタインですね。もともとテキサス・レンジャーズで監督をやっていた方なので当然、セイバーメトリクス的考え方を身につけていたわけです。彼が最初に日本に来たのは1995年ですが、ポール・プポという統計の専門家をフロントに招聘して積極的にデータの活用を推し進めた。それで万年Bクラスだったロッテをいきなり2位に押し上げ、ファンのあいだでも大変支持されていたんですが、残念ながら彼のやり方は当時のフロントやコーチ陣に受け入れられなかった。やっぱり「俺たちの意見よりもデータを見るのか!」と反発する人が多いわけです。
――日本のプロ野球全体が、職人芸のようなスカウティングを頼りにしていた時代ですよね。
鳥越 やっぱり「職人さんの粋な腕を評価する」という文化が日本にはあるわけですね。しかしその後約10年間、ロッテはBクラスに沈んだため、ファンは余計にバレンタインの復帰を待望するようになっていったのです。
――そのバレンタインがロッテの監督に復帰したのは2004年で、1期目と2期目には約10年の間がありますよね。ちょうどこの時期はビリー・ビーンの手法がメジャーでかなり注目され始めた時期だと思うのですが、その間にセイバーメトリクスを導入していった日本の球団ってあるんでしょうか?
鳥越 ボビーが戻ってくるのと同時期、2004年に日本ハムファイターズが東京から北海道に本拠を移したのですが、それを機に、2005年頃に導入しています。デトロイト・タイガースのGM補佐から、阪神の総務部次長へと歴任された吉村浩さんをヘッドハンティングしたんですね。彼はセイバーメトリクスの知識を持っていて、1億円かけてBOS(Baseball Operation System)というシステム作り、それを基にフロント主体でチーム作りをやっていくことになったんです。
一方で同じ頃ロッテに復帰したボビーは、パ・リーグの予告先発制度を活用して、相手の先発投手に相性のよい打者を選んで毎試合打順を組むという大胆なことをやって、前の日4番だった里崎が次の日にはスタメン落ち,その翌日は9番だったりするもんだから「猫の目打線」なんて呼ばれていたりしましたね。結局2005年シーズンはロッテがパ・リーグのチーム得点1位の攻撃力でクライマックス・シリーズを勝ち抜き優勝、阪神との日本シリーズは4勝0敗の圧勝で日本一になったわけです。そのシリーズでの両チームの総得点33−4は、いまでもネット上で大差の例えとして使われていますよね。
――ロッテと日ハム以外に、セイバーメトリクスを導入していった球団ってどういうところがあるんですか?
鳥越 今だと、楽天が2012年から導入していますね。8月から立花陽三さんという、元々ソロモン・ブラザーズ、ゴールドマン・サックス、メルリンチなどで証券マンをやってた人を球団社長に迎えたんですね。彼はまず「我々でもわかるように楽天の戦力を数値化しろ」と指令した。そのためにセイバーメトリクスの分析をしている会社と契約して、2012年のシーズンが終わったところで分析結果を見てみたら、田中将大投手を中心に投手陣は揃っていて十分戦えるが、打線の方は4番・5番が穴だということがわかった。そこで右の長距離砲に狙いを定めて調査したところ、スカウトがA.J(アンドリュー・ジョーンズ)とマギーをリストアップしてきた。そこで立花さんが自ら交渉に向かい中軸を埋めた。そして2013年、投打がうまく噛み合って日本一になったわけです。
それからソフトバンクも日本IBM、クロスキャットとともに「χ援隊(かいえんたい)」と名付けられたデータ解析、レポート配信システムを構築しまして、スコアラーだけでなく、首脳陣や選手すべてに支給されたiphone、ipadにリアルタイムで分析したデータを配信、チーム内で共有できるようになりました。パ・リーグ優勝がかかった2014年10月2日の対オリックス戦で、10回裏1アウト満塁、一打決めればサヨナラ優勝という場面での松田がベンチ前でスタッフが手にしたデータを凝視しているシーンはちょっと感慨深いものがありましたね。
――パ・リーグを中心にセイバーメトリクスが普及して勢力図がどんどん書き換わっていったわけですね。しかしこれだけセイバーメトリクスが有名になってきているのに、セ・リーグのチームは導入していないんですか?
【ここから先はチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は2月も厳選された記事を多数配信予定です!(配信記事一覧は下記リンクから順次更新)
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201502
<前へ
2 / 2