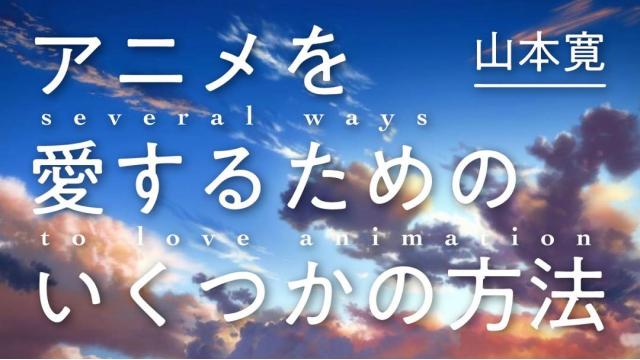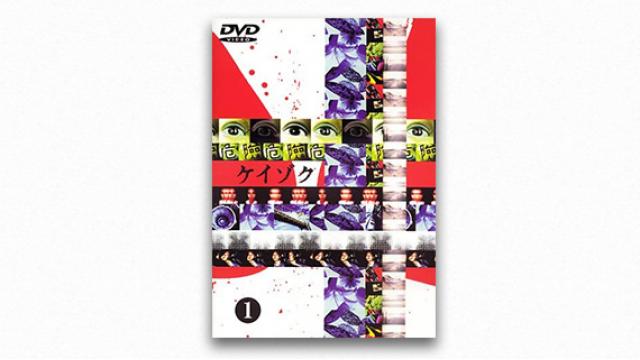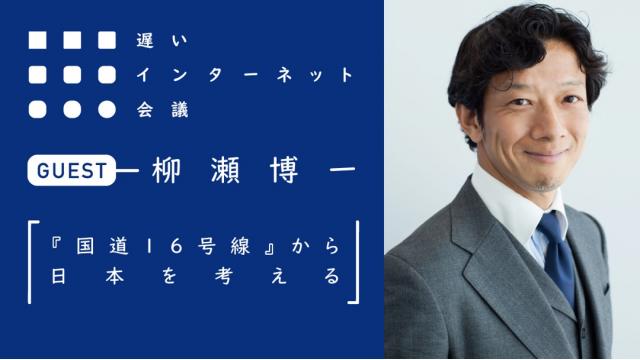-
【新着動画のお知らせ】「シン・エヴァ」が公開延期になったので、「序・破・Q」をあらためてふりかえる感想戦
2021-01-23 21:00
いつもPLANETSチャンネルをご視聴いただき、ありがとうございます。
新着動画のお知らせです。
本来であれば、1/23(土)に公開予定だった『シン・エヴァンゲリオン劇場版』。
本作の公開を待ち望む宇野常寛とその仲間たちが、これまでの新劇場版「序」「破」「Q」をあらためてふりかえる感想戦を2時間を超える大ボリュームで行いました。
ご自身のエヴァとの出会いを思い出しながら、ぜひ、ご覧ください!
※ネタバレ全開でお届けしますので、未見の方はご注意ください。
【動画】
「シン・エヴァ」が公開延期になったので、「序・破・Q」をあらためてふりかえる感想戦
https://www.nicovideo.jp/watch/so38157144
また、宇野常寛と編集者の井本光俊さんによる『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』の実況配信を1月22日(金)に行いました。こちらも合わせてご覧ください。
h -
【今夜21時から見逃し配信!】石岡良治×福嶋亮大「2020年の想像力」
2021-01-23 12:00今夜21時より、批評家の石岡良治さんと文芸批評家の福嶋亮大さんをお招きした遅いインターネット会議の完全版を見逃し配信します。
24時までの限定公開となりますので、ライブ配信を見逃した、またはもう一度見たいという方は、ぜひこの期間にご視聴ください!
石岡良治×福嶋亮大「2020年の想像力」見逃し配信期間:1/23(土)21:00〜24:00
コロナ禍によってエンターテインメントが大きな打撃を受けた2020年。「鬼滅の刃」「愛の不時着」「梨泰院クラス」「BTS」「TENET」「MIU404」といった既存ジャンルのヒットコンテンツから、ライブや演劇のオンライン配信といった新動向まで、ステイホームの環境下でカルチャーシーンがどう変動したのか、ゲストのお二人とともに振り返ります。
※冒頭30分はこちらからご覧いただけます。https://www.nicovideo.jp/watch/so379859 -
【お知らせ】「Daily PLANETS」メール配信エラーに関するご報告
2021-01-23 02:40いつもPLANETSチャンネルをご視聴いただき、ありがとうございます。
弊社PLANETSチャンネルより毎平日配信しております「Daily PLANETS」について、一部チャンネル会員様へメールでの記事のご案内が一定期間できていなかったことが発覚しました。
現在、原因究明および状況改善に向けて対応しておりますので、いましばらくお待ちください。
なお、記事については、ログインした状態でニコニコ動画「PLANETSチャンネル」のページへ訪問いただければご覧いただけます。 お手数ですが、各webブラウザより以下のURLヘアクセスして、お読みいただけますと幸いです。https://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga
チャンネル会員の皆様には多大なご迷惑をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます。 引き続き、何卒よろしくお願いいたします。
PLANETS編集 -
読書のつづき[二〇二〇年八月]日本の夏、停滞の夏|大見崇晴
2021-01-22 07:00
会社員生活のかたわら日曜ジャーナリスト/文藝評論家として活動する大見崇晴さんが、日々の読書からの随想をディープに綴っていく日記連載「読書のつづき」。酷暑と第二波真っ只中の連日の感染拡大の報に、大見さんの読書生活も確実に蝕まれていった二〇二〇年八月。台湾民主化の父・李登輝の死去や香港での民主化運動の弾圧など東アジア政治に暗雲が垂れ込め、歴代最長となった安倍政権にも退陣の声が囁かれる中で、日本の停滞を見つめる戦後75年目の夏が過ぎてゆきます。
大見崇晴 読書のつづき[二〇二〇年八月]日本の夏、停滞の夏
八月一日(土)
もう八月になってしまった。今月はクレジットの利用代金が高額で何十万。とはいえ、ほとんどが交通費なので仕方がないのだが、こうしてみると交通費をクレジットカードで支払うのも考えものかもしれない。もっとも昨年のキャッシュレス決済・ポイント還元事業を政府が推進してから、いろんな決済をクレジット決済にする習慣になってしまったから、現金払いに戻せる自信もない。
クレジット払いをしていて不安になるのは、このCOVID-19伝染の沈静化が進まないかぎりは、いつか急に手元資金が尽きるようなことがあって、クレジットを返済できなくなる日が訪れる気がしてならないためだ。出費を減らすには本を買わないことが一番簡単かもしれない。積ん読がたくさんあるのだから、それを丁寧に読み込んでいけばよいのだと思うけれど、なかなか誘惑に勝てずに本を買っている。
今日は明け方四時に眼が覚めてから一度覚醒したあと、十時まで寝込んでいた。昼食後に横になると、自然とまた眠りこけていた。蓄積疲労が抜けないんだろうか。
注文しておいた古書が続々と届く。
地元の図書館に借りていた本を返却する。
なんとも息が切れるかんじがする。地元古書店で矢作俊彦[1]『悲劇週間』を買う。呆れるくらいに見たい番組がない。見逃していた「かりそめ天国」を見る。日本の古書店で以下の本を注文した。
田中成明『現代法理学』
ペレルマン『法律家の論理』
『イギリスの政治思想』I~IV
東出昌大と杏が離婚。この疫病が広まる最中、不信の対象が家庭にいるのは精神的負荷になるから理由もわからなくはない。
I・A・リチャーズ『新修辞学原論』を少し読む。バークレーが引かれていた。
今日の東京のCOVID-19新規感染者は四七二人とのこと。これでテレワークが広まってくれないか。満員電車は御免被りたい。
李登輝[2]の死を受けて中国の官僚政治家の歴史に関する書籍を改めて読む。そういえば、このあたりについて「自己宣伝」という観点から草森紳一が本を書いてたはずだが、実際はどうなのだろう。このころの中国の政治家たちの言葉は含蓄がある。林彪の毛沢東批判など分析として面白い。「あの豚のような独裁者は、まず人に意見を言わせてから否定しようとする」「否定から入るな、という否定で冒険主義を進める」。やはり権謀術数というのは中国史に学ぶところがある。日本であれば太平記や平家物語、吾妻鑑に梅松論などがそれに当たるのだろうか。江戸時代などには太平記読みが多かったというのに、その意義が見落とされている気がする。
音泉のプレミアム版がPCブラウザからもアクセス可能になったと言うので、ログイン設定を済ませる。
しっかりとは読めていなかった表象文化論学会のハラスメント規定を読みなおす。
角川グループ、新社屋がある所沢にはマンホールも角川グループのアニメやマンガのものが設置されているそうだ。街のディズニーランド化を実現しているようで、『物語消費論』のころの大塚英志氏の構想や仮説を現実化してきている。そういう意味では、大塚英志氏ご自身がバブル期に「空間プランナー」などと怪しい肩書きを名乗ったことを自嘲的に語っていたはずが、今なら何と発言するのだろう。そして、角川歴彦氏と大塚英志氏がいなくなったら、企業としてのアイデンティティを見失ってしまうのではないか。そのことが懸念されてしまう。
香港警察が海外に居住している民主化運動家たちを取り締まろうとして指名手配を始めた。香港に戻れば逮捕されるだろうとのことだが、そうでなくとも親中国であれば身柄が拘束される恐れがあるのではないか。イギリスかアメリカでないと安心ができない。
新規感染者が劇的に増えているように思われる昨今だが、七月二三日からの四連休で一気にウィルスが広まったのだろう。原因ははっきりしている。二週間後の盆のころになれば少し数字が落ち着いて、更にその二週間後の九月頭くらいになると盆休みを原因した感染者増加があるんじゃないか。そのあたりで通常なら秋国会(臨時国会)が召集されて、各種特措法が通過するはずである。八月十五日の終戦記念日のあとに安倍総理辞任の声が高まる気がするが。
レイモンド・ウィリアムズ[3]『テレビジョン』を買い忘れていることに気づいた。
広島カープの最下位、昨年から佐々岡が投手陣の整備を任されていたことを考えると、この大惨事になったのは「妥当」というより他ないし、佐々岡は結局二年続けて投手陣整備に失敗したわけだから、原因と結果を見つめ直してほしい。それができなければ、来年の秋には監督辞任の足音が聞こえてくる。
[1]矢作俊彦 一九五〇(昭和二五)年生。日本の小説家、マンガ家。ダディ・グース名義でマンガ家としてデビューするが、『マイク・ハマーへ伝言』(一九七七)でハードボイルド小説作家としての評価を確立。一九八〇年にマンガ家の大友克洋の原作者として『気分はもう戦争』に関わる。『気分はもう戦争』は物語でも絵でも革新的とされ、大いに話題を呼んだ(作家や文芸評論家たちが批評の題材にした)。八〇年代には司城志朗とタッグを組み冒険小説を発表し好評を博す。『スズキさんの休息と遍歴』(一九九〇)は、自動車雑誌「NAVI」編集長鈴木正文(現「GQ Japan」編集長)をモデルにした小説だが、日本の小説で最もヴォネガットの『チャンピオンたちの朝食』からの影響を露にした作品となった。この小説が三島由紀夫賞候補作となったこともあり、以後純文学作家としての側面が大きくなる。日本が関西と関東で分割され、吉本興業が関西政界を牛耳るというブラックな世界を描いた『あ・じゃ・ぱん』(一九九七)でBunkamuraドゥマゴ文学賞を、『ららら科學の子』(二〇〇四)で三島由紀夫賞を受賞。『悲劇週間』(二〇〇五)はフランス文学翻訳者の堀口大學を主人公に据えた小説であるが、フランス文学(の翻訳文体)へのオマージュにもなっている。
[2]李登輝 一九二三年生、二〇二〇年没。台湾の政治家。第四代目の中華民国の総統を務めた。大陸からの移民ではなく、台湾に従来から生活をしていた本省人であり、初の直接選挙によって選び出された総統であったことから、台湾民主化の父とされる。現在知られているような台湾のイメージは李登輝時代に築かれた部分が大きく、それ以前は一九四七年から一九八七年までの四〇年は「白色テロ」と呼ばれる戒厳令下であった。
[3]レイモンド・ウィリアムズ 文学・文化評論を中心に活動をしていた研究者。一九六〇年代から評論の対象はマスメディアにも広がり、『コミュニケーション』(一九六六)、『テレビジョン』(一九八四)のような著作も刊行している。ウィリアムズの影響を受け、カルチュラル・スタディーズと呼ばれるサブカルチャーも含めた文化研究が大学でなされるようになった。
八月二日(日)
草森紳一の『江戸のデザイン』を注文する。
眼精疲労がひどい。
関川夏央『文学は、たとえばこう読む』が面白そうだ。
理髪店でカットを済ませる。
今日で大河ドラマの『麒麟がくる』は十回ぐらい放送を見送っていると思うのだが、このままで当初の予定通りの放送回数を消化することができるのだろうか。越年をしないと難しい。
アキラ100%が秋田の観光大使と知って驚く。吉本の芸人でなくとも、ちゃんと地方公共団体の仕事を受けている芸人もいるのだな。とはいえ、冬の地方営業は、小島よしおもそうだけれど、裸で寒そうだ。
TBSの良原アナ、まだ全然こなれてないけれど、どうにもこなれる雰囲気がない。ガツガツしていなくて好ましく思えるか、それともハングリー精神のなさと捉えるか。
なんとなく、むかしの文芸誌「重力01」を読んでみたが、経済学者の西部忠の議論や意見が敷衍されていないのは何なのだろう。重要な示唆的な発言も多いのだが。
大杉 ちょっと話をずらしますが、一時、鎌田さんが「重力」に女性を加えるか加えないかっていう話をしていたじゃないですか。でも原理への服従ということで、それで果たして女性が加わることがあり得るのかっていう問題をちょっと考えたんですけれど、NAMも女性が少ないらしいし。 鎌田 原理への服従で女性が加わる? 僕にとっては服従だけど、強すぎる言い方だったら撤回します。経済的自立が原理だから、その通り動いてみよう、そういう感じ。(「重力01」p.17)
このひとたちは一体なにを話しているのだろう。少なくとも座談会を編集するときに、もう論旨が汲み取れるような日本語にするものだが。そういう恥じらいや読者の視線といったものが頭に浮かばないのだろうか。と思って読み進めると座談会構成を大杉重男[4]が担当しているとあって、これでは雑誌が短命に終わるのも仕方がないかなと思わされた。
それから大杉重男氏に対して保坂和志氏が批判的だという記事をどこかで見かけたが、その一連のやりとりがあったことを踏まえた上で次のような発言を読むと、「だからなに?」以上の言葉が出てこなかった。あてこすりにも程がある。
大杉 保坂のは将棋雑誌の一般読者からも不評だと思う。『羽生』なんて嘘ですよ。保坂は羽生が最初からすべてを見通している神みたいに語っているけれど、羽生はやっぱり終盤力で勝っているのではないか。(「重力01」p.18)
大杉氏世代の文藝批評家がそれ以前の批評家たちと異なり、若年層からの人気を勝ち取れなかったのも、こうした「ためにする」議論が多かったからなのだろう。
今年の東京は、七月は一日しか晴れの日がなかったそうだ。ガルシア・マルケスの『百年の孤独』の舞台となったマコンドのようだ(もっとも、あちらは年単位で雨が続いたはずだが)。そうと知ると、最近気が塞いでいたのは、天候が原因だったのかもしれない。
インドのパンジャーブ州で密造酒を飲んだ人たちが大量死。メチルアルコールを含んだ(戦後間もなくの日本で言えば)「バクダン」だったことが原因だそうだ。何故こんなにも密造酒が出回ってしまうのだろう。インドの流通事情、酒税について知りたいところだ。なにかしら密造に庶民が走ってしまう構造的な原因がある。しばしば「戦後のどさくさ」という定型句が使われるが、そのころの日本と同じようなことが日常的に起こっているというのは、平時の国としては考えものである。
昨日の読売新聞で二階氏がインタビューに答えているのを読む。「もうはまだなり、まだはもうなり」という格言を思い出してしまった。
声優の桑原由気[5]のネットラジオを課金して視聴しているのだが、好きが講じて寄席を開いていることを彼女が話していて、真顔でサンシャイン池崎が引いているのに笑ってしまった。K-PROというのは、いま女性たちにとって、ひとつのロールモデルになっているのかもしれない。
[4]大杉重男 一九六五(昭和四〇)年生。日本の近現代文学研究者。群像新人文学賞(評論部門)を受賞した「『あらくれ』論」は、筒井康隆に激賞された。以後、徳田秋声を中心に研究を進めている。「重力」は二〇〇一年ごろの評論を中心とした雑誌。
[5]桑原由気 一九九一(平成三)年生。日本の女性声優。漫才コンビ天津の向と「桑原由気寄席」を開催している。「桑原由気と面白いひとたちのらじお」では、ゲストに呼ばれたトム・ブラウンのみちおが自分の観ていたアニメの声優と共演できることを喜んでいた。同番組のゲストは、佐久間一行、トム・ブラウン、サンシャイン池崎、虹の黄昏、Aマッソ、ネルソンズ、蛙亭、真空ジェシカなど。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
1/22(金)放送!『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』をアマプラで観ながら実況します
2021-01-21 21:30
1/22(金)の夜に、宇野常寛と編集者・井本光俊さんがAmazonプライムビデオで『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』を観ながら実況をする生放送を行います。
『シン・エヴァンゲリオン劇場版』が公開延期となり寂しいこの頃ですが、『破』を観ながらこれまでの新劇場版について振り返りましょう。
※同時間帯に、「金曜ロードショー」で『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 TV版』が放送されていますが、本番組で視聴するのはAmazonプライムビデオで配信されているバージョンです。
ご自宅でステイホームしながら、二窓で一緒に映画を視聴してください。
ご視聴はこちらからhttps://live.nicovideo.jp/watch/lv330116489▼放送日時
1/22(金)20:45〜
(映画は21:00頃から視聴開始します)
▼出演者
宇野常寛(評論家・PLANETS編集長)
井本光俊(編集者)
▼『ヱヴァ -
トランスフォーマー(5)「合体するロボットたちの主体とリーダーシップ」|池田明季哉
2021-01-21 07:00
デザイナー/ライター/小説家の池田明季哉さんによる連載『"kakkoii"の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝』。今回からは改めて『トランスフォーマー』について、玩具としてのプロダクト展開を歴史的に辿っていきます。日本のタカラとアメリカのハズブロ社の2社によって作り上げられた「トランスフォーマー」シリーズは、日本とアメリカ、それぞれの美学の綱引きによって移り変わっていきました。今回はその中でも「合体戦士」に着目し、合体にまつわる日米の価値観の違いをひもときます。
池田明季哉 “kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝トランスフォーマー(5)「合体するロボットたちの主体とリーダーシップ」
こんにちは、池田明季哉です。前回からかなり間が空いてしまいました。実はこの間、1年住んでいたイギリスから日本へと帰国していました。そしてイギリスに滞在した経験を元に書いた小説が電撃大賞で賞をいただき、その出版に追われていました。『オーバーライト──ブリストルのゴースト』というタイトルで、4/10に発売され、続編である『オーバーライト2──クリスマス・ウォーズの炎』が10/10に発売されています。慌ただしい日々を送っていましたが、おもちゃ遊びを欠かしたことはなく、改めておもちゃの可能性を整理していきたいと思っています。よろしくお願いします。
────
今回からは、トランスフォーマーの展開について補足していきたい。 ここまで「G1」と呼ばれる初期トランスフォーマーのリブランディングがどのような想像力で行われたかを推察し、そしてハリウッド映画版が美学の上でどのように行き詰まったかを整理してきた。いわば原点と現在地点の双方から挟み撃ちにするかたちで、トランスフォーマーが描いてきたイマジネーションを分析してきた。 しかしこれはトランスフォーマーというブランドが歩んできた35年以上の長い歴史の、あくまで両端にすぎない。その歴史のなかで「魂を持った乗り物」の想像力もまた、大きく変遷してきた。補足をしてなおすべてを語りきることはできないが、特に重要だと思われるアイテムやシリーズの宿した想像力について、メディアでの描かれ方と突き合わせながら確認していきたい。 トランスフォーマーは、日本文化とアメリカ文化の両義性に本質があると定義した。そしてトランスフォーマーの想像力もまた、日本のタカラとアメリカのハズブロの関係に象徴されるように、日本的な美学とアメリカ的な美学の綱引きによって移り変わっていった。長い歴史を持つぶん、提出されたデザイン・語るべき文脈もまた膨大である。そのすべてを網羅的に紹介できないことは心苦しいが、重要な想像力を持つアイテムをピックアップして、その想像力について論じていきたい。
合体戦士は強いか、弱いか
1984年にスタートしたトランスフォーマーはそのラインアップを拡げ、1985年には1つのロボット形態に2つのマシン形態を持つ「トリプルチェンジャー」であるブリッツウィングやアストロトレイン、また複数のトランスフォーマーが合体する「合体戦士」である「ビルドロン巨人兵 デバスター」といった、印象的なキャラクターが登場した。
▲ビルドロン巨人兵 デバスター。6体のロボットが合体する。(出典:『トランスフォーマージェネレーション デラックス ザ・リバース:35周年記念バージョン』 (メディアボーイ)P13)
まず、この「合体戦士」の受け止められかたについては触れておきたい。「複数の主体を持ったロボット/マシンが合体すると、さらに強くなる」という文化は、1970年代の数々の日本ロボットアニメをはじめ、タカラにおける玩具発のシリーズとしては「ミクロマン」、そしてそれを引き継いだ「ダイアクロン」の時点ですでに確立されていた。デバスターの原形となった「ダイアクロン 建設車ロボ」もまた、こうした想像力を下敷きにしていると見ていいだろう。
▲ダイアクロン建設車ロボ。(出典:『ダイアクロンワールドガイド』(ホビージャパン)P72)
ところがデバスターには、明確に異なった特徴がある。確かに合体によって強力な力を得るのだが、合体する6人の意志がバラバラのため、知力が下がっているという弱点が与えられているのである。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
[新連載]インフォーマルマーケットから見る世界──七つの海をこえる非正規市場たち 序説:「インフォーマルマーケット」とは何か|佐藤翔
2021-01-20 07:00
今月から、国際コンサルタントの佐藤翔さんによる新連載「インフォーマルマーケットから見る世界──七つの海をこえる非正規市場たち」がスタートします。新興国や周縁国に暮らす人々の経済活動を支える場として、実は欠かすことできない存在である非正規市場(インフォーマルマーケット)たち。世界五大陸に広がるそのネットワークの実態を地域ごとにリポートしていきながら、グローバル資本主義のもうひとつの姿を浮き彫りにしていきます。初回は、世界に拡がるインフォーマルマーケットの全体像について解説します。
佐藤翔 インフォーマルマーケットから見る世界──七つの海をこえる非正規市場たち序説:「インフォーマルマーケット」とは何か
はじめまして、ルーディムス株式会社代表の佐藤翔と申します。ゲーム業界専門のシンクタンクであるメディアクリエイトという会社で数年間にわたり、世界各地のゲーム市場の調査をしてまいりました。現在はコンテンツ市場の海外進出に関するお手伝いをさせていただいています。とりわけ新興国のゲーム産業や市場、そして正規の販売ルートを外れた非正規市場、すなわち「インフォーマルマーケット」との付き合いは、コンサルタントとしての私の最初の勤務国であるヨルダンで働いていた頃から数えて、10年目になります。 この連載では、その過程で接することになった五大陸に広がる多様なインフォーマルマーケットと、それらをつなぐ七つの海を股にかけた人々のネットワークという視点から、私なりの考察を展開していければと思います。
まず、なぜ私がこのように五大陸のインフォーマルマーケットを研究するハメになったのか、というところから、お話しをしていきましょう。
ヨルダンで出会った『シェンムー』
2011年、ヨルダンの首都、アンマンにあるゲーム業界団体、Jordan Gaming Taskforceというところで私が勤務していた頃の話です。私はチェルケス人の上司の指導の下、ヨルダンのゲーム会社の海外進出のために、戦略を策定するという仕事を任されていました。仕事が終わってから町を歩いていると、違法コピーの店をそこら中に見かけました。やけに数が多いな、とは何となく感じてはいましたが、その頃には自分には関係のないことだなと思い、ちょっと中を覗く程度で、あまり気にかけることなく通り過ぎることがほとんどでした。
▲ヨルダンでの佐藤の講演の様子。
私が少しだけ考え方を変えたのが、ヨルダンのゲーム屋の店主との対話です。断食月(その年は8月でした)のころ、マーケティングの勉強だと思って現地の人を見習い断食しながら働いていた頃だったかと思いますが、私の友人で、新しい風力発電機を発明しようとしているヨルダン人の起業家が、彼の知り合いのゲーム屋の店長を紹介してやる、インタビューをしてみてはどうか、と言ってくれたのです。
翌日、彼にその店に連れて行ってもらいました。店に入ってすぐの所には"Microsft"や"Micosoft"というロゴの入った中国製の携帯ゲーム機ケースがあり、左右には海賊版としか思えないゲームが置かれた棚がいくつも並んでいるという所で、奥の方にやや体格の大きい店主さんが立っていました。パッと見はヨルダンではどこにでも見かける、どうしようもない店です。しかし、私が彼に最近のアンマンにおけるゲームの売れ行きなどについてのインタビューをしながら、店内をよく見渡すと、『シェンムー』、それもきれいなパッケージの、まごうことなき正規品のドリームキャスト『シェンムー 一章 横須賀』日本語版が、神棚よろしく、店の一番立派な棚の最上段に、それはそれは丁寧にまつられていたのです。私が店主さんにそのことを尋ねると、「『シェンムー』は俺の人生を変えたゲームなんだ。俺は『シェンムー』に出会ったからゲームを売る商売をしているんだ!」と、なぜか誇らしげに返答してきました。
▲『シェンムー I&II』プロモーション映像
だったらちゃんと正規品を売ってセガのクリエイターに利益を還元しろよ、と私が心の中でツッコミを入れたのはさておき、この時に私が率直に感じたのは、こんな怪しげなゲームの販売店をやっているような奴は、確かにどうしようもない奴だけれども、彼らは単に儲かるから、それしか売り物がないからではなく、彼らなりにゲームが好きだからこんな商売をやっているんだな、ということでした。当時は今ほど様々な調査技法を身に着けていませんでしたし、「インフォーマルマーケット」という表現も知りませんでしたが、今にして思えば、この経験こそがこうした正規市場でないマーケットでものを売っている人々、さらにはそのマーケット自体の生態系に目を向けるようになったきっかけだったようです。
新興国のリアリティとしてのインフォーマルマーケット
さて、話は前職での仕事に移ります。私は日本におけるゲーム業界のシンクタンクであるメディアクリエイトに入社して2年後、新興国のゲーム市場の調査を行うようになりました。自分のバックグラウンドはヨルダンですが、中東だけではなく、南アジア、東南アジア、中南米など、世界のあらゆる新興国のゲーム市場について、可能なかぎり的確な情報提供を行うことを求められるようになりました。
そうして様々な場所を訪れる中で最も印象的だったものの一つがモロッコでの体験です。モロッコの私の友人は、正規のショッピングモールのゲーム販売店を見せてくれた後、モロッコ最大の非正規市場デルブ・ガレフに連れていく際にこう言ってくれました。「Sho Sato、ショッピングモールで見て分かるものなんてのは見せかけの、薄っぺらなものに過ぎないんだ。あんなところで誰もゲームなんて買っちゃいない。あれは仮想現実みたいなもんでリアルじゃあない。このデルブ・ガレフこそが俺たちのリアルなんだよ!」。
▲正規市場であるモロッコのショッピングモールのゲーム屋と玩具屋。(筆者撮影)
▲モロッコのインフォーマルマーケットのひとつ、デルブ・ガレフのゲーム屋とPC屋。(筆者撮影)
▲デルブ・ガレフの上空写真(出典)
彼は、自分がどれだけここに流れ着いたありとあらゆる日本の中古ゲームを買って遊んできたかをとうとうと語ってくれました。親子三代で非正規流通品のゲームをさばいている店も案内してもらいました。そして彼は今や、モロッコを代表するゲーム開発者の一人になっています。きれいなショッピングモールを見て、きらびやかなオタクコンベンションに参加するだけでは、ゲームがどのような商流になっているのか、ユーザーがどのようにゲームを遊んでいるのか、そしてどのようにゲームが生まれてくるのか、こうした新興国のリアリティを把握することは絶対にできません。
驚くべきことは、こうしたマーケットが一地域に限らないことです。ダウンロード版のゲームが増えてきたとはいえ、オフラインの商流は、家庭用ゲームの比率が高い日本企業にとっては現在でも非常に重要です。結局、ゲーム市場の実態を可能なかぎり客観的なかたちで知るには自分の足で稼ぎ、自分の目で確かめる以外に手段はありません。そのため、お客様に新興国市場の正確な姿をお伝えするため、私は休みの日であっても寸暇を惜しみ、世界各国のゲーム市場を回るようになりました。
こうした調査の結果、東南アジア、中南米、インド、中東、サブサハラアフリカ、東欧、中央アジア、ありとあらゆる地域にインフォーマルのマーケットがあり、しかも地元経済に重要な役割を果たしており、ゲームユーザーの好みさえ規定し、さらには現地のゲーム開発者のゲームプレイ経験に大きな影響を与えていることを目の当たりにしてきました。そしてこうした観察を通じて、大部分の新興国ではフォーマルマーケットがインフォーマルマーケットを規定しているというよりも、インフォーマルマーケットが圧倒的な存在で、フォーマルマーケットはそこに乗っかっているに過ぎないのだ、ということが分かってきました。 さらに、どうも非正規市場には、一定の特殊性と共通性があるのだ、ということがつかめてきました。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
「アニメ・イズ・デッド」その後~2021年を占う|山本寛
2021-01-19 07:00
アニメーション監督の山本寛さんによる、アニメの深奥にある「意志」を浮き彫りにする連載の第16回。かつて山本さんが「アニメ・イズ・デッド」と題した講義で、作品のテーマや思想を追求する姿勢を失い、ひたすら動物的に「萌え」を消費するようになった日本アニメの状況を批判してから4年超。毎クールの「覇権」争いなど、さらに不毛さの加速した現状を受けながら、2021年からのアニメの行く先を展望します。
山本寛 アニメを愛するためのいくつかの方法第16回 「アニメ・イズ・デッド」その後~2021年を占う
この連載でも何度か参照している、僕が2016年夏に大阪で行った講義「アニメ・イズ・デッド」であるが、あれから4年超経った2021年、アニメはどうなったか、どうなっていくかを今回述べてみたい。
この講義の概要を改めて説明すると、アニメ視聴者たちの発信が2007年を境に、SNSを中心にアニメ業界に対する脅迫・恐喝に近い発言力を得て猛威を振るい始め、2009年からは「モダニズム」の崩壊と「ポストモダン」の隆盛、つまりテーマや思想の議論は急激に衰退し、ただひたすら「萌え」を享受し「動物的」な現実逃避に走るという消費スタイルが一般化する。それがさらに2011年の東日本大震災を経て、もはや現実世界の解釈や読み直し、批評としてアニメを捉えることを皆極度に忌避するようになった、つまり現実逃避が加速した、というものだった。
しかし、この講義でも述べたが、これはアニメ作品が世間から一本もなくなるということではない。 アニメが文化として滅ぶ、ということの証左だと言いたいのだ。
ではここで、「アニメ・イズ・デッド」にもう一つの要素を加えよう。「覇権主義」「勝ち負け主義」である。 これはかつて某作品の宣伝番組で某氏が宣言した「覇権」という語をきっかけに瞬く間に浸透したものだが、SNSの猛威が高まるにつれ人々は「自分が何を好むか」ではなく、「皆が誰を好むか」を気にし始め、付和雷同で多数に合わせるという動きを見せた。つまりそれが、「数が多いもの(作品)が勝ち」という、作品の内容の評価そっちのけの強固な価値観として定着してしまったのだ。 これは、それまでなんとなくあった、少なくとも議論の対象にはなっていた「傑作=駄作」の判断基準がポストモダン化によって無力化し、さらにはSNSの同調圧力によって個々人の「好き嫌い」の価値観にまで干渉するようになった結果であると言える。
僕はその「勝ち負け」の駆け引きの瞬間を目の当たりにしている。『宮河家の空腹』(2013)という作品はTVではなくUstreamで連続配信されたのだが、第1話の際のコメント欄がオンタイムで「是か? 非か?」と皆しばらく様子見をしていたのだ。やがて僕のアンチがどっと押し寄せ、どこまで傑作だったかはともかく特に瑕疵のない本作に「史上最悪の駄作」とまでの悪罵が押し寄せるに至った。 コメント欄が「是非」「勝ち負け」を即決する場となったのだ。
その「覇権主義」「勝ち負け主義」が去年、また猛威を振るった。『鬼滅の刃』(2019)である。 まさにここ数年の「覇権」を獲ったと言って過言ではない本作だが、遂に『劇場版 無限列車編』(2020)が長年「覇権」を握っていた『千と千尋の神隠し』(2001)を超え、歴代興行収入1位を更新したことで話題となった。 しかし、やはり誰もがこう思うのではないだろうか?
え、これが……??
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
堤幸彦とキャラクタードラマの美学(2)──メタミステリーとしての『ケイゾク』(前編) 成馬零一 テレビドラマクロニクル(1995→2010)〈リニューアル配信〉
2021-01-18 07:00
(ほぼ)毎週月曜日は、ドラマ評論家の成馬零一さんが、時代を象徴する3人のドラマ脚本家の作品たちを通じて、1990年代から現在までの日本社会の精神史を浮き彫りにしていく人気連載『テレビドラマクロニクル(1995→2010)』を改訂・リニューアル配信しています。『金田一少年の事件簿』で一躍ヒットメーカーに躍り出た堤幸彦が1999年に手がけた、テレビドラマ史に残る問題作『ケイゾク』。サンプリングとリミックスを旨とし、最終的に自己破壊でしかリアルを表現できないという、90年代の時代精神を体現した作品でもありました。
成馬零一 テレビドラマクロニクル(1995→2010)〈リニューアル配信〉堤幸彦とキャラクタードラマの美学(2)──メタミステリーとしての『ケイゾク』(前編)
1999年の『ケイゾク』
堤の映像は土9のみならず、佐藤東弥、大谷太郎といった日本テレビのディレクターたちに大きな影響を与え、その後の土9のドラマはもちろんのこと、日本テレビのドラマの映像を書き換えてしまったと言っていいだろう。しかし堤は現状に満足していなかった。
彼らにしたらある種、ショックだったと思うんですよ。ただ、僕自身はずっと土曜9時でやっても、何の広がりもなかったワケです。自分の位置がテレビ的にどうなのかっていうのもわかるし、いくら暴れん坊みたいにやっていても、結局はドラマを作るっていう、ベーシックな仕事の基本はなんら変わらないっていう、そういう意味で寂しくなってきたなと思っていた、ちょうどそういう時期に、渡りに船で『ケイゾク』の話をいただいたんです。なら、もう一回チャンスがあるだろうなぁって、それでやってみたんですね。(1)
堤が土9の仕事に限界を感じはじめていた頃、蒔田光治の仲介で、TBSの植田博樹と出会う。編成時代の植田は、TBSのドラマが持つ保守性にフラストレーションを抱えていて、なんとか新しいドラマを作れないかと考えていた。そんな時に堤が手がけた『金田一』を見て、これはTBSでは作れないドラマだと驚いたという。 しばらくして、植田はプロデューサーに復帰することとなり、1999年の1月からはじまるドラマを急遽、立ち上げなければならなくなる。その時にTBSでは作れない新しいドラマを作るため、堤幸彦とコンタクトを取る。
TBSのブランドイメージって僕的には非常に高かったんですよね。第2NHK的というか、絶対、自由に作れる世界じゃないなっていう気がなんとなくしていたワケです。ところが、そこにいた植田という男が、これが、僕が今まで見た中で一番の暴れん坊でね、スレスレの人だったんです。(2)
視聴率ではフジテレビや日本テレビに遅れをとっていたものの、当時のTBSにはNHKに次ぐ老舗というイメージが強かった。中でもテレビドラマ、特に金曜ドラマに関しては「ドラマのTBS」という圧倒的なブランドがあり、外部ディレクターの堤にとっては、プレッシャーの大きな仕事だったのだろう。 そんなTBSの社員ということもあり、植田に対しても、自分とは違う世界を生きるエリートだと感じ、どこまでドラマ作りに対して本気なのかと様子を窺っていた堤だったが、企画を進めていくうちに植田の情熱は本物だと感じ、やがて意気投合するようになっていく。そして、ドラマ史に残る問題作『ケイゾク』(TBS系)が生まれることになる。
▲『ケイゾク』
ミステリーに対する醒めた視点
『ケイゾク』は、東京大学法学部を首席で卒業した警部補・柴田純(中谷美紀)が迷宮入り(ケイゾク)となった事件を専門に捜査する部署・警視庁捜査一課弐係に配属されるところから始まる。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
【今夜21時から見逃し配信!】柳瀬博一 「『国道16号線』から日本を考える」
2021-01-16 12:00今夜21時より、東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院教授の柳瀬博一さんをお招きした遅いインターネット会議の完全版を見逃し配信します。
24時までの限定公開となりますので、ライブ配信を見逃した、またはもう一度見たいという方は、ぜひこの期間にご視聴ください!
柳瀬博一 「『国道16号線』から日本を考える」見逃し配信期間:1/16(土)21:00〜24:00
首都圏をぐるりと巡る、全長326キロの環状道路・国道16号線。この道がつなぐエリアは、3万年前から現代にいたるまで、日本の歴史に大きな役割を果たしてきました。各地に残る縄文・弥生・古墳時代の文化の痕跡に始まり、頼朝が武家政権樹立の礎とした鎌倉、江戸開拓に至るまで道灌や後北条氏、家康らが押さえた重要拠点の数々、明治期の富国強兵・殖産興業を支えた横浜・横須賀の港湾、そして戦後の米軍進駐を経て郊外カルチャーの発信地になった福生……。これらの発展
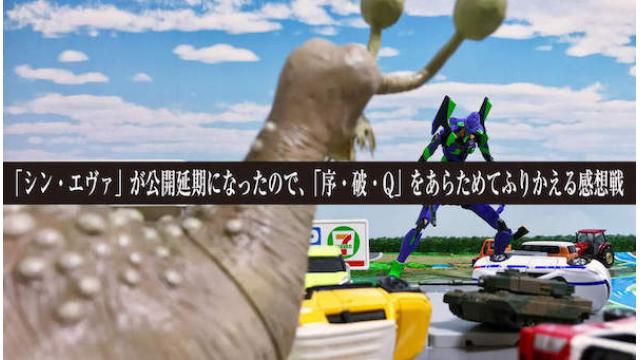

![読書のつづき[二〇二〇年八月]日本の夏、停滞の夏|大見崇晴](https://secure-dcdn.cdn.nimg.jp/blomaga/material/channel/article_thumbnail/ch413/1898861?1612487274)


![[新連載]インフォーマルマーケットから見る世界──七つの海をこえる非正規市場たち 序説:「インフォーマルマーケット」とは何か|佐藤翔](https://secure-dcdn.cdn.nimg.jp/blomaga/material/channel/article_thumbnail/ch413/1985949?1612138581)