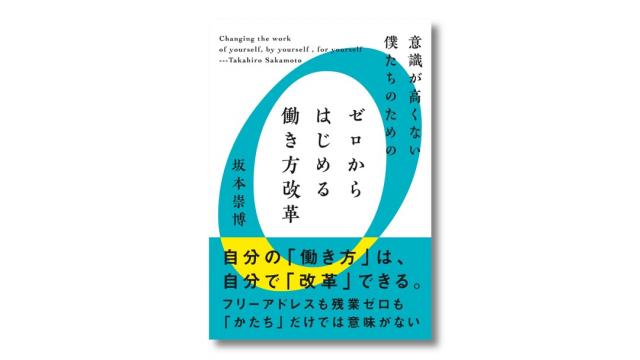-
【本日開催】民主主義をアップデートする シビックテックの可能性と課題|大西ラドクリフ貴士×隅屋輝佳×藤井宏一郎(リアル開催&生中継あります)
2021-11-16 07:00おはようございます、PLANETS編集部です。
(ほぼ)毎週火曜日の夜に開催中の「遅いインターネット会議」。今月も有楽町のコワーキングスペース・SAAIでのリアル開催を実施しています!
本日開催のテーマは「民主主義をアップデートする シビックテックの可能性と課題」です。
PLANETSチャンネルなど各スタンドでは生中継もありますが、気になる方はぜひ会場へ遊びに来てください。
11月16日(火)19:30〜民主主義をアップデートする シビックテックの可能性と課題|大西ラドクリフ貴士×隅屋輝佳×藤井宏一郎
今回の「遅いインターネット会議」では、シビックテックによる民主主義のアップデートの可能性について考えます。
ゲストは、リクルートを経て、国際情勢や歴史認識に関する議論を通じ国籍や人種を超えた相互理解を促すためのサービス作りや、SNSとは異なる対話プラットフォーム提供を行う大西ラドクリフ貴士 -
「横浜の地で外人に勝利する」ということは何を意味したのか──1890年代の日本野球|中野慧
2021-11-15 07:00
ライター・編集者の中野慧さんによる連載『文化系のための野球入門』の第16回「『横浜の地で外人に勝利する』ということは何を意味したのか──1890年代の日本野球」をお届けします。19世紀末、「鹿鳴館外交」時代から日清戦争での勝利を経て徐々にナショナリズムの機運が高まっていた時期、外来スポーツはどのように受け止められていたのか。「野球」とナショナリズムの結びつきから、「体育会系的態度」と「興行としての野球」誕生の源泉に迫ります。
中野慧 文化系のための野球入門第16回 「横浜の地で外人に勝利する」ということは何を意味したのか──1890年代の日本野球
2021年の東京五輪では、それまで当たり前のように受け止められてきた「スポーツ」というものの価値に大きく疑問符がつけられた。ひとつ象徴的な例として挙げられるのが、サッカー五輪代表の主将・吉田麻也の発言と、それに対する人々の反応だろう。五輪開催前の7月、東京を中心にコロナ患者の受け入れ増による医療逼迫がメディア上で盛んに報じられていた。そんな状況のなか、吉田は大会前最後の親善試合直後に「有観客での開催を再度検討してほしい」という趣旨のコメントを行った[1]。このコメントに対し、SNS上やニュースプラットフォームの一般ユーザーを中心に「アスリートのワガママだ」といった批判の声も多く上がった。 いわゆる「体育会系」に対する批判の声は、近年特に高まってきている。大きなきっかけは、2018年に起こった日本大学アメリカンフットボール部の選手による反則タックル事件だろう。日大の選手が、対戦相手の関西学院大学のキープレイヤーに対して後方から危険なタックルを行い負傷させた、というものである。「日大の指導者から選手に対して具体的な指示があったのではないか」ということが取り沙汰されたが、真相はいまだに明確になっていない[2]。 しかし、そもそも今の日本で言われるような「体育会系」という集団はどのようにして形成されてきたのだろうか。また、その体育会系に対して「批判」は行われてこなかったのか──。 こういった問題を考える上で、草創期の日本野球で起こった出来事は大きなヒントを与えてくれるように思う。そこで今回から、19世紀末から20世紀初頭の「世紀の変わり目」に、日本野球の揺籃の地となった一高で起きた3つの事件について論じてみたい。 重要な事件は下記の3つである。
①インブリー事件(1890年) ②横浜外人倶楽部戦(1896年) ③一高生・藤村操の自殺(1903年)
今回はまず、①と②について見ていきたい。
野球版生麦事件? インブリー事件からわかる一高生たちの背景
1870年代〜1880年代の日本の野球は、一高以外にもさまざまな場所で野球の同好会的な団体が発足していた。まず、後の札幌移転を念頭に現在の芝公園内に設置された開拓使仮学校(現在の北海道大学の前身)、波羅大学(現在の明治学院)、東京英和学校(現在の青山学院)、駒場農学校(現在の東京大学農学部などの前身)、立教大学などの学校をベースにした同好会が存在していた。さらには、アメリカで鉄道技術を学んだエンジニアであった平岡凞(ひらおか・ひろし)を中心に新橋鉄道局内で作られた有志団体・新橋アスレチック倶楽部、かつての徳川御三卿の一角・田安徳川家当主の徳川達孝(とくがわ・さとたか)が設立したヘラクレス倶楽部、都下の慶應義塾や東京高等商業学校(現在の一橋大学)などの野球好き学生が集まった連合チームである溜池倶楽部……といったクラブチームが次々に生まれた。 現代と大きく違うのは、どれも基本的に有志の自発的な結社だったという点だ。これは草創期のアメリカで生まれたクラブチームとも同じである。学校内部で制度化された「部活」というものはまだなく、「学校」はあくまでも、仲間が集まるきっかけとしてあった。 そのなかでも、明治学院の「白金倶楽部」はエール大学で野球をプレーした経験を持つアメリカ人教師マクネアの指導を受けて無類の強さを誇っていた。野球史のなかで「日本野球最初の覇者」として扱われがちな一高も、1890年時点までは日本野球界の頂点にいたわけではなかったのだ。 第13回で述べたように一高は、1889年に東京の向ケ岡(現在は東京大学農学部などが入る弥生キャンパスとなっている)に移転し、1890年には寄宿舎が完成した。そこでは次世代の日本を担う若者を育成するために「籠城主義」「校友会」という2つの思想・仕組みを軸にした学生文化が形成されつつあった。それまでの一高の学内スポーツではボートが人気と実力を誇っていたが、寄宿舎完成以降は野球部がしだいに人気を集めるようになった。校内ではノックが熱気を帯び、昼休みにはキャッチボールと試合がおこなわれ、それを見守る者たちが自然発生的に応援団の起源となる集団を形成していった[3]。 その明治学院・白金倶楽部と一高が、1890年5月に向ケ岡の一高グラウンドで相まみえた。しかし蓋を開けてみると6回時点で6−0と白金倶楽部が大量リード。そんな中、当時明治学院で教えていたアメリカ人宣教師ウィリアム・インブリーが教え子たちを応援しようと、試合開始から遅れて一高グラウンドにやってきた。最初は正門から入ろうとしたところ、守衛が英語を解さないため、いくら説明しても校内に入れてもらえない。そこでインブリーは、正門ではなくグラウンドそばの低い垣根をまたいでグラウンドに入っていった……。すると、一高を応援していた一高生たちがインブリーを見咎めて詰め寄り、激昂した学生のうちの一人がインブリーに重傷を負わせた[4]。これが「インブリー事件」である。 ここまで書いてきて、一体何が起こったのかが皆目、見当がつかないはずである。アメリカ人教師インブリーは、なぜ重傷を負わねばならなかったのだろうか。 まず単純に、そもそも一高チームが白金倶楽部に大差で負けており、応援していた一高生たちのあいだにフラストレーションが溜まっていた、ということがあるだろう。しかし彼らの抱えていたフラストレーションには、単純に「大差で負けていた」ということにとどまらない背景があった。 ちょうど1890年頃から一高の校是となったのが「籠城主義」だった。籠城主義は、校長の木下廣次が「汚濁に塗れた世間から青年たちを隔離する」必要性を感じたことによって生まれたものだが、その「世間の汚濁」というのは色事・賭事などに限らず、明治前半期の日本を覆った過剰な欧化主義から守る、という意味合いもあった。 1880年代の日本は、世に言う「鹿鳴館時代」であった。当時の日本の大きな課題のひとつは欧米列強との不平等条約の改正であり、当時の外務大臣であった井上馨は外交交渉を首尾よく進めるには日本人が西欧文化を受け入れている様子を外国人に伝えることが必要だと考え、西洋風の迎賓館「鹿鳴館」を、現在の千代田区内幸町付近に建設し、連日のように外国の高官や商人たちを招いて園遊会や舞踏会、夜会、バザーなどを催した。しかし庶民の生活向上をよそに宴会に明け暮れていること、過剰な欧化政策に対する批判が次第に高まるようになっていたのである。
▲鹿鳴館。Rijksmuseum, Public domain, via Wikimedia Commons(出典)
1880年代の日本では、それまでの「脱亜入欧」からしだいに、日本という国が持つ伝統的な価値を見直すナショナリズムの時代へと移行しつつあった。1890年はちょうど、前年に発布された日本初の近代憲法「大日本帝国憲法」のもとで帝国議会が初開催され、戦前の道徳の支柱となった「教育勅語」も宣下された年である。日本が近代国家としての枠組みの整備をようやく完了したタイミングでもあった。 そんな中、インブリーが正門を通るのではなく垣根を越えて入ってきたことも、一高生たちにとっては問題であった。なんといっても一高は「籠城主義」であり、校内は清浄の地、校外は汚濁の地である。したがって一高校内にもし部外者が入ろうというときには必ず「正門を通る」という儀礼を行わなければならない。そういった強烈な観念が一高生に浸透しているなかで、こともあろうに「アメリカ人」が「垣根を越えて入ってくる」というのは、彼らにとって許しがたいことであった。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
レゴブロックを花に、そして、ブロッコリーを木に。──「見立て」をつかって日常を豊かにする方法
2021-11-12 07:00おはようございます。
今日はWebマガジン「遅いインターネット」の最新記事と、併せて読んでほしいおすすめ記事をご紹介します。
先日公開されたのは、ミニチュア写真家・見立て作家の田中達也さんと、レゴ認定プロビルダーの三井淳平さんとの特別対談です。
食器や家具、日常のちょっとした道具が全然違うものに見えてしまう経験は、多くの人が共有できるものだと思います。そうした「見立て」の力をアートに落とし込むクリエイターの視点からは、世界はどのようにみえているのでしょうか。二つのクリエーションに通底するメカニズムと鑑賞者の抱く共通感覚から、人間が持つ普遍的な想像力の輪郭について語っていただきました。
今回の記事と併せて、こちらの記事も(もういちど)読んでみませんか?
コロナ禍を経て特に苦しい立場に置かれている業界のひとつが、音楽や演劇といったライブエンターテインメントの世界です。先々の公演予定が真っ白に -
意識が高くない、いち営業マンの帰宅術が働き方改革プロジェクトになるまで|坂本崇博
2021-11-11 07:00
働き方改革アドバイザー・坂本崇博さんの『意識が高くない僕たちのためのゼロからはじめる働き方改革』が、ついに本日、Amazon・全国書店等にて発売となりました。今日のメルマガでは、同書のプロローグを特別に公開します。現在の「働き方改革」の問題点とは何か。いち「コミュ障」のアニメオタクが、延べ10万人超の働き方改革支援を行うに至るまで、どんなことがあったのか。同書の核となる部分を実体験をもとに語っていただきます。
【PLANETS公式オンラインストアでも販売中!】20年以上にわたり社内における自分自身や周囲の働き方改革を推進し、さらに働き方改革プロジェクトアドバイザーとして毎年数十社、延べ10万人超の働き方改革を支援してきた著者 坂本 崇博がその経験をもとに「そもそも働き方改革とは何か?」を定義するとともに「真の働き方改革推進ノウハウ集」としてその推進手法やテクニックを体系化。組織として働き -
『梅切らぬバカ』── 隣家から向けられた視線|加藤るみ
2021-11-10 07:00
今朝のメルマガは、加藤るみさんの「映画館(シアター)の女神 3rd Stage」、第22回をお届けします。今回ご紹介するのは『梅切らぬバカ』です。文化庁主催の「ndjc:若手映画作家育成プロジェクト」で選出・製作された、和島香太郎監督作品。とある田舎の古民家で暮らし50歳を迎える自閉症の息子・忠さんと母親の珠子、ふたりに向けられた視線の変化からるみさんが思う、他者との共存のあり方とはどんなものなのでしょうか。
加藤るみの映画館(シアター)の女神 3rd Stage第22回 『梅切らぬバカ』── 隣家から向けられた視線|加藤るみ
おはようございます、加藤るみです。
先月、じいちゃんを見送りました。
じいちゃんは7月くらいから食欲がない、食べたものの味がしないと言っていて、最初はもしかしたらコロナに感染したんじゃないか? と疑い検査をしてもらったんですが、結果は陰性。 高齢だから単に食欲が落ちたといっても、味がしないのはなんでだろうかとずっと家族で話していました。 わたしはネットで原因を探したりしたけど、わかるはずもなく……。 このご時世、検査をするにも時間がかかって、改めてコロナが憎たらしくてしょうがなかったです。 そして、原因が何かわからないまま最初に病院に行ってから1ヶ月ほどが経ち、最終的に悪性リンパ腫という血液のガンだということがわかりました。 「まさか、じいちゃんが」と思いました。 高齢とはいえ、最近まで外仕事をしていたタフな人だったし、じいちゃんの母親は110歳くらいまで生きて町から長寿の表彰をされた人でもあったので、わたしたち家族はじいちゃんも長生きするもんだろうと勝手に思っていました。 それから2、3ヶ月で容態が波のように上下するようになり、じいちゃんが亡くなる1日前に「もうあと1週間くらいかもしれません」という知らせがあって、特別に面会ができることに。 けれど、わたしと姉は大阪に住んでいるので、とりあえず2日後に会いに行くよう予定を調整しました。 間に合ってくれと願いながら。 でも、間に合いませんでした。 まさか、こんな突然だとは思いもしなかった。 その日、わたしは緊急事態宣言が明けて久々に奈良公園の近くへ夕食を食べに行っていた帰りで、駐車場でわんわん泣きました。 本当に子供みたいにわんわん泣きじゃくっていたので、さぞ鹿もびっくりしたことでしょう。 思い返すと悲しいけど笑ってしまいます。 じいちゃんは病院を転々としたけど、最後はばあちゃんが入っている介護施設に隣接された病院に入院していたので、最期はばあちゃんの手を握って亡くなったそう。 じいちゃんはおとなしくて、いつも気が強いばあちゃんに一方的に言い包められていて(笑)、わたしから見て仲が良い夫婦という感じではなかったけど、なんだかんだじいちゃんはばあちゃんのことを想っていて、最期までじいちゃんはカッコいいなと思いました。 じいちゃんが大好きでした。 小さな頃から、近くに住んでいたのもあったけど、小学生の頃は土日はほぼじいちゃんちに泊まりに行っていたので、親と同然、いや親よりも心安らぐ存在でした。 長いこと一緒にいる家族には、多少なりとも嫌なところや直してほしいところが出てきたり、「むかつく」と思うこともあるけれど、じいちゃんにかぎっては嫌なとこがひとつも見当たらなくて、とにかく優しい人でした。 寡黙だけど、たまにおちゃらけると笑顔がとてもチャーミングな人。 葬儀に来てくれた人がじいちゃんのことを「優しいおじいちゃんだったね」と、たくさんあったかい言葉をかけてくれました。じいちゃんの人柄を現すかのように。 私の知らないところで、じいちゃんがたくさんたくさん愛されていたことに涙が出ました。 じいちゃんが骨になる姿を見るのは嫌だと思っていたけど、遺骨を見たら気持ちが整理できたような気もした。 そういえば、はなちゃ(犬)のときもそうだった。 それに、「さすが丈夫なじいちゃんだわ」と、ビックリするくらいしっかりした骨で、なんだか誇らしくなりました。 改めて、自慢のじいちゃんだと思えました。 葬儀を終えて、小さな頃に「じいちゃんが死んだら嫌だな」と考えていたことが現実になってしまって、大人になって歳を取るということはどうしようもなく虚しくて切なくて、自分でもよくわからない気持ちだけど、今までの思い出を抱きしめていくしかないんだろうなと思います。 たくさん想っていたはずなのに、わたしは欲張りだから、もっともっとああしておけば、こうしておけばって考えてしまう。 昨年ははなちゃ、今年はじいちゃん。 大好きなふたり(ひとりと一匹)がいなくなったダメージはでかいけど、ふたりとも長生きして頑張ったよねと思うようにします。 そう思うしかないよね。 まだまだわたしは生きていかなくちゃいけないから、前を向いて明日も明後日もふんばります。
さて、かなり前置きが長くなってしまいましたが、この一ヶ月、じいちゃんの死があって、家族について考える時間が増えました。 自分についてもそうだけど、自分を考えるたびに一緒に浮かんでくるのは家族の存在。
今回紹介する映画は、家族がテーマのお話です。 母親と自閉症を抱える息子の日常を描いたヒューマンドラマ『梅切らぬバカ』という作品です。
若手映画作家を育てる文化庁主催の「ndjc:若手映画作家育成プロジェクト」において選出・製作された和島香太郎監督作。 監督は過去にドキュメンタリー映画の編集に携わり、障がい者の住まい問題に接してきた経験に着想を得て、この作品を執筆したそうです。
54年ぶりに主演を務める加賀まりこさんと、ドランクドラゴンの塚地武雅さんが親子役で共演。 都内の古民家で占い師をしている母親・山田珠子と自閉症を抱える息子・忠さんが、地域コミュニティとの不和や社会の偏見といった問題と向き合いながら、生きていくさまを描いています。
珠子は息子の忠さんと二人暮らし。 毎朝決まった時間に起床して、朝食をとり、決まった時間に家を出る。 忠さんが50回目の誕生日を迎えたとき、珠子は気づく。「このまま共倒れになっちゃうのかねえ?」と。 自立の第一歩として忠さんはグループホームに入居するも、些細な争いからグループホームを抜け出してしまう……。
この作品の空気感。 なんと言葉に表したらいいのやら……。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
【本日開催】民藝からケアへ|鞍田崇(リアル開催&生中継あります)
2021-11-09 07:00おはようございます、PLANETS編集部です。
(ほぼ)毎週火曜日の夜に開催中の「遅いインターネット会議」。今月も有楽町のコワーキングスペース・SAAIでのリアル開催を実施しています!
本日開催のテーマは「民藝からケアへ」です。
PLANETSチャンネルなど各スタンドでは生中継もありますが、気になる方はぜひ会場へ遊びに来てください。
11月9日(火)19:30〜民藝からケアへ|鞍田崇
名もなき人々の手で作られ、日々の暮らしで使われる日用品にこそ、鑑賞のための美術品にはない「美しさ」と「いとおしさ」が宿ることを教えてくれる「民藝」。その発想は、誰かの生きづらさを日常の所作の中で共有し、世界との関係を結び直していくための現代的な「ケア」の体験とも通底していると、哲学者の鞍田崇さんは言います。
すべてが性急につながりすぎてしまった情報環境の下で、両者が培ってきた思索と実践を結びあわせながら、私 -
よしもとばなな──無自覚な娘|三宅香帆
2021-11-08 07:00
今朝のメルマガは、書評家の三宅香帆さんによる連載「母と娘の物語」をお届けします。今回取り上げる作家は小説家・吉本ばななです。数々の印象的な「食」を描いてきた吉本ばななの諸作品を、現在連載中のエッセイと重ね合わせ、「母」と「食」をめぐる関係性を論じます。
三宅香帆 母と娘の物語第三章 よしもとばなな──無自覚な娘
「どうして君とものを食うと、こんなにおいしいのかな。」 私は笑って、 「食欲と性欲が同時に満たされるからじゃない?」 と言った。 「違う、違う、違う。」 大笑いしながら雄一が言った。 「きっと、家族だからだよ。」 (「満月―キッチン2」(よしもとばなな『キッチン』新潮文庫p135)
吉本ばなな[1]は、食欲旺盛な作家である。 それは単なる食いしん坊という意味でなく、小説やエッセイを含めた吉本ばなな作品において食事の場面が多いことを指す。たとえばデビュー作『キッチン』の最初の一文は「私がこの世でいちばん好きな場所は台所だと思う」だった。あるいは『ハゴロモ』のほたるはインスタントラーメンを、『TSUGUMI』のまりあは父のくれたせんべいを、『哀しい予感』の弥生はカレーを食べていた。 吉本ばなな作品は、過剰なまでに食事の場面を反復する。 吉本ばななの小説とエッセイを交互に眺めると、そこには彼女の作品でなぜ食事が繰り返されるのか、その理由が浮かび上がってくる。そこにはある意味、無自覚に描かれた、母と娘の物語が背後に存在していた。
1.ごはんをつくらない母──『High and dry (はつ恋)』
現在吉本は、WEBサービスnoteで、エッセイ〈どくだみちゃん と ふしばな〉シリーズ[2]を連載している。 インターネットで発表される吉本ばななの文章は──ある意味、無防備に──食事への執着を語る。しかしそれを読み解くと、吉本作品はなぜ食欲旺盛なのか、そのヒントとなる描写がひそかに綴られていた。そこには彼女の母をめぐる葛藤が潜んでいたのである。
私には(そういう意味では)お母さんはいなかった。 私の具合が悪いときに、何が食べたい? と聞いてくれる人はいなかった。 (吉本ばなな『お別れの色 どくだみちゃんとふじばな3』p33、幻冬舎、2018年)
「何を食べたい?」と聞く人。これが母の定義である、とエッセイの中で吉本ばななは言う。 彼女の父母の没した4年後に始まるnoteで、自分の母はごはんを作らない人だった、と吉本は語る。ここで思い出されるのは、2004年に刊行された吉本の小説『High and dry (はつ恋)』(以下『はつ恋』)[3]だ。 『はつ恋』の主人公・夕子の母は、たまに「上の空モード」になる。注目したいのは、その症状を夕子が挙げる際、必ず最初に「ごはんを作らない」点を挙げることだ。
たとえばうちのお母さんは、本に熱中したり、何かですごく落ち込んだりすると、ごはんを作るのも電気をつけるのもそうじをするのもみんな忘れてしまう。(『はつ恋』p68)
もう私はかなり大人になってきたので、自分で何か作って食べたり、勝手に風呂をわかして入ったり、自分の選んだ時間に寝たり起きたりできるから全然かまわなかったのだが、幼い頃にそれが起こると、かなりきついことだった。(p69)
多分、村上さんのお母さんはうちのお母さんと違って、人であるまえにまず、プロのお母さんだろう。 だから、晩御飯作り忘れたり、十四時間も寝っぱなしだったり、子供の送り迎えをすっかり忘れてしまっていたりすることは絶対にない。(p70)
そして夕子が語る理想の母親像は、2017年のnoteで吉本自身が語った「私の具合が悪いときに、何が食べたい? と聞いてくれる人」という理想の母親像とほぼ一致する。
いつでも同じ時間にごはんを作ってくれる人がいたら、どんなにいいだろう。「時差ぼけのお父さんが起きてきたときにみんなでいっせいに夜中の二時にファミリーレストランに行く」そういう種類の楽しさは大好きだけれど、でも、いつでも振り向いたら私を見てくれている、いつでも家に、私のためにいてくれて世話をすることがいちばん大事だというお母さんがいたらどんなにいいだろう。 (『はつ恋』p70-71。下線部は筆者による)
そもそも『はつ恋』は、思春期の女の子の初恋を主題とした小説である。そのような青春小説において、ふいに作者自身の葛藤の対象である「ごはんをつくらない母」の影が登場することは注目に値するだろう。もちろん『はつ恋』が作家の私小説などと言いたいわけではない。むしろここには作家自身が意識しているかどうか分からない、もしかすると無意識の範疇で描かれる、「ごはんをつくらない母」の反復を見ることができるということだ。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
暮らしにもっと植物を、都市に土の手触りを
2021-11-05 07:00おはようございます。
今日はWebマガジン「遅いインターネット」の最新記事と、併せて読んでほしいおすすめ記事をご紹介します。
先日公開されたのは、編集者・ライターの小池真幸さんが、「界隈」や「業界」にとらわれず、領域を横断して活動する人びとを紹介する連載「横断者たち」、第5回の再構成版です。
今回は、プランツディレクターの鎌田美希子さんに話を伺いました。「土から離れて暮らしてしまっている」都市において、私たちはいかにして植物との関係性を取り結んでいけばよいのか。「人と植物の距離をもっと近づける」ための方法を考えます。
今回の記事と併せて、こちらの記事も(もういちど)読んでみませんか?
滋賀県のとある街で、推定築100年の町家に住む菊池昌枝さん。この連載ではひょんなことから町家に住むことになった菊池さんが、「古いもの」とともに生きる、一風変わった日々のくらしを綴ります。初回は、菊池さんが町 -
アイデアを行動に移すための「行動移行術」──(意識が高くない僕たちのための)ゼロからはじめる働き方改革 第20回〈リニューアル配信〉
2021-11-04 07:00
大手文具メーカー・コクヨに勤めながら「働き方改革アドバイザー」として活躍する坂本崇博さんの好評連載「(意識が高くない僕たちのための)ゼロからはじめる働き方改革」を大幅に加筆再構成してリニューアル配信しています。今回は、働き方改革のために思いついたアイデアを実践するまでにどんな壁があるのか、そしてその壁を乗り越えるにはどうすればいいのかについて分析します。「エフェクチュエーション」の理論を引きながら、坂本さんの実体験に則した独自のノウハウでその実践過程を論じていただきました。
【新刊情報:PLANETS公式オンラインストアにて先行予約受付開始!】 本連載をベースにした『意識が高くない僕たちのためのゼロからはじめる働き方改革』の発売が決定しました!
20年以上にわたり社内における自分自身や周囲の働き方改革を推進し、さらに働き方改革プロジェクトアドバイザーとして毎年数十社、延べ10万人超の働き方改革を支援してきた著者 坂本 崇博がその経験をもとに「そもそも働き方改革とは何か?」を定義するとともに「真の働き方改革推進ノウハウ集」としてその推進手法やテクニックを体系化。 組織として働き方改革を推進する立場の方がもちろん、今の仕事にモヤモヤを感じていたり、もっとイキイキ働きたいと考えているすべての人に読んでもらいたい一冊です。
さらにPLANETS公式オンラインストアでは、先行予約特典として本日よりオンラインイベント「働き方改革1000本ノック」への参加権付き先行予約受付を開始しました。お申し込みはこちらから!
(意識が高くない僕たちのための)ゼロからはじめる働き方改革〈リニューアル配信〉第20回 アイデアを行動に移すための「行動移行術」
あらすじ
今回は、働き方イノベーターとしての行動特性を身につけるための習慣である「行動移行術」について紹介していきます。 これまで解説したテクニックを駆使して現状を変えるアイデアを具体的に浮かべる(幻想する)ことができたなら、後は実践あるのみです。しかし、なかなかそれが難しいものです。 イノベーターはこうした「行動に移すことの困難さ(壁)」をどう打破しているのかという問いについて考える上で、「そもそも、行動に移す上でどんな困難さ(壁)があるのか?」を整理しておきたいと思います。
人はアイデアが行動に移せないと次第に燃えなくなる
私の働き方改革の実践において不可欠な最後の力は、幻想を実行に移す「行動力」です。 しかし多くの場合、自分が過去得てきた経験や最近知った情報をもとに「こうすればいいのでは?」とアイデアを浮かべるまではできても、それを実行に移すことが困難と言われています。 会社に入りたてで改革アイデアが浮かびやすい若者ほど、その困難さに直面しがちです。 私がそうであったように、会社に入ってすぐの頃ほど、様々な非効率さが目に留まり、「自分が何かを変えてみせる」と目を輝かせるケースは多いと思います。私はこの状態を「可燃性が高い」と表現しています。ちょっとしたきっかけで燃え上がり、熱くなる状態です。 しかしながら、彼らにはそのアイデアや想いを「行動に移す術」が不足しているが故に、悶々とした日々を送ることになってしまうことも少なくありません。 こうした状態に陥ると、飲み屋で同僚に「俺の考えた最強のアイデア」を延々と語ったり、「なんで会社はこれをやってくれないんだ」「会社は早く働き方改革をしてくれよ」と愚痴ったりして、やさぐれていきます。この状態を「難燃性症候群」と表現します。すなわち何らかの実現を妨げる困難さに直面して熱い想いが湿気ってしまい、働き方改革に対する熱が若干冷めている状態です。 そしてこの状況がますます悪化すると、人は「不燃性」になってしまいます。もう自分では働き方を変えようと考えることもなく、それどころか周囲の可燃性が高い人材の発言や行動に水を差して、難燃性症候群に陥らせてしまいます。 このように、アイデアが浮かんでも行動に移せないという事態は、人の熱意を冷まし、湿らせていってしまいます。
アイデアを行動に移せる仕組み(型)に加えて、「技」も必要
もちろん、人の価値観は多様であるべきですし、組織があればそこには可燃性から不燃性までいろいろな状態の人が混在していて当然です。全員が必ず私の働き方改革を意識し実践しなければならないということはありません。 ただし、私が着目したい問題は「湿気の伝播」です。たとえ何人かが壁に直面して難燃性・不燃性の状態になったとしても、それぞれがその個性を「人に押し付ける」ことをしなければ組織の多様性は維持されます。しかし、前述の通り、難燃性症候群や不燃性症候群の人は、可燃性の人にも影響を与え、その発言や行動を湿らせてしまうことが多いです。これでは、多様性は損なわれ、次第に「燃えない組織」として画一化していってしまいます。 こうした状況を防ぐためにも、組織は一人ひとりが何らかのアイデアを浮かべた時に行動に移せるよう後押ししてあげる型づくりが重要になります。 アイデア提案採用制度や、直属の上司を超えて課題意識や提案を受け付ける「目安箱」のような仕組みなどがその一例です。 一方、個人としても、せっかく浮かんだアイデアや幻想なのですからきちんと実現できたほうが楽しいはずです。そのためにはアイデアを行動に移せる技(行動特性)を身につけることが不可欠です。その力とはすなわち、「行動に移す上で直面する壁」を乗り越えるためのテクニックです。
アイデアを行動に移す上で直面する3つの壁
では、その壁とはどういうものでしょうか。私はこの3つであると考えます。
1 自分にはそのアイデアを実行できる十分な資源(人・モノ・金・情報)がない
2 そのアイデアを実行したときに得られるメリットに確信が持てない
3 成果を実現するまでの明確な実行計画(プラン)が立てられない
これらのどれか一つにでも該当すると、アイデアは浮かんだが実行には二の足を踏むか、実行できないとあきらめてしまうという状況になってしまうのです。 たとえば、以前私は「一人ひとりが私の働き方改革に意識を向けてもらえるように、学校教育の制度から見直すべきだ」と思い浮かんだことがあります。 なぜなら、組織に所属する人の多くが、「イチニンマエ(みんなができることができる)」であろうとして、組織の伝統や慣例に沿って活動するという行動特性は、小学校から高校までの画一的かつテストの点数至上主義の教育システムに原因の一つがあると考えたからです。 誰かが設定したテスト(ミッション)で高い点数をとることが「イチニンマエ」として評価されるという経験を長年積むことで、人の脳には「提示されたミッションをクリアする」ことが自分の評価を決めると錯覚してしまうのかもしれません。そうした「イチニンマエ主義」で組織に所属すると「何かミッションを提示してもらえば、それをこなす」ことに注力することが当たり前になってしまいます。結果として、「ヒトリマエ」になって自分で自分の働き方を決めたり、短期的なミッションになってもいない働き方改革に意識と労力を割こうとする行為は「非合理的」と判断されてしまうのではないかと考えたのです。 そうした想いがある中で、欧米など他国では、日本の授業とは大きく異なり「答えがわかった人は手を挙げて」ではなく「わからない人は質問して」「自分なりに思ったことを発言して」という授業スタイルがあることを知って、そうした教育スタイルを日本でも普及できればと思いついたわけです。 しかし、私はいちサラリーマンであり、教育者でもなければ文科省の職員でもありません。 教育スタイルを変えたいと思っても、使える資源や協力してくれる人は手元には一つも見当たりませんでした。また、もし本当に教育スタイルを変えることができたとしても、新卒一括採用や終身雇用などの「イチニンマエを生み出す」ための様々な仕組みが存在している中で、いったいどれほどの効果があるのか確証が持てませんでした。さらには、「もし自分が100億円もっていたら」と仮定して幻想をしてみたものの、最終的なゴールまでの道筋は浮かばず、計画が立てられませんでした。 見事に行動に移す上ことを妨げる「3つの壁」すべてに直面してしまったわけです。 結果として、異業種交流会の飲み会などで「日本の教育は変わるべきだ!」と管をまくくらいしかできないまま「難燃性症候群」に陥りかけていました。 また、会社の中においても、マネジャーになってできることが増えた分、やりたいことが大きくなるほどに同じ壁に直面するようになりました。 たとえば、私の働き方改革を世の中に伝えるべく、「社員教育」というビジネスに進出したいと思ったのですが、さすがにいきなりそんな組織は作れず、どこまでどのように進めれば事業として成果があげられるのか明確な計画も立てられないという状況に直面していました。
[ここまでのポイント] 1 アイデアを浮かべ、幻想を描いても、実行できなければストレスになる。 2 その結果、人は次第に難燃性・不燃性となり、組織全体に湿気を伝播させて、冷めた組織として画一化してしまう。3 そうしたアイデアを実行を移すことができなくなる原因として、3つの壁(実行する上での資源がない、メリット・成果が見えない、ゴールまでの計画が立てられない)が存在する。4 この壁の一つにでも直面すると、アイデアが浮かんでも実行に移しづらくなる。
さて、ここまでアイデアを行動に移す上では、3つの壁があり、それによって行動がとれないと解説しました。 しかし、実はこの壁は一種の固定概念であり、その壁を乗り越えないと進めないという錯覚に陥っているのかもしれません。 それに気づかされたのが、以前に触れた「エフェクチュエーション」という研究書との出会いでした。 ここからはこのエフェクチュエーションという理論についてより詳しく解説しながら、3つの壁の存在そのものを疑い、乗り越えるための視点を整理していきたいと思います。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
「あだち充劇場」の集大成としての『クロスゲーム』| 碇本学
2021-11-02 07:00
ライターの碇本学さんが、あだち充を通じて戦後日本の〈成熟〉の問題を掘り下げる連載「ユートピアの終焉──あだち充と戦後日本の青春」。今回から、あだち充の現状最後の少年誌連載作品である『クロスゲーム』を読み解きます。消化不良のまま終了した前作『KATSU!』とは一転、新世代の編集者とのタッグで「逆『タッチ』」をコンセプトに始まった王道の恋愛野球漫画の成立背景とその作品史的な立ち位置を解説します。
碇本学 ユートピアの終焉──あだち充と戦後日本社会の青春第20回 ①「あだち充劇場」の集大成としての『クロスゲーム』
「喪失」を描き続けるあだち充
「クロスゲーム」は死者と向き合うことがひとつのテーマになってますけど、それはやっぱり自分の年齢的なものだと思う。兄貴も亡くなりましたから、いろんなことを自分なりに整理して描きました。 54歳から6年間、60歳手前まで連載したのか。『週刊少年サンデー』の最後の作品として、満足してますよ。ラストもいい感じだったなと。ああいうラストを選ぶことができた。これで週刊連載はもういいと思えました。燃え尽きましたね。〔参考文献1〕
どうせこの作品で、週刊連載は最後だと思ってたから、開き直って「あだち充劇場」をやるしかないと思ってました。ここまで読者に見捨てられなかった漫画家なんだから、もう何やってもいいんじゃないかなと。それが意外と、今までと違う漫画になったんです。〔参考文献1〕
前作『KATSU!』が2005年12号で最終回を迎え、わずか10号しか期間をあけずに、2005年22・23合併号から2010年12号まで約6年間連載をしたのが『クロスゲーム』だった。 インタビューであだち充が答えているように今作が現在のところではあだち充作品における最後の週刊連載作品となっている。
以前にも紹介したように、本連載ではあだち充のデビュー以降の作品史を四期に分けたことがある。下記にその第三期についての記述を引用する。
第三期は『H2』(1992〜1999年)、『じんべえ』(1992〜1997年)、『冒険少年』(1998〜2005年)、『いつも美空』(2000〜2001年)、『KATSU!』(2001〜2005年)、『クロスゲーム』(2005〜2010年)。連載誌が「少年サンデー」と「ビッグコミックオリジナル」の二誌であり、『クロスゲーム』が現状では最後の「少年サンデー」で連載した野球漫画となっている。
前回も取り上げたように、『クロスゲーム』の担当編集者・市原武法は小学館に入社し、「少年サンデー」に配置されてからずっとあだち充の担当をやりたいと言っていた。当時の「週刊少年サンデー」編集長だった三上信一はその意気を買い、それまでのあだち充の担当者たちのバトンを引き渡すように、「あだち先生を頼むぞ」という気持ちも含めて市原を『KATSU!』の終盤で担当編集者に指名。市原が企画の立ち上げからあだち充作品に関わるのは、この『クロスゲーム』が初めてとなった。 市原がこの時点であだちの担当編集者となって『クロスゲーム』に関わり、その後に「ゲッサン」を立ち上げなければ、今現在まであだち充が漫画連載をしていた可能性はかなり低かったのではないか。あだち充を少年漫画家として再生させる上で、市原が担当編集者になったのは、かなりギリギリであったものの、なんとか間に合ったという感じがする。 そして、市原の熱意をきっかけに、開き直ってあだち自身が「あだち充劇場」をやろうとしたことで『クロスゲーム』はそれまでのあだち充作品の集大成となった。そして、兄の死の影響があり、プロ編へ移行できずに最終巻で強引にまとめて終わらすことになった『KATSU!』では描ききれなかったものを、しっかりと引き継ぎながら描ききった作品となった。
「クロスゲーム」は最初から短い巻数で、ちゃんとした話をやろうと話してました。僕の担当では、木暮がもともと「あだち充ファン」だったけど、市原ほどのファンはいないかな。市原は僕の漫画をすべて憶えてる。特に「タッチ」は何から何まで憶えてる。 野球の話をやろうということになって、最初の1巻分は、主人公たちの子ども時代をちゃんと描こうと決めました。そこをちゃんと描いておけば、あとでなんとでもなるだろうと思った。〔参考文献1〕
「逆『タッチ』を描いてほしいんです」という口説き文句を連載開始前の打ち合わせの際に市原があだちに言った。 「面白いな、それで行こう」とあだちが了承したことでこの『クロスゲーム』は始まることになった。 『タッチ』といえば、1980年代を代表するラブコメ&野球漫画の金字塔であり、あだち充の代表作である。多くの人が『タッチ』と聞いて思い浮かぶのは、双子の上杉兄弟と幼馴染の朝倉南の三角関係だろう。そして、上杉兄弟の弟の和也が夢半ばで死んでしまい、彼の夢だった「朝倉南を甲子園に連れていく」という目標を兄の達也が引き継ぐかたちになって野球を始めたというものだと思われる。 市原が「逆『タッチ』」と言った時点で、亡くなるのは主人公の側ではなくヒロインの側だというイメージがあだちにもすぐ浮かんだのだろう。そう言った市原もヒロインとなるべき登場人物のひとりを殺してくださいと言っているようなものだった。 『タッチ』という作品があまりにも国民的な漫画だったからこそ可能になった「逆」バージョンとしての『クロスゲーム』は、ずっと第一線で戦い続けた少年漫画家のあだち充だからこそ描ける、いわば「あだち充劇場」を使ったデータベース消費的な作品でもあった。
あだち充作品では主要キャラクターだけでなく、物語の途中で主要人物に関係のあるキャラクターがある日突然亡くなってしまうことが多い。そのことで「人が死にすぎ」「主要人物の誰かが死ぬのが定番なんですか?」と言われてしまうのだが、物語の展開上仕方ないこともあるし、上杉和也のように連載前から死ぬことだけは決められていたキャラクターもいる。 人はいつか死ぬという現実を、あだち充はただ漫画で描いているだけだと考えるほうが自然でもある。また、あだちが好きだと公言している落語や時代劇では、人が亡くなるのは不自然ではないということもあるかもしれない。
あだち充は三男一女の末っ子であるが、3歳半上のあだち勉は戦後すぐの生まれだった。長兄は戦中生まれである。 あだち兄弟のような戦後生まれの「団塊の世代」は、人口ベースで見ればもっとも人口の多い層である。 筆者の父もあだち勉と同学年で、下に弟がいてふたり兄弟なのだが、幼い頃に墓参りに一緒に行った際になにも刻まれていない小さな墓石があり、父たちの生まれなかった姉だったと祖母から聞かされたことがある。戦後すぐの状況で栄養不足でありながらも働きすぎていたせいで流産したのだと祖母は教えてくれた。このように戦争体験者だった彼らの両親は戦後の復興と共に多くの子を作ったが、戦後すぐの貧しい期間においては生まれなかった子どもも多くいたし、大人になるまで成長できずになくなってしまう子どもたちもたくさんいた。 あだち充たち戦後生まれの世代は戦後の復興と共に成長していったが、同時に人が亡くなるのは今よりも当たり前で自然で身近なものとしてあったはずだ。 経済復興と核家族化が広がっていくと人が生まれるのも亡くなるのも病院というケースが当たり前のように多くなっていった(現在では緩和ケアなども増えており、かつてのように家で家族に看取られることや、大事な家族を看取ることを選ぶ人も増えてきているが)。
人間が生きていく中で抱えてしまうそんな「喪失」を当たり前のこととして描いているのがあだち充作品である。そして、人はいつか死んでしまうというリアリズムを漫画に持ち込んでいるとも言えるのではないだろうか。 バトル漫画などでは人が死ぬのは当たり前のものかもしれないが、そうでなくても日常生活の中で人がふいにいなくなってしまうという現実を、あだちは少年漫画でずっと描いてきたとも言えるだろう。 あだち充が主体性と責任を持つ大人という成熟へ向かっていく物語を描き続けてきたことと、物語の中でふいに人が亡くなってしまうことは繋がっているのではないだろうか。彼の漫画は夢を魅せる(夢に留まらせる)ためではなく、夢から醒ませて現実と向き合うための物語だからである。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。