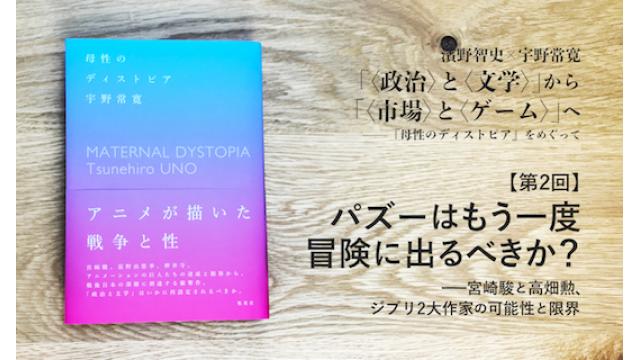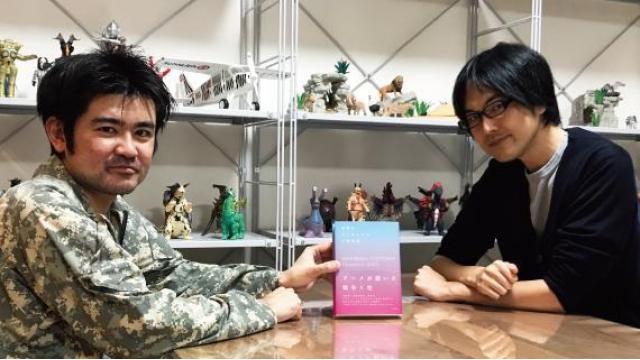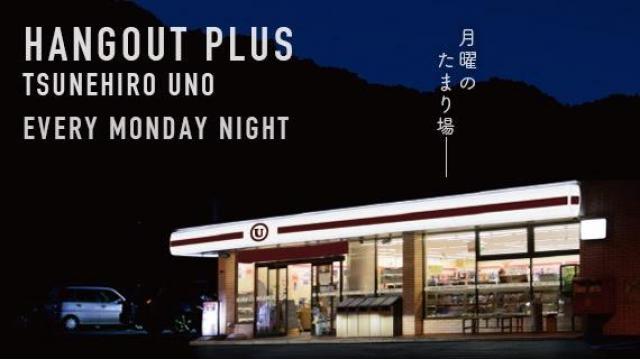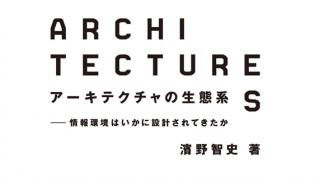-
イデとニュータイプを「いま」考える――富野由悠季と押井守 濱野智史×宇野常寛「〈政治〉と〈文学〉」から「〈市場〉と〈ゲーム〉」へ――『母性のディストピア』をめぐって(3)
2017-11-03 07:00
10月26日に発売された、宇野常寛の待望の新著『母性のディストピア』。その内容を題材にして、長年の盟友である濱野智史氏と共に日本のこれまでとこれからについて語ります。富野由悠季が『伝説巨神イデオン』を通じて予言的に描き出した状況と、押井守の映像アート『めざめの箱舟』の意外な可能性について取り上げます。(構成:斎藤 岬) ※その他の回はこちら。(第1回、第2回、第3回、第4回、第5回)
『伝説巨神イデオン』にみる富野由悠季の想像力の臨界
▲『伝説巨神イデオン』
濱野 今回、『母性のディストピア』で何に一番驚いたかって、宇野さんがまさかこれほど『伝説巨神イデオン』を高く評価していたとはということなんですよ。 僕の個人史的には、『伝説巨神イデオン』を観るより先に、まず『新世紀エヴァンゲリオン』から受けたファースト・インパクトがあって。そもそも僕は『エヴァ』を観た時、『機動戦士ガンダム』の再放送も未視聴で、全く富野的想像力も知らなかった。それでTV版の『新世紀エヴァンゲリオン』を観て、当時その後すぐに出版された『庵野秀明 スキゾ・エヴァンゲリオン』(大泉実成)『庵野秀明 パラノ・エヴァンゲリオン』(竹熊健太郎)をむさぼるように読んだわけなんですよ。 で、やっぱあの本を読むと、「『ガンダム』ってそんなに影響されるもんなのか」「『伝説巨神イデオン』とか『デビルマン』ってそんなにやばいの?」と思うわけですよ。そこでTSUTAYAに行ってビデオテープ(!)を借りたり、ブックオフで古本マンガ漁ったり、一応、それなりにオタク的教養を身につけようとする基礎作業はした。まあ、僕の場合は「初心者の館」レベルで止まってしまっているのですが。
▲庵野秀明 『スキゾ・エヴァンゲリオン』(編・大泉実成)『庵野秀明 パラノ・エヴァンゲリオン』(編・竹熊健太郎)
ただ、僕の富野さんの評価は、もちろんすばらしいクリエイターだとは思うけれども、宮崎駿や高畑勲に比べたら作品にブレがありすぎるという印象なんですね。宇野さん含め、富野ファンの皆さんには大変申し訳ないんですが……。 確かに「ファーストガンダム」と呼ばれる最初の『機動戦士ガンダム』はすごいと思った。あ、ちなみにちゃんとこれはTSUTAYAでTV版を全話借りて観ましたよ。大学のメディアセンターでビデオテープをダビングして保存した記憶すらある(笑)。 ただ、僕はファーストガンダムをSF作品というより、登場人物の自意識や人間関係をめぐるドロドロのリアリズムと、独特のセリフ回しが面白すぎると受け取ったタイプで。実はモビルスーツとかニュータイプといったSF設定周りはあまりピンと来なかった。『母性のディストピア』でもずっと指摘されている通り、ニュータイプっていうアイディアがある種「取ってつけたもの」感があるじゃないですか。映画版で若干設定が盛られていたけれど、「はっきり言ってこの話、ニュータイプ関係ある?」っていうのが正直な印象だった。ララァを奪いあってなんかニュータイプ同士が戦いながら論争してるけど、テレパシー以上のものはあるのか。まああとは普通に予知能力的にアムロが強いのは分かるけど、あんなのシューティングゲームとかに究極に没頭すれば目覚めるゲーマー的反射神経としか思えなかった。だから正直、「ニュータイプが人類を変える」って、何を言いいたいのかわからなかった。それが率直な感想だったんですね。
▲『機動戦士ガンダム』
ただ、その『機動戦士ガンダム』では取ってつけたオカルト要素に過ぎないと感じたものが、その後すぐに続いて『伝説巨神イデオン』を借りて観たら「これはヤバい!」と。正直、問題発言スレスレですけど、「こりゃオウムとか出て来るわけだわ、この国」と思いましたよね、当時10代の自分は。「これが商品化されるって、狂ってるなこの国」と思って、なんか逆に元気が出た(笑)。 いやしかし、『伝説巨神イデオン』の内容って、口で説明するのはちょっと難しい。遺跡を発掘したら異星人に攻撃され、その遺跡が実は巨大ロボットで、そのせいで異星人に追われて遺跡に乗り込んだまま逃げ出すはめになり……僕は90年代後半に映画版の接触編・発動編を借りて観て、ちょっともう記憶も曖昧なんですが、最後は無限エネルギー「イデ」が発動して人類も異星人も全滅する展開ははっきり覚えています。あれを観たら、なるほど「人類補完計画」とかも言い出すわけだと思いましたが、しかしこれはめちゃくちゃすぎる(笑)。 ちなみに今回、インタビューの前に『イデオン』を見返そうと思ったのですが、Amazon Prime Videoだと打ち切りになったテレビシリーズしか見れなくて、それでもイデオンがやばいのはよくわかった。そりゃこんなのTVで流したら打ち切りになるよな、と。だからこそあれにトラウマ的影響を受けるクリエイターがいるのは非常によくわかる。
宇野 富野由悠季という作家の何がすごかったかというと、要するにその想像力だったと思うんです。たとえばニュータイプ。あれは明らかに当時の超能力ブームの影響なのだけど、あの空間を超越して遠く離れたところにいる人間の意識と意識が直接衝突していくというあの発想は、いまとなってはもう完全にインターネットのことにしか見えない。 そして『伝説巨神イデオン』に出てくる「イデ」というのは、言ってみればニュータイプ的なコミュニケーションを可能にするシステムですよね。富野由悠季が偉大だったのは、それをまさに「ディストピア」として提示したこと。システムが発達して、人間と人間が中間物を挟むことなく直接ぶつかると本当にとんでもないことが起こるというのは、まさに今この世の中で起こっていることですよね。富野は80年代前半に「そんなことが起こると人類が滅ぶ」ときわめて正確に予言しているんだけど、残念ながらその富野由悠季自身が、それを克服することができなかった。世代的なものもあるのか、当時のヒッピー崩れのオカルトブーム、要するにニューエイジから離陸できなかった。
濱野 まさに『伝説巨神イデオン』で描かれている「イデ」というのは、いわゆる人工知能的なものに近くて、いまの人類が普通にもっている言語的なコミュニケーション手段、それは例えば和平交渉でも相互理解でもいいんですけれども、そういった凡庸な政治学的なり社会学的な想像力をはるかに超えた何かを提示してはいるんですよね。それが最後全てをぶっ壊して終わるから、まあむちゃくちゃなんだけれど、僕は今回の宇野さんの本を読みながら、じゃあ逆に「イデ」がうまく機能して、世界がより豊かで多様性を認め合うことができた世界線があったとしたら、それってどんなものなんだろうってことは、すごく考えるべきだと切実に思ったんですよ。 「イデオン」っていう名前自体が「理想」(イデア)そのものだけど、実はいま、これって21世紀の人類がリアルに問われている「理念」の問題でもあるわけじゃないですか。だから宇野さんが『伝説巨神イデオン』を出してくるとは思わなかったから結構衝撃だったんですが、非常に腑に落ちるところがあった。『イデオン』は正直自分の中で、20年くらいそれこそ黒歴史じゃないけど記憶の奥底に封印されていた作品だったので、そこはグッときましたね。
宇野 『イデオン』はイデという僕たちの世界観を根底から覆すようなシステムを手にしたのに、人間は愚民であるから、それを使いこなせずに全員死にました、という話ですよね。イデというのはシステムの問題、つまり濱野智史的に言うとアーキテクチャの問題であって、ニュータイプは主体の問題なんですよね。だから、こそ富野由悠季はイデを描くんだったら、それと対となるニュータイプをもっとガチで描くべきだった。いや、描いているんだけど、結局うまくいかなかった。 『母性のディストピア』でも散々書いたように、富野由悠季はニュータイプ的な主体の問題が存在するというところまでは行ける。問題設定自体はすごく正しかったし、優れていたと思う。
濱野 ふむ。しかしニュータイプ的なものはオカルトにすぐ近接してしまうから、描くのは本当に難しいと思うんですよね。それは富野さんだけじゃなくて、みんなそうだと思うんですが……。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
パズーはもう一度冒険に出るべきか?——宮崎駿と高畑勲、ジブリ2大作家の可能性と限界 濱野智史×宇野常寛「〈政治〉と〈文学〉」から「〈市場〉と〈ゲーム〉」へ——『母性のディストピア』をめぐって(2)
2017-11-02 07:00
10月26日に発売された、宇野常寛の待望の新著『母性のディストピア』。その内容を題材にして、長年の盟友である濱野智史氏と共に日本のこれまでとこれからについて語ります。第2回は宮崎駿と、『母性のディストピア』では扱いきれなかった高畑勲の話題を中心に、ジブリ2大作家の可能性と限界について考察します。(構成:斎藤 岬)※その他の回はこちら。(第1回、第2回、第3回、第4回、第5回)
異界を覗き込む宮崎作品の可能性
濱野 前回も触れた通り、僕は『母性のディストピア』で取り上げた3人の作家で言うと完全に宮崎駿派だったんですよ。 特に『天空の城ラピュタ』が最高に好きで。あれは宮崎駿も「ベタベタの冒険活劇でいいじゃないか」と開き直って作っている気がする。『母性のディストピア』で宇野さんは「宮崎駿は『母性的なもの』がないと飛べなくなった」と指摘していましたが、『ラピュタ』はそういう意味でも本当に象徴的ですよね。つまり、パズーはシータがいないと飛べない。確かに僕は子供の頃から思っていたんですよ。「守るべき女の子がいなきゃ、飛ぶ意味なんてない。そして自分にはシータが降りてくることも、ラピュタを見つけることもないな」と(笑)。リスクを追って人類未踏の世界に辿り着くこそ冒険だったわけですが、もはや冒険/探検すべき領域が地球上に残っていないことは、20世紀後半に生まれた人間として、子供でももう分かるじゃないですか。だから、あのベタベタの冒険譚の道具立ての揃い具合が、最高にノスタルジックな夢をみせてくれるし、「バルス!」祭りが未だに盛り上がるのも、そんなものは完全に「嘘」だということをこれみよがしに見せてくれるカタルシスがあるからだと思うんですよね、あのラストシーンに。
▲『天空の城ラピュタ』
ちなみに僕が一番好きなのは、シータとパズーが見張り台の中にいて、ドーラたちがその会話を伝声管越しに聞いているところからのシーン。その後、軍に見つかって攻撃から逃れながら、仲間とはぐれて2人きりでラピュタに行く。本当に男の子のご都合主義的ロマンスでうざったいなあと思うんだけれど、「本当にラピュタがおそろしい島なら、ムスカみたいな連中に渡しちゃいけないんだ」というパズーのセリフをドーラたちが「盗聴」していることによって、ムスカたちとの戦いという冒険の正当性も担保されていて、実に巧みだし、それこそ自分にも「こんな冒険あったらいいなあ」とも思うシーンなんですよ(笑)。 『天空の城ラピュタ』って、最初に空から女の子が降ってくるところからも明らかなように、男の子のご都合主義的ロマンスの集合体でしかない。だから、ラストの後の2人がどうなるかは描けない。描きたくないでしょう。僕も見たくない。あの二人が、シータの出身地であるゴンドアの谷で仮に結婚したって絶対に幸せになれない(笑)。
宇野 絶対にならないよね。シータはパズーを生活保守に調教することしか考えないだろうから。そもそも『天空の城ラピュタ』はやはり諦めの物語でしょう? もう男の子は飛べない、冒険は諦めて畑を耕そう、という結末ですからね。
濱野 飛ぶためにはムスカと同じようにロストテクノロジーを求めるしかない。でも結婚後に飛ぶことを諦められなくて、牧畜とか開墾とかに飽きて冒険に出ようとするパズーの絵があまりにも容易に想像できる。というか、断言しますけど、自分がパズーなら3年で絶対シータと別れますね(笑)。なんの断言だよって感じですけど。
宇野 地上に戻ってからのパズーは「俺は本当は飛行機に乗りたいんだ」と思っているのに、無理やり農業をやらされたり、そのことで夫婦生活もうまくいかなくなったり、そういう人生が待っているわけだよ。
濱野 「あそこから本当の『バルス(崩壊)』が始まるのに」といつも思う。だから宮崎駿っていうのはそういう存在だと薄々わかってるんだけれど、でもアニメだからそれでいいじゃんって僕は思っていたんですよね。今回、宇野さんの著作を読んで、いまさらながら、その開き直りから目を覚まされた感じがあった。
宇野 ああ、家庭を「バルス」ね(笑)。だから、宮崎駿はその未来を乗り越えるためには、やはり飛ぶんじゃなくて「潜る」しかなかった。 具体的には『となりのトトロ』で彼が切り拓いた世界の延長線上にもっといろいろやれたことがあったんじゃないかってことなんですよね。
▲『となりのトトロ』
宮崎駿が書いた『となりのトトロ』のエンディングテーマの歌詞に「子供のときにだけ あなたに訪れる」というのがあるんだけど、日常の中の異界を覗き込む力を、どうやって大人の世界に拡張していくか。本当はこれが宮崎駿が一番向き合っていくべき問題だったと思うのだけど、『となりのトトロ』の先に進めなかったと思うんですよね。 あれは「飛ぶ」だけではなくて、日常の中に異界を発見して、そこに「潜る」ことを発見している。ここには『天空の城ラピュタ』で宮崎駿が未練たっぷりに断念したものとは別の可能性があったはずなんだよ。 やっぱり、『魔女の宅急便』からはまた元の路線に、つまり「飛ぶ」ことに回帰している。あの作品の背景にあるのはバブル期の都市の気分だったわけで、それは要するにあの宮崎駿ですらバブルの狂騒に若干とはいえ肯定性を見出そうとしていた一瞬があった、ということなのだけど。つまり『となりのトトロ』の日本は失われてしまった。だけど、もしかしたら今の都市化された日本にも、人間を飛ばせる力があるのかもしれない、『天空の城ラピュタ』に接続してロストテクノロジーの力で飛ばなくても、つまり失われた近代的な、男性的なロマンティシズムに賭けなくても精神的に豊かに過ごしていく方法があるのかもしれない、というのが『魔女の宅急便』だったんだけど、結局、宮崎駿はあれを自分自身の、つまりあの作品でいうとトンボの物語としては描けずにあくまで理想化された少女、つまりキキの物語としてしか描けなかった。『母性のディストピア』で取り上げた「少女は飛べる/男たちは飛べない」問題ですね。男性というか、自分自身が飛ぶ物語を描こうとすると、自虐たっぷりに豚のコスプレをする(『紅の豚』)か、ナルシスティックにキムタクと同一化(『ハウルの動く城』)するしかなくなっていく。でもそれって結局自己憐憫のようなものの先には進めなかったように思う。
▲『魔女の宅急便』
だから僕は本当は『となりのトトロ』の延長線で何らかの新しい可能性が見い出せていればよかったのにって思っている。 これは昔、大塚英志さんが書いていたんだけど『となりのトトロ』もその原型の『パンダコパンダ』も、何が異様かって普通だったら最後に異世界の住人と子どもは別れて終わる。異界の住人たちはいつの間にか見えなくなって、少女はちょっと大人になる。『この世界の片隅に』のように妖怪を見る力、異界を覗く力を失ったかわりに、ちょっと大人になって代わりに性的なものに目覚めていく、という通過儀礼的な物語になるのが普通。でも『パンダコパンダ』も『となりのトトロ』はそうならないんだよね。あの話の中でトトロとサツキ、メイの別れは描かれない。
▲『パンダコパンダ』
濱野 一切描かれていないですね。そのかわりにエンドロールのアニメでは母親が帰ってきて終わる。そこもまた非常にうまい。
宇野 あの異様さを大塚英志は、近代主義者の立場から批判的に書いているんだけど、僕は逆の感想を持っているんですよ。あれは、サツキとメイがトトロたちと別れないからいい。 あの時期までの宮崎駿は、あのまま異界を見続けることによって、自身からは既に失なわれてしまっているその力を、なんとかして取り戻したいと思っていたところがあったんだと思う。だからこそ糸井重里の「忘れものを、届けに来ました」というコピーが採用されていたわけでさ。あそこで子どもが異界の住人と別れることで成長するという教科書的な成熟を、彼は信じていなかったはず。 だから、そういった「もう一つの宮崎駿」を見たかった気もする。宮崎駿的には『となりのトトロ』のアップデートが『千と千尋の神隠し』なんだろうけど、その進化が本当に正しかったのかについては、もっと議論されていいと思う。『千と千尋の神隠し』は「出会い」と「別れ」がある、とてもオーソドックスな成長譚になっていて、そこが逆に物足りないんだよね。
▲『千と千尋の神隠し』
濱野 なるほど……。トトロは僕も当然傑作だと思っていましたが、その想像力を伸ばせ、というところまでは僕の想像力が至っていなかった(笑)。トトロは凄すぎるんですよね……。 ちなみに僕も『千と千尋の神隠し』は全然評価もしていないし、個人的にも全くピンと来る部分のなかった作品ですね。ハクというキャラも好きになれない。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
押井守・庵野秀明・こうの史代——アトム/ゴジラの命題の継承者たち 濱野智史×宇野常寛「〈政治〉と〈文学〉」から「〈市場〉と〈ゲーム〉」へ——『母性のディストピア』をめぐって(1)
2017-11-01 07:00
10月26日に発売された、宇野常寛の待望の新著『母性のディストピア』。その内容を題材にして、長年の盟友である濱野智史氏と共に日本のこれまでとこれからについて語ります。第一回は『シン・ゴジラ』や『この世界の片隅に』といった作品を参照しながら、〈政治〉と〈文学〉が断絶してしまった情況について考えます。(構成:斎藤 岬)※その他の回はこちら。(第1回、第2回、第3回、第4回、第5回)
なぜ今『母性のディストピア』を世に問うのか
▲『母性のディストピア』
濱野 今日は『母性のディストピア』がなぜ今、このタイミングで出たのかをあらためて聞くところから始めたいと思います。それはもちろん本の中にも書かれていますが、今回、僕が対談相手に選ばれたのは、その聞き手役として最適だからではないかと思っています。 僕の『アーキテクチャの生態系』と宇野さんの『ゼロ年代の想像力』は、ちょうど同じ2008年に出ているんですよね。でも、宇野さんと僕の批評家としての立場は本当に当時から全く違っていて、僕はこの本で扱われているようなサブカル批評にまったく興味がない。ずっと「アーキテクチャ」、つまりサブカルのようなコンテンツそれ自体より、それが消費される環境のほうに関心を払ってきた。だから本当はここにいる2人は「水と油」のような関係のはずなんだけど、だからこそこの10年、同じ日本社会を別の角度から観察しあうことができた、そんな関係でもある。
▲『アーキテクチャの生態系』(濱野智史)、『ゼロ年代の想像力』(宇野常寛)
そこで今日は、お互いデビューから約10年という文脈も含めて総括できればいいなと思っています。宇野さんがなぜこのタイミングでこういう本を書いて、そこから何を読み解くべきなのか、本書の中と外の話を両方していければと思います。
ではまず本書の中についてから行きましょう。率直な僕の感想を言うと、まず「序にかえて」には完全に同意で、何も付け加えることがないですね。いま、この国の現実には、本当に語る価値のあるものは存在しない。日本、そして日本の批評言語は、完全に世界から取り残されている、これは完全に同意します。さらに宇野さんは、安倍晋三やSEALDsについて語るよりも、ナウシカやシャアについて語るほう有意義だとすら断言する。これはかなりの極言で、僕もハッとさせられたのですが、人によっては「宇野は現実逃避に走った」と思い込んで、その先を読まずに終わるかもしれないと想像してしまいました。この序文は宇野さん的にもかなり勇気がいる内容だったのではないですか。
宇野 そう、間違いなく「序にかえて」だけ読んで、罵詈雑言を浴びせてくる人がいると思う。それも、匿名のTwitterでグチグチと他人の悪口を書くことや、実効性や具体的な成果を度外視して自分探し的な市民運動に「参加」することが現実へのコミットだと勘違いしている人たちから、間違いなく標的にされると思う。 でも、それはまあ、言ってみれば僕の仕掛けた大きな罠で、続く「第1部」は要するにインターネットのアーキテクチャに支援されて現実を単純化する人たち――具体的には今挙げたような極右と極左の困った人たち――のやっていることこそが、実は言葉の最悪な意味での「文学」「サブカルチャー」にすぎないこと、そしてそれを戦後日本が延々と反復してきたことの分析からはじまる。つまり、この本を読まずに罵倒するであろう自称「政治的な人たち」を、戦後社会の病理として分析するところからはじまる。彼らの「読まない」「悪口をいうために読む」行為や、その結果出てくるであろう「オタクがアニメに現実逃避している」という批判こそが、僕の分析の正しさを証明するような構造になっている。
濱野 まさに第6部のタイトルが「『政治と文学』の再設定」で、現実の日本社会への分析と提言に戻る。実際に宇野さんがそこで展開しているのは、再設定は無理だから、〈市場〉と〈ゲーム〉でいいじゃないか、ということですよね。もはや〈政治〉と〈文学〉がつながるなんて、いまは誰も思っていない。つまり〈市場〉と〈ゲーム〉の時代に適応した新しい主体を考えた方がいい。戦後のサブカルチャーの遺産を手がかりに日本からGoogleとは違う新しいモデルを出せたらいいよね、といった話に着地している。ここはあとでもっと詳しく話し合えればと思いますが。
宇野 正確にはもう「日本から」でなくてもいいと思っていて、たとえば富野由悠季の遺伝子を受け継いだアジアやアフリカの作家や企業がそれをやる、でも全然構わないし、その方が夢があるとすら思っています。 この国の人たちは、まだ〈政治〉と〈文学〉を接続して成熟した市民社会を形成することだけが唯一の道筋だと思い込んで行動している人が多すぎると思うんですよ。でも本当は〈政治〉と〈文学〉の問題自体が、既に〈市場〉と〈ゲーム〉に置き換わっていて、この変化があまりに急激なので全世界が戸惑っている。にもかかわらず、日本だけが2周半くらい遅れた議論をしている。 その状況からどう現代に対応しようかと考えたときに、まずは西海岸に追いつこうと号令をかけるのは僕の仕事ではないと思うんですよ。まずはそれがないと始まらないのだけど、どちらかというと僕はかつての日本車がそうであったようにアメリカン・スタンダードを二次創作的にハックするほうに興味がある。だから戦後文化の奇形児としての日本の戦後アニメーションを総括して、そこで育まれた思想、美学、世界観から現代の「〈市場〉と〈ゲーム〉」の問題を考えたのが第6部と「結びにかえて」なんですよ。
濱野 まさにそこが今回の宇野さんの著作の独自なポジションを形成していると思いました。日本人は結果的に、21世紀にも入って戦後も70年以上経つというのに、いわゆるマッカーサーに言われた「永遠の12歳」の幼稚さの状態に留まってしまっている、もちろん戦後、いかに「対米ケツ舐め外交」的状態から決別し、大人として自立したリベラル民主主義国家になろうとしてきた人々がいたか。そこにいかに膨大なロマンと、挫折と屈折の物語が折り重ねられてきたか。それは分かる。でも、その「政治と文学」を結びつける回路で人々を駆動しようとするのは、もはやどうしようもなく困難な現実がある。 これは前から思っていたのですが、大学で「インターネット・メディア論」的なことを教える時に痛感するのは、インターネットって本当にアメリカの「表現の自由」という建国以来掲げてきた「正義の物語」――建国の父たちから受け継いだ理念――とあまりにも自然に結びついて生まれてきたアーキテクチャなんですよね。個人は誰もが表現する権利がある。何人もそれを奪ってはならない。そこにすっと、自然とインターネットやパーソナル・コンピューターといったものが出てくる下地があるわけですよ。 でも、こういうハッカー文化的な背景を大学で話していても、なんだか本当に虚空に向けて話しているような気持ちになってくる。もう民度が低いとかどうとか、そういうレベルじゃないんですよね。そして僕は教室で「ポカーン」とする若者たちに向かって、もはや語るべき「政治と文学」の共通言語がないと感じる。ただ共通しているのは、みんなiPhoneかスマートフォンは持っているという現実だけ。だからもう最近は、「iPhoneはみんな持ってるよね、スティーブ・ジョブズって知ってる? 『1984』って知ってる?」とYouTubeを見せるところから授業を始めて、いかに西海岸的なものに自分たちの日常性が覆い尽くされているか……みたいな話をするんですが、正直自分としても厳しいんですよ。「こんなの中高レベルの基礎教養として抑えておいてくれよ!いったい中高の『情報』の授業は何を教えてるんだよ!」と怒りすら覚える。 はっきりいってこんなことも知らずにただスマホでTwitterとLINEとソシャゲだけ使っている日本の(若者に限らないですが)現状を見ているとですね……僕はまさに「インターネットの奇形児」としての日本のゼロ年代のネットサービス群に可能性を見て、『アーキテクチャの生態系』を書いたのですが、最近はかなりゲンナリしているのが正直なところです。
宇野 そうですね。かといってじゃあ、今の日本の社会のことなんて知らないよ、と言ってしまうのは無責任だし、なにより僕は感情的にちょっとそれは難しい。やっぱりね、僕は出自的に「自分はグローバルな市場のプレイヤー、つまり世界市民だから国民国家なんて旧いローカルな回路の問題なんてどうだっていい。日本がイヤなら出ていくだけなんで」なんて言えないですよ。だから第6部では現代の日本のことにもしっかり紙幅を割いています。 今回の総選挙はいみじくもそれを体現してしまったような気がするけれど、日本の政治はこの30年間、時間が止まったままでいる。転向前の小沢一郎や小泉純一郎がプレイヤーだった頃と同じように、テレビポピュリズムによる55年体制との対決、あるいはその延命が主題になり続けている。平成の「改革」というのは要するに、この国をグローバル化と情報化に対応させるための改革というプロジェクトだったのだけど、それは完全に失敗して、今となっては保守にも革新にもほとんど改革勢力は残っていない。残っていた少数の勢力も小池百合子に騙されて彼女の自爆に巻き込まれ、ほとんど求心力を失ってしまったわけでしょう? この「平成」という改革の時代の決定的な敗北には当然のことだけれど、実に複雑な背景があってたくさんの要素が絡み合っている。ただ、僕はもっとも決定的だったのは情報環境というかメディアの問題だったと考えているわけです。実際に、平成の改革勢力は自分たちが武器に選んだテレビポピュリズムに振り回されて自滅していったわけだし、現在の二極化にはインターネットが絶大な悪影響をもたらしてしまっている。この現状に対する処方箋として、戦後サブカルチャーの「失われた可能性」の批判的発展を提案して、その延長線で「市場とゲーム」の時代の主体の問題に接続していく、という構成ですね。第6部以降が長いのはそこまで詰め込んだからで、それでもまだ書きたいことがあって連載中の『汎イメージ論 中間のものたちと秩序なきピースのゆくえ』に続くという。
押井守の「政治と文学」
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
濱野智史『S, X, S, WX』―『アーキテクチャの生態系Ⅱ』をめざして 第1章 東方見聞録 #1-1 NRT発: 3/6~3/7~3/6: on United【不定期配信】
2017-06-13 07:00
情報環境研究者の濱野智史さんの新連載『S, X, S, WX』―『アーキテクチャの生態系Ⅱ』をめざして が始まります。来たるべき時代の情報社会/現代社会を読み解くための試論を展開しようとする濱野さん。第1章では、Googleを訪ねるために西海岸へと向かいます。
『S, X, S, WX』
―『アーキテクチャの生態系Ⅱ』をめざして
第1章 東方見聞録
#1-1 NRT発: 3/6~3/7~3/6: on United
2017年3月6日、私は太平洋の上にいた。ユナイテッド航空、NRT17:55発 SFO10:10着の便だ。そのとき私は洋上にてある夢を見ていた。だが、それは眠る時にみる夢のことではない。夢よりも深い覚醒のなか、私がこれから本連載を通じて、いや人生を通じて現実のものとしたい、夢である。
その内容は、かつて筆者が宇野常寛との共著『希望論』(NHKブックス、2012年)と小熊英二編著『平成史』(河出書房新社、2012年)に寄稿した小論「情報化:日本社会は情報化の夢を見るか」に書きつけたことである。その要約は後者から引用すれば次のようなものとなる:
日本の情報化は、インフラ層の普及・整備という点では成功したが、アプリケーション層(特に経済/政治領域)においては、さしたる変化ももたらしていない(中略)。それは、変化を望まない既存勢力にとっては「成功」であろう。しかし日本社会全体にとっては、少なくともグローバルな規模でポスト工業社会への移行は進んでいることは明らかである以上、「失敗」であろう。せいぜい成功しているといえるのは、インフラの価格破壊を実現し、百科事典や音楽やアニメを無料でダウンロード可能にするという、デフレ消費を推し進めたくらいのものである。
こうした見立ては、「日本の情報化はカスだった」という印象を与えかねないかもしれない。しかしこれはあながち間違いではない。前節の冒頭でも見たように、結局のところ情報化は、情報収集や消費行動といった「消費」の領域に影響を強く及ぼしている傾向が強い。イノベーションを生み出す、政策をつくる、といった「生産」の領域では、まだまだ情報化ないしはネットワーク・メディアはさしたる影響を及ぼしているとは言いがたい。比喩的にいいかえれば、インターネットはいまだ「夜」の世界のメディアなのだ。社会の実権を握り、動かしている政治や大企業の「昼」の世界は、いまだにマスメディアとハイアラーキー(階層型組織)によって動いている。日経新聞を読んで組織内のうわさ話に聞き耳を立てる。それがいまだに日本社会の中核を縛っている。
これはあくまでデータの裏付けを欠いた想像にすぎないが、インターネット(特に匿名掲示板)がしばしばオタクたちのしがない遊戯空間だと思われていたのにも、それなりの構造的背景があるのかもしれない。実社会ではまともにコミュニケーションのできない、正規雇用にもついていないからこそ時間の有り余った、引きこもり気味のオタクが、匿名空間で息巻くという姿が、戯画的にこれまで抱かれてきた。(中略)
しかしこれは少し引いた目線で見れば、平成期において、それまでの昭和的枠組み(大企業での正規雇用といったメンバーシップ)が温存され、そこから「こぼれ落ちた人々」(貴戸理恵論文)たちが、「生きづらさ」の解消と承認欲求を求めて、インターネット空間を夜な夜なさまよっている、という図式ではないのか。あるいは自分たちの怒りや不満が既存の政治勢力やメディアには通っていない不満を抱える人々ではないだろうか。彼/彼女らは、昭和期から強固に残存する「昼」の世界の諸制度なり組織なりにぶつかり、それが変えられるという希望を失っている。だからこそ、誰もが肩書きを外して自由に発言し自由に暴れまわることのできるインターネット空間に夜な夜な出没するしかない。つまりは「昼」の世界への失望と無気力が、「夜」の世界での熱量に転換させられるほかないのである。はなはだ客観性は欠いているけれども、もし平成期における日本のインターネットがどうしようもなく「ダメ」で「厄介」なものに見えるとしたら、そうした下部構造が背景にあるのではないか。
しかし、もし仮にそうなのだとしても、私達はそろそろ情報化の空間を夜の領域にとどめておくのをやめる時がきている。そこが「夜」の領域だというのならば、私達はアメリカ社会の借り物ではない、しごくまっとうで正しい「夢」を見なければならない。本書に収められた各論文は、インターネットを使って私達が何をすればいいのか、何の制度改革に向かって声を集め、それをどこに届ければいいのかを、これ以上はないというほどに明らかにしている。社会保障、教育、労働政策に悩む者たちが、ネットで声を集め、知恵を出しあい、団結しあって、それを何らかの政治勢力に伝え、有効な「票集団」として結集すること。インターネットという自由で双方向なメディアがあれば、既存の政治を縛ってきた「地方」や「組織・団体」の枠を超えて、そうしたコミュニケーションと団結が可能なはずだ。それは胸踊るような「革命」の夢とは違うかもしれないけれども、現にいま、私達の社会が共有すべき夢であるように思われる。
筆者「情報化:日本社会は情報化の夢を見るか」前掲書
私はなぜ西海岸へ向かうのか。それは「現にいま、私達の社会が共有すべき夢である」と断言するためであり、かつ、いまや日本社会だけではなく、国際社会全体が共有すべき夢となったからだ。その理由はのちに述べる。まずは、なぜ私が2017年3月上旬、アメリカ西海岸へフライトしたのか。その背景と経緯から述べることにしよう。
*
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…
・入会月以降の記事を読むことができるようになります。
・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
HANGOUT PLUSレポート 宇野常寛ソロトークSPECIAL(2017年2月27日放送分)【毎週月曜配信】
2017-03-06 07:00
毎週月曜夜にニコニコ生放送で放送中の、宇野常寛がナビゲーターをつとめる「HANGOUT PLUS」。2017年2月27日の放送は、月に一度の宇野常寛ソロトークSPECIALをお送りしました。前半は2月24日に発売された村上春樹の新作長編『騎士団長殺し』のネタバレ全開レビュー、後半ではシークレットゲストとして濱野智史さんをお迎えし、対談「〈沼地化した世界〉で沈黙しないために」に続く議論を展開しました。(構成:村谷由香里)
※このテキストは2017年2月27日放送の「HANGOUT PLUS」の内容のダイジェストです。
村上春樹の新作『騎士団長殺し』レビュー
オープニングトークは、2月24日に発売されたばかりの村上春樹の最新作『騎士団長殺し』のレビューです。
宇野さんは春樹作品の変遷を、「〈デタッチメント〉から〈コミットメント〉へ」という主題で整理します。初期の村上春樹は、「やれやれ」という独白に象徴される〈デタッチメント〉の姿勢――あらゆる価値観から距離をおく、自己完結的なナルシシズムを特徴的な作風としていましたが、1995年の地下鉄サリン事件と、それに取材した『アンダーグラウンド』(1997年)以降は、主体的に世界と関わる〈コミットメント〉の立場へと転向します。そして、オウム真理教をモチーフにした長編『1Q84』(2009-2010年)は、その集大成となるはずの作品でしたが、第3部(BOOK3)になるとカルト教団との対決というテーマは後退し、主人公たちの邂逅や父親との和解が描かれて物語は収束。〈コミットメント〉の問題は消化不良のまま終わりました。
とはいえ、宇野さんは今作には期待していたといいます。過去の春樹作品では、世界と接続する〈回路〉や〈蝶番〉の役割は女性に与えられていたが、それが短編集『女のいない男たち』(2014年)では、より他者性の強い男性に置き換えられていた。そこに新しい主題の萌芽を見ていました。
しかし、本作『騎士団長殺し』は、従来の春樹的な主人公像を延命するためだけの小説になっていると批判します。行方不明の少女の捜索を老人に依頼された主人公が、幼少期に亡くした妹に似た少女を救うことで自信を取り戻し、別れていた妻との復縁に成功するという筋ですが、そこから主人公の〈成熟〉を読み取ることはできない。〈最初から与えられていたものの回復〉という意味で、『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』(2013年)と同様、熟年世代の「自分探し」の物語にすぎず、作者ほど自己愛の強くない人間はついて行けないといいます。
さらに、本作において重要なのは、実は主人公と少女や妻の関係ではなく、依頼者の熟年男性・免色渉との関係だったといいます。主人公の分身であり同時に他者でもある同性との交流によって、世界に対する想像力を開く、いわばBL的な主題にこそ作品のポテンシャルがあったのではないかと指摘しました。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…
・入会月以降の記事を読むことができるようになります。
・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
【緊急対談】濱野智史×宇野常寛「〈沼地化した世界〉で沈黙しないために」
2017-02-24 07:00
元・アイドルプロデューサーにして社会学者の濱野智史さんと宇野常寛が、マーティン・スコセッシ監督の『沈黙 -サイレンス- 』を題材に、ポスト・トゥルースにおける〈沈黙〉の超克について議論します。〈沼地〉と化した世界で、我々は何を語るべきなのか?
『沈黙』の何が沈黙を破らせたのか
宇野 このたび濱野智史さんはマーティン・スコセッシ監督の映画『沈黙 -サイレンス- 』を観たことをきっかけに、約1年半に及ぶ沈黙を破る決意をしたということで、僕も連絡をもらって非常に驚いたんだけど。なぜそういう考えに至ったのか説明からお願いできますか。
濱野 確かに『沈黙』は、沈黙を破るきっかけの1つになった作品ですが、同時に沈黙したくなるような作品で………………………。
『前田敦子はキリストを超えた』という、クリスチャンの方々に喧嘩を売っているような、それでいて中身や心意気だけはガチのキリスト教信者丸出しみたいな本を出しておいて……本当は「超えた」ではなく「≒(ニアリーイコール)」くらいにしたかったのですが……しかしそれでは売れないので、すみません! という謝罪も含めて、諸々懺悔しながら話し始めるしかないんですけれども。
僕自身はキリスト教徒ではないんですが、文学(テキスト)として、あるいは思想(の原点/原典)としての旧約・新約聖書は、素人なりに読んでいるつもりでいます。そういう立場から『沈黙』を観ると、あまりにも「沼」が深い。
いきなり大きな話をすると、このご時世、みんな〈沈黙〉したほうがいいわけですよ。Twitterもニコニコ動画も2ちゃんねるも、全てのソーシャルメディアを使うピープルは、スコセッシの『沈黙』を観ていますぐ喋るのをやめろと。言葉の斧を沼に投げ捨てろと。映画では(踏み絵を)「踏め!」という意味で「トランプ(Tramp)」という言葉が出てきますが、まさにTwitterをトランプすることによって、今すぐトランプ(TRUMP)を引きずり下ろさなければならない、という気持ちになったし、なると思うんですよ、いまこのタイミングで観れば。
もちろん世界的な状況だけでなくて、僕自身も、トランプに比べればはるかに小さな炎上とはいえ、地獄の炎に焼き尽くされて、ボロボロになってアイドルという《宗教》から転んでしまった。自ら作ったアイドルグループが、結局当初掲げた理念を達成できず、地下アイドルという沼に引きずり込まれ、根を張ることができず、僕自身もプロデューサーから棄教し、逃亡したにも関わらず、磔にもされていない………。
俺は何をしているのか。
とにかく失語症からのリハビリテーションを始めなくてはいけない。
だから、Twitterとかに感想をつぶやくのではなく、キチジローのように告解すべきだと考えたんです。
宇野 つまり『沈黙』は、現在のソーシャルメディア社会とトランプ現象を象徴する話になっていて、そこに触発されたと。
濱野 はい。では、まずはこの映画のあらすじ的なところから話しを始めましょう。
『沈黙』はトゥルース(真実)or トランプ(棄教)という映画です。
まず、イエズス会の若い2人の宣教師が日本にやって来てくる。キリシタン狩りが始まっていて、もう危ないのにも関わらずです。
なぜならキリスト教こそが普遍的な真理であるという教えを信じているし、だからこそ、その教えを広めにはるばる西方よりやってくる。しかし、最初のうちは隠れキリシタンに匿われて、なんとかやっていくんですが、やっぱりキリシタン狩りに捕まってしまう。
当然、自分も磔にされるのかと思いきや、むしろ待遇はけっこういい。そのかわりに、目の前で隠れキリシタンたちが水刑、火刑、吊るし刑、ありとあらゆる手段で虐殺されていく。そして、かつて一緒に来た友人の神父もやはり捕まっていて、目の前で殉教していく。
もうやめてくれ。もう目の前でそんなに虐殺しないでくれ。自分を早く殺してくれ(でもキリスト教徒なので、当然、自殺はできない)。殉教させてくれ……と主人公のロドリゴは懊悩する。
……もうこの時点で、実は主人公は「手のひらの内」なんですね。日本の権力者側は分かりきっていて、「農民の信者たちをどんなに殺しても、キリスト教徒は殉教でパライソ(天国)に行けると喜んで死ぬから、根絶やしにできないのだ、と主人公に説明する。そこで我々日本人は考えた。『宣教師を棄教させる』と絶大な効果があるのだ、と。そして主人公に「転べ」(棄教しろ)とじわりじわりと迫るわけです。
そもそも主人公のロドリゴは、敬愛する師フェレイラが日本で棄教したという噂を聞いて、「俺たちの大尊敬する先輩が、教えを捨てるわけがない!」と立ち上がって、はるばる日本までやって来た。
だが、紆余曲折の末、結局終盤でフェレイラと会えるわけですが、彼は仏教の研究者になって日本人の名前をもらい、「キリスト教がいかに日本にとってダメな宗教か」という本まで書かされている。当然、2人は論争になる。いや、論争にもならない。ロドリゴは「何か言うことはないのですか?」と静かに問う。それに対してフェレイラの答えは最初から決まっている。俺の後に続け、と。
あえて、アイドル用語でいえば「流出せよ。他界せよ」というわけです。
中学3年の『沈黙』論から全ては始まった
濱野 僕は麻布中学の出身なんですが、実は中学3年の時に、現代文の授業で5人1組で修士論文を書くという課題があって、その時に僕が選んだのが遠藤周作の『沈黙』だったんです。理由は特になくて、なんとなく選んだんですが。
それで、論文を書くために友達の家に集まったんですが、そいつの家にNEO・GEO(ネオジオ)があって『サムライスピリッツ』とかで遊びまくった。ラスボスの「天草四郎時貞」を倒したりして(笑)。で、最終的に「俺が全部書いておくわ」という話になって、1万字くらいの評論をパッと書いたんです。だから、僕が初めて書いた評論のテーマは『沈黙』なんですよね……。
しかも、その時たまたまロラン・バルト的な「日本の中心は空虚である」とか、構造主義的な「ゼロ記号こそが中心として機能する」いった、いわゆる否定神学的なコンセプトを知ってしまった。それで僕は、「『沈黙』という作品は、最後に「声が聞こえる」のはおかしいけど、ゼロ記号による否定神学的構造とは理論的には整合性が取れていると思います」というような論文を書いて提出した。そしたら、「引用文献に引っ張られすぎているのでB判定」と返ってきて、「あれ〜? 結構自信作だったのにな〜」と少し悔しかった。
もうひとつ決定的だったのが、その後高2のとき、これはクラス全員で、夏目漱石の『こころ』について30×30字原稿用紙で900字くらいの小論を書く課題があったんです。これは50人のクラスの中でトップ3に選ばれ、全員の前で読み上げられたのですが、内容は「腹を切った乃木大将はバカだと思うし全く共感できない。しかし、それに感染して手紙を書いて自殺した先生の情熱は確実に何かを残したし、正直嫉妬するレベルだ」と。
この『沈黙』論と『こころ』論を書いた時点で、『前田敦子はキリストを超えた』を書くのは必然だったのだな、とようやく自らを振り返ることができました…。そして、アイドルプロデューサーになって大失敗し、いよいよ本当に沈黙を破って公的に謝罪しなければ……と思ったタイミングで、なんとも偶然にもスコセッシ監督による『沈黙』が公開された。僕の半生のタイムラインが全てつながった、偶然と必然の重なる瞬間でした。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…
・入会月以降の記事を読むことができるようになります。
・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
私は如何にして執筆するのを止めてアイドルを愛するようになったか――濱野智史が語る『アーキテクチャの生態系』その後 ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.377 ☆
2015-07-30 07:00チャンネル会員の皆様へお知らせ
(1)メルマガを写真付きのレイアウトで読む方法について
会員の方は、メルマガ冒頭にある「webで読む」リンクから閲覧すると画像などがきれいに表示されます。(初回はニコニコへのログインが必要です)
(2)Gmail使用者の方へ、メルマガが届かない場合の対処法
Gmailをご使用の場合、メルマガが「メイン」の受信ボックスではなく「プロモーション」に配信される場合があるようです。もしメールが受信できていない場合は「プロモーション」ボックスを確認の上、お手数ですがメールに「スター」を付けていただくようお願いいたします。「スター」を付けていただくと「メイン」ボックスに通常どおり届くようになります。
(3)ニコ生放送のメール通知を停止する方法について
PLANETSチャンネルのニコ生放送をあまりご覧にならない場合は、放送開始時のお知らせメールの配信を停止することができます。
(設定方法)ニコニコトップ(http://www.nicovideo.jp/)を開く→画面右上の「メニュー」から「アカウント設定」を開く→ぺージの左下にある「メール配信サービス」の「変更」をクリック→「ニコニコ生放送」をクリック→「【ニコニコ生放送】ニコ生アラート(メール)チャンネル版」の「変更する」クリック→PLANETSチャンネルの「変更する」をクリック→「停止」が表示されていることを確認
私は如何にして執筆するのを止めてアイドルを愛するようになったか――濱野智史が語る『アーキテクチャの生態系』その後
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.7.30 vol.377
http://wakusei2nd.com
2008年に出版され、その後のネットカルチャー分析に多大な影響を与えた情報環境研究者・濱野智史さんの著書『アーキテクチャの生態系』。その名作がこのたび文庫化されたことを記念して、現在はアイドルグループ「PIP」のプロデューサーとして活躍する濱野さんにその問題意識の変遷を聞きました。
現在のアイドルブームだけでなく、Facebookの日本での流行、そしてISIS問題まで、2015年現在の視点から幅広く語ってもらいました。
【発売中!】濱野智史『アーキテクチャの生態系: 情報環境はいかに設計されてきたか』ちくま文庫
mixi、2ちゃんねる、ニコニコ動画、ケータイ小説、初音ミク…。なぜ日本には固有のサービスが生まれてくるのか。他の国にはない不思議なサービスの数々は、どのようにして日本独自の進化を遂げたのか。本書は、日本独自の「情報環境」を分析することで、日本のウェブ社会をすっきりと見渡していく。ウェブから生まれた新世代の社会分析、待望の文庫化。(Amazon内容紹介より)
▼プロフィール
濱野智史〈はまの・さとし〉
1980年生、情報環境研究者/アイドルプロデューサー。慶應義塾大学大学院政策•メディア研究科修士課程修了後、2005年より国際大学GLOCOM研究員。2006年より株式会社日本技芸リサーチャー。2011年から千葉商科大学商経学部非常勤講師。著書に『アーキテクチャの生態系』(NTT出版)、『前田敦子はキリストを超えた 宗教としてのAKB48』(ちくま新書)など。2014年より、新生アイドルグループ「PIP」のプロデュースを手掛ける。
◎構成:稲葉ほたて
■『アーキテクチャの生態系』その後
――今日は『アーキテクチャの生態系』の文庫化にあわせて、この本が出た当時のことや濱野智史さんの現在の考えについてお聞かせいただきたいと思います。まず、この本を久々に読み返してみて、実はもう今のネット文化とはだいぶかけ離れた世界の話を書いているな、と思いました。
濱野:僕としても、過渡期のことを書いた自覚がある本なんですよ。
初音ミクも、すごく立派な存在になったものだと思うのですが、もうあの頃のハチャメチャさは失われてしまった。マネタイズを考えるとなると、既存の手法に近づくのは仕方ないですよね。だって、今やミクなんて最も使いづらいIPになっていて、近年のアイドル文化以前のアイドルみたいでしょう(笑)。生身の人間でないだけにコントロールしやすかったということの裏返しなんですが。
ニコニコ動画にしても、今思えば僕にとっては初期の、ニコニコ生放送を始める前の時期が面白かったんですね。
その後のドワンゴさんの動きで大きかったのは、確かにニコニコ生放送です。あれにプレミアム会員は優先的に視聴できる権利をつけることで、会員数が一気に伸びて成功した。ただ、その結果として運営がそういう方向に寄ってしまった。もちろん、生放送は生放送で、頭のおかしい配信者ばっかりで神がかって面白かった時期もあったんです。それに、技術的にもストリーミングのほうが伸びしろがあって、何よりもユーザーも面白がったのも事実です。
だから、こうなったのは必然ではあるのですが、やはりこの本を書いた時点での「ニコニコ動画」の絵は、ニコニコ自身が捨てたということになるとは思います。まあ、完全に捨てたというのは言いすぎなんですけど。
――淫夢動画のようなアングラな場所では、匿名のN次創作だって健在ですしね。ただ、表に見せられるカルチャーとしては、実は地下アイドルという文化の勃興と並行するかたちで、歌い手やゲーム実況者みたいなステージ文化が大きく台頭していったというのが、その後のニコニコ動画の歴史であるように思います。
濱野:YouTuberなんかも、そういう流れの延長線上で「お金になるから」という理由で登場してきた人たちですよね。
2年くらい前に、月刊カドカワさんのニコニコ動画特集に寄稿したとき、「ドワンゴは早くアイドルを作れ」と書いたんです。その時点で、アイドルにとっての劇場文化の重要性はわかっていたので「ニコファーレをとっととアイドルのための劇場にすればいい」と書いたのですが、結果的にはニコニコ超会議がある種アイドルと会える場所として機能していきましたね。
ただ、ドワンゴさんは、やはり自分たちでコンテンツを作るのには抵抗があるんでしょう。KADOKAWAと組んだことからも分かるように、コンテンツは属人性を大きくしたほうが強くなるのは理解していると思うんです。でも、そのときに自分たちの趣味のようなものが反映されるのには抵抗があるんだろうな、と。川上さんのようなネット技術畑出身の人は、プラットフォームとしての中立性にこだわっていて、特定のコンテンツに肩入れするのは避ける、どうもそういう感覚がある気がします。在特会のチャンネルが開かれるのを拒まなかったのだって、そういう発想が根底にあるんじゃないかな、と。
■ 2007年に起きたオタク文化の変貌
―― 一方で読み返してみて驚いたのが、当時は「Webの未来を書いた本」に見えたこの本が、むしろ今読むと、あの時期に表に出てきたゼロ年代前半のネット文化の秀逸な解説本に見えてしまったことです。
濱野:目次を見れば分かるのですが、この本は過去の話をひたすら書いてる本ですからね。
実際、ニコニコ動画の盛り上がりにしてもいくつかの歴史的要因がありますからね。2000年代までのオタク文化の積み重ねがあり、ブロードバンドやパソコンの浸透率があり、動画まで含めた一通りのマルチメディアがウェブに揃った時期だったというのがあって……という、その文脈をひと通り解説しようとした結果、「アーキテクチャの生態系」というまとめ方になったのかなと思います。
――今となってはニコニコもネット有名人たちの集まりのようになっているし、あの頃に匿名のN次創作があれほど盛り上がっていた文脈も、年々見えづらくなっている気もします。N次創作だって、実はゼロ年代前半のネットの同人文化で流行していたものですよね。別にニコニコ動画で急に生まれたものではないんですよね。
濱野:はい、もちろんそうですよね。それでいうと、90年代後半から2000年代前半くらいまでのいわゆる「ホームページ」って、同人活動の一環として自分のイラストを公開したりするような場所としても機能していましたよね。実際、2000年代にこの本を書いていた頃、会社で大学生のネット利用実態の調査をすると、ホームページを作る人は腐女子だとかのオタクばかりだったんですよ。アニメのキャラクターのイラストを描いたり、ドリーム小説を書いたり、掲示板を置いてコミュニケーションしたり、という。
まあ、ブログもない時代の、リア充なライトオタクが出てくる以前の話です。学校でおおっぴらにオタク趣味を言えない人が、ネットで仲間を探したり、作品を公開していて、そういう大学生たちの半年に一回のオフ会としてコミケがあった……そういう時代です。
――たぶん、そういう空気の中でゼロ年代前半を通じて、HPや2ちゃんねるで、M.U.G.E.NやBMSやAAやMADなどが盛り上がっていき、ニコニコ動画の登場で最盛期を迎えたというのが、2015年から振り返ったときのN次創作の歴史だと思います。実はあの2007年頃って、そういうマグマのように溜まっていたゼロ年代前半のオタク文化が一気に噴出した時期でもありますよね。
濱野:そうそう、あの2006年から2007年の頃って、ちょうど「涼宮ハルヒの憂鬱」が大ヒットして、明らかにぱっと見がオタクではない子たちが、「私、オタクなんです」と言い出した時期なんです。ちょうど動画サイトが登場して、アニメをネットで見られるようになり、10代の暇を持て余している層の共通のネタ元としてアニメが機能してはじめたんです。
そのときに、4,5人でパッと集まって盛り上がれるコンテンツを作るときに、アニメはとても「便利」なものだと発見されたんですね。というのも、「踊ってみた」や「コスプレ」のような、何かのテンプレをもとに真似したりアレンジするためのデータベースが、オタク文化には豊富にあったんです。その構図は現在の「MixChannel」に至るまで変わらないですね。
――二次元のオタク文化が市民権を得た背景には、動画サイトの存在があった。まあ、そこでみんなが見ていたのは、違法にアップロードされたものでしょうけど(笑)。
濱野:しかも、「涼宮ハルヒの憂鬱」って、当時としては作り手も若くて、それまでのアニメとは雰囲気も違っていたんです。なにしろ、当時の我々は「えっ、萌え要素って極限すれば3つでいいんだ」と驚きましたからね(笑)。別に10人とか20人なんて要らない、意外とツンデレとドジっ子とクールキャラくらいでイケる。これが衝撃だった。そういう話も含めて、新しい空気をまとっていたアニメでした。
実際、2007年に高校生を調査したときには、すでに「私たち、学校に"SOS団"を作ってるんです」みたいなことを言う子たちがかなりいました(笑)。ニコニコ動画でも「踊ってみた」をいろんな大学のサークルがやってましたよね。
――こういうゼロ年代前半の深夜アニメブームやネット文化の文脈を押さえた上で、硬派なネット論を語れる人材として、濱野さんが必要とされた瞬間だったのかなと思いました。
濱野:当時は世界的にフラッシュモブが話題になっていた時期でもあって、みんなで簡単に参加して同期する娯楽がネット文化全体としても流行っていました。そういう文脈を踏まえて書かれた本でもありますね。
■ アイドルへの興味に連続性はあったのか?
――それにしても、ここまでゴリゴリとアーキテクチャだけで議論を進めていく硬派な本は、このあと出てこなかったですね。最近になると、もうプラットフォームの運営者が表に出てくるので、そうなると中の人の「運営思想」を直接聞いていく発想の方が強いですよね。Facebookやニコニコ動画も、今だったらザッカーバーグや川上さんなんかの発言から分析しようと思うのが普通でしょうし。
濱野: まあ、そりゃ創業者にインタビューした方が話も早いですよね(笑)。Facebookの本にしたって、結局はザッカーバーグに取材したものになる。でも、僕はそういうのには関心がないんです。だって、「運営」の本って、結局は「その人がそう思いました」という話にしかならないでしょう。日本人が好む歴史って、戦国時代にしても幕末にしても、人物伝ばかり。でも、そういう属人的な話には興味がないんですよ。
――でも、その後に濱野さんが興味を向けたグループアイドルって、まさに仕組みをいかに運用していくかという「運営」の力が勝負を決める場所ですよね。
濱野:確かに。アイドルって要は人間そのものがコンテンツですから、「運営」すらも消費対象として重要になる。
AKBもそう。AKBがここまで大きくなったのは、巨大化してもいまだに「運営≒秋元康」が2ちゃんねるを見ていることだと思うんですよね。運営は2ちゃんねるが燃えると分かって燃料を投下して、2ちゃんねるのユーザーも「秋元の野郎」と返していく。いわゆる理想の民主主義の形というか、市民が討議しあって世論が熟して、政治家が選ばれて……というハーバーマスが理想とするような「公共圏」的な結託ではなくて、そこでは運営とオタクがともに文脈をズラしてツッコミ続ける「ネタ的コミュニケーション・システム」としての結託と連鎖が、今でも行われているんですよ。そこは、運営が2ちゃんねるを一切見ないふりをしたと言われているハロプロとの大きな違いですね。あっちは、DVD化の際にオタのコールを全てカットして販売したりしてたそうですから。
――その辺のテクニックって、やはり秋元康さんなんでしょうか?
濱野:秋元さんが「2ちゃんねるまとめ」をプリントしたものを会議なんかで見ていた、という話は聞きますね。少なくともオタは運営もメンバーも見ていると思うからこそ、「イエーイ見てるー?」状態になってモチベ高く2ちゃんねるとかに書き込みをするわけで、非常に独特の空間になっている。
そもそも秋元さんはラジオの放送作家上がりの人で、ハガキ職人的な世界観をよく知っているわけですよね。ああいうハガキ職人の文化は、匿名性がとても強くて、そのコミュニケーションもディスクジョッキーと真正面から語るよりは、延々とハシゴ外しを繰り返して、ズラし続ける感じ。
――つまり、深夜ラジオみたいな場所は、視聴者と番組の運営スタッフの距離が非常に近い"プレ・インターネット"になっていて、そこで秋元さんはネット的な感受性を鍛えられていた……という感じですか。
濱野:そうですね。『前田敦子はキリストを超えた』(編注:2012年に出版された濱野さんの著書/ちくま新書)では、そうした運営論というか、秋元康論は一切書かなかったですけど、実はAKBが成功した理由への僕なりの回答は、そこにあるんですよね。それどころか、秋元康という人は、ずっとそれだけをやってきた人なんじゃないか、と。AKBは、彼が80年代からやってきたことが、2ちゃんねるやTwitterが大きな力を持ってしまう時代に、突然マッチしてしまっただけなんです。
ただ、大きくなっても運営がそういうコミュニケーションを恐れなかったのは、本当に凄いですけどね。実はこういう文化を作ったのはハロプロだったのだけど、さっきも言ったように彼らは受け手の意見は聞かないふりをした。まあ、2ちゃんねるの話なんてまともに聞くわけないですから、別にそれって悪いことでもなんでもないですよ(笑)。それに対して、逆にAKBは運営が明らかに「聞いてまーす!」という態度で、悪ノリ的にユーザーと結託しようとした。そこが凄かった。
――この『アーキテクチャの生態系』が登場した当時、クリエイティビティが宿っているのは、ユーザーなのかアーキテクチャなのか、みたいな議論がありましたが、それに対して、いまこの場で濱野さんがおっしゃっているのは、両者をコーディネートする媒介としての「運営」が肝になってくるという話にも聞こえますが……。
濱野:それはそうなのですが……やっぱり、僕がそういう話をやりたくはないんですよ、うん。
――でも、そうなるとウェブサービスに対して「運営」から分析していく流れにも、必ずしも話がわかりやすいからだけでない、理論的な根拠があると言えませんか。
濱野:確かにそうなんですけどね……。でもその一方で、「これじゃあ、秋元さんが死んだら終わりじゃん」とも思ってしまうんですね。それは日本文化のある種の弱さというか弱点でもあって、要するに一代限りのワンマン社長で文化が終わっていくのではダメだと思うんです。そこはアーキテクチャに落としこむ必要があると思うんです。普遍化したい、という欲求が社会学者としてある、というのかな。
――いや、この話を掘り下げたいのは、濱野さんのその後の活動とこの本の連続性を聞いてみたいからなんです。それこそニコニコ動画なんてその後、実況者や歌い手の疑似恋愛と結びついた文化が大きく台頭して、社員たちが「もうイベント会社だよね」と自嘲するくらいにイベントドリブンのサービスになってしまい、さらに当時は裏に隠れていた川上さんがニコニコの運営論を自ら話すようになったわけですよ。今思えば、これってアイドルブームと並行する動向です。その後の濱野さんはインターネット論から一見して離れたように見えて、理論の水準ではやはりこういう日本的インターネットの最先端の動向と並走していたと思うんです。
濱野:なるほど! まあ、そういう意味では、僕はグループアイドルにしか興味がないというのはありますね。グループアイドルって、要はメンバー一人ひとりにピンで立っていけるほどの実力はないんです。でも、そういう娘たちを集めると、メンバー同士やファン同士や運営との関係性で、驚くほど多くの物語が勝手に生まれていく。そのダイナミズムが面白い。
そしてこのグループアイドルで重要になるのが、仕組みなんです。アイドルって、別に歌も踊りも重要じゃないから、とにかく「人」の”配置”と”構成”が全てであるとしか言いようがない。ポジションとか、曲順とか、そういうのですね。PIPなんて最初のうちはカバーしかやってないから、曲すら重要じゃない。ただ、誰がどういう順番でどこで何を歌うか。それだけをひたすら設計し、設定する。、何人グループにするか、誰をどういう仕組みで選抜するか、みたいな配置と構成の設計が、全体の動向を大きく左右するんです。それは、僕があの本で書いた意味での「アーキテクチャ」とは厳密には違いますが、やはりプログラミングに近い何かがあるのは事実です。
実際、僕のPIPでの主な仕事なんて、ライブの曲順を決めながら「いや、この順番では着替えが発生するな」と順番をいじり続けることだとかで、ほとんどソートというか順序づけをしているだけです。ところが、本当にそれだけのことから、もうおよそ人間世界にある様々な情動が勝手に生成されてきて、あらゆるものをドドドドドと巻き込んでいくんです。これ、なかなか体験していない人には伝わらないかもしれないんですけどね。
――そう聞くと、『アーキテクチャの生態系』の問題意識からアイドルに向かう連続性は見えてきますね。
濱野:以前、学生時代にネトゲ廃人だった友人にアイドルの説明をしたら、完全にネトゲの用語で意思疎通ができたことがあるんですよ。
例えば、AKBの人気が持続している理由として、「NMBとかSKEとかどんどん作っていって、新規が入りやすいようにしてるんだよ」と言ったら、「ああ、なるほど、新鯖を作るってことか!」と言われて、「そうそう!」みたいな(笑)。
――グループアイドルの運営とネトゲの運営はそっくり(笑)。
濱野:そっくりどころか、実はほとんどネトゲの運営手法と同じなんですよ。運営がやたらと2ちゃんねるの板に張り付いて、どんな悪口を書かれているか確認して対処するとか、そういう話まで含めて(笑)。
【ここから先はチャンネル会員限定!】PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は今月も厳選された記事を多数配信します! 配信記事一覧はこちらから↓
-
【ほぼ惑ベストセレクション2014:第7位】ありきたりの「ファスト風土」論にはもう飽きた!「新しい郊外論」のためのマスタープラン――國分功一郎×濱野智史『常磐線から考える』 ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 号外 ☆
2014-12-28 11:10
【ほぼ惑ベストセレクション2014:第7位】ありきたりの「ファスト風土」論にはもう飽きた!「新しい郊外論」のためのマスタープラン――國分功一郎×濱野智史『常磐線から考える』
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2014.12.28 号外
http://wakusei2nd.com
2014年2月より約1年にわたってお送りしてきたメルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」。この年末は、200本以上の記事の中から編集長・宇野常寛が選んだ記事10本を、5日間に分けてカウントダウン形式で再配信していきます。第7位は、國分功一郎さん・濱野智史さんの対談企画「常磐線から考える」です!(2014年9月16日配信)これまでのベストセレクションはコチラ!
▼編集長・宇野常寛のコメント
この記事の取材のとき、僕はテレビの収録で同行できなかったんだけれど、合間に國分さんや濱野のツイッターを眺めていたらとても楽しそうで、すごく嫉妬した記憶があるんですね。
東京の西側とはまた違う文脈で形成されてきた、「東側」のベッドタウンとしての常磐線エリアには、戦後の中流文化とはまた違った意味での豊かさと貧しさが同居しているはず。前者を伸ばして後者に立ち向かうことが、これからの社会を考える上で大事なことになってくる。2020年の東京オリンピックを前にして、日本人の意識は、被災地を中心にした「衰退する地方」と、ますます人もお金も集中する都市部へと引き裂かれていっている。そのどちらを考えるときにも、「中間的な存在」である常磐線エリアの街について考えることが大きな手がかりになるのではないかということを、この原稿を読んでずっと考えていたりします。
Twitter上での熱いやりとりをきっかけに、7月のとある休日を使って行なわれたこの対談企画。濱野さんの生まれ故郷である新松戸を出発点に、途中PLANETSのエグゼクティブ・サポーターである「モウリス」の助力と提案で、つくばエクスプレスの駅周辺にあるショッピングモールを訪問し、最後に國分さんの故郷である柏を巡りました。
二人の思想家の「ジモト」を巡りながら見えてきた、「新しい郊外論」のためのマスタープラン(基本計画)とは――? 本日の「ほぼ惑」では、ダイジェスト版のレポートをお届けします。対談の全容は、何らかのかたちで全文公開を予定しています。今回の「ほぼ惑」ではその「新しい郊外論」のイントロダクションをお見せします!
▼プロフィール
國分功一郎(こくぶん・こういちろう)
1974年生まれ。柏出身の哲学者。高崎経済大学経済学部准教授。専門は17世紀のヨーロッパ哲学、現代フランス哲学。また、哲学、倫理学を道具に「現代社会をどう生きるか」を「楽しく真剣に」思考する。著書に『暇と退屈の倫理学』(朝日出版)、PLANETSメルマガでの人気コーナーを書籍化した『哲学の先生と人生の話をしよう』(朝日新聞出版)、自らが積極的に関わった小平市の住民運動について書かれた『来るべき民主主義──小平市都道328号線と近代政治哲学の諸問題』(幻冬舎新書)などがある。今回の「柏論」は國分さんたっての希望で実現することになった。
濱野智史(はまの・さとし)
1980年生まれ。新松戸出身の情報環境研究者/アイドルプロデューサー。慶應義塾大学大学院政策•メディア研究科修士課程修了後、2005年より国際大学GLOCOM研究員。2006年より株式会社日本技芸リサーチャー。2011年から千葉商科大学商経学部非常勤講師。著書に『アーキテクチャの生態系』(NTT出版)、『前田敦子はキリストを超えた 宗教としてのAKB48』(ちくま新書)など。2014年より、新生アイドルグループ「PIP」のプロデュースを手掛ける。
◎構成:立石浩史、中野慧
■新松戸〜流山を歩く
7月12日、午後過ぎ。前日までの台風の影響が心配されましたが、この日は予想を覆す快晴となりました。暑すぎるくらいの天気の中、JR常磐線の新松戸駅前に集合。
▲駅の東側は住宅や畑が広がり、のんびりとした雰囲気です。
▲新松戸駅前にて。この日、國分さんはツイキャスで実況しながらの収録でした。
國分さん、濱野さん、P編集部2人の4人でまずは濱野さんの生まれ故郷である新松戸を歩きます。國分さん曰く『暇と退屈の倫理学』の延長線上の仕事であるとのこと。
■今一度、郊外論を問いなおす
國分 この20年くらい「郊外」が注目を浴び続けていますよね。僕は柏生まれ柏育ちなんですけど、柏はこの郊外というものの純粋形態ではないかと思っているんです。今日はその直観を、実際に濱野さんと街を歩きながら検証してみたい。
論壇では2000年代半ばから「ファスト風土」という言い回しが流行しました。けれども僕は、「今さら何を言っているんだ」という気持ちでした。「遅いよ」と。僕は自分が幼い頃から「ファスト風土」で生活してきて、そのことについてとても苦しいという感覚があった。ですから、その感覚に気づいてそれを理解しようとするひとがこれまでいなかったことに端的に驚いたのです。論壇なるものはなんと鈍感なのかと思った。
僕が感じていた苦しさというのは、幼い時の感覚であることもあってなかなか描写しづらいんですけれど、歴史の欠如と関係しているように思います。歴史の無い土地、荒野に、家だけが建てられて人が住んでいるというイメージですね。
都内に通勤しているサラリーマンの家庭であれば、親と子どもは週末以外顔を合わせない。土地にある歴史やコミュニティと人間が切り離されて、アトム化されて生きている場所――今からあの時の感覚を言葉にしてみるとそのように言えるかと思います。
90年代より積極的に郊外に言及されている論客に宮台真司さんがいらっしゃいます。以前、宮台さんとお話ししたときに出身地を聞かれたんです、「國分さんは小平の出身なんですか?」って。「いえいえ、今住んでいる小平ではなく、柏ですよ」と答えたら、「あんまりいいイメージがないな」とおっしゃっていた。その時、なんとなく「なるほど」って感覚があったんです。現代の新しい空虚を生きる若者についてずっと考えてこられた宮台さんが「なんとかしなければならない」と思われている街の典型が柏なのかも知れない、と。
濱野 テレクラが駅前にあって、援交が盛んで……というイメージですね。しかし、何故かはわからないですけど(笑)、國分さんが郊外出身というイメージがなかったんですよ。PLANETSの人生相談連載を読んでいると、失礼ですが地方の強固なコミュニティがあるところで育った方なのではないかと思っていました。だから柏出身と聞いたとき意外だったんですよ。
國分 そうなんだね。僕がそのような印象を与えるのはなぜだかよく分からないけど、『暇倫』で扱った問題、たとえば、消費社会の問題とか、何をしていいか分からないアイデンティティの不安の問題については、自分が柏のようなところで生まれ育ったからこそ敏感でいられたんじゃないかと思っているんだ。
街とそこに住む人とのアイデンティティについて考えたいというのが今回の課題です。その時に重要なのは、もともと荒野だったところに家を建てたようなイメージで捉えられる郊外にも、当然ながら歴史があるってこと。つまり「郊外」というレッテル貼りによって、町の歴史の地層を見えにくくしていることがある。これをはじめに言っておきたい。
そういう「見えにくくなっている歴史」の話を出すと、どうしても「ふるさとのよさを再発見する」的なノスタルジックなものになってしまいがちなんだけど、そうじゃない方法で街の歴史にアクセスできないか。それが僕自身の課題なんですね。
もう僕は柏には住んでいないけれど、そのアクセス方法についての考えを作って、自分の気持ちに対する決着をつけたい。要するに……僕は柏があまり好きじゃないんです。生まれ故郷だから愛着はあるんだけど、同時に強い違和感も持っている。そんなことを考えているときに濱野さんがお隣の新松戸出身であり、かつニュータウンの問題を真剣に考えていることを知りました。それで今回の企画にお誘いしたんですよ。
濱野 この企画に誘ってもらったきっかけは僕が藻谷浩介さんの『しなやかな日本列島のつくりかた』(新潮社)のブックレビューをネット上に書いたことですよね。僕も以前は國分さんと同じように、生まれ育ったニュータウンを空虚な場所だと思ってきました。新松戸で生まれ、小学校高学年からは千葉ニュータウンと「郊外から郊外」へと移り住みました。
当時は生き辛いとまでは思っていませんでしたが、確かにこの場所で生きている人間はアトム化されるしかないというか、國分さんがおっしゃるように自分の住んでいる町には歴史もなければコミュニティもないと思っていました。松戸と柏という町は兄弟という感じがしていて、國分さんとは同じバックグラウンドだと思います。
■かつて疎外的だった郊外は、意外といい町になっている!?
國分 柏と松戸は、地理的にも千葉県の北部で隣接しているし、東京に通勤する人が多いという点でも似ている。でも、濱野さんと新松戸を歩きながら違いも見えてきたね。たとえば道路の作り方が全然違う。新松戸の豊かな街路樹のある道には落ち着きを感じる。こういう道は柏にはあまりないと思います。
当然だけど、柏より松戸の方が東京に近いので開発が早い。駅前に関して言うと、松戸はうまく開発できなかった。柏はゆっくり開発できたからダブルデッキなどを作れて割とうまくいった。けれども道路に関して言うと、落ち着いた街路樹のある松戸の道路のようなものはうまく作れていない。松戸には、全国的に有名な桜の通りもありますよね。
▲新松戸の「けやき通り」の入り口。
▲並木道が整備されています。
濱野 僕が子どもの頃の80年代〜90年代にかけては、あんなに木が立派では無かったと記憶しています。20年かけて木が育ったのではないでしょうか? 『しなやかな日本列島のつくりかた』の書評にも書いたのですが、欧米などでは、街路樹が育ち景観がよくなり町が成熟すると、地価が下がらないらしいんですね。詳細を調べてみる必要はありますけれども。今日訪れた新松戸なんかは地価は下がっているでしょうけど、街路樹が育って、いい雰囲気の街になっていますよね。
國分 僕はこの景観を見て、なんとも言えない町の成熟を感じました。新松戸は予想以上にいいところでビックリ。
濱野 もう少しサバサバした「郊外」というイメージだったんですが、僕もいい意味で予想を裏切られました。
國分 新松戸を歩いてみて一番面白かったのは濱野さんの新松戸のイメージが変わったということだな(笑)。
濱野 「郊外」と言うとどうしても「疎外されている」という感覚を生みやすい。僕もこれまでの論客のように「疎外されたものへのひねくれた愛着」みたいなものを持っています(笑)。今日は「相変わらずサバサバしてんな〜」とか言って懐かしむのかと思いきや、ほぼ20年ぶりに訪れてみると町が成熟していて驚きでした。「新松戸は意外にいい町じゃん! 俺、ずっとここ住んでりゃよかったじゃん!」と逆に「疎外」されましたね(笑)。
町のビルがほとんど増えていないのも面白いと思いますね。新松戸って、開発時に家もマンションも区画を余らせずに作っちゃったので、今は街の流動性が下がっているんじゃないでしょうか。駅前の風景もあまり変わっていない。逆に言うとこれから再開発してもいいぐらいの、ある種穏やかすぎるぐらいの景観だと思います。
▲新松戸駅前の風景。奥には流鉄流山線の幸谷駅付近の踏切。赤いビルはかなり古そう。
■鉄道が変える町の歴史駅周辺をしばらく歩いてから、2人は常磐線と並行して走る「流鉄流山線」(単線鉄道)にもぶらりと乗車しました。流山線の幸谷駅は、常磐線の新松戸駅に隣接しています。
▲流鉄流山線の車両。
▲流山線の路線図。幸谷駅とJR常磐線の新松戸駅はすぐそば。國分 さきほど流山線に乗りましたが、二人とも乗るのは初めてだったね。新松戸から北部の方に行って戻って来ましたけど、途中の風景は、農村風景→ニュータウン→農村風景→ニュータウンのようになっているんですね。つまり流山は、新しいマンションやキレイな家が最近どんどん建設されている一方で、昔は柏や松戸よりも栄えていた土地なので、古い大きな農家なんかも残っている。それが交互に現れる。
それにしても、新松戸(幸谷駅)からちょっと電車に乗っただけで、大きな農家があるような場所に行けるというのは、大きな発見だったね。
濱野 この辺りは流山電鉄のロジックで町が作られていないんですね。普通は電車が通ると、町が付帯されてできあがるんですが、全くそういう感じではない。
國分 100年前に敷かれた電車だからね。それにしても歴史的に見ればこの辺りの町は栄枯盛衰がすごいよね。
流山は明治のはじめあたりはとても栄えた街だった。少し離れてるけど鰭ヶ崎(ひれがさき)なんかもそうですね。でも、常磐線の建設計画が出てきた時、流山や鰭ヶ崎はそれに反対したんですね。蒸気機関車からはき出される火の粉で火災が発生するのを恐れてのことだったらしいです。当時はかやぶき屋根だからそういう気持ちがでるのも当然かもしれない。
でも、柏はそれを受け入れたんですね。僕は松戸の方はよく知らないんだけど、実際、常磐線は松戸や柏の地域を通っている。その後、常磐線の沿線は発展を続けるわけだけれど、鉄道を拒んだ地域は発展から取り残されてしまった。
ところが最近は逆に、つくばエクスプレスが通ったことによって流山が活気づいている。マンションもバンバン建って、盛り上がっているね。つまり流山というのは明治以来、鉄道の敷設に関連する形で町が変動してきた。
▲流鉄流山線の車窓からの風景。新興の住宅も目立ちます。
▲流鉄流山駅にて。駅の改札では駅員が切符を切っており、ICカード式の改札はおろか、磁気乗車券の自動改札機も導入されていませんでした!ちなみに駅奥の森林は駅員さん曰く空き地とのこと。ほんの近くに流山市役所がある「旧」市街地です。
■郊外は使い捨て?
濱野 僕の郊外のイメージは「使い捨て」なんですよ。僕は家族で、手狭だった新松戸のマンションから千葉ニュータウンの一軒家に90年ごろに引っ越したんですけど、引っ越したときは空き地だらけで、コンビニもろくにありませんでした。「この町は明らかに失敗だ。マイホームなんていらねえよ!」と思ったんですよね。僕は千葉ニュータウンの都市計画は失敗していると思いますが、その理由は、当時人口が20万人ほどに増えていないといけないのに全然達しておらず、そこに電車を引いてしまたったことにあると思っています。
僕はその後中学受験して都内の学校に2時間かけて通っていたから、青春時代は千葉ニュータウンにほとんどいませんでした。だから何の思い入れもないんですよ。大人になってからも4回しか帰省していない。なぜなら帰りたくないから。何もないし、遠いし、親もうるさいから(笑)。
國分 少年時代の濱野さんはそういう思いだったんだ。俺も「何かおかしい」って感覚があったな。人間のそういう感覚は大事なんだと思う。でも、やはり新松戸の街路樹は象徴的だよ。「町というものがこうやって育っていくんだ」といういい感じがした。
濱野 樹って、植えてみるもんなんですね。他にも、駅から歩いて数分のところに流通経済大のビルができたりしていましたね。大学ができることで町はまた成熟するものだと思います。反面、新松戸は子どもの数が劇的に減っている印象を受けました。象徴的だったのが、住んでいたマンションの近くに妹が生まれた産婦人科があったのですが、その医院が看板を取り外していたことです。
つまり、産婦人科の病院がマンションの側からひとつ無くなることが意味していることですよね。これまたマンションのすぐ近くの「新松戸中央公園」で遊ぶ子どもの数が、土曜の昼下がりという時間帯にも関わらず、昔と比べて少なかったことも印象的でした。
▲流通経済大学・新松戸キャンパス。
▲左手前の屋上のある白い建物が濱野さんの妹さんが生まれた元・産婦人科の病院。濱野さんが住んでいたマンションの10階から望む風景です。
▲新松戸中央公園。広大な運動場ではスポーツチームの子供たちがクラブ活動のスポーツに興じていました。でも、子どもの数はまばら。
■幼少期のアーキテクチャが情報環境研究者・濱野智史を生成した濱野 今日10何年ぶりに新松戸に来てみて、郊外は意外と残っているものだなと感じました。逆に千葉ニュータウンのような町が今後どうなっていくのかにも興味があります。アメリカ風の車社会に最適化していくのだと思いますけど。 それにしても人間というものは環境ひとつでこんなにもどうにもこうにもなってしまうものなのかと。僕はもともとアーキテクチャが人に与える影響を社会学的に研究してきたわけですけれども、そういうことを研究するようになったのには、自分の出自や生育環境が多いに関係していると思います。僕は新松戸ではマンションの10階に住んでいて、4、5歳までエレベーターの10階のボタンを押せなかったんですね。だから家から下の階へは行けずに、上の階に住んでいた一つ年上のお兄さんの家に遊びに行ってファミコンをして、「ゲームすげえ!」と衝撃を受けたりしていました。「ブランコよりこっちだ!」みたいな感じで(笑)。
そこでの生活環境がこうして今の研究につながっていたりするわけです。単に10階に住んでいただけなんですけどね。環境が僕の幼少期の行動を決め、ゲームの環境が人をハマらせ……とか、先ほどの「郊外で生まれ育つと人間が疎外されていく」という話も、環境があっさり人間を作ってしまう典型例だと思います。
國分 街を考える上では、当然のことながらアーキテクチャの視点が重要になってくるということだよね。 -
ありきたりの「ファスト風土」論にはもう飽きた!「新しい郊外論」のためのマスタープラン――國分功一郎×濱野智史『常磐線から考える』 ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.159 ☆
2014-09-16 07:00
ありきたりの「ファスト風土」論にはもう飽きた!「新しい郊外論」のためのマスタープラン――國分功一郎×濱野智史『常磐線から考える』
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2014.9.16 vol.159
http://wakusei2nd.com
Twitter上での会話をきっかけに、「人生」を考える哲学者・國分功一郎×「情報環境」を考える研究者・濱野智史という、千葉出身の二人の思想家の「ジモト」を巡る企画がほぼ惑で実現。そのダイジェストをお届けします!
Twitter上での熱いやりとりをきっかけに、7月のとある休日を使って行なわれたこの対談企画。濱野さんの生まれ故郷である新松戸を出発点に、途中PLANETSのエグゼクティブ・サポーターである「モウリス」の助力と提案で、つくばエクスプレスの駅周辺にあるショッピングモールを訪問し、最後に國分さんの故郷である柏を巡りました。
二人の思想家の「ジモト」を巡りながら見えてきた、「新しい郊外論」のためのマスタープラン(基本計画)とは――? 本日の「ほぼ惑」では、ダイジェスト版のレポートをお届けします。対談の全容は、何らかのかたちで全文公開を予定しています。今回の「ほぼ惑」ではその「新しい郊外論」のイントロダクションをお見せします!
▼プロフィール
國分功一郎(こくぶん・こういちろう)
1974年生まれ。柏出身の哲学者。高崎経済大学経済学部准教授。専門は17世紀のヨーロッパ哲学、現代フランス哲学。また、哲学、倫理学を道具に「現代社会をどう生きるか」を「楽しく真剣に」思考する。著書に『暇と退屈の倫理学』(朝日出版)、PLANETSメルマガでの人気コーナーを書籍化した『哲学の先生と人生の話をしよう』(朝日新聞出版)、自らが積極的に関わった小平市の住民運動について書かれた『来るべき民主主義──小平市都道328号線と近代政治哲学の諸問題』(幻冬舎新書)などがある。今回の「柏論」は國分さんたっての希望で実現することになった。
濱野智史(はまの・さとし)
1980年生まれ。新松戸出身の情報環境研究者/アイドルプロデューサー。慶應義塾大学大学院政策•メディア研究科修士課程修了後、2005年より国際大学GLOCOM研究員。2006年より株式会社日本技芸リサーチャー。2011年から千葉商科大学商経学部非常勤講師。著書に『アーキテクチャの生態系』(NTT出版)、『前田敦子はキリストを超えた 宗教としてのAKB48』(ちくま新書)など。2014年より、新生アイドルグループ「PIP」のプロデュースを手掛ける。
◎構成:立石浩史、中野慧
■新松戸〜流山を歩く
7月12日、午後過ぎ。前日までの台風の影響が心配されましたが、この日は予想を覆す快晴となりました。暑すぎるくらいの天気の中、JR常磐線の新松戸駅前に集合。
▲駅の東側は住宅や畑が広がり、のんびりとした雰囲気です。
▲新松戸駅前にて。この日、國分さんはツイキャスで実況しながらの収録でした。
國分さん、濱野さん、P編集部2人の4人でまずは濱野さんの生まれ故郷である新松戸を歩きます。國分さん曰く『暇と退屈の倫理学』の延長線上の仕事であるとのこと。
■今一度、郊外論を問いなおす
國分 この20年くらい「郊外」が注目を浴び続けていますよね。僕は柏生まれ柏育ちなんですけど、柏はこの郊外というものの純粋形態ではないかと思っているんです。今日はその直観を、実際に濱野さんと街を歩きながら検証してみたい。
論壇では2000年代半ばから「ファスト風土」という言い回しが流行しました。けれども僕は、「今さら何を言っているんだ」という気持ちでした。「遅いよ」と。僕は自分が幼い頃から「ファスト風土」で生活してきて、そのことについてとても苦しいという感覚があった。ですから、その感覚に気づいてそれを理解しようとするひとがこれまでいなかったことに端的に驚いたのです。論壇なるものはなんと鈍感なのかと思った。
僕が感じていた苦しさというのは、幼い時の感覚であることもあってなかなか描写しづらいんですけれど、歴史の欠如と関係しているように思います。歴史の無い土地、荒野に、家だけが建てられて人が住んでいるというイメージですね。
都内に通勤しているサラリーマンの家庭であれば、親と子どもは週末以外顔を合わせない。土地にある歴史やコミュニティと人間が切り離されて、アトム化されて生きている場所――今からあの時の感覚を言葉にしてみるとそのように言えるかと思います。
90年代より積極的に郊外に言及されている論客に宮台真司さんがいらっしゃいます。以前、宮台さんとお話ししたときに出身地を聞かれたんです、「國分さんは小平の出身なんですか?」って。「いえいえ、今住んでいる小平ではなく、柏ですよ」と答えたら、「あんまりいいイメージがないな」とおっしゃっていた。その時、なんとなく「なるほど」って感覚があったんです。現代の新しい空虚を生きる若者についてずっと考えてこられた宮台さんが「なんとかしなければならない」と思われている街の典型が柏なのかも知れない、と。
濱野 テレクラが駅前にあって、援交が盛んで……というイメージですね。しかし、何故かはわからないですけど(笑)、國分さんが郊外出身というイメージがなかったんですよ。PLANETSの人生相談連載を読んでいると、失礼ですが地方の強固なコミュニティがあるところで育った方なのではないかと思っていました。だから柏出身と聞いたとき意外だったんですよ。
國分 そうなんだね。僕がそのような印象を与えるのはなぜだかよく分からないけど、『暇倫』で扱った問題、たとえば、消費社会の問題とか、何をしていいか分からないアイデンティティの不安の問題については、自分が柏のようなところで生まれ育ったからこそ敏感でいられたんじゃないかと思っているんだ。
街とそこに住む人とのアイデンティティについて考えたいというのが今回の課題です。その時に重要なのは、もともと荒野だったところに家を建てたようなイメージで捉えられる郊外にも、当然ながら歴史があるってこと。つまり「郊外」というレッテル貼りによって、町の歴史の地層を見えにくくしていることがある。これをはじめに言っておきたい。
そういう「見えにくくなっている歴史」の話を出すと、どうしても「ふるさとのよさを再発見する」的なノスタルジックなものになってしまいがちなんだけど、そうじゃない方法で街の歴史にアクセスできないか。それが僕自身の課題なんですね。
もう僕は柏には住んでいないけれど、そのアクセス方法についての考えを作って、自分の気持ちに対する決着をつけたい。要するに……僕は柏があまり好きじゃないんです。生まれ故郷だから愛着はあるんだけど、同時に強い違和感も持っている。そんなことを考えているときに濱野さんがお隣の新松戸出身であり、かつニュータウンの問題を真剣に考えていることを知りました。それで今回の企画にお誘いしたんですよ。
濱野 この企画に誘ってもらったきっかけは僕が藻谷浩介さんの『しなやかな日本列島のつくりかた』(新潮社)のブックレビューをネット上に書いたことですよね。僕も以前は國分さんと同じように、生まれ育ったニュータウンを空虚な場所だと思ってきました。新松戸で生まれ、小学校高学年からは千葉ニュータウンと「郊外から郊外」へと移り住みました。
当時は生き辛いとまでは思っていませんでしたが、確かにこの場所で生きている人間はアトム化されるしかないというか、國分さんがおっしゃるように自分の住んでいる町には歴史もなければコミュニティもないと思っていました。松戸と柏という町は兄弟という感じがしていて、國分さんとは同じバックグラウンドだと思います。
■かつて疎外的だった郊外は、意外といい町になっている!?國分 柏と松戸は、地理的にも千葉県の北部で隣接しているし、東京に通勤する人が多いという点でも似ている。でも、濱野さんと新松戸を歩きながら違いも見えてきたね。たとえば道路の作り方が全然違う。新松戸の豊かな街路樹のある道には落ち着きを感じる。こういう道は柏にはあまりないと思います。
当然だけど、柏より松戸の方が東京に近いので開発が早い。駅前に関して言うと、松戸はうまく開発できなかった。柏はゆっくり開発できたからダブルデッキなどを作れて割とうまくいった。けれども道路に関して言うと、落ち着いた街路樹のある松戸の道路のようなものはうまく作れていない。松戸には、全国的に有名な桜の通りもありますよね。
▲新松戸の「けやき通り」の入り口。
▲並木道が整備されています。
濱野 僕が子どもの頃の80年代〜90年代にかけては、あんなに木が立派では無かったと記憶しています。20年かけて木が育ったのではないでしょうか? 『しなやかな日本列島のつくりかた』の書評にも書いたのですが、欧米などでは、街路樹が育ち景観がよくなり町が成熟すると、地価が下がらないらしいんですね。詳細を調べてみる必要はありますけれども。今日訪れた新松戸なんかは地価は下がっているでしょうけど、街路樹が育って、いい雰囲気の街になっていますよね。
國分 僕はこの景観を見て、なんとも言えない町の成熟を感じました。新松戸は予想以上にいいところでビックリ。
濱野 もう少しサバサバした「郊外」というイメージだったんですが、僕もいい意味で予想を裏切られました。
國分 新松戸を歩いてみて一番面白かったのは濱野さんの新松戸のイメージが変わったということだな(笑)。
濱野 「郊外」と言うとどうしても「疎外されている」という感覚を生みやすい。僕もこれまでの論客のように「疎外されたものへのひねくれた愛着」みたいなものを持っています(笑)。今日は「相変わらずサバサバしてんな〜」とか言って懐かしむのかと思いきや、ほぼ20年ぶりに訪れてみると町が成熟していて驚きでした。「新松戸は意外にいい町じゃん! 俺、ずっとここ住んでりゃよかったじゃん!」と逆に「疎外」されましたね(笑)。
町のビルがほとんど増えていないのも面白いと思いますね。新松戸って、開発時に家もマンションも区画を余らせずに作っちゃったので、今は街の流動性が下がっているんじゃないでしょうか。駅前の風景もあまり変わっていない。逆に言うとこれから再開発してもいいぐらいの、ある種穏やかすぎるぐらいの景観だと思います。
▲新松戸駅前の風景。奥には流鉄流山線の幸谷駅付近の踏切。赤いビルはかなり古そう。
■鉄道が変える町の歴史
駅周辺をしばらく歩いてから、2人は常磐線と並行して走る「流鉄流山線」(単線鉄道)にもぶらりと乗車しました。流山線の幸谷駅は、常磐線の新松戸駅に隣接しています。
▲流鉄流山線の車両。
▲流山線の路線図。幸谷駅とJR常磐線の新松戸駅はすぐそば。國分 さきほど流山線に乗りましたが、二人とも乗るのは初めてだったね。新松戸から北部の方に行って戻って来ましたけど、途中の風景は、農村風景→ニュータウン→農村風景→ニュータウンのようになっているんですね。つまり流山は、新しいマンションやキレイな家が最近どんどん建設されている一方で、昔は柏や松戸よりも栄えていた土地なので、古い大きな農家なんかも残っている。それが交互に現れる。
それにしても、新松戸(幸谷駅)からちょっと電車に乗っただけで、大きな農家があるような場所に行けるというのは、大きな発見だったね。
濱野 この辺りは流山電鉄のロジックで町が作られていないんですね。普通は電車が通ると、町が付帯されてできあがるんですが、全くそういう感じではない。
國分 100年前に敷かれた電車だからね。それにしても歴史的に見ればこの辺りの町は栄枯盛衰がすごいよね。
流山は明治のはじめあたりはとても栄えた街だった。少し離れてるけど鰭ヶ崎(ひれがさき)なんかもそうですね。でも、常磐線の建設計画が出てきた時、流山や鰭ヶ崎はそれに反対したんですね。蒸気機関車からはき出される火の粉で火災が発生するのを恐れてのことだったらしいです。当時はかやぶき屋根だからそういう気持ちがでるのも当然かもしれない。
でも、柏はそれを受け入れたんですね。僕は松戸の方はよく知らないんだけど、実際、常磐線は松戸や柏の地域を通っている。その後、常磐線の沿線は発展を続けるわけだけれど、鉄道を拒んだ地域は発展から取り残されてしまった。
ところが最近は逆に、つくばエクスプレスが通ったことによって流山が活気づいている。マンションもバンバン建って、盛り上がっているね。つまり流山というのは明治以来、鉄道の敷設に関連する形で町が変動してきた。
▲流鉄流山線の車窓からの風景。新興の住宅も目立ちます。
▲流鉄流山駅にて。駅の改札では駅員が切符を切っており、ICカード式の改札はおろか、磁気乗車券の自動改札機も導入されていませんでした!ちなみに駅奥の森林は駅員さん曰く空き地とのこと。ほんの近くに流山市役所がある「旧」市街地です。
■郊外は使い捨て?
濱野 僕の郊外のイメージは「使い捨て」なんですよ。僕は家族で、手狭だった新松戸のマンションから千葉ニュータウンの一軒家に90年ごろに引っ越したんですけど、引っ越したときは空き地だらけで、コンビニもろくにありませんでした。「この町は明らかに失敗だ。マイホームなんていらねえよ!」と思ったんですよね。僕は千葉ニュータウンの都市計画は失敗していると思いますが、その理由は、当時人口が20万人ほどに増えていないといけないのに全然達しておらず、そこに電車を引いてしまたったことにあると思っています。
僕はその後中学受験して都内の学校に2時間かけて通っていたから、青春時代は千葉ニュータウンにほとんどいませんでした。だから何の思い入れもないんですよ。大人になってからも4回しか帰省していない。なぜなら帰りたくないから。何もないし、遠いし、親もうるさいから(笑)。
國分 少年時代の濱野さんはそういう思いだったんだ。俺も「何かおかしい」って感覚があったな。人間のそういう感覚は大事なんだと思う。でも、やはり新松戸の街路樹は象徴的だよ。「町というものがこうやって育っていくんだ」といういい感じがした。
濱野 樹って、植えてみるもんなんですね。他にも、駅から歩いて数分のところに流通経済大のビルができたりしていましたね。大学ができることで町はまた成熟するものだと思います。反面、新松戸は子どもの数が劇的に減っている印象を受けました。象徴的だったのが、住んでいたマンションの近くに妹が生まれた産婦人科があったのですが、その医院が看板を取り外していたことです。
つまり、産婦人科の病院がマンションの側からひとつ無くなることが意味していることですよね。これまたマンションのすぐ近くの「新松戸中央公園」で遊ぶ子どもの数が、土曜の昼下がりという時間帯にも関わらず、昔と比べて少なかったことも印象的でした。
▲流通経済大学・新松戸キャンパス。
▲左手前の屋上のある白い建物が濱野さんの妹さんが生まれた元・産婦人科の病院。濱野さんが住んでいたマンションの10階から望む風景です。
▲新松戸中央公園。広大な運動場ではスポーツチームの子供たちがクラブ活動のスポーツに興じていました。でも、子どもの数はまばら。
■幼少期のアーキテクチャが情報環境研究者・濱野智史を生成した濱野 今日10何年ぶりに新松戸に来てみて、郊外は意外と残っているものだなと感じました。逆に千葉ニュータウンのような町が今後どうなっていくのかにも興味があります。アメリカ風の車社会に最適化していくのだと思いますけど。 それにしても人間というものは環境ひとつでこんなにもどうにもこうにもなってしまうものなのかと。僕はもともとアーキテクチャが人に与える影響を社会学的に研究してきたわけですけれども、そういうことを研究するようになったのには、自分の出自や生育環境が多いに関係していると思います。僕は新松戸ではマンションの10階に住んでいて、4、5歳までエレベーターの10階のボタンを押せなかったんですね。だから家から下の階へは行けずに、上の階に住んでいた一つ年上のお兄さんの家に遊びに行ってファミコンをして、「ゲームすげえ!」と衝撃を受けたりしていました。「ブランコよりこっちだ!」みたいな感じで(笑)。
そこでの生活環境がこうして今の研究につながっていたりするわけです。単に10階に住んでいただけなんですけどね。環境が僕の幼少期の行動を決め、ゲームの環境が人をハマらせ……とか、先ほどの「郊外で生まれ育つと人間が疎外されていく」という話も、環境があっさり人間を作ってしまう典型例だと思います。
國分 街を考える上では、当然のことながらアーキテクチャの視点が重要になってくるということだよね。 -
週刊 宇野常寛のラジオ惑星開発委員会~7月14日放送Podcast&ダイジェスト! ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.122 ☆
2014-07-28 07:00
週刊 宇野常寛のラジオ惑星開発委員会~7月14日放送Podcast&ダイジェスト!
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2014.7.28 vol.122
http://wakusei2nd.com
毎週月曜日のレギュラー放送をお届けしている「週刊 宇野常寛のラジオ惑星開発委員会」。
前回分の放送のPodcast&ダイジェストをお届けします。
7月14日(月)21:00~放送※7月21日(月・祝)の放送はお休みでした
「週刊 宇野常寛のラジオ惑星開発委員会」■(宇野常寛海外渡航中につき)代打パーソナリティ
濱野智史(情報環境研究者・アイドルプロデューサー)
twitter
http://twitter.com/hamano_satoshi
■ゲスト
PIPメンバー
「アイドルをつくるアイドル」をコンセプトとして、濱野智史さんがプロデュースするアイドルグループ「PIP:Platonics Idol Platform」のメンバーが登場!
登場メンバー:石川野乃花・牛島千尋・空井美友・鈴木伶奈・豊栄真紀・羽月あずさ・濱野舞衣香・森崎恵・山下緑・柚木萌花
PIP公式サイト
http://platonics.jp/
▼7/14放送のダイジェスト
☆オープニングトーク☆
今週は宇野常寛が海外渡航中につき、濱野智史さんが代打パーソナリティを担当! 濱野さんが「patagonia」の同じ柄のTシャツを8枚所有している理由とは!? そして、PIPのコンセプトとその狙いとは?
☆PIPメンバー紹介☆
ラジ惑史上過去最大の10人ゲスト!PIPメンバーが各30秒で自己紹介していき、ニコ生アンケートで印象的だった3人を選抜してトークします。
☆ムチャぶりスケッチブック☆
トミヤマDが考えた話題からニコ生アンケートでトークテーマを決定。今回は「集団的自衛権について」牛島千尋さん、森崎恵さん、山下緑さんにお話いただきます。どりーこと山下緑さんは、自身の政治的心情を明らかにします!
☆48開発委員会☆
PIPのドルオタメンバー石川野乃花さん、豊栄真紀さん、濱野舞衣香さん、柚木萌花さんが、それぞれの推しメンの魅力を語ります。もかろんこと柚木さんNMB48薮下柊ちゃん論がアツい!
☆今週の一本☆
空井美友さん、鈴木伶奈さん、羽月あずささんが、自分がいちばん語りたいものについて自由にトーク! 空井さんは千葉ロッテの魅力について熱弁をふるいます。
☆メール読み☆
これまでのコーナーで活躍したメンバーでメール読みします。「PIPでやってみたいことは」という質問に、山下緑さんが児童養護施設をつくるという夢を語ります。
☆延長戦トーク☆
メンバー全員登場で、今回の放送の感想トークをします。濱野Pからの公開ダメ出しも!?