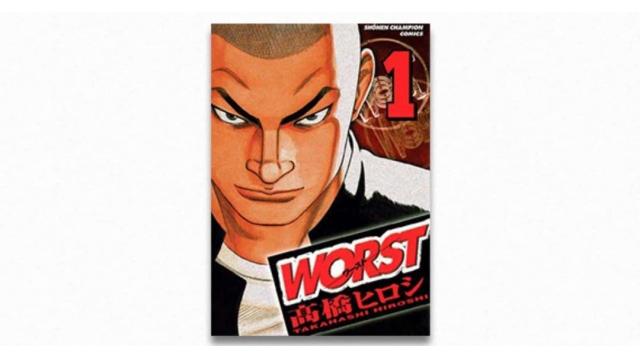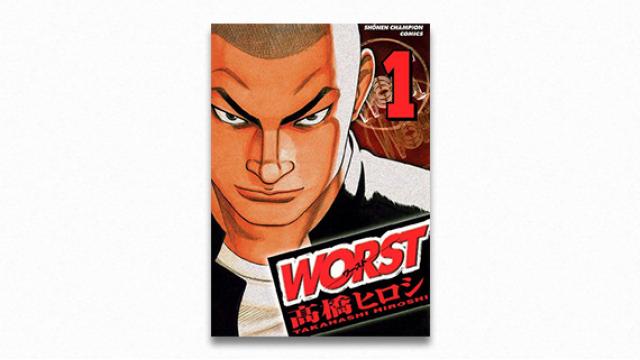-
坊屋春道を/から「卒業」させる/する方法 『WORST』| 宇野常寛
2020-06-08 07:00
今朝のメルマガは、『宇野常寛コレクション』をお届けします。今回は、髙橋ヒロシによるヤンキー漫画『WORST』を取り上げます。1990年代を代表する傑作不良漫画『クローズ』の続編として描かれ、12年の歳月をかけて2013年に完結した『WORST』。前作主人公・坊屋春道なきあとの鈴蘭男子高校の抗争を通じて描かれた、「最強の男」と「最高の男」をめぐる葛藤とは? ※本記事は「楽器と武器だけが人を殺すことができる」(メディアファクトリー 2014年)に収録された内容の再録です。
宇野常寛コレクション vol.23坊屋春道を/から「卒業」させる/する方法 『WORST』
〈「オレはおまえらと同じで/よそを放り出されて鈴蘭へ来たただの勉強ぎらいさ/ただちょっと違うのは/オレはグレてもいねーしひねくれてもいねえ!/オレは不良なんかじゃねーし悪党でもねえ!!〉
髙橋ヒロシによる90年代を代表するヤンキー漫画『クローズ』は、主人公・坊屋春道の自分は不良「ではない」という宣言ではじまった。引用したのはそんな彼=春道が物語の冒頭、転入してきたばかりの高校で貴様は何者だと問われたときの返答だ。 舞台となる架空の高校・鈴蘭男子高校はとある街にあるいわゆる「底辺」高校だ。不良少年の巣窟である同校では、その社会の「覇権」をめぐって常に派閥抗争が繰り広げられている。しかし所属する生徒の大半が不良高校生である鈴蘭は常に群雄割拠の状態にあり、もう何世代にもわたり「統一政権」が生まれていないのだという。世代を超えて数えきれないほどの不良少年がその統一を夢見て入学し、3年間をケンカに明け暮れて過ごし、そして鈴蘭統一の志半ばで卒業していく……そんなループが永遠に続く世界に、春道は転校してきたのだ。 春道は圧倒的な戦闘力を見せつけ、彼に戦いを挑む鈴蘭内の各派閥の領袖たちをことごとく破ってゆく。その勇名はやがて彼を他校との抗争の中に導いてゆくが、春道はその挑戦者たちをもことごとくほぼ初戦でノックアウトしてゆく。なぜ春道は「強い」のか。 答えは既に春道自身の口から語られている。春道は「グレてもい」なければ、「不良なんか」でもないからだ。 坊屋春道は劇中でほとんど唯一、鈴蘭の統一など不良少年社会での権力の獲得に興味を「示さない」人物として描かれている。そう、「グレてもいない」し「不良でもない」春道は単に「勉強が嫌い」で「ケンカが好き」なだけで、決してアウトローであることに意味を見出していないのだ。したがって「鈴蘭のてっぺん」にも「大人社会への反抗」にも興味がない。彼が戦う理由はふたつ、仲間を守るためと自分の快楽、面白さのためだ。そんな春道に、鈴蘭の統一や不良少年社会での覇権を夢見る少年たちが次々と挑戦し、そして敗れていくことで物語は進行する。
これが意味するところは何か。髙橋ヒロシがここで描いているのは、ヤンキー漫画がその数十年の歴史の中で育んできた男性ナルシシズムの更新、「カッコイイ男」のイメージの更新だ。そう、髙橋ヒロシの作品世界において「強さ」とは「カッコよさ」の、「男」の価値を反映したものに他ならない。より「カッコいい」男こそが、より「強い」のだ。したがって、作中ほぼ無敵の坊屋春道は髙橋ヒロシの生み出したあたらしい「カッコよさ」を体現するキャラクターに他ならない。
春道は不良少年たちの世界──思春期の数年間だけそこに留まることができるモラトリアム空間、疑似的な社会──の中での自己実現に拘泥する少年たちの挑戦を愛情をもって次々と退ける。「不良」である彼らは一般の社会から疎外されたアウトローであるという自覚を持ち、それゆえにもうひとつの社会での自己実現を権力奪取というかたちで目論む。しかし、そんな自己実現に全く興味を示さない春道に敗れることで、彼らはことごとく転向してゆく。疑似社会での期間限定の自己実現ではなく、ケンカすることそれ自体を楽しみ、魂を燃焼させることに美的な達成を見るという春道の示したモデルに転向してゆくのだ。(劇中で春道と互角以上の戦いを展開することができたのは、同様に権力闘争に興味を持たない林田恵・通称リンダマンのみだ。) ここで髙橋が坊屋春道という男に託したのは、これまでのヤンキー漫画の美学の延長線上にありながらも、少なくとも従来の意味では「グレてもい」なければ、「不良なんか」でもない、しかし明らかにこの国の「ヤンキー」文化の延長戦上にあるあたらしい「男」の理想像に近づいていくのだ。、「大人社会への反抗」に意味を見出し、アウトローであることにアイデンティティを見出さ「ない」男の理想像に他ならない。だからこそ、この物語では従来のモデルの不良少年が春道の影響下に転向してゆくという物語が描かれたのだ。
そんな坊屋春道の最後の戦いは、全国的な勢力を誇る不良少年グループ「萬侍帝國」の幹部・九頭神竜男とのタイマンだ。不良少年社会=疑似社会の頂点に君臨する九頭神はまさにこの物語で描かれてきた古い、従来の「不良」を代表する存在だ。そう髙橋ヒロシは物語の結末に、春道のこれまでの戦いとは何だったかを総括し、改めて読者に示すエピソードを配置したのだ。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
宇野常寛 月島花は坊屋春道を超えられたか――クローズ/WORSTが描いた男性性の臨界点(PLANETSアーカイブス)
2019-03-29 07:00
今朝のPLANETSアーカイブスは、宇野常寛による髙橋ヒロシ論をお届けします。傑作不良漫画『クローズ』の続編として描かれ、12年の歳月をかけて昨年完結した『WORST』。坊屋春道なきあとの鈴蘭を描いた本作を通じて見えてくる『クローズ』が描いた男性性の臨界点とは。(初出:ダ・ヴィンチ2013年11月号) ※この記事は2015年3月16日に配信された記事の再配信です。
〈「オレはおまえらと同じで/よそを放り出されて鈴蘭へ来たただの勉強ぎらいさ/ただちょっと違うのは/オレはグレてもいねーしひねくれてもいねえ!/オレは不良なんかじゃねーし悪党でもねえ!!〉
髙橋ヒロシによる90年代を代表するヤンキー漫画『クローズ』は、主人公・坊屋春道の自分は不良「ではない」という宣言ではじまった。引用したのはそんな彼=春道が物語の冒頭、転入してきたばかりの高校で貴様は何者だと問われたときの返答だ。舞台となる架空の高校・鈴蘭男子高校はとある街にあるいわゆる「底辺」高校だ。不良少年の巣窟である同校では、その社会の「覇権」をめぐって常に派閥抗争が繰り広げられている。しかし所属する生徒の大半が不良高校生である鈴蘭は常に群雄割拠の状態にあり、もう何世代にもわたり「統一政権」が生まれていないのだという。世代を超えて数えきれないほどの不良少年がその統一を夢見て入学し、3年間をケンカに明け暮れて過ごし、そして鈴蘭統一の志半ばで卒業していく……そんな無限ループが永遠に続く世界に、春道は転校してきたのだ。
春道は圧倒的な戦闘力を見せつけ、彼に戦いを挑む鈴蘭内の各派閥の領袖たちをことごとく破ってゆく。その勇名はやがて彼を他校との抗争の中に導いてゆくが、春道はその挑戦者たちをもことごとくほぼ初戦でノックアウトしてゆく。なぜ春道は「強い」のか。
答えは既に春道自身の口から語られている。春道は「グレてもい」なければ、「不良なんか」でもないからだ。
坊屋春道は劇中でほとんど唯一、鈴蘭の統一など不良少年社会での権力の獲得に興味を「示さない」人物として描かれている。そう、「グレてもいない」し「不良でもない」春道は単に「勉強が嫌い」で「ケンカが好き」なだけで、決してアウトローであることに意味を見出していないのだ。したがって「鈴蘭のてっぺん」にも「大人社会への反抗」にも興味がない。彼が戦う理由はふたつ、仲間を守るためと自分の快楽、面白さのためだ。そんな春道に、鈴蘭の統一や不良少年社会での覇権を夢見る少年たちが次々と挑戦し、そして敗れていくことで物語は進行する。
これが意味するところは何か。髙橋ヒロシがここで描いているのは、ヤンキー漫画がその数十年の歴史の中で育んできた男性ナルシシズムの更新、「カッコイイ男」のイメージの更新だ。春道は不良少年たちの世界──思春期の数年間だけそこに留まることができるモラトリアム空間、疑似的な社会──の中での自己実現に拘泥する少年たちを愛情をもって退ける。「不良」である彼らは一般の社会から疎外されたアウトローであるという自覚を持ち、それゆえにもうひとつの社会での自己実現を権力奪取というかたちで目論む。しかし、そんな自己実現に全く興味を示さない春道に敗れることで、彼らはことごとく転向してゆく。疑似社会での期間限定の自己実現ではなく、ケンカすることそれ自体を楽しみ、魂を燃焼させることに美的な達成を見るという春道の示したモデルに転向してゆくのだ。(劇中で春道と互角以上の戦いを展開することができたのは、同様に権力闘争に興味を持たない林田恵・通称リンダマンのみだ。)
ここで髙橋が坊屋春道という男に託したのは、これまでのヤンキー漫画の美学の延長線上にありながらも、少なくとも従来の意味では「グレてもい」なければ、「不良なんか」でもない男の理想像、「大人社会への反抗」に意味を見出し、アウトローであることにアイデンティティを見出さ「ない」男の理想像に他ならない。だからこそ、この物語では従来のモデルの不良少年が春道の影響下に転向してゆくという物語が描かれたのだ。
そんな坊屋春道の最後の戦いは、全国的な勢力を誇る不良少年グループ「萬侍帝國」の幹部・九頭神竜男とタイマンだ。不良少年社会=疑似社会の頂点に君臨する九頭神はまさにこの物語で描かれてきた古い、従来の「不良」を代表する存在だ。そう髙橋ヒロシは物語の結末に、春道のこれまでの戦いとは何だったかを総括し、改めて読者に示すエピソードを配置したのだ。
タイマンの前半、春道は九頭神に対して劣勢を見せる。戦いを見守るのは春道の後輩・花澤(通称ゼットン)と九頭神の舎弟・トシオだ。呑気にタイマンを見守るゼットンに、トシオは問いかける。「おまえアニキ分がやられているのによくそんなもん食ってられるな!」と。しかしゼットンは動じない。それどころか「オレはあの人(春道)の子分でも舎弟でもない」と告げる。これは間違いなく、春道がその登場時に述べた自己規定の言葉と対応したものだ。「不良」でもなければ「グレて」もいない春道の後輩は「子分」でも「舎弟」でもないのだ。そしてゼットンはトシオに告げる。「九頭神竜男が最強の男なら坊屋春道は最高の男よ! たかが最強程度で最高に勝てるわけがねーだろうが!」と。
「最強の男」とは何か。それはアウトローたちのもうひとつの世界での自己実現=権力奪取を夢見る少年たちの到達点だ。現実の社会と歴史に生きる証を見つけられなくなった代わりに、もうひとつの社会ともうひとつの歴史を生きることで自己実現を果たそうとするアウトローたちの到達点だ。対して「最高の男」とは何か。それは「最強の男」が目指す疑似社会での自己実現に背を向け、いま、ここの一瞬の魂のきらめきに美的な達成を見出す生き方だ。何かのために戦う(ケンカする)のではなく、戦うこと自体が目的なのだ。ある自己実現のモデルを追求し、その中で強弱を競い勝ち抜いた人間が「最強」だとするのなら、最初からそのモデルの限界を前提とし、別のモデルを追求している人間が「最高」なのだ。「最強」が「最高」に「勝てるわけがない」のはそのためだ。
『クローズ』の世界にはたとえばほとんど「大人」と「女性」が登場しない。そう、彼らには乗り越えるべき「父」も、守るべき「女」も存在しないのだ。かつての男性的なもの=最強の男が通用しなくなった新しい世界の、あたらしい男性性のモデルを提示すること、それが『クローズ』の主題であり坊屋春道が体現した「最強から最高へ」の変化なのだ。(そして髙橋ヒロシの手を離れ、オリジナルのストーリーが展開する前日譚の映画「クローズZERO」シリーズはまさに、主人公が父を乗り越え、ヒロインを救い鈴蘭統一を目指す「最強の男」の物語として描かれ、春道の転入直前の春に主人公が鈴蘭を統一を果たせずに卒業するシーンで終わる。映画版の制作者たちは、髙橋ヒロシが坊屋春道という主人公を通して『クローズ』が提示した世界観の本質を正しく理解し、新旧の主人公を対照的に配置したのだろう。)
そして物語は春道の影響下に「最強」から「最高」へとその生き方を変化させていった少年たちの卒業を描いて幕を下ろす。ある者は大工、ある者はボクサー、ある者はミュージシャン──それぞれの夢を現実社会の中に見出し、彼らは卒業していく。たとえその夢が実現できなくとも、夢を追うその過程に快楽を見出すことができれば、彼らは「最高」でいられるだろう。しかし、物語のエピローグは読者をあたらしい迷宮へといざなっていく。当の春道だけが、「最高の男」の頂点に立つ坊屋春道だけが「卒業」することができず、留年し鈴蘭高校に留まったことがエピローグでは描かれるのだ。
そう、この物語では坊屋春道だけが「卒業」することができなかったのだ。もっと言ってしまえば春道だけが「成長」することができなかったのだ。なぜならば、『クローズ』における成長=卒業とは「最強の男」的な生き方からの「卒業」であり、登場した時点で既に「最高の男」である春道にはその必要がなかったからだ。
では、春道はその後どこに向かっていけばいいのだろうか。この巨大な問いに立ち向かったのが、『クローズ』の続編である『WORST』だ。
■ PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
宇野常寛『母性のディストピア EXTRA』第3回 坊屋春道はなぜ「卒業」できなかったのか
2018-03-09 07:00
2017年に刊行された『母性のディストピア』に収録されなかった未収録原稿をメールマガジン限定で配信する、本誌編集長・宇野常寛の連載 『母性のディストピア EXTRA』。90年代を代表するヤンキー漫画『クローズ』の登場人物の中で、唯一勝利や覇権に興味を示さなかった坊屋春道。ヤンキー社会の擬似的な自己実現に無関心だからこそ「最高」の男でありえた春道は、仲間たちが「成長」するなかなぜ「卒業」できなかったのか--? (初出:集英社文芸単行本公式サイト「RENZABURO[レンザブロー]」)
▲『クローズ(1)』
「最強の男」から「最高の男」へ
高橋ヒロシ『クローズ』は90年代を代表するヤンキー漫画である。月刊「少年チャンピオン」に1990年から1998年まで連載されていた同作は、マイナー雑誌の掲載と言うこともあり決してメジャーな作品ではなかった。しかしヤンキー漫画ファンのあいだで9年の長期連載のあいだにじわじわとファンを獲得、さらには松本人志など芸能人のマスメディアによる紹介などでその支持を拡大していった。2000年代にはその前日譚的な物語を描く『クローズZERO』が二回にわたって映画化されいずれもヒットを記録している。現在もその続編『WORST』が連載中で高い支持を得ており、高橋ヒロシおよび『クローズ』シリーズは現代におけるヤンキー漫画を代表する存在であると言えるだろう。
なぜ高橋ヒロシで、なぜ『クローズ』なのか。本連載の読者は疑問に感じるかもしれない。しかし本連載でこれまで論じてきた問題を追究する上で、高橋ヒロシという作家について論じることは非常に大きな意味をもつと私は考えている。そのためにまず『クローズ』の概要をもう少し詳しく説明しよう。
物語の舞台は「とある街」とされる。地名は明かされないが、作中の描写から考えて人口数万〜十数万人の地方都市と思われる。(ファンコミュニティにおいては高橋の在住している長野県松本市がモデルと言われている。)この「とある街」のいわゆる「底辺」高校(男子校)が鈴蘭高校だ。「カラスの学校」の異名を持つこの鈴蘭高校は、地域でも有数の不良生徒の集まる学校として知られている。と、いうより全校生徒の大半がいわゆる「不良生徒」であり、彼らはそれぞれ数人から数十人、多い場合は百人単位で派閥を構成し、学校社会の覇権を獲得するために日々抗争を繰り返している。物語の前半はこの鈴蘭高校内の派閥争いが、中盤以降は他校との抗争が描かれることになる。だが、物語の主人公の春道は、いや春道だけはこの覇権抗争に一切興味を示さない。
〈オレはおまえらと同じで/よそを放り出されて鈴蘭(ここ)へ来たただの勉強ぎらいさ/ただちょっと違うのは/オレはグレてもいねーしひねくれてもいねえ!/オレは不良なんかじゃねーし悪党でもねえ!!〉
これは序盤のエピソードで「お前は一体何ものだ」と尋ねられた春道が自らのスタンスを語る場面での台詞である。そう、彼は不良でもなければグレてもいない。作中最強クラスの戦闘力をもつ主人公でありながら、権力抗争に一切関心がないだけではなく、ここで春道はそもそも自分は「不良」ではないと宣言している。春道は単に「勉強が嫌い」で「ケンカが好き」なだけで、決してアウトローであることに意味を見出していないのだ。したがって「鈴蘭のてっぺん」にも「大人社会への反抗」にも興味がない。春道の行動原理は目の前の快楽(楽しそうなことがある、女の子と知り合える)の追求と、仲間を守る、このふたつだけなのだ。圧倒的な戦闘力(ケンカの強さ)をもち、鈴蘭とその周辺をめぐる状況を一変させることができる春道だが、劇中の登場人物の中で彼だけがそんな勝利と覇権に興味を示さないのだ。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
なぜ"マイルドヤンキー"を描けなかったのか――松谷創一郎×宇野常寛が語る『クローズ EXPLODE』 ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.096 ☆
2014-06-19 07:00
なぜ"マイルドヤンキー"を描けなかったのか
――松谷創一郎×宇野常寛が語る『クローズ EXPLODE』
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2014.6.19 vol.096
http://wakusei2nd.com
ゼロ年代国内映画市場に大きなインパクトを残した『クローズZERO』『ZERO Ⅱ』。
そして今春、キャストと設定を一新して公開されたさらなる続編『クローズ EXPLODE』は、
高橋ヒロシが作り出したこの「鈴蘭」という箱庭世界にどうアプローチしたのか!?国内映画の動向に詳しいライター/リサーチャーの松谷創一郎と、大の『クローズ』好きでもある宇野常寛が語った。
初出:『サイゾー』2014年6月号(サイゾー)
近年のヤンキーマンガの金字塔である『クローズ』が、最初に映画化されたのは07年の『クローズZERO』だ。小栗旬・山田孝之主演の“イケメン映画”としても人気を博してヒットを果たした同作は09年に続編『ZEROⅡ』も公開された。そしてこの春、さらなる“新章”として再び『クローズ』映画が登場。キャストも設定も一新された『EXPLODE』、そのワルさのほどは──?◎構成:藤谷千明
▲『クローズEXPLODE』
監督/豊田利晃 脚本/向井康介、水島力也 出演/東出昌大、柳楽優弥、勝地涼ほか 配給/東宝 公開/14年4月12日 高橋ヒロシのマンガ『クローズ』映画化シリーズの新章と位置づけられ、前2作から出演者を入れ替えた新作。前作『ZERO』の3年生たちが卒業したことにより空席となった鈴蘭高校の頂点を目指す内部抗争に加え、不安定な状態にある鈴蘭を狙う他校や周辺地域のヤクザらアウトローが絡み合う、盛大な勢力争いが始まる──。
【対談出席者プロフィール】松谷創一郎(まつたに・そういちろう)
1974年生まれ。著書に『ギャルと不思議ちゃん論』(原書房)、『どこか〈問題化〉される若者たち』(共著/恒星社厚生閣)など。
■『クローズ』新章――大ヒットした『ZERO』2作を超えられるのか?
宇野 『クローズ EXPLODE』(以下、EXPLODE)は今年の邦画の中では面白いほうだけど、『クローズZERO』(以下、ZERO)【1】、『クローズZEROⅡ』(以下、ZEROⅡ)【2】の前2作ほどのエポック感はなかったですね。野心的なことをやろうとした形跡はあるけど、あまり成功しているとは言えない。前2作は映画界全体と闘っていたというか、国内のエンタメシーン全般に対してインパクトがあったと思うんだけど、今回はすでに確立された『クローズ』ブランドの中での比較的大きい花火にしかなっていない感じがした。及第点と褒められる映画の中間くらいにある作品かな、と。
松谷 僕も同じ感想ですね。
宇野 松谷さんは本作を、今年の邦画の中でどう位置づけますか?
松谷 日本映画自体が去年から引き続いて低調な状況です。企画が細っている中で、「貴重なアクション映画」であることは特筆すべきことでしょう。日本映画は、アクションが弱いですからね。こうした中でシリーズものの『EXPLODE』は内容も及第点、興行収入もおそらく10億円を超えるでしょうから、十分に健闘してる。ただ、『ZERO』の興行収入25億円、『Ⅱ』の30億円と比べると弱いし、「Yahoo!映画」のレビュー点数が前2作に比べて異様に低い。原作や前作ファンが、かなりがっかりしていることがうかがえます。
宇野 一言でいうと、『ZERO』ってゼロ年代の邦画ブームの、一番いい時期の大花火だったんですよね。あの時期は、メジャーシーンでヒットを狙いながらも、いや、メジャーだからこその大予算を用いてチャレンジングなことをやれる空気があって、そして作品的にも成果を残したものがいくつかあった。その代表例が『ZERO』と『告白』だったと思う。
松谷 06年に21年ぶりに邦画のシェアが洋画を逆転し、以降現在まで好調な日本映画の波を作ってきた作品のひとつといえるでしょうね。07年に『ZERO』、09年に『ZEROⅡ』、10年に『告白』。ゼロ年代後期の日本映画を語る上で、『ZERO』はもっと見直されてもいい作品です。
宇野 そういういい流れがあったのに、その遺伝子が今はあまり残っていないんだなということが、今の邦画の状況をみるとよくわかる。その中で『EXPLODE』はすごく健闘しているんだけど、前2作や原作といかに闘うかというところで力尽きていて、独自の表現を確立するまでには至っていない。
松谷 マンネリ感もありますよね。ただ、それはキャストで克服できる問題だとも思いました。だって浅見れいなが一番よかったと思うくらい、前2作と比べてキャラが弱まっていた。主人公の鏑木旋風雄【3】役の東出昌大の演技も決して良くなかった。この撮影は『ごちそうさん』【4】の前でしょうしね。
宇野 『ごちそうさん』をやって鍛えられた後の今の東出くんなら、もっといけただろう、と。
松谷 そう。ただ、脇役もそんなに良くなかったんですよ。『ZERO』は、線が細くて作品的にはどうしても狂言回し的な役回りになる小栗旬【5】を、山田孝之や高岡蒼甫といった役者がしっかりとバックアップしていた。一応今回も、柳楽優弥(強羅徹役)【6】がいたけれど、それでも弱かった。
宇野 あとは勝地涼(小岐須健一役)【7】が与えられた役割を一生懸命こなしてるくらいかな。あれだけたくさん登場人物がいた中で、あの2人しか印象に残ってない。『ZERO』の2作を踏襲しようとし過ぎていて、例えば強羅のキャラクターって、ほぼ『ZERO』の芹沢多摩雄(山田孝之)【8】から貧乏っていう設定を抜いただけじゃない。というか、そもそも今回はキャラが多すぎたと思う。
松谷 キャラが立ってないんですよ。三代目J Soul Brothersの2人(ELLY、岩田剛典)は特にそうでした。例えば『ZEROⅡ』で漆原凌(綾野剛)【9】が傘を差して出てきたシーンはすごく記憶に残ってるじゃないですか。彼はあれが出世作になりましたよね。そういう掘り出し物な感じの役者が今回はいない。
宇野 今回でいうと早乙女太一【10】が本当はそうなるはずで、悪くないけど柳楽優弥に負けてたよ。藤原一役の永山絢斗【11】も同様で、悪くはないんだけど……という。総合点は決して低くないんですよね。主演の東出くんも、演技力には問題があったかもしれないけど、フィジカル的な存在感はあったと思う。脚本に関しても「これだけ勢力がいて話がまとまるのかな?」と思ったけど、終わった後には「よくまとめたな」という印象を持った。でもやっぱりヤクザやOBのオッサンのドラマに頼っているところが弱いとも思う。
原作の『クローズ』の世界では大人や女性がほぼ出てこず、不良男子高校生だけが存在する世界になっているでしょう? あれって要は今でいう「マイルドヤンキー」的な世界観の先駆けだと思うんですよ。「守るべき女」とか「反抗すべき教師」や「超えるべき父」がいない世界で、ヤンキーはアウトローでもなんでもなく、趣味でケンカをしているだけ。
けれど、今ようやくオヤジ論壇がマイルドヤンキー的なものに気づき始めたことが象徴的だけれど、東京の鈍感なホワイトカラー層を観客に巻き込むには、従来のヤンキー観やアウトロー観に接続するためのクッションが必要だったと思うんですよね。だから、『ZERO』では大人や女子を配置していて、まさに「ゼロ」というか『クローズ』の世界観の入門になっていた。その「『クローズ』とは何か」というメタ解説的な要素は今回も踏襲されていたけれど、『EXPLODE』の場合はそれを構造ではなくてセリフや安っぽいトラウマエピソードで説明していて、僕は「そういうのが全部キャンセルされているのが”鈴蘭”なのに」と思った。
もっというと、『ZERO』2作はそのまま「高橋ヒロシ」と「三池崇史」だった。つまり、「マイルドヤンキー」的世界観の代名詞である『クローズ』と、三池監督が撮ってきた日本のヤクザ映画が、そのまま滝谷源治と父親(岸谷五朗)の関係になっていた。そうやってその2つの中間をうまく立てて、学園の外側の要素を本当に最小限にして「鈴蘭入門」のドラマを作ることができていたんだけど、『EXPLODE』はドラマを構成しているのが鈴蘭の外側にいる人たちになってしまっていた。
松谷 そこはやっぱりプロデューサーの山本又一朗【12】の考えなんだと思いますよ。脚本にクレジットされている「水島力也」は山本さんの変名ですが、もう還暦を迎えている人だから、「理由なく何かを目指す」ということが考えづらいのかもしれない。結果、今回も「父親との葛藤」みたいな動機付けをしてしまったのでしょう。
宇野 その「理由なく何かを目指す」ことが気持ちいいっていうのが高橋ヒロシイズムなのに、そこを理解しないで描いてしまっていたんじゃないか。「なんでガキの喧嘩に夢中にならないといけないんだ」という藤原のセリフがあったけど、あれはまさに脚本家の叫びだと思うんですよ。原作に対して無理解な人間が、無理やり自分に言い聞かせるために饒舌に言い訳を重ねているみたいな印象を受けた。原案を山本又一朗が握っているとはいえ、豊田利晃【13】監督と向井康介【14】脚本なわけですよ。90年代サブカルの血を引いたゼロ年代中堅コンビがビッグタイトルに挑戦した結果、ベテラン三池崇史と若手の武藤将吾【15】のコンビの『ZERO』に負けてしまったというか。前2作からのマンネリを回避するためにいろんな策を講じていたのもわかるし、複雑なプロットをなんとかしようと頑張っていたとは思うんだけど。
■豊田利晃監督復活作?「内面」を捨てた面白さ
松谷 豊田監督の話をすると、復帰後の3作が正直、悪い意味で「よく今の時代にこんなことできるな」というような作品ばかりでした。ユナボマー事件をヒントにした『モンスターズクラブ』(12)は主人公が自問自答してるだけだし、『I’M FLASH!』(12)も新興宗教の教祖がどんどん内閉的になる作品。そこに『EXPLODE』がきたから、考えようによっては、今回「復活」と捉えていいんじゃないかと思うんです。豊田監督は自分で脚本を書くし、『青い春』『空中庭園』以外はオリジナル作品。そんな彼が、演出だけでもここまでエンターテインメントなことができる、ということを証明したとも言えるわけです。もちろん、そこには若い頃の『ポルノスター』にあったようなゴツゴツした才気みたいなものは見られないですが。
宇野 結局それって、豊田さんのような、ゼロ年代のインディーズ系、単館系の映画をつくってきた90年代サブカルに出自を持つ映画監督たちの、現代的な疎外感を男の子の自意識問題に仮託するアプローチの文法自体が古くなっているってことなんじゃないかな。
松谷 でしょうね。中年監督の若者気分がいかにくだらないかってことなんですよ。でもそれは映画ムラでは温存されてしまう。映画マニアや評論家は映画しか見ないし、そういう自意識問題を抱えている中年ばかりだから。そう考えると今回の豊田監督の使い方っていうのは、うまい落とし所を見つけたと思えます。
宇野 このくらいの世代の監督って2系統あると思うんですよね。ひとつは「山下敦弘マイナス才能」というか、男の子の自意識問題と童貞マインドをどう維持するかにしか興味がないような一群。
1 / 1