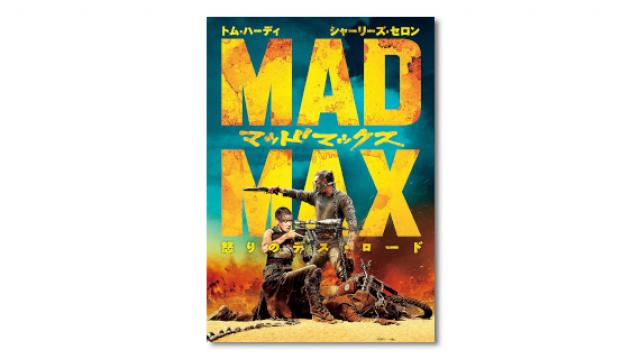-
宇野常寛 NewsX vol.34 ゲスト:森直人 「映画にとってMCUとは何か」【毎週月曜配信】
2019-06-17 07:00
宇野常寛が火曜日のキャスターを担当する番組「NewsX」(dTVチャンネルにて放送中)の書き起こしをお届けします。5月14日の放送のテーマは「映画にとってMCUとは何か」。映画評論家の森直人さんをゲストに迎え、ディズニーやサブスクリプションサービスといった巨大資本のもと、MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)がどのように映画を変えていったのかについて議論します。(構成:籔和馬)
NewsX vol.34 「映画にとってMCUとは何か」 2019年5月14日放送 ゲスト:森直人(映画評論家) アシスタント:後藤楽々
宇野常寛の担当する「NewsX」火曜日は毎週22:00より、dTVチャンネルで生放送中です。 番組公式ページ dTVチャンネルで視聴するための詳細はこちら。 なお、弊社オンラインサロン「PLANETS CLUB」では、放送後1週間後にアーカイブ動画を会員限定でアップしています。
アイアンマン=個人とキャプテン・アメリカ=国家の関係
後藤 NewsX火曜日、今日のゲストは映画評論家、森直人さんです。宇野さんと森さんは長い付き合いなんですよね?
宇野 もう10年以上の付き合いですよね。気がついたら、長いですね。
森 それこそ10年ぐらい前にMCUが始まったときが最初の出会いだったような気がするんですよ。
宇野 森さんは、僕が最も信頼する映画評論家の人のひとりなんだよ。
森 いやいや、恐縮でございます。
宇野 僕は個人的に森さんが書いたものの読者で、僕のほうから是非ともウチの媒体で書いてくださいと声をかけて、それからずっと付き合っています。
森 でも、ちょいちょい良いタイミングで呼んでいただいて、それで毎回おもしろい話なので、今日も『アベンジャーズ/エンドゲーム』(『エンドゲーム』)とMCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)いうテーマもさすが。これは宇野さんと話したかった。
後藤 いつぶりなんですか?
森 前は『ラ・ラ・ランド』と『ダンケルク』のふたつを(音楽ジャーナリストの)柴那典さんと話したときに、宇野さんも一緒だった。1年に1回ぐらいは会うんちゃう?
宇野 なんだかんだで1年に1回ぐらいですね。
森 だから、その年の一番注目すべきタイトルが出てくると会うよね。今年は早くも出ちゃったけどね。
宇野 その度に森さんと話さなきゃという気になって、毎回いろいろと理由をつけて呼んでいます。
後藤 今日のテーマは「映画にとってMCUとは何か」です。
宇野 前半は歴代のMCUの歴代の22作品を振り返りながら、各作品について話して、後半はMCUというシリーズ自体が今の映画産業、エンターテイメント、映画という表現自体に対して、どういう影響を長期的にもたらすのかというところまでいけたらいいなと思っています。
後藤 最初のキーワードは「いま、MCUを振り返る」です。
宇野 『アイアンマン』から『エンドゲーム』に至る、トニーがアイアンマンになってから、トニーが死ぬまで22作を順に振り返りながら、森さんと話していけたらと思います。
後藤 年表がこちらです。
宇野 MCUが始まったのが2008年だから、もう11年前ですね。
森 『アイアンマン』は2008年公開でしょ。ここにDCの作品を並べると、面白いんですよ。『ダークナイト』が同じ2008年公開なんですよ。この頃、マーベルとDCはいい勝負というか、DC勝っているんじゃないかぐらいの勢いがありましたよね。
宇野 DCは『ダークナイト』がヒットして『アベンジャーズ』が公開されるまでは、興行収入的にも、映画の評価的にも勝っているんですよね。
森 それがこの10年で逆転しちゃったのも、ひとつの歴史なんですよ。フェイズ1のあたりは、完全にオバマが調子いい時代なんですよ。オバマは2009年の初頭に大統領就任でしょ。だから、『アイアンマン』の1作目はすごく明るくて「イエス・ウィー・キャン」感がすごいんですよ。
宇野 『アイアンマン』と『ダークナイト』の公開時期はほとんど離れていない。でも、『ダークナイト』はブッシュ時代の総括でテーマ的にも露骨に9.11以降のアメリカのさまよえる正義をどう引き受けるかという、すごく時代に沿ったテーマと寝て、世界的に大ヒットした映画なんですね。対して、『アイアンマン』はブッシュ時代があって、オバマに切り替わって、その古き良きアメリカの正義が完全に滅んだ後に、もう一回どのようにしてアメリカらしさを、もっと言えばアメリカ的な男性性を定義するのか、という部分が前面に出ていた。
森 だから、この話を宇野さんとしたかった。MCUの最初は、そこからなんだよね。初期はDCの作品が暗くて、マーベルの作品は明るかった。ただ、だんだんオバマが怪しくなってくると、マーベルの作品も暗くなる。
宇野 クリストファー・ノーランの『ダークナイト』三部作を仮想敵にしていたことは、もう間違いないですよね。元々DCとマーベルはレーベル的にもライバルだし、『アイアンマン』の冒頭もアフガニスタンのシーンから始まる。トニー・スタークというキャラクターに託された、イラク戦争以降のアメリカンマッチョイズムを信じられなくなった男性性の在り方が、『アイアンマン』のテーマ。『アイアンマン』は2や3を観ても、基本的にはトニーの自分探しの話なんですよ。
森 完全にそうですよね。次のエポックでいうと、フェーズ2の『キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー』(『ウィンター・ソルジャー』)かな。この映画の監督は、『エンドゲーム』のアンソニー&ジョー・ルッソ兄弟。MCUにおいて、ルッソ兄弟の監督作がひとつの大きな生命線になっている。最初が『ウィンター・ソルジャー』なんですよ。次が後半になっちゃうんですけども、『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』(『シビル・ウォー』)。次が『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』(『インフィニティ・ウォー』)。そして、『エンドゲーム』。この4作はトランプ時代になっていく流れと、気持ちいいくらい連動しています。
宇野 やはり『アイアンマン』と『キャプテン・アメリカ』というのは誰もが認める対の存在なんですよね。『アイアンマン』は、9.11以降の男性性のあり方、「私」のあり方、プライベートをテーマにやったんだよ。対して『キャプテン・アメリカ』はパブリックなんですよね。イラク戦争以降、9.11以降のアメリカの正義をどう再定義するか。特に2作目の『ウィンター・ソルジャー』、あと3作目の『シビル・ウォー』が、そのテーマを正面から引き受けていっている。
森 僕は『ウィンター・ソルジャー』と『シビル・ウォー』を観たときに、DCみたいじゃんと思った。
宇野 『ウィンター・ソルジャー』はエポックでしたよね。『ウィンター・ソルジャー』までのマーベルの映画はエンターテイメントの映画としてはよくできているけれど、クリストファー・ノーランのバットマンが到達している領域を考えると、もっといろんなものを詰め込めるだろうという不満が常にあった。それを『ウィンター・ソルジャー』でかなり追いついてきた。
森 MCUの作品は批評として語るには、ややエンタメ度だけでいきすぎているところがあったんだけれど、『ウィンター・ソルジャー』からは変わったね。特に『シビル・ウォー』は『エンドゲーム』への流れを考えても重要作。
宇野 『シビル・ウォー』は良いですよね。
森 もしかしたら『シビル・ウォー』は『エンドゲーム』を別格にするとシリーズ最高傑作かもな。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
これから映画はオペラ・歌舞伎化していく――『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』が示す「自己参照の時代」の到来(森直人×宇野常寛)(PLANETSアーカイブス)
2018-08-20 07:00
今朝のPLANETSアーカイブスは、『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』をめぐる森直人さんと宇野常寛の対談をお届けします。J.J.エイブラムス監督による本作の「出来の良さ」から見えてくる映画に対する欲望の変化、20世紀の劇映画の名作を参照する二次創作的なアプローチがもたらす新たな課題とは?(初出:「サイゾー」2016年2月号) ※この記事は2016年2月24日に配信した記事の再配信です。
▲Amazon.co.jp『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』 宇野 僕は全然『スター・ウォーズ』マニアではないんですよ。さらに言うと、J.J.エイブラムス【1】も世間ほど高く評価していなかった。『スター・トレック イントゥ・ダークネス』(13年)がそうだったように、脚本のギミックで勝負しようとする作品が多くて、どうにも小賢しく感じていた。映画的な快楽を全然信じていないし使えない人なんだな、と。唯一好きだったのが『SUPER8/スーパーエイト』【2】で、あの作品に現れていた、映画史的なものに対するノスタルジックな視線のほうが、エイブラムスのオタク性が有効に働くと思っていた。今回も彼の二次創作作家としての才能がプラスに働いたんじゃないか。こんなこと言ったらファンに怒られるかもしれないけれど、単純に1本の映画として観た時、シリーズ全7作の中で一番「出来が」いいと思う。これはこれで褒め言葉に聞こえないかもしれないけど(笑)。
【1】 J.J.エイブラムス:1966年アメリカ生まれ。高校・大学時代から映画音楽や脚本に携わり、98年に『アルマゲドン』の脚本に参加。2000年代は『エイリアス』や『LOST』など人気テレビドラマシリーズの脚本を手がけ、05年には『ミッション:インポッシブルⅢ』、その後『スター・トレック』等の監督を務める。
【2】『SUPER8/スーパーエイト』:監督・脚本/J.J.エイブラムス製作/スティーヴン・スピルバーグほか 公開年/11年
79年、オハイオ州で自主制作のゾンビ映画を撮ろうとしていた少年たちは、夜中に線路で貨物列車の炎上事故を偶然撮影する。貨物に積まれていたのは宇宙人であり、彼らの周囲と街全体は恐慌に陥ることに。スピルバーグ監修、エイブラムス監督による『未知との遭遇』『E.T.』へのオマージュ的作品とされる。
森 僕も感想をひと言でまとめるなら「すごく上手」に尽きる。まったくストレスを感じずに楽しみました。とはいえ基本的にそれは想定内で、もしルーカスが監督するんだったら「今度は何をしでかすのか?」と皆ドキドキしていたと思うんですけど(笑)、J.J.がやるとなった時、誰もがある程度安心したんじゃないかな。宇野さんのおっしゃることもよくわかるんですけど、J.J.に対する世間の評価は『スター・トレック』のリブートを優等生的に成立させた時点でかなり固定したと思うので、今回も確実に80点を取ることは予想できていた。でもエピソード7は「無難以上の出来」だったと思う。
宇野 きっちり現代風にアップデートされていましたね。今初期三部作を観ると、恥ずかしくなるくらいストレートに、少年の社会化の物語から始まって父殺しの神話に接続していくというのをやっている。それが今回は、物語構造はほぼエピソード4を踏襲し、主人公格を黒人の青年と若い女の子に分散していて、政治的な配慮と共感のアイコンの分散として非常にうまく機能していた。キャラクター消費として旧来のファンの欲望を満たしつつ、現代の新しい神話として再提示するという役割を果たしていた。その時点でこの映画は、我々の期待しているものをクリアしていたと思う。
もともと『スター・ウォーズ』って、ストーリーは省略が多くて繋がっていないし、ドラマ性もとってつけたような薄っぺらさがあって、脚本・演出共に出来がいいとは言いがたかった。でも発想が新しくてエポックメイキングだからそれでいい、というものだったと思う。新三部作(エピソード1~3)は逆に、現代の技術で世界観を拡張することが望まれていたにもかかわらず、旧三部作と同じテンションで展開されてしまったためにどこか焦点がぼやけていたように思う。今回はその反省から、しっかりとマーケットの要請を押さえていましたよね。加えて、単純に現在の技術で『スター・ウォーズ』をしっかりやると、絵面はそんなに変わらないのにものすごくレベルアップしている。その快楽と、ヒロインの女優がものすごくいいというプラスアルファがあった。まさかエイブラムスの撮った『スター・ウォーズ』で、普通に役者がいいと思うなんてことがあると思っていなかった(笑)。ただ、往年の『スターウォーズ』ファンはこういう「過不足のないつくり」はすごく嫌がるかもしれませんね。まったく「らしくない」とも言えるので。
森 ルーカスは ILM【3】を立ち上げただけあって、デジタルジャンキーな側面があるでしょう。そのせいで新三部作はVFXの進化の過渡期をそのまま表していた。特にエピソード1『ファントム・メナス』(99年)はまだデジタルとフィルム撮影が交じっていて、どこか映像の実験に走っている印象です。でも今作は、シリーズで初めて3Dカメラで撮られたものなんだけど、同時に「旧三部作への回帰」がテーマにあって、映像もアナログの特撮と最新のCGを絶妙に組み合わせている。役者も活きているし、模型フェチ心をくすぐる物質感もあって、最適解と言っていいほどバランスがいい。観賞後は思わずトミカのおもちゃとか買っちゃいますよね(笑)。
J.J.は66年生まれで、エピソード4(77年)をリアルタイムで観ている世代。つまり『スター・ウォーズ』は彼の文化的原体験のひとつです。だからファン目線で批評的に作ることができていて、オールドファンの欲望のツボを突いてくるし、同時にビギナーも感染させる力がある。物語の途中から観てもハマるようにできているのは、J.J.がテレビドラマの仕事で培った話法が大きいのかもしれませんね。
『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(15年)について対談した際に宇野さんは、15年は大作シリーズのリメイクやリブートが多くて、20世紀生まれのキャラクターを消費する段階に入っているという話をされてました。それはさらに進んで、20世紀のキャラクターやコンテンツを21世紀の技術で強化するやり方が本流になりつつある。そういう意味で今作は、破天荒な天才オリジネーターより、“使えるヤツ”的な最優秀フォロワーが重宝されがちな時代の象徴的な成功作であり、J.J.はフォロワータイプの代表選手だと明らかにしたんじゃないかな。
【3】ILM:ルーカスが立ち上げた特殊効果・VFXのスタジオ。「インダストリアル・ライト&マジック」の略。ルーカスフィルム買収により、現在はディズニー傘下にある。
宇野 今回、エピソード7への評価とは別に、このSW現象を見ていて、僕らの映画に対する欲望自体の変化を感じた。実際、エピソード7を観てそこそこ満足している自分を顧みたときに、映画に対する欲望がオペラに対するもののようになってしまっているんですよね。映画というのは究極的には20世紀のもので、特に大衆娯楽映画をグローバルに拡大する動きは戦後のものだった。そして今、グローバルな映像産業においては、20世紀のビッグタイトルを温め直す娯楽が興行の中心に来ている。もちろんそうでない映像産業はローカルかつミニマムに移っていくんだけど、少なくともハリウッドはそうなってしまっている。結果、ある程度の規模以上のグローバルな映画はオペラや歌舞伎のように、20世紀のノスタルジーで駆動する名作への二次創作的なアプローチとして、再解釈の精度とユニークさを競う自己参照の時代になっていくんだと思う。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
3D・4D化の時代に映画表現が挑戦すべき課題とは? ――森直人・宇野常寛が語る『マッドマックス 怒りのデス・ロード』 (PLANETSアーカイブス)
2018-08-13 07:00
今朝のPLANETSアーカイブスは、興行面でも批評面でも高い評価を得た2015年の映画『マッドマックス 怒りのデス・ロード』の記事をお届けします。本作のヒット作から見えてくる映画表現のこれからの可能性とは? 映画評論家の森直人さんと宇野常寛が、『ゼロ・グラビティ』『ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション』などの作品と比較しながら語り合いました。(初出:「サイゾー」2015年10月号) ※この記事は2015年10月27日に配信した記事の再配信です。
Amazon:『マッドマックス 怒りのデス・ロード』
森 実に30年ぶりのシリーズ最新作となった『マッドマックス 怒りのデス・ロード』ですが、率直な感想は「理屈抜きでめっちゃ面白い」に尽きる(笑)。そこにあえて理屈をつけるならば、初期映画のハイパーグレードアップ版をやっているってことですね。
リュミエール兄弟の『列車の到着』【1】やジョン・フォードの『駅馬車』【2】までの「活劇」の黎明期、サイレント映画や初期トーキー映画を具体的に参照している。『駅馬車』は今ではクラシックの代名詞のような扱いになっているけど、同作が公開された1930年代当時のハリウッドは西部劇が一回衰退している時期で、ジョン・フォードは大手の映画会社ではことごとく企画を蹴られてしまい、インディペンデント系会社に持ち込んで作られた低予算映画なんです。『マッドマックス』シリーズも元はオーストラリアの低予算映画から始まったものなので、成り立ちもよく似ている。監督のジョージ・ミラーは、ジョン・フォードの映画史の神話に、自分を重ね合わせているところがあるのではないでしょうか。今回の『デス・ロード』は、『駅馬車』のアクション部分を拡大して、ストーリーはシンプルに削ぎ落としている。それゆえ初期映画感を明確に打ち出しているように見えました。
【1】『列車の到着』
正式タイトルは『ラ・シオタ駅への列車の到着』。1895年にフランスで製作された、50秒間のサイレントフィルム。映画の発明者といわれるリュミエール兄弟の手による作品。
【2】『駅馬車』
監督/ジョン・フォード 出演/ジョン・ウェイン 公開/1939年(アメリカ)
アリゾナからニューメキシコに向かう駅馬車に乗り合わせた人々の人間模様と、彼らへのアパッチの襲撃と応酬の様子を描く。西部劇史上のみならず、映画史を代表する傑作と呼ばれることも多い。
宇野 『デス・ロード』はある種の境界線にある映画で、ギリギリ20世紀の劇映画にとどまっているという印象を受けました。いま映画は3Dや4Dの影響によって、初期映画への先祖返りというか、動く絵を体験するというアトラクションに近づいている。『ゼロ・グラビティ』【3】がまさにそうなんだけど、その点『デス・ロード』は物語を失う寸前で踏みとどまっている。
この作品の評価は、ライムスター・宇多丸さんのようにフェミニズム的な側面も含めて丁寧に読み解いていくタイプと、町山智浩さんのように初期映画などの歴史を参照しつつも基本は「バカ映画」とするタイプの大きく2つに分かれていますよね。
前者はアクションの連続の中に物語を最大限詰め込んで踏ん張っているところに着目していて、後者は物語が必要とされなくなっている、映画という制度の、物語への依存度が相対的に下がる段階についての意識に注目して語っているわけです。実はこのふたつの立場は一見対立しているようで、とても近い状況認識を示していると思うんですよ。それがすごく象徴的だと思う。
【3】『ゼロ・グラビティ』
監督/アルフォンソ・キュアロン 出演/サンドラ・ブロック、ジョージ・クルーニー 公開/2013年
宇宙空間で事故に遭った宇宙飛行士と科学者が、生還を目指してサバイバルする様相を描いた。3Dを前提として作られており、「活動写真」としての映画で話題を呼んだ。
森 そのパラレル感はすごくよくわかる。ジェームズ・キャメロンの『アバター』で3D映画が本格的な段階に入った時から、「2回目の映画史」というべき流れが始まっていると僕は思っています。ハイパーリアルに進化した映像技術でシンプルな見世物をやる。そこを意識している作品は、物語の構造もどんどん単純化させている。それはまさに『ゼロ・グラビティ』がそうだし、結果的にかどうかはわからないけど『デス・ロード』も然り。
でも映画のリニアな構造を持たせるためには、何らかの物語を最低限選択しなければいけない。その時に「どんな物語を選択すれば今において最適解なのか」という“判断”がとても重要になってくる。『デス・ロード』でいえば今までのマッチョな男性主人公を引き継ぐのではなく、シャーリーズ・セロン演じる女戦士フュリオサを中心にしたヒロイン活劇にするという判断があった。『ゼロ・グラビティ』の主役も同様に女性だったことは示唆的ですよね。そう考えると、おそらく町山さんも宇多丸さんも基本的な認識や立脚点は同じで、ただ“判断”の部分から意味をどの方向に生成するかで違いが見えるのではないでしょうか。総合的に言うと、『デス・ロード』はとにかく一番基本的なことを、精度を最大限に高めてやろうとしたってことだと思うんです。
宇野 それでいうと、シャーリーズ・セロンの演技はすごく良かった。主演のトム・ハーディがちょっと食われちゃったんじゃないかと思うほど。
森 彼は『ダークナイト・ライジング』でベインを演じていましたけど、あれ自体が『マッドマックス』やその影響下にある『北斗の拳』的なキャラクターだった(笑)。宇野さんがさっき仰った「ギリギリ20世紀の劇映画」というニュアンスは僕もすごくよくわかるんです。例えば構造も「行って、帰ってくる」だけの極めてシンプルなものなんだけど、より重要なのは前半パートが「逃走」で後半パートが「闘争」になっていること。「行って」の部分は、自由を奪われていた女性たちがイモータン・ジョーの独裁国家から必死に逃げる。
「帰って」の部分は、当初の目的地だったフュリオサの故郷“緑の地”が不毛の地になっていたから、じゃあ戻って戦おうと。奴隷たちが革命を起こす話に旋回する。つまりアクションとエモーションがぴったり連動している。映画の根源的な快楽が高純度で実現されている。そのうえでキャラやマシンはシリーズ前3作のデザインワークを引き継ぎ、こってり盛りに盛りまくっているというバランスがすごく面白い。
だから『ゼロ・グラビティ』がほぼCGアニメーションに近いものなのに対し、『デス・ロード』は実写アクションという20世紀的な映画言語に踏みとどまって勝負している。それは監督の世代性も大きい。なんせ70歳のベテランですから。例えば話題になった火を噴くダブルネックギターのドゥーフワゴンも、基本のセンス自体は60~70年代風でしょう。シアトリカルでロック・ミュージカル的。『ヘアー』を通過してKISSに遭遇したみたいな(笑)。積まれたアンプもヴィンテージ物のマーシャルだったりね。そんなことを堂々とやる人が今いないから、一周回って新鮮に見えたんじゃないかな。
宇野 『ゼロ・グラビティ』と比べると、『デス・ロード』は表現論と物語を積極的に重ね合わせようとはしていなかった、とは言えるでしょうね。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
★号外★ 9/15(金)開催! 柴那典×森直人「情報環境は映画/音楽の快楽をどう変えるのか コミュニケーション消費以降の文化とその批評について」
2017-09-13 07:30
イベント情報のお知らせです!
今週9月15日(金)19:30〜「映画と音楽」をテーマにしたイベントを開催します。
ハリウッドの大作映画が脱物語化し、ノスタルジー産業化し、アニメ/特撮化し、大衆音楽がフェスとiTunesに引き裂かれて、かつてのレコード文化を捨てたとき、20世紀を支えた映画/ポピュラー・ミュージックはいかに変質しつつあるのでしょうか?
音楽ジャーナリスト・柴那典さんと映画評論家・森直人さんが語り合います。
会員割引券もあります! ぜひ皆様お越し下さい。
★★イベント詳細・お申込はこちら★★
▼概要
日時:2017年9月15日(金)
19:00 開場(受付開始) 19:30 開演 21:00 終演予定
場所:STRATUS TOKYO-Mistletoe Base Camp Tokyo-
東京都 港区 北青山 2-9-5 スタジアムプレイス青山 8F
▼登壇者プロフィール( -
これから映画はオペラ・歌舞伎化していく――『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』が示す「自己参照の時代」の到来(森直人×宇野常寛)【月刊カルチャー時評 毎月第4水曜配信】 ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.526 ☆
2016-02-24 07:00チャンネル会員の皆様へお知らせ
PLANETSチャンネルを快適にお使いいただくための情報を、下記ページにて公開しています。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/ar848098
(1)メルマガを写真付きのレイアウトで読む方法について
(2)Gmail使用者の方へ、メルマガが届かない場合の対処法
(3)ニコ生放送のメール通知を停止する方法について
を解説していますので、新たに入会された方はぜひご覧ください。
これから映画はオペラ・歌舞伎化していく――『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』が示す「自己参照の時代」の到来(森直人×宇野常寛)【月刊カルチャー時評 毎月第4水曜配信】
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2016.2.24 vol.526
http://wakusei2nd.com
今朝のメルマガは、『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』をめぐる森直人さんと宇野常寛の対談をお届けします。J.J.エイブラムス監督の手による本作の「出来の良さ」から見えてくる、映画を中心とした映像文化の変容とは?(初出:「サイゾー」2016年2月号(サイゾー))
(出典)公式サイト
▼作品紹介
『スター・ウォーズ/ フォースの覚醒』
監督/J.J.エイブラムス 脚本/J.J.エイブラムス、ローレンス・カスダンほか 出演/ハリソン・フォード、マーク・ハミル、デイジー・リドリーほか 配給/ウォルト・ディズニー・モーション・ピクチャーズ 公開/15年12月18日
エピソード6で描かれたエンドアの戦いから30年後が舞台。姿を消したルーク・スカイウォーカーを探しながら、レイアたちはレジスタンスを結成して銀河帝国の残党「ファースト・オーダー」と戦っていた。砂漠の惑星に住む少女レイは、レジスタンスのメンバーがルークの所在地図を託したBB-8と出会い、その戦いに参加してゆく。途中、ファースト・オーダーから逃げ出したストームトルーパーのひとりフィンとも行動を共にすることになる。エピソード4~6の旧三部作、1~3の新三部作に次ぐ新たな章の幕開けとなるエピソード7。
▼対談者プロフィール
森 直人(もり・なおと)
1971年生まれ。ライター/映画評論家。著書に『シネマ・ガレージ~廃墟のなかの子供たち~』(フィルムアート社)、共著に『ゼロ年代プラスの映画』(河出書房新社)など。
『月刊カルチャー時評』過去の配信記事一覧はこちらのリンクから。
【お知らせ】本メルマガで『現代アニメ史講義』を連載中の批評家・石岡良治さんが月イチのレギュラーニコ生番組「石岡良治の最強☆自宅警備塾」でスター・ウォーズを語ります! 『フォースの覚醒』から放映中の最新アニメシリーズ『反乱者たち』、その他スピンオフまで幅広く扱います。今週木曜放送予定。番組ページはこちらから。
宇野 僕は全然『スター・ウォーズ』マニアではないんですよ。さらに言うと、J.J.エイブラムス【1】も世間ほど高く評価していなかった。『スター・トレック イントゥ・ダークネス』(13年)がそうだったように、脚本のギミックで勝負しようとする作品が多くて、どうにも小賢しく感じていた。映画的な快楽を全然信じていないし使えない人なんだな、と。唯一好きだったのが『SUPER8/スーパーエイト』【2】で、あの作品に現れていた、映画史的なものに対するノスタルジックな視線のほうが、エイブラムスのオタク性が有効に働くと思っていた。今回も彼の二次創作作家としての才能がプラスに働いたんじゃないか。こんなこと言ったらファンに怒られるかもしれないけれど、単純に1本の映画として観た時、シリーズ全7作の中で一番「出来が」いいと思う。これはこれで褒め言葉に聞こえないかもしれないけど(笑)。
【1】 J.J.エイブラムス:1966年アメリカ生まれ。高校・大学時代から映画音楽や脚本に携わり、98年に『アルマゲドン』の脚本に参加。2000年代は『エイリアス』や『LOST』など人気テレビドラマシリーズの脚本を手がけ、05年には『ミッション:インポッシブルⅢ』、その後『スター・トレック』等の監督を務める。
【2】『SUPER8/スーパーエイト』:監督・脚本/J.J.エイブラムス製作/スティーヴン・スピルバーグほか 公開年/11年
79年、オハイオ州で自主制作のゾンビ映画を撮ろうとしていた少年たちは、夜中に線路で貨物列車の炎上事故を偶然撮影する。貨物に積まれていたのは宇宙人であり、彼らの周囲と街全体は恐慌に陥ることに。スピルバーグ監修、エイブラムス監督による『未知との遭遇』『E.T.』へのオマージュ的作品とされる。
森 僕も感想をひと言でまとめるなら「すごく上手」に尽きる。まったくストレスを感じずに楽しみました。とはいえ基本的にそれは想定内で、もしルーカスが監督するんだったら「今度は何をしでかすのか?」と皆ドキドキしていたと思うんですけど(笑)、J.J.がやるとなった時、誰もがある程度安心したんじゃないかな。宇野さんのおっしゃることもよくわかるんですけど、J.J.に対する世間の評価は『スター・トレック』のリブートを優等生的に成立させた時点でかなり固定したと思うので、今回も確実に80点を取ることは予想できていた。でもエピソード7は「無難以上の出来」だったと思う。
宇野 きっちり現代風にアップデートされていましたね。今初期三部作を観ると、恥ずかしくなるくらいストレートに、少年の社会化の物語から始まって父殺しの神話に接続していくというのをやっている。それが今回は、物語構造はほぼエピソード4を踏襲し、主人公格を黒人の青年と若い女の子に分散していて、政治的な配慮と共感のアイコンの分散として非常にうまく機能していた。キャラクター消費として旧来のファンの欲望を満たしつつ、現代の新しい神話として再提示するという役割を果たしていた。その時点でこの映画は、我々の期待しているものをクリアしていたと思う。
もともと『スター・ウォーズ』って、ストーリーは省略が多くて繋がっていないし、ドラマ性もとってつけたような薄っぺらさがあって、脚本・演出共に出来がいいとは言いがたかった。でも発想が新しくてエポックメイキングだからそれでいい、というものだったと思う。新三部作(エピソード1~3)は逆に、現代の技術で世界観を拡張することが望まれていたにもかかわらず、旧三部作と同じテンションで展開されてしまったためにどこか焦点がぼやけていたように思う。今回はその反省から、しっかりとマーケットの要請を押さえていましたよね。加えて、単純に現在の技術で『スター・ウォーズ』をしっかりやると、絵面はそんなに変わらないのにものすごくレベルアップしている。その快楽と、ヒロインの女優がものすごくいいというプラスアルファがあった。まさかエイブラムスの撮った『スター・ウォーズ』で、普通に役者がいいと思うなんてことがあると思っていなかった(笑)。ただ、往年の『スターウォーズ』ファンはこういう「過不足のないつくり」はすごく嫌がるかもしれませんね。まったく「らしくない」とも言えるので。
森 ルーカスは ILM【3】を立ち上げただけあって、デジタルジャンキーな側面があるでしょう。そのせいで新三部作はVFXの進化の過渡期をそのまま表していた。特にエピソード1『ファントム・メナス』(99年)はまだデジタルとフィルム撮影が交じっていて、どこか映像の実験に走っている印象です。でも今作は、シリーズで初めて3Dカメラで撮られたものなんだけど、同時に「旧三部作への回帰」がテーマにあって、映像もアナログの特撮と最新のCGを絶妙に組み合わせている。役者も活きているし、模型フェチ心をくすぐる物質感もあって、最適解と言っていいほどバランスがいい。観賞後は思わずトミカのおもちゃとか買っちゃいますよね(笑)。
J.J.は66年生まれで、エピソード4(77年)をリアルタイムで観ている世代。つまり『スター・ウォーズ』は彼の文化的原体験のひとつです。だからファン目線で批評的に作ることができていて、オールドファンの欲望のツボを突いてくるし、同時にビギナーも感染させる力がある。物語の途中から観てもハマるようにできているのは、J.J.がテレビドラマの仕事で培った話法が大きいのかもしれませんね。
『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(15年)について対談した際に宇野さんは、15年は大作シリーズのリメイクやリブートが多くて、20世紀生まれのキャラクターを消費する段階に入っているという話をされてました。それはさらに進んで、20世紀のキャラクターやコンテンツを21世紀の技術で強化するやり方が本流になりつつある。そういう意味で今作は、破天荒な天才オリジネーターより、“使えるヤツ”的な最優秀フォロワーが重宝されがちな時代の象徴的な成功作であり、J.J.はフォロワータイプの代表選手だと明らかにしたんじゃないかな。
【3】ILM:ルーカスが立ち上げた特殊効果・VFXのスタジオ。「インダストリアル・ライト&マジック」の略。ルーカスフィルム買収により、現在はディズニー傘下にある。
宇野 今回、エピソード7への評価とは別に、このSW現象を見ていて、僕らの映画に対する欲望自体の変化を感じた。実際、エピソード7を観てそこそこ満足している自分を顧みたときに、映画に対する欲望がオペラに対するもののようになってしまっているんですよね。映画というのは究極的には20世紀のもので、特に大衆娯楽映画をグローバルに拡大する動きは戦後のものだった。そして今、グローバルな映像産業においては、20世紀のビッグタイトルを温め直す娯楽が興行の中心に来ている。もちろんそうでない映像産業はローカルかつミニマムに移っていくんだけど、少なくともハリウッドはそうなってしまっている。結果、ある程度の規模以上のグローバルな映画はオペラや歌舞伎のように、20世紀のノスタルジーで駆動する名作への二次創作的なアプローチとして、再解釈の精度とユニークさを競う自己参照の時代になっていくんだと思う。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は今月も厳選された記事を多数配信します! すでに配信済みの記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201602
-
3D・4D化の時代に映画表現が挑戦すべき課題とは? ――森直人・宇野常寛が語る『マッドマックス 怒りのデス・ロード』 ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.438 ☆
2015-10-27 07:00チャンネル会員の皆様へお知らせ
PLANETSチャンネルを快適にお使いいただくための情報を、下記ページにて公開しています。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/ar848098
(1)メルマガを写真付きのレイアウトで読む方法について
(2)Gmail使用者の方へ、メルマガが届かない場合の対処法
(3)ニコ生放送のメール通知を停止する方法について
を解説していますので、新たに入会された方はぜひご覧ください。
3D・4D化の時代に映画表現が挑戦すべき課題とは?
――森直人・宇野常寛が語る『マッドマックス 怒りのデス・ロード』
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.10.27 vol.438
http://wakusei2nd.com
▲マッドマックス 怒りのデス・ロード
興行面でも批評面でも高い評価を得た今夏公開の映画『マッドマックス 怒りのデス・ロード』。このヒット作から見えてくる映画表現のこれからの可能性とは? 映画評論家の森直人さんと宇野常寛が、『ゼロ・グラビティ』『ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション』などの近作と比較しながら語り合いました。
初出:「サイゾー」2015年10月号(サイゾー)
▼作品紹介
『マッドマックス 怒りのデス・ロード』
監督/ジョージ・ミラー 脚本/ジョージ・ミラーほか 出演/トム・ハーディ、シャーリーズ・セロンほか 公開/15年6月20日
27年ぶりとなった『マッドマックス』シリーズの新作。原題は『Fury Road』。核戦争後の文明が荒廃した世界が舞台になっている。砂漠の荒野をさまようマックスはある時、砦の独裁者イモータン・ジョーの一団に囚われる。その後、ジョーの配下の女隊長・フュリオサが彼の妻たちを連れて逃亡し、ジョーとその狂信者たち“ウォーボーイズ”はマックスを“輸血袋”として車にくくりつけたまま、彼女たちを追い始める。途中、車から逃れてフュリオサたちと遭遇したマックスは、そのまま彼女たちの逃走に同行し、共に戦うことになる。
▼対談者プロフィール
森 直人(もり・なおと)
1971年生まれ。映画評論家、ライター。著書に『シネマ・ガレージ~廃墟のなかの子供たち~』(フィルムアート社)、共著に『ゼロ年代プラスの映画』(河出書房新社)など。
森 実に30年ぶりのシリーズ最新作となった『マッドマックス 怒りのデス・ロード』ですが、率直な感想は「理屈抜きでめっちゃ面白い」に尽きる(笑)。そこにあえて理屈をつけるならば、初期映画のハイパーグレードアップ版をやっているってことですね。
リュミエール兄弟の『列車の到着』【1】やジョン・フォードの『駅馬車』【2】までの「活劇」の黎明期、サイレント映画や初期トーキー映画を具体的に参照している。『駅馬車』は今ではクラシックの代名詞のような扱いになっているけど、同作が公開された1930年代当時のハリウッドは西部劇が一回衰退している時期で、ジョン・フォードは大手の映画会社ではことごとく企画を蹴られてしまい、インディペンデント系会社に持ち込んで作られた低予算映画なんです。『マッドマックス』シリーズも元はオーストラリアの低予算映画から始まったものなので、成り立ちもよく似ている。監督のジョージ・ミラーは、ジョン・フォードの映画史の神話に、自分を重ね合わせているところがあるのではないでしょうか。今回の『デス・ロード』は、『駅馬車』のアクション部分を拡大して、ストーリーはシンプルに削ぎ落としている。それゆえ初期映画感を明確に打ち出しているように見えました。
【1】『列車の到着』
正式タイトルは『ラ・シオタ駅への列車の到着』。1895年にフランスで製作された、50秒間のサイレントフィルム。映画の発明者といわれるリュミエール兄弟の手による作品。
【2】『駅馬車』
監督/ジョン・フォード 出演/ジョン・ウェイン 公開/1939年(アメリカ)
アリゾナからニューメキシコに向かう駅馬車に乗り合わせた人々の人間模様と、彼らへのアパッチの襲撃と応酬の様子を描く。西部劇史上のみならず、映画史を代表する傑作と呼ばれることも多い。
宇野 『デス・ロード』はある種の境界線にある映画で、ギリギリ20世紀の劇映画にとどまっているという印象を受けました。いま映画は3Dや4Dの影響によって、初期映画への先祖返りというか、動く絵を体験するというアトラクションに近づいている。『ゼロ・グラビティ』【3】がまさにそうなんだけど、その点『デス・ロード』は物語を失う寸前で踏みとどまっている。
この作品の評価は、ライムスター・宇多丸さんのようにフェミニズム的な側面も含めて丁寧に読み解いていくタイプと、町山智浩さんのように初期映画などの歴史を参照しつつも基本は「バカ映画」とするタイプの大きく2つに分かれていますよね。
前者はアクションの連続の中に物語を最大限詰め込んで踏ん張っているところに着目していて、後者は物語が必要とされなくなっている、映画という制度の、物語への依存度が相対的に下がる段階についての意識に注目して語っているわけです。実はこのふたつの立場は一見対立しているようで、とても近い状況認識を示していると思うんですよ。それがすごく象徴的だと思う。
【3】『ゼロ・グラビティ』
監督/アルフォンソ・キュアロン 出演/サンドラ・ブロック、ジョージ・クルーニー 公開/2013年
宇宙空間で事故に遭った宇宙飛行士と科学者が、生還を目指してサバイバルする様相を描いた。3Dを前提として作られており、「活動写真」としての映画で話題を呼んだ。
森 そのパラレル感はすごくよくわかる。ジェームズ・キャメロンの『アバター』で3D映画が本格的な段階に入った時から、「2回目の映画史」というべき流れが始まっていると僕は思っています。ハイパーリアルに進化した映像技術でシンプルな見世物をやる。そこを意識している作品は、物語の構造もどんどん単純化させている。それはまさに『ゼロ・グラビティ』がそうだし、結果的にかどうかはわからないけど『デス・ロード』も然り。
でも映画のリニアな構造を持たせるためには、何らかの物語を最低限選択しなければいけない。その時に「どんな物語を選択すれば今において最適解なのか」という“判断”がとても重要になってくる。『デス・ロード』でいえば今までのマッチョな男性主人公を引き継ぐのではなく、シャーリーズ・セロン演じる女戦士フュリオサを中心にしたヒロイン活劇にするという判断があった。『ゼロ・グラビティ』の主役も同様に女性だったことは示唆的ですよね。そう考えると、おそらく町山さんも宇多丸さんも基本的な認識や立脚点は同じで、ただ“判断”の部分から意味をどの方向に生成するかで違いが見えるのではないでしょうか。総合的に言うと、『デス・ロード』はとにかく一番基本的なことを、精度を最大限に高めてやろうとしたってことだと思うんです。
宇野 それでいうと、シャーリーズ・セロンの演技はすごく良かった。主演のトム・ハーディがちょっと食われちゃったんじゃないかと思うほど。
森 彼は『ダークナイト・ライジング』でベインを演じていましたけど、あれ自体が『マッドマックス』やその影響下にある『北斗の拳』的なキャラクターだった(笑)。宇野さんがさっき仰った「ギリギリ20世紀の劇映画」というニュアンスは僕もすごくよくわかるんです。例えば構造も「行って、帰ってくる」だけの極めてシンプルなものなんだけど、より重要なのは前半パートが「逃走」で後半パートが「闘争」になっていること。「行って」の部分は、自由を奪われていた女性たちがイモータン・ジョーの独裁国家から必死に逃げる。
「帰って」の部分は、当初の目的地だったフュリオサの故郷“緑の地”が不毛の地になっていたから、じゃあ戻って戦おうと。奴隷たちが革命を起こす話に旋回する。つまりアクションとエモーションがぴったり連動している。映画の根源的な快楽が高純度で実現されている。そのうえでキャラやマシンはシリーズ前3作のデザインワークを引き継ぎ、こってり盛りに盛りまくっているというバランスがすごく面白い。
だから『ゼロ・グラビティ』がほぼCGアニメーションに近いものなのに対し、『デス・ロード』は実写アクションという20世紀的な映画言語に踏みとどまって勝負している。それは監督の世代性も大きい。なんせ70歳のベテランですから。例えば話題になった火を噴くダブルネックギターのドゥーフワゴンも、基本のセンス自体は60~70年代風でしょう。シアトリカルでロック・ミュージカル的。『ヘアー』を通過してKISSに遭遇したみたいな(笑)。積まれたアンプもヴィンテージ物のマーシャルだったりね。そんなことを堂々とやる人が今いないから、一周回って新鮮に見えたんじゃないかな。
宇野 『ゼロ・グラビティ』と比べると、『デス・ロード』は表現論と物語を積極的に重ね合わせようとはしていなかった、とは言えるでしょうね。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は今月も厳選された記事を多数配信します! すでに配信済みの記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201510
1 / 1