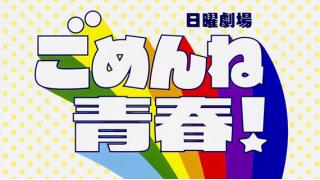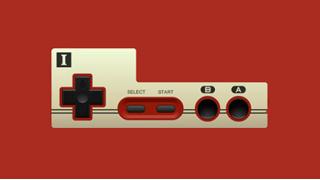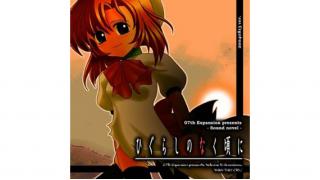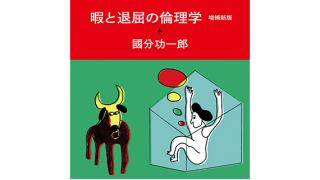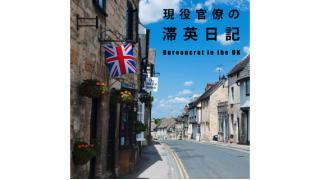-
月曜ナビゲーター・宇野常寛 J-WAVE「THE HANGOUT」3月9日放送書き起こし! ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.282 ☆
2015-03-16 07:00※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
月曜ナビゲーター・宇野常寛J-WAVE「THE HANGOUT」3月9日放送書き起こし!
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.3.16 vol.282
http://wakusei2nd.com
大好評放送中! 宇野常寛がナビゲーターをつとめるJ-WAVE「THE HANGOUT」月曜日。ほぼ惑月曜日は、前週分のラジオ書き起こしダイジェストをお届けします!
▲先週の放送は、こちらからお聴きいただけます!
■オープニングトーク
宇野 時刻は午後23時30分を回りました。評論家の宇野常寛です。今日はみなさんにひとつ報告があります。4月から、日本テレビ系の朝のワイドショーのコメンテーターをやることになりました。「スッキリ!!」という番組ですね。毎週木曜日のレギュラーの予定なんですが、ひとつ問題がありまして、この番組、一回も見たことないんですよ。マジで。
僕ね、基本的にテレビって、ドラマとアニメと「横山由依(AKB48)がはんなりめぐる 京都いろどり日記
」の三つしか見ないんですよ。テレビバラエティの、空気を読めという同調圧力が前提にあって、空気を読めないやつをちょっとマイノリティとしていじるような、ああいった笑いのとりかたってなんかちょっと嫌だなって気持ちもすごくあるし、この番組でもよく言っていますけれどテレビワイドショーの、毎週ひとり悪目立ちした人とか失敗した人を生贄にしてきてみんなで石を投げて、自分は良識の側にいるって安心したいだけのああいった悪い文化にも正直反吐が出るんですよ。ついでに言うと、テレビ業界人の、いまだに自分たちが世界の中心にいて自分たちが社会や世間を作っていますっていうあのモードにも、本当にうんざりしているんです。
ちなみに今日も某局とケンカしてきました。だからこそ、自分が出る時は絶対にザ・テレビっていう感じの空気に流されないようにしたいなと思っているんです。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
▼PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は3月も厳選された記事を多数配信予定!
配信記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201503
-
世界が「木更津」化したあとに――『ごめんね青春!』 ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.281 ☆
2015-03-13 07:00※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
世界が「木更津」化したあとに――『ごめんね青春!』
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.3.13 vol.281
http://wakusei2nd.com
本日のメルマガは、宇野常寛による『ごめんね青春!』批評です。『木更津キャッツアイ』『あまちゃん』などで時代の空気を絶妙に掴んできたクドカンは、今作ではなぜこれまでのような切れ味を発揮できなかったのか? この10年余りの社会状況・情報環境の変化から考えます。
初出:『ダ・ヴィンチ』2015年3月号(KADOKAWA)
クドカンこと宮藤官九朗の最新作『ごめんね青春!』は、主にその低視聴率による「苦戦」で世間に知られる結果になってしまった。しかし、そもそも彼の作品が視聴率的にヒットしたのは東野圭吾原作の『流星の絆』くらいの話で他は良くてもスマッシュヒット、といったところだろう。二度も映画化されたロングセラー『木更津キャッツアイ』も本放送の視聴率はぱっとしなかったし、あの『あまちゃん』でさえも、内容的には凡作としか言いようがない『梅ちゃん先生』に平均視聴率では負けていた。クドカン作品の魅力とは、端的に述べれば広く浅く拡散していくものではなく、深く刺さるタイプのものなのだ。
だから僕は本作をその視聴率的苦戦をもって何か言おうとは思わない。現に僕自身、このドラマを毎週楽しみにしていて、最後まで面白く観ていたのは間違いない。
しかし残念ながらその一方で、僕はこのただ楽しく、面白いドラマに物足りなさを感じていたことも正直に告白しようと思う。もちろん、テレビドラマに楽しく面白い以上の価値は必要ない、という考えもあるだろう。しかし、少なくとも僕はクドカンドラマにそれだけではないものを感じてこれまで追いかけてきたのだ。
今思えば『池袋ウエストゲートパーク』はモラトリアムの「終わりの始まり」の物語だった。長瀬智也演じるマコトが思春期の終わりに、それまで足場にしていた「ジモト」のホモソーシャルの限界に直面する。そして同じ長瀬智也が主演を務めた『タイガー&ドラゴン』はいわゆる「アラサー」になった主人公が、若者のホモソーシャルとは一線を画した大家族的な共同体に軟着陸していく過程を描いていた。そして長瀬が32歳で主演を務めた『うぬぼれ刑事』は、完全に「おじさん」になった主人公がもう一度、大人のホモソーシャルに回帰していくさまを描いていった。要するに、クドカンは自分よりも8つ年下の長瀬智也の肉体を借りて男性の成熟を、歳の取り方を描いてきた作家でもあるのだ。同世代の同性たちからなる若者のホモソーシャルが加齢とともにゆるやかに解体し、やがて(擬似)家族的なものに回収されていく。しかしクドカンの想像力は教科書的な成熟と喪失の物語を選ぶことはなく、やがて男の魂は新しい、大人のホモソーシャルに回収されていったのだ。
クドカンのドラマから僕がいつも感じるのは、部活動的なホモソーシャルだけが人間を、特に男性を支えうるという確信と、その一方でこうしたホモソーシャルの脆弱さに対する悲しみだ。この確信と悲しみの往復運動が、クドカン作品における長瀬智也の演じるキャラクターの変遷をかたちづくり、あるいは『木更津キャッツアイ』シリーズでクドカンが描いてきた儚いユートピアのビジョンに結実していった。
この視点から『木更津キャッツアイ』について振り返るのならば、人間がこうした部活動的なホモソーシャル、同世代の、同性からなる非家族的な友愛の、「仲間」的なコミュニティに支えられたまま(「まっとうな近代人」の感覚からすればモラトリアムを継続したまま)歳をとって死んでいくという人生観を提示し、しかもそれを幸福なものとして描き出したところが衝撃的だったと言える。そして『タイガー&ドラゴン』以降の作品は、クドカン自身がこの『木更津キャッツアイ』で提示したものを自己批評的に展開していったものに他ならない。
思えばクドカンが台頭したゼロ年代は、「仲間主義」と「ホモソーシャル」の台頭した時代だった。90年代的な恋愛至上主義文化の反動から、恋愛やファミリーロマンスでは人間の欠落は埋められないという世界観が支持を集め、まず『ONE PIECE』的な仲間主義が台頭し、そして「日常系」アニメ(『けいおん!』『らき☆すた』)からAKB48、EXILEまでホモソーシャル(では正確にはない。これらのコミュニティには紅/緑一点の異性すらいない。ミソジニー傾向の代わりに、ボーイズ・ラブ的な友愛の関係性が支配している)の中での非生殖的、反家族的な関係性がジャンル越境的に国内ポップカルチャーにおいて支配的になっていった。そう、今思えば『木更津キャッツアイ』はその後10年に起こることを先取りしていた作品だった。
あれから10年余り、世界はある意味すっかり「木更津」化した。
若者向けのポップカルチャーはすっかり木更津キャッツアイ的な「ホモソーシャル2.0」の原理が支配的になった。『木更津キャッツアイ』は企画当初『柏キャッツアイ』であったことが象徴的だが、彼らがジモトを愛する理由は、そこに地縁と血縁があるからではなく、自分たちの「仲間」の思い出が、歴史があるからだ。だから同作に登場した青年たちは自分たちの内輪ネタとサブカルチャーの「小ネタ」で凡庸な郊外都市である木更津を、自分たちにとっての「聖地」に変えていった。
そして今、こうしたコンテンツ依存のジモト愛の喚起、町おこしはむしろ地方自治体の常套手段と言っても過言ではなくなった。2013年に社会現象的ブームを巻き起こし、後世にはおそらくクドカンの代表作として語り継がれるであろう『あまちゃん』の放映時に、舞台となった岩手県三陸地方がこうした「聖地」化によって大きくクローズアップされたことは記憶に新しい。
そう、この10年余りのあいだに、世界はすっかり「木更津」化したのだ。
クドカンの話に戻そう。クドカンの一連の試行錯誤の集大成が『あまちゃん』だったことは間違いない。クドカンはここで、戦後の消費社会史をアイドルというアイテムを用いて総括した。ここでは前述のクドカンがそれまで培ってきた「ジモト」への視線が、戦後社会の精神史を描く上で大きく寄与していたのだが、本作『ごめんね青春!』では『あまちゃん』では扱われなかった男性の成熟とモラトリアムの問題が再浮上することになった。本作のプロデューサーはTBSの磯山晶、『池袋ウエストゲートパーク』にはじまる一連の長瀬智也主演作品や『木更津キャッツアイ』を担当した人物だ。主役を務めるのは長瀬よりも6歳若い錦戸亮。彼が演じる高校教師が、勤務先の男子校と近所の女子校の合併のために尽力しながら、30歳になっても引きずっている青春の日のトラウマに決着をつける、という物語が展開した。
これは言い換えれば、『木更津キャッツアイ』で一度男女を分離した、少なくともロマンチック・ラブ・イデオロギーやファミリー・ロマンス信仰とは異なるかたちの救済を提示したクドカンが、もう一度男女を出会わせようとしたもの、とひとまずは言えるだろう。しかし、残念ながらこのコンセプトは物語前半で空中分解してしまった。
本作では当初激しかった主人公の属する男子校と、合併先の女子校との対立は物語の序盤(第三話)であっさりと解決する。男子生徒嫌いの急先鋒だった黒島結菜演じる女子校側の生徒会長が、自分たちはこれから「男子」と書いて「アリ」と読む、と宣言する。あまり気の利いたセリフ回しではないが、それはまあ、いいだろう。しかし、その後同作はホモソーシャル同士の衝突を正面から描くことはなくなり、端的に言ってただの学園ラブコメになってしまう。もちろん、ただの学園ラブコメであることが悪いわけではない。ただ、この瞬間にどうしてこの複雑な設定が存在するのか、その意味はなくなってしまった。
こうして「再び〈男女〉を出会わせる」というコンセプトを失ってしまった同作は、最終回へ向けて主人公の教師・平助のトラウマの解消、高校時代に犯した罪の告白と清算(彼なりの「青春」への決別)に焦点を移すことになる。そして、最終回で平助は自分が担任していた学年の卒業式に学生服で乱入し、自分の「卒業」を宣言して青春に別れを告げる。思春期の恋が生んだ葛藤にケリをつけて、次のステージに進む。教師をやめ、満島ひかり演じる女子校の教師と結婚し、自分は学校をやめて地元FM局のDJになる。大いに結構だが、ここで提示された「成熟」モデルが、僕にはどうにも魅力的なものには見えなかった。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
▼PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は3月も厳選された記事を多数配信予定! 配信記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201503
-
「プレステ2」「Xbox」が告げる〈仮想現実の時代〉の終焉(中川大地の現代ゲーム全史) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.280 ☆
2015-03-12 08:10【お詫び】本日配信の「ほぼ日刊惑星開発委員会」ですが、編集作業に時間がかかってしまい、今朝の午前7時に配信することができませんでした。楽しみにしていただいていた読者の皆様、大変申し訳ございませんでした。さきほどより配信・公開いたしましたので、ぜひ、ご覧ください。今後ともPLANETSのメルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」を楽しみにしていただけますと幸いです。
※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
「プレステ2」「Xbox」が告げる〈仮想現実の時代〉の終焉(中川大地の現代ゲーム全史)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.3.12 vol.280
http://wakusei2nd.com
好評の大河連載『中川大地の現代ゲーム全史』は今月よりペースアップし、月2回配信でお届けします! 今回は新章となる第9章「和ゲー成長期の終わり/二極化してゆくゲーム産業」のプロローグです。2000年前後のIT革命、Xboxの登場などグローバル化の荒波のなかで、日本のゲーム産業はどう変わっていったのでしょうか――?
「中川大地の現代ゲーム全史」
第9章 和ゲー成長期の終わり/二極化してゆくゲーム産業
2000年代前半:〈仮想現実の時代〉終期(1)
前回までの連載はこちらのリンクから。
■〈夢の欠片〉としての日本ゲームの終焉
かつて宇宙開発への期待が人類のテクノロジカルな進歩の中核を担っていた〈夢の時代〉、2000年や21世紀といった数字は、そのままSF的な「未来」の世界観を表象する記号に他ならなかった。第二次世界大戦後の経済成長によって、1950〜80年代あたりを生きた先進国の人々は、その時点までの数十年間のスパンの間に、未曾有の科学技術の発展が人類の文明生活を一変させるさまを経験した。そして、その進歩のビフォー/アフターの落差が、ますます拡がりながら未来の時間軸にも折り返されてゆくと信じたのだ。それゆえ、アーサー・C・クラークの『2001年宇宙の旅』に代表されるように、たかだか半世紀以内の間に人類が宇宙へと生活圏を広げたり、意識を持つ人工知能が人類に哲学的な問いをもたらりする、見果てぬ〈夢〉が実現されているはずの「現代」からは飛躍した年代として、2000年代は想像されていた。
そんな想像力が影響してか、メモリ容量の少ないコンピューター黎明期に制作されたプログラムでは、年号処理が2000年以降の使用を想定してしていなかった。したがって、現実の2000年のテクノロジーをめぐっては、様々な情報処理システムが同年になると誤動作を起こすかもしれないという「2000年問題」への懸念が、世界を騒がせるに至った。言うなれば、かつて人々がイマジナリーに抱かれていた00年代の技術への〈夢〉と、現実の〝進歩の遅さ〟との齟齬を示す事象として起こったのが、2000年問題だったと言えるだろう。
第4章までに論じてきていたように、コンピューターゲームとは、テクノロジーの系譜としては、元々は宇宙開発に代表される巨大科学への〈夢〉がハッキングされ、パーソナルな体験の提供物へと解体・民主化されていく過程の徒花として生まれた〈夢の欠片〉とも言える技術産物だ。それゆえ、2000年問題で〈夢〉の頓挫が露呈したのと同様、2000年代前半は、世界の最先端を切り拓いてきた日本ゲームの進歩が、ひとまずの頭打ちを迎えた時代だったと言える。
1980〜90年代にかけては、家庭用ゲームの代替わりに駆動されるかたちで、絶えず新たなゲームジャンルが生み出されてきた。しかし90年代後半にポリゴン表現を用いたゲームのカンブリア爆発的な試行錯誤を経て一通りの文法化がなされたことで、据え置き型ゲーム機でプレイできるゲームデザインの破壊的イノベーションは一段落を迎える。以後は3D空間内のアクションをゲームパッドでいかにコントロールするかという基本的な操作系を一定程度規格化しつつ、主にはハードの更新にともなうポリゴングラフィックの高精細化のような漸進的なイノベーションの段階に入ってゆく。
加えて、右肩上がりの成長を続けてきた国内の家庭用ゲーム市場もまた、1998年を境に縮小に転じていた。内容面のみならず市場規模のうえでも、日本ゲームは高度成長期を終え、バブル崩壊後の経済全体の傾向から10年ほど遅れて下降線を辿り始めていたのである。
その一方で、ゲームと同じく宇宙開発に端を発するもうひとつの技術系譜であったインターネットの急激な普及は、いよいよ時代のモードを変えつつあった。ADSLなど常時接続型の安価なブロードバンド環境も整えられたことで、結局、2000年問題によってもいささかも水差されることなく、IT革命は進行。もはや情報技術が一部の専門家や好事家のフェティッシュの具ではなく、誰もが仕事や生活で日常的に扱う実用インフラとなったことこそ、この時代のゲームにとっての最も重大な環境的前提に他ならない。
なぜならこの変化によって、遊戯の体験を通じて一般家庭に先端的なテクノロジーの息吹をもたらすという、ファミコン以降のテレビゲーム機が担い続けてきたフラッグシップとしての役割が、完全に終焉を迎えてしまったからだ。GUIを備えたパソコンや、1999年に「iモード」をはじめとするネットサービスも始まった携帯電話といった実用機器で、様々なアプリケーションをクリックひとつで使えたり、WWWのサイバースペースを際限なくネットサーフできたりする環境が自明化したことは、コンピューターゲームが〈仮想現実〉として先行提供してきたテクノロジー体験が、同質の生活現実によって追いつかれてしまったことを意味していた。のみならず、人々の可処分時間や金銭を費やす遊戯性の体験としても直接的に競合し、ゲーム市場縮小の一因となった側面さえ否定できない。
つまりは、宇宙開発の〈夢の欠片〉として始まり、「ここではないどこか」の体験を創り続けてきたスタンドアローンゲームの体現する〈仮想現実の時代〉のひとまずの終焉期として、00年代前半は位置づけられるだろう。
具体的な状況としては、据え置き型ゲーム機のハード性能の進歩による3Dグラフィックスの要求クオリティの高まりや投資金額が高額化し、商業的なゲーム開発が大規模化してきたことの影響が大きい。とりわけ、市場を制するゲーム機が00年発売の「プレイステーション2」へと代替わりしたことが決定打となって、体力のある大規模ベンダーしか市場に残れなくなってきた。
▲プレイステーション2(ソニー・コンピュータエンタテインメント)
【ここから先はチャンネル会員限定!】
▼PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は3月も厳選された記事を多数配信予定! 配信記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201503
-
Cerevo岩佐琢磨インタビュー「ものづくり2.0――DMM.make AKIBAとメーカーズ・ムーブメントの現在」(後編) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.279 ☆
2015-03-11 07:00※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
Cerevo岩佐琢磨インタビュー「ものづくり2.0――DMM.make AKIBAとメーカーズ・ムーブメントの現在」(後編)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.3.11 vol.279
http://wakusei2nd.com
ハードウェアベンチャーCerevo代表の岩佐琢磨さんインタビュー後編は、知られざるハードウェア・スタートアップの歴史、そしてDMM.make AKIBAを中心としたメーカーズ・ムーブメントのこれからについて伺いました。前編はこちらのリンクから。
■ ハードウェア・スタートアップの歴史
――そろそろ、ハードウェアベンチャーの歴史について聞きたいんです。そもそも、家電のデジタル化はどこから始まったのでしょうか。
岩佐 2000年代の頭に「デジタル家電革命」が起きたんですよ。例えば、ボイスレコーダーからカセットが不要になったのが、この時期です。アナログな部品の物理的機構がすべてシリコンに置き換わって、NAND型フラッシュメモリやSDメモリーカードみたいなものが入ることで、デジタルプロセッサで全て構築できるようになったんです。
ちょうどその頃、電子機器の受託生産を行う「EMS」という業態が流行って、自社で工場設備を持たなくても、既存部品の組み合わせでモノがつくれるようになりました。
そうなれば、もう自分たちで部品を設計しなくていいんです。実際、大手メーカーの安いボイスレコーダーなんて、自社部品はほとんど入っていないですよ。
――その背景にあったイノベーションは何だったのでしょうか。なんとなく、「ムーアの法則」でマイクロプロセッサが小型化していく波が、家電にも押し寄せてきたというくらいのイメージなのですが……。
岩佐 いや、「小型化」は本質ではないです。家電メーカーは自社でアナログな部品を組み合わせて、テレビなどの表示機器を作っていて、その機能が小さなチップに収められるようになったのは、まさに仰るように「ムーアの法則」の賜物です。でも、別に「Intel 8086」のような汎用処理チップは、PC用として既にだいぶ前からあったわけです。
だから一番重要なのは、90年代後半から家電に向けて専用のマイクロプロセッサ、いわゆるSoC(System on chip)を作る発想「それ自体」が登場したことです。家電の機能をチップに収めて、「全世界のテレビメーカーがこれを買ってくれたら、このチップへの初期投資数十億円がペイできる」なんて発想を抱く人たちが世界中で登場したわけです。当時は、かなりぶっ飛んだ発想でしたがその後当たり前になりました。
――IT産業の発想で家電ビジネスを捉える連中が登場したわけですね。
岩佐 世界中のメーカーがアライアンスを組んで、共通規格を作り始めたのもこの90年代末のことです。
例えば、SDカードの登場がこの時期でした。「SDアソシエーション」への入会を募って、スロットやカードの普及を頑張る人たちなどが出てきたんです。USBやBus共通化もこの時期ですよ。昔は、液晶や端末はもちろん、データの転送もエラーの訂正も独自方式だったんですね。それを、この時期にチップベンダーたちが、「そうした方が儲かるよね」という発想へと切り替えたんです。
――そうして自社工場を持つ必要がなくなった結果、2000年代に入ってハードウェアベンチャー企業が登場しはじめた、と。
岩佐 僕らが始めるよりも3年くらい前、具体的には2002~2004年頃に、世界中で同時多発的に第一次ハードウェア・スタートアップの人たちが登場しました。
そこで彼らが取った戦略は2通りです。「性能は多少低くても、デザインさえ格好良ければ売れる」という"デザイン派"と、「既成品より遥かに性能は低いけど、半額にしよう」みたいな"値下げ戦略派"の人たちです。安物のデジカメは、後者の流れから出てきたものです。一方で、いま主流のネットと接続するスマート家電のような戦略はありませんでした。
その中で大成功したのが、海外勢の「Flip」ですね。ソニーが20年続けた全米ビデオカメラシェアを一つだけ蹴落としていた製品です。ただ、現在も生き残っているのはVIZIO社くらいかなあ。Flipを製造したPure Digital Technologies社も、最終的にCiSCO社に買収されてしまいました。
ちなみに、iRobotの創業は1990年ですが、彼らはずっとBtoBの産業用ロボットを扱っていて、家庭用ロボットへの参入は2002年です。まさに、みんなが同時期に家庭向けに入ってきたわけですね。
▲Cerevoが企画・開発したスマート・スポーツ用品ブランド「XON(エクスオン)」の第1弾製品、スノーボード・バインディング「SNOW-1(スノウ ワン)」。
▲左右それぞれの足にかかった荷重やボードのしなりを計測し、そのデータをBluetooth連携したスマートフォンへリアルタイム転送することが可能。スノーボードのさまざまなテクニックを習得・上達することができる。
――結局、当時の新興企業が上手く残れなかった理由は何だったのでしょうか?
岩佐 まず、デザイン派の人たちはコピーされてしまいました。デザインでの差別化なんて、せいぜい1年くらいしか持たないんです。実際、プラスマイナスゼロの加湿器デザインが発売された直後からウニョウニョした形の加湿器が増えてますよね。一時的にシェアを奪っても、すぐに形をパクられてしまうので、あとは価格勝負の持久戦です。そうなると、時価総額ウン兆円の大企業に勝つのは難しい。値下げ戦略派の人たちも同様の理由で、倒れていきました。
だから、敗因は戦略ミスに尽きます。この辺の中小企業はもう2005、6年くらいにはだいぶ経営が厳しくなっていて、リーマン・ショックが起きた2008年くらいには倒産したり、再生ファンドに売られたりして、消えてしまいました。
――岩佐さんは、まさにその時期に登場したわけですが、勝算はどの辺りにあったのですか?
【ここから先はチャンネル会員限定!】
▼PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は3月も厳選された記事を多数配信予定! 配信記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201503
-
Cerevo岩佐琢磨インタビュー「ものづくり2.0――DMM.make AKIBAとメーカーズ・ムーブメントの現在」(前編) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.278 ☆
2015-03-10 07:00※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
Cerevo岩佐琢磨インタビュー「ものづくり2.0――DMM.make AKIBAとメーカーズ・ムーブメントの現在」(前編)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.3.10 vol.278
http://wakusei2nd.com
「グローバルニッチ」な製品を発信し、世界中から注目を浴びるハードウェアベンチャーCerevo。今回のメルマガでは代表の岩佐琢磨さんに、起業のきっかけとなった原体験や、ハードウェア・スタートアップの歴史、そしてDMM.make AKIBAの抱く野望についてインタビューしました。
▼プロフィール
岩佐琢磨(いわさ・たくま)
1978年生まれ、立命館大学大学院理工学研究科修了。2003年から松下電器産業(現パナソニック)株式会社にてネット接続型家電の商品企画に従事。2007年12月より、ネットワーク接続型家電の開発・販売を行なう株式会社Cerevo(セレボ)を立ち上げ、代表取締役に就任。世界初となるインターネットライブ配信機能付きデジタルカメラ『CEREVO CAM live!』や、既存のビデオカメラをライブ配信機能付きに変えてしまう配信機器『LiveShell』シリーズなどを販売。
◎聞き手・構成:稲葉ほたて
■ DMM.make AKIBAの"裏"仕掛け人?
――岩佐さんがここ(取材場所のDMM.make AKIBA)に入居したのは、どんな経緯からですか?
岩佐 いや、そもそも僕と小笠原さんとDMMで、この施設を仕掛けたようなものです。だから、機材のほとんどは僕が選定していますし、「秋葉原につくろうよ」と言い出したのも僕です。そこに自分で入らなくてどうする、という感じですね(笑)。
――そんなに深く関わっていたとは、知りませんでした。ITのイメージが強い渋谷や六本木ではなくて、秋葉原を選んだ理由は何ですか?
岩佐 まさに、渋谷や六本木が、既に特定の業種の人間が集まる街になっているからですよ。
もちろん、産業が特定の場所に集まっていることは大事です。例えば、iPhoneアプリを作っている会社が2つ営業に来て、所在地が葛飾区と六本木だったら、なぜか後者の方が信用度が高いと判断されそうでしょう?。あくまでもイメージですが、そういう現実があるのも事実です。
僕たちハードウェアベンチャーには、そういう聖地的な場所がなかったんです。だから、僕は2007年に起業したときから、ずっと「そういう場所をつくろうぜ」と言ってきました。自分たちが旗を振って、「ハードウェアベンチャーといえば、やっぱアキバだよね」と思われるようにしたいんですね。
――大田区や品川区ではなくて、秋葉原でなければならない理由はありましたか?
岩佐 販売店が多くて、部品も買える。店舗間のネットワークもあるので、テストマーケティングがやりやすい。その意味で、もう秋葉原はいきなり最適解です。しかも、日本でハードウェアといえば、ずっと秋葉原のイメージだから、とても自然です。
あと、ハードウェアの場合は、海外戦略が重要になるのも大きかったです。「どこからお前は来たんだ?」と聞かれたときに、秋葉原なら「ああ! 知ってるぞ!」となりやすい。Tokyoのゲームやアニメを売っている街に、日本の最先端のハードウェア屋が集まっていると思われたら、なんだか良いじゃないですか。
▲Cerevoのライブ配信機能搭載スイッチャー「LiveWedge」(上)。ビデオカメラやパソコンをつなぐことでテレビ番組のようなカメラ切替やエフェクトに加えライブ配信が可能。高度な専門機材ではなく、タブレット端末から操作できる(下)。
■ 「ファミコンなんて薄っぺらくて、面白くない」
――今日は、岩佐さんに日本のハードウェアベンチャーの歴史を聞きたくて来たんです。
岩佐 了解です。どこにもまとまっていない話ですが、大きな流れは語れると思います。
――……なのですが、取材のために調べながら、ビジネス系のメディアでの岩佐さんの発言の端々から、相当にガチなオタクであるとわかったので、少しその話をしたいな、と(笑)。実は、自作PCやパソコンゲームをかなり嗜まれてますよね?
岩佐 ええ、そうですね(苦笑)。大阪にいた頃は、ずっと日本橋に通ってました。
……確か高1のときだったかなあ。当時は、自作PCじゃないとゲームが出来ない時代だったんですね。まだWindows 3.1で、Intel386からIntel486に移行するくらいの頃だったと思いますね。その頃にDOS/Vにハマって、洋ゲーの世界に行ったんです。
――早くから、パソコンゲームはやり込まれていたんですか?
岩佐 最初は小学生のときです。友人の家に父親のPCがあって、それで『大戦略Ⅲ’90』をやったらドはまりしたんです。でも、その友人とは違う中学に進むことになってしまい、もう彼の家には入り浸れない。これは困ったと思って(笑)、両親にねだって中古のPC-286C(EPSON製PC98互換機)、と「大戦略III’90」を購入してもらったんです。
当時は膨大な知識量がモノを言うゲームが好きで、だから一番最初にハマったのも、フライトシムと戦略シミュレーションゲームでした。「大戦略」は数百種類の兵器の情報が全て頭に入っているかで、戦略の組み立て方が全く変わってくるんです。その流れで「工画堂スタジオ」や「マイクロプローズ」の作品にハマって……ああいう当時のソフトハウスとともに育った人間ですね。フライトシムも500ページの辞書みたいな取扱説明書を読んで、プレイしていました。
――結構、ヤバい中学生ですよね。
岩佐 逆にコンシューマーゲーム機のゲームなんて、中学にいってからは全然やらなかったですからね。「あんなのは薄っぺらくて、面白くないな」と思っている子供でした。結局、初代PlayStation(以下、PS)も買わなかったです。それどころか、セガサターンもスーパーファミコンも買ってない。ファミコン以降でPS2より前のゲーム専用機はひとつも買ってないですよ。そのPS2もほぼ『GranTurismo』シリーズ専用機でしたし。まあ、自動車が好きなだけなんですけど(笑)。家庭用ゲーム機は、どうしても深みがない気がして、嫌いだったんですね。
■ Cerevoの原体験はゲーマー活動にあり?
――それだけパソコンゲームをやっていたとなると、やはりパソコン通信もやってましたか?
岩佐 中学生の頃には草の根ネットに入りびたってました。親が寝てからこっそり電話からモデムへと回線を繋ぎ変えて(笑)。でも、これが現在のCerevoでの事業の原体験なんですよ。
もう若い人には想像がつかないかもしれないけど、インターネットがなかった時代には、学校は「箱庭」だったんです。学校の小さなクラスが世界そのもので、そこに自分と同じものを好きな人がいなければ、もうおしまい。しかも、僕はすっかり軍事オタクになっていたので、「どこのミサイルのフィンの高さが何ミリだ」みたいな話をしていて毎日楽しいという、実にイカれた、ダメな中学生になっていた(笑)。
ところが、ある日そこにパソコン通信って世界が現れて、ネットに繋いだら見たこともない世界が広がっていた。フライトシムが好きな中学生や大人のおっちゃんたちと繋がれて――ああ、やっぱり日本には1億人がいて、オトンもオカンも学校の連中もみんな知らないけど、学校に縛られないもっと広い世界があるんだ――そんなふうに思えたんです。いちクラスの中では誰もほしいと思ってくれない超ニッチな商品であっても、実は日本だけでも1万人や10万人、世界に目を向ければ50万人や100万人がいる。中学生の頃にマニアックな草の根BBSの世界を覗いてそれを肌で感じたことは、やはり僕の原体験として鮮烈に残っているし、現在もなおその記憶を引っ張り続けています。
――つまり、Cerevoの「グローバルニッチ戦略」の原点には、パソコン通信でのオタク体験があったと。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
▼PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は3月も厳選された記事を多数配信予定! 配信記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201503
-
月曜ナビゲーター・宇野常寛 J-WAVE「THE HANGOUT」3月2日放送書き起こし! ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.277 ☆
2015-03-09 07:00※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
月曜ナビゲーター・宇野常寛J-WAVE「THE HANGOUT」3月2日放送書き起こし!
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.3.9 vol.277
http://wakusei2nd.com
大好評放送中! 宇野常寛がナビゲーターをつとめるJ-WAVE「THE HANGOUT」月曜日。ほぼ惑月曜日は、前週分のラジオ書き起こしダイジェストをお届けします!
▲先週の放送は、こちらからお聴きいただけます!
■オープニングトーク
宇野 今日は冒頭から悲しいお知らせがあります。僕のアイドルオタク仲間の某W大学の学生さん、仮にM君としておきましょう。そのM君が昨晩オタ卒しました。「オタクを卒業」、略してオタ卒です。
彼は乃木坂46の生駒里奈ちゃんのファンだったんですけど、もう、この3月2日の夜の時点で、乃木坂46のファンではないんです。オタクじゃないんです。彼は本当に生駒ちゃんが好きで、将来的には生駒ちゃんと付き合うためにテレビ局か秋元康事務所か、もしくは集英社のヤングジャンプ編集部に就職するって息巻いていたんですよ。なんでヤングジャンプなのかは僕にはまったく想像がつかないんですけども。
そんな彼に、昨晩彼女ができたんです。彼は高田馬場にある、とあるシェアハウスに住んでいるんですね。で、そのシェアハウスには、うちの編集部でインターンをしている留年の決まった早稲田大学理工学部の某学生が一緒に住んでいるので、インターンの彼からいろいろ情報が入ってくるんです。どうやら、高田馬場のシェアハウスに、昨日の夜、別の同居人の知り合いらしき女の子が遊びにきたんです。で、うちのインターン生の証言によると、次の日の朝に、初対面のはずのM君とその女の子がなんか抱き合っていたらしいんですよ。わかりますか? 前の晩の夜にみんなでわいわい遊んで、次の日の朝にはもう抱き合っていたらしいんです。それで、その日の夜に正式に付き合うことになって、生駒ちゃんからの卒業を宣言したと。お互い一目惚れだったらしいですよ。間接的に僕にまで写真が送られて来ましたからね。二人のツーショットの写真なんですけど、ちょっと照れながらピースしているんですよ。しかも、学生の分際で寿司とか取っているんです。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
▼PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は3月も厳選された記事を多数配信予定!
配信記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201503
-
『ひぐらしのなく頃に』が到達したところ――「共同性」と「公共性」の相克の果てに(中川大地) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.276 ☆
2015-03-06 07:00※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
『ひぐらしのなく頃に』が到達したところ――「共同性」と「公共性」の相克の果てに(中川大地)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.3.6 vol.276
http://wakusei2nd.com
本日のメルマガは、『現代ゲーム全史』連載中の中川大地による『ひぐらしのなく頃に』論のお蔵出しです。のちの「カゲロウプロジェクト」や「ダンガンロンパ」シリーズ、『僕だけがいない街』(「マンガ大賞2014」2位作品)など、10年代のヒットコンテンツにも大きな影響を与えたと言われる「ひぐらし」。当時としては珍しく、同人作品から出発しアニメ化など多数のメディアミックス展開も行なわれたこの作品のインパクトを改めて振り返ります。
初出:『パンドラvol.3』講談社BOX、2009年
「中川大地の現代ゲーム全史」これまでの連載はこちらのリンクから。
■はじめに〜「放送中止騒動」から考える
2007年9月、京都府京田辺市で16歳の少女が手斧で父親を殺害した事件の発生を機に、当時放映中だったアニメ版『ひぐらしのなく頃に解』に対し、作中の残酷な描写が事件を連想させることなどを理由に、いくつかの放送局で打ち切りや放送自粛の措置が執られた。これを受け、同時期のアニメ『School Days』の最終回放送中止と並んでそれなりに物議を醸したことは記憶に新しい。
もちろん、そのこと自体はアニメやゲームに限らず、その時代時代のサブカルチャー表現が事あるたびに陥ってきた、凡庸なトラブルの一つでしかない。事件と『ひぐらし』に直接的な影響関係などないことが公判の経緯からも明らかであったのは案の定であったし、逆に「何か犯罪があればすぐアニメやゲームをスケープゴートにするマスコミの偏向報道」に憤り、自分たちの愛好ジャンルが置かれている不当な地位の低さを受動的に嘆くオタク側の論調も旧態依然としたもので、取り立てて新たな状況や議論の深まりをもたらすものでなかったことは、今となっては明らかである。
というよりも、世間なんていうのは、そんなものだ。もし『ひぐらし』ファンとして、あの騒ぎでの作品の扱いに不当さを感じ、つい“公憤”めいたものを抱いてしまった人がいたとしたら、逆に自分が興味も利害関係もないローカルな領域の社会的事象について、いかに自分が無理解な「世間」の一部としてしか存在しえないかに思いを馳せてみたらいい。
ただ、一見あまり幸福でないこの“接触事故”が逆説的に示しているのは、02年の夏コミでの原作ゲーム発売以来、基本的にはコアなオタク的感性の極致にあるところから始まり発展していった『ひぐらし』のメディアミックス展開が、見知らぬ世間のまなざしに出会えるだけの広がりの獲得に成功していたという事実だ。だからこそ、あの時点において、『ひぐらし』は一部ファンダムの島宇宙内で評価される狭い共同性の範囲を超え、「中高生への悪影響を懸念される」だけの資格を得はじめていたのだとも言える。
つまり07年の騒動は、『ひぐらし』ムーブメントが、ある意味では社会的な責任を問われるまでの成熟を遂げた、ささやかなメルクマールとしてあったと思ってみるのも、一つの手だと思う。
実際、騒動を受けたあるネットインタビューで、原作者の竜騎士07はこんなことを語っている。
「自分たちの作品はメッセージがくどすぎる、メッセージ性が強すぎる、と言われることが多いんです。批評家の方々にも、「道徳の本じゃないんだから、価値観を強く押し付けるな」と怒られてきた。でも、今回のことで思ったのは、くどいと言われても自分なりのメッセージを書き切ってよかったと思います。京都の子がもし『ひぐらし』をプレイしてくれたら、今回の事件は起こす前に、それが正しい行為であるか考えてくれたのでないかと思うことがあります。」(『OhmyNews』07年11月9日記事「[ひぐらしのなく頃に解]放送中止騒動 竜騎士07さんインタビュー(中)」より)
説教上等……!
生真面目なこの原作者は、ゲームやアニメの立場の弱さを糾弾する前に、無理解・無関心な世間なり社会なりと本気で切り結ぶためには、たとえ批評家風情がいかに表現形式上の洗練のなさを厭おうと、メッセージの鮮明さこそが何よりの武器となることを確信しているのである。
そしてその確信どおり、『解』の正味の作品性に鑑みて、アニメの放送を打ち切った局よりも、OP映像の一部差し替えなどによって放送を続けた局の方が多かった。そんなもう一面の事実に注視してみれば、受け手である私たち一人一人にとって、あの騒動の経験を、より有用なものとして捉え返せるのではないだろうか。
たとえば、放映中止の憂き目に遭ったアニメ版『解』の第12〜13話といえば、「皆殺し編」中盤のクライマックス部分。つまり前原圭一たち主人公メンバーが過去の編で繰り返してきた短絡的な殺人の惨劇の過ちに自発的に気づき、仲間の北条沙都子を苛烈なDVから救い出すため、互いの相談と連帯によって、見事に社会的な勝利を勝ち取るくだりの直後である。具体的には、「部活メンバー」−「学校全体」−「雛見沢連合町会」と、順を追って協力者コミュニティの規模を拡大しながら、市の児童相談所に地道な陳情闘争を行っていくという展開だった。
ここに立ち現れているのは、内輪の幸福を追求する「共同性の論理」が、その共感範囲の線引きを可能なかぎり外へ外へと拡げていくプロセスの果て、容易には共感しあえない他者と出会い、生存資源の配分を調停する「公共性の論理」に直面していくという主題性だ。
そしてこの作中展開は、同人ゲームの小コミュニティから始まって漫画やアニメや実写映画と、空前のメディアミックス展開を遂げた果てに、まったく予期しなかった社会事件に直面することになった、このときの『ひぐらし』ムーブメントの成長過程そのものにも、重ね合わせることができるのだ。
このような具合で、言葉で語られるメッセージに耳を傾けるだけが能ではない。『ひぐらし』というコンテンツには、作品面でも現象面でも、「共同性の論理」と「公共性の論理」の相克を、様々なレベルで見出すことができるのだ。さしあたりはそんなお題でもって、私たちの『ひぐらし』体験の諸相を、段階的に腑分けしていってみたいと思う。
■同人ノベルゲーム発の「メディア・シャッフル」展開
まず、物語を載せる「器(メディア)」のレベルに焦点を当て、外堀を埋めておきたい。
『ひぐらしのなく頃に』という物語作品は、同人制作によるパソコン用の「ノベルゲーム」と総称される種類のデジタルメディアで提供されるコンテンツとして、誕生した。
改めて確認しておけば、ノベルゲームとは、小説形式で逐次的に表示されるテキストを、描写シークエンスに対応した登場キャラクターの絵や背景画、およびBGMや効果音といった視聴覚要素によって演出するというスタイルで、プレイヤーに物語を体験させるソフトの通称である(作品で力点の置かれる演出要素の違いによって「サウンドノベル」「ビジュアルノベル」等と呼称することもあり、『ひぐらし』の場合は「サウンドノベル」をジャンル名としている)。
1990年代後半以降に発展したノベルゲームが歴史的に積み重ねてきたコンテンツ傾向として、タイプの異なる多数の美少女キャラクターそれぞれとの恋愛や交遊を疑似体験する「美少女ゲーム」の媒体に使われるケースがほとんどであった。つまり、目標とするヒロインを「攻略」するため、いかに正しい選択肢を選び続けて思惑通りのシナリオに進んでいくか、という試行錯誤の過程をゲームとして遊ぶわけである。そのため、基本的にプレイヤーは全ヒロインのシナリオ分岐を制覇すべく、何度も繰り返しプレイするのが、こうしたジャンルのソフトにおける当然の受容形態となっていったのである。
さらに、プレイヤーによるこうした能動的な繰り返しの体験性に順応してきた00年代初頭になると、今度はその順応を逆手に取って、「世界が超越的な力によってループしている」ことを劇中の登場人物が自覚していることを示唆するメタフィクション的な描写を行ったり、あえて選択肢を排除することでプレイヤーに無力感を味わわせたりするようなトリッキーな作劇によって、ある種の前衛性を表現したかのようにみえる作品群が登場してきたのである。
以上、少々クドいおさらいとなったが、『ひぐらし』もまた、こうした一連の流れの中に系譜づけられる一作であることは間違いない。「鬼隠し編」から「祭囃し編」までの全8話の連なりを通じて、昭和58年6月近辺の雛見沢世界が何度も繰り返されるという特異な趣向や、その要因となる古手梨花や羽入の存在は、特殊なノベルゲームの発展史抜きには、まず考えられなかった設定だ。つまり、この物語はメディア自体の性格がもたらすきわめて強力なコンテンツ干渉性と、そのユーザーコミュニティの強固な文脈依存性とが帰結した、「共同性の論理」の結晶のような産物と言えるのである。
しかし『ひぐらし』が画期的だったのは、そうしたノベルゲーム的なリアリティへのリテラシーがなければ理解しがたい全体構造と物語の同一性はそのままに、個々の各編を別々の作家・版元から出版してみせた漫画版や、全編をシリアルに配列したアニメ版、そして実写映画版まで、表現特性の振れ幅が極端に広いメディアミックス展開を成功させたことだ。
結果として、メディアとコミュニティの垣根によって従来きわめて狭いレンジでしか受容されることのなかったハイコンテクスチュアルなノベルゲーム的作劇が、ほぼ初めて一般エンターテインメントのフィールドに解放されるかたちとなった。
そうした仕掛けが、最終的にどこまで受け入れられるのかは、各メディアでの展開がまだ途上である現在のところはまだ未知数だ。しかし、すでに従来のノベルゲームのユーザー層からすれば、世代や性別を越えたはるかに多様な文化トライブに属する人々が多様な入り口からファンとなり、裾野が広がっているのは間違いない。
こうしたメディア・シャッフル状況は、もはや単なる「共同性の論理」の拡大の域を越え、幅広い受け手たちの間で『ひぐらし』の物語が「公共性の論理」として機能するような、横断的なインフラを提供しつつあるのではないだろうか。
■「ジャンルの転調」が実現する「真のゲーム的リアリズム」
続いて、物語がまとう「様式(ジャンル)」のレベルに話を進めよう。
『ひぐらし』原作のゲームジャンル名である「サウンドノベル」と銘打たれた初めてのゲームは、1992年チュンソフト発売の家庭用ゲームソフト『弟切草』である。先述の通り、やがてほとんど成人向け美少女ゲームの代名詞のようになっていく90年代後半以降のノベルゲーム全体の傾向とは異なり、この作品は基本的には万人向けのサスペンスホラーであった。しかし、「元祖」であるこの作品が特徴的だったのは、プレイヤーの選ぶ選択肢によって、描かれる物語のジャンル性格そのものが、推理ミステリーから心霊ホラー、スパイ冒険ものやスラップスティックコメディ等々、登場人物の設定から何から根こそぎ変わってしまうという、分裂症的なシナリオ分岐を持っていたことだ。分岐した物語相互に何の関連性もなければ、選択肢を選んだ後の物語の変化にも特に必然性や整合性はない。完成度の高い本格推理ホラーとしてヒットした次作『かまいたちの夜』等に比べて、黎明期ゆえの自由すぎる粗削りな作品だったと言うほかないだろう。
筆者が思うに、本来はチュンソフトの登録商標である「サウンドノベル」の名を継承した『ひぐらし』の物語の転調スタイルは、どこかこの『弟切草』を彷彿とさせる、「面白ければ何でもアリ」な横紙破り的性格への“原点回帰”を果たしているような気もするのである。
というのは、第4話までの出題編に対応して各編の物語を裏返していく後半の『解』のスタイルは、従来のミステリーという物語ジャンルの約束事を、大きく打ち破るものだったからだ。
『解』の冒頭を飾る第5話「目明し編」こそ、出題にあたる第2話「綿流し編」の双子トリックを、犯人側の視点から見るかたちで真相を示していくという、ミステリー的にオーソドックスな「解答」の体を為していた。しかし、続く第6話「罪滅し編」以降の展開は、そうしたストレートな意味での「解答」の体裁を捨て、かわりにノベルゲーム的な「世界ループ」の設定と主題が立ち現れてくる。この点こそ、本作への賛否が大きく分かれるポイントになっているのは、周知の通りである。
確かに、ミステリーという様式的な伝統の蓄積が、物語の構成性を高め、コアなミステリーファンだけでなく、多くの人々にとってもなじみやすいオープンなエンターテインメントの作法として定着している実績は見過ごせない。実際、メディアミックス化が進んでいる『ひぐらし』の前半パートは、そうしたミステリーとしての趣向性の高さに支えられて、大きな支持を得ているのは間違いないからだ。
しかし、だからといってミステリーというジャンルの「大きな共同性」に沿った方が、ノベルゲーム的な世界ループ系の「小さな共同性」よりも普遍的で公共性に近づけるのかというと、事はそう単純ではない。稲葉振一郎が『モダンのクールダウン』において、近代フィクションにおける「(SFやミステリーなどの)ジャンル小説」と「純文学」の理念的な本質性を区別してみせたように、ジャンルの島宇宙の規模が大きかろうが小さかろうが、一定の様式や約束事への同調をはかるという意味で、共同性は共同性である。対して本来の文学の持つ公共性とは、あくまで異なる約束事同士の間を、メタレベルから関係づけることだ。特定の共同性がともすれば陥ってしまう排外性や暴力性に警鐘を鳴らし、その共同性の外部にある他者への共感の芽を担保することこそが、その役目である。
そう考えれば、『解』の展開がミステリーの縛りを捨てて、世界ループものや青春もの、そして明朗な冒険活劇へと、次々とジャンルを転調していったこともまた、明らかだ。ジャンル小説的手法であろうが自然主義的リアリズムであろうが、ひとつの物語ジャンルを採用するとき、それは必ず描写リアリティの性格を規定し、描きうるテーマやストーリーの拘束条件となり、特定の共同性に回収される慣性を帯びてしまうのが、ポストモダン時代のフィクションの宿命である。
だからこそ、描くべきテーマが優先されるものとしてあるとき、『弟切草』という原点の時点で萌芽的に示しされていた、複数のジャンルを並列化できるノベルゲームのメディア特性が威力を発揮する。すなわち、単にプレイの繰り返しで世界をループさせられるというだけでなく、同一パッケージの作品世界に対して、異なるジャンル的リアリティをもつ複数のシナリオで重層的にアプローチすることで、現実のもつ多面性や全体性を体感させる手法が採りうること。
余談になるが、この特性こそ、東浩紀が想定した概念よりもさらにベーシックで一般性の高い、真の「ゲーム的リアリズム」と名づけられるべきものではないだろうか。90年代後半以降の美少女ゲームしか見なかった東の場合、あくまで閉塞したループ世界にプレイヤーの立場を重ね合わせるセカイ系的な感傷(=「感情のメタ物語的詐術」)という特殊な事例にのみ、この概念を限定してしまっていた。しかし、ゲーム史的な観測点のスパンを遡ることで、「リアリズム」と呼称すべき文学的性質がよりハッキリするかたちで概念をアップデートできるのではないかと、もののついでに提案しておきたい。
ともあれ、個々のジャンルの共同性に限定されないメタな立場から、現実なるものの多面性を感得することこそ、すなわち公共性にほかならない。サウンドノベルの忘れられていた原初的性格に則るかたちで、『ひぐらし』というコンテンツがジャンル転調的な作劇手法を採用していたこともまた、本作が「公共性の論理」を志向してゆく諸相の一面であるのは、まぎれもないことではないかと思う。
■「雛見沢症候群」は「ミステリー」を内破する
『ひぐらし』が進めた「様式」破壊の意味を、もうすこし詳しく掘り下げてみたい。
『ひぐらし』が昭和58年の雛見沢村という、祟りへの信仰の残る村落共同体の舞台設定を採用し、凄惨な猟奇殺人事件をめぐるストーリーを展開しているのは、横溝正史に代表される田舎の前近代的な共同体の因習や怨念を犯罪の背景に用いた、典型的な日本ミステリーの類型の踏襲にほかならない。
こうした、戦後の高度経済系長期に確立された横溝ミステリーの王道は、奇異な前近代的風習や、超自然的な祟りの実在を示唆する言い伝えなどによって一見おどろおどろしく殺人事件がカモフラージュされているものの、最終的にはあくまでも動機を持った人間による現実的なトリックとして推理され、すべての謎が解かれるというのがお約束だ。ここから、ミステリーという物語様式の批評的な意味での本質を敷衍すれば、犯罪という前近代的な不条理に対し、近代主義的・人間主義的な理性に基づく論理的な推理によって立ち向かい、屈服するという形式だと定義することができる。つまり、基本的には「幽霊の正体見たり枯れ尾花」的なかたちで、前近代的な共同体社会の迷妄や抑圧性を否定し、人々を啓蒙主義的な理性に基づく近代社会の公共価値に馴致させるためのイデオロギー装置としての骨格を持っている。
ただし、犯罪トリックや犯罪者の描き方によっては、逆に近代合理主義の暴走を、時代に取り残されたマイノリティの側から告発する作品が紡がれる場合もある。笠井潔などの立場によれば、もともとミステリーやSFといったジャンル小説の批評的な存在意義は、突き詰めれば「公共性」を僭称する無自覚な「共同性」でしかない近代の「裸の王様」ぶりを相対化し、自然主義的リアリズムの閉塞を打ち破りうる点にあるとされている。要は古典的な近代−反近代という対立軸のスキームを提示できるフォーマットだということだ。
だが、こうしたミステリーという表現形式が、近代主義の理想を掲げたり、逆にその暴力性を衝いたりするビビッドな機能を保っていたのは、まだ日本各地に田舎の古い共同体社会のリアリティが残っていた、せいぜい1980年代くらいまでのことだろう(だからこそ、『ひぐらし』の舞台は、昭和58年に設定されている)。そうした現実の前近代の圧力がなくなり、古典的な近代主義の理想がもはや理想たりえなくなったポストモダン社会たる現在では、もはやミステリーは愛好者たちの島宇宙内で“ネタ”として安全に消費されるバロックとしてしか存在しえないのだ。
そうした認識に立ったとき、物語を真に受け手の現実に届くものとして機能させようとするなら、ミステリー的な約束事の遵守などは、もはや二の次の問題ではないだろうか。
その意味では、『ひぐらし』の物語の前半の惨劇の原因となる「雛見沢症候群」という、人間の内面的な狂気を描く猟奇ミステリーの醍醐味を台無しにしてしまうSFめいた“反則設定”の導入にさえ、ジャンルのお約束を内破する積極的な意義を見出すことが可能かもしれない。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
▼PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は3月も厳選された記事を多数配信予定! 配信記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201503
-
【『暇と退屈の倫理学』再版記念!】國分功一郎×宇野常寛「個人と世界をつなぐもの」 ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.275 ☆
2015-03-05 07:00※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
【『暇と退屈の倫理学』再版記念!】國分功一郎×宇野常寛「個人と世界をつなぐもの」
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.3.5 vol.275
http://wakusei2nd.com
本日のメルマガは、國分功一郎さんの『暇と退屈の倫理学 増補新版』の再版記念! 前回の刊行時に行なわれた國分先生と宇野常寛の対談を掲載します。『暇倫』で提示された〈消費〉と〈浪費〉という概念、そして『リトル・ピープルの時代』で示された〈ハッキング〉。その思想的ポテンシャルをいま改めて考えます。
▼3/7発売予定、13000字の新規加筆も!
國分功一郎『暇と退屈の倫理学 増補新板』(太田出版)
「わたしたちはパンだけでなく、バラも求めよう。
生きることはバラで飾られねばならない」
明るく潑剌と、人生の冒険に乗りだすための勇気を!
新版に寄せた渾身の論考「傷と運命」(13,000字)を付す。
序章 「好きなこと」とは何か?
第一章 暇と退屈の原理論──ウサギ狩りに行く人は本当は何が欲しいのか?
第二章 暇と退屈の系譜学──人間はいつから退屈しているのか?
第三章 暇と退屈の経済史──なぜ“ひまじん"が尊敬されてきたのか?
第四章 暇と退屈の疎外論──贅沢とは何か?
第五章 暇と退屈の哲学──そもそも退屈とは何か?
第六章 暇と退屈の人間学──トカゲの世界をのぞくことは可能か?
第七章 暇と退屈の倫理学──決断することは人間の証しか?
付録 傷と運命──『暇と退屈の倫理学』新版によせて
(Amazon 内容紹介より)
▼そして……大事なお知らせ
大好評をいただいている人生相談連載「帰ってきた『哲学の先生と人生の話をしよう』」ですが、國分先生がイギリスでの在外研究準備のためしばらくお休みとなります。
ですが……人々の悩みがより深まったとき、哲学の先生は再び我々の前に姿を現すであろう――。皆様、悩みを深めて連載再開をお待ちください!
「哲学の先生と人生の話をしよう」これまでの連載はこちらのリンクから。
ポップカルチャーを通じて「想像力」の変遷を分析し、2011年『リトル・ピープルの時代』を出版された批評家の宇野常寛さんと、哲学者として「どう楽しむか? どう生きるか?」をテーマに同年『暇と退屈の倫理学』を出版された國分功一郎さん。震災以後、揺らぐ日本社会で生きるヒントを、ポップカルチャー、ネットワーク、哲学、そして政治と文学の中に、おふたりはどう見出そうとしているのでしょうか。
◎構成:井上佳世
◎初出:「すばる」2012年2月号(集英社)
■ 人間と世界構造の間にあるもの
國分 僕は宇野さんの著書『ゼロ年代の想像力』(以下『ゼロ想』)を読んで、これは本当にすごいと思いました。”『ゼロ想』ショック”と呼べるほどのインパクトを受けたんですね。
90年代以降、陳腐な絶望意識と自己意識みたいなものがずっと日本の思潮を覆っていた。批評家たちもそれに対する有効な対案を出せず、そのすっきりしない状況の中でだましだましやっていくしかないというような雰囲気になっていた。ところが、その中に宇野さんが颯爽と現れて、「いや、ゼロ年代にはこんなに新しい想像力が出現しているんだ」ということを、ものすごい量の情報と鋭利な分析で教えてくれたわけです。しかも、サブカルの領域を通じて、でした。
サブカルに関する批評というのは、「自分が好きなものをみんなに認めてもらいたい」とか、「自分が好きな作品はすごいんだ」といった自己承認欲求に貫かれたものばかりで、僕はそれが全然つまらなかった。でも、宇野さんの『ゼロ想』は、90年代、ゼロ年代のカルチャーを主な対象としつつも、それ以前を、もっと言えば戦後日本の歴史みたいなものを背後に感じさせる書き方でした。いわば、自分たちが今どこにいるのかを伝えようとする歴史家意識みたいなものが感じられて、そこにすごく惹かれたんです。
宇野 なぜあの本のタイトルに「想像力」とつけているかというと、こういうことなんです。いわゆるポストモダン的なアイデンティティ不安や公共性の定義が難しくなる問題というのは、旧い言葉を使えば「政治と文学」の関係、つまり世界と個人を結ぶ回路を従来の言葉では記述できなくなったことだと言い換えることができる。大きな物語こそがまさに近代的な政治と文学を関係づけるものだったのだから、それが失効した後に出現するものは何だろうか、と。それを考えるために必要なもの、ということで「想像力」という言葉を当てているんです。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
▼PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は3月も厳選された記事を多数配信予定! 配信記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201503
-
落合陽一×宇野常寛「〈映像の世紀〉の終わりに――視覚イメージのゆくえ」(前編) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.274 ☆
2015-03-04 07:00※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
落合陽一×宇野常寛「〈映像の世紀〉の終わりに――視覚イメージのゆくえ」(前編)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.3.4 vol.274
http://wakusei2nd.com
本日のメルマガは、落合陽一さんによる好評連載『魔法の世紀』のスピンオフとして、昨年11月に行なわれた宇野常寛との対談をお届けします。落合陽一はいかにして「現代の魔術師」になることを志したのか、そして今改めて〈魔法の世紀〉というコンセプトを解説します。
落合陽一『魔法の世紀』これまでの連載一覧はこちらのリンクから。
初出:NICA プレオープニングクロスセッション「落合陽一 × 宇野常寛『魔法の世紀』21世紀のテクノロジーカルチャーを語り尽くす」(2014年11月16日開催)
宇野 僕が主宰しているメールマガジンで、いま落合さんに「魔法の世紀」というタイトルの連載をしてもらっています。僕はメールマガジンと紙の本と両方出しているのですが、正直に言って、この「魔法の世紀」は今手がけている全ての媒体の中でも目玉企画だと思っています。つまり、これは僕が今編集者として最も力を入れている連載であって、来年の目標の一つは、この「魔法の世紀」をベストセラーにして、日本の文化シーンと思想シーンに「一石」――どころか「大砲」を撃ち込むことです。
この「魔法の世紀」という言葉は、僕が落合さんにロングインタビューをしたときに対話の中で生まれたものです。研究内容かがアート作品にどう昇華されているのかを聞いたとき、「20世紀が『映像の世紀』だとすると、研究者にしてアーティストの落合陽一は『魔法の世紀』を表現しようとしているんですよね」と指摘したのがキッカケです。
連載では、そこから話を広げて、落合陽一の構想する「魔法の世紀」を思想的に定義づけ、アートやデザインにおいてどう展開するのか、そして人間と文化、情報の関係がどうシフトするかを考えてもらっています。まずは落合さんにその概要を話していただきましょうか。
■ CGの歴史はディスプレイからモノへ
落合 わかりました。僕の名前は、落合陽一といいます。名前をググると、TEDで喋ったり、ホリエモンとよくわからない8次元ディスプレイの話をしていたり、テクノロジー系の雑誌に載っていたりすると思います。
▲「これは幼少期の写真です(笑)」(落合氏)
そうそう、最近では「Time」誌と「Fortune」誌と「Forbes」誌がやっているワールド・テクノロジー・ネットワークの、今年のアワードノミニーになりました。渡航に23万円かかると言われて、授賞式に行くのはやめましたけど(笑)。
では、そんな僕が何をやっているか。普段はメディアアーティストと、コンピューターグラフィックス(注:以下、表記はCG)のリサーチャーをしています。
CGの技術が始まったのは1960年代です。基本的には、「コンピュータの中でどうやって絵を作るか」をずっとやってきたのですが、90年代にハリウッドで盛り上がったときに成熟してしまいました。そこで僕は「モニターの外でどうやって画像を作るか」を研究しています。口で説明すると、ちょっとアレですけどね。ただ、僕としては、2100年の情報技術をどう作っていくかを考えているつもりです。
例えば、138億年前、宇宙が誕生したときから物質はあるわけです。でも、CGが生まれたのは1963年です。138億年して,人間はコンピュータの中にもう一つの世界を作って操作できるようになったってことです。例えば、マウスでクリックするアイコンなんかがありますよね。ああいうふうなグラフィカルなユーザーインターフェイスを探求していく歴史が始まったのが、そのときです。90年代になると、今度はARをOSのアプリに入れて、触って操作できるユーザーインターフェイスや触って操作できるようなコンピュータも登場しました。ところが、2000年代になると、研究者たちはちょっとやることがなくなって来たんです。デジタル世界でできることが減ってきた。たとえば『ターミネーター2』の中に液体金属のロボットが出てきますよね。あんな感じで「形が変わるようなコンピュータってできるんじゃないの?」というような研究が始まったんです。
そこで今、僕が話しているのは、「分子サイズのコンピュータがたくさんあって全体の形が変わるコンピュータはなかなか大変なので、それを出来そうな範囲内に収めよう」ということです。そして、そうなると「物体自体よりもそれを包み込む環境、例えば物理場のほうが重要だよね」となる。僕が考えているのは、要は物理場をどうやってコンピュータでコントロールして、この物質世界を動かすかなんです。見た方が早いので、簡単にお見せします。
見ていただければわかりますが、実は上手く場を制御すれば、たとえCGの世界ではなかったとしても、物体はわりと自由に空中に浮かぶんです。そうしたら、今度はその場自体のxyzの位置、三次元位置を変えてしまえば移動できる。でも、簡単そうに話すのですがこの世界は「何だって出来てしまうCGの中の世界」とは違ってリアルの世界なのです。というのも、この世界には重力があって、そう簡単に物体は動かないんです。そこで、僕は移動させる場を重力よりも強い力で制御しようと考えました。そうすれば、コンピュータの外でも、コンピュータの中と同じように自由にものを動かしたり、飛ばしたり、浮かべたりできると思ったわけです。
▲「PIXIE DUST」
まさに、それが僕の研究者としてのテーマです。例えば、普通は重力があれば、粉は下に落ちますよね。でも、ある一定の秩序を持った「場」があれば、空中に降り注ぐ粉をその場に留めておける。すると、そこが一瞬で三次元のディスプレイになるわけです。これはつまり、コンピュータの中にある秩序をコンピュータの外に持ってきて、表現をしているということだと思うんです。しかも、今後は何百個ものモノをコンピュータの計算によって制御する、よりコンピュータの力を使ってコンピュータらしい振る舞いを考えるのが、ホットな分野になると思っていますから、今はそこをガリガリとやっています。
最近CNNから取材されたんです。実は来年、映画の中では『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に出てきたホバーボードが発売される予定らしくて、「レビテーション=空中浮遊」の特集をやってたんですよ。最近は、日本のメジャーな番組にも出させて頂くようになりました。僕が日本のメディアに出るひとつの理由としては、日本の研究者を増やしたいという目的もあります。研究者は英語で研究発表をするので、日本にリーチする機会があまりないので、メディアにでてなるべく研究の面白さを伝えようとしています。海外に優秀な研究者は沢山いるけど、日本には中々いないですから。
▲「アリスの時間」
研究以外にも作品作りもしています。たとえば、この「アリスの時間」という作品は物体が12個並んでいて、そこに光を当てて1個の映像を作ったものです。昔、プロジェクターが普及する前に、OHPという実物投影機がよく使われていたんです。その原理は、光を当てて、レンズで集めて、鏡ではね返すというものだったのですが、これも同じですね。LEDが当たった文字盤で反射した光が、上のレンズで一度変換されて、スクリーンに映像で映るんですよ。
言わば、モノをフィルムの代わりに並べてアニメーションを作ったわけです。宇野さんとよく話すのですが、かつてはマスに向けて表現する際には、印刷可能なフィルムや紙などの状態にするしかなかったんです。具体的には、映画や本ですよね。でも、今の時代は「魔法の世紀」だから、物体から物体へと表現を移せるのだと示したかったんです。それのコンセプトを物体を直接映像に変換する装置として表現しました。ちなみに、これは海外でウケました。ハリウッドがお金を出している「SIGGRAPH」という世界で一番大きいCGのカンファレンスで、テクニカルとアートのプレスが両方とも俺の作品で埋まったんです。あとで聞いたら、40年間やっていて、そんなことは初めてだったと言われました。そんな感じに毎日楽しく研究したり作品作ったりしています。
■ 「魔法の世紀」を貫く3つのキーワード
落合 さて、今日のテーマは、まさにこの「魔法の世紀」なんですが……ちょっといいですか?
連載を読んでいる人は手を上げてください……4人いますね。ということは、今日の人口の5%くらいは取っているわけですね、素晴らしい。じゃあ、軽く説明します。
まず、僕はこの「映像の世紀」から「魔法の世紀」へ、という流れを一つのパラダイムだと思っています。僕は本来、テクノロジーの研究者なので、「テクノロジーをどうやって我々、現代人が噛み砕いて考えていくのか」を誰かの代わりに考えているつもりです。でも、誰の代わりなんだろう……みんなの代わりに考えているんですかね(笑)。
宇野 昔だったら、思想家や哲学者や芸術家が語っていたようなことを、今やテクノロジーの担い手自身が語っているわけでしょう。この現実自体が「魔法の世紀」のコンセプトそのものだと思う。
落合 そうだと思うんです。それで話を戻すと、まさにフランシス・ベーコンが16世紀にテクノロジーの思想について考えていて、「自然を征服する」というコンセプトを掲げたんです。彼は、科学技術を用いて、いかに自然を加工して人間の意のままに操っていくのかを重視したんですね。彼の思想が象徴的ですが、この発想は西洋の至るところに現れているものです。例えば、噴水が好きな人は手を上げてください。噴水の好きさ具合を5段階で表してみましょう……"5"がふたりしかいない!!(笑)。
僕は「噴水」を西洋思想の一番の現れだと思っています。なぜならば、洪水を引き起こすような制御しづらい存在の象徴である「水」を、人間が作った庭園の真ん中に置いて、しかも重力に逆行して形を作っているからですよ。それは人間が自然を克服したことの一つの象徴だと思うんですね。西洋文化は、そういうふうにこの地球上のあらゆるものをいかに「神の御わざ」ならぬ「人間の御わざ」でコントロールしていくかをやってきたんです。僕が21世紀を「魔法の世紀」と呼んでいるのは、それがもっと爆発して、我々があらゆる存在にコンピュータ技術を用いて干渉できるようになってきたことを言っているに過ぎません。
では、そんな「魔法の世紀」とはどんな時代なのか。今のところ、重要なポイントは大きく3つあると思っていて、”Magically”、”Logically”、"Physically”です。
まず、”Magically”の意味は、「まるで魔法のように、それが何で起こっているかわからないし、何を使っていても関係ない」ということですかね。テクノロジーが秘匿されるってことです。
例えば、Twitterをつぶやくときに、スマホでもパソコンでもテクノロジーは何でも構わないわけです。なぜなら、僕たちが最終的にやりたいことは、自分の何らかの思いをWebに乗せていくことであって、その間にあるツールは別に関係がないからですよ。それって、魔法みたいでしょう。
魔法も何で動いているのかわからない。「炎よ出よ!」と言うと、なぜ炎が出るかわからないが、とりあえず炎は出る。この「わからないけどできる」というのが、「魔法の世紀」を説明する一つの大きなパラダイムですね。
二番目の”Logically”については、「論理的」という意味ではなくて、「コンピュータで動く」という意味です。コンピュータで一度ロジック化されているので、あらゆるものはコンピュータによって、プログラミングによって論理的に記述することで、コントロール可能になるわけです。
そして、最後に重要なのは、それらが”Physically”を志向していることですね。例えば、アイドルのプロモーションビデオがもし全て単なるCGとかだったら、きっとテンション下がりますよね。一方で、ライブではオタクがガンガン盛り上がるわけですよ。我々はもう、実際にあるもの以外にあまり価値を持たなくなっていると思うんです。
それはデジタル社会が繁栄して、コンピュータがこの世界をくるんでしまったからだと思いますね。かつてはコンピュータが希少だったから「デジタルすげえ」だったけど、ここまでコンピュータが豊富になってしまうと、もはや「フィジカルすげえ」に回帰してしていくわけです。
■ 魔法の世紀で何が変わるのか
落合 では、こういう特徴を持つ「魔法の世紀」への変化で何が起きるのか。ここでも俺は3つのキーワードを挙げたいと思います。それは、パーソナライズ、インタラクティブ、直接的な表現、です。具体的に説明しましょう。
例えば、僕たちは映画を観るとき、携帯電話の電源を消すように言われてしまって、Twitterでつぶやくことはできないわけです。ここに象徴的ですが、映画というのは全員で一つのスクリーンを見ている一方で、僕たち観客同士は互いの存在を意識していないんです。でも一方で、本来なら現在は、いつでも誰かに話しかけられて、相互にコミュニケーションがとれる時代のはずなわけですよ。映画監督のような一人の偉い人が情報を発信するんじゃなくて、僕たちは相互にコミュニケーションしながら、それをコンテンツとして咀嚼していく。相互ネットワークの「NtoN」の関係なわけです。これが「魔法の世紀」の一つのキーワードで、俺は「パーソナライズ」と名づけています。
あと、「インタラクティブ」ですね。昔は例えば、「黒澤明死ね!」とかつぶやいても、黒澤明には伝わらなかったわけじゃないですか。だけど、今Twitterでそんなこと言ったら、エゴサーチした黒澤明がへこむわけです(笑)。
宇野 実際に、作家も映画監督も毎日エゴサーチしてはヘコんでるからね。今、いい編集者というのは、いかに担当作家にエゴサーチを気にさせないかみたいな仕事になっている。
落合 みんなが「死ね死ね」言ったらその作家はへこむし、逆に褒めたら喜ぶ。まさに、この社会全体がインタラクティブになっていることを示してますよね。
あと、最後の一個がすごく重要で、昔は代理表象が可能だったんです。例えば、絵画や小説でもわりと直接的ではない表現を使って、伝えたいことを象徴させる。伝えたいことを何かに代理させて、表象していたわけです。だから、婉曲的で、コンテクストがあって、感情があって……という、そういう世界でした。
でも今って、わりと直接的な「キラキラして綺麗」とか「でかい」とか「すごい時間かかってそう」とか、そういうアートがYouTubeでバズったり、Twitterですごい勢いで流れたりする時代になっています。昔は間接的に表現してきたものが、今は直接的な表現になっている。しかも、フィクションの世界を表現するよりは、ライブやこの社会全体とつながっている表現自体が一番刺さるようになっている。こういうふうに、コンピュータが作った大きなネットワークや枠組みの中で、あらゆるモノや哲学が変わろうとしているわけです。そこで、この時代を「魔法の世紀」と名づけているわけです。
宇野 いやあ、説明が手慣れてきたね。この半年、いかに「魔法の世紀」と言い続けてきたかということだよね(笑)。
落合 そうなんですよ。あ、いつでもTwitterにリプライをくれていいですよ、僕はいつでも見てますから。意見やコンテンツに対して双方向的になる、それが魔法の世紀ですからね。
■ 戦後思想から見た「魔法の世紀」
宇野 僕は落合さんにロングインタビューをしたとき(『静かなる革命へのブループリント』に収録)に、「明確に一つの時代が終わろうとしているな」と思った。
色々なことに僕は手を出してるように見えるけど、究極的にはサブカルチャーの評論家なんですよ。だから、これまでアニメや漫画について議論することが多かった。その視点で言うと、戦後日本のアニメは、すごく特別な位置にある。村上隆が世界に出ていくときにアニメ的な意匠を用いたことには、まさに必然性があった。戦後アニメーションはまず戦後日本的なアイロニーの結晶であった。要するに近代国家としての精神的成熟を迎えないまま、経済大国化したネオテニー的主体としての日本の自画像が、もっとも如実に、そして批評的に出現していたのが戦後アニメーションだった。
そしてさらに同時に、アニメは完全な「虚構=作家が意図したもの以外に存在できない映像」でもある。ここには二重の「ねじれ」があって、第一に戦後アニメを形成する文化空間自体が「アメリカの影」によってネオテニー的に「ねじれ」ている。そして第二に、こうしたアイロニカルな文化空間はアニメのような完全な虚構を通してしか現実、つまり戦後的アイロニーの本質にアプローチすることができなかった。僕はここが重要だと思うんです。
と、いうのも結局、20世紀というのは、映像という虚構をマスメディアで広範に共有させることで、社会を形成するということにたどり着いた時代だったから。だからこそ、アニメーションという映像こそが戦後日本の精神性を代表するものであり得た。
落合 共通のコンテクストはテレビによって作られていましたからね。
宇野 そう、戦後日本の、とくに政治の季節の終わった70年代以降はテレビを中心としたサブカルチャーについて語ることが、もっとも効果的にこの国の文化空間を批評することだった。これは単純にメディア史を考えても必然的なことで、20世紀前半はラジオが普及した結果、あちこちにファシストが出てきて人類が滅びかけた時代だった。そこで後半は逆に、「じゃあ、マスメディアというのは政治からちょっと距離をとりましょう。とりあえず西側諸国ではそういう建前でいきましょう」ということになって、政治権力から切り離したテレビメディアを50年くらいやった結果、今度は政治漂流やポピュリズムを誰も止められなくなってしまった。
これが、20世紀というまさに「映像の世紀」の本質で、社会を形成する一つのビジョンを作り、それを極めて受動的に消費できるようなメディアを作り、それを社会全体が共有することで何かを維持してきた。
しかし今日はそんな時代が終わる、いや、すでに終わっているという話をする場です。
サブカルチャーの世界の人間として語るなら、その終わりはサイバーパンク的なものの終わりだと言い換えられるし、戦後日本の精神史的に言えば、連合赤軍〜オウム的なものの終わり言える。アメリカ的に言うとヒッピーカルチャーからカリフォルニアン・イデオロギーへの流れが一段落し、その果てにまったく別のものが台頭し始めていると言えるはず。
要するにこれは68年以降先進国が共有していた、革命が信じられなくなったとき、つまり社会を変えることが信じられなくなったとき、自分の脳内に何かを注入することによって、自分を変えようと、納得させようとする思想が台頭してきた。テレビが代表するような20世紀的な虚構がもっとも力を持ったのはこの時代だと思う。そして、いまこの時代が終わろうとしている。
落合 そうして変わった人間が、今度はマスメディアに乗って自分のメッセージを伝えれば、人間がどんどん変わっていくというわけですよね。でも結局、それって一人のトップ思想をコピーしただけで、彼らは一つの理念で動いているにすぎない。その人の脳みそが単に拡大しただけで、総体として大きな人間が生まれたに過ぎない。でも、今の時代はそうじゃなくて、本当は一人ひとりが個別に動くわけです。それは圧倒的孤独ともいえるけど、コンピュータのもたらしたつながりが逆に個別性を招いた結果です。
宇野 日本の場合、20世紀後半的な虚構が破綻してしまったのがオウム真理教だった。あれって元々は、信者にヘッドギアをかぶせ、『風の谷のナウシカ』と『機動戦士ガンダム』と『宇宙戦艦ヤマト』を組み合わせた架空歴史設定やカルト思想を注入していけば、いつの間にか悟りを開けて、特に社会に害を与えることもなく勝手に成仏できるという思想だったはずなんだよ。ところが、結局は自分たち自身がそれを信じられなくなって、「ガチに国務大臣やマスコミを暗殺して、地下鉄にサリンを撒かないと、俺たちはもう駄目だ」というところにまで行ってしまった。まさに虚構を自分の中に注入して自分を変える「虚構の時代」の敗北であったと思う。
じゃあ、どうすればいいか。それをインターネットに付き合いながら、世界中の人間が考えていたのが、実は世紀の変わり目前後の20年間だと思うんだよね。僕もずっとそのことについて考えていた。その中で僕は、落合さんの研究を見たときに、「ここにたぶん一つの答えがあるんじゃないのかな」ということを思ったわけです。
例えば、20世紀後半の人間は触覚を変えようと思ったときに、自分の脳の中で発生している電気信号を変えようとする。これまでは、少なくとも20世紀後半の人間たちは、たとえば本当はザラザラしたものを触っているのに、スベスベしているものを感じるように人間の認識の方をいじろうとしてきた。しかし落合君の研究というのは、むしろ板の表面をコントロールして、あるときはザラザラ、あるときはスベスベするように触感をいじっている。つまり、人間の脳内をいじるのではなくて、人間とモノとの関係をテクノロジーでいじろうとしている。
これは、なかなか僕くらいの世代までの人間は思いつけない。なぜなら、僕らの世代はやはり「虚構の時代」という「映像の世紀」の終わりに出て来た世界観に毒されすぎていて、社会全体を革命的に「大きな物語Aを大きな物語Bに変えることで変えてしまう」のか、あるいは「自分を納得させるようなロジックを脳内に注入する=ヘッドギアをかぶってしまう」のかの二択で考えてしまって、第三の道を考えられない。しかも、それがテクノロジー的に可能だとも、最近までは思っていなかった。そういう中で、まさに落合陽一の研究というのは、第三の道をかなりクリアなイメージで出していると感じたわけです。
落合 まさに、僕はHMD(ヘッドマウントディスプレイ)をかぶるのが嫌いなんです。どちらかというと、テクノロジーは完全に人間から秘匿されるべきだと思っていて、テクノロジーのことにはかまけずに生きていきたいんです。だって、インターネットに常時接続されて、インターネットでダベるために生きていたら、人間はインターネットに食われている状態じゃないですか。インターネットの恩恵を受けつつも、僕たちは僕たちらしく生きていくべきだと思うんです。コンピュータと我々どっちが主体的な存在なのかということです。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
▼PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は3月も厳選された記事を多数配信予定! 配信記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201503
-
もう始まっているかもしれない!?第三次世界大戦を止めるため、僕たちにできること(橘宏樹『現役官僚の滞英日記』第6回) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.273 ☆
2015-03-03 07:00※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
もう始まっているかもしれない!?第三次世界大戦を止めるため、僕たちにできること(橘宏樹『現役官僚の滞英日記』第6回)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.3.3 vol.273
http://wakusei2nd.com
本日のメルマガは『現役官僚の滞英日記』第6回です。「イスラム国」やシャルリー・エブド風刺画事件のイギリス国内での受け止められ方と対照させつつ、〈日本人の、日本人による、日本人のための国際感覚〉を考えます。
橘宏樹『現役官僚の滞英日記』前回までの連載はこちらのリンクから。
みなさん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ロンドンの橘です。この2月末は、ウィリアム英王子が初訪日していましたね。少々髪は薄くなりましたが、世界的な人気者の彼の動静がきっと紙面を毎日賑わせていたことと思います。
一方、イギリス紙面の関心事は、緊迫するウクライナ情勢、来る5月下院総選挙に向けた各党の政策論争も熱気を増す一方で、イスラム国関連の大きなニュースが続いています。2月25日には、イギリス人少女3人がイスラム国の活動に参加するためにシリアに入国したというニュースが報じられました。そして、本日(2015年2月27日(金))ロンドン各紙は、揃って一面で、後藤さんを含め幾人もの人質殺害に関わったとされるイスラム国のイギリス人テロリスト「ジハーディー・ジョン」の詳しい身元が特定されたことを大きく報じました。彼の生い立ちや「マンチェスター・ユナイテッドのファンだった」少年時代のエピソードなど、SUN(大衆紙)に至っては少年時代の写真のアップが一面に掲載されていました。本稿第1回でも触れたとおり、現在当該地域に空爆を実施しているイギリスにとって、そして、ロンドン・オリンピック開催が決まった日の翌日2005年7月7日にアルカイダによるロンドン同時多発テロ事件で50数名を失ったイギリスにとって、国際的テロリスト集団の主要メンバーにイギリス人が参加していることのショックは大きいのです。
今回は、イスラム国・対テロ戦争・風刺画事件関連の一連の事件に関するロンドンの有識者らの見方についてご紹介するとともに、私たちにもできることについて個人的なアイディアを述べたいと思います。
▲日曜日のピカデリーサーカス周辺。散歩日和。
■ 報復の連鎖
ご存知のとおり、イスラム国は、英米ら有志連合軍の空爆攻撃に対する報復として、欧米人・日本人の人質の処刑を行ってきました。私自身も、湯川さん、後藤さんが無念の死を遂げたことを、同じ日本人として大変悲痛に思います。他の多くの犠牲者とともに、ご冥福を心からお祈りしています。その一方で有志連合軍の空爆では、子供達を含む大勢の犠牲が出ており、これに対する報復としてイスラム国がヨルダン人パイロットの焼殺動画を公開すると(動画では空爆の悲惨さがこれでもかと強調されます。)、ヨルダンは女性死刑囚の死刑を執行。すると、イスラム国は他のヨルダン空軍パイロットの実名と懸賞金を発表します。このように、もはや、どの件においてどちらが悪いということは重要ではなくなり、ただ「報復の連鎖」が綿々と続き、ひたすら泥沼化していっているのが現状です。
そして、この報復の連鎖は中東のみならず欧州内でも展開し始めました。1月7日、ムスリム(イスラム教徒)を侮辱する風刺画を繰り返し掲載してきたフランスの漫画新聞社シャルリー・エブドの絵師が襲撃を受けて殺害されたことを皮切りに、フランスでは風刺画に対する報復テロが、報告されているものだけで147件生じたとされています。そして、これに対する報復として、1月7日の週だけでモスクへの火炎瓶投下が26回行われるなど、イスラム教徒一般に対する報復事件が多発し始めました。このような「報復の連鎖」が続く緊急事態を憂う大勢の市民が集い、1月11日、パリでは「反テロ・デモ行進」が行われました。イギリスのキャメロン首相、イスラエルのネタニヤフ首相、パレスチナ自治政府のアッバス議長、フランスのオランド大統領、ドイツのメルケル首相ら、各国首脳が参加して大きな注目を集めました。(尚、370万人もの人が参加したと報道されており、日本でも大きな関心を集めたかと思いますが、この人数の根拠に疑問を呈する有識者もいる旨は書き添えたいと思います。)しかし、デモの願いも虚しく、2月14日にはデンマークで風刺画家を標的としたと見られる連続襲撃事件が生じています。
このように、イスラム国と欧米の間で、「報復の連鎖」が途切れることなく続いてしまっています。あるロンドンの有識者は「もはやどちらが良い悪いの問題ではない。この連鎖のせいで、特に、1月7日の風刺画事件以降は、欧米の雰囲気は「対テロ戦争」から「対ムスリム戦争」になってしまっている。」と評していました。そして、「大勢の参加した反テロのデモも、表現の自由のためのデモと、半ば同一視されて、全体として反イスラム・デモの様相を呈してしまっている。」と言います。ムスリム側も、ムスリム関係機関が、イスラム教はテロを認めていない、という声明をいくら出しても、かき消されてしまっている印象です。この雰囲気を懸念したからこそ、オバマ大統領も、2月18日、自ら主催した対テロ・サミットで「(我々の戦いは)対テロ戦争であって、対イスラムの宗教戦争ではない。」と敢えて強調したのだと思われます。結果として、過激派ではない一般のイスラム教徒までもが、迫害される危険を感じて、反発感情を強めてしまってきているようです。不安と反発が呼び合って、誰もがいかにもそうなりそうだと懸念し、また、誰もがそうなってはいけないと希う、明らかに愚かな二項対立に事態が収斂していこうとしているというのが、今のところ、残念な現実であるようです。
そして、あるシンポジウムの合間の立ち話で、ある紳士が「過去の世界大戦は、通常兵器による正規軍同士の戦闘が主で、開戦日も終戦日がはっきりしていた。しかし現代の戦争は、生物兵器も含め、一方的で無差別なテロ行為が攻撃手段である。テロ集団が民間人に対して一方的に武力行使する。日常生活全体が戦場になる。報復の連鎖が続いてエスカレートしていくなかで、いつの間にか戦争状態に陥っていることになるから、開戦日も終戦日もはっきりしない。我々はもしかしたら、もう既に第三次世界大戦のなかにいるのかもしれない」と話していたことが強い印象に残っています。
▲電気自動車の充電スタンド。ロンドンには25,000箇所の充電スタンド、10万台のEVが導入されているとのこと。
■ 連動するリスク
このような欧米・中東の状況を日本の人々はどのように捉えているのでしょうか。ロンドンと東京では認識にどのような違いがあるでしょうか。私は、日本語のWEBニュースサイトやBLOGOSなどで日本の言論にもある程度接しています。なるべくいろいろなものを読み比べているつもりではありますが、当然限界があるでしょう。また一方で、これもまた限られた機会ではありますが、英国内の各種報道媒体に接するほか、ロンドンでシンクタンクや大学が開催するシンポジウムに参加したり、勉強会の場等で有識者と雑談したりするなどして、ロンドン(の知識階級)の認識にも触れています。その範囲で、最も違いを感じるのは、ロンドン(及びおそらく欧州全体)には、イスラム国との対テロ戦争と、フランスでの風刺画及び報復テロ事件を、全体としてひとつの文脈として捉える見方が強いことだと思います。
もっと言えば、これらに加えて、ウクライナ情勢、ギリシャ債務危機、パレスチナ問題、イラン動静などはすべて、互いに連動するリスクとして捉えられていると言って良いでしょう。そして、煎じ詰めれば、これらの問題がドミノ的に連鎖して、英米独仏が団結して対処できる能力を超えたレベルで同時多発的に「危機」が起きたらどうしよう、という懸念、そしてイスラム国・テロ勢力はきっとそれを狙っているだろう、という恐怖感が共有されていると感じています。だからこそ、全世界に分布する不安や恐怖をマネジメントしよう、という考えから、「グローバル・ガバナンス」というテーマが欧米を中心にずっと議論されてきているのだと思います。
他方で、イギリス、特にロンドンの投資家・ビジネスマンがこのような切迫した危機感を抱き、すべての国際問題を一括して捉えようとするのは、ある意味で当然とも言えます。というのも、「シティ」と呼ばれる、イングランド銀行を中心に営まれ続けてきたロンドン中枢部の伝統的エリート社会のメンバー(ジェントルマン)らは、投資環境と石油価格の「安定」(含、彼らにとって予測可能であること、またはコントロール下にあること)が至上命題である国際金融を生業としています。彼らは、シティからイングランドを、イングランドを通じてイギリス連邦をコントロールしようとし、そしてイギリス連邦を通じて、全世界の約三分の一を占める旧英領(=コモン・ウェルス各国)を、そして、旧英領を通じて、全世界に影響力を行使し(ようとし)ています。このように「シティ」はレバレッジ(テコの原理)にレバレッジを重ねて、国際政治経済における影響力を確保し(ようとし)ているというのが私の基本認識です。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
▼PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は3月も厳選された記事を多数配信予定! 配信記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201503