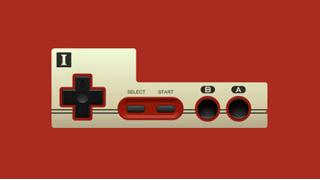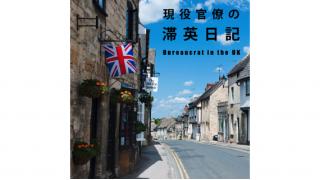-
スマホ時代の到来と日本的ソーシャルゲームの展開 〜『ドラゴンコレクション』『探検ドリランド』『神撃のバハムート』〜(中川大地の現代ゲーム全史)【毎月第2水曜配信】 ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.468 ☆
2015-12-09 07:00チャンネル会員の皆様へお知らせ
PLANETSチャンネルを快適にお使いいただくための情報を、下記ページにて公開しています。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/ar848098
(1)メルマガを写真付きのレイアウトで読む方法について
(2)Gmail使用者の方へ、メルマガが届かない場合の対処法
(3)ニコ生放送のメール通知を停止する方法について
を解説していますので、新たに入会された方はぜひご覧ください。
スマホ時代の到来と日本的ソーシャルゲームの展開 〜『ドラゴンコレクション』『探検ドリランド』『神撃のバハムート』〜(中川大地の現代ゲーム全史)【毎月第2水曜配信】
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.12.09 vol.468
http://wakusei2nd.com
本日のメルマガでお届けするのは『中川大地の現代ゲーム全史』最新回。ついに2010年代に突入します。プロローグにあたる今回は、情報技術が世界を覆い尽くした状況を概観しつつ、スマートフォンを媒介としたソーシャルゲームの大発展時代を振り返ります。
第11章 デジタルゲームをめぐる地殻変動/汎遊戯的世界への芽吹き
2010年代前半:〈拡張現実の時代〉本格期(1)
▼執筆者プロフィール
中川大地(なかがわ・だいち)
1974年生。文筆家、編集者。PLANETS副編集長。アニメ・ゲーム関連のコンセプチュアルムックの制作を中心に、各種評論・ルポ・雑誌記事等を執筆。著書に『東京スカイツリー論』(光文社)。本メルマガにて『中川大地の現代ゲーム全史』を連載中。
前回:デジタルゲームを変えた「ソーシャルゲーム」市場の勃興〜『釣り★スタ』『サンシャイン牧場』『怪盗ロワイヤル』〜
■深化してゆく〈拡張現実の時代〉
2010年代を〈拡張現実の時代〉の本格期と呼ぶに足る実感を、多くの人々にもたらしたのが、スマートフォン普及の本格化であった。前章で述べたように、これは2007年のiPhone登場を嚆矢に、グーグルが開発した汎用OSであるAndroidを搭載した機器が登場して二大陣営を形成することで、様々な機種を擁する一般的なカテゴリーとしての成立を見るに至った結果の出来事だ。その世界的な潮流は、「ガラパゴスケータイ(ガラケー)」という蔑称さえフラットに定着してしまった国産フィーチャーフォンのシェアを、急速な勢いで置き換えていくことになる。
その使用感はもはや「電話」のそれではなく、インターネット端末としてのパソコンの役割をほとんどカバーすると同時に、携帯型ゲーム機が追求してきたタッチパネル式の操作系や、GPSと連動して自らの位置情報がリアルタイムに把捉される機能など、現実空間におけるユーザーの視聴触覚的な認知が拡張されていく経験を、広範な層に提供するものだったと言える。手帳や地図、時刻表に文庫本、カメラや音楽プレイヤー、それにゲーム機と、およそ現代人が外出先で必要とするであろう、あらゆるタイプの実用的・娯楽的なコンテンツの享受方法が手元の小さなデバイスに統合・ネットワーキングされたことで、人々の日常の時間と空間、そしてお金の使い方が大きく変化していったのである。
様々な生活シーンに密着した機器が登場したことで、グーグルやアップルをはじめとする巨大プラットフォーマーや行政機関が、人々のネット上での検索履歴や消費行動など日々生成されるライフログを中心にした「ビッグデータ」を容易に収集することが可能になり、その解析を通じた新サービスやAIの開発、統治の効率化といった応用が進むことへの期待と不安が取り沙汰されるようになる。
より先端的なテクノロジーの領域では、汎用的なヘッドマウントディスプレイ「Oculus Rift」や、スマホのコンセプトをさらにウェアラブル化したデジタル眼鏡「Google Glass」のような、VR・ARのコンセプトを直截に具現化する民生プロダクトが登場。さらには、可塑性の高い樹脂素材などによって3DCGデータを物体化する3Dプリンターのような技術が次代のイノベーションをもたらす「IoT:Internet of Things(モノのインターネット)」の象徴として注目されるなど、デジタル世界と現実空間との垣根を引き下げる事象が注目され始めたことも、いよいよ〈拡張現実の時代〉が深化していく指標に数えられよう。
(関連記事)
Cerevo岩佐琢磨インタビュー「ものづくり2.0――DMM.make AKIBAとメーカーズ・ムーブメントの現在」(前編)
Cerevo岩佐琢磨インタビュー「ものづくり2.0――DMM.make AKIBAとメーカーズ・ムーブメントの現在」(後編)
過剰を抱えた人間のためのフロンティア――DMM.make AKIBAが目指す次のインターネット(プロデューサー・小笠原治インタビュー)
こうした情報環境下で顕著になっていったのが、「コンテンツ消費からコミュニケーション消費へ」という動向だ。音楽や書籍、映画といったエンターテインメント作品の流通経路や摂取手段が、もはやジャンルを問わずにパッケージメディアから解放されてネットに移行し、スマホやパソコン、ないしスマートテレビ等で気軽に受容できるようになったことは、前時代における文化愛好者の夢の実現であるはずだった。
しかしながら、ビジネスの現場で実際に起こったことは、各コンテンツの接触体験が基本的に無料で摂取可能なSNSや動画サイト等と並置されるようになったことで、それらのコミュニケーションに費やされる可処分時間の競合に晒され、かえってユーザーの財布の紐が堅くなるという事態であった。ウェブ2.0的なデジタルメディアの双方向化が行き着いた結果、プロのエンターテイナーが一斉供給する拘束時間が長く完結性の高い「作品」よりも、アマチュア同士が刹那に交換する個別的なメッセージやちょっとしたUGCを共有する「体験」の方が、より時間を費やす価値のある体験として選好されるようになっていったのである。
同様の傾向は、ソーシャルメディアの土俵内における支配的なプラットフォームの変遷という局面においても見出すことができる。例えば2000年代後半に隆盛したmixiのような蓄積型の日記コンテンツと相互承認式のコミュニティ形成をベースにしたSNSは、運営サイドによる仕様変更の迷走もあって、2010年代には廃れていく。かわりに140文字制限式のミニブログをユーザー同士が一方的にフォローしあうTwitterや、「いいね!」ボタンによる気軽な共感表明が可能なFacebookといった、より刹那的でライトな交流手段を持つフロー型SNSが国内でも台頭。
多くの国産サービスはiモードなどのケータイ特化型のインターネット利用形態に適応しすぎていたため、スマホ対応がいまいちこなれなかった。対して海外サービスの方は、もともと世界標準のPC用インターネットをそのまま利用する前提のスマホにおいても完成度の高いクライアントアプリを早期にリリースすることができた。デバイスハードの移行が、そのまま支配的なサービスの移行をも帰結したわけである。
そして、このようなきめ細かなコミュニケーション環境の確立は、国内外における人々の社会レベルの現実的事象との関わり方を、良くも悪くも左右していくことになる。
スマートデバイスやソーシャルメディアによる個人の情報発信力の拡大は、元をたどれば第2章に述べたように1960年代のアメリカ東西両海岸におけるハッカーたちの反体制的な社会変革のマインドが、スティーブ・ジョブズやマーク・ザッカーバーグといったイノベーターたちのパーソナリティを介して具現化したものに他ならないが、その直接的な継承者として名を馳せたのがジュリアン・アサンジ率いる情報リーク運動「ウィキリークス」や、仮面姿の匿名ハッカー集団「アノニマス」といったハクティビズムのムーブメントであった。時には非合法的なハッキング手段に訴えてでも国家機関や大資本に巣くう腐敗を詳らかにし、サイバー攻撃で懲らしめようというのが、その正義感の内実だ。
彼らの活動は欧米先進国型の形態と言えるが、アフリカや中東、アジアの途上国における「ジャスミン革命」や「アラブの春」といった民主化要求運動における大衆動員のツールとしてもソーシャルメディアの役割が注目され、半世紀前の〈夢の時代〉における世界的なカウンターカルチャーの隆盛を彷彿とさせるような同時代性さえ醸成されていく。
しかしながら、リベラルな理念先行だった〈夢の時代〉のハッカーマインドとは異なり、ソーシャルメディアの普及と活用が単に人間の生々しい現実と結託する価値中立的な道具となっている〈拡張現実の時代〉にあっては、母体である欧米的価値とは、まるで相容れないベクトルへの動員に使われることもままあった。その最大の鬼子が、アメリカによるイラク戦争の矛盾が生んだイスラム原理主義勢力「イスラム国」のような存在であろうことは論を待つまい。
(関連記事)
ソーシャルネット時代のリアリティと「イスラム国」――日本人は"ヤツら"とどう向きあうべきなのか(軍事評論家・黒井文太郎インタビュー)
このような功罪両面を持った「動員の革命」は、日本にあっても大きな変動をもたらしていく。転機となったのが、戦後最大の天災となった2011年3月11日の東日本大震災と、それによってもたらされた福島第一原発の深刻な事故であった。発生当時、東北から関東にかけてのインフラが広範に麻痺する中、様々なデマや風評といったノイズを伴いながらも、被災者救助などに携帯情報端末やSNSが概ね有効に機能したという経験や、脱原発運動を皮切りに久しく日本では沈静化していた大規模デモなどの社会運動が復活を遂げたりと、世界的動向に同期するソーシャルメディアの政治社会的動員が顕在化したのである。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は今月も厳選された記事を多数配信します! すでに配信済みの記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201512
-
「人生100年」時代にどう生きるべきか(石川善樹『〈思想〉としての予防医学』第7回)【毎月第2火曜配信】 ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.467 ☆
2015-12-08 07:00
毎月第2火曜は、予防医学研究者・石川善樹さんの『思想としての予防医学』をお届けします。今回は、前世紀には予想もされていなかった「人生100年」時代を迎え、私たちがこれから考えるべきライフプランの「基本思想」について解説します。
▼執筆者プロフィール
石川善樹(いしかわ・よしき)
(株)Campus for H共同創業者。広島県生まれ。医学博士。東京大学医学部卒業後、ハーバード大学公衆衛生大学院修了。「人がより良く生きるとは何か」をテーマとして研究し、常に「最新」かつ「最善」の健康情報を提供している。専門分野は、行動科学、ヘルスコミュニケーション、統計解析等。ビジネスパーソン対象の講演や、雑誌、テレビへの出演も多数。NHK「NEWS WEB」第3期ネットナビゲーター。
著書に『最後のダイエット』、『友だちの数で寿命はきまる』(マガジンハウス)など。
本メルマガで連載中の『〈思想〉としての予防医学』これまでの記事一覧はこちらのリンクから。
前回:「面白い」を科学の眼でとらえるには(石川善樹『〈思想〉としての予防医学』第6回)
前回、私は20世紀に、人類はほとんど別の生き物のような存在になったということを書きました。
これまで私たちは「人生50年」と考えて、とにかくがむしゃらに仕事をして、その後は年金暮らしをすればいいじゃないかと考えていました。しかし、20世紀の人類は、「飢えと貧困」というこれまで人類を苦しめてきた二大要素にある程度の解決を着けて、爆発的に平均寿命を伸ばしてしまいました。その傾向は今後も続いていくはずです。おそらく現在の現役世代の人々が高齢者になる頃には、平均寿命が100歳になっている可能性は決して少なくありません。
私は、この「人生100年」時代に突入する可能性を真剣に考えて、この文章を読んでいる20代~40代の皆さんは自分の仕事や生活を設計していくべきだと考えています。高齢者になってから考えるのでは、もう遅い問題です。おそらく年金支給の年齢だって、その頃には引き上がっています。現在の制度は、よもや年金給付者がその後数十年を当たり前に生きていくなんてことを想像だにしていない時代の産物だからです。
私はこういう時代のキャリアプランとして、ひとまず50歳を節目にすることを提唱しています。それはこの年齢が、まだ人間が新しいことに挑めるだけの体力がある、ギリギリの年齢だからです。そうして、この50歳を節目にした第二のキャリアの中で、人生の終末期にあたる最後の時期の生活を、金銭的にも健康的にも支えるための様々な準備をするのです。
現在、定年退職後の男性サラリーマンで、特にやることがなく、日々を手持ち無沙汰に暮らしているという人は沢山います。残念ながら、いくら人生100年の時代が近づいていても、65歳などになってしまった人間にはなかなか新しいことが出来ないのです。だからこそ、この50歳という年齢を意識して、自分のふたつ目のキャリアプランを考えるのが重要です。
さて、それではこの50歳以降の二つ目のキャリアプランとは、いったいどんなものでしょうか。
それは、やはり若い人間の考えるものとは大きく違ってきます。この50歳という年齢に入ると、もう精神的にも肉体的にも若い頃のようには行きません。
そうなったとき、どうやら人は気の合う仲間と仲良く暮らしたりして、朝起きてから夜寝るまで一瞬一瞬をいかに幸せに生きていくかが大事になるようです。
しかし、そういうプライベートな幸せが大事になっていく一方で、「世の中を変革したい」などのパブリックな夢はしぼんでいきます。若い頃のようにムチャな働き方をして、気の合わない人間とでも仕事をして、社会を良くしようと考える――という発想はやはり取れなくなってしまうようです。
これはどっちが良いか悪いかというものではなく、そういうものなのです。
ですから、こういうことを踏まえると、人生の最初の50年は社会の幸せになる仕事に邁進して、セカンドキャリアの25年程度は自分や自分と気の合う仲間の幸せを大事にした仕事をやって生きていく、というのは人生のライフステージに合った考え方なのかもしれません。
また、こんなふうに考えることも出来ます。
私たちはこれまで人生のキャリアを考えるときに、自分という「個人」のやりたい夢と、「社会」の中で求められる価値の二つをいかに整合させるかに悩んできました。しかし、いまや人生は「一毛作」ではなくて「二毛作」になっている……と考えると、ファーストキャリアでは社会のために生きて、セカンドキャリアでは自分の夢に生きる、ということも選択肢の視野に収められるようになるはずです。
■ 主婦は「人生二毛作」をすでに生きている
こうした問題について私たちの社会は、あまり真剣に考えてきませんでした。しかし、現状でも100歳とまでは言わなくとも、80歳や90歳まで生きる人は決して少なくないのです。彼らは、子育てを終えて定年退職をしてからも、何十年という時間を生き続けます。
そのとき、どういう生き方が幸せなのかを、私たちは考える必要があります。
ところで、実はずっと前からこういう生き方を実践してきた人たちがいます――それは、日本の専業主婦の人々です。
こういう仕事で高齢者の人々と会うと、すぐに気づかされるのが日本の女性の高齢者の元気さです。男性の高齢者は、皆それぞれに若い頃にエネルギッシュに働いていたのだろうと思いますが、どこかシュンとしていて、趣味も少なく淋しげにしている人が多い。それに対して、女性の高齢者の方は趣味や友人づきあいを持っている人も多く、旅行に出かけたりして、とても元気です。僕もこういう仕事で健康セミナーなどを始めた頃、なぜ「おばあさんたちばかりが、こんなに元気なのだろう?」と不思議に思ったものでした。
その後、徐々に分かってきたのは、彼女たちがまさに50歳の頃にセカンドキャリアを真剣に考えていたことでした。
この時期、女性たちはちょうど子育てを終えて、また肉体的にも閉経期や更年期障害などに悩まされます。しかし、それが結果的に彼女たちに、自分の人生と真剣に向き合わせているように思います。ここで多くの主婦の女性たちは、人生に一区切りをつけます。そして主婦として家族のために生きてきた自分の人生を見つめなおして、今後の自分の人生を考えるようになります。
一方で、男性の方はというと、50歳の頃に女性のような問題に直面することは、良くも悪くもありません。そうして定年退職まで必死で会社のために働くのですが、65歳になってはたと気づいてみれば、特に趣味もなければ仕事を離れた友人もいない――そんな人はざらにいます。しかも、先ほども言ったように、この年齢まで行ってしまうと、もう新しいことを始めるのも難しい。そうして、多くの男性はただ燃え尽きていくのです。
しかし、本当に大事なのは、絶好調のときにこそ次の準備をしておくことです。
棋士の羽生善治さんは七冠のときに「将棋の五手目に何を指せばいいか」について書いた研究本を出して、当時の多くの人を不思議がらせました。こういうふうに自分が良い時期にしっかりと視点を変えていく姿勢は、とても大事なことです。
50歳の頃に女性のような悩みに直面しない男性は、かえってこの時期に羽生さんのように視点を自ら大胆にずらすのが必要になります。そして、むしろ女性たちからこそ、その後の人生の生き方を学んでいく姿勢が大事になるのだと思います。
■ 長く活躍する研究者は“分野を変える”
とはいえ、これからの50歳以降の人生は、趣味に遊ぶだけでなく、しっかりと稼いでいく必要もあります。もはや現行の年金制度がそのまま持続するのは難しいからです。こういう時代に上手にセカンドキャリアを築くためには、何が必要なのでしょうか。
以前、価値ある研究を続けられた人(ノーベル賞受賞者も含む)と、そうではなかった人について研究した論文がありました。それによれば、長く活躍を続けた研究者は平均して5回、大胆に自分の研究分野を変えていたのだそうです。それに対して、一発屋のような業績しか残せなかった研究者は、一つもしくはせいぜい二つの研究分野に固執して一生を終えていたそうです。
▲遺伝子の研究でノーベル生理学賞を受賞した利根川進氏は、受賞後に記憶の研究に分野を変えた。(出典)
日本の利根川進さんなどはその典型と言えます。彼は自分がノーベル賞を受賞した途端に研究分野をガラリと変えて、神経科学の道へと転向しました。また、若き日のアインシュタインなどもそうでしょう。彼は相対性理論の研究をする前に、ブラウン運動や流体力学などの様々な分野の論文を執筆しています。
この研究結果は、私たちがまさに自分の分野を上手く切り替えて、長く活躍を続けていくためのヒントになるように思います。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は今月も厳選された記事を多数配信します! すでに配信済みの記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201512
-
月曜ナビゲーター・宇野常寛 J-WAVE「THE HANGOUT」11月30日放送書き起こし! ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.466 ☆
2015-12-07 07:00チャンネル会員の皆様へお知らせ
PLANETSチャンネルを快適にお使いいただくための情報を、下記ページにて公開しています。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/ar848098
(1)メルマガを写真付きのレイアウトで読む方法について
(2)Gmail使用者の方へ、メルマガが届かない場合の対処法
(3)ニコ生放送のメール通知を停止する方法について
を解説していますので、新たに入会された方はぜひご覧ください。
月曜ナビゲーター・宇野常寛J-WAVE「THE HANGOUT」11月30日放送書き起こし!
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.12.7 vol.466
http://wakusei2nd.com
大好評放送中! 宇野常寛がナビゲーターをつとめるJ-WAVE「THE HANGOUT」月曜日。前週分のラジオ書き起こしダイジェストをお届けします!
▲先週の放送は、こちらからお聴きいただけます!
■オープニングトーク
宇野 時刻は午後11時30分を回りました。みなさんこんばんは、宇野常寛です。今日は久しぶりにテレビの話をしちゃおうかなと思っています。僕は4月から、日本テレビ系の朝のワイドショーの「スッキリ!!」という番組に出ているんです。僕としては珍しく、この半年の間スタッフさんとも共演者さんとも仲良くやっているんですよ。僕はテレビっぽいテレビ番組にでると、9割くらいの確率でケンカをして辞めちゃうんですけれど、「スッキリ!!」は奇跡的に続いているんです。
その理由として、同世代の男子が多くて、話が合うのが大きい気がしているんです。僕の2歳年上の総合演出の服部さんや、アシスタントプロデューサーの鶴田さんとか。出演者だと、森アナウンサーや上重アナウンサーとか、コメンテーターの坂口孝則さんとかですね。このへんが僕の同い年で、僕のやろうとしていることにけっこう理解を持ってくれているんですよ。坂口さんなんかは「スッキリ!!」で共演する前から、僕がつくっている雑誌『PLANETS vol.9』に記事を書いてくれたりしている人なんです。
特にスタッフの方が、僕のアンチテレビ的な考え方を利用して、番組の幅を広げようとしてくれているんですよね。僕のことをよく調べてくれていて、最初からそのつもりで話を持ちかけてきているんですよ。このラジオも聴いてくれているはずだし、僕の本とかもよく読みこんでくれています。
あとはMCの加藤浩次さんの存在ですね。この人は正直に言って、僕と意見が合うタイプではないと思うんですよ。ガンダムが好きで、左翼が嫌いで、J・J・エイブラムスが嫌いなのは意見が合うんですけれど(笑)、ほかはそんなに合うタイプじゃないと思うんです。でも合わないなりにお互いそれをけっこう楽しんでいるような感じで、わりとうまくやっていると思うんですよね。
そんな感じで、スタッフの一部には「仲良し木曜日」と呼ばれているくらいなんです。聞くところによると、他の曜日はそんなに和気あいあいとしていないらしいんですよね。せっかくそういう環境でやらせてもらっているんだから、来年からはもう少し番組に踏み込んでいきたいなと思っています。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は今月も厳選された記事を多数配信します! すでに配信済みの記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201512
-
戦後史としてのロボットアニメと〈移体性〉――フランス人オタクと日本アニメ熱狂の謎に迫る 『水曜日のアニメが待ち遠しい』著者 トリスタン・ブルネ インタビュー 前編(毎週金曜配信「宇野常寛の対話と講義録」) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.465 ☆
2015-12-04 07:00チャンネル会員の皆様へお知らせ
PLANETSチャンネルを快適にお使いいただくための情報を、下記ページにて公開しています。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/ar848098
(1)メルマガを写真付きのレイアウトで読む方法について
(2)Gmail使用者の方へ、メルマガが届かない場合の対処法
(3)ニコ生放送のメール通知を停止する方法について
を解説していますので、新たに入会された方はぜひご覧ください。
戦後史としてのロボットアニメと〈移体性〉――フランス人オタクと日本アニメ熱狂の謎に迫る『水曜日のアニメが待ち遠しい』著者 トリスタン・ブルネ インタビュー 前編(毎週金曜配信「宇野常寛の対話と講義録」)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.12.4 vol.465
http://wakusei2nd.com
今朝のメルマガは、日本史の研究者であり翻訳家でもあるトリスタン・ブルネさんのインタビューの前編です。フランスにおける日本のサブカルチャー受容の過程をまとめた著書『水曜日のアニメが待ち遠しい』を下敷きに、オタク文化、特にロボットアニメのグローバルな視点から見た本質について語り合います。
▼プロフィール
トリスタン・ブルネ
1976年フランス生まれ。ジュネーヴ大学大学院博士後期課程在籍。日本史学研究。翻訳家。日本のアニメ、マンガなどに造詣が深く、フランス語版『北斗の拳』をはじめマンガの翻訳に携わる。2004年に初来日。以後、留学経験を経て、現在は、日本の大学や語学学校で、フランス語、フランス思想の講師もつとめている。
■ なぜ日本のアニメはフランスで受容されたのか
宇野:ブルネさんのご著書『水曜日のアニメが待ち遠しい:フランス人から見た日本サブカルチャーの魅力を解き明かす』を読ませていただきました。本当に素晴らしかったです。たいへん勉強になりました。
ブルネ:ありがとうございます。
▲トリスタン・ブルネ『水曜日のアニメが待ち遠しい』誠文堂新光社
宇野:フランスで日本のアニメやマンガがポピュラリティーを得ているというのは、日本国内でも有名な話です。ただその紹介のされ方は、「フランス人にもわざわざ日本のアニメを追いかけている変わった人がいる」という文脈で、面白おかしくデフォルメされている場合がほとんどだった。また、これは僕自身が日頃から感じていることですが、日本のアニメが海外で支持されている、という話を過剰に解釈して安易なナショナリズムに結びつけてしまう日本人のファンも少なくありません。その中でこの本は、その受容の実態を、フランス人個人の経験とアカデミックな視点の両面からまとまって紹介した、初めての例だと思います。
ブルネ:まさにそれが、この本で目指したことです。僕自身はこれまで計6年ほど日本に住んでいますが、1976年に生まれてから20代半ばまでは、日本アニメを浴びるように見て育った一人のフランス人オタクでした。それが2004年の初来日の際、たまたま日本の踏切の音を聴いて、初めて触れたはずのその音にノスタルジーを感じたことから、自分の人格形成における日本アニメの大きさに気づき、この問題を歴史的に考え始めたんです。ただ状況はフランスでも同じで、日本のアニメやマンガを深刻なイシューとして語ろうとしても、「単なる社会現象だ」と済まされてきた。今回の本の出発点は、「僕たちが生きてきた時代は何だったのか?」ということを、アカデミックな観点を含めて、個人の経験からわかりやすく追おうとしたことにあったんです。
宇野:ご自身が強く惹かれてきた日本アニメの奇妙な魅力と、その結果生まれた、フランスでのポピュラリティーの謎を解き明かしたい、と?
ブルネ:そうですね。「解き明かしたい」と同時に、そもそもそこにある巨大な「謎」の存在を多くの人に知ってほしい、という気持ちでした。誰もが当然のように「日本のアニメはフランスで人気がある」と言いますが、それ自体がすでにおかしな話でしょう。日本とフランスは、社会も文化のあり方も、基本的にはまったく異なる国ですから。
宇野:この本の面白さの最大のポイントは戦後の日本のアニメが結果的にですが、戦後の西側諸国が広く共有していた中流家庭、アッパーミドルのライフスタイルや価値観を表現するものになっていて、それが世界的なポピュラリティーの源泉になった、ということを指摘しているところだと思います。日本アニメのポピュラリティーを語ろうとするとき、アニメが好きな人も嫌いな人も、むしろ逆に日本の独自性に結びつけて考えがちですよね。つまり、アニメ肯定派は、日本の伝統的な価値観が現代の映像文化に引き継がれて開花した、と主張する。一方の否定派は、それをオリエンタリズムと批判する。どちらもグローバルな評価の根拠に、一種の日本性を見ていることは変わりません。が、ブルネさんの本は逆です。むしろ、戦後の先進国に薄く広く共有されていた、アッパーミドルの価値観に注目をされている。
ブルネ:おっしゃったように、日本でもフランスでも、すべての先進国は、戦後の20世紀後半に、それまでの価値観が大きく変わる経験をしました。高度経済成長で物質的に豊かになっただけでなく、人々の人間関係や、日常生活のあり方が変わったわけです。たとえば僕は、パリ郊外の新興住宅地の生まれですが、この「郊外生まれ」という経験も、戦後の先進国ではありふれたものになっていきました。しかし問題は、こうして厚みを増した中間階層の存在を、歴史の上で位置付ける視点がない、ということです。
意外かもしれないんですが、フランスは国家の力が強い国で、いまもエリートを頂点にした階層的な価値観がある社会です。そして国の物語である歴史も、「エリートと民衆の対立」という構図で記述されてきました。ところがこの構図には、支配層であるエリートとも、従来の民衆とも違う、戦後に増えた中間階層の位置がない。歴史から自身の正当性を与えられないことは、不安です。僕は、日本アニメの人気の背景には、こうした中間階層の不安や不満を解消したという点があると思っているんです。
宇野:ただ、ここで素朴な疑問として浮かぶのは、それがなぜアメリカのホームドラマやハリウッド映画ではなかったのか、ということです。これについてはいかがですか?
ブルネ:西ヨーロッパとアメリカは、いつもセットで「西洋」と呼ばれますよね。しかし、ヨーロッパの社会の基本的なユニットは「村」ですが、新大陸であるアメリカにはそれがない。ただ、荒野が広がっているだけです。人の経験の出発点となるものが違うので、フランスからアメリカに行くと違和感があるんですね。一方、一見かけ離れた日本には、フランスと同じような村のユニットがある。その意味で、じつは日本の方が、空間のあり方や、そこでの人々の営みの形態が近いんじゃないでしょうか。
宇野:ユーラシアとアメリカでは、根本的に地理感覚や空間感覚が異なるせいで、ハリウッド映画やアメリカのテレビドラマは、フランスの中産階級のカルチャーを表現するツールになり得なかった、と。
ブルネ:フランスも日本も、郊外の広がりによって何かが失われるという経験をしています。でもアメリカの郊外は、いわばゼロから作られたものでしょう。
宇野:郊外化もモータリゼーションも、日本やヨーロッパにとっては、トラディショナルなものの喪失だったけれど、アメリカにはその喪失感がないということですね。中流化や郊外化を言い換えると、アメリカ的なライフスタイルの受容でもあったと思います。もっとはっきり言うと、ヨーロッパではマーシャル・プランによって、日本ではGHQの占領政策の中で、既存のスタイルを上書きしながら進行したものだった。
ブルネ:実際、日本アニメでは、その喪失感がよく主題になりますよね。たとえば『となりのトトロ』も『平成狸合戦ぽんぽこ』も、埼玉の郊外や多摩ニュータウンで失われたものをテーマに扱っている。しかし同じ経験をしたはずのフランスには、なぜかこの種の物語があまりないんです。フランス人が求めるものがそこにはあったんですね。
宇野:僕は本州で生まれたのですが、10代の頃何年か、北海道に住んでいたんです。今の話で言うと、北海道はアメリカですね。100年前から人が住んでいなかったところがほとんどなので、一見、本州と同じような郊外都市が広がっていも、今おっしゃったような喪失感はありません。しかし本州は違う。中流化を支えた郊外都市はクリーンで明るい一方でどこか物悲しい喪失感が漂っている。国外に住んだことはないですが、北海道と本州の両方を住んだ経験から、その違いは非常に共感できます。
■「偽の成熟」としての巨大ロボット
宇野:その一方で、アニメというのは風景を絵に置き換えるわけで、現実より一段、抽象性が高いですよね。そのことによっても、共感性は高まったと思うのですが?
ブルネ:抽象性も大事な要素ですよね。たとえば、フランスで初めて大人気になった日本アニメは、1978年に放送が開始された『UFOロボ グレンダイザー』でした。このグレンダイザーのような巨大ロボットも、抽象性の高いひとつのモチーフです。
宇野:そしてロボットは定義上、人工知能を持つもののはずですが、日本の巨大ロボットは、なぜか乗り物です。ここには直接何かにコミットするのではなく、間接的なコミットでありたい、という欲望があると思うんです。
ブルネ:そうですね。操縦者が必要です。
宇野:日本のロボットアニメはマーチャンダイジングと関係があって、小さい男の子の成長願望に訴えかける表現でした。非常に力強く、大きな身体への憧れでもあった。しかしその一方、どこかであれは偽物だ、という感覚があります。同様に、日本でもヨーロッパでも、アメリカのライフスタイルを取り入れて郊外に家を持ち、中流的な生活を築くことが憧れであると同時に、偽物でもあるという感覚があると思うんです。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は今月も厳選された記事を多数配信します! すでに配信済みの記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201512
-
学園都市の異常なる日常 〜人文系軽視なんてとんでもない⁉︎~ (橘宏樹『現役官僚の滞英日記:オクスフォード編』第2回)【毎月第1木曜配信】 ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.464 ☆
2015-12-03 07:00チャンネル会員の皆様へお知らせ
PLANETSチャンネルを快適にお使いいただくための情報を、下記ページにて公開しています。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/ar848098
(1)メルマガを写真付きのレイアウトで読む方法について
(2)Gmail使用者の方へ、メルマガが届かない場合の対処法
(3)ニコ生放送のメール通知を停止する方法について
を解説していますので、新たに入会された方はぜひご覧ください。
学園都市の異常なる日常
〜人文系軽視なんてとんでもない⁉︎~
橘宏樹『現役官僚の滞英日記:オクスフォード編』第2回【毎月第1木曜配信】
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.12.3 vol.464
http://wakusei2nd.com
今朝のメルマガでは、英国留学中の橘宏樹さんによる『現役官僚の滞英日記』最新回をお届けします。この秋よりロンドンからオクスフォードへと学びの場を移した橘さん。観光客の目線ではただの田舎町にも思えてしまうオクスフォードですが、その「内部」に隠されている「異常なる日常」とは? まるでハリーポッターのような入学式の様子や、学生同士の交流で見聞した「オクスフォード独特の知的風土」についてレポートします。
▼プロフィール
橘宏樹(たちばな・ひろき)
官庁勤務。2014年夏より2年間、政府派遣により英国留学中。官庁勤務のかたわら、NPO法人ZESDA(http://zesda.jp/)等の活動にも参加。趣味はアニメ鑑賞、ピアノ、サッカー等。
本メルマガで連載中の橘宏樹『現役官僚の滞英日記』これまでの配信記事一覧はこちらのリンクから。
※本稿の内容(過去記事も含む)に関して、皆様からのご質問や、今後取材して欲しいことを受け付けたいと思います。こちらのフォームまたはTwitter(@ZESDA_NPO)にお寄せいただければ、できるかぎりお応えしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。橘です。現在、オクスフォードでの学生生活が6週間ほど過ぎたところです。田舎街に引っ込んで、大学とカレッジ(寮)を自転車で往復する毎日です。ロンドンでの日々に比べて、非常に静謐な環境で穏やかに暮らしています。
ロンドンで学んでいた時期は、経済、社会、政治、芸術の世界的中心地に暮らしていましたから、ある意味新しい気づきを得ることは容易でした。対して、オクスフォードは本当に、大学しかない小さな田舎町です。
クラスメイトたちとの関係やアカデミックな交流はより濃密になったのですが、社会的な活動範囲はかなり狭くなりました。各界の最先端を走るPLANETSファミリーの方々の記事を拝読して非常に刺激を受けているなかで、この連載ではどういう内容で貢献できるだろうかと考えながら暮らしています。
オクスフォードの知の伝統を伝えるレポートは世のなかに既にたくさんありますから、それで終わらないようなものをご報告できたらいいなと思っているのですが、ようやく最近になって、900年近くかけて構築されてきた知のプラットフォームのスタイルと、その様式の目的や必然性、場合によってはその弱点、それから教育の方法論とその背景にある哲学やスタンスといったことについてならば、僕からみなさんにご報告するに値することがあるかもしれない、と思えるようになってきました。
そこで手始めに今回は、オクスフォード大学の入学式の様子や、学生たちとの交流の中で感じた微妙な違和感、知のプラットフォームの一端を担う勉強会の様子についてご報告したいと思います。
■ オクスフォード大学の入学式
10月初旬、オクスフォード大学の入学式に参加しました。新入生は、男性は白い蝶ネクタイ、女性は紐タイをして、アカデミックガウンを羽織ります。(蝶ネクタイなんて生まれて初めてつけましたよ。)衣装は街中の商店で売っています。黒いスーツも含めて上から下まで揃えると、だいたい300ポンド(6万円くらい)はかかります。このアカデミックドレスによる正装は、卒業式のほか、学期末試験の際にも着用するとのことで、この時はさらに胸にカーネーションも挿すそうです。
▲入学式のついでにハリーポッター風のコスプレも楽しむクラスメイトたち。(この中に僕は居ません)
入学式は、カレッジとユニバーシティそれぞれが主宰するものが同日に行われました。まず朝、カレッジの方では、食堂を兼ねた大講堂に集められた正装した新入生にパンとコーヒーとデザートが振舞われました。
しばらくガヤガヤと歓談していると、銅鑼(!)が打ち鳴らされ、静粛になったところ、真っ赤なアカデミックドレスを羽織ったカレッジの校長から式辞がありました。概ね、「さあ、今日はいよいよmaticulation(マティキュレーション=入学式。後述)だね、行っておいで。あ。その前に写真撮ろっか」というような内容で、全体的に新入生を歓迎するどころか、むしろ「送り出す」「共に行く」という寛いだ雰囲気でした。正装する校長の佇まいも、さしずめ子供の入学式に同行する一張羅のお父さんという風です。
▲カレッジの中庭、正装して記念写真に臨む友人達
▲カレッジの校長らしき人物
もっとも、こうした空気はカレッジや校長のキャラクターごとに異なるかもしれませんが、厳しさや身分の上下がはっきり示されているなかでも、上の者(教員)から下の者(学生)に対する確かな愛情というか、「見守っているよ」という視線、包容力を、この大学での生活を形作る様々な決まりごとの端々から感じられます。
伝統とは形式主義にあらず。様々な決まりごとや習慣は、長く若者の愛し方を洗練させてきた工夫そのものであり、オトナ達が温かい愛情を通わせてこそ機能する教育手段に過ぎないのだな、と。
30歳を過ぎてまた学生をやることからなおさら、そういうことが染み入るように感じられる思いがします。たとえそれが、エリートがエリートを選んで与える、時に鼻持ちならない類の愛情であったとしても。
この点、ロンドンでの学校は、膨大な課題と必読文献を浴びせるとともに、厳しいクリア基準を課し、オフィスアワーに教授を訪ねればいろいろ教えてもやるが、「学ぶもドロップアウトするも自己責任」というような比較的突き放したスタンスでしたから、実に対照的に感じられます。
カレッジの中庭で記念のポートレートや集合写真を撮影した後、今度は、ユニバーシティが主宰するmaticulation(マティキュレーション)と呼ばれる儀式に参列しました。いわゆる正式な入学式としてイメージしていただいて良いのですが、これによって入学を「許可する」、オクスフォードの学生の身分と権利を「授与する」という意味が強いようで、ゆえに厳しく正装が求められています。カレッジ2~3個でひとグループにされた1000人程度の新入生(家族等の入場は不可)が、指定された時間に天井画の美しい格調高い講堂に集められました。
▲maticulation直前の会場内。
しばらくすると、オクスフォード大学の校章を背負ったシンプルながらもゴージャスなアカデミックガウンを羽織った学長が、いかにも儀典用というような、大きな錫杖を持った人に先導されながらゆっくり入場し高座に立ちます。その後、代表の教授がラテン語で何か呼びかけ、学長が何か応えるというやりとりがありました。続いて、”Ladies and gentlemen, welcome to Oxford”と英語で挨拶を始めたので、「うわ。ラテン語かよ。全然わからんよ。ラテン語でこの後も式辞が続くのか……?」と不安に思っていた会場からは安堵の笑いがどっと起こりました。
▲別アングルから。正面の高座に学長が、下の座席に教授陣やカレッジの校長等が座ります。
その後は、おそらく20分にも満たないジョーク交じりの講話があり、内容は、概ね、「ここは古いだけじゃない。最先端だ。最高だから頑張れ。楽しめ」的な、わりとあっさりとしたものでした。何か印象深いことを言おうという力みも、重々しくやろうという姿勢も感じられませんでした。
現在学長を務めるのはイギリス出身の化学者であるアンドリュー・D・ハミルトン(Wikipedia)ですが、彼はオクスフォード大で学生歴も教員歴もない学長(史上初)です。ハミルトン学長がこうした力みのないキャラクターであるのは、着任してまだ数年と間もないためオクスフォード的重厚感に染まっていないからなのか、もともとリベラルが信条であるからなのか(元イエール大学長)はわかりませんけれど。
そして、事実上、この講話だけでmaticulation自体も終了しました。カレッジは38個ありますし、学長も多忙ですから1日で終わらせたいようで、厳かさは保ちつつも、回転数を重視した進行であったということでしょう(つまり、学長は同じジョークを10回は言うのでしょう)。
退場後の学生たちは、それぞれ友達や家族とともに、格調高い建物や緑をバックにして、アカデミックコスプレ撮影会を大いに楽しんでいました。そして、その日の晩のうちに、僕の同級生たちのfacebookのプロフィール写真は、誇らしさと喜びに満ちた笑顔へと次々に更新されていきました。
ちなみに、僕がロンドンで通った1年目の大学では、このような儀式どころか、入学式すらありませんでした。第一週は登録や諸手続、オリエンテーションがあり、次週から「はい、授業開始~!」という感じでした。これはこれで簡単ですが、なんだか物足りなさも感じていました。あらためて、だいぶリベラルな学校だったのかなと思います。しかしさすがに卒業式はあるようで、この12月僕も参加する予定です。アカデミックドレスの貸衣装もあるようです。
また、遠い昔に参加した東京大学の入学式を思い出しますと、武道館に全新入生と家族約1万人が集まる巨大な催しで、半日がかりで一度きり。来賓、総長の式辞・祝辞、新入生代表の宣誓、現役学生部員の演舞や演奏など、なかなか長い構成だったと記憶しています。総長式辞は新聞やネットで公表され、時宜によってはある種のメッセージ性も込められます。家族も出席できるので「晴れの日の喜びを分かち合う」というような意味もあり、歓迎側の学生にも出番があります。学生コミュニティへの歓迎行為が公式行事内にまで位置づけられているという点では、イギリスの前2校に比較すれば特徴的とも言えましょう。僕がたまたま経験した3大学間の比較だけでも、実に三者三様だなと思いました。
■「日本では人文学軽視」ニュースの衝撃
新生活が始まるなか、上記のmaticulationの前後、諸手続きの行列、パーティーなどの場で初対面同士の会話をする機会があちこちであります。その度に、国籍や専攻問わず多くの人から、「日本では大学の人文系学科が廃止されるらしいな」という話題を頻繁に持ちかけられたことは、正直驚きでした。
しかも、「最近の日本のトピックと言えば、あれでしょ」とばかりに、まっすぐにこの話が上がってきます。すべての人が「人文系を軽視するなんて愚かな考えは信じられない」という反応でした。おかげで初対面同士、しかも、また会うのかどうか微妙な者同士の会話でも、かなり場が持って助かりました。
実際のところは、文科省の通知に「説明不足」があったことから誤解が広がっているわけなのですが……。
「国立大の「文系廃止」の誤解はなぜ広がったのか? 原因は「舌足らず」の通知文 文科省は火消しに躍起だが…」 (産経新聞2015年9月7日)
英語有力メディアでも、産業界からの需要が少ない人文系学科は削減されるというような論調で報道周知されてしまっていました。しかも、今夏の記事にもかかわらず、11月になっても、「おー日本人かあ、日本と言えば……」という場面で、多くの人の脳裏にすぐ浮かぶくらいにインパクトが強かったようなのです。
”Japan Rethinks Higher Education in Skills Push” Liberal arts will be cut back in favor of business programs that emphasize research or vocational training”(The Wall Street Journal )
理系の学生含め、それぞれがやや興奮しながら「人間性の本質を探求する重要さ」を力説するのを聞くたびに、オクスフォード大学界隈では、哲学・歴史といった人文学系学問、いわゆる教養(リベラル・アーツ・Liberal Arts)に対するただならぬ思い入れがあって、このニュースはそれを刺激したことは確かなのだな、と思われました。
他方で、ややちゃぶ台を返すようですが、逆にこの報道に対する過剰反応の方に違和感を感じてみることもできると思います。その場合は、予算逼迫の度ごとに人文不要論が何百年ものあいだ幾度となく提起されてきたからこそ、これに猛烈に反駁する伝統もまたオクスフォードに育まれているのかもしれない、という仮説を立てることも可能かもしれません。
▲大学のグッズを売る商店。カレッジごとに紋章や模様が異なります。
■「一応、哲学やってます(照)」に感じる違和感
また、日を追うにつれて、オクスフォードの人々は「人文系軽視に怒る」にとどまらず、「哲学・歴史を学ぶことは普通よりちょっと素敵であると思っている」ようにも感じられてきました。非常に微妙なニュアンスではあり、あくまで僕が交流した範囲での印象論ですが、もう少し、具体的に描写したいと思います。
まず、学生同士は初対面で自己紹介をかわす冒頭、必ずと言って良いほどお互いの専攻を聞くわけなのですが、概して理系の人たちは、社会科学系の人には、「ふーん。おもしろそうねー。興味深いわねー」というリアクションをとります。いたって普通です。
でも、哲学・歴史系の人に対しては、「(きゃ or おお、かっこいい)」という表情、そして時には「自分なんて実験してる(またはシャーレ覗いてる)だけのオタクだから……」という自虐混じりのリアクションまでとる、という違いがなんとなく見受けられるように思います。
そして、哲学・歴史系専攻側も、「はは。それほどでもないよー。あなたの学問だって興味深いと思うよー」というような、うっすら上から目線のリアクションがあるような感があります。この感じは、一時日本で少し槍玉にあがったこともある「学校どこ?」「『一応』、東大です」に似ているかもしれません。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は今月も厳選された記事を多数配信します! すでに配信済みの記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201512
-
『ドラがたり――10年代ドラえもん論』(稲田豊史)第5回 ふたりのファム・ファタール 前編【毎月第1水曜配信】 ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.463 ☆
2015-12-02 07:00チャンネル会員の皆様へお知らせ
PLANETSチャンネルを快適にお使いいただくための情報を、下記ページにて公開しています。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/ar848098
(1)メルマガを写真付きのレイアウトで読む方法について
(2)Gmail使用者の方へ、メルマガが届かない場合の対処法
(3)ニコ生放送のメール通知を停止する方法について
を解説していますので、新たに入会された方はぜひご覧ください。
『ドラがたり――10年代ドラえもん論』(稲田豊史)第5回 ふたりのファム・ファタール 前編【毎月第1水曜配信】
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.12.02 vol.463
http://wakusei2nd.com
本日お届けするのは『ドラがたり――10年代ドラえもん論』(稲田豊史)の第5回。今回からは「しずか」と「ジャイ子」という、ドラえもん作品内でも特異な立ち位置にいる2人の女性キャラクターに焦点を当てます。しずかに託されたセクシャリティ、そしてジャイ子だけが持つ「非『ドラえもん的』」な要素とは?
▼執筆者プロフィール
稲田豊史(いなだ・とよし)
編集者/ライター。キネマ旬報社でDVD業界誌編集長、書籍編集者を経て2013年にフリーランス。『セーラームーン世代の社会論』(単著)、『ヤンキーマンガガイドブック』(企画・編集)、『ヤンキー経済 消費の主役・新保守層の正体』(構成/原田曜平・著)、評論誌『PLANETS』『あまちゃんメモリーズ』(共同編集)。その他の編集担当書籍は、『団地団~ベランダから見渡す映画論~』(大山顕、佐藤大、速水健朗・著)、『成熟という檻「魔法少女まどか☆マギカ」論』(山川賢一・著)、『全方位型お笑いマガジン「コメ旬」』など。「サイゾー」「アニメビジエンス」などで執筆中。
http://inadatoyoshi.com
PLANETSメルマガで連載中の『ドラがたり――10年代ドラえもん論』配信記事一覧はこちらのリンクから。
前回までは、3回分を費やしてのび太というキャラクター、および「のび太系男子」と呼ばれる3〜40代男性の精神構造上の難儀(生きづらさ)について述べた。今回は、『ドラえもん』に登場する代表的な2人の女子、しずかとジャイ子について考察してみたい。
なお、ファム・ファタール(仏:Femme fatale)の直訳は「運命の女」。宿命的な恋愛対象の女、もしくは男を破滅・堕落させる魔性の女のことを指す。新約聖書に登場するサロメ、キューブリック映画でおなじみのロリータ、谷崎潤一郎『痴人の愛』のナオミ、連合赤軍幹部の永田洋子、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』のクェス・パラヤなどが代表的なタマである。
●しずかに託されたセクシャリティ
まずは、言わずと知れたのび太の将来の結婚相手にして『ドラえもん』世界のヒロイン、しずちゃんこと源静香(しずか)について考えよう。しずかはピアノ、バイオリン、テニスなどをたしなみ、ぬいぐるみが大好き。学校の成績は上々で、優等生の部類に入る。典型的な昭和マンガのアイコン的美少女であり、教室のマドンナ(死語)。のび太が惚れるのは無理もない。こちらの連載を大幅に加筆修正した書籍が発売中です!
『ドラがたり のび太系男子と藤子・F・不二雄の時代』☆★Amazonで詳しく見る★☆ -
猪子寿之の〈人類を前に進めたい〉第3回「自然の情報量を生かしたアートを作りたい」【毎月第1火曜配信】 ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.462 ☆
2015-12-01 07:00チャンネル会員の皆様へお知らせ
PLANETSチャンネルを快適にお使いいただくための情報を、下記ページにて公開しています。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/ar848098
(1)メルマガを写真付きのレイアウトで読む方法について
(2)Gmail使用者の方へ、メルマガが届かない場合の対処法
(3)ニコ生放送のメール通知を停止する方法について
を解説していますので、新たに入会された方はぜひご覧ください。
猪子寿之の〈人類を前に進めたい〉第3回「自然の情報量を生かしたアートを作りたい」【毎月第1火曜配信】
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.12.01 vol.462
http://wakusei2nd.com
今朝のメルマガは、チームラボ代表・猪子寿之さんによる連載〈人類を前に進めたい〉の第3回です。
チームラボはなぜ今、水や木や生き物のような自然物を〈デジタイズド〉しようとしているのか。そして、そもそもなぜキャラクターのような〈依代〉を用いようとしないのか? 数々の作品の根底にある「人間とアートの新しい関係」について聞きました。
▼プロフィール
猪子寿之(いのこ・としゆき)
1977年、徳島市出身。2001年東京大学工学部計数工学科卒業と同時にチームラボ創業。チームラボは、プログラマ、エンジニア、CGアニメーター、絵師、数学者、建築家、ウェブデザイナー、グラフィックデザイナー、編集者など、デジタル社会の様々な分野のスペシャリストから構成されているウルトラテクノロジスト集団。アート・サイエンス・テクノロジー・クリエイティビティの境界を曖昧にしながら活動している。
47万人が訪れた「チームラボ踊る!アート展と、学ぶ!未来の遊園地」などアート展を国内外で開催。他、大河ドラマ「花燃ゆ」のオープニング映像、「ミラノ万博2015」の日本館、ロンドン「Saatchi Gallery」、パリ「Maison & Objet 20th Anniversary」など。2016年はカリフォルニア「PACE」で大規模な展覧会を予定。
http://www.team-lab.net
◎構成:真辺昂、稲葉ほたて
前回記事:猪子寿之の〈人類を前に進めたい〉第2回「(僕らのつくる)世界はこんなにもやさしく、うつくしい」
(実は)デジタルと自然は相性が良い
猪子 今日は宇野さんに見てもらいたいものがあるんだよね。前回までのテーマに「自然」というものがあったと思うんだけれど、チームラボでは今まさに「リアルな自然」とデジタルを組み合わせたプロジェクトをやっているんだよ。
デジタルって、よく自然から最も遠いような偏見を持たれているけれど、僕は木の机とかの方がよっぽど自然から遠いと思っているんだよね。だって厳密に言うと、木の机って自然を破壊してできたものじゃん。すべての物質的な人工物は自然の破壊によってつくられていて、僕は自然と対立する存在だと思うんだよね。
それに対してデジタルというのは、ネットワークやセンシングを使って光や音を出しているだけなので、基本的には非物質で、物理的にはなんの影響ももたらさない。デジタルと自然って、実は相性が超良いんじゃないかなと思っているんだよね。
宇野 まあ、究極的には波を当てているだけだもんね。自然をまったく加工しない、壊さないアプローチだよね。
猪子 そうそうそう。そういうことを考えて、チームラボではリアルな都市や自然そのものをデジタイズドして、庭や水族館や街をそのままアートにするプロジェクトをやっていて、それに「デジタイズド・ネイチャー・アート・プロジェクト」や「デジタイズド・シティ・アート・プロジェクト」みたいな名前をつけたりしているんだよ。
“Digitized City Art”, “Digitized Nature Art” プロジェクト
http://www.team-lab.net/concept/digitizedcityartproject.html
▲Drawing on the water surface created by the dance of koi and boats – Mifuneyama Rakuen Pond / 小舟と共に踊る鯉によって描かれる水面のドローイング- Mifuneyama Rakuen Pond
https://www.youtube.com/watch?v=Nc_F2BjVBIU
http://www.team-lab.net/all/art/mifuneyama.html
猪子 たとえば、これは2015年の夏にやった「小舟と共に踊る鯉によって描かれる水面のドローイング」というプロジェクトなんだけど、いま言った自然とデジタルの共存がよくわかると思う。
この作品は、佐賀県武雄市にある『御船山楽園』という、名勝として国登録記念物に指定されている、非常に自然豊かで美しい庭で行ったんだけど、その庭の真ん中に大きな古池があってさ、その上を小舟がすーって動いているのね。
だから、その水面をセンシングしていて、デジタルの鯉をその船の動きに合わせて躍らせてみた。最初のうちは、小舟が静かに浮かんでいると周りに集まってくるし、動き出すと避けながら踊る感じなんだけど、少しずつ鯉が泳ぎながら筆跡を残しながら溶けていき、最終的には舟の動きに合わせて鯉が踊った跡が水面にドローイングしたようになっていく。これは、まさに自然を自然のままデジタルによってアートにした作品で、こういうのをやってみようと思ってるんだよね。
猪子 いま新江ノ島水族館でやってる「えのすい×チームラボ ナイトワンダーアクアリウム2015」という展覧会とかも、そういうプロジェクトの一つかな。
▲えのすい×チームラボ ナイトワンダーアクアリウム
http://www.enosui-wonderaquarium2015.com/
▲花と魚- 相模湾大水槽 / Flowers and Fish- Enoshima Aquarium Big Sagami Bay Tank
チームラボ, 2015, インタラクティブデジタルインスタレーション, 音楽:高橋英明
https://www.youtube.com/watch?v=GDkLZHI4DLo http://www.team-lab.net/all/art/flowersandfish.html
▲呼応する球体と夜の魚たち / Resonating Spheres and Night Fish
チームラボ, 2015, インタラクティブデジタルインスタレーション, 音楽:高橋英明
https://www.youtube.com/watch?v=WExlhugszS0
http://www.team-lab.net/all/art/resonatingspheres_fish.html
▲呼応する小さな海 / Small Resonating Sea
チームラボ, 2015, インタラクティブデジタルインスタレーション, 音楽:高橋英明
https://www.youtube.com/watch?v=ge8Zsddo8wA
http://www.team-lab.net/all/other/resonating_sea.html
▲お絵かき水族館 / Sketch Aquarium
チームラボ, 2013https://www.youtube.com/watch?v=AnAqB7LZUb8
http://www.team-lab.net/all/products/aquarium.html
▲インタラクティブオーシャンバー / Interactive Ocean Bar
teamLab, 2015, Interactive Digital Installation, Endless, Sound: teamLab
https://www.youtube.com/watch?v=58Ndx2dt9DM
http://www.team-lab.net/all/products/interactiveoceanbar.html
▲チームラボカメラ / teamLab Camara
チームラボ, 2010
https://www.youtube.com/watch?v=Pfb1taVJ5Achttp://www.team-lab.com/teamlabcamera
“えのすい”って本来は17時で閉館するんだけど、その閉館後の夜の水族館を使わせてもらったんだよね。昼間は通常の水族館の営業をしていて、夜は水族館をそのまま使ってアート空間にしている。メインの「花と魚」は、基本的に魚がすいすいと自由に泳いでいるんだけど、これもセンシングで魚が水槽の縁に近づくと花が散るようになっている。
▲Flowers and Fish - Enoshima Aquarium Big Sagami Bay Tank / 花と魚 - 相模湾大水槽
https://www.youtube.com/watch?v=GDkLZHI4DLo
http://www.team-lab.net/all/art/flowersandfish.html
猪子 あと、これも宇野さんに紹介しておきたいな。これは、長崎県のハウステンボスにある500メートルくらいの運河の沿道にある作品だね。
▲Resonating Trees / 呼応する木々
https://www.youtube.com/watch?v=u3RRxERP7P0
http://www.team-lab.net/all/art/resonatingtrees.html
この道を人が歩いていくと、木に近づいたときに色や音楽がインタラクティブに変わっていくんだよ。で、その木の光は、両隣の木とか対岸の木に伝播していく。だから、500メートル先とかから光の変化がやってきたりして、「あ、人がいるな」と分かるようになっているわけ。ロマンチックだよね(笑)。
……でも、いまはそんなでもないかな。というのも、もともとはあまり人気のない場所だったんだけど、アート空間に変えちゃったせいで人がすごい集まっちゃって、すごい派手になって有料の船とかが通るようになり始めちゃったらしい(笑)。
まあ、こんなふうにデジタイズドすることで、自然をそのままアートにしちゃおう、みたいなことをやっているわけ。もちろん、ここで言う「自然」は環境に近い意味だから、同じことを街でもやってみたいんだけどね。というか、そもそもこのモチーフが固まっていったのは、「PLANETS vol.9」で「オリンピックの開会式を街全体でやろう」と考えていたときだしね。
宇野 そうなんだ。
▲『PLANETS vol.9 東京2020 オルタナティブ・オリンピック・プロジェクト』収録
猪子 この企画を考えていたときに、「競技場のあるなしはあまり重要じゃなくて、デジタイズドすれば東京そのものがオープニング会場になるんじゃないか」と思ったんだよね。デジタル化することで全く新しい体感の都市にできるじゃないか、街をまるごと街のままアートにできるんじゃないかと思ったのね。
いまは自然のほうが面白いと思っているから、当面は自然でいろいろやっていきたいなあと思っている。
「自然」のもつ情報量の可能性
宇野 なるほどね。まず、この「デジタイズド・ネイチャー・アート・プロジェクト」って、前回までに見てきた作品群とは逆のアプローチをしているよね。つまり、ここまでの作品群は「人工物を自然物のように描く」という作品で、今回の作品は「自然物を人工物のように描く」っていうことをやっているというのは、一つ言えると思う。
その上でね、絶対に他のところからくるつまらない突っ込みだと思うから先に僕がわざと聞くとさ、なんで「自然そのもの」じゃだめなの?
だって「自然のほうが面白い」のなら単に美しい自然を眺めればいい、って言い出す人って絶対いると思うのね。チームラボの作品を見ないで、その理屈だけ聞いちゃうと。
猪子 確かに、昨日もある人にそのツッコミはされた(笑)。
でもさ、そういう言い方はすべての人工物を否定することにならない?
昔から人間は自然の力を借りながら、いろんな人工物を創ってきたわけだよ。彫刻のようなアートだけじゃなくて、小屋だって道路だって、全部そうだよね。あらゆる人工物は自然からつくられているわけでさ。そういう人工物の歴史から言えば、むしろ僕らはかなり自然そのものを活かした人工物をつくっていると思うよ。その、木や石を削って彫刻をつくるかわりに、自然そのものの力を借りて、自然をそのままにアートにしているんだよ。
宇野 なるほどね。すべての人工物=アートは自然の加工物で、普通のアートはたとえば木を切ったり貼ったりして、加工しまくっているわけだけど、チームラボの場合は波を当てているだけでなんで、木そのものの力を最大限使って、アートをつくっていることになると。
これらは石や木そのものの力を最大限に使った「アート」であると認識しているわけだね。
猪子 新江ノ島水族館では魚も作品になっているんだけど、やっぱりスクリーンやビルのような物質よりも、水や木や生き物のような自然物の方が、情報量が圧倒的に大きいなと思うんだよね。だって、生命を彫刻だと思ったら、その情報量は凄いわけじゃない。最高級のロボットですら比べ物にならないよね。
宇野 まあ、生命のほうが人工物よりも乱数供給源として優秀だよね。
でも、だいぶ猪子さんの作品の背景にある思想が見えてきたように思うね。つまり、猪子さんは従来の、モノを中心としたアートという存在に対して、加工しすぎることで自然の持つ情報量を殺す方向に行っていると考えている。ところが、その一方で現在のデジタル技術を使えば、自然が持っている情報量をそのまま活用したアートができてしまう。
そういう発想が根底にあって、この「デジタイズド・ネイチャー・アート・プロジェクト」が作られているんだね。
なぜモノではなく空間なのか
宇野 ちなみに、猪子さんは「庭」とかは好きなの?
猪子 すごい好きなんだよね。
宇野 まあ、空間があれだけ好きなら、庭も好きだよね。じゃあ、実際につくったことはあるの?
猪子 いや、ない。まあ、「Floating Flower Garden」は一応、庭のつもりでつくったんだけどね。
▲Floating Flower Garden – Flowers and I are of the same root, the Garden and I are one / Floating Flower Garden – 花と我と同根、庭と我と一体
https://www.youtube.com/watch?v=siZhynevhUE
http://www.team-lab.net/all/art/ffgarden.html
宇野 よく言われる話だけれど、「自然 対 人工」の表現については二通りの考え方があって、一つは西洋みたいに完全に自然を支配して、飼い慣らしてしまおうという発想だよね。ところが、その対極として、まさに日本的な、庭の中に一つの人工的な自然をつくって、そこから先は自然に任せるという方向がある。そのときに、猪子さん自身は、自分のことをどっちに近いと思っているんだろう。
猪子 うーん。人間が造った街や庭にしろ、自然そのものの森にしろ……やっぱり、そこに物理的に介在せずにアートにするのが、少なくとも今は面白いんだよね。
宇野 なるほどね。ちなみに、俺の印象では、猪子さんというアーティストは、どちらかというと後者の日本庭園の思想に近い。
ただ、実はちょっと違うアイデアを考えている印象もあるんだよね。ここまで紹介された作品は、デジタルという質量のない波を当てると、自然の一部が人工物のように人間には見えてしまうことを利用しているんだよ。だけど、猪子さんがそこで抱いている興味は、現実の自然とは少し違った新しい世界を目の前に広げていくことにある気がしてるんだよね。
その意味で、俺にとって猪子さんは、日本的想像力をデジタルの力によって半歩ずらしている作家だし、だからこそ猪子さんは空間をつくるのが好きなんだろうな、とも思う。
猪子 うん、好き。
宇野 ただ、面白いのは平面の作品ですらも空間っぽいことだよね。展示の仕方からして、すでに空間を意識しているしね。
そうなってくると、なぜ猪子寿之はこんなにもモノじゃなくて空間ばかりをつくるのかは興味が湧いてくるんだよね。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は今月も厳選された記事を多数配信します! すでに配信済みの記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201512
<前へ
3 / 3